-
暖冬 弘妙寺で早くも福寿草咲く 伊那西スケート場教室を中止

伊那市高遠町の弘妙寺で、例年より2週間ほど早く福寿草が花を咲かせています。 5日の伊那地域の最高気温は12.2度で平年と比べ7.1度高く3月下旬並みとなりました。 伊那市高遠町の弘妙寺の境内には1週間程前から福寿草が咲き出し、現在15輪程花を咲かせています。 田中住職によりますと、2月にはたくさんの花が咲き、見頃は3月いっぱいだということです。
-
熊肉猪肉食べ放題 山のめぐみに感謝

クマやイノシシなどのジビエ料理を味わうイベント山のめぐみ感謝祭が23日、伊那市の竜門で行われました。 山のめぐみ感謝祭は竜門の社長で猟師の小阪洋治さんが、自ら仕留めたクマやイノシシを多くの人に楽しんでもらおうと行われたものです。 肉の仕入れ値がかかっていないことから飲み放題食べ放題で3000円と格安で提供されました。 店内にはおよそ140人が訪れめったに味わうことができないジビエ料理を楽しんでいました。
-
伊那地域でこの冬一番の冷え込み

28日の伊那地域は放射冷却の影響で最低気温がマイナス5.7度を記録しこの冬一番の冷え込みとなりました。 そんななか伊那市美篶の国道361号沿いでは十月桜が花を咲かせています。
-
大晦日間近 そば店大忙し

大晦日を間近に控え伊那市中央のそば処こやぶでは、年越しそばのそば打ちや発送作業に追われています。 そば処こやぶは創業42年で28日は年越しそばの準備に追われていました。 北は北海道から南は九州沖縄まで予約注文が入っていて発送分を含めた予約はおよそ5000食にのぼります。 店内では発送作業も行われ打ったそばは早速箱に詰められていました。 社長の伊藤祐一さんと息子の顕さんなど5人がそばを打ちピークとなる29日と30日は朝5時から12時間以上打ち続けるということです。
-
みはらしファームに2016本の〆の子

伊那市羽広の農業公園みはらしファームで28日、〆の子の飾りつけが行われました。 みはらしファームでは毎年西暦にちなんだ数の〆の子を飾り付けていて28日は来年の2016年にちなんで2016本を飾りました。 〆の子は西箕輪保育園の園児や公園内のしめ縄教室の参加者が作ったものです。 みはらしファームの関係者など30人ほどが園内に総延長およそ1.2キロの縄を張りめぐらし新年を迎える準備を整えていました。 〆の子は年明けの17日に行われる、みはらしファームのイベント、せいの神で燃やされるということです。
-
オーケストラをバックにピアノ演奏

長野県と山梨県の6つのピアノ教室に通うこども達がオーケストラ演奏をバックに練習の成果を披露するコンサートが、19日、伊那文化会館で開かれました。 コンサートは、国内で活躍するプロのオーケストラと一緒に演奏することでよりピアノを好きになってもらおうと、南箕輪村の望月音楽教室が開いたものです。 19日は、6つの教室に通う園児から高校生までの71人が演奏を披露しました。 望月音楽教室では、「1人で演奏するのとは違い映画音楽のような演奏が体験できるいい機会。長くピアノを続けてほしい」と話していました。
-
酒井一さん 木で干支の置物製作

伊那市西春近の酒井一さんは、来年の干支申の置物を製作しています。 元大工の酒井さんは、毎年木を使って干支の置物を作り、友人や親せきの他病院や市役所などにプレゼントしています。 今年は、6匹の猿が組み合わさって1つの作品となります。 酒井さんの住む諏訪形区では、来年御柱祭があるということで、地域住民が1つの大きな「猿(えん)」になって祭りを盛り上げていきたいと話していました。 酒井さん宅の庭には、他にも猿の置物が並べられていて訪れた人の目を楽しませています。
-
新年準備 坂下神社でしめ縄の取り付け

今年も残すところあとわずか。年末最後の日曜日となった27日は、伊那市の坂下神社で、しめ縄の取り付けなど新年の準備が行われました。 坂下神社では、今年一年飾られていたしめ縄を取り外し、新しいものに付け替える作業が行われました。 氏子総代会が先週の日曜日に新しいしめ縄としめ飾り、御幣を作りました。 本殿も含め境内には恵比寿神社や高田神社など4つの社殿があり、全部で10か所に新しいものを取り付けます。 境内入口の大鳥居には、3.5メートルのしめ縄を飾りました。 坂下神社の二年参りには、主に市街地から毎年600人ほどが訪れ、午前0時前後には大鳥居の外まで参拝客が列を作るという事です。 氏子総代会では大晦日の午後11時から甘酒や、みかんと餅のセットを無料で振る舞うほか、年越しそばを200円で販売するという事です。
-
ラーメン大学 施設利用者にラーメン振る舞う

伊那市御園のラーメン大学伊那インター店は、市内の障害者施設に通う利用者を招いてラーメンを振る舞いました。 22日は、市内3つの福祉施設の利用者13人がラーメン大学に来ました。 ラーメン大学では、25年前から毎年施設利用者にラーメンを振る舞うため、割引券を伊那市に寄贈しています。 お盆と年末合わせて120人分を振る舞っています。 今日は利用者がチケットを利用してラーメンを味わいました。 店は今年で創業38年で、何か地域に貢献できればと始めた取り組みだということです。 小松光明店長は「美味しいという声を聞くと嬉しい。これからも続けていきたい」と話していました。
-
東春近保育園 園舎完成

建物の老朽化と保育園の統合により建設が進められていた伊那市の東春近保育園の園舎が完成し、26日、地域住民を対象にした見学会が開かれました。 東春近中央保育園の園児は、年明けの6日から新園舎での生活を始めます。 26日は、園舎完成式が行われ、来年4月に統合する東春近中央保育園と南部保育園の年長園児54人が歌を披露しました。 東春近保育園は、中央保育園の東側に新たに建てられたもので、木造平屋建てで延床面積はおよそ1,360平方メートルです。 屋根には太陽光パネルが設置された他、ペレットボイラーが導入されています。 室内は、全長52メートルの長い廊下が特徴で、保育室7室と未満児室が2部屋あり定員は150人です。 建物の建設にかかった費用は、5億6千万円となっています。
-
冬休み中の小学生対象の書初め教室

子ども書初め教室が26日伊那市のいなっせで開かれ、冬休みに入った小学生が書道の指導を受けました。 書初め教室には市内の児童33人が参加しました。 上伊那の書道教室の指導者でつくる書晋会のメンバー6人が講師を務めました。 教室は、プロの指導を受ける機会にしてもらおうと伊那市生涯学習センターが毎年開いています。 講師は、「線が曲がらないようにまっすぐに」「筆を立ててしっかり引くように」などとアドバイスしていました。 書晋会では、「書道を通して集中力が養われる。気持ちを引き締め、新たな気持ちで新年を迎えてほしい」と話していました。
-
石川県出身の佐藤ヒロキさんが喫茶梨麻でコンサート

石川県出身のシンガーソングライター佐藤ヒロキさんのライブが、18日、伊那市の喫茶梨麻で開かれました。 佐藤さんは、全国を旅しながらコンサートを開いています。 梨麻では、年に数回店内で音楽ライブを企画していて、佐藤さんは2年前にも1度演奏を披露しています。 18日は、お店の常連客およそ30人が訪れ、オリジナル曲などおよそ10曲を披露しました。 梨麻の沖村隆さんは、「今年はオープン15周年の節目の年。お客さんにいい時間を過ごせてもらえたと思う」と話していました。
-
春日神社に巨大絵馬寄贈

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校と伊那中学校の生徒が、巨大絵馬を作成し、西町の春日神社に24日奉納しました。 春日神社に奉納されたのは、伊那弥生ヶ丘高校の美術部と書道部、伊那中学校の美術部がそれぞれ制作した巨大絵馬です。 弥生ヶ丘高校の絵馬は、中心に親子猿が描かれていて、招福などの文字は、書道部が書きました。 伊那中学校の絵馬は、松竹梅などめでたいものと、親子猿が描かれています。 春日神社は、毎年二年詣りで多くの参拝客が訪れるということで、その際出迎えるものとして、神社近くの弥生ヶ丘高校と、伊那中学校に、巨大絵馬の制作を依頼し、今回初めて奉納されました。 弥生ヶ丘高校と伊那中学校の生徒が制作した巨大絵馬は、来年1月いっぱい春日神社に掲示されます。
-
荒井区の子どもたちがクリスマス会で交流

地域の小学生が学年の枠を超えて交流する荒井区こどもクリスマス会が23日、伊那市の伊那中学校体育館で開かれました。 クリスマス会は荒井区や荒井区青少年育成会などが開いたもので小学生と保護者、地区役員などおよそ230人が集まりました。 企画運営は6年生が主体となって実施され会場の飾りつけやプレゼントの買い物などこの日のために準備をしてきました。 サンタクロースに扮した6年生が会場に現れると子どもたちは手を伸ばしてプレゼントを受け取っていました。 荒井区青少年育成会ではクリスマス会のほか、子ども相撲大会や、キックベースボール大会などを実施していて「地域の子どもたちの交流をサポートしていきたい。」と話しています。
-
2015ニュースTOP10 <伊那市>
今年も残すところあとわずかとなりました。 伊那ケーブルテレビでは、地域の様々なニュースや話題をお伝えしてきたわけですが、25日から3日間にわたり伊那市、箕輪町、南箕輪村のこの1年を振り返ります。 伊那谷ネットのアクセスランキングを基に、3市町村のニューストップ10をお伝えします。 初日のは、伊那市です。 10位 伊那西高校新体操部、個人・団体で全国制覇 9位、伊那市が「子育て世代にピッタリな田舎部門」で1位を獲得 8位、松茸のあたり年となり、バイキング方式の販売が盛況 7位、伊那市の新しい副市長に林俊宏さん 6位、伊駒アルプスロードのルート案決まる 【5位 飯島食堂105年の歴史に幕】 伊那市坂下の老舗中華料理店「飯島食堂」が、1月31日に閉店しました。 閉店が決まりテレビや新聞に取り上げられると、多い時には1日200食のかつ丼を提供するほど連日長い行列が出来ました。 1世紀以上地域に愛された飯島食堂は、105年の歴史に幕を閉じました。 【4位 大学ラグビー招待試合で、明治が同志社を下す】 6月7日に行われた試合には、「重戦車」と呼ばれ前へ前へ突進するスタイルが特徴の明治と、場面展開に応じたボール回しが特徴の同志社の対戦となりました。 試合は前半26対14と明治がリードし、後半に同志社が逆転しますが、ラスト同志社の反則で認定トライを許し、33対28で明治が勝利しました。 【3位 伊那市美篶のナイスロード沿いに、複合福祉施設みぶの里が完成】 みぶの里は、リハビリ付きのデイサービスのほか、入居し生活できる特養が29床、ショートステイもできる在宅支援を目的とした老健が80床設けられた複合施設です。 施設を運営する、社会福祉法人しなのさわやか福祉会では「安心と信頼を寄せてもらえる、心のこもったサービスを提供していきたい」と話していました。 【2位 NEC長野閉鎖で地域に波紋広がる】 NECは、車載機器などを開発・生産しているNEC長野の機能を、平成28年度末までに東京のNECプラットフォームズ㈱に移管すると2月に発表しました。 NECプラットフォームズは、去年4つの子会社を統合して発足しました。 NEC長野の閉鎖は、分散している工場を集約しものづくりの技術を融合すると共に、グローバル競争力のある製品の創出を図ることを目的としています。 【1位 高遠城址公園の観光客減】 天下第一の桜の名所として知られる高遠町の高遠城址公園の花見客の数が、天候不順などにより去年と比べて今年は激減しました。 今年は、16日間のさくら祭り期間中に晴れたのは4日間のみでした。 祭期間中の有料入園者数は15万8千人で、去年よりおよそ7万人減りました。 今年の伊那市ニュースランキングでした。
-
11月月間有効求人倍率1.39倍 6か月連続上昇
上伊那の11月の月間有効求人倍率は1.39倍で、10月を0.06ポイント上回りました。 求人倍率は6か月連続で上昇しています。 新規求人数は、1,444人、新規求職者数は580人で、上伊那の11月の月間有効求人倍率は、10月を0.06ポイント上回る1.39倍でした。 求人倍率は5月から6か月連続で上昇しています。 ハローワーク伊那では雇用情勢について「着実に改善が進んでいる」とコメントし、3か月連続で上方修正しました。 求人の数は安定していますが、求人の内容や派遣の動向に今後注視が必要としています。 来年度卒業予定の新規高卒者の就職内定率は90.5%で、去年より2.2ポイント上回っています。
-
伊那西スケート場 冷え込みに期待

伊那市横山の天然リンク・伊那西スケート場の安全祈願祭が24日、行われました。 24日朝の伊那地域の最低気温は3.6度と暖かく、氷は、一部が薄く張っているのみで、関係者は今後の冷え込みに期待を寄せています。 伊那市横山の伊那市営・伊那西スケート場です。 夏場は運動場として利用されていて、11月20日に水を張りました。 9日に全面結氷しましたが、このところの暖かさと23日の雨で、ほとんどが溶けました。現在は、一部に薄く氷が張っている状態です。 24日は、伊那市教育委員会や地元の関係者などが参加し、今シーズンの安全を祈る祈願祭を行いました。 伊那西スケート場は、1959年、地元関係者が冬場の農業用水を活用して整備し、1984年に市営となった、50年以上の歴史を持つ天然リンクです。 スケート場を管理している武田用水組合の武田 孝平さんは、今後の冷え込みに期待を寄せています。 伊那西スケート場は、2013年度は19日間営業し1,256人が利用、2014年度は19日間営業し908人が利用しています。
-
全県にノロウイルス注意報発令
長野県は「ノロウイルス食中毒注意報」を24日全県に発令しました。 県内で感染性胃腸炎患者の届け出数が増加していることや、全国的にノロウイルスによる集団感染が多発していることから、今日、注意報を発令しました。 ノロウイルスによる食中毒は、12月から3月の寒い時期にかけて多発するのが特徴です。 長野県では、食品を加熱処理する、作業前には手洗いを行うなど、食中毒予防を呼びかけています。
-
濃い霧の朝 南からの暖かな湿った空気の影響

24日朝の伊那地域は、南からの温かく湿った空気の影響で濃い霧となりました。 長野地方気象台によりますと、日本の南岸を、前線を伴った低気圧が通過し南から暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、今朝、濃い霧となりました。 25日以降は冬型の気圧配置に移行するため、30日頃まで比較的晴れの安定した天気になりそうだという事です。
-
シティプロモ撮影大詰め

伊那市の魅力を市内外に発信するシティプロモーション映像「イーナ・ムービーズなつかしい未来」の撮影も大詰めを迎えています。 22日はエキストラが参加しての撮影が行われました。 伊那市は、市内外に向けて人々の生活や子育て支援、豊かな自然環境などを撮影しています。 22日は、伊那市の映画館「旭座」で撮影が行われ、エキストラ40人が参加しました。 これまでは、行事などをメインに撮影してきましたがエキストラを使って撮影するのは初めてです。 総合演出を務めるのは伊那市芸術文化大使の柘植伊佐夫さんです。 22日は、現在制作中の秋編の最終撮影です。 柘植さんにとって思い出深い映画館を秋編のメインに使いたかったということです。 旭座は大正初期に建てられた映画館です。 今後は、編集作業に入り来年1月から冬編の本格的な撮影がスタートします。 伊那市のプロモーション映像は来年3月の完成を予定しています。 1月にはHPを開設し撮影風景や動画などを載せていく計画です。
-
冬至 伊那小学校の給食にかぼちゃや柚子を使ったメニュー

22日は「冬至」です。伊那市の伊那小学校では、かぼちゃや柚子を使った献立の給食が提供されました。 この日は二十四節気のひとつ「冬至」で、一年日のうち昼の時間が最も短いとされる日です。 冬至の日にかぼちゃを食べ、柚子湯に浸かると風邪をひかないとされていることから、伊那小学校のこの日の給食にはかぼちゃの煮物と柚子の和え物が出ました。 栄養職員の輿あかねさんは「昔からの言い伝えを意識して丈夫に過ごしてもらいたい」と話していました。
-
子育て情報を安心安全メールで配信
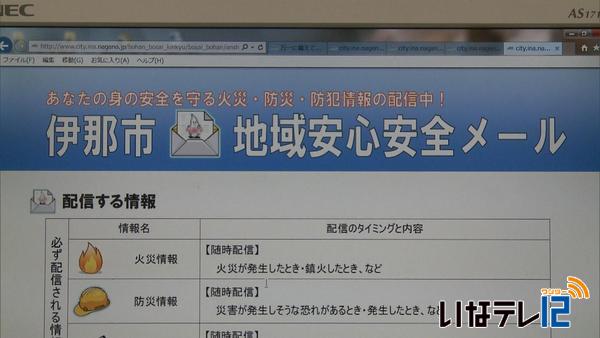
伊那市が防犯や防災情報をメールで配信している地域安心安全メールで新たに子育て情報の提供を行います。 伊那市が行っている安心安全メールは火災や防災、イベント情報などの提供を平成 年から行っていて21日現在、1万6891人が登録しています。 来年1月1日から0歳から2歳向けの情報を提供します。 登録すると子育て支援センターの講座やイベント情報、児童手当や保育園入園等手続きに関する情報を受信できます。 伊那市では、「メールの配信登録や情報利用料は無料で子育て中の人に利用していただきたい」と登録を呼びかけています。
-
満蒙開拓青少年義勇軍について 矢澤静二さん講演
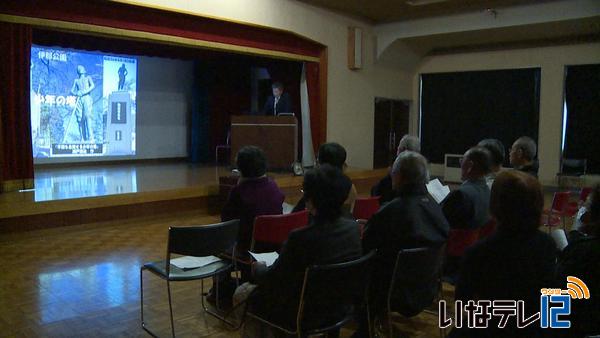
伊那市の西春近公民館で人権同和教育講座が18日に開かれ、上伊那教育会の矢澤静二さんが「上伊那の満蒙開拓青少年義勇軍~戦時下における人権と教育を考える~」と題して講演しました。 矢澤さんは、これまでの研究を元に、義勇軍創設までの流れや、上伊那の義勇軍の送出状況とその特徴などを解説しました。 矢澤さんによりますと、上伊那からはおよそ600人が義勇軍として満州に渡り、91人が亡くなったということです。 昭和15年頃までは、市町村ごとに義勇軍の割り当てが決められていましたが、その後教育関係者に義勇軍の送出の協力を要請し、結果、割り当て人数を上回る多くの人が義勇軍に送り出されることになったということです。 当時の教育が子どもに与えた影響は大きかったと説明し「戦争は人権破壊だ」と話しました。 講演では、教育会に唯一1枚だけ保管されている義勇軍の勧誘に使ったパンフレットも紹介されました。 講演は、戦後70年を迎え、上伊那とも大きく関わりのある満蒙開拓青少年義勇軍がなぜ送り出されたのかなどについて改めて考えてもらおうと、西春近公民館が開いたものです。 会場には30人程が訪れ矢澤さんの話に耳を傾けていました。
-
園児が〆の子作りに挑戦

伊那市の西箕輪保育園の園児は21日〆の子作りに挑戦しました。 21日は年長園児およそ50人が参加し〆の子を作りました。 指導にあたったのは保育園近くにある農業公園みはらしファームの職員4人です。 園児たちは職員に教わりながらワラの束をなっていました。 〆の子には願い事を書いた札をつけ28日にみはらしファームに飾りつけられるということです。
-
もうすぐクリスマス ケーキ作り

クリスマスを間近に控え伊那市山寺のフランセ板屋では、クリスマスケーキ作りが始まっています。 予約だけで1000個以上が入っていてこれから作業はピークを迎えます。 レンガ造りの店構えで知られるフランセ板屋は明治20年創業。 店内はサンタクロースをあしらったぬいぐるみなど赤と白、緑の装飾でクリスマスムードを演出しています。 厨房ではクリスマスケーキ作りが始まっていて、パティシエが1つ1つ丁寧に飾りつけを行っていました。 9種類で各30個ずつのプレミアムケーキは11月末ですでに予約済みとなっているほか、オーソドックスないちごに生クリームのデコレーションケーキは1100個ほどの予約が入っているということです。 ケーキ作りのピークとなる23日ころからはスタッフを増員し対応にあたることにしていて、フランセ板屋では予約を除きさらに1000個ほどの販売を見込んでいます。
-
高遠町公民館でそば打ち講座

年越しに向けて、伊那市高遠町の高遠城址公園内にある高遠閣で8日、そば打ち講座が開かれました。 講座には、伊那市内から18人が参加しました。 講師は、高遠そば組合の飯島進さんら3人が務めました。 講座は、年越しに向けて家庭でも打ち立てのそばを味わってもらおうと、高遠町公民館が毎年開いているものです。 この日は、長谷入野谷でとれたそば粉を使って1人500グラムから700グラム打ちました。 公民館によりますと、これまで受講した人の中に高遠町内でそば店を出した人もいるということです。 飯島さんは「こねばち3年のし3月、きり3日。まずはこねる工程を何度も何度も練習してコツをつかむことが大切」と話しました。 高遠そば組合では「家庭でそばを打つ人を増やして、最終的には伊那のそば文化の裾野を広げていきたい」としています。
-
ポーラ☆スター発表会

伊那と塩尻の新体操教室ポーラ☆スターの発表会が20日、伊那市の市民体育館で開かれ子供たちが日ごろの練習の成果を発表しました。 発表会では園児から高校生までのおよそ110人が参加し日頃の練習の成果を発表しました。 ポーラ☆スターは伊那市と塩尻市に教室があり毎年この時期に合同で発表会を開いています。 20日は、個人の演技の他団体での演技、保護者が参加しての演技が披露されました。 会場を訪れた家族は、子どもの演技をビデオカメラや写真におさめていました。 また20日は、8月のインターハイで個人、団体とも全国優勝した伊那西高校新体操クラブも発表しました。
-
「上牧里山づくり」が炭の窯出し

伊那市上牧の住民グループ「上牧里山づくり」の炭焼き窯で20日、炭の窯出しが行われました。 20日は上牧里山づくりのメンバーおよそ10人が集まり炭の窯出しを行いました。 窯はドーム型で縦170センチ、横150センチ、高さが110センチほどあります。 今月7日に火入れを行い近くの間伐材を50センチほどに切り2週間かけて燃やし炭にしました。 メンバーが窯の中から炭を取り出すと出来栄えを確認していました。 今回は炭焼きの煙の臭いを抑えるため二次燃焼装置を設置しました。 メンバーによると「少なからず効果があったとして」今後も対策を検討していくということです。 今回つくった炭は区民に活用してもらうほか地域の行事で使うことにしています。 上牧里山づくりは窯の近くに囲炉裏や足湯も作る計画で住民が集える場所にしていきたいと話しています。
-
箕輪町でクラフト体験イベント

子ども達にものづくりの楽しさを知ってもらうクラフト体験イベントが、19日、箕輪町文化センターで開きました。 イベントは、郷土博物館、図書館、公民館の三館連携事業として毎年この時期に開かれているものです。 今年は、科学の楽しさを知ってもらおうと特別企画としてサイエンスショーが行われました。 イベントや学校の授業で科学の実験などを指導している飯島町の「学校支援ボランティアわくわく」が、液体窒素を使った実験を披露しました。 実験では、食べ物や植物、紙などを液体窒素の中に入れ、どのような反応を起こすかを確かめました。 このうち風船は、中の空気が冷やされて水が発生するなどと説明していました。 他にも、液体窒素の中に手を入れたらどうなるかを実際にやってみせていました。 会場ではこの他に、万華鏡やビニールロケット、クリスマスツリーづくりなど9つのブースが設けられ、訪れた200人以上の親子連れで賑わっていました。
-
移住希望者向けに空き家を活用して園児数増を

伊那市高遠町の「高遠第2第3保育園の存続と未来を考える会」は、移住希望者に現在ある空き家を紹介し、早ければ今年度中に移住をすすめる計画です。 17日は荒町公民館で会議が開かれ、今後の活動などについて会員が意見を交わしました。 会によりますと、現在、県外在住の子育て世代3家族が高遠町の長藤・藤沢・三義地区に移住したいと申し出ているということです。 会では、移住希望者の住める場所を提供し園児数増に繋げようと、候補として、御堂垣外地区の教員向け住宅2軒と、塩供地区の空き家1軒を挙げています。 現在、どちらも住んでいる人はいないため、住むには掃除や改装などが必要になるということです。 また市から出る空き家の改装についての補助金も、現在の10万円から増額するよう要望するということです。 会は、今年中に白鳥孝市長に要望書を提出する予定です。 早ければ今年度中に空き家の改装などを行い、準備が整えば希望者が移住してくるということです。
82/(日)
