-
伊那市出身の女性がシカゴでインディペンデント映画の撮影に取り組む

米国シカゴでインディペンデント映画の制作をしている伊那市出身の梶野純子さん(32)が、米軍の基地問題をテーマとした新作の撮影を沖縄で進めている。企画立案から撮影までを手掛ける作品は2作目。米軍の暴行によって傷ついた少女が10年後、事件の当事者だった兵士の子どもを誘拐する竏窒ニいう同作品は、最初は復讐のために子どもを誘拐した主人公が、誘拐した子どもとのかかわりを通じて徐々に自己回復していく物語。さまざまな思いが交錯するこのテーマを形にするまでには、6カ月を要したという。
やりたいことを見つけるために日本の大学を中退して渡米した梶野さんは、現地で出会ったインディペンデント映画に魅了され、インディペンデント映画を撮影している監督に頼み込んで弟子入り。大学でも映画学科へと編入し、撮影のノウハウを学んだ。卒業後は他人の脚本に基づく作品を撮影していたが「自分の思いを精一杯伝えたい」と脚本から自身で手掛けた作品を制作することを決意した。
「アメリカ映画だけど日本人を主人公にしたかった」という第1作は、ブルースを歌うために単身でシカゴに渡った日本の女の子を主人公としたコメディータッチのミュージカル「Homesick Blues(ホームシックブルース)」。ろくに言葉も通じない中、厳しい現実に直面する彼女だが、持ち前のバイタリティーとさまざまな人との出会いを通して成長していく。
同作品の短編版はシカゴ国際映画祭、ハワイ国際映画祭など、さまざまな映画祭で入選し、話がまとまり次第、長編版の制作を進めていく。
新作については「映画を通して改めてこの問題を提起するだけでなく“消耗品”という感覚でとらえられている米軍兵士の社会的背景まで踏み込みたい」と熱意を語る。
現在梶野さんは、両作品への支援を求めており、「出身地である上伊那からぜひ協力してもらえれば」と話している。また、完成作の地元上映にも意欲を見せている。
問い合わせは、junkokajinojp@yahoo.ne.jpまで。
【インディペンデント映画】大手の制作会社や配給会社に依存せずに制作・配給される映画。 -
地域筋トレ教室

南箕輪村は介護予防事業の一環で、各地区の公民館を巡回して地域筋トレ教室を開いている。24日は中込公民館であり、9人が参加して筋力トレーニングのやり方を学んだ。
介護を必要とせず、いつまでも元気に暮らすために、筋力トレーニングなどの運動が有効といわれることから各地区で2日間ずつある。おおむね65歳以上の人が対象で、役場理学療法士の山崎一さんが指導する。
初日は、筋力は80歳で60%低下すること、高齢者でも筋力が向上する報告があることなどを紹介し、筋力トレーニングで基礎代謝の上昇や身体能力の向上、転倒予防などの効果が期待できることを説明した。
体力測定で握力、開眼片足立ち、歩行速度を測ったあと、ひざを支えるために必要なひざ上の筋肉、腹筋、大でん筋など重点的に鍛えるトレーニングに挑戦した。 -
箕輪町食生活改善推進協議会総会
箕輪町食生活改善推進協議会は24日、06年度総会を町保健センターで開き、事業計画、予算案などを承認した。
事業計画は県食生活改善推進大会、研修視察、食と健康を考えるつどいパート21。地域での日常活動は伝達講習会、ファミリークッキング、ヘルスサポーター21、ボランティア(ふれあい広場、離乳食教室など)、保健センター栄養指導室の清掃。予算総額は8万4423円。
原美代子会長は、「家族をはじめ自分、すべての人、物に感謝し、明るく楽しく元気に活動しよう」とあいさつした。 -
伊水会書展

上伊那を中心とした書道家46人による第27回伊水会書展が26日、伊那市の県伊那文化会館で始まった。漢文などをテーマとした古典的な書から、現代的な前衛作品まで約140点が、訪れた人を楽しませている=写真。28日まで。
額装や軸装などが中心で、うちわに思い思いの言葉を書きとめた作品もある。現代の人にも楽しんでもらえる展示会にしたい竏窒ニ、文字数の少ないものや、日々の日常を綴(つづ)った朗らかな作品なども、多く並べた。
また、「十七帆を書く」をテーマに、東信の時代の書家・王義之の叢書を写した臨書も展示する。
文字の形を崩すことで、その言葉の意味を表現する前衛作品には、抽象芸術を思わせる面白い作品が多い。
伊水会の主宰・千葉耕風さんは「墨の濃淡まで楽しめる展示会。作品を通して作者の思いを感じてほしい」と話していた。
入場無料。午前10時縲恁゚後5時半(最終日は午後3時半まで)。 -
パートナーシップ南みのわ総会
パートナーシップ南みのわ(酒井八重子会長)の06年度総会は24日夜、村民センターであった。06年度役員、活動計画、予算案などを承認した。
活動計画は男女共同参画フェスティバル参加、あいとぴあ研修会参加、男女共同参画基礎講座参加、理事者との語らい、会員同士の交流会、箕輪町との交流、文化祭への参加、パートナーシップ南みのわ通信発行(年2回)、ミニ勉強会、むらづくり賞への活動登録など。予算総額は15万902円。
酒井会長は、「パートナーシップ南みのわも丸5年。皆の協力でここまでやってこれた。“命の平等”という言葉は男女共同参画とイコールではないかと思う。男女共同参画は今が旬。絶大なるご支援、ご協力をお願いしたい」とあいさつした。
06年度役員は次の皆さん。
▽会長=酒井八重子▽副会長=三沢澄子、高橋紀美代▽会計=原敏子▽幹事=植田さち子、堀伊都子、小池つる子、清水伝乃丞、井原夏二▽監査員=丸山千恵子、纐纈泰治 -
ほどよい運動で健康増進
箕輪町教育委員会主催の「健康貯筋体操教室」が24日、町民体育館で始まった。
生活習慣病予防に効果的な運動を通して健康増進を図るとともに、参加者の親ぼくを深めて、仲間づくりをする。毎年恒例の教室で、続けて受講する人も多い。
講師は、健康運動指導士の宮沢繁美さん=松川町。8月末までの全12回あり、ウォーキングや自分の体重を使った軽い筋力トレーニング、セルフマッサージ、ストレッチなどに取り組む。
初回は約20人が参加。宮沢さんは健康貯筋について「運動をすることで健康を貯めていくイメージ」と説明し、「運動を続ける楽しみも感じてもらいたい」と呼びかけた。
参加者たちは正しいウォーキングから挑戦。▽顔を起こす▽遠くを見る▽背筋を伸ばす▽つま先を前に向ける竏窒ネどと指導を受け、姿勢や足の運びに注意して管内を歩き、心地よい汗を流した。
教室は随時参加を受け付けている。希望者は生涯学習課(TEL70・6602)へ。 -
陶芸家宮崎守旦さん県内初の個展

1999年、伊那市高遠町芝平に築窯してから、県内では初となる、陶芸家・宮崎守旦さん(58)の作陶展は28日まで、同市西春近のかんてんぱぱホールで開いている=写真。
ろくろと石膏(こう)型などで作った花器、酒器、茶器のほか、湯のみ、小皿などの食器、合計100余点を出品。左右対称ではない、独自の形を追求した作品に来場者の足が止まっている。
つぼを成形した後、半分に割って作った「二彩片口鉢」や携帯用の酒器「呉洲抱瓶」、直径60センチの大作「泥刷毛目大皿」など、既製品とは違う人の手で作った味のある作品ばかりが並ぶ。
宮崎さんは東京都青梅出身。地元に築窯するが「作陶を続けるなら山間の場所がよい」と工房を芝平に移し、作陶歴は30余年。今後は「ろくろでなく、てび練りで自分なりの形を表現していきたい」と話している。
午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。入場無料。 -
箕輪町公民館の生涯学習4講座の合同開講式

箕輪町公民館の生涯学習講座「ふきはら大学」「ふきはら大学院
」「あざみ学級」「ふれあい学級」の合同開講式が23日、町文化センターであった。4講座を受講した計72人の新入生それぞれが、学習のスタートを切った。
開講式で柴登巳夫同公民館長は「学ぼうとする気持ちを持ち続けて努力してほしい。学習の中で多くの仲間との気持ちの通じ合いを深めて」と式辞を述べた。
受講生代表のふきはら大学院新入生、花沢千恵子さん(63)=松島春日町=は「これからの私たちは、特に意欲と緊張感が必要となるが、先輩、指導員の方々と楽しく勉強していけることを期待したい」とあいさつした。
開講式の前には、箕輪町芸術文化協会の藤田隆美会長が「ことば縲怺ト事の魅力に惹かれて縲怐vと題して記念講演をした。
4講座では文学、健康、音楽、歴史などの生涯学習のメニューを受講生が自ら決め、趣味の世界や友情の輪を広げていく。 -
犬のしつけ方教室 実技始まる

県動物愛護会上伊那支部と伊那保健所は21日、県伊那文化会館東側多目的広場で、犬のしつけ方教室の実技講習を始めた。14日に学科講習を終え、実技は6月11日までの全4回を予定している。
この日は11組の受講生が参加。飼い主の横を犬が一緒に歩く方法を家庭犬インストラクター5人から学んだ。最初は犬同士で吠え合ったりと大騒ぎだったが、次第に慣れてくると参加者の指示通りに犬も歩くようになっていった。
コーギー犬の「そら」ちゃん(生後1年)のしつけのために参加している花岡敏彦さん(44)=南箕輪村=家族4人は「散歩の時に跳びついてくるのが激しかったのでしつけを学びたかった。一緒に静に歩けてよかった」と話した。
犬のしつけ方教室は、かみぐせがあるなどで、同保健所へ引き取られる所有権放棄頭数を減らすために1993年から始まり、14年目を迎える。
所有権放棄頭数が106頭だった93年度と比べると、05年度は38頭に減少。飼い主への飼育の指導が徹底されたほか、避妊処置の普及が進んで、子犬の引き取り頭数が減ったのが要因だという。 -
保健補導員がゴミ処理施設を視察

宮田村保健補導員会(新谷秀子会長、30人)は23日、駒ケ根市と伊那市のゴミ処理施設を研修視察。家庭から出される廃棄物が、どのように処理されているか目で確かめ、ゴミ減量化の意識を高めた。
駒ヶ根市の伊南行政組合不燃物処理場では、同組合の小松政巳さんから施設の概要、処理の状況などを聞いた。
実際に場内をまわり、手作業で一つひとつの不燃ゴミを分別している現場も見学した。
不燃物を処理するのに「10キロ60円、10トンに換算すれば60万円もの経費がかかっています」と教えてもらうと、一斉に驚きの表情。
家庭で分別することが、再資源化、減量化につながると改めて痛感していた。
一行は伊那市の中央清掃センターにも足を運び、可燃物の処理状況も見た。 -
男性のための健康料理教室

男性のための健康料理教室が24日、駒ヶ根市保健センターで開かれた。市保健福祉課が3年前から行っている事業で、60代を中心に約30人が参加。第二の人生は家事も分担し、自分自身で健康を守ろうと、ワイワイにぎやかに料理した。
主食とみそ汁、サラダの3品に挑戦。ほとんど厨房に入った経験がない人も多く、不器用な包丁さばきもみられた。
「どれくらい塩を入れたらいいの」「まだ、ゆでないとダメかね」と、あらゆる段階で質問する姿も。
指導にあたった栄養士は「男性が一番できないのが料理の段取り。脳を使うパズルゲームだと思って、楽しんでみてほしい」と話していた。
栄養バランスも考えながら、美味しそうな男の料理が見事に完成。ある男性は「今まで家事は全て女房任せ。料理することも全くなかったが、今後はいくらかでも協力しないと」と話していた。 -
箕輪町女性団体連絡協議会総会

箕輪町女性団体連絡協議会(釜屋美春会長)の総会が22日夜、松島コミュニティーセンターであり、06年度事業計画や予算などの5議案を原案通り可決、承認した。
佐々木清子前会長が「私たち女性が学び、進歩向上を目指し、取り組んでいかねばならないことを信じている」とあいさつ。釜屋会長は「これからの社会が抱える問題に対し、女団連のネットワークを活用し、取り組んでいきたい」と呼びかけた。
本年は町長から町政に対する考えを聞くための模擬議会(8月24日)を、約15年振りに実施することを決議。そのほかの事業計画は「男女共同参画フェスティバル」(6月25日)、「人権・男女共同参画のつどい」(11月26日)竏窒ネどとした。 -
箕輪町図書館の「紙しばい読み方講座」始まる

箕輪町図書館(平井克則館長)の事業「紙しばい読み方講座」がこのほど、同図書館であり、伊那朗読の会会長の小林豊子さんの指導で、町内に住む読み聞かせに興味のある10人が学習を始めた。講座は全2回で、28日にもある。
小学校などで読み聞かせボランティア活動などをする人たちに、学習の場を提供する目的で昨年から始まった講座。絵本と紙芝居を読む時の違いを学んだり、互いに読み、聞き合いながら学習していく。
初日は実際に紙芝居を受講生らが読んで、小林さんが批評したりした。題材はヒヨコと母親鳥との関係を描いた作品で、それぞれが声の強弱や速さ、間の取り方などを工夫し、思い思いに音読した。
小林さんは「どういう意図で書かれているかを理解し、それに相応しい読み方で」と助言した。
6月18日からは朗読講座が、小林豊子さんの指導で始まる。8月20日までの全3回の講座。申し込み期間は6月2日まで。問い合わせは箕輪町図書館(TEL79・6950)へ。 -
伊那東郵便局 季節の花でやすらぎ演出

伊那市中央区の伊那東郵便局ロビーで6月9日まで、華道家元池坊伊那支部中部ブロックの青年部らが、生け花を飾り付けている。局内はスズランなどの花で彩られ、利用客を楽しませている。
青年部の花の展示奉仕は、10年以上続く年間活動の一環で、公共機関に花を飾り、地域の皆さんの気持ちを和らげたい竏窒ニの思いで始まった。
期間中は、青年部の市内在住会員でつくる中部ブロックのメンバー約10人が交代で2作品づつを展示。花は会員の庭先に咲くスズラン、コデマリなどの季節の花を中心に、チョコレートコスモス、レースフラワー、カラーなどが並ぶ。
会員の一人の平澤佐和子さん=伊那市中央区=は「花で局内を明るくしたい。利用客の方の心がいやせたら」と話した。
土・日曜日、祝日は休み。午前9時から午後5時まで。 -
遠照寺・色鮮やか大輪 ボタン見ごろ

伊那市高遠町山室の遠照寺(松井教一住職)のボタンが見ごろを迎え、色鮮やかな大輪の花々が華麗に咲き競い、来場者を魅了している。
遠照寺によると、冷え込みなどの影響で例年より1週間遅く、最盛期は今週末ごろになる見通しで、6月初旬まで楽しめる。
毎年訪れているという上田市の玉井孝さん(74)、清美さん(73)夫婦は「きれいだし、種類も多くて見事なボタン。素晴らしいね」と話していた。
松井住職の母が先代をしのび、24年前に3株を植えたのが始まり。現在では170種類・約2千株に増え、「ボタン寺」として知られる。毎年、上伊那をはじめ、県内外から約5千人が訪れるほか、アマチュアカメラマンにも人気を集める。
入園料は高校生以上400円(団体20人以上は割引)。問い合わせは、遠照寺(TEL94・3799)へ。 -
自転車啓発活動

自転車利用者のモラルとマナーの向上を図ろうと駒ケ根警察署、伊南交通安全協会駒ケ根支会(赤羽根徳彦支会長)、駒ケ根市は22・23日朝の通勤・通学時間帯に、JR駒ケ根駅に隣接する2カ所の駐輪場でチラシを配布するなどの啓発活動を行った。自転車に乗って駅までやって来た高校生らに駒ケ根署員や安協役員らがチラシを手渡し「安全に注意して運転して」などと呼び掛けた=写真。盗難防止用の自転車用ワイヤーロック錠も希望者にプレゼントした。
チラシには「大丈夫? その乗り方で!」として自転車運転中の携帯電話の禁止やライトの点灯などの交通ルールを守ることの大切さや、歩行者に対する注意義務などが記されている。
啓発活動は24日も同駅駐輪場で行う。 -
伊那おやこ劇場・大芝でイベント

伊那おやこ劇場は21日、南箕輪村大芝高原研修センターで「おやこまつり縲怩ツくろう!はしろう!あげよう!縲怐vを開いた。伊那市西箕輪の、みはらしファーム内「工房Coo」の佐野博志代表から凧作りを学び、5月の青空に飛ばした。
伊那市、南箕輪村などの上伊那から、園児や小学校低学年を中心に50人の子どもと、保護者の計約100人が集合。ビニール袋やわりばし、紙などの材料で縦横50センチほどの大きさの凧を作り、表面にはオオカミ、ウサギなどの動物、家族の顔などの絵を描いた。
自分のお気に入りの凧は、近くの運動場で上げた。子どもたちは周りの友達には負けまいと、汗だくになって走り回ると、その活力に大人らは少し疲れた様子だった。
凧づくりの前には、伊那おやこ劇場の会員有志でつくるサークル・きらっぴー親子劇団が、おなじみの昔話「さるかにむかし(合戦)」を上演し、喜んだ。 -
箕輪西小6年生22人を「セーフティーリーダー」に委嘱

伊那署は22日、健全育成活動を推進して子どもの規範、防犯意識の向上を図る施策「わが家のセーフティーリーダー」に、箕輪西小学校の6年生22人を委嘱した。
証明書が入ったネックストラップなどを一人ひとりが受け取ると、児童代表の林結花児童会長が「箕輪西小の最高学年として、登下校や学校活動では、1年生から5年生の友達をまとめ、楽しい学校生活づくりになるよう取り組む」と誓った。
小嶋惣逸署長は「世の中には自分たちの都合だけで悪いことをする人がいる。地域の人たちが皆さんの安全のために頑張っているが、自分たちで考えて行動することも必要。一年間の活躍を期待しています」と話した。
地域の非行、防犯活動などへの参加を促すため、01年度から毎年ごと、管内の小学校を指名している。これまでの学校は、通学路の危険箇所の確認、「こどもを守る安心の家」への訪問、家族や下級生に対する防犯などの啓発活動竏窒ネどをしている。
伊那署管内で本年あった声かけ事案は、4月17までに伊那市内で6件。前年は伊那市16、箕輪町7、南箕輪村3、高遠町1の合計27件で、特に下校時の午後3時から5時の間、全体の約6割が発生している。
箕輪西小のほか、6月中旬に伊那市の手良小学校も委嘱する。 -
楽しく美しく歌声響かせ 南信合唱祭・21グループ交流

第62回南信合唱祭が21日、県伊那文化会館大ホールであった。特別ゲストを含む21グループが、会場に澄んだ美声を響かせた。南信合唱連盟の主催。
本年は新伊那市誕生、権兵衛トンネル開通を記念して市内などで活躍するグループをゲストに招き開催。「出逢(あ)い」をテーマにそれぞれが曲を選曲し、同じ会場で発表する機会を楽しんだ。
音の厚みを考え2つの合唱団が合同参加した駒ヶ根女声コーラス、アンサンブル飯田や、来年創立50周年を迎え、記念演奏会に向けてさまざまなジャンルの曲に取り組んでいる伊那混声合唱団などが魅力ある歌声を披露した。
ゲストの岐阜大学コーラスクラブは約70人の大所帯で「学園天国」など3曲を続けて合唱。学生らは看護服、サッカーユニホーム、浴衣、作業着などの衣装を着て、手振りや動作を交えて、観客を盛り上げた。会場からは手拍子が巻き起こり、アンコールの要求にも答えた。 -
駅前が花でパッと
住民手づくりの広場が完成
宮田村のJR宮田駅前に、住民手づくりの広場が完成。27日午前10時から現地で開園式を行う。空洞化が顕著な同駅前だが、植栽された色彩豊かな花々で一変。駅利用者をはじめ、多くの人の目を楽しませており「村の玄関口として、憩いの空間になれば」と関係者は期待を寄せている。
手がけたのは駅周辺の住民有志でつくる「一輪の会」(小沢常明会長)。廃屋などもあり寂しい状態だった駅東側の空き地を、計画から半年余りで整備した。
「さみしい駅前を何とかしたい」と始まったが、熱意に地権者も快諾。地元の建設業者も協力し、会員自ら汗を流して作業した。
村の地域づくり支援事業も活用して花壇も整備。村を象徴する梅の花のデザインにするなど細部にもこだわりが。今後も随時、季節の花を植えていく計画だ。
今はマリーゴールドなどがちょうど見頃。満開の花畑が、駅の乗降客を迎えている。
「色々なタイミングも上手に重なり、皆さんの協力でここまで漕ぎつけた。少しでもキレイにしていきたい」と会員。
開園式当日もテープカットして、地域一緒になって祝う予定だ。 -
青島堤防桜保存会「さくら功労者」受賞を報告
財団法人「日本さくらの会」から今春、桜の保存や愛護運動などに功績のあった「さくら功労者」として表彰を受けた伊那市美篶青島の三峰川右岸堤防沿いに植わる桜並木を守る青島堤防桜保存会の橋爪正昭会長ら3人が19日、市役所の小坂樫男市長を訪ね、受賞の報告をした。
洪水時の堤防決壊防止などのため、大正時代に約1800本が植えられたが、後に砂利採取の車両道路に使用することから大半が撤去され、現在はソメイヨシノ約40本が残る。96年に青島区全92戸の区民で発足し、病害虫防除や施肥、せん定などの手入れをして管理に当たってきた。
見ごろの時季には、残雪の中央アルプスを背景に桜を撮影するアマチュアカメラマンも多いという。秋の紅葉も見応えがあり、人気を集める名所となっている。
橋爪会長は「先人が残してくれた桜を守ろうと始めた取り組みが実った。今後は、さらに桜を増やしていければ」と話していた。
小坂市長は受賞を祝福し、今後の活動に一層の期待を寄せた。 -
買い物にマイバック持参しよう
箕輪町消費者の会(唐沢順子会長、52人)は20日、町内の大型店など3店舗でマイバックキャンペーンを実施し、買い物客に対してマイバック持参の必要性を訴えた。
キャンペーンは5年以上続けていて、年2、3回、町内の大型店の協力を得て店頭で、買い物時のマイバック持参を呼びかけている。
この日は会員をはじめ、町女性団体連絡協議会のメンバーも協力し、合わせて10人が参加。例年通りジャスコと西友に加え、今回初めてJA上伊那箕輪町支所でも取り組んだ。
会員らは店頭に、「進めよう!ごみ減量 お買い物には買い物袋マイバッグを持参しましょう」と印刷されたのぼり旗を立て、ごみの減量、地球温暖化防止、資源保護といったマイバック持参の効果を記したチラシを配布して啓発。ジャスコと西友では用意した手持ち型やリュックサック型など、数種類のバックも販売した。
毎年販売しているバックは昨年度、過去最高の100個以上を売り上げたが「なかなか買い物袋を持参してくれる人は少なく、まだまだ関心は薄い」と唐沢会長。「活動が実るように、今後も活発的にPRしていきたい」と話していた。 -
宮田村町一区敬老会

宮田村の町一区分館(東野昌裕分館長)は21日、06年度の敬老会を村商工会館で開いた。招待された70歳以上のお年寄り207人のうち約60人が出席し、長寿と健康を共に祝った。
ステージでは保育園児や有志のグループらによる歌や踊りなどの出し物が多彩に披露された=写真。出席者らは時折一緒に歌を口ずさんだり手拍子を取ったりしながら演芸に見入るなど、楽しい宴のひとときを過ごしていた。 -
三峰川自然再生事業終了地視察

三峰川みらい会議は20日、自然再生事業が終了した三峰川の観察会を開いた。約50人が参加し、三峰川の在来河原植物について学んだり、整備が完了した河原の様子を見学した。
観察会は、治水、自然環境の保全、河川空間の利用などを調整する自然再生事業「三峰川みらい計画」が終了したことに伴い企画した。
参加者は、環境調査などを担当した関係者から、樹木の伐採や河原の拡張などが行われた場所や、この河川に自生する希少植物などの説明を受け、整備が終了した場所にもこういう植物が生えてくることが期待されることなどを学んだ。
整備では、冠水しやすい場所を設けることで、大きな樹木が生育しにくい環境をつくったり、対岸へ行き来できる飛び石を3カ所に設置し、住民に親しまれる河川づくりを目指した。 -
塩じい講演会
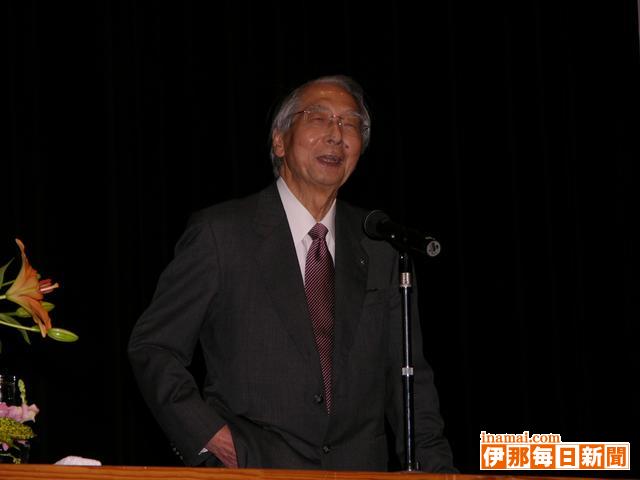
今年創立40周年を迎えた駒ケ根青年会議所(加藤道生理事長)は21日、塩じいの愛称で知られる元財務大臣の塩川正十郎さんを講師に招いての記念講演会と記念式典を駒ケ根市文化会館で開いた。式典で加藤理事長は「日々変化する環境の中で表向きの議論に踊らされることなく、本質を深く見つめる目を持って伊南地域をさらに盛り立てていきたい」と力強く決意を述べた。
式典に先立って開かれた塩川さんの講演会は市民ら約900人が詰めかける盛況。満員の聴衆を前に塩川さんは歯に衣着せぬ持ち前の舌鋒で政治を鋭く斬った=写真。「今の国会はビジネスライクになり過ぎ。もっと先を見通した議論をしないと国は良くなっていかない」「戦後すぐにできた現在の社会保証制度を今後も維持していくのは少子高齢化などの状況からも無理がある。保険でなく、税金でまかなう制度に根本的に変えなければならない」などと力説。消費税率改正を含めた大改革の必要を説いた。 -
登内時計記念博物館の遅咲きシャクナゲ見ごろ

伊那市西箕輪の登内時計記念博物館にある遅咲きのシャクナゲが見ごろを迎えている=写真。色形とも美しい約800株が、訪れた人の目を楽しませている。
現在咲いている種類はヤクシマシャクナゲやホソバシャクナゲなどが中心。シャクナゲには、美しい花をつける周期があり、今年はちょうど良い年に当ったため、花の状態も良いという。
今は鮮やかなピンク色が美しいつぼみと、形の美しい花の両方が楽しめる一番良い時期で、見ごろは今週いっぱいとなる。花は今月末まで楽しめる。 -
環境ピクニック、今年も開催

上伊那・下伊那の95事業所が参加する「天竜川水系環境ピクニック」が21日、6地区10カ所の天竜川水系河川であり、4180人が河川一斉清掃に取り組んだ。上伊那の民間企業でつくるリサイクルシステム研究会など主催。
企業などが個々に取り組んできた清掃活動を連携して行うことで、一層の環境向上を図ることを目的とした活動で13回目。上伊那は62事業所から2785人が参加した。家族連れや地域住民の参加が多く、ごみは年々減少しているという。
参加者は、それぞれの担当区域のごみを収集。川辺の在来植物の生育に深刻な影響を与えるアレチウリの駆除にも取り組んだ。
この日集まったごみは空き缶3454個、空きびん1323個、ペットボトル2千個で、どれも昨年より大幅に減少したが、伊那地区は、6地区の中でも最も多くのごみが集まった。 -
美篶地区住民が場広山でハイキング

新緑を楽しみながら交流を深めよう竏窒ニ21日、伊那市美篶地区の住民、約300人が参加するハイキングがあった。参加者は、道端に生えた山菜を摘んだりしながら初夏のハイキングを楽しんだ。
美篶地区の青少年育成会と公民館による取り組みで17回目。場広山は新山地区にあるが、美篶地区や美篶小学校の財産区があり、小学生が整備に訪れたりしている。しかし、そのことを知らない人も多いため、ハイキングをしながら美篶の財産について知ってもらおう始めた。大人から子どもまで、幅広い年代層が参加するため、住民同士の絆を深める場にもなっている。
高烏谷山を目的地として場広公民館をスタート。途中、財産区を管理している委員から説明を受けながら場広山のことを学んだ。
山頂では、それぞれが持参したお弁当を味わった。 -
250種類が次々と

中川村片桐横前の知久島覚一さんの畑では、ジャーマンアイリスがようやく咲き始めた。約8アールの花畑には250種類のジャーマンアイリスが植えられ、6月10日ころまで次々とゴージャスの花を咲かせる。
開花は例年よりも1週間ほど遅れ、現在30-50種類が咲いている。開花期間中は一般開放され、園内はスロープを整備し、車いすでも花を見て回ることができる。
22日からは越百園のデイサービスの利用者もと訪れる。 -
駐車車両の1割以上がドアロックせず
宮田村防犯指導委員会(増田忠直会長)はこのほど、村内6カ所の村営駐輪、駐車場で防犯診断を実施した。調査した自動車の1割以上がドアロックをしていない状態で、所有者に注意を促した。
14人の指導員が2組に分かれ、JR宮田駅周辺や中心商店街に点在する駐輪、駐車場で診断。
駐車中の自動車37台のうち、5台はドアロックしていなかった。また、1台はカギが付いたままの状態。対象車両には注意書を貼って、所有者に自覚を求めた。
自転車は34台中、2台がカギ無し、無施錠で、9台が防犯登録がされていなかった。
31台は姓名住所などの記名がなく、放置と思われる自転車も12台にのぼった。
201/(火)
