-
夏日…伊那の最高気温25・1度
高気圧に覆われ、青空が広がった22日、伊那市の最高気温は25・1度と夏日を記録した。暑い1日で、半そで姿で歩く人が目についた。
4月中に夏日になることは、それほど珍しいことではないそうだが、「こんなに暑くなるとは思わなかった」と長そでをまくり上げたり、「あなたは、日焼け防止対策はしなくていいの?」と日傘を差し、長そでを着込む女性も。
長野気象台によると、23日も高気圧に覆われて晴れるが、日本海に低気圧が進むため、夕方から雲が広がる。 -
昭和伊南総合病院の充実を求める会が要望書提出

伊南地区の住民でつくる「昭和伊南総合病院の充実を求める会」(林奉文代表)が22日、杉本幸治駒ケ根市長のもとを訪れ、昭和伊南病院の救命救急センター存続、院内助産院の早期実施などを求める8事項を示した要望書を提出し、一つひとつの事項についての市長の見解、今後の方針について懇談した=写真。
救命救急センター機能の存続については「救命救急がなくなることで医師のモチベーションが下がり、患者も昭和伊南への信頼を寄せなくなること」と指摘。
これに対し杉本市長は「市としても、昭和伊南の救命救急センターの位置付けを守っていきたい。しかし、整形の常勤医師がいない現状にあり、いかにして医師確保が課題。この病院のよさを伝える中で医師確保につなげていきたい」とした。
また、院内助産所に関しては、「出産の7割は正常分娩。ぜひ伊那中央病院と連携する中で、昭和伊南では助産師が正常分娩を扱うという風にできないか」との意見も出たが、「病院で助産所を設置する場合、万が一のケースに備えるためにもやはり常勤の医師がいないとできない。常勤医師がいない現状では、院内助産所は無理」と説明し、医師確保が最重要課題であることを改めて示した。
懇談を終え、林代表は「努力の姿勢は見えるが、簡単に進められる問題でないだけになかなか難しい。なるべく情報提供してもらい、病院、行政、住民が連携して対応していかなければならないと感じている」と話していた。 -
琴伝流大正琴全国普及会がギネス記録を報告
今月13日に静岡県のグランシップの大ホールで開催した第23回琴伝流全国大会で、2864人による大正琴の一斉演奏に挑戦し、見事ギネス記録を更新した駒ケ根市福岡の琴伝流大正琴全国普及会の北林篤副会長が21日、杉本幸治市長のもとを訪れ、英国から送られてきたばかりの認定書を披露した=写真。
琴伝流は大正琴の世界で全国2大流派の一つとなっている。今回は日本一の高さを誇る富士山のある静岡県で全国大会を開くことになり、何か記録に挑戦しよう竏窒ニ、大正琴の一斉演奏のギネス更新企画。当初は富士山の高さ3776メートルにちなみ、この人数で演奏ができないかと画策したが、会場の都合から、3千人以内で記録更新を目指すことになり、各地で活動する琴伝流の教室に呼びかけたほか、一般からの参加も公募。結果、これまでの1034人を1830人上回る人員が集まった。
ギネス認定を受けるには▽5分以上演奏すること▽必ず指揮者をつけること竏窒ネどが条件とだったため、スクリーンに映した指揮者を写し、「茶摘」「さくらさくら」など童謡4曲のメドレーを6分12秒にわたって演奏。その場でギネス認定を受けることができた。
北林副会長は「当日はベテランから初心者まで、顔も知らない人とともに音楽を奏で、達成感を共有した。それは舞台の上で演奏する普段とは異なり、参加した方にも大変良い経験になったと思います」と話していた。 -
飯島町慈福院の第27回北街道延命地蔵尊祭り開催

飯島町七久保地区北街道区(67戸、野原正明総代)は20日、「第27回北街道延命地蔵尊祭り」を集会所「ハーモナイス」で開いた。家族連れなど、多くの住民が集まり、祭りを祝うとともに多彩な催しを楽しんだ。
祭りはこれまで延命地蔵尊が安置されている慈福院の境内で行われてきた。しかし、天候を気にせず多くの住民に参加してもらえるようにと、04年から室内で行うようになり、地元の保育園児や小学生、趣味のクラブなどがそれぞれに催しを披露するようになった。
最初のステージでは、七久保保育園の野原聖太君、倉家将君、那須野歩香ちゃんが、この日のために練習してきた「どうぶつ体操」を披露=写真。かわいらしい踊りに大人も子どもも笑顔を見せ、会場からはおひねりが投げられた。
野原総代(63)は「地区としては一番大きな行事。普段はあまり接点がない小さい子どもとお年寄りもこういう機会には交流できると思うので、多くの人に来て、気楽に楽しんでいってほしい」と話していた。 -
伊那中央病院防災訓練
万一の火災発生に備えて伊那市の伊那中央病院(小川秋実院長)は21日、08年度前期防災訓練を行った。病棟の3階にある屋外テラスのごみ箱から出火した竏窒ニの想定で訓練開始。消火班の職員が消火器を持って駆け付け、初期消火に当たるが消火できず…。本部長を務める芝伸彦副院長の指示で防火扉を閉める一方、自力で動けない入院患者を病室の窓から数人がかりで抱えて運び出したり、逃げる途中に転倒し、頭を打って意識不明となった職員を臨時救護所に搬送して救急処置をする訓練などが行われた=写真。
いざという時に臨機応変に対応するため、多くの職員には訓練スケジュールなどが示されなかったこともあり「どうすればいいの」と戸惑う職員の姿も見られた。
終了後の講評で小川院長は「今回は本部長を副院長に任せて現場を見させてもらった。反省点を参考にして、よりよい防災体制に生かしていきたい」と述べた。訓練を見守っていた伊那消防署員は「あたふたしていた。全員が防災マニュアルを知っていないと自分が何をすればいいのか分からず、指示を待っていることになる。次回に生かしてほしい」と述べた。
後期訓練は11月実施の予定。 -
行者にんにくを使って料理実習 村研究会など
南箕輪村の「行者にんにく研究会」(小林幸雄会長)と、農と食の大切さを考え活動する「輪の会」(木村歌子会長)は23日、村公民館調理室で行者にんにくを使った料理実習を開いた。両会員計10人に加え地元住民4人が参加し、調理を通じて同食材について学んだ。
料理実習は、行者にんにくに注目してもらうため、村内の生産者でつくる同研究会が「輪の会」に協力を呼び掛け、初めて計画。今が旬となる葉っぱの部分を使い、餃子(ぎょうざ)作りを体験した。
このほか、葉は豚肉炒めや、酢味噌和えにしたり、根はてんぷらにしたりして食べることができると紹介。食材に興味があって参加したという主婦(50)=神子柴=は「ニラの代用で料理ができそう。この機会にどういう食べ方ができるか学びたい」と話した。
研究会によると、ユリ課ネギ属の多年草の山菜である行者にんにくは、山で修行する行者がスタミナ源として食したのが名前の由来。繁殖力は弱く、発芽から生育するまで7、8年を要する。食べると血行をよくする働きがあるという。
調理するため行者にんにくの葉を刻む参加者(右) -
第1回みのわ祭り実行委員会
箕輪町のみのわ祭り実行委員会が21日夜、町役場であり、08年みのわ祭りについて話し合った。会長は、みのわ祭り検討委員会の会長を務めた唐沢修一さんが就任。検討委員会で提言された会場や日程を承認した。
みのわ祭りについては、07年の反省会であった「20年の節目を迎え、祭りを検討する時期にきている」「祭りは仕事のようで負担。上から言われて役員がやる祭りがこれ以上続くなら、やめたほうがよい」などの意見から、検討委員会(各種団体の代表や中学生含む公募委員ら32人)を立ち上げ、昨年11月から2月にかけて、運営方法などを検討。運営を担う実行員会は、行政主体から民間主体への移行を目指し「行政、民間の半々で構成し、会長は民間とする」ことを提言した。
08年みのわ祭り実行委員会は検討委員会の提言に基づき、公募による委員の募集や検討委員会メンバーから参加者を募り、構成。町の行政や民間団体、サークルなどに所属する26人が現在名を連ねている。今後、さらに実行委員会参加を呼び掛け拡充を図る方針。
第1回の実行委員会で承認した日時は、例年通り7月の最終土曜日で、7月26日。会場は国道153号バイパス(十沢交差点縲恂・輪町交番入口交差点)とバイパスから天竜公園へと続く道、バイパスの隣りを平行して走る工専道路。
ポスター図案などの募集方法は、昨年一般公募し、集まった点数が少なかったことを考慮し、「デザインを委託し、数点の候補から選ぶようにしてはどうか」「作品1点に絞らず、小学生などに書いてもらった作品をすべて張るのはどうか」などの意見が出た。
今回は、小学生から一般まで公募することに決定。賞金の代わりに図書券などの賞品に変更となった。唐沢会長は「小学校などに足を運び、協力を呼びかけたい」とした。
また、納涼花火大会の協賛金についても協議。協賛金は商工会役員を中心に事業者を回り集金してきたが、集金の負担が大きく、協賛金のあり方について検討委員会から実行委員会での検討が提言された。1戸500円で全戸から集めている市町村もある竏窒フ意見も検討会では出ていた。
実行委員会は他市町村の協賛金の集め方などを参考に、今後検討していく。
第2回の実行委員会は5月12日、午後7時から町役場で予定。 -
上伊那郡民生児童委員総会
辰野町、箕輪町、南箕輪村、宮田村、中川村、飯島町の民生・児童委員による上伊那郡民生児童委員協議会は22日、上伊那郡民生児童委員総会を箕輪町文化センターで開いた。
加藤寿一郎会長は「最近は高齢化が進み、一人暮しの高齢者や高齢者家庭からの相談も増えてきている。また住民のニーズも多様化してきている。私たちの基本的な姿勢は社会的奉仕の精神、基本的人権の尊重、職務場の地位の政治的中立、この三つをしっかり踏まえ活動していきたい」とあいさつ。
式典では9年勤続表彰があり、上伊那地方事務所の宮坂正巳所長から受賞者に表彰状が渡された。
受賞者代表の辰野町の三浦薫子さんは「これからも民生委員信条の隣人愛を持って社会福祉の増進に努めるという気持ちを持ち、日々過ごしていきたい」とあいさつした。
式典後には、長野県看護大学の北山秋雄教授が「児童・高齢者への虐待について 現状と課題」と題して講演した。 -
南箕輪村交通安全協会定期総会
2008年度南箕輪村交通安全協会定期総会は23日夜、村役場講堂であり、会員ら約80人が出席し、本年度の事業計画など5議案を承認した。役員改選では会長に飯島英之さん、副会長に清水貴男さん、会計に増沢宮雄さんを再任するなどした。
本年度は「交差点と交差点付近及び生活道路の事故防止」を村の重点事項とし、事故防止のための啓もう活動や環境整備に取り組むことを確認。飯島会長は再任のあいさつで、「1つでも村内の交通事故がなくなるよう誠心誠意、努力したい」と決意を述べた。
交通安全運動の重点としては、▽高齢者の交通事故防止▽飲酒運転の根絶▽シートベルト・チャイルドシート着用の徹底▽夕暮れ時と夜間の交通事故防止▽自転車安全利用の推進竏窒フ5つを上げた。
07年、村の交通事故発生状況は物損事故376件(前年比32件減)、人身事故100件(同20件増)、死者0人(同2人減)、けが人118人(同20人増)だった。
役員改選で自己紹介する新役員のみなさん -
南箕輪村消防団長 松沢武夫さん(53)
「今まで宮島団長の下で副団長を4年間やってきた。今まで学んできたことを自分が団長としてやっていかねばという自覚がある。団員の命を預かる身として、災害現場の中で事故を起こさないよう、幹部の人たちや行政と一緒になってやっていきたい」
村消防団に入団したのは20代前半で、地元田畑の第3分団1部の団員としてスタート。その後は中学時代に取り組んだブラスバンドの経験を生かそうと、先輩に誘われて本部ラッパ隊に所属し、ラッパ長まで務めた。35歳で一時退団し、4年前、49歳で副団長として復帰。そして、本年度4月、団長の職を任された。
一家の二男だったため、本来なら消防団に入団することはできなかったかもしれない竏秩B当時は団員確保がそれほど困難ではなかったため、1家族から1人が入団すればよかった。しかし、21歳の年、入団を予定していた人がキャンセルしたため自分に声が掛かり、入団することを決めたという。
「もともと消防団には、地域との密着力という魅力を感じていたので、入団するきっかけができてうれしかった。密着力は現代社会の方がよりいっそう消防団には大切なことだと思う。人とのつながりの中で、みんなが住んでいることを忘れてはいけない」
同時多発の大規模災害が起きたときなど、消防団は地域住民の生命、財産を守る、身近で頼れる存在であってほしいと願う。
「全国的に消防団の人員確保が課題となっている。『お酒を飲む人たちの集まり』『早朝の訓練が大変だ』など、新入団員の勧誘のときに断られてしまうことがあるが、大切なのは、自分たちの地域は自分たちで守りたいという気持ち」
昨年度からは、地域にある信州大学農学部の学生が入団し始めるなど、個人の防災意識の高まりを感じている。「在学中の短い期間だけだが、消防団の役割を理解し、一緒に活動できることがうれしい。団での経験を地元に帰ってから生かしてくれれば」
「各分団で定数割れしてしまっている状態。消防団の考えをもっと地域に浸透させていかねば。災害が起きてからではなく、いざというときは自分たちで守っていかねばという意識を持ってほしい」
田畑で鉄工所を経営する。趣味はスキー。23歳くらいから本格的に取り組み、現在は指導員の資格を持つ。南箕輪村スキークラブ会長として、スキーの魅力を地域に広めている。
(布袋宏之) -
中曽根のエドヒガンザクラ満開

箕輪町の中曽根公民館北のエドヒガンザクラ(権現桜)が満開となった。
樹齢千年といわれ県内にあるエドヒガンの巨木の3本の指に入り、県の天然記念物に指定されている。
県の内外から訪れた観光客やアマチュアカメラマンたちは、「すごいもんだな」「大きい」と感嘆し、咲き誇る権現桜の姿をカメラに収めている。 -
南箕輪村消防団・赤十字奉仕団 合同春季訓練

南箕輪村の消防団と赤十字奉仕団は20日、2008年度の合同春季訓練を大芝公園陸上競技場で開いた。消防団の団長以下135人、赤十字奉仕団の委員長以下78人が参加し、規律訓練や救命講習などで、一つひとつの動きをしっかりと確認し、有事に備えた。
式典で唐沢一直村長が「災害はいつ起きるか分からないもの。本日の訓練が災害を抑えるための第一歩となる」と式辞。松沢武夫団長は「団員が安全かつ、的確に行動するための大切な訓練。団員としての自覚を持って臨んでほしい」と訓示した。
春季訓練では、消防団員が規律訓練や分列行進などを実施。奉仕団員がAED(自動体外式除細動器)の取り扱い方法などを学んだ。
式典では、3月に東京であった自治体消防制度60周年記念式典で、村消防団が「消防団等地域活動表彰」を受賞したことを伝達した。 -
萱野高原山開き

箕輪町の萱野高原で20日、高原の山開きを行い、今シーズンの安全を祈願した。今季は10日早いオープンとなり、同日開催した「ミズバショウ祭り」には、高原の春を楽しもうと訪れた町内外の約100人が振る舞いのとん汁やおにぎりを味わったり、高原を散策したりして楽しんだ。
町観光協会主催の高原山開きには関係者約30人が出席し、神事を行った。観光協会長の平沢豊満町長は「萱野高原は住民や関係者のおかげで憩いの場として定着してきた。貴重な観光資源として、さらなるみなさんの協力で育ててほしい」とあいさつした。
標高1200メートル、伊那谷を一望できる萱野高原。高原を訪れた人たちは「箕輪町民謡を楽しむ会」による萱野高原音頭の踊りや、地元アマチュアバンド「たそがれシーラック」の演奏などを満喫し、700株の水芭蕉が群生するなどの高原を散策した。水芭蕉は5月上旬まで楽しめるという。
この日は、「信州かやの山荘」がオープン、11月10日までの営業を開始した。宿泊予約などの問い合わせは、(TEL0265・79・2822)へ。 -
「春らんまんのみはらしまつり」にぎわう
伊那市西箕輪の農業公園「みはらしファーム」は20日、地元産の花や野菜の販売、スタンプラリーなど各種イベントを繰り広げる「春らんまんのみはらしまつり」を行った。県内外から多くの家族連れらが同施設に集まり、にぎわいをみせた。
恒例の「アスパラ釣り」「一貫目ゲーム」「シイタケ打ち」な10数種類の催しを開催。「ポン菓子を作ろう」は随時あり、大きな音とともに米が菓子に変るのを楽しみ、もちつき大会は、子どもたちが協力して作ったもちを来場者に配るなどして、盛り上がった。
「ジャンケンに勝てたら野菜を激安奉仕」と急きょ開かれたイベントなどもあった -
入園者数700万人突破 高遠城址公園

「天下第一の桜」として有名な伊那市高遠町の高遠城址(し)公園の入場者数が20日午後、1983(昭和58)年の有料化以来累計700万人を突破した。市や市観光協会などは節目を祝うため、該当者と前後2人ずつに記念品を贈った。
700万人目は家族5人で訪れた山梨県北杜市の小学3年生、小沢史遠(しおん)君(8つ)。父の修一さん(31)が地元特産のアリストロメリアの花束や「高遠さくらホテルペア宿泊券」などを受け取った=写真。修一さんは「びっくりしている」、史遠君も「うれしい」と笑顔だった。
市観光協会によると、園内のタカトオコヒガンザクラは散り始めで、23日ごろまで楽しめる。今季の入園者数は30万人を見込んでいる。 -
中川村消防団、村直営診療所と南消防署と連携し、患者のトリアージ救急搬送までを訓練

中川村消防団(団員167人、下平道弘団長)は20日、観閲式を開き、村営の片切診療所(南宗人院長)と伊南行政組合南消防署(田中利寛署長)と連携した患者の搬送訓練を展開した。診療所の南医師が患者の重傷度を判断し、搬送先の病院を指定。南署の救急隊が救急車で搬送し、村消防団の救護班は医師の判断に基づき判別された患者らの手当てに当たる。消防団、病院、消防署が連携して、こうした訓練を行うのは上伊那でも初めて。近隣病院の医師確保が深刻化する中、今後は重症患者の搬送に時間を要するケースが出てくると想定されるため、連携のもとで患者のニーズを的確に把握し、早期救出につなげようというのが今回の訓練の狙いだ。
◇ ◇
各地で病院の医師不足が深刻化する中、中川村から最も近い駒ケ根市の昭和伊南総合病院でも、産婦人科、整形外科、小児科の医師不足がいまだ解消しない状況。現状では「重症患者の受け入れは困難」との判断から、重症患者の救急搬送は伊那市の伊那中央病院や飯田市立の各病院に搬送してもらう方針をとっている。
しかし、同村から伊那や飯田まで患者を搬送した場合、想定される所要時間は少なくとも1時間。一方、重症の救急搬送は、1分1秒が患者の生命を左右する。
そのため重症患者を少しでも早く搬送するには▽患者の緊急性を見極めるトリアージ▽早期対処▽搬送する消防署との連携竏窒ェ必要と認識。今回の訓練が実現した。
訓練に参加した片切診療所の南医師(54)は「実際に訓練をしてみて、反省する点もあったので、いい機会になった。今後に生かしたい」と話していた。
また、村消防団の下平団長(48)は「地域の医療体制が十分とは言えない中、中規模、大規模災害に限らず、今後ますます連携が大切になると思う」と話していた。 -
世界的ビオラ奏者の兎束俊之さんが、宮田村の自宅でこけら落としコンサートを開催
宮田村を拠点として活動する弦楽合奏団「アンサンブル信州in宮田」の音楽芸術監督で世界的なビオラ奏者・兎束俊之さん(60)が20日、同村駒ケ原に建てた自宅でオープニングコンサートを開いた。コンサートには兎束さんと交友が深く、ともに演奏活動を展開してきたピアノ奏者の石井克典さんも駆け着け、「信濃の国」ほか、クラシックの名曲数曲を披露=写真。集まった観客を魅了した。
音楽文化の発信地としていきたい竏窒ニの願いを込め、この地に自宅を設けた兎束さん。最初の演奏会には、アンサンブル信州を育てる会の委員のほか、村関係者、住民など約60人が集まった。
兎束さんは「半世紀、ビオラを弾いて生きてきた。逆に言えばこのことしか分からないということなので『この村はこういう風に生活しているんだ』ということを指導していただき、生きていきたいと思うのでよろしくお願いします」と語り、石井さんとともに演奏を披露。中でも、ワーグナーの「マイスタージンガー前奏曲」は、兎束さんの知人・鈴木行一さんが兎束さんのために編曲しており、いつの間にか「信濃の国」に変化。凝った演出に、聴衆は盛んに拍手を送った。
また、この日は全国各地で活動する演奏家が兎束さんのために駆け、それぞれに演奏を披露。1曲ごと演奏が終わるたびに盛大な拍手を送った。 -
宮田村の白心寺で第19回白心寺花まつり
宮田村町2区の浄土宗・白心寺(山田弘之住職)で20日、第19回花まつりが開かれた。稚児行列には地元の子ども約30人が参加。お釈迦様を乗せた象の乗り物を引きながら町内を巡り歩き、町民に甘茶を振舞った=写真。
地域の子どもたちのためにできる行事を竏窒ニ、先代住職の時から始まった花まつり。毎年工夫を重ねる中で、子どもが楽しめる出店やゲーム、アトラクションも増やしてきた。また、村民も寺の取り組みに主体的に協力しており、壮青年部の部長を務める後藤孝浩さん(47)=新町=は「地域の若い人たちも参加してくれるようになってきた。来年は20周年を迎えるため、稚児衣装を来て稚児行列をしたり、内容を充実させたい」と語る。
また、山田住職(46)は「先代から取り組んできてくれた人たちの思いを引き継ぐ形で、今もまつりを続けている。子供たちが少なくなっている中、明るく、楽しく、仲良くが一番大切なことだと思う」と話していた。 -
日本棋院上伊那支部囲碁大会

日本棋院上伊那支部(神田福治支部長)は20日、総会記念囲碁大会を伊那市のサンライフ伊那で開いた。小学4年生から80歳代までの32人が参加。3段以上のA級と2段以下のB級の2部門に分かれ、1人5局ずつ対局する変則リーグ戦で順位を競った=写真。
上位は次の皆さん。
▼A級(1)荻原理機弥(箕輪町、5段)(2)福沢秀伸(伊那市、5段)(3)小林利美(伊那市、3段)(4)広瀬三信(3段)▼B級(1)田中宏道(西春近北小4年、2段)(2)渡部光彦(宮田村、2段)(3)山崎洸(南箕輪中2年、2段)(4)横田勉(飯島町、初段) -
手良地区大運動会

伊那市の手良公民館は20日、第30回手良地区大運動会を手良小学校グラウンドで開いた。多くの住民が家族連れで参加し、満開のサクラの下で元気いっぱいに競技を楽しんだ。
むかで競走、満水リレー、玉入れ、障害物競走など、趣向を凝らしたたくさんの競技が行われたほか、30年前には各地の運動会でよく行われていたという、自転車をゆっくり走らせる「スロー自転車競走」も復活して話題を呼んだ。地区対抗の綱引きでは力の入った接戦が展開され、応援席からも大きな声援が飛ぶなど、会場は熱気に包まれた=写真。
熱戦の結果、中坪地区が昨年に続いて連覇を果たした。
結果は次の通り(カッコ内は得点)。
(1)中坪(57)(2)八ツ手(45)(3)下手良(37)(4)野口(25) -
高尾町社協花見

伊那市の高尾町(守屋武夫総代)と高尾町社会福祉協議会「ふれあい高尾会」(西村カツ子会長)は19日、満開のサクラが咲く高尾公園で花見を楽しんだ。約20年前から続く毎年の恒例行事。住民約60人が参加し、お年寄りも子どもも入り混じってにぎやかに楽しいふれあいのひとときを過ごした=写真。
参加者は降り注ぐ暖かい日差しの下、ひらひらと舞い散るサクラの花びらを見ながら、社協役員や住民らが持ち寄った手作りのご馳走に舌鼓を打ち、歌やハーモニカ演奏、大型紙芝居などの余興に興じていた。 -
南箕輪中卒業生 村の松くい虫対策に募金寄付
南箕輪村の南箕輪中学校を1950(昭和25)年度に卒業した同年会は22日、村の松くい虫対策の資金にしてほしいと、同年会で集めた3万3055円を村森林セラピー協議会に寄付した。同年会幹事長の小林広幸さん(72)=北殿=が役場を訪れ、荻原文博会長に手渡した。
寄付は、古稀の記念で大芝高原多目的広場に植えたコヒガンザクラの木の下で同年会を開こうと15日、同所に村内外から同年生36人が集まったのがきっかけ。席上で村の松くい虫対策へ募金をしようと話が持ち上がり、寄付金を集めたという。
小林さんは「寄付金を有効に使い、森林整備をしながら対策を取っていってもらいたい」と期待。村は大芝高原のアカマツの松くい虫対策として06年度から、薬剤の樹幹注入を毎年度実施していて、本年度は事業費1千万円で、約600本のアカマツに施す予定だ。
荻原会長に寄付金を手渡す小林さん(左) -
箕輪町図書館19年度利用統計
箕輪町図書館が07年度の図書館利用統計を発表した。
箕輪町図書館の蔵書数(3月31日現在)は6万8428冊。
07年度貸し出し冊数は12万1986冊(前年度比3%減)で、町民1人当たり4・6冊の貸し出しとなった。
内訳は絵本4万6524冊(前年比1%減、小数点以下四捨五入以下同)、児童書2万1177冊(前年度比2%増)、文芸書1万5618冊(前年度比15%減)、ビデオ7519本(前年度比16%減)、雑誌1万0055冊(前年度比12%増)など。
箕輪町図書館での人気の本は▽一般書(コミック類は除く)=(1)「東京 07」(まっぷる)昭文社(2)「還らざる道」内田康夫(著)、祥伝社(3)「日本語の故郷一唱歌ゑほん」小沢吉良(絵)、小学館▽児童書(コミック類は除く)=(1)「かいけつゾロリのきょうふのプレゼント」原ゆたか(作・絵)、ポプラ社(2)「かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん」原ゆたか(作・絵)、ポプラ社(3)「かいけつゾロリとなぞのひこうき」原ゆたか(作・絵)、ポプラ社▽絵本=(1)「がたんごとんがたんごとん」安西水丸(作)、福音館書店(2)「どうぶつのおかあさん」小森厚(文)、福音館書店(3)「ころころころ」元永定正(作)、福音館書店竏秩B -
オーケストラと共演 南箕輪村から3小中学生出場
5月4日、大阪である、第20回フリューゲル・ピアノ・コンチェルト・フェスティバル(日本アーティストビューロー主催)の全国大会に、南箕輪村の望月音楽教室伊那レッスン室から村内の小中学生3人が出場する。大会はプロのオーケストラと共演することができるため、それぞれ本番を楽しみに練習している。
出場するのはシニア・スチューデント・コンチェルト部門の大塚智哉君(13)=南箕輪中2=、リトル・コンチェルト部門の米窪拓哉君(10)=南箕輪小5=、藤沢優花さん(10)=同4=。3人は部門別の課題曲集から選曲し、全国区テープ審査、地区本選大会を勝ち上がり、「グローバルフィルハーモニー管弦楽団」と共演できる全国大会出場を決めた。
4年連続出場の大塚君は、ベートーベン「ソナタ第8番ハ短調Op. 13『悲愴』より第1楽章」で挑戦。「オーケストラと共演できることが何より楽しみ。この大会のために練習してきた」と意気込んでいる。
初出場の米窪君は「緊張しそうだけど、これまでやってきたことを発揮できればうれしい。全国大会に出場できるだけで夢のよう」。ベートーベン「ソナチネ第5番ト長調より第1楽章」を大会で演奏する。
藤沢さんの演奏曲はブルグミュラー「『25のやさしい練習曲』より やさしい花」。2年連続出場で、「前回よりうまくできるよう頑張りたい。早くプロの人たちと演奏したい」と本番を楽しみにしている。
全国大会は全4部門に約100人が出場。3人を指導する望月音楽教室の望月玲子さん(主宰)と、平林千枝さんは「人の心に届く、春の日差しのような暖かな音でピアノを奏でてきて」と期待している。
全国大会出場の証明書を手にする大塚君、米窪君、藤沢さん(左から)。 -
上伊那北部消防連絡協議会定期総会
辰野町、箕輪町、南箕輪村の消防団でつくる上伊那北部消防連絡協議会は18日、定期総会を箕輪町の地域交流センターで開き、08年度の事業計画案や予算案を承認した。
08年度の主な事業は次の通り
▽水防訓練(5月18日)▽幹部訓練(5月31日)▽県ポンプ操作大会激励会(7月27日)▽正副分団長研修(9月6日)▽ラッパ訓練▽幹事会竏窒ネど。
08年度の同協議会負担金は辰野町16万4800円、南箕輪村13万8200円、箕輪町17万7千円で、計48万円。
08年度の上伊那北部消防連絡協議会の役員は次のみなさん
▽会長=平沢久一(箕輪町消防団長)▽副会長=武居保男(辰野町消防団長)、松沢武夫(南箕輪村消防団長)▽評議員=小松孝寿(箕輪町消防団副団長)、古村幹夫(辰野町消防団副団長)、藤田政幸(南箕輪村消防団副団長)▽幹事長=倉田昌(箕輪町消防団本部長)▽幹事=林国久(辰野町消防団本部長)、唐沢英樹(南箕輪村消防団本部長)、上田康夫(辰野町消防団消防主任)、宮下裕司(南箕輪村消防団消防主任)▽書記=滝沢光義(箕輪町消防団消防主任)▽参与=内山朝高(箕輪消防署長)、丸山均(辰野消防署長)、加藤純治(南箕輪村役場総務課長)竏秩B -
染織作家・小山憲市展

上田市在住の上田紬の染織作家、小山憲市さんの展覧会が19日、伊那市生涯学習センター2階の展示ギャラリーで始まった。
県内外で展覧会を開いているが、南信では伊那で2度目。
遠目には一色に見える着尺は、近くで見ると何色もの糸で織ってあり、それぞれに質感も異なる。「着る人を引き出せるシンプルな着物を作りたい」と着心地も含め色、糸、質感にこだわり、じわじわと味わいが出る作品づくりをしている。今回は訪問着、帯、着尺など約50点がある。
「着物は実用着からファッションに替わり、おしゃれ感も違ってきている。洋服では出せないその人らしさを着物で出したい。今の時代に作りたいものを探りながらやっている」と小山さん。「ギャラリーなので気楽に見て、触って、知ってほしい。何か心に残って帰ってもらえたらうれしい」と話している。
展覧会は20日まで。午前9時縲恁゚後4時。 -
エッセー集「風景の中の人びと 伊那谷の里山今昔点描」出版
箕輪町
赤羽稔章さん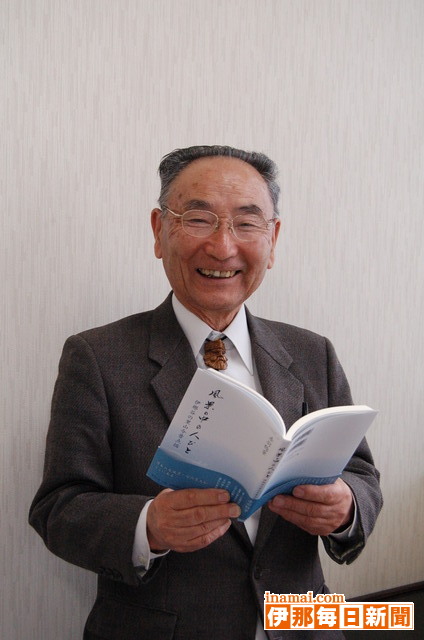
「一番印象にあるのが農村の戦前戦後の風景。今となっては全てが思い出になるが、そこには自然の風景があり、セミが鳴いていたり、ニワトリの声がしたり、音も自然も必ずくっついている。戦争中で食べるものもない状況だったが、それでも今とは違う温かな暮らしがあった。それを書きたいと思った」
生まれ育った伊那市高遠町荊口の風景、子ども時代の思い出、父母との関わり、今の暮らしの中での思いや散歩のことなどをつづったエッセー集「風景の中の人びと 伊那谷の里山今昔点描」を出版した。
長野県内の公立小中学校で教員を勤め退職。現在は長野県陸上競技協会上伊那支部陸協副会長(日本陸連S級公認審判員)を務めている。
出版は今回が3冊目となる。1冊目は「実南天」(1998年)、2冊目は「残月の小道」(2003年)。いずれもエッセー集で、「実南天」は教員時代の作品や妻の看病の様子、「残月の小道」は小さいころのこと、教わったことなどを自然と結びつけて書いた。
「何かもう1回出してみたい」。そんな思いで06年の始め、高遠のころのことを書いた3、4編の短いエッセーを手に東京の郁朋社を訪ねた。「やりませんか」という言葉をもらい出版を決め、同年の暮れころから本格的に執筆を始めた。
「うそは書けない」と高遠町誌、三義村誌などを参照し、取材もし、表現にもかなり神経を使った。
「小さいとき、夕焼けはいいな、山の中はきれいだなと感じていた。山の中で子どもが大勢いたわけではない。小学校の同級生はたった5人。孤独ではないけど、寂しかったんだと思う。寂しいから自然の美しさに引かれ、感じたのかもしれない」
ずっと心に残る自然の美しさ、心の風景が全編を通じてつづられている。
「160ページの本にするのは大変だったけど、仕上がった本を手にして、これが本かなと思った」と満足の1冊になった。
教員時代、文集に寄せた作文を読み、涙してくれた同僚がいた。「ぼくの作品を読んで感動してくれる人がいるなら書いてみよう」。そう思い、始めた執筆。何かを表現したいと、作詞や書にも取り組んでいる。
手元に届いた真新しい本の題字は自らが書いた。4月下旬、全国の書店に並ぶ。(村上裕子) -
春山登山シーズンに合わせ、中アで遭難救助訓練

春登山が増える時期に合わせて、市民ボランティアでつくる中央アルプス山岳救助隊(唐木真澄会長)と駒ケ根警察署県警山岳救助隊が19日、中央アルプス千畳敷付近で遭難救助訓練を実施した。18人の隊員が参加し、自分自身の身を守りながら遭難者を安全に救助する方法を確認した。
訓練は普段は個々に活動している個々の隊員が雪山での救助に関する知識を共有するとともに、意志疎通を図ることなどを目的としている。例年5月にしていたが、今年は残雪の多い4月に早めた。
今年は滑落事故の発生を想定し、捜索、救助、搬送までを訓練。遭難者を搬送する訓練では、専門的な機材を用いず、身近な装備品を代用して搬送する方法を用いた訓練を展開し、遭難者を搬送する時には自分たち自身がなだれに巻き込まれないような安全な場所を確保すること、搬送している間も声をかけるなどして遭難者の顔色を確認しながら行うことなどを確認した。
唐木隊長(64)=伊那市西春近=は「今年、中アは残雪もかなり多い。春登山などで入山する人は天候を見極め、重装備で臨んでほしい」と話していた。
昨年駒ケ根警察署管内で発生した遭難は死亡事故2件を含む6件。千畳敷カール東側下斜面は絶えず雪面が凍結しているが、南アルプスの眺望が良く、写真愛好家などが入り込むことも増えており、滑落事故も発生している。また今年は特に残雪が多く、雪庇(せっぴ)となっている場所も多いという。 -
松島神社例大祭 19、20日の両日にぎわう
箕輪町松島区の松島神社例大祭が19、20日の両日、同神社などであった。地元小学生が本堂で「浦安の舞」を奉納したり、鼓笛隊が区内を練り歩いたりした。バナナチョコレートや焼きぞばなどの露店も境内に並び、両日にぎわった。
区内の女子児童12人が巫女(みこ)の衣装をまとい6人1組ずつに分かれ、「すず」「扇」の舞をそれぞれ奉納。ビデオカメラなどを片手に持った保護者ら約40人が本堂に集まり、舞姫たちのかわいらしい姿を笑顔で見守った。
本堂で「浦安の舞」を披露する舞姫たち -
伊那谷新酒祭り

伊那谷の9つの酒蔵が持ち寄った自慢の新酒を飲み比べる「第6回伊那谷新酒祭り」が19日、満開の桜に彩られた伊那市の春日城址公園で開かれた。地元の商店主らでつくる「ルネッサンス西町の会」(向山等会長)主催。
訪れた人たちは1枚につきグラス1杯の酒を味わえるチケット(7枚つづり千円、3枚つづり500円)を買い求めると、各酒造メーカーがテントにずらりと並べた銘柄の中からどれを飲もうかと品定め。メーカーの担当者に「こっちの方が辛口ですよ」などとアドバイスを受けて酒を選ぶと、一口ずつじっくりと味わった。飲み終わると早速次の銘柄の酒を選んで注いでもらい、微妙に違う味や香りを比べて楽しんでいた=写真。
「ルネッサンス西町の会」会長の向山さんは「今年は天気も良く、風も穏やかで絶好の日和だ。桜の下でおいしい酒を存分に味わってほしい」と話した。
きき酒コンテストのほか、風船パフォーマンスのゴンベエワールド、小出太鼓、アフリカンドラム演奏などのアトラクションもあり、雰囲気を盛り上げた。
22/(月)
