-
愛の鐘竣工 22日イベント

南箕輪村の大芝高原内にある愛の鐘の改修工事が完了しました。
22日には恋人が愛を誓うイベントが行われます。
村では今年の7月から愛の鐘の整備を行ってきました。
事業費はおよそ300万円となっています。
改修工事は、台座を新しくしたもので御影石が使われています。
その周りには花壇も整備されました。
愛の鐘は恋人岬で知られる静岡県の旧土肥町、現在の伊豆市と姉妹都市を結んだ翌年の平成4年に旧土肥町から贈られました。
22日土曜日にはカップルなどに恋人宣言証を発行するイベントが行われることになっています。 -
蜜ロウで来年の干支「巳」置物づくり

今年も残すところ10日余りとなりました。
伊那市御園の小松養蜂園では来年の干支の置物作りが行われています。
小松養蜂園の小松実治さんは、18年前から蜜ロウで干支の置物を作っています
作業は、今月初めから始まっていて18日は、毎年この作業を手伝っている障害者社会就労センター「ゆめわーく」の利用者が応援に駆けつけました。
小松養蜂園で使う蜂の巣箱をゆめわーくの利用者が作っていることが縁で毎年作業を手伝っています。
クレヨンとロウを溶かし、専用の型に流し込み2時間ほどかけて固めます。
ロウが固まった後、型を外して完成です。
利用者たちは小松養蜂園の小松実治さんから作り方を教わりながら作業にあたっていました。
今年は、仙丈ヶ岳をバックにヘビが2匹いるものやヘビが帽子をかぶったものなど3種類、およそ300個作る予定です。
作業は22日まで行われることになっていて、完成した置物は、ゆめわーくの利用者が日頃おせわになっている人たちに贈るということです。 -
クリスマス会で虹の会が読み聞かせ
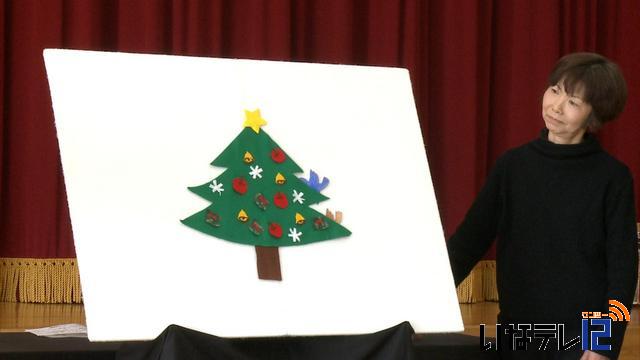
箕輪町公民館松島分館の子育て学級スマイルクラブのクリスマス会が17日開かれ、箕輪町図書館のボランティアグループ「虹の会」が読み聞かせなどを行いました。
クリスマス会は松島コミュニティセンターで開かれ、10組ほどの親子が参加しました。
虹の会は、箕輪町図書館の読み聞かせボランティアグループで、月に1度図書館で読み聞かせを行っているほか、スマイルクラブのクリスマス会でも毎年読み聞かせを行っています。
今年は小さや子どもたちのために、パネルシアターなど一緒に楽しめるものを選んだということです。
子ども達は掛け声をかけたり体を動かすなどして楽しんでいました。
虹の会では、「小さな子どもも楽しんでよく聞いてくれ、やりがいがありました」と話していました。 -
ぽかぽか陽気 最高気温11.9度

16日の伊那地域は最高気温11.9度と、11月下旬並みの暖かい一日となりました。
この日の伊那地域の最高気温は11.9度まで上がり、11月下旬並みの暖かさとなりました。
伊那市の春日公園では、子ども達がいつもより薄着で遊んでいました。
長野地方気象台によりますと、これは、低気圧が日本海上空を通過し、暖かく湿った空気が流れ込んだことによるものだということです。
17日の午後からは、再び冬型の気圧配置となり、18日以降は平年並みか平年より寒くなりそうだということです。 -
昭和11年会 村に寄付

南箕輪村の昭和11年会は14日、村に5万円を寄付しました。
14日は、代表の太田茂さんと堀始春さんが役場を訪れ、唐木一直村長に寄付金を手渡しました。
昭和11年会は、昭和11年に南箕輪尋常小学校に入学したおよそ100人でつくる会で(卒業時は南箕輪国民学校)、2年に1回のペースで同年会を開いていました。
しかし、高齢により会うことができなくなったため今年10月に解散しました。
今回は、解散に伴い会費の残額5万円を村に寄付するものです。
太田さんは「同級生とは気を許せる仲。これからもお互いに声をかけ合っていきたい」と話していました。 -
上古田地域に新水源

箕輪町は、大雨などの際に水道水が濁ることがあった上古田地域に安定した水の供給を行おうと、新たな水源となる井戸2基を完成させました。
14日は、井戸の通水式が行われ、関係者およそ20人が完成を祝いました。
上古田地域の水源は、湧水と表流水のため大雨が降ると水の濁りが増し、家庭で使う水道水が濁ることがありました。
町では、平成18年豪雨災害の後、別の水源についての調査・研究を行っていて、今年10月に2基の井戸が完成しました。
深さ100メートルと50メートルの井戸で、1日にあわせて190立方メートルの水をくみ上げることができます。
通水式の後参加者らは、くみ上げた水が運ばれてくる上古田浄水場を見学し、業者から施設についての説明を受けていました。
今後は、これまでの湧水と新たな井戸水で上古田全戸と中原の一部、あわせておよそ300世帯に水を供給します。 -
年賀はがき受け付け開始

今年も残すところあと半月となりました。日本郵便株式会社は、15日から年賀はがきの受け付けを開始しました。
伊那郵便局には年賀はがき投函用の特設ポストが設置され、訪れた人が早速投函していました。
伊那郵便局管内では、今年の年賀はがきは、去年より1.4%、4万通多い、およそ291万通を予想していて、引き受けのピークは27日頃になりそうだということです。
25日までに投函した年賀はがきは元旦の配達に間に合うということで、伊那郵便局では早めの投函を呼びかけています。 -
最優秀賞に上牧20会

地域の環境整備や福祉活動、伝統芸能の伝承などに取り組んでいる個人や団体に贈られる伊那市地域づくり大賞の今年度の最優秀賞に上牧20会が選ばれました。
最優秀賞を受賞した上牧20会は地区の高齢者や民生委員など27人で組織し平成12年に発足しました。
地域の園児や小学生と交流したり、花壇の整備などの活動を行っています。
10日は、伊那市役所で表彰式が行われ優秀賞などを受賞した7団体と個人2人に白鳥孝伊那市長から表彰状などが手渡されました。
伊那市地域づくり大賞は地域の活性化を目的に各地域で様々な活動に取り組む団体などを表彰するもので平成22年度から行われています。
上牧20会の代表の小沢つね子さんは「高齢者が多くなる中で少しでもお互いに交流できる場を増やしていきたい」と話していました。
白鳥市長は「こうした活動が一つでも増えていく事が大事。みなさんの取り組みが市民の模範となってほしい」と話していました。 -
高遠中の生徒が車いす寄贈

伊那市高遠町の高遠中学校の生徒が10日、特別養護老人ホーム「さくらの里」に車いす2台を寄贈しました。
10日は、高遠中学校3年の吉田ひなたさんと古村翔也君がさくらの里を訪れ、車いすを寄贈しました。
高遠中学校では、年に3回地域住民にアルミ缶回収を呼びかけ通学途中に集めています。
回収したアルミ缶を換金して車いすをさくらの里に贈るのは今年で4年目です。
吉田さんは「地域の人たちの協力で集まったお金で購入しました。ぜひ使ってください」と挨拶しました。
さくらの里では「車いすは利用頻度も高いので大変助かります。有効に使わせていただきます」と感謝していました。 -
世相を映す変わり雛

今年1年の世相を映す変わり雛が、南箕輪村神子柴の岩月人形センターに飾られています。
「梅ちゃん先生高視聴率雛」
朝の連続ドラマ梅ちゃん先生が大ブレイクしました。
「ロンドン五輪大健闘雛」
ロンドンオリンピックで、日本人選手が38個のメダルを獲得しました。
「ノーベル医学賞受賞雛」
IPS細胞の開発で山中伸弥教授がノーベル賞を受賞しました。
会場には、今年の世相を映す変わり雛6体が並んでいます。
岩月人形センターでは、開店以来毎年変わり雛の展示を行っていて、他にも平成19年からのものを並べています。
展示は、来年3月3日までとなっています。 -
町消防団第6分団統合40周年

箕輪町の長岡・北小河内・南小河内で組織する箕輪町消防団第6分団の統合40周年記念式典が9日、南小河内公民館で開かれました。
12月1日に統合40周年を迎えたことから長岡・北小河内・南小河内で組織する第6分団統合40周年記念式典が開かれました。
式には町の関係者やOBなど110人が出席しました。
小笠原岳大分団長は「今後も地域の安全・安心に務め第6分団の誇りを胸に団員が一丸となって消防団活動に精進したい」と挨拶しました。
また、初代分団長を務めた清水俊彦さんは「発足当初は120人の規模でスタートし地域の皆さんに盛り上げていただいた。」と当時を振り返り、「今後も地域のみなさんに期待に答えられるよう頑張ってほしい」と激励していました。
第6分団は現在30人の団員で活動しています。
今年行われた県のポンプ操法大会自動車ポンプ車操法の部で初優勝を果たすなどの成績を収めています。 -
高遠美術館に響く生の音楽堪能

伊那市のサン工業(株)の社員教育の一環で二胡&ポップスコンサートが8日、伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれました。
サン工業では社員教育の一環として、生の音楽を聴こうと毎年コンサートを開いています。
出演したのは、歌手で元H2Oの赤塩正樹さんです。
赤塩さんは駒ヶ根市在住で、サン工業が行っている英語教育の講師をしていることが縁で今回出演することになりました。
赤塩さんはジャズやクリスマスソングなどを歌ったほか、H2Oのヒット曲も披露しました。
会場には社員や地域住民などおよそ140人が訪れ、美術館に響くプロの歌声を堪能していました。 -
赤穂浪士が交通安全呼びかけ

11日から年末の交通安全運動がはじまりました。
伊那市役所前のナイスロードでは、山寺義士踊り保存会のメンバーが赤穂浪士の姿で道行くドラーバーに交通安全を呼びかけました。
11日は、山寺義士踊り保存会のメンバーや伊那交通安全協会など、およそ60人が参加しました。
交通安全運動は飲酒の機会が増えたり、路面が凍結して事故が起きやすいこの時期に毎年行われています。
運動の重点は高齢者の事故防止、飲酒運転の根絶などとなっています。
参加者たちは、ドライバーに「安全運転でお願いします。」などと呼びかけながら啓発チラシを配っていました。
伊那警察署管内の今年1月から12月10日までの交通死亡事故件数は5件で6人が亡くなっています。
年末の交通安全運動は12月31日まで行われます。 -
桜の冬支度本格化

11日の伊那地域の最低気温はマイナス8.7度とこの冬一番の寒さとなりました。
伊那市の高遠城址公園では来年の観桜期に向け桜の冬支度が本格化しています。
11日は、桜守の稲辺謙次郎さんら3人が高所作業車を使って作業を行っていました。
冬支度は、毎年11月中旬からはじまり公園内にある桜およそ1500本の手入れを行います。
作業は雪の重みで枝が折れないよう枯れた枝を払い、切り口には殺菌防腐剤が塗られていました。
この他にも枝を支える支柱の取り替えや木を叩いて中に空洞がないかチェックしていました。
稲辺さんはこの時期に桜の手入れをすることが大切と話していました。
高所作業車を使った作業は今月20日まで行われることになっています。
年明けからは市内各地の桜の木を見て回るということです。 -
園児がツリーの飾りつけ

クリスマスを前に、南箕輪村北部保育園の園児が10日、クリスマスツリーの飾りつけをしました。
この日は園児90人が、リズム室に置かれたツリーにクリスマス飾りを取り付けました。
園児は気に入った飾りを手に持ち、高いところは保育士に抱え上げてもらうなどして取り付けていました。
北部保育園のクリスマス会は21日に予定されています。 -
信大生が野沢菜漬けを学ぶ

南箕輪村の信州大学農学部の学生が9日、村内の農家の女性から野沢菜の漬け方を教わりました。
漬け方を教わったのは信大農学部の地域交流サークル「かーみやん」のメンバー6人です。
かーみやんと村の農家女性でつくる南箕輪村輪の会は農業を通して交流をしています。
その中で、学生から野沢菜漬けを教えてもらいたいと要望があり3年前からメンバーに漬け方を教えてもらっています。
輪の会の畑で8日、収穫した野沢菜27キロを使い、細かく刻んで漬ける切漬けと、そのまま漬ける長漬けの2種類の漬け方を教わりました。
学生たちは塩加減や葉の並べ方などメンバーから手ほどきを受け作業をしていました。
野沢菜漬け以外にも大根や白菜の漬け方なども教わりました。
9日漬けた野沢菜漬けはお正月頃に食べごろになるということです。 -
積雪で子ども達が雪遊び

8日の伊那地域は、今年初めて平地にも雪が積もりました。
南箕輪村の大芝公園では、雪遊びをする子ども達の姿が見られました。
長野地方気象台によりますと、9日の夜から10日の朝にかけて冬型の気圧配置が強まるため、県内全域で雪の降るところが多くなりそうだということです。 -
読書感想文 小中学生18人を表彰

上伊那の小中学生を対象にした読書感想文のコンクール、ニシザワ文芸コンクールの表彰式が8日、伊那市の創造館で行われました。
この日は受賞した18人の小中学生に、(株)ニシザワの荒木康雄社長から賞状が手渡されました。
最優秀賞には、小学生低学年の部に箕輪東小2年の福澤怜久くん、高学年の部に赤穂小6年の林和花さん、中学生の部に東部中1年の古畑花音さんが選ばれました。
コンクールは、伊那市で本屋として創業した(株)ニシザワが、地域の小中学生に本から様々なことを学んでもらいたいと毎年開いているもので、今年で9回目になります。
今年は上伊那郡内の小中学校27校から、過去最高の1430点の応募がありました。
荒木社長は「本をたくさん読んで、いろんなことを学び、文章にすることで自分の気づきを持ってもらいたい」と話していました。 -
ふるさとCM大賞NAGANO 西箕輪中知事賞

長野朝日放送が主催するCMコンテスト「ふるさとCM大賞NAGANO」で、西箕輪中学校が制作した伊那市のCMが2位にあたる知事賞に選ばれました。
西箕輪中学校のCMは、総合学習でCM制作コースを選んだ3年生12人が制作しました。
今年5月から取り掛かり、およそ4か月かけてつくりました。
コンテストは、市町村が地元の魅力をPRするもので、伊那市の作品として応募した西箕輪中の作品は、見事知事賞を受賞しました。
CMのタイトルは「ウマウマ動画」馬刺しの魅力をPRするものです。
構成から撮影までを全て生徒が行いました。
今年の、コンテストには県内から91作品の応募がありました。
伊那市のCMが知事賞に選ばれたのは今回が初めてということです。
西箕輪中生徒が制作したCMは、長野朝日放送で来年50回放送されることになっています。 -
南箕輪村営農センター 園児にりんごプレゼント

南箕輪村営農センターは、地域でとれたりんご「サンふじ」を7日、村内の5つの保育園にプレゼントしました。
このうち中部保育園には営農センターの宮下勝美会長ら関係者およそ10人が訪れ、園児1人ひとりにりんごを手渡しました。
りんごのプレゼントは、消費拡大と地産地消を目的に平成17年から行っています。
サンふじは、太陽が沢山あたるよう袋をかけず栽培するため、甘味が増すいうことです。
村と営農センターでは、サンふじの栽培に力を入れていて、りんごを栽培した田中實さんは園児の笑顔に喜んでいました。
園児らは、もらったりんごを大切に抱えて友達と見せ合っていました。
営農センターでは、村内5つの保育園に全部で780個のりんごを贈った他、小中学校にもあわせて800個プレゼントするということです。 -
北園高校保護者とそば打ちで交流

東京の北園高校の保護者らが2日、伊那市西春近を訪れ、そば打ち体験をしました。
北園高校は、伊那市西春近自治協議会と森林の里親促進事業の協定を結んでいます。
協定では北園高校の生徒が西春近の区有林などを整備することになっています。
そば打ち体験は生徒が活動している西春近について保護者など関係者に知ってもらおうと企画されました。
2日はおよそ30人が参加し、地元の住民に教わりながら、そばを打っていました。
森林の里親促進事業の協定は去年5月に結ばれ、今年春には、生徒およそ300人が桜の木を植える活動を行っています。
訪れた保護者は、「自然豊かな伊那市で活動できることは、学生にとって貴重な体験。
地元の人たちもあたたかく、いい所だと思った。」と話していました。 -
鈴木福君の像お披露目

伊那市の子ども大使に任命されている子役タレント、鈴木福君の等身大の像が伊那市のタウンステーションにお目見えしました。
4日は、福君の像のお披露目式が行われ白鳥孝伊那市長や伊那市に住む福君の曽祖母、近くの伊那保育園の園児などが参加しました。
9月から10月に東京都で著名人の等身大の像をベンチに座らせるイベントがあり終了後に福君から伊那市に寄贈されました。
ベンチは上伊那林産協同組合が地元産のスギなどを使って製作しました。
白鳥市長は「通り町の活性化に一役かってくれる」と期待していました。
園児たちは福君の像に触ったり記念撮影をしたりしていました。
福君の像は来年1月までタウンステーション伊那まちで展示されることになっています。
それ以降は、図書館など市内の公共施設に置かれることになっています。 -
らっこルームクリスマス会

伊那市の伊那公民館の子育て教室、らっこルームのクリスマス会が3日行われました。
クリスマス会には10組の親子が参加し、サンタクロースからプレゼントをもらいました。
らっこルームは交流の場として0歳から3歳までの子どもとその親を対象に伊那公民館が開いている子育て教室です。
3日は日影の伊那福音教会の牧師らが訪れ、ハンドベルの演奏や合唱を披露しました。 -
トンネル事故で高速バスに影響

山梨県の中央道、笹子トンネルで天井の板が崩落した事故により高速バスに遅れがでるなどの影響が出ています。
3日は伊那バス株式会社の伊那バスターミナルでは受付の係員が、運行に関する問い合わせや対応に追われていました。
山梨県内の中央自動車道は事故により、通行止めとなっていて高速バスは国道へ迂回して運行しています。
伊那バスによりますとこれにより伊那地域と新宿を走るバスの到着に30分から1時間ほどの遅れが出ているほか事故後はバス1本につき3、4人のキャンセルがあるということです。
伊那バスは高速バスについて「到着に遅れはあるものの、バスは平常通り運行している。乗客の方にはできるだけ不便のないよう運行していきたい」と話しています。
今回の天井崩落事故を受け、中日本高速道路では、笹子トンネルと同じ構造の、恵那山トンネルの緊急点検を3日、実施しました。
点検の結果については、早い段階で公表したいとコメントしています。 -
地元産そばを味わい地域交流

箕輪町の沢区の住民有志でつくる、沢国道バイパス花の会は2日、恒例のそば祭りを沢公民館で開きました。
このそば祭りは、沢区を通る国道153号バイパスの未使用区間を利用し、そばの花を育てた事がきっかけとなり、平成6年から開かれ今年で19回目となります。
会場には、50席ほどが用意されましたが、お昼近くになると家族連れなどが訪れ満席に近い状態となっていました。
今年は、150人分を用意したという事ですが、予想以上の客の入りに、調理室では、急ピッチに作業が行われていました。
訪れた人達は、打ちたてのそばに舌鼓を打ちながら、近所の人たちとの会話を楽しんでいました。 -
信大とCATV 情報発信の課題探る

大きな災害が起きたとき、ケーブルテレビには、どのような情報提供が求められるのかを探るフォーラムが11月29日長野市で開かれました。
信州大学と県内32のケーブルテレビ局でつくる日本ケーブルテレビ連盟信越支部長野県協議会の主催です。
岡谷市で8人の犠牲者を出した2006年7月の豪雨災害や去年3月の県北部地震で、地元のケーブルテレビが行った放送の事例報告とパネルディスカッションがありました。
信大とケーブルテレビの県協議会は、地域への貢献を目的に今年7月に連携協定を結んでいて、今回のフォーラムはその一環です。
パネルディスカッションでコーディネーターを務めた信州大学の笹本正治副学長は、「防災の文化は、災害が起きた時に前進する。地域に新しい文化を生み出すよう努力していきましょう」とケーブルテレビとの連携強化を強調しました。 -
24か国から外国人が箕輪町を視察

アジア地域セーフコミュニティトラベリングセミナーで日本を訪れている外国人が1日、箕輪町を視察しました。
箕輪町を訪れたのは、世界24か国でセーフコミュニティの認証を受けた地域の外国人など、およそ90人です。
セーフコミュニティトラベリングセミナーは、各国の取り組みを学び知識を深めようと2年に1度開かれているもので、日本での開催は初めてです。
箕輪町は、今年5月にWHO世界保健機関からセーフコミュニティの認証を受けていて、その取り組みについて学ぼうと、今回箕輪町を訪問しました。
箕輪消防署では、ロープを使った訓練やほふく救出訓練が行われ、参加者は写真を撮るなど熱心に見学していました。
ある参加者は「見たことのない訓練だったが、みんな真剣にやっている姿を見て大変勉強になった」と話していました。
一行はこの後、このほどセーフコミュニティの認証を取得した小諸市の認証式典に出席することになっています。 -
天竜川に伊那谷の風物詩

伊那谷の冬の風物詩「ザザムシ漁」が1日に解禁となり、愛好者が漁を楽しみました。
この日は雪が降る中箕輪町の天竜川で、木下に住む小森一男さんが漁を楽しんでいました。
ザザムシ漁は、毎年12月1日が解禁日で、虫踏み許可証を取得した愛好者が2月いっぱいまで漁を楽しみます。
小森さんは、知人に道具をもらったのをきっかけに10年前からザザムシ漁を始めました。
毎年、期間中週末になると川に入るという小森さんは、今年も解禁を心待ちにしていたということです。
かんじきを履いて石についたザザムシをはがし、四手網で捕っていきます。
小森さんは「今年の解禁日の収穫はサイズも小さいし量も少ない。温暖化が影響しているのかもしれないが、もうしばらくすれば成長してたくさん捕れるだろう」と話していました。
天竜川漁業協同組合によりますと、この日までに虫踏み許可証を取得した人は15人いたということです。 -
西春近北保育園 おでんパーティー

伊那市の西春近北保育園の園児は30日、日頃お世話になっている地域の人を保育園に招きおでんを作って交流しました。
30日は、保育園の運営に携わる区長や民生児童委員などおよそ20人を保育園に招き、自分達で収穫した野菜を使っておでんを作りました。
年長園児29人は、「左手を猫の手にして」などとアドバイスを受けながら、包丁を使って材料を切っていました。
おでんができるまでの間、園の庭で一緒に遊び、交流を深めていました。 -
年末特別警戒 出陣式

1日からの年末特別警戒を前に出陣式が30日、伊那警察署で行われました。
出陣式では、伊那署管内の市町村のイメージキャラクターと県警マスコットのライポくんも参加し、期間中の犯罪と交通事故の発生抑止を誓いました。
警察署管内の全市町村のキャラクターとライポくんが参加しての活動は県内初の試みです。
出陣式で伊那防犯協会連合会の白鳥孝連合会長は「力をあわせて事件や事故のない地域をつくりましょう」と挨拶し、伊那警察署の田中泰史署長は「管内の犯罪は減少傾向にあるが年末は犯罪が起こりやすい。気を引き締めて犯罪抑止に努めましょう」と呼びかけました。
出発を前に、5体のキャラクターの共同宣言を署員が読みあげました。
この後参加者とキャラクターは、パトカーや白バイ、青色パトカーに乗り込み啓発活動に出発しました。
伊那署によると、今年1年間に管内で起きた傷害や詐欺などの刑法犯は、10月末現在557件となっています。
去年の同じ時期に比べて106件減少していますが、子どもや女性に対する声かけやひったくりが起きているということで「引き続き犯罪抑止に努めていく」としています。
62/(金)
