-
おふくろの味教えて、子育て学級調理実習
宮田村公民館子育て学級は6日、ベテラン主婦を講師に・スおふくろの味・スを学ぼうと、調理実習を行なった。乳幼児を子育て中の若い母親25人が参加。偏りがちな栄養バランスも考えながら、食の大切さを見つめ直した。
町1区の池上靖子さんの指導で、巻き寿司、まめサラダ、ミルクけんちん汁の3品に挑戦。
普段の家庭の食事にはあまり使わない食材もあり、若いママたちは新鮮な気分で調理に取り組んだ。
主婦大先輩の池上さんに聞きながら、料理の知恵やコツも習得。異世代間の交流も深めていた。 -
ニシザワが本を寄贈
ニシザワ(本社・伊那市、荒木康雄社長)は、上伊那の38小学校の図書館に絵本などの本を寄贈している。創業80周年を迎えた3年前から続く事業。初日の6日は、箕輪町の箕輪中部小学校(小野正行校長、694人)へ本を届けた=写真。
ニシザワは、1924(大正)年、伊那市通り町に「西澤書店」として創業。これまでの感謝を伝えるため、創業原点である図書の寄贈を始めた。今年は、38校に希望の図書をリストアップしてもらい、82万円分(600冊以上)の図書を購入した。
箕輪中部小を訪れた荒木社長は「地域の未来を支える担い手である子どもたちの健全な育成に役立てば」と本を同校図書委員3人に手渡した。図書委員長の田中まみちゃん(12)は「卒業するまでの期間に寄贈していただいた本を全部読みたい」と話した。
今後、ニシザワのスパーなど各店舗の店長が各小学校へ本を寄贈する予定となっている。 -
安協女性部交流研修会

伊南、伊那、高遠の各交通安全協会女性部員らが一堂に集まっての交流研修会が3日、駒ケ根市のアイ・パルいなんで開かれた。役員ら約50人が出席し、各地区での活動事例や体験発表などを行ったほか、駒ケ根警察署の渋谷保人交通課長の講話を聴いた。
活動事例発表で伊南地区からは駒ケ根市の赤穂小学校2年1組(伊東美春教諭)の児童29人が登場し、交通安全創作劇「泣いた赤鬼」と交通安全の替え歌に乗せた花笠音頭を披露=写真。交通ルールの大切さを懸命に訴え、参加者から大きな拍手を受けた。 -
高遠町引持地区で数珠回し

新年事始めの伝統行事「数珠回し」が4日、伊那市高遠町の引持地区であった。地区住民など約30人が集まり、長さ20メートルほどある大きな数珠を回しながら今年の五石豊穣や家内安全などを願った=写真。
大きな数珠を広げて輪になり、参加者全員で念仏を唱えながらその数珠を回す伝統行事。右に3回、左に3回数珠を回すほか、1カ所だけ大きな玉がついており、それが自分のところへ来た時に礼拝する。
引持地区では例年、農事の事始めとされている2月8日に実施してきたが、より多くの人に参加してもらおう竏窒ニ今年は8日に一番近い日曜日に実施。小学生の参加もあった。
伊藤裕偉組合長は「伝統を引き継いでいくためにも出れる人に出てもらうようにしていきたい」と話していた。 -
権兵衛トンネル開通後1年~文化交流~
伊那市のみはらしファームであった権兵衛トンネル開通1周年記念イベント。「木曽のなァ、中乗さん…」と伊那に木曽節が響いた。
権兵衛トンネル開通をきっかけに、合唱、民謡、食文化、スポーツなどさまざまな分野で地域住民同士の交流が目立つようになった。「せっかく始まった交流。これからも続けたい」と交流を通した地域発展への期待も込める。
伊那で木曽節を披露する機会が多くなった木曽踊保存会の田沢博会長=木曽町=は「トンネルが開き、みはらしファームや伊那中央病院などに来る会員がいる。生活道路になりつつある」と話す。
新年度事業で、木曽町の旧市町村単位にある民謡を集めて交歓会を開く計画で「伊那節の皆さんにも声をかけたい」と考えている。
「木曽町の福島関所まつりなどで伊那節も披露されている。双方のイベントなど機会をとらえて交流し、衰退していくまちの発展につなげたい」と楽しみにしながら伊那へ来る。
伊那、木曽の両地域で、それぞれ開かれる音楽祭には、相互に合唱グループや小学生らが出演。無理せず、継続できるような形が定着しつつある。
伊那のスプリングコンサートや「い縲怩ネ音楽祭」に参加した木曽の小学校関係者は「伊那の子どもたちのレベルは高く、参考になる」と話した。コンサートを企画するNPO法人クラシックワールド事務局長北沢理光さんは「お互いに刺激を受ける」という。
昨年6月の権兵衛トンネル開通記念の「手づくりの第九演奏会」には、伊那、木曽の両地域から一般公募した団員約300人がステージに立った。
開通前は別々に練習していたが、開通後は一堂に集まり、完成度を高めた。
団員は合唱に限らず、ソースかつどんやそばを食べに出かけたり、木曽から伊那に来て忘年会をしたりと地域の情報を交換する場にもなったようだ。
また、昨年2月、高遠町で伊那谷・木曽谷そば打ち交流会があり、両地域のそばグループから約30人が集まった。
地元産そば粉を使い、辛味大根を添えた高遠そば、具を煮たなべでひと口ほどのそばをゆでる投汁(とうじ)そば、つゆにすんき漬けを入れたすんきそばを用意。高遠そばを試食した木曽の参加者は「後から辛味がきて、おいしい」、木曽のそばに、地元住民は「すんきそばはすっぱいと思ったけど、さっぱりしている」と互いのそばを食べ比べた。
その後、高遠町の山室そばの会メンバーらが木曽ふるさと体験館=木曽町=に出向き、投汁そばを味わった。
同会は「トンネル開通で、交流のきっかけができた。これからも続けたい」と食文化での地域の活性化をねらう。
◇ ◇
木曽に本部を置く「kanaバレエスタジオ」の国崎智絵さん=木曽町=は昨年7月から、伊那市生涯学習センターで教室を開いている。
「トンネルが開いて近くなった。一人でも多くの人に、バレエの基礎を学んでいただきたい」と始め、地元の小学生や一般の約10人に指導。
月4回のペースで、木曽から約45分かけて通う。「大雪の日は、電車を使って塩尻経由で来た。やっぱりトンネルを利用すると便利」と木曽竏宙ノ那間の近さを実感した。
4月、木曽で開くスタジオ発表会には、伊那の生徒も出演するそうで、木曽と伊那の生徒同士が交流する場を持つ。
◇ ◇
さまざまな催し物を企画する県伊那文化会館にも、木曽からの来館者が増えた。
トンネル開通を機に、木曽の学校や木曽文化公園などにポスターやチラシを持ち込み、イベントをPR。開通前、ほとんどいなかった木曽からの観客は、開通後、千人規模のイベント(昨年秋縲・月)で30人ほどが入り、宣伝効果は表れている。プラネタリウムにも、小学生がクラス単位で年間に何度か訪れた。
「トンネル出口から近いこともあり、音楽や演劇に興味がある人は来館する」と利便性を挙げる。
一方、伊那市生涯学習センターは、木曽からの観客がいるものの「思った以上に、集客に結びついていない」。
今後、木曽へのPR方法を検討し、人を呼び込み、地域に潤いをもたらすことができればと考えている。 -
高校生ファッションショー開催

南信地区の高校生や服飾専門学校生によるファッションショー「colorful snow(カラフル・スノー)」が4日、伊那市の生涯学習センターであった。高校生など多くの観客が駆けつけ、若い感性でデザインされたファッションの数々を楽しんだ=写真。
3年目となるファッションショーには今年、赤穂高校、上伊那農業高校、諏訪実業高校の高校生や、専門学校生の9人がデザイナーとして参加。作品発表に臨んだ。
モデルはそれぞれの友人、知人などで、ヘアメイクまですべてを自分たちで手掛けている。
テーマである「colorful snow(カラフル・スノー)」をイメージした個性豊かな作品をまとったモデルが続々と登場。仕切りにシャッターを切る観客の姿も見られた。
また、2着が変化していく「展開Show」は、新感覚で観客の目を楽しませていた。 -
みはらしファームで権兵衛トンネル開通1周年記念イベント開催

権兵衛トンネル開通1年となった4日、伊那市西箕輪の農業公園「みはらしファーム」は「開通1周年記念イベント」を開いた。地元客のほか、木曽方面から訪れた観光客などでにぎわい、踊りや地元の名物料理などを楽しんだ。
イベントは、権兵衛トンネル開通イベントの時のオープニングセレモニーでも演奏した伊那市西春近の「小出太鼓」の太鼓演奏と木曽節保存会の「木曽節」でスタート。
開通1周年を記念した宝投げやトンネル開通にちなんだゲームを開催したほか、地元野菜の販売やローメンやソースカツ丼など、伊那地域の名物料理屋台も並び、訪れた人を楽しませた。
また、トンネル伊那口では交通安全を祈念して木曽方面から来た普通自家用車限定500台を対象に茅の輪くぐりを実施。記念品を贈呈するとともに市内の観光施設への誘導も行った。 -
【記者室】祝 プロ棋士内定
駒ケ根市出身の大沢健朗さん(20)が日本棋院の認定する囲碁のプロ棋士内定を決めた。今年の入段者は全国でわずか6人という超難関。少しばかりの努力で成し得ることではない▼プロ棋士を目標と定めたのは小学生の時だが、周囲に勧められたのではなく自らの意志だったというから驚く。小学校卒業と同時に名古屋に移り住み、日本棋院の院生として囲碁一筋に精進を重ねた末に少年の日の一途な夢を見事実力で勝ち取ったのだから、並外れた強固な意志を持っていなければとても到達できなかったことだろう▼プロといっても収入が保証されているわけではない。対局で一つ一つ勝っていかねば前途が開けないのだ。厳しい世界だが、今後の健闘を心から祈りたい。(白鳥文男)
-
駒ケ根市の大法寺で節分厄除け

節分の3日、駒ケ根市赤穂北割一区の大法寺(藤塚義誠住職)で厄除けの法要と豆まきが行われた。300人を超える檀徒や一般の人たちが本堂に集まり、住職らが「南無妙法蓮華経竏秩vと唱える中、手を合わせて家内安全や健康長寿、交通安全、学業成就などを祈願した。
法要後、豆まきが行われた。中央に進み出た年男、年女らが「福は内」と威勢よく掛け声をかけながら豆やみかんなどを投げた=写真。集まった人たちはご利益にあずかろうと、夢中になって手を伸ばしたり身を乗り出したりして投げられる豆を拾っていた。 -
節分厄よけ盛大に、

中川村葛島の延寿院(伊佐栄豊住職)の節分会護摩祈とうが3日、同寺の本堂で盛大に行われた。上下伊那を中心に県内外から約300人の信徒が参拝、本堂に祭られた不動明王像に厄よけや無病息災、家内安全、諸願成就などを祈願した。
伊佐住職は願木に点火、赤々と燃え上がる護摩の火を前に「星供祈願文」を奏上、願主の名前を読み上げ、御加持(おかじ)を行い、集まった信徒や家族ひとり一人の身体健全、厄難消滅を祈願した。
祈とうに先立ち、伊佐住職は経文の1節「遠仁者陳道富久有智(仁に遠い者は道に疎く、智を有する者は久しく富む)」と書かれた掛け軸を披露し「この文が鬼は外、福は内のもとになっている」と節分の意義に触れた。
この後、信者らはお札やお守り、福豆、節分まんじゅうなどを受けた。
また、節分会に合わせ、隣接の宅幼老所かつらの利用者が新聞紙を何重にも張り、職員が顔を描いた、個性豊かな手作りだるまの開眼供養もした。 -
うぶ声講座、母子と交流

妊娠中の夫婦が出産や子育てに備え一緒に学ぶ宮田村の「うぶ声講座」は30日、7カ月の育児相談に参加していた母子と交流。赤ちゃんと接し、先輩の母親たちから育児などのアドバイスを受けた。
抱かせてもらったり、あやしたり。生まれてくる我が子の姿を重ねながら交流を深めた。
育児について熱心に話しを聞く姿も。母親としての自覚も高めていた。 -
箕輪町警部交番連絡協議会報告会
箕輪町警部交番連絡協議会(小林紀玄会長)はこのほど、交番近況報告会を町内で開き、倉田千明交番所長から06年の箕輪町の治安情勢を聞いた。
犯罪発生状況は、刑法犯の届出件数202件。05年と比べ80件減少した。器物損壊、万引き、詐欺、自販機荒らしなどは減少し、車上狙い、自転車盗、空き巣・忍び込み、部品狙いは増加した。地域別発生状況は、松島83件、沢39件、木下30件など中心部は多いが、昨年よりは減少。中心部から少し離れた地域でわずかだが増加した。「車上狙いや車の部品狙いが多いので、特に注意してほしい」と話した。
交通事故発生状況は、人身事故が126件で05年と同数。死者は05年は0だったが06年は3人。負傷者は9人増えて167人。物損事故は573件で1件増加した。
伊那署管内は人身事故が88件、物損事故が123件それぞれ減少したが、町は減少率が低かった。「交差点の出合い頭の事故が多い。広域農道や春日街道に出るときはしっかり停止し、安全確認してほしい」と注意を呼びかけた。 -
伊那谷炭々隊が炭材づくり

地域の森の健康を願い、森林整備や間伐材の有効利用などに取り組む特定非営利活動法人森の座はこのほど、間伐材の有効利用の一環「伊那谷炭々隊(いなだにすみずみたい)」活動で、南箕輪村内の森で間伐をして炭材づくりをした。
森の座は05年11月発足。会員は県内外の13人。
長野県コモンズ支援金事業として「伊那谷炭々隊」活動を始めた。伊那谷の森林整備で出た間伐材の有効利用を目的に、山の手入れが進むことを目指している。
支援金で炭材を割ることができる薪割り機を購入。地域で間伐材の有効利用を目的に炭窯を作って活動する仲間とネットワークを組み、その炭窯に森の座が間伐材を持ち込み、炭に焼いてもらっている。
作業には会員、一般合わせて6人が参加。炭窯に詰める一回分の炭材を作った。
森の座では、「炭を非常時の燃料や床下の除湿剤など日常的に使うことで地域の森を感じることができる」とし、今後、地域産の炭を地域産の間伐剤を利用した箱に入れて販売するという。 -
プロ棋士誕生へ

日本棋院が認定する囲碁のプロ棋士に駒ケ根市梨の木出身の大沢健朗さん(20)=名古屋市東区=が内定した。同院の07年度入段者(4月1日付)は全国でわずか6人。超難関の突破に関係者は喜びにわいている。
大沢さんは所属する日本棋院中部総本部でプロを目指す院生の成績上位者同士が昨年8月から今年1月22日にかけて戦った総当りリーグ戦で25勝3敗の1位を獲得し、プロ棋士の座を勝ち取った。両親への報告に郷里を訪れた大沢さんは「プロとしての戦いがこれから始まる。これまでにも増して厳しい世界だから喜んでばかりはいられない。取りあえずは1勝が目標だが、勝つためにさらに実力をつけていきたい」と4月のプロデビュー戦に向けて意欲を燃やしている。
大沢さんは小学4年生の時に囲碁を始めた。現中川村教育長の北村俊郎さんらに指導を受けるうち、駒ケ根市中沢出身のプロ棋士下島陽平さんにあこがれてプロになろうと固く決意。日本棋院中部総本部の院生試験に合格し、小学校卒業と同時に名古屋市に移り住んで囲碁一筋に精進を重ねてきた。 -
【権兵衛トンネル開通1年~その後の地域~労働力】

「市では06年度施策の一つに企業誘致を掲げ、取り組んできた結果、昨年は7つ、今年3月には新たに5つの誘致が締結される予定となっている。みなさんの中には求人難になるのではないかという懸念もあると思う。木曽の方から来てもらったり、地元に帰ってきてもらうような政策をとっていかなければならないと考えている」 今年1月、伊那商工会議所議員の新年の集いに招かれた小坂樫男伊那市長は述べた。
地方ではいまだ景気回復の実感が薄いと言われている中、上伊那地域の昨年の労働市場は、主要産業の製造業が引っぱる形で毎月4千人前後の有効求人数を記録。昨年10月には月間有効求人倍率が1・6倍となるなど、県内他地域と比較しても高水準で推移している。
こうした中、トンネルの向こう側から労働力を呼び込もうと動く上伊那企業も増えてきている。
◇ ◇
木曽福島町の職業安定所「ハローワークきそふくしま」では、トンネル開通から昨年12月までに伊那地域にある企業166社の261件、679人分の求人情報を公開し、実際に14人が伊那地域で就職した。職安の担当者は「こうした動きが出てきたのはトンネル開通後といっていい。互いの地域で、通勤圏内としての認識が広まっている。逆に、伊那まで求人情報を見に行った方が早いという人もいるようです」と話す。
その伊那の職安には、木曽地域から48人が登録し、9人が就職を決めている。
職安関係者の間では「案外少なかった」という印象もあるようだが、地域間交流が深まるのに連れ、こうした動きも活発化するのではないかとの見方もある。いずれにせよ、権兵衛トンネルの開通が独特な産業事情を抱える木曽住民の職業の選択の幅を広めたことには間違いない。
◇ ◇
求人の絶対数で見ると、伊那地域の5分の1縲・0分の1程度しかない木曽地域だが、有効求人数を有効求職者数で割った有効求人倍率でみると、月によっては県平均を大きく上回る月もある。
しかし、求職者がきちんと職を得ているかというと実情は異なる。月間有効求人倍率1・55倍を記録した昨年10月には、求職者340人に対し527件の求人があったが、実際に就職したのは36人。需要と供給が合致していない。
こうしたミスマッチが生じる背景には、木曽地域特有の産業形態と労働者事情が大きく関係している。
製造業が弱い木曽地域では、労働時間が不規則で土日・祝日休みがとれないサービス業やシーズンに合わせて働く季節雇用が約6割を占めている。一方、職安を通じて仕事を探す人の中心は家庭を持つ中高年世代。こうした求職者の場合、週末に休みを取れたり、時間的な融通の利く職場を希望する人が多く、サービス業を望まない傾向にあるという。
木曽福島職安の担当者は「一般的に、有効求人倍率は産業の活発な地域で高くなったりするが、木曽は季節に合わせて変化する特種な地域。賃金的レベルが高く、週末休みがとれる製造業を希望する人もいるが、こちらでは紹介も限られてしまうのが現状。ちょっと遠くても製造業の求人が多い伊那地域も含めて就職を考える人が増えているのは事実だと思います」と語る。
◇ ◇
木曽地域から伊那地域に出店した人もいる。
木曽郡上松町などに美容室2店舗を構える久保竹志さん(39)は昨年10月、南箕輪村の春日街道沿いに美容室「EX Turban」をオープンした。
オープンから約3カ月。現在は辰野方面から駒ヶ根方面まで、幅広い地域から利用者が来店しているという。「時々『新しくオープンしたから来てみた』っていう木曽のお客さんもいますね」とスタッフの一人は話す。
トンネルの開通を見込み、4、5年前から準備を進めてきた。スタッフは伊那地域で新たに雇用したが、美容の基本となる「技術」を移転するにも、互いに行き来できる最も近い地であると認識している。久保さんは「人口もあり、人の流れもある伊那での出店を考えていた。トンネルが開通したことで遠かった伊那が身近な地域となった」と話す。
“地域になくてはならないお店”を方針に掲げる同店では、伊那地域でも地域密着型の事業展開を図り、この地に根付いていこうとしている。 -
おやじ塾健康長寿講座

中・高年男性を対象にした宮田村公民館(白鳥剛館長)のおやじ塾は31日、健康長寿講座を村民会館で開いた。塾生ら15人が参加し、村老人福祉センターの保健師伊藤美奈さんによる「ますます元気! 健康長寿の秘訣」を聴いた=写真。
伊藤さんはメタボリック・シンドローム(内臓脂肪症候群)が心筋梗塞(こうそく)や脳卒中の発症率を高めることについて説明した上で健康長寿の秘訣について、食べすぎない▽運動習慣▽ぐっすり眠る▽笑う竏窒ネどを挙げ「皆さんが先頭に立って宮田村をますます元気な村にしていってほしい」と呼び掛けた。 -
「議員報酬上げるな」申し入れ

市民のくらしを守る駒ケ根みんなの会(林高文代表代行)は1日、駒ケ根市役所を訪れ、市議会議員の報酬を引き上げないよう中原正純市長宛てに申し入れた=写真。林代表代行は「特別職報酬等審議会が引き上げを答申したが、この時期に議員の報酬だけを引き上げるのは市政の厳しい現状や社会情勢などからも到底納得できず、市民の理解も得られるものではない。引き上げないよう強く要望する」として申し入れ書を原寛恒助役に手渡した。原助役は「基本的に審議会の答申は尊重する方向だが、総合的に判断することになる。要望は市長に伝える」と述べた。
昨年12月に白紙諮問を受けた市特別職報酬等審議会(渋谷敦士会長)が1月23日に中原市長に手渡した答申では、議員定数を現行の21から6減の15と決定したことなどによりこの機会に見直しを行うことが必要だとして、議員の報酬を▽議長40万5千円▽副議長33万9千円▽議員31万4千円竏窒ノ増額することが妥当としている。条例による現行額(カッコ内は増額率)は▽議長=38万3千円(5・7%)▽副議長=32万6千円(4・0%)▽議員=29万8千円(5・4%)竏秩B市議会議員の報酬は06年度の答申では据え置きだったが、厳しい財政状況を踏まえて1%自主削減している。 -
文化財防火デーパトロール

文化財を火災、震災などの災害から守るため全国的に文化財防火運動に取り組む「文化財防火デー」(1月26日)の一環で、箕輪町文化財保護審議会などは1月31日、町内の文化財5カ所をパトロールし文化財や文化財保管施設の防火対策などを確認した。
毎年、町の文化財を数カ所ずつ巡回し、建物、電気配線や電気機器の漏電点検、火災報知器や消火器の点検などをすると同時に、文化財の確認もする。
今年は旧三日町公民館、長松寺の地蔵尊、長岡神社本殿、長岡神社本殿造営記録文書、普済寺文書が対象で、審議会委員、箕輪消防署員、町教育委員会生涯学習課文化財係職員の計10人が見回った。
長松寺では、審議会委員が地蔵尊の作者などを説明し、地蔵尊や周囲の状況を確認した。防火対策は管理されていて問題なかった。旧三日町公民館では、消防署から、消火器をだれもが取り出せる場所に置くなどの口頭指導があった。 -
権兵衛トンネル開通後1年~交通~

国道361号伊那木曽連絡道路(権兵衛トンネル)の交通量は昨年12月末で、109万台を超えた。伊那インターチェンジ(IC)の利用台数が10%増加するなど高速道路と一体になった広域的な活用がみられる。木曽の国道19号を通過する大型車両の流入による混乱が心配されたが、伊那建設事務所では「渋滞も、暴走車もなく順調に推移している」と話す。
木曽建設事務所の交通量データ(開通翌日縲・2月末)によると、伊那から木曽が54万1663台、木曽から伊那が54万9142台。一番多かった日は、ゴールデンウィーク中の5月4日で1万台を突破した。1日当たりの平均は、両方向合わせて、平日が2745台、休日が4418台。通行車両の45%が県外車の利用となっている。
観光バスを含む大型車の混入率は累計で13・7%。2月当初と比べ、3倍以上に増えた。
木曽からの流入車両に対応し、南箕輪村沢尻に沢尻バイパスを建設、伊那市街地へう回させている。
昨年6月、伊那建設事務所の交通調査(12時間)で、361号から左折して沢尻バイパスを通った車が11・6%(515台)増、そのまま直進して川北信号機を下った車が9・3%(378台)増だったことがわかった。春日街道西側に位置する広域農道で一部拡幅、歩道設置が進められたが、大萱信号機の通過は3・8%(164台)増にとどまった。伊那インター線は10・3%増。
伊那建設事務所は、周辺道路整備の必要性について、大型車の通行に対応できる道路だが、交通実態を踏まえ、今後、検討するとしている。春には、車の流れを把握するため、範囲を広めて交通量を調査する。
◇ ◇
市町村合併や権兵衛トンネル開通に伴い、伊那市は「伊那地域における新たな交通ネットワークシステム構築のための検討会」を設け、新市の総合的な交通体系を検討している。
観光客の誘致や地域振興などの観点から▽新市発足に伴う旧市町村の生活交通のあり方▽権兵衛トンネルを利用した広域的な交通ネットワーク▽地域の観光資源を生かすための公共交通のあり方竏窒ネど木曽地域を含め、具体的な運行計画を練る。
地域住民アンケートで、伊那竏猪リ曽間の連絡バス利用を尋ねた。
その結果、伊那は「ぜひ利用してみたい」「条件次第で利用してみたい」が24・6%で、「全く利用しない」は34・3%だった。
利用ニーズの目的地は温泉、中山道宿場、開田高原、JR木曽福島駅などが上位を占めた。
検討会の座長を務める信州大学教育学部教授の石沢孝さんは「名古屋への直通バスがあるのに、JR木曽福島駅を利用する人がいる。ビジネス的な利用は十分にある」とみる。
一方、木曽は「利用してみたい」というニーズが48・2%で、「全く利用しない」の9・3%を大きく上回った。買い物、観光・保養、娯楽、通院などの利用ニーズが多かった。
料金設定は、いずれも500円縲恊迚~程度に集中している。
また、伊那・木曽を訪れた観光客の伊那竏猪リ曽間の連絡バス利用のニーズは約3割だった。利用する条件に▽運行本数が多ければ▽時間帯が合えば▽料金が安ければ竏窒ネどが挙がった。
今後、公共交通、観光交通、利用者らの現状や問題点をヒアリング調査し、新市の総合的な交通体系の基本方針をまとめる。
タクシー業界では、開通前に全くなかった木曽行きの利用が目立つ。
伊那市街地からJR木曽福島駅までのタクシー所要時間は約40分で、料金は9千円ほど。岡谷市まで行ける距離という。
伊那タクシーは月に数十件、木曽方面へ出向いている。JR木曽福島駅の送り迎えをはじめ、仕事や飲み会(週末)の帰りなどに利用する人が目立つという。夏場には観光を目的とした利用もあり「恩恵を受けている」という。
白川タクシーは月に数件で、JR木曽福島駅の活用がほとんど。地域住民が「近くなった木曽に行ってみるか」と奈良井宿や開田高原を観光で回るケースもあった。
今後の見通しについて「劇的に増えることはないだろう」と予測するが、花見の時期、高遠城址公園を訪れた観光客が立ち寄る一つの選択肢になると期待する。
木曽の情報は、観光パンフレット程度しかなく、ドライバーは実際に回って見た情報を交換している。
現状では、定期便の運行には至らないようだ。
昨年2月の開通後から、伊那バスは権兵衛トンネル開通記念としてバスツアーを企画。「トンネルを経由したコース設定は需要がある」といい、人気は高い。
これまで木曽の各所を見学する「木曽馬の里縲恁茆ヤ明神温泉」、トンネルを経由する「美しい上高地紅葉ツアー」など4コースが終了。地元を中心に、約1500人が利用し、関心の高さをうかがわせた。
7日からは「昼神温泉ツアー」がスタート。また、木曽見学として御嶽山周辺を組み入れている。 -
南箕輪村輪の会研修会

農と食の大切さを考え活動する南箕輪村輪の会は31日、研修会を村公民館で開き、おはぎなどの調理実習をした。
地元の郷土食を学ぼうと、おはぎと、上伊那地域で一般的な米粉を使うおやきを作った。会員と一般2人の計10人が参加。会員の植田さち子さん、酒井八重子さん、原敏子さんが講師を務め、材料はおやきを作っている大芝高原の味工房から地元食材を購入した。
おやきは、米粉に熱湯を加えてこね、沸騰した湯の中に入れて煮た後、もう一度、砂糖を少量加えてよくこねる。参加者は仕上がりの硬さを手で触って確認し、原さんから「こねていてボールに付かなくなってきたのが目安」とアドバイスを受けた。
生地を平らにつぶしてから小豆あんを入れて包む方法を教わり、「皮の厚さを均等にするのが難しい」と話しながら作っていた。
試食と一緒に漬物の食べ比べもし、参加者が持ち寄った各家庭の味自慢をしながら食べた。 -
交通栄誉章受章報告

交通安全に大きな功労があったとして第47回交通安全国民運動中央大会(17日、東京都)で交通栄誉章緑十字銀賞を受けた駒ケ根市赤穂南割の小町谷美枝さん(62)が29日、駒ケ根市役所を訪れ、中原正純市長らに受章を報告した=写真。小町谷さんは「大勢の方の活動のおかげでたまたま私が受章できた。安協の皆さんや家族の協力に感謝したい」と喜びを語った。中原市長は「今後の手本にもなること。受章を機に引き続き地域の安全・安心のため、先頭に立って活躍してください」と激励した。
小町谷さんは交通安全協会の活動に二十数年携わり、2000年からは伊南安協の女性部長を務めるなど、地域の交通安全推進に長年尽力してきた。 -
箕輪町長寿クラブ連合会研修総会
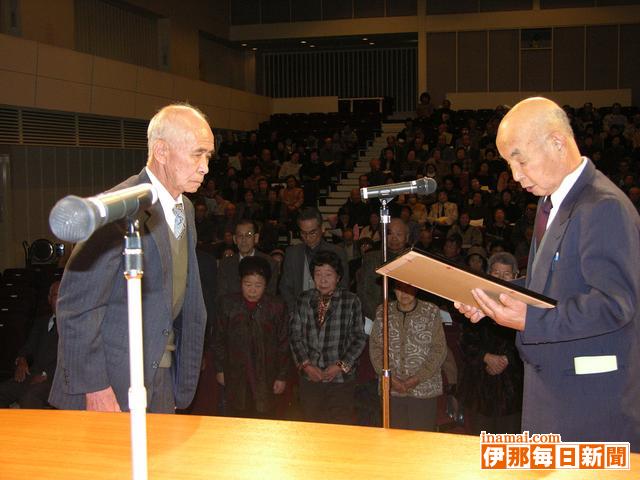
箕輪町長寿クラブ連合会は30日、06年度研修総会を町文化センターで開いた。感謝状と表彰状の贈呈をし、賢い消費者になるために飯田消費者生活センター所長の講演を聞いた。
町内には19単位クラブあり、各クラブごとに活動している。総会には約400人が出席。浦野順司会長は、「日ごろはクラブ活動に献身的な協力をいただき、単位クラブで活躍いただいている」と感謝し、「1年に1度の総会。皆が痛切に感じている消費者問題を学んでほしい」と話した。
感謝状は長寿クラブに6年以上在籍し役員を務めた人で各単位クラブの推薦者の中から選考。本年度は21人。表彰状は、地域の荒廃地を整備して花を植える活動に取り組んだ沢長寿クラブに贈った。
受賞者を代表して松島北部の松田貫一さんは、「連合のため、よきおじいさん、おばあさんとして、いつまでも健康で連合のボランティア活動に励みたい」と謝辞を述べた。
アトラクションでは、音楽を楽しみながらボランティア活動に取り組む箕輪町と伊那市在住者でつくる「たそがれシーラクバンド」の生演奏を楽しんだ。
感謝状受賞者は次の皆さん。
泉沢久雄、中坪昌子、中坪智恵子、伊藤春子、松田貫一、藤沢初子、市川芳子、金沢もヽ江、上田芳子、武井和美、今井孝子、遠藤七資、木村文也、鳥山博世、北條憲雄、浅野よ志子、小森みよ子、矢島光、井沢行正、川上みや子、根橋健康 -
青年海外協力隊
ニカラグアから帰国
箕輪町
関理恵子さん
04年12月、青年海外協力隊の04年度第2次派遣隊員として中米のニカラグアに赴任。2年間の活動を終え今年1月、帰国した。
青年海外協力隊は、中学で隊員OBの話を聞いたのが最初の出会い。しばらく忘れていたが、大学生になって隊員を目指していたことを思い出した。
小学4年から教員になる夢を持ち続け、上越教育大学に進学した。「魅力のある先生は人として魅力がある。幅を広げたい」と、米国でのボランティア活動に参加。卒業後、「広い価値観を持ちたい」と埼玉YMCAで4年半勤務した後、青年海外協力隊駒ヶ根訓練所に入った。
ニカラグアには青少年活動で赴任。首都・マナグア市にある外務省管轄のNGO職業訓練校で、教育担当者としてクラスを持った。生徒は8歳から18歳。貧困、家庭内暴力、親が、あるいは本人がドラッグユーザーなど深刻な問題を抱えている。子どもが働くなとはいえない現状のため手に職をつけることが目的で、訓練を通して育成を図る。
活動は最初から順調だったわけではない。赴任するとディレクターが代わっていたために「呼んでいない」と言われ、訓練したスペイン語も、生活上は問題ないが、仕事となるとついていけない。
「赴任して3カ月から6カ月は毎日泣くくらい苦しかった。思いが伝わらない悔しさ。子どもたちに完全にバカにされた」。そんな中でも理解してくれる子どもたちを頼りに、信頼関係を築いていった。8カ月を過ぎてからは月日の流れが早く、振り返れば2年はあっという間だった。
教えたのはブレスレットやビーズアクセサリー作り。図面を見て作れるように指導し、将来的に自分たちで出来るように、2年目は子どもが子どもに教える形にまでなった。
一貫して伝えてきたことは「責任感」。帰国前、子どもたちが「最初はうるさかったけど、今は言いたいことがわかる。責任を持つことができた」「自分を好きになって、相手を思いやることができた」と言ってくれた。「これが一番の収穫でした」。
ニカラグアは非常に治安が悪い。幸い強盗などの被害に遭うことは無かったが、気の休まるときはない。それでも、「ニカラグアは私に合った」という。「イエスかノーで言いたいことを言う。関係が悪くなっても互いに言い合って良くなる。毎日笑顔があって、本気で怒って。ありのままの一人の人間として受け止めてくれる国。居心地が良かった」。
帰国後、青年海外協力隊の短期派遣で、再びニカラグア行きを考えている。
「自分の中で、貧困な状況に置かれている子どもたちの整理がつかない。やるせない思い。私一人ではどうにもならないけど、子どもが一瞬でも多く笑顔でいられることをしたい。たぶん答えは出ない。もがきですね」
あと1年くらいもがいて、その先は長野県の小学校教諭を目指す。「人に伝えることで理解を深めることが大切。自分だけの国際理解より、皆での国際理解が今は必要。今度は、大好きな日本で自分が影響受けたことを還元し、日本の子どもたちと、もがいて生きていきたい」。 -
【権兵衛トンネル開通1年~その後の地域~観光】

「これまでは塩尻を回らなければ来れなかったけど、トンネルが開通してからは約30分で来れる。木曽にも温泉はあるが、こういう体験施設を兼ねそろえている場所はない。観光やレジャーで来るのにはとてもいい。何より、(高速と違って)通行料金がいらないのがいいね」。
塩尻市木曽平沢に住む百瀬順次さんはこの日、家族連れで伊那市西箕輪のみはらしいちご園を訪れた。初めていちご園を訪れたのはトンネル開通直後のこと。その後は、月に1、2回ほど伊那側を訪れ、日帰り温泉施設「みはらしの湯」などをよく利用している。
権兵衛トンネルの開通は、上伊那の観光産業にも新たな刺激を与えている。この1年で大きな影響を受けたのは伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームや南箕輪村の大芝高原など、トンネル近郊の観光施設だ。
みはらしファームの体験農園の一つ、「伊那みはらしいちご園」では、ここ1、2年、来場者数が6万人台の前半まで落ち込んでいた。しかし、昨年は近年の実績を1万人以上上回る7万3千人が来場した。
泉沢勝人組合長は「予約データの中にも木曽から来ている人の情報がある。昨シーズンのピーク時には、木曽の人が毎日来ることもあった」と話す。
また、施設利用者の約半分を占める中京圏のお客にも、変化があった。「団体客より家族連れなど個々に来る人が増えた。木曽の国道19号から権兵衛トンネルを抜け、帰りは伊那インターを利用する人が増えているんだと思う」と語る。
◇ ◇
一方、トンネルから離れた地域には、それほど大きな影響はない。
駒ヶ根市を訪れる観光客の数は1992年の170万人をピークに、年々緩やかな減少傾向にあり、ここ数年は130万縲・40万人前後で推移する頭打ちの状態が続いている。
トンネル開通当初は、木曽谷とのアクセスルートが新たに開けたことにより、観光客数増のきっかけになれば竏窒ニ明るい希望を持った関係者も多かった。しかし、開通から1年経った現在、観光客の大きな増加には結びついていないようだ。
駅前の食堂の店主は「駒ケ根名物のソースかつ丼を食べに木曽から来た竏窒ニいう客も時折来るよ。トンネル開通以前にはこんなことはなかったね。まあ、今のところはもうけにつながるほどじゃない小さな動きだが、少しずつでも将来の活性化につながってくれればいいんじゃないか」と期待を託す。
駒ケ根市観光協会は駒ケ根と木曽を1日で回れる一つの観光地域として大都市圏にアピールしていこうと動き出している。協会の情報企画部長宮澤清高さんは「中央アルプスを挟んではいるが、点と点ではなく、つながった面としてとらえ、一つの観光ルートとしてコースをつくって提案していくなどの具体策に取り組んでいきたい。両地域の住民の間で互いの交流も始まったところなので、今後の展開に大いに期待したい」と話す。
◇ ◇
1年目はトンネル効果の恩恵があった観光施設にとっては、今後も持続的に観光客を確保することが課題となっている。
南箕輪村の大芝荘の山・ス文直支配人は「1年目は物珍しさも手伝って来てくれた。今後は毎年来てもらえるような取り組みをしていかなければならないが、大芝高原だけではせいぜい1日もあれば見て回れてしまう。これまで1泊だった人に2泊してもらえるようなプランを提供していくためには、上伊那の他地域と連携していくことも必要だと感じている。これからは観光メリットをいかにして共有するか」と語る。
大芝荘では広域連携に向け、他市町村への呼び掛け開めている。構想の中には、各市町村の観光名所を巡る「観光タクシー」などもあり、こうした企画は大型バスで訪れる観光客にも利用してもらえるのではないかと期待をかけている。 -
高校生ファッションショーの準備進む

自らの作品を多くの人に見てほしい竏窒ニ、ファッションショー「Colorful Snow(カラフル・スノー)」を2月4日、伊那市駅前ビル「いなっせ」で開く高校生や専門学校生が、本番に向けた最終準備を進めている=写真。
今年で3回目となる取り組み。その年ごとで服飾に関心のある高校生や専門学校生が集まり、ショーをつくり上げている。
今年は、赤穂高校、上伊那農業高校、諏訪実業高校の高校生と、専門学校生の9人がデザイナーとして参加。頭の中を雪のように真っ白にして、そこから自分たちなりにさまざまな色をつけてみよう竏窒ニいう思いから、「Colorful snow」をコンセプトとした。
ショーはグループごとの4部構成として、デザイナーの個性をそれぞれにまとめたほか、「展開Show(ショー)」と題して2着の服がさまざまに変化する新しい分野にも挑戦する。
代表者の大木大輔さんは「学生たちががんばってやっているので、ぜひ見に来てほしい」と呼び掛けている。
いなっせ6階ホールで午後2時から(会場は午後1時半)。チケットは20歳以上が千円、20歳未満が500円(前売りはなし)。 -
寒に咲く、スノードロップ

悲しい伝説の花、スノードロップが、駒ケ根市北割1区の手づくりガーデン喫茶プチ(中城澄子店主)の庭で純白な花を咲かせている。
今咲いているのは小花の早生系、1回り大きな花もまもなく咲き出す。
スノードロップはヒガンバナ科、和名「ユキノハナ」「マツユキソウ」とも呼ばれる。
アダムとイブがエデンの園を追われた時、天使がイブを元気づけようと、雪に触れ、スノードロップに変えたという言い伝えがある。 -
長谷道の駅のレストランでまきストーブ講座

伊那市長谷、道の駅・南アルプスむらにあるレストラン「野のもの」(吉田洋介代表)で30日、「薪(まき)ストーブクッキング講座」があった。市内外から集った参加者たちは、まきストーブやダッチオーブンを使って、イタリア料理に挑戦した。
まきストーブを備える同レストランが調理への活用法を学びたいと、一般にも参加を呼びかけて開いている講座で、2回目。初回に続き、市内でイタリア料理の指導をしている生パスタの製造・販売店「蔵部」の渡辺竜朗さん(35)を講師に迎えた。
メニューは、イタリアの冬の料理の代名詞とされる「バーニャ・カウダ」と、魚料理「アクアパッツァ」の2品。おいしく作りあげるポイントや、調理時におけるまきストーブの有効な使い方を教わった。
箕輪町から訪れた50代の女性は初めて参加。「家にまきストーブがあるけど、料理などになかなか生かせれていないので、コツを教わりたかった。(講座を通して)料理の幅が広がりそうです」と話していた。 -
伊那市生涯学習センター新講座 飾り寿司作り

伊那市生涯学習センターは新講座「飾り寿司を作ろう」を始めた。市駅前ビルいなっせに市内の主婦ら約30人が月に2回ほど集まり、パンダやバラの花を太巻の断面に表現する寿司づくりに熱中している。
講座は、昨年12月18日から始まり、本年2月19日までの計5回。諏訪市清水の寿司処「すし春」の店主小平晴勇さん(57)を講師に招き、受講者らが毎回、新しい題材に挑戦している。
3回目となる29日夜の講座では、アニメキャラクターのアンパンマンの顔が題材。目、ほっぺた、鼻などの各パーツごとに巻寿司を作り、それらを一枚ののりで巻き上げて完成させた。
小平さんは「細工寿司は各パーツをどう組み合わせればよいのか考えることで脳のトレーニングになる。家族が一緒になって作ることでコミュニケーションも深まる」と話していた。
受講生らは、太巻きの断面に見事に顔が表れると「かわいい」などと感激の様子。一人の主婦は「家でも孫に作って食べさせてあげたい」と笑顔を見せていた。 -
伊那図書館読み聞かせ講座

伊那市立伊那図書館で28日、読み聞かせ講座の第1回「本の楽しさをつたえる『ブックトーク』と『読み聞かせ』」があった。市内を中心に約50人が、本の魅力をバラエティ豊かに伝えるブックトークの方法などを熱心に学んだ。
3回連続講座で、第1回は伊那小学校図書館司書の矢口芙美子さんが講師を務めた。
ブックトークは、本を紹介する方法の一つで、あるテーマに沿って数冊の本をつなぎながら紹介する。本を読んでもらうことを目的とするため、対象は小学2年生くらいからで、トークの組み立て例として▽テーマに合わせて本を集める▽対象や状況などを考えて本を選ぶ▽紹介順序を決める▽変化をもたせる工夫をする▽紹介した本のリストを作り配布する-ことを説明した。
「本のソムリエ、あるいは試食販売のおばさんやお姉さんと思ってもらうといい。相手が本に関心を持つように、さわりをちょっと紹介する」とし、ブックトークには、「テーマに合わせて数冊の本を紹介すると全体の雰囲気が出て、相乗効果で一冊の本の面白さが際立つ効果がある」と話した。 -
箕輪町消防団夜警巡視

箕輪町消防団は昨年12月中旬から、各分団ごとに町民の安心、安全のため火災予防を呼びかけて夜警に取り組んでいる。29日夜、平沢豊満町長、消防署長、箕輪町警部交番所長、消防団長らが各分団を巡視し、団員を激励した。
第4分団の屯所では幹部12人が整列。岡孝之分団長が、夜警実施状況を報告した。第4分団は、昨年12月25日から2月10日まで延べ27日間の日程で、午後7時45分から10時半まで、4人が木下区内を2回夜警している。
平沢町長は「長期間寒い中ご苦労様。年末年始に火災がなく安心して暮らしている。まだ火を使う機会が多い。安全安心のまちづくりのため、予防消防に徹底してほしい」、平沢久一団長は「空気が乾燥し火災が発生しやすい。予防消防に努めて頑張ってもらえばありがたい」と訓示した。
箕輪町警部交番の倉田千明所長は、「夜警活動は地域の方の安全を守るため非常に大事。交通事故に遭わないように、また車上被害に遭わないよう車の管理をお願いする。健康に留意して頑張って」と激励した。
夜警状況は、第1分団2月1日まで延べ34日、第2分団2月13日まで延べ38日、第3分団2月3日まで延べ27日、第5分団3月7日まで延べ32日、第6分団2月15日まで延べ53日。
201/(火)
