-
高遠小5 カヌーで三峰川下り

伊那市の高遠小学校の遠足が28日にあった。好天に恵まれ、5年生は手作りのパドルを使い、カヌーで三峰川を下った。
地域の自然に触れようとカヌー作りに取り組む5年生(北村勝行教諭、35人)は、夏休みなどに地域材でパドルを作った。児童たちから「パドルを使いたい」と声が上がり、遠足で川下りを計画。事前に、プールや高遠湖などでカヌーをこいだり、ひっくり返った場合の対処法などを練習して臨んだ。
伊那小から木製の手作りカヌーを借り、児童たちは高遠町の山田河原駐車場付近の三峰川を出発。約6キロ下流の榛原河川公園を目指した。
1そうに児童4人が乗り込み、石の位置などを確認し「右、右」と声をかけながら、パドルで操作。川の流れがあるところは2人ずつが交代で乗り、水量が少ないところはカヌーを持ち上げて歩き、協力し合い、榛原河川公園手前までこいだ。
川の流れに怖さを感じた児童もいたようだが、男子児童(10)は「底をすったところもあったけど、楽しい。今度は自分たちで作ったカヌーに乗りたい」と話した。
冬休みには、カヌー作りに挑戦する。 -
いけばな池坊展

華道家元池坊伊那支部(有賀サエ子支部長)の創立60周年を記念した「いけばな展竏忠ヤ・心みつめて」が28日、伊那商工会館イベントホールで始まった。10月1日まで。
会場にはコスモス、リンドウ、ワレモコウなど季節の花を使い、伝統的な生け方に加え、現代の建築様式に合わせた生け花約400点が並ぶ。正面には、節目を祝い、松を中心に、赤・白色のウメモドキ、ヒバなどを生け込んだ教授者11人の合作(幅5メートル、高さ3メートル)が飾る。
また、教授者が指導する高校生の作品も。
作品は前期と後期に分け、29日終了後に入れ替える。
有賀支部長(70)=箕輪町=は「家庭や地域の支えがあって、60年の節目を迎えることができた。心をいやす一輪の花の美しさを見ていただきたい」と話す。
伊那支部は1948(昭和23)年に発会。引立教授者64人を含めた会員は約1560人。1年おきに支部花展を開くほか、地元の公立病院などで生け花を飾っている。
開催時間は午前10時縲恁゚後5時(30日は6時)。入場料300円。 -
伊那東部中・合唱部 全国大会出場を報告
伊那市の東部中学校合唱部(寺沢直子部長、約80人)が10月8日、東京都・NHKホールであるNHK全国学校音楽コンクール中学校の部に出場する。同大会の全国大会出場は創部以来初めて。26日夕、部長、副部長、唐沢流美子顧問の5人が市役所を訪れ、小坂樫男市長に大会での健闘を誓った。
同合唱部は、南信地区大会(出場12校)、県大会(同21校)、関東甲信越大会(同14校)をすべて最高賞の金賞で勝ち上がり、全国大会出場の切符を手に入れた。本大会では、全国から11校が集まり、課題曲と自由曲の2曲で歌声を競う。
自由曲の「IMBENI(インベニ)縲恪ーの夜明け縲怐vは、合唱部のために作詞、作曲され、アフリカのサバンナの地平線から太陽が昇る様子をイメージした作品。打楽器のマリンバの伴奏で、部員35人が混声5部合唱する。唐沢顧問によると、マリンバを伴奏とした自由曲は全国でも珍しいという。
地区大会が始まる約1カ月前から楽器を手にしたというマリンバ奏者の常田大希君(3年)は「サバンナの大自然をイメージし、合唱に合った演奏を心がけたい」。寺沢部長は「ここまでこれたのも仲間の力があったからこそ。みんなで1位を取れるよう頑張りたい」と意気込みを語った。 -
小学6年生が赤穂中授業参観

駒ケ根市の赤穂、赤穂東、赤穂南の3小学校の6年生約300人は27日、来春入学する赤穂中学校を訪れ、中学生の授業の様子を参観した=写真。教室をいくつか回って先輩の授業の様子をじっくり見学した児童らは「数学が超難しい」、「英語って全然分からなかった」、「中学生は授業に集中していてすごい」などと小声で感想をささやき合っていた。
体育館では先輩の生徒が中学での生活について「先生は厳しいけれど頼りになる」、「行事はすべて生徒会が行う」、「部活動はとても楽しい」などと紹介した。担当教諭は科目に英語が加わることや、前期、後期にそれぞれ中間と期末の2回のテストがあることなどを説明した上で「いろいろ不安もあると思うが、今一番大切なのは毎日しっかり生活し、きちんと小学校を卒業すること。皆さんの入学を待っています」と呼び掛けた。 -
オカラコづくりに挑戦 十五夜の伝統行事楽しむ

上伊那地方に伝わる十五夜の伝統行事である「オカラコ」づくりが27日、伊那市の旧井沢家住宅であった。地元住民でつくる伊那部宿を考える会(田中三郎会長)の企画。会員15人が参加し、もち米をすりつぶしてつくった「オカラコ」などを縁側に供え、満月が出てくるのを待った。
忘れ去られつつある伝統行事を後世につなげよう竏窒ニ昨年から始まり今回で2回目。参加者たちは、水に一昼夜浸したもち米6キロを2基の石臼を使ってすりつぶし、鏡もち状にした。縁側には五穀豊穣(ほうじょう)を願い、各自で持ち寄ったサトイモやカボチャ、ススキなどを一緒に供えた。
「懐かしい光景だね」「子どものころはもちをつまみながらつくったもの」などと60縲・0歳代の会員らは、昔を振り返りながら「オカラコ」づくりを楽しんだ。供え終わったもちは、野菜と一緒に味噌や醤油仕立ての汁にして食べる予定だ。 -
夏まつりの行方は?
2年に一度の宮田村のみやだ夏まつりは来年が開催年にあたり、村は25日に各区長から今までの反省も踏まえて意見を聞いた。「動員的な受け止めをして参加している人も多い」といった意見や、今までも議論になった内容のマンネリ化などが再度浮上。村は昨年のまつり後の反省会で前向きな意見が寄せられたこともあり、開催を前提にしているが、費用対効果などの面からも岐路に立っている。
当初は毎年開催していた夏まつりだが、2004年から隔年に変更。前回の昨年は各区が中心となる従来の踊りに加え、参加団体を募って新たな取り組みを掘り起こすなど、改革も進めている。
村商工観光係は、区長会の意見を集約して来年の開催に向けて前進させる予定だったが、再度検討を深めることに。
「色々な面で曲がり角に来ていることも確か。改めて区長さんの意見など聞きながら議論を深めていく」と同係は話す。 -
七久保小学校が手紙渡し、82回目

)
1通の手紙に安全運転への願いを込めて-。飯島町七久保小学校4、6年生53人は26日早朝、七久保の広域農道沿いで、交通安全、無事故を願い、恒例の手紙渡し活動をした。
同校は1967年4月から春秋の全国交通安全運動に合わせ、手紙渡し運動を展開し、今回で82回目。
児童らは通勤途中のドライバーに大きな声で「おはようございます」と声を掛け「スピードは控えめにして」「飲酒運転は絶対にしないで」など気をつけて欲しいことや、安全歩行への決意を書いた手紙を手渡した。ドライバーは「ありがとう、後で読ませていただきます」と受け取っていた。 -
宮田中創立60周年で同窓会が心身たくましくと善意

宮田村宮田中学校の創立60周年を記念して同校同窓会(浦野英喜会長)は25日、100インチのプロジェクターや大型ハイビジョンテレビなど150万円相当を同校に寄贈した。「心身たくましい子どもに育ってほしい」との願いから、記念誌や記念式典を行うのではなく、生徒にとって有意義な実用品を選択。同窓生や地域の多大な善意に、同校や村教育委員会は「生徒の成長した姿で恩返ししていく」と感謝した。
同窓会は創立35周年、50周年にも記念事業を行なっているが、今回はあえて「子どもたちのために実のあるものを贈ろう」と重視。当初80万円を目標に同窓会員や地域の賛同者に善意を募ったが、倍近い寄付が集まった。
給食のランチルームで使う丸イス320脚、DVDプレイヤー2台、スポットライト一式、さらに各教室分の電波時計11台も購入。
この日は浦野会長、副会長の田中正登さん、春日敏治さん、会計の加藤瞳さんが同校を訪れ目録を手渡した。
新井洋一教育長、帯刀昇校長は「いずれも学校教育に欠かせない備品。皆さんの厚意をかみしめ、大切に使わせて頂く」と感謝。
浦野会長は「学校のみんなが使えるものを選んだ。厳しい時代だからこそ、子どもたちの心と体の健全を願ってます」と話した。
同校は1947(昭和22)年創立で、卒業生は3月末現在で7037人を数える。 -
絶好の秋晴れ、宮田小が遠足

宮田村宮田小学校は絶好の秋晴れとなった26日、遠足を行った。学年ごと元気に目的地へ。歩いて地元の素晴らしさを再発見した。
2年生は郷土の川に親しもうと、天竜川、太田切川へ。村内の大久保ダムを見学したり、川遊びを満喫した。
道中では、栗や木の実を拾ったり、友達同士会話を楽しんだり。徐々に秋色が増す風景を体で感じていた。
他の学年も登山したり、工場やお寺の見学、公園遊びなど多彩な内容で遠足を楽しみ、友情も深めていた。 -
赤穂小秋の交通安全教室

秋の全国交通安全運動(21日縲・0日)期間中の25日、駒ケ根市の赤穂小学校(高野普校長)は1・2年生を対象にした秋の交通安全教室を開いた。児童らは室内で啓発ビデオを見た後、グラウンドに出て横断歩道を安全に渡る訓練を受けた。信号機のない横断歩道の渡り方では、歩道の手前に車が止まった時も安心せず、車の後ろから別の車が追い越して来ないかよく確かめることなどを教員らに繰り返し指導されていた=写真。
指導後、児童ら一人一人に「安全な歩き方仮免許証」が手渡された。今後1週間ほど教員らが児童らの様子を見守った上で・ス本免許証・スが交付される。
同小は26日に5・6年生、27日に3・4年生を対象に交通安全教室を開く。 -
「老いから知恵を! 若さからエネルギーを!」作品展

日本の伝統的な民芸品などの制作を通じて高齢者と若い世代に心の交流を図ってもらおうと駒ケ根市の駒ケ根高原美術館が8月に開いた作品制作講座「老いから知恵を! 若さからエネルギーを!」の作品展が同館で10月14日まで開かれている=写真。市内の2歳縲恍・w生など約30人が参加して制作した正月飾り、わら細工の花瓶、和紙を使った紙人形など約20点のほか、指導に当たった駒ケ根市高齢者クラブ連合会(高坂繁夫会長)の会員らの絵画、写真、陶芸、書道など約50点が展示されている。同企画の一環として8月、美術館学芸員が赤穂中学校美術部員を対象に行った出前講座で生徒らが制作した絵画「50年後の私」約30点も併せて公開されている。
入館料は大人千円、大学・高校生800円、小・中学生500円(土曜日無料)。問い合わせは同館(TEL83・5100)へ。 -
南箕輪中「若竹祭」28、29日
南箕輪村立南箕輪中学校の文化祭「若竹祭」は28、29日に開く。
テーマは「南中物語(ストーリー)」。サブテーマは「完成させよう 全員が活躍し力を合わせてつくる 若竹祭という名のハッピーエンド」。
28日は開祭式、選択発表、有志発表、展示見学、生徒会企画、綱引き。29日は合唱祭、講演会、展示見学、文化系クラブ発表、閉祭式。
選択発表会は2年選択体育「なわとび」、3年選択英語「『不思議の国のアリス』劇」、3年選択体育「跳び箱・マット」、3年選択音楽「琴演奏」。有志発表は太鼓演奏「屋台囃」。生徒会企画はクラス対抗のミニ運動会で、種目は台風の目リレー、熊が出たぞゲーム、人文字。文化系クラブ発表は吹奏楽部、科学部。
講演会は伊那市西箕輪公民館長の城取茂美さんが「21世紀を生きる3つのヒント」と題して話す。 -
箕輪中ふきはら祭28、29日
箕輪町立箕輪中学校の文化祭「ふきはら祭」は28、29日、「CIRCLE〈輪〉縲恪ナ高の瞬間を最高の仲間と縲怐vをテーマに開く。
28日は開祭式、弁論会、ステージ発表、展示見学、スポーツフェスティバル。29日はステージ発表、合唱コンクール、閉祭式。
弁論会のテーマは「伝えよう自分の想い 受け止めよう相手の想い」。全校が選んだ各学年2人、計6人の弁士が想いを伝える。
ステージ発表Iは箕輪太鼓Jr、各学年総合。発表IIは古田人形部、2年選択ア・カペラ、3年選択ア・カペラ、2年選択英語。発表IIIは合唱部、2年選択ミュージックレストラン、3年選択ミュージックレストラン、3年選択ダンス。発表IVは演劇部、吹奏楽部。
スポーツフェスティバルの種目はN人N+1脚、4000メートル仮装リレー。展示発表は、各クラスのほか生徒会、部活、2年選択、3年選択がある。 -
宮田中「梅樹祭」28、29日に

みんなで創りあげる文化祭に‐。宮田村宮田中学校は28、29日に「第49回梅樹祭」を開く。生徒会など一部の生徒が盛り上がるのではなく、全校で準備段階から協力。環境問題や募金を通じて世界の子どもたちに目を向けた取り組みもあるなど、多彩な視点で学習の成果を発表する。
今年は「証(あかし)縲恷ヲそう今このときこの場所にいる証を」テーマに掲げた。
「一部の人だけでなく、全校みんなで盛りあがることを重視しました」と梅樹祭実行委員長の岸本彩香さんは話す。
必要な資金は地域の協力でアルミ缶を回収。給食の牛乳ビンのふたを全校で5月から集め始め、立派な壁画パネルも完成した。
初日の開祭式は牛乳パックや空きビン、空き缶を再利用したリサイクル楽器の演奏も。
選択教科に加え総合学習の取り組み発表を初めてプログラムに盛り込み、展示やステージで披露する。
学級代表の弁論大会、演劇部、吹奏楽部の発表、運動会形式のわれらの広場なども。保護者や地域にも開放し、友情を深めながら励む今の姿を伝える。
岸本さん、小田切昂軌生徒会長は「とにかくみんなで楽しみ思い出にしたい」と期待。全員で成功に結び付けようと準備は万端だ。主な日程は次の通り。
【28日】開祭式(午前8時50分)▽弁論会(9時20分)▽選択教科発表(10時15分)▽演劇部発表(午後1時15分)【29日】総合学習発表(午前8時半)▽吹奏楽部発表(午後12時45分) -
十五夜の風習「オカラコ」を給食で

十五夜の25日、宮田村宮田中学校は上伊那地方に伝わる十五夜の風習「オカラコ」の汁物を給食に。生徒たちは郷土の伝統に舌鼓を打った。
「オカラコ」は季節の根野菜や米をつぶした丸餅を供える風習。十五夜の翌日にみそ汁に入れて食べるのが昔からの習わしだ。
近年では継承する家庭も少ないが、宮田中では4、5年前から十五夜にあわせ、給食で伝統をつないでいる。
この日も大根やカボチャなどが入った汁を食べた生徒たち。同校栄養士の小原啓子さんは「食を通じて少しでも地域の伝統に親しんでもらえれば」と話していた。 -
姫宮神社祭典で浦安の舞
宮田村南割区の姫宮神社秋季例祭は22日に宵祭り、23日に本祭りを開き、地元の女子高生4人が巫女に扮して「浦安の舞」を優雅に奉納した。宵祭りは年番の新田区が余興を用意。寸劇や踊りなど多彩な演目で、華やかに秋祭りを祝った。
同神社では昨年初めて例祭で浦安の舞を奉納。今年も昨年に引き続き地元日本舞踊グループ「鶴乃会」が協力した。
巫女になった4人も昨年と同じ中村千鶴さん、馬場桃香さん、多田井優海さん、吉沢友里恵さん。いずれも今年から高校に進学したが、初心にかえって稽古を積んできた。
「このような地域の祭りに出演し、伝統に親しむことは良いことだと思う」と師匠の中村ゆみさん。
宵祭りでは神社で奉納し、大田切区の大田切獅子とともに舞台にも出演。幻想的な4人の舞姿に、訪れた人たちは固唾を飲んだ。
続いての新田区による余興は楽しく賑やかに。8つの班や有志が練習を積んできた演芸を披露し、歓声があがった。 -
【国画会会員 画家 柴田久慶さん】

中学の時、級友らとともにごみを埋める縦穴を学校の一隅に掘った。数メートルのかなり深い穴だ。中央部に残った、身長を超える高さの土の塔を見て雷に打たれたような衝動を受け、スコップをつかんで彫刻を始めた。あっけにとられる級友らを尻目に、独り夢中になって人間の姿を彫った竏秩B級友の話によると、飛んで来た先生が彫刻の出来に目を見張ったという。
「遊びなどではなく、真剣だった。だがなぜ突然そんなことをしたのか今でも分からない。作品として残したいとか人に見せようなんて考えはなく、ただ彫りたかった。その前後のことは全然記憶がない。覚えているのはあの日、あの場所で一心不乱に彫った、ただそれだけだ」
◇ ◇
伊那市手良の農家の出身。子どものころから絵が好きで「プロになれなくてもいいから一生描いていくつもり」でいた。高校の先生に勧められて美大を受験したが落ちた。家庭も豊かではなく、浪人してまでも竏窒ニいう気持ちもあって東京の会社に就職。だが都会の水が肌に合わず、実家に帰って印刷会社などでデザインの仕事をしながら黙々と絵を描いていた。20歳代後半になり「どうせなら何をおいても好きなことをやろう」と覚悟を決め、勤めをやめた。
画家としてやっていける自信がついたのは40歳を過ぎてから。県展で86年に県知事賞、87年には10年に一度しか与えられない記念賞を受賞した。
前後して国画会では新人賞、国画賞を受賞。厳しい審査を通過して準会員となったが、次に目指した正会員はさらなる高みにあった。全国から優秀な作家が集まっている国画会の正会員の座は簡単に手に入るものではない。数年間挑戦を続けるうち、認められたい思いがあせりに変わり、自分を見失った。
ある年、出品の期日が目前に迫っても描き上がらなかった。午後から朝まで夜通し飲まず食わずで描いたが、いい色が出るはずはない。朝見たらひどい様相になっていた。さらに丸一日間、何も食べずに必死になって描き続け、いくらかましな出来になった。
「何とか出品にこぎつけることができた。恐る恐る会場に行ってほかの作品と比べて見たら、それほど恥ずかしくない程度に仕上がっていてちょっとほっとしたね。しかし、こんなことやっていては体を壊してしまう、もっと力をつけないといけない竏窒ニあの時に痛感させられた」
2年後、晴れて念願の正会員として認められた。見渡せば芸大出ばかり、という世界。だが、芸大どころか美大にさえも行かなかった自分でもここまでやれるんだ、と大きな自信になった。
「宝になっているのが感受性の豊かさ。それは大事にしたい。若い時は人に話もろくにできず、劣等感の塊だった。だが、それが逆に今の冷静な見方につながっているともいえる。順調に来た人には得られないものかもしれないね」
◇ ◇
ずっと人体を描いてきた。表面でなく、内面的な人間の在りようを表現しようと苦しんで描いてきたが、年齢と経験を重ねるにしたがって絵に対する取り組み方も変化し、肩の力を抜いて描けるようになった。
「以前は内面をぶちまけるような絵、思いつめたような快くない絵を描いていた気がする。だが周りを見てみれば、きれいな物は自然の中にいくらでもあるんだ。絵はまず美しくなければならない。美しいものに迫りたい。生み出したいんだ。作品の良し悪しは見る人にお任せだから自分にはどうしようもないが描く喜びは…。何かが生まれ、形になっていくこの充足感は自分にとって何物にも代えがたいものなんだ」
(白鳥文男) -
下平幼稚園運動会

駒ケ根市の下平幼稚園(米山さつき園長)で22日、園児らが待ちに待った親子運動会が開かれた。快晴の秋空の下、かけっこやダンスなどさまざまなプログラムに出場した園児らは練習の成果を発揮して元気よく伸び伸びと走ったり踊ったり。保護者も園児と一緒になってさまざまな競技を楽しんだ。
『親子でゴーゴー』は(1)園児の乗った一輪車を親が押して走る(2)親におんぶした園児が玉入れ(3)フープに親子が一緒に入り、走ってゴール竏秩B出場した親子は楽しそうな笑顔でゴールを目指した=写真。観衆からは「頑張れ」、「もう少しだ」などと大きな声援が飛んでいた。
応援に詰め掛けた保護者らは躍動する元気な姿をビデオに収めようとカメラのレンズを向けながら、子どもの成長ぶりに目を細めていた。 -
信州大学農学部で地域連携フォーラムが開催

地域の行政や住民、企業と大学との連携について考える「地域連携フォーラム2007」が22日、南箕輪村の信州大学農学部であった。各方面の代表者によるパネルディスカッションでは農山村の再生のために大学、住民、地域行政などが、それぞれの立場から取り組むべき課題について考えた=写真。
基調講演では、島根大学名誉教授の保母武彦氏が農山村再生策について提言。三位一体改革の影響で厳しい財政状況を強いられている地方の自治体に対し「生き延びるだけなら守りだけでいいが、生き残るには攻めが必要」と指摘。積極的な姿勢で「島まるごとブランド化」などに取り組む島根県海士町の事例を紹介し、「立て直しにはまず、行政担当者の意識改革が大切。役場が替われば地域も変わる」と語ったほか、「大学側は真剣になっている地域の人たちを一緒に取り組み、結果にも責任を持つことが必要」とした。
また、パネルディスカッションでは、飯田市企画部の井上弘司企画幹が同市におけるグリーンツーリズムへの取り組みを紹介。過疎高齢化地域では地域が持続していくための振興策となりつつあることを示し、住民一人ひとりが考えながら取り組む中で地域の持ち味を発揮していくことの大切さを訴えた。 -
十五夜の「オカラコ」特別展

今年の十五夜(仲秋の名月、旧暦の8月15日)は9月25日にあたるが、宮田村民会館内にある向山雅重民俗資料館で、村内に伝わる十五夜の風習「オカラコ」の供え物を再現した特別展示が行われている。
村内では米をつぶして丸い鏡餅のようにした「オカラコ」を十五夜に供える風習があったが、現在では継承している家庭はごくわずか。
村教育委員会は「身近にあった習わしを見つめ直してもらおう」と昨年に続いて特別展を企画した。
町三区の白鳥静子さんが手作りしたオカラコに、里芋などの根菜、お神酒、ススキなどを昔ながらに飾り付け。満月も浮かべて風情を見事に再現した。
訪れた人たちは懐かしがったり、「オカラコって初めて聞くね」と興味深げ。情緒あふれる村の文化を再発見している。 -
「スペイン・アンダルシアの旅」展

駒ケ根市と東京都在住の知人らが集まった駒ケ根倶楽部(池田恭一代表)が今年3月から4月の1カ月間にわたって旅行したスペイン・アンダルシア地方の楽しい思い出をこめた絵画と写真の展示会が駒ケ根市の大沼湖畔「森のギャラリーKomorebi」(こもれび)で10月1日まで開かれている。駒ケ根市の画家加納恒徳さんの油彩画や池田さんのパルテル画、現地でのスケッチなど約20点の絵画のほか、旅の楽しさがしのばれるスナップ写真の数々や思い出の品などを多数展示している。
旅に参加したのは20縲・0歳代の男女9人。自炊生活をしながらレンタカーでアンダルシアの28カ所を訪れ、異国の自然や文化をたっぷりと楽しんだ。
入場無料。午前10時縲恁゚後5時。火、水曜日定休。問い合わせは喫茶エーデルワイス(TEL83・3900)へ。 -
お茶の水女子大生が伊那小参観
お茶の水女子大学(東京)の学生26人が20日、教育実地研究のため伊那市の伊那小学校の総合学習・活動授業を参観した。学生らは児童たちと一緒に授業を受けながら、今まで自分たちが経験してこなかった・ス教育感・スを身に付けていった。
約30年前から総合学習・活動を先進的に始めている同小には、毎年、全国の教育関係者らが授業参観に訪れている。お茶の水女子大の訪問は初めてで、同大学関係者によると、「子どもにとって必要な学力とは何かを考えるため」訪れたという。
参加したのは、文教育学部人間社会学科の1年生を中心とした学生。林の中に作った基地やロープの遊具で遊んだり、牛乳パックから紙を作ったりと活動する、低学年、高学年、特別支援学級の計14クラスの授業を見学した。
田んぼに生息する生物を捕まえ、育てようと活動する3年森組の授業を見学した、仲手川ひとみさん(18)は、児童たちと一緒にトンボやカエルを手づかみで採集。「実体験を重ねることで、自分の気持ちを素直に表現できる子どもが育っているのだと感じた」と話していた。
児童たちと昆虫採集を楽しむ女子大生たち -
伊那弥生ケ丘高校生が中川中学校で模擬授業

私たちの先生は高校生-。中川村の中川中学校で18日、伊那弥生ケ丘高校(伊那市)生徒による模擬授業があった。同高校3年の北原拓真君が1年2組29人に社会科日本史の縄文時代、弥生時代を教えた。中学生は熱心にノートを取るなど真剣に授業を受けていた。
職業や勤労に対する理解を深め、進路意識を高めるキャリア教育の一環。高1年2人、3年2人が来校。教育実習計画に沿い、片桐校長から「教員志望の心構えと授業の見方」の講義を受けた後、先輩教諭の話を聞いたり、各教室を回って授業参観もした。
5時間目は4人を代表して、北原君が1年2組の社会科の模擬授業に挑戦した。
北原君は縄文時代のイメージ図を使って、概要を説明した後、黒板に、旧石器時代と縄文時代の相違点を列挙し、項目ごとに、副読本で確認させながら、授業を進めた。「1万年前」「縄文土器」「磨製石器」「三内丸山遺跡」と重要字句に丸印を付けるなどして、ポイントを押えた。
堂々とした北原君の先生ぶりに、生徒たちは全く私語もなく、鉛筆を走らせたり、説明に耳を傾けていた。
50分間の授業を終え、北原君は「とても緊張した。ただ、自分で説明しただけに終ってしまった。教えることは難しい」と感想を。一方、中学生は「黒板の字は見やすかった」「説明は分り易かった」と好評。片桐校長は「内容も良く、授業の組み立ても良かった」とほめていた。 -
世話して馬と友だちに、宮田小、中学校特別支援学級が交流学習

宮田小、中学校の特別支援学級の子どもたち9人は20日、馬の世話と乗馬を飯島町のアグリネーチャーいいじまで体験した。ただ楽しむだけでなく、フンの片付けなど一緒に汗して交流。動物と接するなかで、思いやりの心も育んだ。
最初は「ちょっと怖い」と話す児童もいたが、愛らしいポニーにエサをやり「かわいい」と満面の笑顔に。
ポニーより数倍大きいアメリカンクォターホースの「スキップ」のブラッシングも行い、フンを片付けるなど馬房の清掃もした。
「スキップ」と友達になった子どもたち。順番に乗馬も体験し、「気持ちいい」と堂々の騎手ぶりをみせた。
宮田小5、6組と宮田中若草学級の交流は年に数回実施。この日は飯ごうすいさんも行い、若草学級は同所に宿泊して、自然体験を満喫した。 -
天竜川 いのちの鎖

伊那谷の中央を流れる天竜川は、諏訪湖から河口まで約213キロ。中央アルプスや南アルプスの清流と合流し、人々の暮らしの中を流れ、遠州灘から太平洋へ注ぐ。
台所からの排水、工場排水、農地からの浸透竏窒サの天竜川の上流に暮らしている私たちの日々の暮らしは、全て下流へとつながっている。森の栄養分は川を通じて海に注がれ、魚のいきものたちを育む。生きている川でなければ、そのいのちの栄養分を下流に運ぶことはできない。
天竜川河口に広がる砂浜は、絶滅が心配されるアカウミガメの産卵地。天竜川が運ぶ砂がこの砂浜を形成してきた。上流に住む私たちが、このアカウミウガメの未来に大きく関わっていることは、言うまでもない。
伊那市新山小学校がある新山地域は、世界一ちいさなハッチョウトンボのふるさととして知られている。ハッチョウトンボも、一定の自然条件のもとでなければ育まれない貴重な生物だ。今春、珪藻研究者飯島敏雄さん(諏訪市在住)を迎えて、新山小学校で野外授業が開かれた。その授業の中で、ハッチョウトンボを育む水の中を観察し、そこに日本一大きな珍しいクチビルケイソウという珪藻の存在を確認した。ハッチョウトンボの幼虫が餌にしているミジンコは、この珪藻をエサにしている。つまり、このクチビルケイソウが生き続ける水環境を保つことが、ハッチョウトンボを守ることにつながるのだ。
この野外授業での観察で、貴重な珪藻の存在を知り、その水環境が、新山地域を流れる新山川、三峰川を経て天竜川につながり、その先に広がる砂浜で産卵するアカウミガメにつながる竏秩B
「天竜川河口に行って見たい」「アカウミガメの産卵を見てみたい」。新山小学校の子どもたちの中で、そんな気持ちがふくらみ、7月末、親子で天竜川河口の砂浜へ出かけることになった。 -
粘土に夢中、子育て学級
宮田村公民館の子育て学級はこのほど、粘土で一輪挿しをつくろうと挑戦した。親子で楽しむ姿もあり、今後は素焼きして色を塗る。
大原区の仁科智弘さんの指導で、28組の親子が参加。久しぶりに粘土にさわる若い母親も多かったが、みんな夢中になって励んでいた。
仕上げた作品は11月の村文化祭に出品する計画だ。 -
南極の氷が飯島小、中に届く

南極の氷が届いたよ-。飯島町の飯島小学校と飯島中学校に19日、南極観測船「しらせ」が南極から運んできた貴重な南極の氷が届き、子どもたちを喜ばせた。
このうち、飯島小学校では体育館で全校児童に披露。子どもたちはクーラーボックスから取り出された縦10センチ、幅20センチほどの氷の固まりを見て「わあ、すごい!」と歓声を上げた。
氷は町出身で飯島町中町在住の自衛隊長野地方協力本部、伊那地域事務所の松田千眞男さんらが持ち込んだ。
松田所長は飯島町担当の山浦和之さんと2人で訪れ、贈呈を前に、児童らにスライドを使って南極について話した。
この中で、松田所長は「南極観測船『しらせ』は11月に出発し、オーストラリア経由で1カ月掛かって南極の昭和基地に到着する。南極ではオゾン層や地質、生物について研究している」と説明。南極にすむクジラやアザラシ、ペンギンが紹介されると、子どもたちは興味津々の様子で画面に見入った。オーロラの写真には「きれい!」「オーすごい!」と感嘆の声が上がった。
同校ではこの氷は理科の実験などに使う計画。 -
伊那技専から受託の職業訓練修了
宮田村商工会(前林善一会長)運営の宮田ビジネス学院が、県伊那技術専門校から受託した求職者対象のITビジネス応用力養成コースがこのほど、366時間に及ぶすべての日程を終えた。11人の受講者全員が修了し、それぞれ次のステップへ向かった。
閉講式で、石川秀延伊那技専校長が「これからが勝負。努力を重ね、意欲あふれる頼もしい人材になることを期待しています」とあいさつ。一人ひとりに修了証を手渡した。
受講者は20代から50代の女性。年齢もキャリアもさまざまだが、3カ月に及ぶ訓練は全員にとって新たな転機となったようだ。
「若い人たちからいろいろ学ばせてもらった。この頑張りを胸に就職活動に励みたい」などと語り合い、パソコン技術や各種資格を取得するだけでなく、仲間の輪もはぐくんだ3カ月間を振り返った。
##写真
修了証を受け取り3カ月間を振り返った -
第1回日本工業大学マイクロロボコン高校生大会で優勝
箕輪工業高校1年
井上大樹君(16)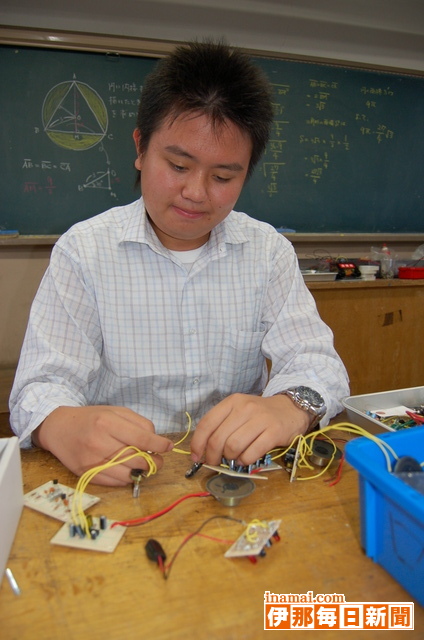
初めてのロボット作りは楽しかった竏秩B
今月1日、日本工業大学(埼玉県)が開催した「第1回日本工業大学マイクロロボコン高校生大会」に自身で製作したマイクロロボット“Robot Industries1号”とともに出場。全国から集まった約100台のロボットを抑えて優勝した。
大会は2・54センチ角しかない“1インチロボット”がコースを周回するタイムを競い合うというもの。競技者は主催者から事前配布されたキットを使ってロボットを製作し、中に組み込むマイクロコンピューターを調節して、黒いケント紙の上に描かれた5ミリ幅の白いラインの上を正確かつ迅速に追跡するようにしていく。
「優勝できるとは思わなかったので、嬉しい」と笑顔を見せる。
◇ ◇
“ロボコン”ってどんなことをやっているのだろう竏秩Bそんな興味から、友人2人を誘って大会へのエントリーを決め、8月上旬からロボット製作を開始した。ロボット製作は初めてだったが、電子工作などではんだ付けなどは経験したこともあり、ほどなくしてロボットは完成した。早速動かしてみようとスイッチを入れたが、動かない。もともと大学から配布されたキットは、ただ組み立てただけでは動かない代物。そこからプログラムを調整する作業が始まった。
最初は動かないロボットを動くようにするにはどうすればいいか、次は少しずつ動くようになったものを早く走らせるには竏窒ニ、考えながら、調整用のコースを何度となく走らせた。
「どう走らせればいいのかということを考えて、プログラムを作るのは初めての経験だった。やっているうちに新しい発見もあり、動くようになるマシーンを見るのが喜びになった」と振り返る。
◇ ◇ -
高教祖が上伊那農業高校定時制を多部制・単位制高校に統合する計画の再検討を求める街頭活動

長野県高等学校教職員組合(高村裕執行委員長)は14日、08年4月開校となる新しい多部制・単位制高校に統合する上伊那農業高校定時制の、生徒募集停止に反対する街頭活動を伊那市駅周辺などで実施した=写真。
募集停止の見直しを求める活動は今回が初めて。9月県会が開会する9月末までの間に、県内12支部ごとに募集停止反対を求めるチラシ300枚を配布するほか、伊那市の9月議会には「上伊那上農高校定時制と多部制・単位制高校に統合する計画の再検討を求める意見書」(案)と、その採決を求める陳情書を提出している。
反対理由は▽定時制高校に通う生徒数が増加傾向にあること▽現在の定時制高校に通う生徒の多くが不登校経験者など、コニュニケーション面での配慮が必要なケースが多く、そうした生徒が実際に多部制・単位制高校に通えるか竏窒ネど。
内山到副執行委員長は「多部制・単位制高校そのものを否定しているわけではないが、不登校経験者など、多部制・単位制の夜間部が、定時制、通信制が担保できるのかを心配している。現場の教師や生徒、父母の声を聞いたうえでやってほしい」と話していた。
2710/(月)
