-
文化財防火デーパトロール

第52回文化財防火デーの関連行事として、箕輪町文化財保護審議会、箕輪消防署、町教育委員会は26日、町内文化財の防火パトロールをした。火災予防のための周辺環境整備や消火器の設置などを確認した。
パトロールは年1回。町にある指定文化財の防火、防災対策を目的に、文化財の管理者や所有者立ち合いのもと、消防署からアドバイスを受ける。
今年は、白山神社本殿、富田神社、養泰寺観世音菩薩像、高雲寺五大明王、南宮神社本殿・社叢の5件。
82年に町有形文化財に指定された富田神社本殿では、周辺にたばこやマッチなどがないか、ごみがたまっていないか、消火器は設置しているか、電気の配線は老朽化していないか-など、神社内や周辺を見てまわり、併せて、通常は見ることのできない文化財を確認した。
消防署では「神社は普段人がいないので、火災予防が一層大事になる。十分に気をつけてほしい」と注意を呼びかけた。 -
西駒郷作品展

西駒郷の利用者らによる作品展「第7回だれでもアート・ほっと展」が駒ケ根市役所1階ロビーで27日まで開かれている。絵画、書、手芸作品などの力作27点が展示されている=写真。
タイルを使ったモザイク作品「トトロの横顔」は保護部の利用者ら13人が美術専科の時間に作った大作。柔らかな色使いの楽しい作品に仕上がっている。
午前8時30分縲恁゚後5時15分。入場無料。 -
東保育園でコマ回し大会

宮田村東保育園は26日、コマまわし大会を開いた。正月から練習してきた成果を披露。「まわれ、頑張れ」と歓声をあげた。
年少園児は手回しゴマ。年中以上は、園のクリスマス会でプレゼントしてもらったひもでまわすコマで大会に臨んだ。
上手にまわせた子もいれば、失敗して肩を落とす姿も。それでも友だちの元気良くまわるコマに声援を送り、みんなで大会を盛り上げていた。 -
かるた・百人一首「はい」素早い攻防
高遠町の高遠北小学校で24日、恒例かるた・百人一首大会があり、全校児童が楽しんだ。
日本の伝統文化に親しもうと、国語の授業の一環。低学年がかるた、高学年が百人一首に挑み、学年関係なく4人ずつで競った。
年明けから授業を通してかるたや百人一首をしてきた児童たちは、「句がほとんど頭の中に入っている」(担当教諭)。低・高学年いずれも、児童たちは体を前に乗り出し、札をにらみつけては、句が読まれた直後に「はい」と大きな声で素早く取り合った。
何枚とれたか児童一人ひとりに記録賞が渡され、各自が前年の記録を参考に自己評価。2年の女子児童(8)は「いっぱい取れたよ」と喜んでいた。 -
地区活動に関する懇談会

飯島町は23日夜、文化館で地区活動に関する懇談会を開いた。区長や地区公民館長、町、教委など関係者13人が出席し、地区活動の現状と課題のほか、新たな自治組織や指定管理者制度の導入などの課題について意見交換した=写真。
はじめに、教委が地区活動・公民館活動に関する検討会の意見集約を報告。昨年8月2日縲・月27日まで全体会全5回、地区公民館全5回検討してきたが、結論が出ず、意見のまとめとして、(1)地区公民館方式(配置専従方式・派遣方式)(2)中央公民館方式(現状の体制で支援)-両論併記した。
検討経過を受けた基本的考え方として、中央公民館は5館並列を基本にしながら、社会教育主事は地域の実情、ニーズにより地区公民館事業を積極的に支援する。地区公民館の事業実施は、現行地区選出役員体制で行い、地区公民館長の任期を2年とする-とした。
また「協働のまちづくり」を進めるための組織「新たな自治組織」については、出席者からは「現行組織のほかに、新たに組織をつくると、負担増になる」「具体的に形が見えてこない」など懸念の声が上がった。 -
伊那市西箕輪
松岡みどりさん
雌雄2匹の獅子が共に舞う「羽広の獅子舞」は、400年の歴史を持ち、地元の男たちが継承してきた。その男たちに混じって紅一点、3年前からお囃子の笛を吹いている。
◇ ◇
東京都出身。もともと好きだった植物のことを神奈川県の大学で学んだ後、植物に携わる職に就いた。その中で樹木への関心が強くなり「どうせ学ぶなら自然が豊かなところで」と、信州大学農学部に編入。その時から羽広に下宿するようになる。
はじめは獅子舞があることも知らなかった。しかし、時々笛の音が聞こえてきた。「なんだろう」と、畑作りのアドバイスなどをしてくれる近所の男性にそれとなく尋ねた。「その時に質問した三ツ橋さん(屋号)は、獅子舞のお囃子をしている人で『練習だけで本番には出られないかもしれない。男ばっかりだけどやってみるか』と誘ってくれたんです」。
◇ ◇
出身地には伝統的なものがあまり残っていなかったため、地域に根ざしたものへのあこがれが強かった。地域に密着した生活を送ろう竏秩B伊那へ来て決意した。南アルプスを縦走したり、諏訪太鼓を習ったり。自分の畑でカブを栽培し、「羽広かぶ」のつけ方を大家さんに習ったりもした。
「なんでそんなに必死になってきたかって今になって思うと、私は地域の風景の一部になりたかったのかなって。地元との関わりを通して、地元風景の中にいる自分を確認していたんだと思うんです」 -
飯島中学校で入学説明会

飯島町の飯島中学校(竹沢代蔵校長)で23日、4月入学の新1年生の保護者を対象に入学準備の説明会を開いた。会に先だって、入学前に授業や学校を知っておこうと保護者が授業参観もした。
説明会では竹沢校長はチンパンジーのアイとその息子アユムの天才振りや、オオカミに育てられたカマラとアマラを紹介し、環境や教育の大切さを強調した後「中学に入学すると、環境が大きく変わるので、わが子の様子をしっかり見守り、気になることがあったら担任に相談してほしい。中学生活の3年間は一生の土台をつくる時、食生活にも気を配り、充実した中学生活を」と呼び掛けた。
引き続き、心の準備や部活動、生活のきまり、みなり、通学のきまりなど生活全般について説明があった。
このほか、制服や辞典、運動着など1年次に購入する学用品などにも触れた。 -
東中入学説明会

駒ケ根市の東中学校(向山健一校長)は23日、06年度入学予定の小学校児童と保護者を対象とした説明会を同校で開いた。参加者らは中学での生活、学習、規則や入学までの準備などについて担当教諭らの詳しい説明を受けたほか、授業参観や給食の試食、制服の採寸なども行った。中学生用の給食を食べた児童らは「小学校より量が多いな」などと明るい笑顔で話しながら、もうすぐ入学する中学への期待を膨らませていた=写真。
東中への入学予定者は中沢小の20人、東伊那小の18人のほか、本来なら赤穂中に入学するはずの赤穂東小、赤穂南小からの希望者5人を加えた計43人。赤穂地区からの入学は、竜東地区のみでは38人しか新入生がないため、現行の1学年2学級を維持できず1学級となることから、市教育委員会が希望者に東中への入学を認める指定学校変更の特例措置を初めて取ったことによるもの。市教委は来年度以降も当面続けていくとしている。 -
中学生が手作りロボットで競う 上伊那コンテスト2月11日

アイデアを凝らしたロボットを操り得点を競う、第3回上伊那中学生ロボットコンテストが2月11日、伊那市の伊那中学校である。本年は過去最多となる10校、50チームが出場を予定し、熱戦が期待される。上伊那家庭科、技術技術・家庭科教育研究会の主催。
競技は独自のロボットで紙製の輪を運び、筒に掛けることができた数で競う「パニックリング」と呼ばれるルール。2本の腕で輪を挟むタイプや、腕を輪の中に差し込み持ち上げるタイプなど、仕組みや動きが異なる生徒たちの創意工夫が披露される。
午前8時50分に開会式。9時20分から予選、11時10分から決勝大会を開始する。昼休みは、駒ヶ根工業、箕輪工業によるデモンストレーションもあり、関係者は多くの来場を呼びかけている。
上伊那大会に向けて、伊那市の春富中では24日、大会エントリー順位を決定する校内予選会を開いた。3年生の選択授業・技術(林孝一教諭)を受講する19人、6チームのうち、ロボットが完成している3チームが出場した。
校内予選1位に決まった、チーム「雷攻」の一人は「大会までに改良を重ねて、優勝したい」と意気込みを述べていた。 -
「六角観音供養塔」高遠町宝に
高遠町教育委員会は、西高遠諸町の相頓寺跡に残る江戸時代の石造物「六角観音供養塔」を町宝に指定した。
供養塔(高さ2・45メートル、幅70センチ)は、1747年に水上村(現・高遠町藤沢水上)の石工・九兵衛門が製作したことが分かる銘が刻まれている。町には2500体余の石造物があるなかで、石工の名が彫られたものは珍しいという。
難しいとされる六角型の面には観音菩薩(ぼさつ)の名が均整に彫られ、台座には卍字、その下に「緒人皆等得解脱」の文字などが記されており、技術が高く評価されているという。
昨年12月の町文化財保護委員会で、文化財にふさわしいとして意見がまとまり、町教委に申請。23日にあった町教委定例会で町宝への指定を決めた。 -
館報中川が200号発刊

中川村公民館は58年村発足時に創刊し、隔月で発行した「館報中川」が200号を迎え、特集記事満載の特集号(A4判、12ページ)を発刊した。
表紙のカラー写真は「新春の朝陽を浴びる中央アルプスと文化センター」。一般記事は06年成人式(1月3日開催)の新成人のあいさつ、05年度文化祭(11月4縲・日)の展示、ワンポイント体験-など。
特集記事は館報のあゆみ「創造と実践の公民館活動」と題し、第150号(97年9月)から199号(05年11月)の8年間の記事内容と社会状況を紹介した。
また、200号発刊に向け、曽我村長や北村教育長、松村公民館長ら5人が、公民館への思い、期待などを寄稿した。
裏表紙は「館報への提言」と題し、村内の幅広い世代の意見、感想を掲載、村民の生の声が読んで楽しい。 -
バイキング給食楽しむ

宮田村の宮田小学校3年生は19日、バイキング形式の給食を楽しんだ。栄養バランスの大切さも感じながら、自分の好みのメニューを選んだ。
パンやおにぎりの主食、エビフライ、コロッケなどの副菜、サラダ、デザートから、自分自身で好きなものをチョイス。食べれる量も考えて、一人づつトレーに盛った。
「どれにしようかな」とうれしい悲鳴。いつもの給食とはまた違った雰囲気で、食事の楽しさ、大切さを肌で感じていた。 -
お陣屋行燈市に向け、高札設置
江戸情緒を楽しむ飯島町のお陣屋行燈市は2月11、12日、広小路で開かれる。19日、町触組(原裕昭組頭)は市の開催日や場所を記した高札、立て看板などを設置した。
作業は8人が3班に分かれ、高札22本を町の公共施設、商業施設に立て、大型立て看板は多くの人の目に触れてほしいと、道の駅花の里いいじまとショピングセンターコスモ21の2カ所に、国道153広小路交差点前には横断幕も張った。
お陣屋行燈市の今年の目玉は花魁(おいらん)道中、人気の大型時代劇「必殺仕事人」のほか、代官行列、陣馬太鼓、どんどろしし舞など多彩なイベントが繰り広げられ、露店も多数並ぶ。 -
箕輪東小3年1組
ゆとり荘の利用者と交流
箕輪町の箕輪東小学校3年1組(19人、河西高明教諭)は21日、デイサービスセンターゆとり荘を訪れ、歌の発表や風船バレーで利用者と交流した。
3年1組は、2年生のときに生活科の授業でゆとり荘を訪問し、利用者と交流してきた。3年生になり、総合的な学習で地域探検やエースドッジボールなど新しい活動に取り組んできたが、ゆとり荘との交流は続けよう-と決めていたため、今回訪問した。
児童が元気に「こんにちは」と部屋に入ってくると、利用者は拍手で歓迎。児童代表が「お久しぶりです。おじいさん、おばあさんに元気をあげられるように頑張ります」とあいさつ。利用者も知っている曲「雪」などを元気に歌った。
2年生のときは、利用者を音楽会に招待したが、来てもらうのは大変と、今回、音楽会の発表をゆとり荘で再現。「お菓子の好きな魔法使い」の曲を笑顔で大きな声で歌い、「聖者の行進」「運命だ」の2曲をリコーダーで演奏した。利用者は児童の発表に目を細め、手拍子しながら聞いていた。
風船バレーを一緒に楽しもうとグループに分かれ、児童が利用者のそばに来ると、久し振りの再会に手を振る人や、児童が着ていた赤、緑などの衣装を見て「服は自分でこしらえたの?上手にできとるわ」と声をかける人もいて、打ち解けた様子で楽しんでいた。 -
伊那谷伝統文化公演

伊那谷伝統文化公演が21日、伊那市生涯学習センターであった。第一部「伊那の伝統演劇公演」は「伊那の方言劇」「瓜生喬語り芸の世界」の構成。地域住民ら約300人が集まり、語りの世界に浸った。
方言劇には県伊那文化会館付属劇団「南信協同」が出演。披露宴後の様子や電話での家族のやり取り、子どもの成長などを題材に「はあるか(長い間)」「まっくろさんぼん(一生懸命)」「しとなる(成長する)」など伊那の方言を会話に織り込んだ。
劇作家や語りべとして活躍する瓜生喬さんが一幕ごとに「『ひじろ(いろり)』など生活の変化によって使われなくなった言葉がある」「縲怩セに、縲怩セもんで、縲怩ヲなど語尾に豊かさがある」など方言の意味を含めて解説。観客はうなずいたり、楽しんだりして聞き入っていた。
「語り芸の世界」では、瓜生さんが長谷村の孝行猿、駒ケ根市の早太郎をベースにした創作民話を語った。
第2部の中尾歌舞伎公演「人情噺(ばなし)文七元結」は22日。中尾歌舞伎は長谷村無形文化財に指定される。すでに入場整理券はない。
公演は、NPO法人伊那芸術文化協会(荒井孝理事長)が伊那谷にある伝統芸能や言葉の文化を見直す機会にしようと初めて企画。「メンバーの高齢化などから継承が難しい風潮がある。発展する一助になれば」と話し、来年以降も取り組みたいとしている。 -
赤穂小が施設慰問

駒ケ根市の赤穂小学校1年1組(伊東美春教諭)は20日、市内の老人施設エーデルこまがねを訪れ、ケアハウスとデイサービスの利用者約40人に歌や創作劇などを披露してお年寄りらを喜ばせた。
劇は児童らが国語の授業で習った『おむすびころりん』を基にして創作したオリジナル交通安全劇。お馴染みのおじいさんやおばあさんのほか、暴走するドライバーや警察官なども登場し「この標識は何?」などの交通安全クイズやピアニカの演奏なども交えた約20分間の楽しい劇を児童らは生き生きと楽しそうに演じた=写真。利用者らは児童らの愛くるしい演技を見て「かわいいねえ」などと言いながら、大きな声で笑ったり一緒に歌を口ずさんだりしていた。 -
大学入試センター試験

志望校合格を目指す多くの受験生の最初の関門、06年度大学入試センター試験が21日、全国で一斉にあった。上伊那会場の南箕輪村の信州大学農学部と駒ヶ根市の県看護大学でも、大勢が臨んだ。
降雪の影響も心配されたが、幸い交通の妨げとなるような天候とはならなかった。信大農学部には、試験開始の約1時間前から、バスや車などで、上伊那や下伊那の受験生が駆けつけた。
会場の外にある案内板を緊張した面持ちで確認していた受験生も、友人や知り合いの顔を見ると緊張が緩み、励まし合いながら試験に臨んだ。
志願者は信大農学部会場898人、看護大会場が385人。看護大の志願者が昨年より若干上回り、両校の合計も18人上回った。全県の志願者数は1万2人で、昨年より80人減少した。
本年度は英語で初めてリスニングが導入され、受験者は「ICプレーヤー」を使用する。約180人が英語を受験した伊那弥生ヶ丘高校は、受験者が手にとって実物を扱えるよう、サンプルを置くなどして試験に備えた。 -
宮田小のスキー教室

宮田村の宮田小学校5、6年生は20日、駒ケ根高原スキー場でスキー教室を開いた。
5、6年生約200人は学年別、習熟度別に18班に分かれ、中ア山ろくスキー学校のインストラクターの指導を受けながら、板の装着やストックの持ち方、止まり方など基本を実習したり、練習用マットを使うなど、それぞれの力量に合った滑りでスキーを楽しんだ。
中にはリフトで登り、大人顔負けのシュプールを描いて、滑走する児童もいた。
この日は4年生も予定していたが、1クラスが風邪で学級閉鎖になったため、延期になった。 -
リズムとおはなしのへや1月

中川村図書館で19日、「リズムとおはなしのへや」があり、片桐保育園の年少児や親子約80人が参加。職員による絵本の読み聞かせや、松村幸美さんのリズムで楽しいひとときを過ごした。
音楽に合わせ、行進してスタート。
雪やおやつ、ベットとふあふあした物が登場する絵本「ふゆはふあふあ」の読み聞かせ。動物が大きなマスクをする歌「こんこんくしゃ」で盛り上がり、背中のネジをギーギーと巻いて、ロボット体操で楽しいお話のへやを締めくくった。 -
中沢小防犯学習

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)は19日、1・2年生を対象にした防犯学習を行った。視聴覚室に集まった児童ら約60人は、同小を訪れた中沢駐在所の井川久所長らの話や警察官らが演じる寸劇などを通して不審者への対応について学んだ。
駒ケ根署の警察官らが、不審者に声を掛けられて連れて行かれそうになった場合の対応について実演して見せた=写真。寸劇を見た児童らは笛や防犯ブザーを首から掛けていた方がとっさの場合にも手が届きやすいことを知り「かばんから外して首に掛けることにしよう」などと話していた。
寸劇に登場した不審者の服装などについて質問を受けた児童らは「サングラスをかけてマスクをしていた」「模様のある帽子をかぶっていた」「黒い手袋をしていた」などと的確に回答。井川所長は「本当に襲われたら落ち着いて見てはいられないが、どんな人だったか正確に知らせることはとても大切」と呼び掛けた。
同小は26日までに残る学年に対しても理解度に応じた防犯学習をそれぞれ行うことにしている。 -
南小にビデオ寄贈
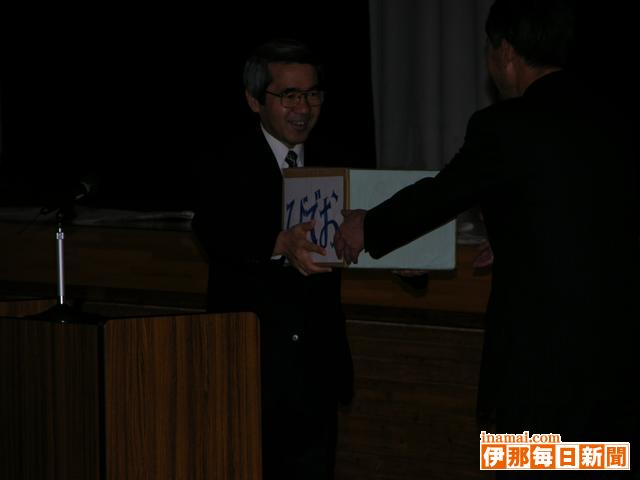
JICA(国際協力機構)駒ケ根青年海外協力隊訓練所(加藤高史所長)は19日、駒ケ根市の赤穂南小学校(白鳥彰政校長)に世界の様子を紹介したビデオテープ240本を寄贈した。加藤所長が南小を訪れ、全校集会の席上で「これを見て世界のことを勉強してください。きっと役に立つでしょう」と児童らに呼び掛けてテープの箱を白鳥校長に手渡した=写真。
同小は贈られたビデオを学習の一環として校内の世界情報センターなどで見るほか、児童らの家庭にも貸し出すなどして活用していきたいとしている。
同小は05年3月にJICAとの共同事業で校内に世界情報センターを設置し、開発途上国の生活や文化を紹介する約1万点の資料を展示している。視聴覚用としてテレビとビデオデッキも備えているが、学習用の映像ソフトがなかったため、駒ケ根訓練所が今回寄贈した。 -
飯島中で百人一首クラスマッチ

飯島町の飯島中学校で19日、新年恒例の百人一首クラスマッチがあった。
1クラスが8チームに分かれ、源平方式で競った。ルールはお手つきは1枚相手から札をもらい、早く取り終えたチームが勝。
筝曲が流れる中、文芸委員長、副委員長が読み手になって、上の句から読み上げると、取り札を囲んだ生徒たちは、身を乗り出し、札の上をすばやく視線を滑らし「ハイ!」と手を伸ばした。
枚数が少なくなると、いよいよ競技は白熱、勢い余って札も舞い上がった。 -
住民に呼びかけて城址保存会が学習会

宮田村の宮田城址保存会(春日甲子雄会長)は19日、宮田城をはじめ県内の山城を調査研究している前岡谷市教育委員長の宮坂武夫さんを講師に学習会を開いた。山城がつくられた中世、戦国時代の流れを分かりやすく解説。宮田城の特徴なども話したが「各地で開発や過疎化で歴史が消えていく。簡単に壊さないで、良い形で子孫に残して」とも呼びかけた。
城址についての理解や村の歴史を多くの人に知ってもらおうと、住民に呼びかけて実施。約50人が北割集落センターに集まった。
県内の山城跡をくまなく自分の足で歩き、確かめた宮坂さん。その途中で出会う人々とのふれあいについても話した。
豊かな人情は豊かな歴史、そして伝承によって育まれてきたことを説明。絶やさないためには、子どもたちに伝えることが大切と語った。
宮田城については図などを使って構造を詳しく解説。
主郭(本丸)を守る土塁が他の城跡に比べて高く築かれていることにふれ、「上部の斜面から攻められないための工夫。でたらめに築いてあるのではなく、使う武器や地形によって綿密に練られている」と説明した。
同保存会は歴史を風化させないようにと、遊歩道など宮田城址の整備をボランティアで実施。学習会で春日会長は「ふるさとのロマンを追いながら、想いを深め、伝えていきたい」と話していた。 -
「コーディネーション運動」学ぶ

スポーツ指導者の育成と資質向上を目的とした講習会が19日、伊那市の県伊那勤労者福祉センター体育館などであった。上・下伊那や諏訪地区から、小中学校職員や保育士など約70人が集まり、順天堂大学大学院助教授の東根明人氏の実技講習などを受講した。伊那教育事務所などの主催。
東根氏は、運動・脳神経の基礎体力を促進させる「コーディネーション運動」について指導した。同運動はヨーロッパを中心に学校体育やスポーツ現場で成果を挙げ、日本でも広まりつつある。同氏による指導は中南信地方では初となり、県内でも2回目となった。
実技講習は、床の上に落ちる寸前のテニスボールを掴み取ったり、ジャンプしながら体を左右に回転して進む運動などを体験。東根氏は「指導者は教える時に、運動のコツを掴んでいなければならない」と、参加者に呼びかけていた。
「コーディネーショントレーニングの魅力と効果」と題した講義もあった。
茅野市の中大塩保育園の保育士・矢島奈緒さん(27)は「遊びながらできる運動を保育園でも取り入れていきたい」と話していた。 -
手作りゲームで仲良し・交流深まる

伊那市の伊那北小学校(笠原富重校長、453人)で18日、冬のお楽しみ集会があった。児童会代表委員会の児童たちが考えたゲームを全校で楽しみ、学年間の交流の和を広げた。
全校児童が仲良くなるための、年2回の恒例行事。本年度からは、一学年から各2人ほどでグループを作り、校舎内を清掃する「縦割り清掃班」ごとで交流を深めた。
児童会代表委員会がつくったゲームは3つ。「爆弾ゲーム」は、グループで丸い円を描き、音楽が鳴っている間は右隣りにハンカチを回し、音楽が鳴り止んだときにハンカチを持っていた人が全員と握手した。
いつ音楽が鳴り止むのか、児童たちは緊張しながらゲームを満喫。負けてしまうと、恥ずかしそうに片手を差し出し、皆から握手を求めていた。
5年生の登内敏八君は「皆でいっぱいお話もできたので、もっと楽しく掃除ができそう」と、グループごとの交流が図れた様子だった。 -
仏のプロサッカーコーチに学ぶ

伊那市の東部中学校で20日、仏のプロサッカークラブチーム「FCボルドー」の育成カテゴリー総括コーチのグレセー・ジャン・ジャク氏の講演会があった。1年生約280人が体育館に集合。生徒たちは、普段は聞けない、フランスのサッカー選手の育成についての話に耳を傾けた。
ジャク氏は21、22日、松本市で開かれる、県サッカー協会の指導者研修会の講師として、17日に来日。日本の中学生と交流がしたい竏窒ニの同氏の意向で、21日までの間、県内の5中学校などで講演会やサッカー教室を開いている。
ジャク氏は、技術、戦術、フィジカル、メンタルがプロ選手に必要な資質と訴え、その中でもメンタルは極めて重要で「同じ素質の選手でも、精神面で差がついてしまう」と強調した。
クラブの育成センターには14縲・8歳の若者が集まり生活。すべての人がプロで成功するとは限らないので、学業も重視して育成しているという。
ジャク氏のコーディネーター・通役で、2年間のブラジルプロリーグ経験のある、前田和明氏の講演もあった。 -
命、性ロマンチックに伝えて
食と暮らしを考え、豊かな地域づくりを目指す長谷村のNPO法人「南アルプス食と暮らしの研究舎」(岡部竜吾理事長)は19日夜、学校教職員や保護者らを対象とした性教育講演会を伊那市生涯学習センターで開いた。
講師はバースコーディネーターの大葉ナナコさん(40)=東京都渋谷区。上伊那内外から集まった保健教諭や保護者、助産士ら約40人に、「いのちはどこからきたの?竏忠ニ庭から始まる性教育」と題して子どもに対する自身の性教育方針を伝えた。
大葉さんは、出産は痛くて苦しいと思っている子どもが多いとし、「生命の素晴らしさを伝える」大人の減少を指摘。
大学教授や産婦人科医の持論を踏まえ、「一番最初に命や性について聞かれたら、正しく、ロマンティックに伝えることが大切。子どもの心が動くように親子の出会いの物語をつくり、自尊感情を持たせるところから始めるといい」とアドバイス。また「大人が協力し合い、ネットワークを作って、より良い社会を築いていってほしい」と呼びかけた。
大葉さんは、「いのちはどこからきたの?竏・歳までに伝える『誕生』のしくみ」「えらぶお産」などの著書がある。全国各地の小中学校や高校などに出向き、成長に合わせて命や性について伝えている。 -
箕輪南小で恒例の百人一首大会

箕輪町の箕輪南小学校(北原文雄校長)で18日、冬恒例の百人一首大会があった。1、2年生は学年ごと1対1で、3、4年生と5、6年生は連学年が混ざった班で臨み、1枚でも多く札を取ろうと熱中した。
1年生のみ40首で参加。正座をし、手はひざの上から札を取るというルールに沿って、児童は向かい合って座り、真剣な眼差しで札を見つめた。
2年生は、1年生のときから生活科と国語の授業で百人一首に取り組み、青、ピンクなど5色の百人一首の札を各自が持っている。1色20首ずつで1年生で60首、2年生で残り40首の札を作った。
学校だけでなく家でも家族と一緒に百人一首をやるなどして1年で60首、2年で20首を追加し計80首を楽しみながら覚えた。3年生で全100首覚えることを目標にしている。
テープから流れる上の句を聞いただけで「はい!」と素早く札を取る児童も多く、静かな中にも大会は熱気を帯び、札の枚数が少なくなるにつれますます白熱。飛び込むように勢いよく手を伸ばして札を取る姿もあった。 -
おやじ塾の新春茶会
宮田村公民館のおやじ塾は18日、新春茶会を開いた。小林敏江さん=南割区=から手ほどきを受け、伝統の礼儀や作法を体験。奥深い茶道の世界を垣間見ながら、新年をともに祝った。
小林さんは茶道の基本を分かりやすく伝授。茶器やお茶の点て方を説明した。
15人ほどのメンバーは、菓子を食べ、さっそく点てたばかりの抹茶を満喫。豊かな香りや味を堪能した。
「お湯の温度はどれくらいがいいの」など、質問もして積極的。小林さんは「家庭でも気軽に楽しんでもらえれば」と話していた。
おやじ塾は結成3年目。中高年男性が生きがいづくりにと集まっているが、今年もどん欲に新たな挑戦をしていく考えだ。 -
赤穂中入学説明会

駒ケ根市の赤穂中学校(諏訪博校長)は17日、来年度入学する児童と保護者らに対する入学説明会を同校で開いた。赤穂、赤穂東、赤穂南の児童約320人が体育館に整列し、先輩の生徒らから中学での生活などについて説明を受けた。
来年度生徒会長の小池綱希君は「入学したらいじめや嫌がらせを絶対にしないように。生徒全員でみんなを待っているから、4月には笑顔で入学してきてください」とあいさつした=写真。
1年生の生徒が代わる代わる児童らの前に立って授業や委員会、部活動、行事などについて紹介し、生徒会係の藤井篤徳教諭が生活全般の心構えなどについて説明した。
児童らは新生活への不安からか誰一人として無駄口もきかず、緊張した表情で一心に説明を聞いていた。
同じ時間、視聴覚室では保護者らが担当教諭らから入学までの準備や心構えのほか、中学での生活などについて説明を受けた。
06年度の同校への入学予定者は319人で県下一。
2510/(土)
