-
本物の投票箱で一票の重み実感 中学校生徒会選挙
伊那市選挙管理委員会が貸し出した投票箱、投票記載台を使った、来年度の正副会長を決める生徒会選挙が市内の中学校で始まっている。1日、春富中学校でもあり、生徒らは本物の箱に投じることで一票の重みを体感した。
会長候補3人、副会長候補男女各3人ずつの計9人の立会演説会の後に、全校生徒528人は意中の候補者の名前に印を付けた用紙を次々と投票=写真。有権者の一人は「本当の選挙をしてるみたいだった」と感想を述べた。
市選管は、将来の有権者となる生徒たちに選挙意識を持ってもらいたいと、1997年度から要望のあった市内の中学校へ選挙箱などを貸し出している。本年度は、伊那、西箕輪、高遠、長谷中など5校が使用する。 -
「さよならイナニシザウルス」
伊那市の伊那西小学校01年度卒業生は2日、同小敷地内へ在学時に埋設した、流木の模型「イナニシザウルス」の解体をした。児童たちの遊ぶ場に老朽化した模型があっては安全ではない竏窒ニ、取り壊した流木を地中に埋め、思い出を振り返った。
同卒業生15人が小学3年生の時、小沢川などで拾ってきた材料を骨に見立てて作った、全長約5メートルの「イナニシザウルス」。約1年間は校舎内に立体模型として飾ったが、5年生時に現在の場所へ「発掘した化石」の姿で埋設していた。
卒業後は毎年8月に同級会を兼ねて皆が集まり、修理作業をしてきたが、本年の修理の際に解体することを決断した。
この日は、卒業生5人と担任だった野口輝雄さん(辰野西小教諭)、保護者の計8人が参加。9年間の歳月が立った模型を前に「お墓になっちゃったね」などと偲びながら、「イナニシザウルス」の頭部や足の骨10本ほどを、埋設していた場所へ埋めた。
参加者の一人、唐木智恵さん(17)=伊那西高校2年=は「皆で楽しく作った思い出がよみがえった。イナニシザウルスの姿はなくなってしまうが、私たちの心の中に生き続けてくれれば」と言葉を噛み締めていた。
解体した「イナニシザウルス」を埋葬する伊那西小卒業生ら -
第3回伊那市民芸術文化祭

第3回伊那市民芸術文化祭が2、3日、伊那市の生涯学習センターで開かれている。さまざまな分野の作品展示や舞台発表が、訪れた人の目を楽しませている。
幅広い人にそれぞれの活動を知ってもらうとともに、発表を通じて互いに刺激し合い、更なる芸術レベルの向上を図ろう竏窒ニ始まった取り組みで3年目。市内を中心に近隣市町村からの参加もある。
展示部門では、絵画、水墨画、写真、生け花、陶芸、パッチワークキルトなど約240作品の応募があったほか、舞台部門では、バレエ、フラダンス、日本舞踊などの19団体が出場。2、5階コーナーには、伊那芸術文化協会の講座受講者らによるお茶席の無料体験コーナーも設けた。
出場者は幼児から年配者までと幅広く、若い人の参加も多いため、例年場内が活気に包まれるという。
来場者は「こういう写真はなかなか撮れない」などと話しながら一堂に並んだ作品の数々を見比べていた。
入場無料。展示部門は午前9時縲恁゚後4時半、舞台部門は午前10時20分縲恁゚後4時半。 -
【記者室】古田人形芝居公演
箕輪町上古田地区を中心に江戸時代から伝承されてきた人形浄瑠璃「古田人形芝居」。箕輪西小学校の古田人形クラブが、結成15周年を迎えた。記念事業の古田人形を語る会で児童は、人形の扱いや役の気持ちを理解する難しさに苦労しながらも、できた喜びを味わい、「来年もやりたい」と話した▼古田人形芝居は箕輪中学校に古田人形部があり、今年から箕輪中部小学校にもクラブが発足した。保存会は児童、生徒が人形芝居を継承していくことに期待を寄せている▼実際に人形に触れ、演じることで、伝統芸能への理解や関心が深まる。将来、後継者になるかもしれない小・中学生も出演する本年度の古田人形芝居定期公演は今日、箕輪町文化センターホールである。(村上裕子)
-
食育講演会

駒ケ根市教育委員会と市内小中学校長会、同PTA、同幼稚園・保育園保護者会は30日、食育講演会を文化会館で開いた。約600人が集まり、内閣府食育推進会議委員で佐久長聖中学高校食育アドバイザーの市場祥子さんの講演「今が大事!心と体を育む食事竏虫汨繧キ子どもたちの健やかな成長を願って」を聴いた。
「命と健康の大切さを子どもたちに伝えるためには何よりも周囲の大人の姿勢が大事」という市場さんは、子どもたちの食生活の現状と食育基本法の理念について説明=写真。その上で望ましい食生活について「早寝・早起き、1日3食しっかり食べる、運動する」の健康3原則を実践することが重要竏窒ニ訴えた。 -
美篶小開校105周年・資料館専門委が企画展
伊那市の美篶小学校資料館の管理・運営をする専門委員会は1日、同小学校開校105周年記念日に合わせ、企画展を開いた。校門脇にある石碑、「二宮金次郎」の石像についての説明や、資料館で保存する手押しポンプ、モロコシの粒をもぐ道具などの実演展示をした。
同石像を調査した専門委員の一人、矢島信之さん(63)=同市青島=によると、二宮像は、1939(昭和14)年に地元出身の畑保雄さんが寄贈。その当時は銅製だったが太平洋戦争で金属不足となり供出され、その後石像に置き返られたという。
矢島さんは、企画展を訪れた児童たちに、家族のため必死に働いた二宮金次郎の功績などを解説。石像が市内の小学校に現在もあるのは貴重で、同小学校など6カ所だけとし、「雨の日も雪の日も見守ってくれている石像に、登下校の際には感謝のあいさつを」と呼び掛けた。
開校記念の企画展で二宮金次郎像について説明する矢島さん -
PPK運動の提唱者、北沢豊治さん(飯田市上郷公民館長)を招きことぶき学級
飯島町文化館で29日、中央公民館のことぶき学級があり、PPK(ピンピンコロリ)運動の提唱者、北沢豊治さん(飯田市上郷公民館長)が「早くぼけて、寝たきりになる秘訣」と題して講演。65人の学級生は体操を組み合わた、楽しい逆説的講話で「いつまでも元気で、病まず、ぽっくりいく」PPKの極意を学んだ。
北沢さんは「寝たきりになる秘訣」に「食生活を改善しない、みそ汁は濃い目にする」を挙げ、食の字を分解すると「人」「良」になる。だから、食生活は極めて大切と述べ、ヤンキーズの松井選手のスタミナの秘訣を「ま(豆類)ご(ごま)わ(ワカメ)や(野菜)さ(魚類)し(シイタケ)い(芋類)」と紹介し「健康には日本食が1番」と勧めた。
また「頭を使わない、いやみを言う」「運動しないでストレスを貯める」「毎日怒ったばかりいると、がんになれる」など、「ボケて、寝たきりになれる秘訣」を伝授したほか、首を廻す、爪もみ、ひざマッサージなど簡単な体操も紹介した。 -
東伊那郵便局で絵画作品展

駒ケ根市東伊那にアトリエを構える造形作家今井由緒子さんが主宰する絵画教室「スタジオイマイ」の受講生らの作品展が同市の東伊那郵便局(小林敏明局長)ロビーで12月22日まで開かれている。駒ケ根市と伊那市に住む受講生6人が山並みや街のたたずまいなどの風景や、花、野菜などの静物をモチーフに思い思いに描いた絵画作品6点を展示。訪れた人たちは待ち時間などに作品に目を向け、1枚1枚じっくりと見入っている=写真。
6作品の展示は8日まで。11日には入れ替えが行われ、新たな受講生の作品が展示される。
今井さんは東京芸術大彫刻科卒。各地で展覧会を開催するなど首都圏を中心に活躍中。96年には駒ケ根高原にモニュメントを制作、設置している。 -
明社協講演会

募金やボランティア作業などの福祉活動をしている明るい社会づくり運動駒ケ根市協議会(堀内照夫会長)は29日、郷土史研究家で同市文化財審議会委員、南田市場土地区画整理事業推進委員会委員長、元上穂区長の竹内滋一さんを講師に招いて「郷土駒ケ根あれこれ」と題した講演会を駒ケ根市福祉センターで開いた。
国道153号線伊南バイパスと交差する新しい道路の愛称が市場大通りに決まったことから「市場」の地名の由来について考えてみたという竹内さんは「記録によると鎌倉時代に現在の市場割に日本岐森(にほんぎのもり)があり、にぎやかな市場が立ったらしい。東山道もここを通っていたと考えられる。バイパスの開通でこの付近が昔の市場の繁栄を取り戻しつつあることを思うと感慨深い」などと話した=写真。
集まった約40人の市民らは感心した様子で大きくうなずいたりしながら竹内さんの話に聴き入っていた。 -
中川西小3年が「もっとたくさん大豆をつくろう」をテーマに発表

昨年度から青少年赤十字研究推進校の指定を受け「気づき、考え、実行する子ども」の具現化を図る中川西小学校で27日、公開授業と授業研究会があった。全県から小中学校の教諭ら約50人が参加した。
公開授業は3年生(片桐操教諭、20人)の総合的学習「もっとたくさん大豆を作ろう-喜久司さんに食べてもらう豆腐をつくろう」の単元。
昨年、大豆を育てた子どもたちはもっとたくさんの大豆を作りたいと、近くの座光寺喜久司さんの畑を借り、喜久司さんに教わりながら、たくさんの大豆を育てた。子どもたちはお世話になった喜久司さんに豆腐を作ってお礼をしようと、1回目の試作を終えた。
この日は午前中、2回目の豆腐づくりをした。公開授業では、各班ごとでき上がった豆腐を試食し、味、見た目、舌ざわりなどの観点ででき映えをチェックし、他の班の豆腐と食べ比べた。
子どもたちは「うちの班の方がおいしい」「表面がざらざらしている」など感想をカードに記入した。
この後「にがりを増やす」「重しを調節する」など、次回への見通しを発表し合った。 子どもたちはたくさんの教諭らに囲まれ、後ろからのぞき込まれながらも、堂々と自然体で授業を受けていた。
この後、「気づき、考え、実行する子どもの育ちを求めて縲恍n域の人々や児童相互のかかわりを通して」をテーマに、同校の征矢浩平教諭が研究、実践発表した。 -
東小PTA、親子でチャレンジ講座
中川村の中川東小学校PTAは25日、校内やふるさと体験館などで、親子でチャレンジ講座を開いた。教諭や地域の人々が講師になり、手作りうどんや陶芸、泥団子づくりなど9講座を楽しんだ。
このうち、玄関前では、講師に鈴木道郎さん(キャンパスビレッジ自然学校)を招き、25人が参加し、アウトドアクッキング、ダッチオープンを使って、焚き火料理をした。
この日の献立はインド料理のチャパティー。ダッチオープンに下こしらえしたタマネギやニンジン、ジャガイモ、サトイモを入れて、火に掛けた。野菜を煮ている間に、全粒粉を水で溶き、こねて、伸ばして生地を作った。
また、ひき肉に卵を混ぜて、よくこねて、生ハンバーク状にし、竹くしに巻き付け、直火で焼くなど、親子が協力し合って、手際よく調理を進めた。
お母さんと2人で参加した山上大輝君(11)は「大変だけど、面白い。煙りが目にしみて痛い」と話していた。 -
親子でバングラディッシュ料理に挑戦

料理を通じて異文化も知ろう竏窒ニ伊那市の大萱保育園に通う年長園児親子13組が25日、バングラデシュ料理作りに挑戦した。 大萱保育園は今年、親子で調理体験を行うことで、食に対する理解を深めてもらうために年長園児の希望者を対象とした「親子クッキング」を実施。第1回目は白玉など和菓子を中心としたメニューに挑戦したところ、好評だった。
今回は同園に娘のヌールちゃんを通わせている信州大学農学部の留学生、ミーア・アブドゥル・ガッファさん夫妻に講師を依頼し、バングラ料理づくりを企画。日本では販売されていない香辛料を使ったり、あちらで食べられている細長い米を使ったりしながら、鶏肉がたっぷり入った野菜の煮物と香辛料が効いたライスカレーの2品に挑戦した=写真。
出来上がった料理は全員で試食。大人も子どもも家でつくるカレーとは違う異国の味を楽しんだ。 -
おしゃべりミュージックコンサート

上伊那の音楽指導者らでつくるMMC(宮田ミュージックサークル)は26日「おしゃべりミュージックコンサート」を宮田村の村民会館で開いた。MMCが指導する2つの小学生グループ、宮田村の「サタデーシンガーズ」と飯島町の「音のカーニバル」が加わって演じるオペレッタ「夜行列車のあとで」が第1部で上演され、観客の盛んな拍手を受けた。第2部では「モーツァルト特集」、第3部では「テレビ、映画、CMなどでおなじみの曲特集」としてMMCのメンバーがそれぞれ得意のピアノやエレクトーン、フルート、ソプラノの歌声などを披露=写真。見事な演奏に聴衆はうっとりと聴き入っていた。
-
南箕輪村の2小学校で邦楽コンサート

南箕輪村の南箕輪小学校と南部小学校で27日、尺八箏の会主催で邦楽グループ「まいまい」が演奏する邦楽コンサートがあった。例年この時期に開くコンサートで、南箕輪小は6年生、南部小は4年生以上が尺八、箏、三味線の演奏の様子を興味深く見つめ、耳を澄ませて邦楽の響きを楽しんだ。
南部小には6人が来校し、箏・三弦・十七弦による「落ち葉の踊り」、尺八も交えたモーツァルトの「まほうの鈴」など古典曲やクラシックなどを演奏。なじみのある「赤とんぼ」「里の秋」など6曲からなる「秋のメドレー」では、児童が演奏に合わせて歌うなどして楽しんだ。
篠笛クラブと太鼓グループ「CoCo龍」の児童による特別演奏もあった。演奏会後は箏、尺八などの楽器に児童が実際に触れ音を出す体験もした。 -
もっと野鳥とふれあいたい
宮田小1年2組、イメージふくらませエサ台づくりに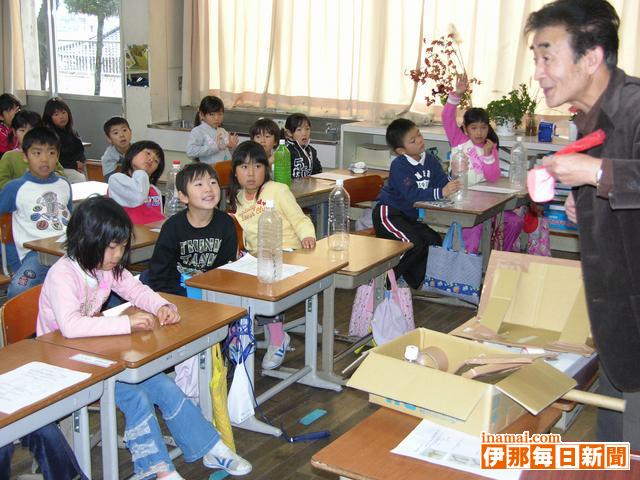
宮田村宮田小学校1年2組は、野鳥を目の前で見たいと取り組みを始めた。28日は日本野鳥の会の小口泰人さん=駒ケ根市福岡=を迎え、村周辺に生息する野鳥の生態をビデオなどで学習。どのようなエサ台を作れば鳥たちが寄って来るか、考えをふくらませた。
同学級は5月と10月に、県野生鳥獣救護ボランティアも務める小口さんから保護しているフクロウなどを見せてもらい、野鳥に興味を持った。
しかし、普段の生活では野鳥を見ることが難しく、児童たちは「もっと目の前で見てみたい。鳥に近付くには、どうしたらいいんだろう」と疑問が深まった。
小口さんにお願いして、野鳥と接する方法をアドバイスしてもらうことに。この日は、弱い鳥、強い鳥で食べるものも違えば、エサの取り方も様々であることを学んだ。
台を作ったり、吊るすなどエサによって近付く方法があることも知ったが、小口さんは「どんな風にしたら鳥が来るか、一人ひとりアイデアを考えてみて」と呼びかけた。
今後は各児童が工夫してエサ台を作成し、家庭に設置する予定。さらにみんなで協力して校内にも設け、鳥との距離を近づけようと子どもたちの夢は広がっている。 -
駒ケ根市民音楽祭

第40回駒ケ根市民音楽祭が26日、駒ケ根市文化会館大ホールで開かれた。市内で活動する24グループが出演し、合唱に器楽演奏に日ごろの練習の成果を披露し合った=写真。
小・中学生では赤穂小合唱部、赤穂南小合唱団、中沢小合唱団、赤穂中3年6組がそれぞれ透き通った美しい歌声を響かせたほか、赤穂南小金管バンド、赤穂中吹奏楽部は吹奏楽を、赤穂中3年8組は筝の演奏を披露して大きな拍手を受けていた。 -
来年の干支を見に行こう、宮田小2年2組
イノシシの姿目に焼きつけ、年賀状に
宮田村の宮田小学校2年2組は27日、来年の干支(えと)であるイノシシを見学に駒ケ根市東伊那の飼育園地を訪れた。年賀状にイノシシの絵を描こうと観察したもので、児童たちは目を凝らして姿を追った。
ある児童の親類が飼育していたことから、イノシシとの対面が実現。子どもたちの大半は初めて見る本物の迫力に「大きい」「かわいい」と歓声をあげた。
柵ごしだが、子どもたちが近寄ると、5頭ほどのイノシシは猛ダッシュで飼育園内を右往左往。
それでもしっかりと目に焼きつけ、まだ幼いことから立派な牙(きば)がないことなど、短時間で集中して観察した。
同学級は昨年も今年の干支である犬を観察して年賀状を製作。今年も近く、絵を描き始める予定だ。 -
宮田小2年中原さんが牛の絵で県知事賞

宮田村宮田小学校2年の中原未帆さん(9つ)=南割区=の牛の姿を描いた絵画作品が、「第21回くらしと牛乳、牛さんありがとう絵画コンクール」(県牛乳普及協会主催)で県知事賞を受賞した。
クラス全員で村内の牧場へ出かけ、牛を観察した時に描いたもの。背中の凸凹感など、草を食べている牛の姿を伸び伸びと、描いている。
コンクールには898点の応募があり、中原さんを含む金賞受賞者12人の表彰式は2日に長野市で開かれる。 -
長編劇映画「Beauty-美しきもの」が大鹿村大磧神社で伊那路歌舞伎シーンを撮影

飯島町在住の後藤俊夫監督(67)がメガホンを取る長編劇映画「Beauty-美しきもの」の撮影が26日、大鹿村大河原の大磧神社舞台で行なわれた。地元の大鹿歌舞伎(映画では伊那路歌舞伎)の上演シーンを撮影した。上下伊那の住民500人余が観客役で出演し、後藤監督の指示のもと、タイムリーな掛け声、即興の野次、花を投げたり、時には笑い転げるなど大熱演で、映画を盛り上げた。
村歌舞伎の演目は平賀源内作「神霊矢口渡」の「頓兵衛住家の段」。美丈夫の新田義峰役の役者が花道をしすしずと登場すると、客席から「待ってました!」「いい、男!」と声が掛かり、矢口の渡し守、頓兵衛の娘、お舟には「ほれちゃだめよ」と、すかさず野次、バラバラと花も飛んだ。
また、熊谷直実が大見得を切ったとたん、かつらが落ち、客席に転げるシーンもあり、エキストラ500人は文句無しの大笑いを演じて、後藤監督も大満足、1回で「ОK」が出た。
参加者は自前や借り物の銘仙の着物、もんぺ、半てん、詰襟学生服、セーラー服など昭和10年代の服装で参加。「本番」の声が掛かり、カチンコが鳴ると緊張するが、準備やテスト時は、酒を酌み交わしたり、お菓子をつまんだりと、ロケを楽しんいた。
家族4人で参加した飯島町七久保の竹沢綾子さんは「たんすの肥やしになっていた着物が日の目を見た。勇気を出して、出て良かった」。大鹿村の近藤元さんは「いつもの大鹿歌舞伎の雰囲気が出ている」と話していた。 -
民話とハーモニカミニコンサート

駒ケ根市のおもしろかっぱ館(小平容大館長)は06年度親子・子どもふれあい事業の11月の巻として25日「民話とハーモニカミニコンサート」を同館で開いた。赤穂公民館の講座が母体となって昨年結成された「はつらつハーモニカクラブ」と、東伊那公民館の講座生らでつくる「おはなしを語る会」のメンバーらが出演し、それぞれ見事な語りと演奏を披露した。
駒ケ根ハーモニカクラブは『夕焼けこやけ』『赤とんぼ』『里の秋』など童謡を中心に郷愁を誘うやわらかな音色で合奏を奏でた=写真。おはなしを語る会は4人が代わる代わる登場して『仁王様の夜遊び』『雪女』などの民話を情緒たっぷりに語った。聴衆は目を閉じて語りやハーモニカを聴きながら晩秋の静かなひとときを楽しんでいた。 -
長編劇映画「Beauty-美しきもの」が飯島陣屋でロケ
飯島町在住の後藤俊夫監督(67)がメガホンを取る長編劇映画「Beauty-美しきもの」のロケが25日、飯島町の信州飯島陣屋で行なわれた。
この日は陣屋の一室を歌舞伎練習場(歌子の家)に見立てて、少女歌子が少年雪夫と踊りの練習をするシーンを撮った。歌子役の兼尾瑞穂さん、大島空良君(雪夫役)のほか、歌子の養父で浄瑠璃の師匠、東浦鶴太夫役の赤塚真人さん、クラスメイトの子役5人が出演。
歌子と雪夫が「梅川・忠兵衛」を情緒たっぷりに踊り、赤塚さんはいぶし銀の演技で、慈愛と厳しさに満ちた父親、師匠役を演じた。
この日はこの冬1番の冷えこみだったが、陣屋前には、身近で行なわれる映画撮影を見学しようと、近所の住民らが集まり、ストーブで暖を取りながら、興味津々の様子で見入っていた。
26日は大鹿村大碩神社舞台で、村歌舞伎の上演シーンを撮影する。飯島町民をはじめ、地元住民500人が観客の役で出演する。
) -
高教組上伊那支部が教育基本法改正反対を訴えるチラシ配り

長野県高等学校教職員組合上伊那支部は24日、伊那市駅前ビル「いなっせ」周辺でチラシ配りを行い、今国会の最重点法案とされている教育基本法の改正法案の廃止を訴えた=写真。
野党の強い反発の中、与党の単独採決で衆院を通過した改正法案は今月17日に参院入り。野党の強い反発により一時審議がストップするなど、与野党の対立は深まっているが、今国会での成立を目指す与党は会期延長も視野に入れて動いている。
それに伴い、教育基本法を守ることを目的とする県内の団体などでつくる「教育基本法を活かす県民ネットワーク」は、23縲・6日、各地で改正法案反対を呼びかけるPR活動を実施。その一環として、同支部は駅前でのPRを行った。
この日は、8校から代表者約15人が参加。道行く人たちに改正法案反対を強く訴えた。田中聡書記長は「改正法案は憲法9条を改正するための足がかり。法案が通れば、国の考え方を教育で縛るようなことが可能となってしまう」と話していた。 -
宮田中若草学級、笑顔で接客交流深め
宮田村宮田中学校の自律学級「若草学級」は23日、村民会館で開かれた心の健康を考えるつどいに参加。陶芸、木工など自身の作品を販売し、会場を訪れた多くの人たちと交流を深めた。
学校で汗して拾い集めたギンナンも人気。買い求める人との会話しながら、3人の生徒が接客に励んだ。
「ありがとうございました」と元気で清々しいあいさつ。訪れた人たちも笑顔で、生徒たちとのふれあいを楽しんでいた。 -
白心寺でコンサート
響き渡る音色と歌声に阿弥陀様もうっとり?!‐。宮田村町2区の浄土宗・白心寺は23日、同村を拠点に活動する弦楽合奏団「アンサンブル信州in宮田」のバイオリン奏者浅井万水美さんら国内外で活躍中の演奏家、声楽家4人を迎えオペラ公演を開いた。十夜法要記念のコンサート。檀家に加え地域住民も数多く集まり、一流の音楽を堪能した。
浅井さんはアンサンブル信州でコンサートマスターを務めるなど、実力ある演奏家。
今回は仲間でチェロ奏者の城戸春子さん、テノール歌手の田代誠さん、ピアノ奏者の腰塚賢二さんと組んで公演した。
本堂に集まった約150人の聴衆を前に、宮田小中学校の校歌など耳なじみの曲からスタート。ムーンリバーといったジャズの定番から、サン=サースの白鳥まで、幅広い楽曲で会場を楽しませた。
同寺の山田弘之住職はアンサンブル信州の運営に協力するなど、音楽文化の地域定着に尽力している。
今までも雅楽など本堂で6回の演奏会を開いてきたが、アンサンブルメンバーによるものは2回目。浅井さんは「宮田を訪れると、、いつも我が家に来たような気分になる」と話し、熱心な地元のファンに音楽の楽しさを伝えていた。 -
箕輪西小古田人形クラブ結成15周年記念行事
古田人形を語る会
箕輪町の箕輪西小学校古田人形クラブの結成15周年を記念して22日夜、古田人形を語る会が西小であった。現役クラブ員、卒業生で箕輪中学校の古田人形部員、古田人形芝居保存会員ら33人が集まり、クラブの活動や人形芝居を語り合った。
古田人形芝居は上古田地区を中心に江戸時代から伝承されてきた人形浄瑠璃。79年に箕輪中学校に古田人形部ができ、92年に箕輪西小にクラブができた。03年には善行青少年、青少年健全育成功労者内閣官房長官賞を受賞した。
クラブは毎月3回程度、保存会員の指導で練習し、校内発表会や12月の古田人形芝居定期公演で「傾城阿波鳴門 順礼歌の段」を発表する。今年は4年生から6年生までの13人が活動。17日には15周年記念公演をし児童、保護者、地域住民ら約200人が鑑賞した。
児童は「足の高さや歩くとき、人形の気持ちがわかるようにというのが難しかった」「教えてもらってなんとかできるようになった」「来年もやりたい」など思いを発表した。
保存会員は「芸に完結はない。それが魅力。一生の趣味という気持ちで続けてくれたらなと思う。ぜひ継続して仲間に入ってきてくれることを希望している」と、クラブの児童による古田人形芝居の継承に期待を寄せた。 -
小沢さちピアノリサイタル

伊那市出身のピアニスト小沢さちさんのピアノリサイタルが22日夜、駒ケ根市の駒ケ根高原美術館別館VITA AMORで開かれた。伊那市の人材教育・派遣業ワーク・トラスト主催。約100人の聴衆が集まり、小沢さんの奏でるベートーベン、ショパン、ブラームスなどの名曲の調べに酔った。小沢さんは曲の合間に語りも披露。「ピアノを弾く時、以前は間違えないように、などと考えながら弾いたものだったが、最近は作曲家の人生に思いをはせながら弾くようになった」などと笑顔で語り掛けた。
小沢さんは伊那北高、桐朋学園大ピアノ科卒。同大弦楽器伴奏研究員修了。現在同大付属音楽教室講師。ソロ、室内楽コンサートのほか、内外の演奏家の伴奏やなどに活躍中。 -
箕輪中学校安全願い隊発足

箕輪町の箕輪中学校で22日夜、生徒の安全を見守る保護者やボランティアの「安全願い隊」が発足した。町内5小学校は、みまもり隊組織がすでに活動しており、箕輪中の発足で町内全小・中学校で子どもを見守る体制が整った。
各クラスの正副学級PTA会長とボランティア8人の計46人でスタート。生徒の登下校時間帯に通学路に出て安全を見守る。都合のつく時間帯で目安は登校が午前7時から8時、下校(冬期)は午後4時45分から6時ころ。登校時は交通安全、下校時は不審者や交通安全を中心にし、特に自宅近くの通学路で人通りが少なく見通しが悪い場所、交通量が激しく危険な場所に立ったり、学区内を散歩する。
隊員は町安全みまもり隊連絡協議会が用意した腕章と帽子を着用する。
発足の会では、隊員を委嘱し、活動を確認。PTA会長は「生活や教育全般で何気なく、そして深くつながることで地域がつながる。この会が子どもと地域がつながる絶好の機会になればと思う」とあいさつした。 -
おしゃべりミュージックコンサート26日に
音楽指導者でつくる宮田ミュージックサークル(MMC)は26日午後2時から、おしゃべりミュージックコンサートを宮田村民会館で開く。メンバーによる演奏のほか、指導する同村の「サタデーシンガーズ」、飯島町の「音のカーニバル」の子どもたちがオペレッタを上演。本番に向けて練習に励んでいる。
コンサートは3部構成で、1部のオペレッタ「最終列車のあとで」は28人の児童が出演。宮田駅に季節を運んでくる列車をイメージし、楽しい歌声に乗ってストーリーが展開していく。
子どもたちは本番に向けて熱心に練習。最高の舞台にしようと、気持ちをひとつにして取り組んでいる。
2部はモーツアルトの名曲を特集し、3部はテレビ、映画、CMなどでおなじみの曲を演奏。MMCのメンバーがピアノ、声楽、フルート、三味線など、多彩な楽器でコラボレーションを繰り広げる。
「子どもたちの元気なオペレッタに、聴き慣れた曲の数々。多くの人に足を運んでもらい、みんなで楽しみたい」とMMCの瀧澤智恵子代表は話す。
チケットは5百円。問い合わせは村民会館85・2314まで。 -
白心寺で十夜法要
宮田村町2区の浄土宗・白心寺(山田弘之住職)は23日、十夜法要を営んだ。檀家を中心にした小学生12人が稚児となり、礼賛舞(らいさんまい)を奉納。先祖を供養し、五穀豊穣、安心した暮らしができることに感謝した。
同寺では毎年、礼賛舞を十夜法要にあわせて奉納。今年も小学3年から6年までの女子が稚児の衣装に着飾り、会場に集まった約100人の檀家の前で堂々と披露した。
十夜法要は同宗派の3大法要のひとつ。かつては陰暦の10月5日から十日十夜続けたことから、その名が付いた。今は農作物の収獲時期とも重なるため、天の恵みに感謝する意味も込められている。 -
伊那ビジネス専門学校 来春新コーススタート
伊那市狐島の伊那ビジネス専門学校(三澤清美校長)は22日夕方、パソコンの高度な操作技術などを習得する新コース「パソコンエンジニア」を来年4月から設けることを発表した。同コースは、高度な技術を持った人材を求める、地域企業が増えたことへ対応するために設置した。
従来のワード、エクセルなどのアプリケーションソフトの習得のほか、パソコン本体のネットワークプログラムの設定、情報システムの開発サポートなどの基礎知識を2ヵ年で学習。一般教養、マナー、簿記などもカリキュラムに組まれている。
就職に向け、「初級システムアドミニストレータ」「MOS検定(マイクロソフト認定技術資格)」など、専門的な資格習得の支援もする。
伊那ビジネス専門学校では、新コース設置のほか、来年度新入生の募集に向け、特待生制度を設けたり、校内のバリアフリー化をするなど、地域に愛される学校づくりに取り組んでいる。
入学希望などの問い合わせは、同専門学校(TEL76・2260)へ。
新入生募集を呼び掛ける新コース「パソコンエンジニア」の担当講師
2710/(月)
