-
南箕輪村4月人事異動内示

南箕輪村は、4月1日付けの人事異動を23日、内示した。異動規模は中規模で、課長級への昇格は一人となっている。
収納対策課長には、産業振興課農政係長の松沢 良行さんが昇格する。
今回の異動では、職員140人の約3割に当たる40人が異動する中規模の異動となっている。
また、今回の人事では、村内で最も園児数が多い中部保育園に、園長の補佐を行う主任保育士を二人配置することにしていて、重点施策の一つである子育て支援の充実を図りたいとしている。 -
緊急交通路25路線追加

伊那市防災会議が17日開かれ、災害時に物資の輸送をするための緊急交通路、25路線を新たに追加した。
会議には、行政や各種団体の代表などが出席し、緊急交通路指定などを含む伊那市防災計画の修正案が了承された。
緊急交通路は、災害時に物資輸送や緊急車両の通行を優先し一般車両の通行を制限する。
これまで、国道153号、361号、伊那インターアクセス道路などは、県が緊急交通路に指定していた。
今回新たに、市が独自に指定した25路線は、県の指定路線を延長するなどして、ヘリポートや避難所を結ぶ。
主なものは、西部広域農道、ナイスロード、環状北線、伊那インター西箕輪線など25路線。
これらの変更点は、県知事との協議を経て最終決定される。 -
伊那浄水管理センター 太陽光発電始まる

伊那市の伊那浄水管理センターに太陽光発電設備が設置され、汚泥処理にかかる電力の一部をまかなうための太陽光発電が始まった。
20日、太陽光発電設備の竣工式が伊那浄水管理センターで行われ、関係者が完成を祝った。
太陽光発電設備は、伊那浄水管理センター水処理棟の屋上に設置されている。
太陽光パネルは190ワットのものが528枚で、年間発電量は11万6千キロワットアワー。
これは、県内公共施設としては最大級の規模になる。
この発電により、伊那浄水管理センターの年間電気料の約1割に相当する139万円の節減が見込まれている。
石油にすると年間2万8千リットル、二酸化炭素では年間20トンの削減効果があるという。
総事業費は約1億1千万円。
竣工式で小坂樫男市長は、「市民の環境問題への意識が高まっている時代。地球温暖化対策推進エリアとして、見学していただくなど環境教育の場にしたい」とあいさつした。
市民が発電量を見られるようにと、伊那浄水管理センターの北側にはモニターも設置されている。 -
伊那市境の三峰川堤防に桜記念植樹

伊那市境の三峰川堤防で20日、桜並木造成記念式典が行われ、54本の桜の苗木が植えられた。
20日は関係者や地域住民が三峰川堤防に集まり、桜の植樹作業を行った。
境区では、三峰川堤防に桜並木を作り憩いの場所にしようと、2年ほど前から委員会を設置して検討してきた。
委員会ではその手始めとして、今回の植樹を計画。
20日は地域住民らが参加し、三峰川堤防の境区の部分、約600メートルにわたり植樹した。
また、地域住民を対象に募集した並木道の名称は「境桜並木」に決まり、小坂樫男伊那市長らが記念の標柱を建てた。
今後は、地区住民が協力して桜並木の管理を行っていくという。
三峰川堤防の青島区の部分も含めると、桜並木は全長2キロにわたる。 -
伊那市4月1日付人事異動内示

伊那市は、4月1日付けの人事異動を19日、内示した。小坂樫男市長の任期満了が近いため、必要最小限の異動に留め、部長級への昇格は一人となっています。
部長級の長谷総合支所次長兼長谷総合支所総務課長には、総務部総務課長の池上 忍(しのぶ)さんが昇格する。
小坂市長の任期満了が近いため、異動は最小限にとどめ、異動総数は175人となった。
また、組織の見直しでは、新たに2つの係を設置することにしていて、●市内にある3つの診療所を統括する「診療係」を保健福祉部健康推進課に、●5月に開館する創造館の運営を担う「創造館係」を教育委員会生涯学習課に設置する。 -
南箕輪むらづくり大賞は「アクセス道路をきれいにしよう会」
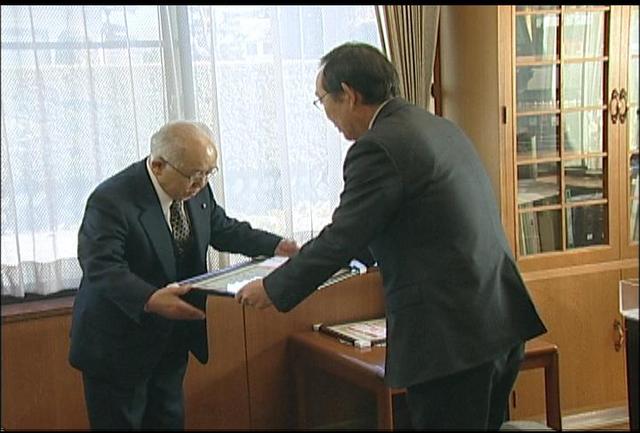
平成21年度の南箕輪村むらづくり大賞に、きれいなアクセス道路にしよう会が選ばれた。
19日は、役場で表彰式が行われ、代表の中島重治さんに賞状などが手渡された。
きれいなアクセス道路にしよう会は、駒美交差点から信大前交差点までの2.8キロ区間で、清掃作業や花壇整備などを継続して続けている。
神子柴地区の住民や企業など80人が活動に参加している。
また、平成17年から42人が桜の管理を続けている、北殿エドヒガンザクラ愛好会は、むらづくり賞に選ばれ、小林広幸会長に賞状などが手渡された。
唐木一直村長は、「幅広い地域活動で、道路管理や村のシンボルを守っていただいてありがたい」と地域のボランティア活動に対し感謝していた。 -
村井知事と語るつどいIN宮田

村井仁長野県知事と語るつどいが19日、宮田村の村民会館で開かれ、地産地消をテーマに地元住民と語り合った。
19日は、上伊那地区の農家や学校給食関係者など約150人が集まった。
最初に村井知事と料理研究家の横山タカ子さんが地産地消について話した。
村井知事は、「上伊那はさまざまな農作物が取れ、地産地消を実現できる環境に恵まれている」とし、「学校給食に地元食材を取り入れたり、産直市場が多数あるなど、地産地消にも力を入れている」と話した。
横山さんは、今はハウス栽培で一年中食べられる野菜が多いことに触れ、「地域の旬の食材を3度の食事で食べることに勝るものはない。ぜひ地元の食材を食卓にあげるようにしてほしい」と訴えた。
また、上伊那で地産地消の推進に取り組んでいる関係者による意見発表もあった。
そのうち、伊那市長谷で農家民宿「未来塾」のおかみ、市ノ羽 幸子さんは、野生動物による農作物被害が深刻で、年をとった農家が野生鳥獣の被害にあって農業をやめることが増えていると話した。
これに対し、村井知事は、「何か手立てがあればとは思っているが、シカやサルを防ぐ柵の中で人間が耕作をする時代。深刻な問題と考えている」と答えていました。 -
総合評価落札方式導入へ

伊那市は18日開かれた第4回伊那市入札等検討委員会で、来年度から、建設工事の一部で総合評価落札方式を試行的に導入したいとの考えを示した。
総合評価落札方式は、価格と価格以外の要件を点数化し、その評価点の合計で落札者を決定する方式。
価格以外の評価は、業者の工事実績や、伊那市と災害協定を締結しているなど地域に貢献しているかどうかなどで評価するもので、今後、内容を検討し、次回7月に開かれる委員会に示される予定。
伊那市は総合評価落札方式の導入により、公共工事の品質を確保したい考えで、県や実施している自治体の取り組みを参考に、来年度の秋ごろから試行的に実施したいとしている。
また、委員会では、建築工事にかかわる実施設計業務と監理業務を一括発注で入札する方式を来年度から試行的に実施する方針が示された。
この方式は、管理業務費用の積算方法が来年度から変更となる事から実施されるもの。
監理は、設計書のとおりに工事が進んでいるかを確認する仕事で、これまでは、建築工事を落札した業者と伊那市が随意契約を結び、委託していた。
伊那市では、来年度から設計と監理を一括で競争入札とする方式を、試行的に行い、より入札の透明性を確保したいとしている。 -
上伊那公立病院等運営連携会議 初会合

上伊那の公立3病院の機能再編などについて検討する上伊那公立病院等運営連携会議が17日、伊那市役所で開かれた。
会議には公立3病院の院長や上伊那医師会会長、また県の担当者ら21人が出席した。
この会議は、公立病院の機能分担や連携、医師確保のための仕組みの構築などについて検討するもので、これら地域医療再生のための事業に国から5年間で22億4千万円が交付される。
会議では救急医療部会や辰野総合病院施設部会などテーマ別に7つの部会が設置されることが了承された。
辰野総合病院施設部会では、回復期機能強化のための辰野総合病院の移転新築について検討していく。
また事業計画にあった公立3病院の経営統合については当面、機能分担と連携に重点を置くことが確認された。
また救急医療部会では今後、駒ヶ根市の昭和伊南総合病院から伊那中央病院へ救命救急センターの指定変更についても協議される。
救急医療について、実情は伊那中央病院が担っているものの、指定変更については駒ヶ根市など地元が難色を示していることから、救急医療部会で検討していく。
伊那中央病院を運営する伊那中央行政組合の小坂樫男伊那市長は「救急医療部会で早急に結論を出してもらいたい」と話している。
救命救急センター指定について会議では、結論を出すのは県だが課題としては認識しているとして、今後地域住民の理解を得ながら協議を進めていきたい竏窒ニしている。 -
担当部署への直通電話導入
伊那市は、現在の代表電話に加え、新たに各担当部署への直通電話を導入する。
直通電話は、24日から導入を始める予定で、27日以降から使用される。
伊那市役所からの電話は、代表電話である78竏・111で着信履歴が残り、履歴をみて掛けなおしても、どの部署がかけたのかわからないという案件が増えたため、今回、直通電話を導入することにした。
番号は、96竏・100から96竏・165まで63あり、各課の係りに直接かけることが出来るようになる。
伊那市では、夜間や災害時などは、交換を通じなくても直接担当部署に電話がかけられるので、対応がスピーディになるとしている。
なお、代表電話はこれまでと変わらず、今までと同様に使用できる。 -
廃棄物不法投棄防止巡回パトロール

上伊那地方事務所や市町村などでつくる上伊那地区不法投棄防止対策協議会は12日、常習的にごみが捨てられている場所の巡回パトロールを行った。
伊那市西町小黒原の市道脇の山林は、片付けてもまたごみが捨てられる常習的な不法投棄個所で、地主が看板を立てても、ビニールヒモを張っても効果はない。
昨年、一帯のごみを取り除いたが、今回訪れてみると、家庭から出るごみを中心にペットボトルや空き缶、ぬいぐるみが捨てられていた。
巡回パトロールをしたのは26人で、伊那市と南箕輪村の3カ所を回った。
伊那市の担当者は、「なかなか効果的な対策がみつからない」と参加者に説明していた。
上伊那地域の不法投棄件数は、ほぼ横ばいで推移していて、昨年度は524件、今年度もこのままいくと昨年度同様の件数になるものと見られる。
市町村別では、駒ヶ根市は減少傾向にあるが、伊那市や南箕輪村では増加傾向にある。
投棄個所は、山林や道路が特に多く、捨てられているのは家庭ごみが大半を占める。
対策協議会では、来年度も不法投棄監視連絡員11人を委嘱し、不法投棄防止に力を入れていくことにしている。 -
庄内地区から箕輪町の卒業生に花束

卒業を間近に控えた箕輪町の小中学生に、町と友好交流推進協定を結ぶ静岡県浜松市の庄内地区から16日、花束が贈られた。
16日は庄内地区の、交流協会の役員が箕輪町役場を訪れ、今年度の小中学校の卒業生と教員、約670人分の花束を手渡した。
花束を受け取った箕輪西小学校6年の吉村僚(りょう)君は、「中学校では勉強を一生懸命頑張りたい」と話していた。
また、箕輪中学校3年の土井ゆいさんは、庄内地区との交流を振り返り、「これからも後輩達がお世話になります。今日はきれいなお花を頂き感謝しています」と話していた。
花束は、それぞれの卒業式で、卒業生一人ひとりに贈られる。
庄内地区の卒業生へのプレゼントは、10年ほど前から続いている。
小学校の卒業式は17日(水)に、中学校の卒業式は18日(木)に行われる。 -
南箕輪村南原保育園竣工式

南箕輪村の南原保育園で16日竣工式が行われ新しい園舎の完成を祝った。
竣工式には、村役場や地元の関係者など50人が出席し園舎の完成を祝った。
式では、年長の園児が太鼓を披露し竣工式に花をそえた。
新しい園舎は、古い園舎を取り壊し、前の駐車場部分も使って建設され、敷地面積は、およそ5000平方メートル。
木造平屋建てで、大芝高原の間伐材などが使われている。
村内の公共施設ではじめて、ペレットボイラーを利用した床暖房が備えつけられたほか、屋根の上にはソーラーパネルが約100枚設置されるなど、環境に配慮した建物となった。
新しい保育園は、今月1日から利用が始まっていて、今後は園庭に芝を張る計画です。
唐木一直村長は「この新園舎を子どもの健全な心身を発達させる場所として、園児一人ひとりが健やかに成長できるよう職員一同力を合わせて頑張っていきたい」と挨拶した。 -
箕輪町議会閉会
箕輪町議会3月定例会は15日、委員会に付託していた議案と追加議案合わせて32議案を可決・同意し、閉会した。
追加議案の主なものは、箕輪中学校武道場建築工事の請負契約が8536万5千円、地域スポーツセンター建築工事の請負契約が2億5998万円、小中学校太陽光発電導入事業の請負契約がおよそ2億4197万円など。
また、議員から、厳しい経済状況を考え、議員報酬を今年度に引き続き来年度も3%削減する議案が提出され、可決された。 -
箕輪町が使用料滞納で法人提訴へ
箕輪町は、大出のそば加工施設「留美庵」の施設管理を委託している法人が土地建物の使用料を滞納していることから、訴えを起こすことを決めた。
15日開かれた箕輪町議会3月定例会に、町が訴えを起こすことについての議案を提出し、賛成多数で可決された。
平澤豊満町長の説明によると、そば加工施設は町と中箕輪農事組合法人が施設管理委託契約を結んでいる。
法人は、町に支払う土地建物の使用料を滞納していて、滞納額は今年1月27日現在、約767万8千円になる。
町では、施設の明け渡しと使用料の支払いを求め、長野地方裁判所伊那支部に訴えを起こす考えで、平澤町長は、1週間以内に準備を進めたいとしている。
中箕輪農事組合法人では、「議案の内容を知らないのでコメントできない」としている。 -
「入野谷」への名称変更条例改正案 否決
伊那市長谷の「南アルプス生涯学習センター」の名称を「入野谷」に変更する条例改正案が、15日開いた伊那市議会で否決された。
市が提出した議案が議会で否決されるのは、新市になり初めて。
同日の伊那市議会3月定例会の本会議で、議会に提出されている43議案について、採決が行われた。
このうち、南アルプス生涯学習センターの名称変更に関する条例改正案について委員長報告の後、討論が行われ、「広く市民から親しまれている「入野谷」とするべき」といった賛成意見や、「設立当初の思いを忘れないためにも、現在の名称を残すべき」といった反対意見などが出された。
採決の結果、賛成7、反対18で、条例改正案は否決された。
小坂樫男伊那市長は取材に対し、「任期中に臨時議会を開き、改めて名称変更の条例改正案の提出を検討したい」と話した。
このほかの平成22年度一般会計予算案含む42議案は原案どおり可決された。 -
小坂市長 議会で最後のあいさつ

今期限りで退任を表明している小坂樫男伊那市長は、3月定例市議会最終日の15日、議会議員に対して、最後のあいさつをした。
小坂市長は「市民や市会議員、職員の皆さんの協力を得て多くの事業を成し遂げることができた。特に市会議員の皆さんとは、時に議論し、貴重な意見を頂き、車の両輪として支えて頂き感謝している」とあいさつした。
小坂市長は、平成6年に旧伊那市の助役に就任して以来、市政に携わった16年間を振り返った。
やり遂げた主な政策として、新伊那中央病院の移転新設、市街地の再開発事業としてのいなっせ完成を挙げていた。 -
長谷地域協 「入野谷」へ名称変更問題なし

9日に開かれた伊那市議会経済建設委員会の委員会審査で、住民への説明不足として否決された、南アルプス生涯学習センターの名称を「入野谷」とする条例改正案について、12日夜開かれた長谷地区地域協議会は、名称変更は問題ないとした。
伊那市長谷総合支所で協議会が開かれ、名称変更について協議した。
南アルプス生涯学習センターは、通称「入野谷」として地域住民や観光客から親しまれている。
条例改正案は、「南アルプス生涯学習センター」を「入野谷」に変更するもの。
協議会で委員からは「入野谷として定着しているので問題はない」「呼びなれている愛称の方が親しみやすい」などの意見が出され、条例改正は問題ないとする認識で一致した。 -
野口俊邦氏出馬表明
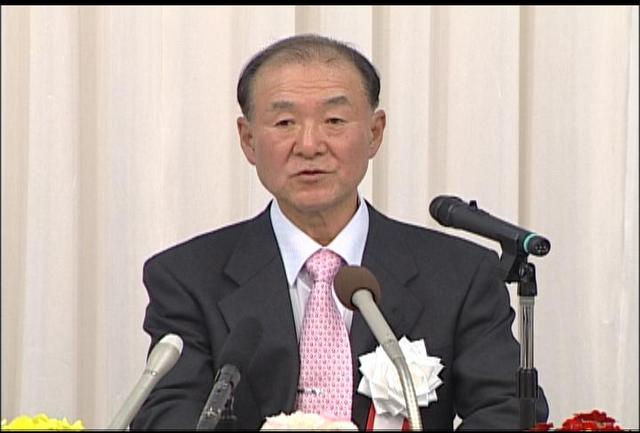
任期満了に伴い4月に行われる伊那市長選挙に、元信州大学農学部長で名誉教授の野口俊邦さんが立候補することを11日正式に表明した。
野口さんは、11日夜、伊那市美篶の信州伊那セミナーハウスで支持者が見守る中記者会見を開き、正式に立候補することを表明した。
野口さんは、具体的な政策はこれからみなさんと一緒に考えていきたいとしながらも、市民と直接対話するお出かけ市長室の設置や住民投票条例の制定、市長の給与・退職金の30パーセントカットなどを掲げている。
無所属での立候補予定で、考え方が一致する政党からの推薦があれば受ける考え。
野口さんは会見で、「伊那市の現状を見れば、必ずしも法にのっとらない、そして責任ある行政でもない。一番問題なのは、市民に冷たい市政が行われていること。これを市民が主人公で、市民にあたたかい市政に展開することが急務だと考えました。みんなの会の皆さんの強いご推薦の中で、私が先頭に立って、この状況を改善するということを決心し、今回立候補させていただくことになりました。」とあいさつした。
11日は、記者会見に引き続き、出馬表明集会が開かれた。
野口さんに出馬を要請した、今の市政に批判的な住民有志でつくる「市民本位の市政をすすめるみんなの会」の代表の1人で、産直市場グリーンファームの小林史麿会長は、「市民の要望に基づく市民参加の市政運営に変えるよう、住民パワーで戦っていきたい」とあいさつした。
立候補を11日正式に表明した野口さんは、67歳。
佐賀県出身で、九州大学を卒業後、1988年に信州大学の教授に就任。2001年から農学部長を1期務めている。
県公共事業評価監視委員会委員長、伊那市情報公開審査会と個人情報保護審査会の委員長も務めた。
立候補に向け、住所は、これまで住んでいた南箕輪村の南原から3月1日に伊那市西町に移している。
伊那市長選挙は、小坂樫男市長が引退を表明し、これまでに新人で前の副市長の白鳥孝さんが出馬を表明している。
伊那市長選挙は、4月18日に告示、25日に投開票される。 -
上山田区がアセス先進地視察へ

新しいごみの中間処理施設の建設候補地の隣接区、伊那市高遠町上山田区の対策委員会は、18日に環境アセスメントの先進地を視察する。
上伊那広域連合の新しいごみの中間処理施設の建設候補地となっている伊那市富県の天伯水源付近の隣接区となっている上山田区は、現地に近いこともあり押出(おしだし)地区を中心に関心が高い地域。
視察するのは、上山田区対策委員会の委員14人で、長野広域連合が可燃ごみの中間処理施設建設に向けて現在進めているアセスの現地調査の現状などを聞く予定。
一行は、18日に、上伊那広域連合や伊那市の職員とともに長野市大豆島(まめじま)の現地を訪れる予定。
上伊那広域連合では、来年度から伊那市の新しいごみ中間処理施設の環境アセスに着手する計画。 -
生ごみ処理器設置補助更新も対象
南箕輪村は来年度から、家庭用生ごみ処理器の設置補助について、更新の世帯も補助対象にする方針。
11日に開かれた南箕輪村議会3月定例会一般質問で、唐木一直村長が答えた。
南箕輪村は、家庭用生ごみ処理器を設置する家庭に、1台上限2万円を補助していて、この補助制度の利用は1回となっている。
村は去年10月に、これまでに補助金を交付した全世帯を対象にアンケートを行った。
521世帯のうち372世帯が回答し、回収率は71・4%だった。
アンケートの中で、「生ごみ処理器の更新時に再び補助があるなら利用したい」と答えた世帯が75・5%あった。
この結果を受け、村では最初の補助金交付から6年以上経過した家庭に対して、再度補助金を交付することにした。
村は、更新10器分を含む合計30機分の補助金60万円を新年度予算に計上している。
今議会で可決されれば、4月1日から実施したいとしている。 -
箕輪町第4次振興計画後期基本計画案を答申
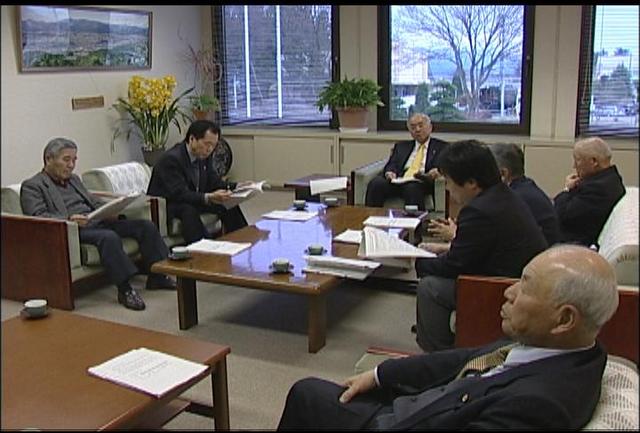
箕輪町振興計画審議会は8日、町の平成22年度から26年度までの施策の方向性を示す第4次振興計画後期基本計画の最終案を平澤豊満町長に答申した。
審議会の柴壽会長らが役場を訪れ最終案を平澤町長に答申した。
審議会では、町の住民満足度調査などの結果を踏まえ後期基本計画の内容を検討してきた。
答申によると、平成22年度から26年度の施策の方向性を示した第4次振興計画後期基本計画は、協働のまちづくりや健康作りの推進、安全安心なまちづくりのためのセーフコミュニティ認証取得を目指した活動に取り組むことなどが盛り込まれている。
平澤町長は、「正式な後期基本計画として位置付け進めていきたい」と話していた。
箕輪町では、第4次振興計画後期基本計画のダイジェスト版を4月中に全戸配布する。 -
優先駐車区画 妊産婦らも利用へ
箕輪町の平澤豊満町長は9日、役場駐車場の障害者などの優先駐車区画を、妊娠中や出産前後の女性なども利用できるよう整備する考えを示した。
同日開かれた箕輪町議会3月定例会一般質問で議員の質問に答えた。
役場駐車場には現在、優先駐車区画は障害者用が2台分、高齢者用が4台分ある。
妊産婦や、心臓機能障害などの内部障害者のための駐車場について、平澤町長は、この6台分の優先駐車区画と併用する考えで、「妊産婦や内部障害者のマークを付け加え、早急に表示させてもらう」と答えた。
町総務課では、今年度中に対応する竏窒ニしている。 -
村事務事業評価に対する検討結果報告

南箕輪村の実施している事業の必要性を検討してきた「むらづくり委員会」に対し、唐木村長は8日、委員会の考え方に対する村の方針を説明した。
むらづくり委員会の唐澤俊男委員長らが役場を訪れ、村長から報告書を受け取った。
委員会では昨年、村が行った事業の効率性や有用性を検討し、その事業が必要かどうかを含めて検討を行った。
検討結果は昨年12月に唐木村長に報告した。
村では、その意見に基づき検討を行い、まとまった村の方針を委員会に伝えた。
委員会が「必要」として報告した防犯灯の整備事業については、唐木村長が村内ではほぼ整備が完了していることを話し、「今後は古くなったものからLEDにしていきたい」と話した。
また交通対策については、来年度中に検討組織を立ち上げ、検討していく方針を示した。
唐木村長は、「委員会の結果には十分配慮したいが、行政として、難しい部分もある。それをご理解いただきたい」と話した。 -
下水道料金未請求 原因内訳示す
下水道使用料の未請求があったことについて伊那市は9日、その原因の内訳を伊那市議会経済建設委員会で示した。
伊那市では、下水道に接続しているにもかかわらず、使用料を請求していなかった事例134件のうち何が要因でミスが起こったのかを調査した。
その結果、過去にアパートなどでは、入居者がいなければ下水道に接続していても、使用開始届けを出さなくてもよいとしていたことがあり、その後、入居者が入っても使用開始届けが未提出のままだったケースが57件、率にして42%を占めた。
また、工事を担当する係から料金の請求を行う係に事務処理が移る時、うまく伝わっていなかったケースが25件で18%、下水道の使用開始届けの必要枚数をチェックしていなかったり、提出してもらった届出を紛失したと思われるケースが19件で14%となった。
また、無届で工事を行った業者もあった。それらはすべて市の指定工事店ではなかったという。
年度別発生件数でみると、平成19年度が39件と最も多くなっていて、次いで平成16年の24件、平成17年の20件となっている。
市では、平成5年から下水道の供用を開始していて、「当時の不完全なシステムを見直さないまま、運用を続けてきたことが今回の問題を招いた」と説明した。
市では今後、聞き取り調査を行い、事実関係を確定するという。 -
高遠城址公園さくら祭り対策会議
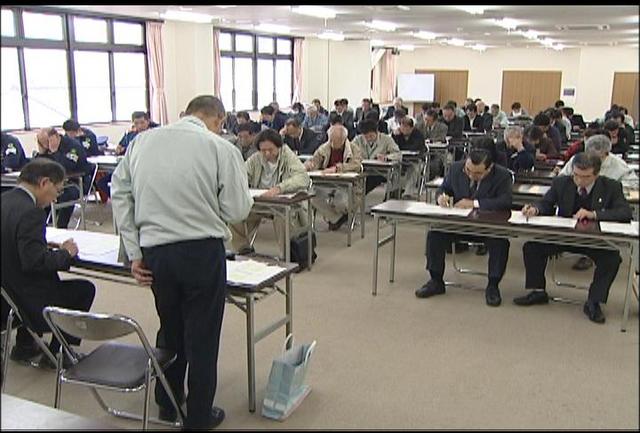
高遠城址公園さくら祭り対策会議が8日、伊那市高遠町の総合福祉センターやますそで開かれた。
会議には各種団体の代表者などおよそ70人が出席し、祭り期間中の交通規制や入園方法、出店者の食品衛生などについて確認が行われた。
去年の祭りでは、高速道路のETC割引により、市内各地で渋滞が起きた。
今回は、その反省を生かし、桜が最盛期となる週末、4月10・11日、17・18日に伊那市役所に臨時駐車場を設け、無料シャトルバスにより送迎すること、高速道路にかかる橋に、諏訪インターや駒ヶ根インター利用を呼びかける横断幕を設置することにしている。
なお、国道152号高遠バイパスが今月完成する予定で、高遠町商店街周辺の渋滞緩和が期待されている。
高遠城址公園の公園開きは、4月1日を予定している。 -
箕輪町が肺炎ワクチン予防接種に補助
箕輪町は来年度、75歳以上の町民を対象にした肺炎球菌ワクチンの予防接種補助事業を始める。
8日開かれた箕輪町議会3月定例会一般質問で、平澤豊満町長が説明した。
肺炎球菌ワクチンの予防接種をすると、肺炎にかかった場合に、軽症で済み、ワクチンの効果は5年位続くという。
箕輪町では、去年1年間で、肺炎など呼吸器系が原因で死亡した人の数が、ガンに次いで2番目に多く、そのうちの81%が75歳以上だったという。
このため町では、75歳以上を対象にワクチン接種の補助を決めた。
ワクチン接種の費用は6千円から7千円で、町は1人あたり3千円を補助します。
来年度予算には、補助費用として100人分、30万円を盛り込んでいる。
この肺炎球菌ワクチンの予防接種補助事業は、上伊那では飯島町が実施しているという。 -
野口名誉教授が市長選 出馬へ

任期満了に伴う4月の伊那市長選挙に、元信州大学農学部長で名誉教授の野口俊邦さんが4日夜、立候補する意向を示した。
4日夜は、現市政に批判的な市民30人ほどが市内で会合を開き、「市民本位の市政をすすめるみんなの会」を立ち上げた。
会は、その場で、野口さんに出馬を要請し、野口さんが受諾した。
野口さんは、南箕輪村在住の67歳、佐賀県出身で、九州大学を卒業後、1988年に信州大学の教授に就任。2001年から信州大学農学部長を1期務めている。
野口さんは、「多くの人にご支持を頂いて、市政を変えなければならないという責任を感じている。その実現のためにがんばりたいという気持ちでいっぱいです」と話していた。
野口さんは、無所属で出馬する意向で、11日に記者会見を開き、正式に出馬表明する予定。
なお、伊那市長選挙では、現職の小坂樫男市長が引退を表明。
前の副市長の白鳥孝さんが出馬を表明している。 -
伊那市の虐待件数 年々増加傾向
伊那市教育委員会は、5日、市内で確認された児童虐待の件数が、年々増加傾向にあることを報告した。
今年度は、2月末現在で59件の虐待を確認している。
5日の伊那市議会3月定例会で報告された。
これによると、平成19年度には、21の家庭で28件の虐待が確認された。翌20年度は30の家庭で40件、今年度は2月末現在で33の家庭で59件の児童虐待が確認され、警察に通報した。今年度は、59件中32件の虐待を、小中学校の教諭や保育園の保育士が発見している。
実の父親や母親からの虐待が90%以上で、父親の家庭内暴力や母親の育児放棄などがあったという。
市では、3歳児検診などで虐待を発見できるような体制づくりを進め、虐待の早期発見につなげたいとしている。 -
中病「内視鏡センターは民間で」
伊那市の伊那中央病院の敷地内に開設する予定となっている医師の「内視鏡技術トレーニングセンター」について、小坂樫男市長は「運営主体は民間に任せたい」とする意向を5日の伊那市議会3月定例会一般質問の示した。
内視鏡技術トレーニングセンターは、県が策定する地域医療再生計画に盛り込まれていて、難しいとされる内視鏡手術の技術トレーニングを行える施設。
5日の議会で、小坂樫男市長は、「施設で研修する医師のほとんどが勤務医となる見込み。トレーニングを行うのは土日に限られ、平日は空いてしまう可能性がある」とした上で「できれば民間でやってもらえればいいと思っている」として、今後、内視鏡の製造メーカーや、医薬品開発企業、信州大学医学部などと連携しながら、運営方法や運営主体を模索していくとしている。
272/(金)
