-
英語教室の子ども達が村に2万円を寄付

南箕輪村の英語教室「放課後英語」で学ぶ子ども達が1日、教室で集めた募金2万円を寄付しました。
この日は教室に通う年長から小学6年生までの10人が村役場を訪れ「地域の緑のために使って下さい」と加藤久樹副村長に2万2千175円を手渡しました。
放課後英語では、国際社会に貢献できる大人になってもらおうと、環境問題についても考えています。
環境のために、授業中に飲み物を飲む時に使う紙コップをやめマイカップにしていて、紙コップを使ったつもりで募金をしようとお金を集めました。
この日は子ども達から加藤副村長に環境に関するクイズが出され、6年生はオゾンホールが広がる季節を「英語で答えてください」と問いかけていました。
加藤副村長が「ウインター」と答えると、子どもから「間違いです。正解はスプリングです」と指摘されていました。
加藤副村長は「村の緑のために大切に使わせてもらいます」と話していました。
今回の寄付は大芝高原の整備に使われるということです。 -
灯油タンクから灯油漏れ
南箕輪村久保で2日、畑に設置されている灯油タンクから灯油が漏れ水路に流れ出しているのが見つかりました。
伊那警察署では流れ出した灯油の量や原因について調べを進めています。
伊那警察署の発表によりますと、灯油漏れがみつかったのは南箕輪村久保の畑です。
昼ごろ水路に油が浮いているのを発見した近くの住民が村役場に知らせ、職員が現場に駆けつけました。
灯油が流れだした水路では、職員らがオイルフェンスを張ったり、吸着マットで灯油を吸い取るなどの作業にあたっていました。
水路近くには田んぼもあり一部に灯油が流れこんだとみられています。
伊那署では灯油が流れだした原因や量について調べを進めています。 -
消防広域化へ 7月3日に協議会初会合

上伊那地域の消防広域化を具体的に検討する協議会が7月に発足し、7月3日に伊那市役所で初会合が開かれます。
31日は、伊那市役所で、伊那消防組合議会全員協議会が開かれ、協議会の組織体制や委員構成、協議事項等の案が報告され、了承されました。
協議会は、設立準備会議を経て伊那市役所で7月3日に初会合が開かれる予定で、平成27年度中に広域消防の新団体発足を目指しています。
説明によりますと、協議会は任意の協議会で名称は「上伊那消防広域化協議会」です。
協議会では、構成する伊那消防組合と、伊南行政組合の市町村長や議員、オブザーバーとして県消防課長と上伊那地方事務所長を加えた18人で協議を進める計画です。
協議会では「広域化の方式について」や「消防本部の位置について」、「消防救急無線のデジタル化」など51項目について検討を行っていきます。
この他に、伊那消防署の移転新築について、平成25年度に用地取得し、平成26年度中に竣工する計画が報告され、了承されました。 -
関東農政局伊那西部支所 事務所開き

老朽化に伴い、今年度から24億円をかけ施設改修が進められる伊那西部地区農業用水。
12月の工事着工を前に、国の出先機関となる農林水産業関東農政局伊那西部支所の事務所開きが、29日に伊那市内で行われました。
この日は、関係市町村や土地改良区連合の関係者などおよそ40人出席し事務所開きをしました。
事務所では、職員3人が常駐し工事の積算や発注、監督業務を行います。
伊那西部地区農業用水は、安定的な農地確保を目的に、昭和47年から昭和62年にかけてつくられました。
水は、南箕輪村から湧水などを取水し伊那市西箕輪までポンプで汲みあげ辰野町から伊那市の西天より上段にある、およそ2500ヘクタールの農地に水を供給しています。
しかし、完成から25年以上が過ぎ、機器の耐用年数が過ぎている事や配管からの漏水など、水の安定供給に支障をきたしてきた事から改修工事の実施が決まりました。
この日、いなっせで開かれた開所式で、関東農政局の狩俣茂雄次長は、「施設改修の事務所としてだけではなく、中央と地方を結ぶ農政の拠点となるよう活用してほしい」と話していました。
伊那西部土地改良区連合の福澤良一理事長は「大きな財産を次の世代へ繋げられるよう、円滑に事業を推進してほしい」と話していました
改修工事は10年の計画で進められ、総事業費は24億円で、このうち3分の2は国が負担、残りを県や地元自体、関係する土地改良区で負担することになっています。 -
伊那広域シルバー人材 4年連続減収
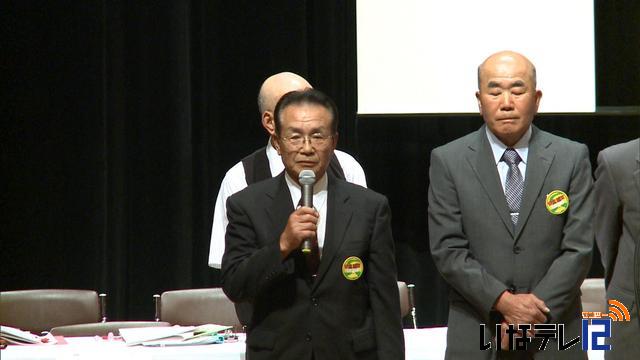
公益社団法人・伊那広域シルバー人材センターの昨年度の契約金額は、前の年度より1400万円減のおよそ3億9800万円で、4年連続の減収となりました。
30日は、伊那市の伊那文化会館で総会が開かれました。
伊那広域シルバー人材センターは伊那市・辰野町・箕輪町・南箕輪村の会員で構成されていて、平成23年度末現在で675人が活動しています。
ピーク時の平成19年度には、およそ5億円を超える契約がありましたが、平成20年のリーマンショック以来、4年連続の減収となっています。
今回の総会では、任期満了に伴う理事の改選が行われ、互選で伊那市の伊藤裕偉さんが新理事長に選ばれました。伊藤さんは、「会員の減少、契約の減少を食い止める事がこれからの課題。先進地の例を参考に独自事業を考えていきたい」と話していました。 -
山本厚生さん「ひと裁ち折り」講座

東京の一級建築士、山本厚生さんによる「ひと裁ち折り」講座が28日、南箕輪村の大芝研修センターで開かれました。
講座は地域の歴史や文化などについて学んでいる伊那谷地域住民大学が開いたもので、会場にはおよそ30人が集まりました。
講師を務めたのは、東京の一級建築士、山本厚生さんで、「ひと裁ち折り」について話をしました。
「ひと裁ち折り」は、山本さんが考案したもので折り紙を折って一直線に切るだけで文字や図柄など様々な形をつくりだす紙遊びです。
参加者は、山本さんの指示通りに紙を折ったあと、1回ハサミを入れてハートの形を作っていました。
「ひと裁ち折り」では左右対称のものだけでなく折り方を工夫することでアルファベットなどの文字を作ることもできるということです。
山本さんは、「「ひと裁ち折り」は頭も使うし人とのコミュニケーションにも役立つ。世代を超え楽しめる遊びとして広めていきたい」と話していました。 -
標高差1200m!伝統の強歩大会

南箕輪中学校の伝統行事、経ケ岳強歩大会が23日に開かれました。
今年は、60回の記念大会となった、強歩大会、スタートの横断幕も同窓会から贈られ新たな物となりました。
午前7時、南箕輪中学校の生徒およそ450人は大芝高原をスタートし、ゴールの経ケ岳8合目を目指しました。 -
フクロナデシコ 南箕輪村南原の畑で見ごろ

南箕輪村南原の伊藤照夫さんの畑では、フクロナデシコがピンク色の花を咲かせ、見ごろを迎えています。
南箕輪村南原の国道361号沿いにある30aの畑一面にフクロナデシコが植えられ、現在見ごろとなっています。
フクロナデシコは、ナデシコ科の1年草で、地中海沿岸が原産です。
もともとトウモロコシ畑だった遊休農地をキレイにしようと伊藤さんが花を植え、今年で2年目になります。
去年秋に種をまき、冬の間も草取りをしてきたという事です。
23日の伊那地域の最高気温は26.6℃の夏日となり、平年より4.2度高い、7月上旬並みの気温となりました。
フクロナデシコの見ごろは、来月初め頃までだということです。 -
台湾の高校生と上農生が農業体験で交流

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒は22日、教育旅行で訪れた台湾の高校生と農業体験などをして交流しました。
上伊那農業高校を訪れた台湾の高校生の生徒達28人です
22日は、班に分かれて上農の生徒達が授業で行っている活動を台湾の生徒たちに紹介しました。
このうち、園芸科学科では、余分な実をつみとる西洋ナシの摘果体験を行いました。
台湾の高校生たちは、上農生たちに教えてもらいながらハサミを使って摘果作業をしていました。
言葉が通じないため、身振り手振りで会話をする姿も見られました。
この他にも、そば打ちや郷土食を味わってもらおうと五平もちづくりも行われ、台湾の高校生たちはこの地域に伝わる食文化を学んでいました。
五平餅づくりを体験した台湾の高校生は「初めて見るものばかりで新鮮でした。食べるのが楽しみです」と話していました。
台湾の高校生の生徒たちは、ホームステイなどをして26日まで日本に滞在するということです。 -
南箕輪中学校の経ヶ岳強歩大会60回記念講演

南箕輪村の南箕輪中学校の恒例行事、経ヶ岳強歩大会は今年で60回を迎えます。
23日の本番を前に、60回の記念として、トレイルランナーの山田琢也さんを招いての講演会が17日開かれました。
講演したのは、下高井郡木島平村のトレイルランナー山田琢也さんです。
トレイルランニングは、舗装されていない山野を走るスポーツです。
山田さんは、全校生徒476人とPTAを前に、映像を使いながら山での走り方について話しました。
山田さんは、17日の朝大芝から経ヶ岳の頂上までを走ってから講演に臨んだということです。
「実際に走ってみて、中学生には大変なコースだと思うが、毎年継続して開催しているこの地域に敬意を表します」と話していました。
経ヶ岳強歩大会は、23日に予定されていて、全校生徒が8合目までの8.3キロを目指して走ります。 -
南箕輪村商工会 新会長に堀正秋さん

任期満了に伴う南箕輪村商工会の役員改選が、16日行われ、新しい会長に、久保の(株)堀建設社長、堀正秋さんが選任されました。
この日開かれた南箕輪村商工会の通常総会で役員改選が行われました。
新しい会長に久保の(株)堀建設社長、堀正秋さんが選ばれました。
新任の挨拶で堀さんは「経済が低迷する中、村や関係者の指導を頂きながら、商工会と地域の発展のために努力していきたい」と話していました。
任期は、3年間で平成27年度の通常総会までとなっています。 -
運動あそび 未満児に力を入れる

南箕輪村が平成18年度から導入している運動あそびの活動報告会が14日、村役場で開かれ、今年度は未満児に力を入れていくことなどを確認しました。
南箕輪村では平成18年度から松本短期大学の柳沢秋孝教授が考案した運動あそびを導入していて今年で7年目です。
現在、1人の運動保育士が村内の5つの保育園で運動あそびの指導を行っています。
今年度は、未満児に力を入れていくとしています。
柳沢教授は、未満児から運動あそびをすることで動ける体の基礎をつくれると話していました。
他に、万歩計をつかって年長の日常生活の活動量を調査する計画です。
出席した保育士からは「子供たちは運動あそびを楽しみにしている」「担任の保育士達も工夫して運動あそびを取り入れている」などと報告がありました。 -
南箕輪村大泉所山でニホンジカの駆除報告

南箕輪村有害鳥獣対策協議会が14日南箕輪村役場で開かれ、西山の大泉所山で始めてニホンジカを駆除したことが報告されました。
協議会には、会員8人が出席し昨年度の事業実績などが報告されました。
それによりますと南箕輪村の飛び地の西山、大泉所山でニホンジカ15頭、南原で2頭が駆除されたことが報告されました。
協議会会長の唐木一直村長は「西山にも、いよいよニホンジカがはいってきた。繁殖力が強いので食害による林業などへの影響が心配だ」と述べました。
今年度村では、昨年度に引き続き罠設置免許取得と更新の補助など、およそ130万円を有害鳥獣対策にあてることにしています -
西駒山草会 第11回西駒山野草展示会

新緑の季節を迎え、上伊那各地で山野草の展示会が開かれています。
南箕輪村の南原公民館では、西駒山草会による第11回西駒山野草展示会が、12日から始まりました。
会場には、10人の会員が育てた300点ほどの山野草が展示されています。
そのうち9割が突然変異でおこる白いまだら模様の「斑(ふ)」が入ったものです。
斑は野生では珍しく、会員が時間をかけて集めたものを交配させながら増やし、育てました。
12日は350人ほどが訪れ、山野草を鑑賞していました。
西駒山草会代表の網野幸治さんは、「斑入りの山野草を集めた展示会は県下でも珍しいのでたくさんの人に見てもらいたい」と話していました。
西駒山野草展示会は明日まで開かれています。 -
母の日 ねんどで手作りカーネーション

13日の母の日を前に、親子がねんどを使ったプレゼントを作る、ものづくり講座が12日南箕輪村の村民センターで開かれました。
講座には保育園児から小学6年生までの29人の子供とその保護者が参加しました。
やわらかい樹脂性の粘土で作ったカーネーションをじょうろの形のポットに乗せた置物を作りました。
子供たちは、保護者と協力しながらねんどをこね、花の形を作っていました。
南箕輪村では、手作りによる心のこもった物づくりを体験してもらおうと、毎月物づくり講座を開いています。
6月には父の日にあわせた体験イベントを行うことになっています。 -
JA上伊那 米穀施設整備始まる

JA上伊那は、米穀施設の老朽化が進んでいることから、施設の再編を進めています。
14施設のうち、3つの施設の拠点施設としての整備が11日から始まりました。
拠点施設の整備が行われるのは、南箕輪ライスセンター、美篶3号カントリーエレベーター、飯島カントリーエレベーターです。
11日は、南箕輪と美篶の増改修工事安全祈願祭が南箕輪ライスセンターで行われ、関係者およそ70人が集まり工事の無事を祈願しました。
JA上伊那は、施設が老朽化していることから、上伊那広域での施設整備を3年から5年の計画で進めています。
総事業費は17億円で、うち拠点施設の整備にかかる10億円を国の補助金で賄います。
南箕輪ライスセンターの整備は、総事業費およそ4億1千万円で、400トンの米を保管できるサイロ5基を新設する他、乾燥機1基を増設し処理能力を向上させます。
整備事業は、9月末の完了を予定しています。 -
猟師のくくりわな 南箕輪村に寄付

南箕輪村田畑の猟師、加藤尚さんは、自身が開発し特許もとったニホンジカ捕獲用のくくりわなを11日村に寄付しました。
加藤さんが寄付したのは、加藤式くくりわな隼10セットです。
従来のものと比べ重さは、2分の1、踏み板部分の面積は2倍で発泡スチロールでできています。
発泡スチロール部分は、村内にある包装・梱包資材などを製造販売している興亜化成と共同開発しました。
このくくりわなの特徴は、踏み板部分の発泡スチロールに切れ目を入れることで3キロほどの荷重がかかると半分に割れる点です。
金属を使った機械式のものと比べて、寒さに強く軽量で、女性や高齢者でも仕掛けやすくなっているということです。
発泡スチロールがVI字型に割れる形が獲物を狙って羽を広げる隼に似ているとして、商品名を隼にしました。
価格は、1セット6,000円で、1月から販売を始め、これまでに500個が売れているということです。
このくくりわなで、去年は長谷で800頭を捕獲したということです。
加藤さんは、ニホンジカが南箕輪村の経ヶ岳などの西山でも見られることに危機感を持っていて、今回の寄付は、そうした実情をアピールする狙いもあります。
唐木一直村長は、「村の猟友会で使わせていただき有害鳥獣から村の山や農地を守っていきたい。併せてシカ肉の活用も考えたい」と話していました。 -
南箕輪村恩徳寺のクロユリ見頃

南箕輪村沢尻の恩徳寺で、クロユリが見頃を迎えています。
先代の住職が2株から徐々に増やし、50年かけて350株ほどになりました。
現在は、200株ほどが見頃を迎えています。
今年は、例年より4日ほど遅く開花し、花は小さめだということです。
恩徳寺のクロユリは、15日ごろまで楽しめそうです。 -
大芝高原でウォーキング講座

南箕輪村の大芝高原で、10日にウォーキング講座が開かれました。
ウォーキング講座は、健康づくりの拠点として森の交流施設が去年10月に完成したことから、南箕輪村が今年度から開催しています。
10日は2人が参加し、大芝高原にあるセラピーロードの、2.5キロのリフレッシュコースを歩きました。
指導にあたった南箕輪村役場の佐藤佳代さんは、「ウォーキングをきっかけに、健康づくりに取り組んでいってほしい」と話していました。
次回は24日に行われることになっています。 -
中部保育園 こいのぼり運動会

南箕輪村の中部保育園で9日、春のこいのぼり運動会が開かれました。
園庭には、こいのぼりが飾られ園児がその下で運動会を行いました。
中部保育園は、新年度が始まってから1か月ほどし、子供たちが慣れてきた頃に、全員で体を動かして交流する機会を作ろうと毎年5月に運動会をおこなっています。
今日は、全員で体操やかけっこ、玉入れなど5種目を行いました。
4月に入園した年少園児のかけっこでは、4人から5人のグループに分かれ、元気よくスタートしていましたが、途中転んで泣き出してしまう子供の姿も見られました。
清水すみゑ園長は「元気に泳ぐこいのぼりのように、大きな心で、大きく育って欲しい」と話していました。 -
まっくんの公式ウェブサイトが完成

南箕輪村のイメージキャラクターまっくんの公式ウェブサイトが完成しました。
ウェブサイトは、去年のゆるキャラグランプリで最下位になったまっくんを応援しようと伊那市のウェブデザイン事務所が無償で立ち上げたものです。
HPには、まっくんのブログや誕生秘話、イベント情報などが掲載されています。
村では、まっくんを通して南箕輪村を広く知ってもらい、足を運んでもらうきっかけにしていきたいとしています。 -
元留学生が上農高校を訪れる

2006年に南箕輪村の上伊那農業高校に留学し、その後高校の教師となったタイ人のジャルター・インタラコンケーオさんが26日、8年ぶりに上農高校を訪れました。
ジャルターさんは25歳。
8年前、上農高校の園芸科学科観賞食物コースに7か月間在籍し、日本語や日本の農業などについて学びました。
歓迎会で塩崎正校長は「こんにちは、おかえりなさい」と現地の言葉で迎え入れました。
これを受けジャルターさんは、日本語で挨拶しました。
ジャルターさんは、難関とされている現地の教員免許の国家試験にトップで合格し、現在、国立の高校で農業やパソコンの使い方を教えています。
26日は、教え子のベンジャマース・アンネーツさんと一緒に校内を見学しました。
訪問は、留学時代お世話になった教師とジャルターさんが交流を続けていたことが縁で実現しました。
この後、慣れ親しんだ施設を見学し、当時教えてもらっていた教師に合うと、久々の再会を喜んでいました。 -
まっくんバス利用者増加

去年10月に増便された南箕輪村の巡回バス、まっくんバスの昨年度の利用者数は、増便前の半年間に比べ、増便後の半年間の方が約1,500人増加した事が、26日の地域公共交通会議で報告されました。
まっくんバスは、去年10月から2台体制となり、一日4便から5便に増便されました。
村の報告によりますと、去年4月から9月までの半年間の利用者が5,508人だったのに対し、増便後の10月から今年3月までの半年間の利用者は7,012人となっていて、1,504人増加しました。
午後に運行される第4便については4月から9月までの利用者が730人、10月から3月までの利用者が1,641人で、911人増加しています。
夕方の時間帯に新たに追加された第5便のみの利用者数は、半年間で320人、月平均にすると53.3人となっています。
唐木一直村長は、「高齢化が進む中、交通手段の確保は重要課題。これからも、より利用しやすい体制を作っていきたい」と話していました。 -
園児がシイタケの菌打ちを体験

南箕輪村中部保育園の園児は24日、大芝高原でシイタケの菌打ちを体験しました。
この日は年長園児38人が参加してナラの原木にシイタケの菌を打ち込みました。
これは、北殿区の住民有志が子ども達に地元の自然の中で思い出を残してもらおうと6年ほど前から行なっています。
子ども達は、住民有志に教わりながら、ナラの原木に開けられた穴にシイタケの菌の駒を打ち込んでいました。
北殿区の小松修一さんは「今日の菌打ちの体験を大人になっても覚えていてもらえたらうれしい」と話していました。
菌打ちが終わると、子ども達はシイタケハウスの原木に生えたシイタケの収穫も体験しました。
なお、北殿区の住民有志では、ナラの原木を手に入れるのが難しいことから、譲ってくれる方を探しているということです。(代表:小松修一さん 0265-72-9615) -
南箕輪村行政評価委員会 28事業についての検討結果を答申

南箕輪村が行っている事業について評価する、南箕輪村行政評価委員会は、28事業についての検討結果を23日、答申しました。
浄化槽維持管理組合事務事業については、必要性なしとしています。
23日は、池上昭雄委員長ら4人が南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に答申書を手渡しました。
評価は、必要性あり、要検討、必要性なしの3段階に分けられ、必要性ありが23事業、要検討が4事業、必要性なしが1事業となっています。
必要性なしとなった浄化槽維持管理組合事務事業については、他の自治体も中止傾向にあり、作業自体を役場が主体的に行うべきでないとしています。
唐木村長は「専門的な見地の中での評価なので、内容を見させていただき検討したい」と話しました。
村では、答申に対する検討結果を6月中に委員会に提示するとしています。
委員会では今年度、39事業についての評価を行うことになっています。 -
V.C.長野ジュニアチームが初練習

南箕輪村を拠点に活動するバレーボールクラブ「V.C.長野トライデンツ」のジュニアチームが21日、南部小学校で初めての練習を行いました。
この日は入団希望者も含めて12人が練習に参加しました。
VC長野トライデンツは、去年からバレーボールの国内3部リーグに参戦しているクラブチームです。
地域のバレー人口の底辺拡大やレベルの向上などを目的に、ジュニアチームを立ち上げました。
選手自ら指導にあたり、「膝を使って」「額の前に手を出して」などと説明しながらトスの上げ方を教えていました。
笹川星哉代表は「バレーがうまくなるのと同時に、バレーを好きになってもらいたい」と話していました。
ジュニアチームは毎週土曜日に南箕輪村南部小学校の体育館で練習を行う予定で、随時入団も募集しているということです。
電話 98-6812(事務局) -
南箕輪村大芝の畑で火事

南箕輪村大芝で21日、畑およそ600平方メートルを焼く火事がありました。
この火事によるケガ人などはありませんでした。
伊那警察署の発表によりますと、21日午前11時14分ころ南箕輪村大芝の畑で火事があり、およそ600平方メートルを焼きました。
この火事による、けが人などはありませんでした。
伊那署では、村内の男性がこの畑を借りて家庭ごみを燃やしていたことから、その火が燃え移ったものとみて調べを進めています。 -
白く清らかに ワサビの花咲く

南箕輪村田畑のわさび畑では、白く清らかなワサビの花が咲いています。
田畑の湧き水を利用して作られた穂高町の有賀均さんが運営する有賀ワサビ園です。
1月から2月ごろ植えたものが主となっています。
ワサビはアブラナ科の植物で、大量のきれいな水のある場所に生育が限定されます。
このワサビ畑の下流は、半沢のホタルで知られるホタルの生息地です。
ワサビは、有賀さん宅で加工して販売しているということです。 -
南箕輪村 新入社員研修会

南箕輪村商工会などは、この春村内の事業所に入社した新入社員らを対象にした、研修会を13日、村の商工会館で開きました。
研修会には、民間の企業や村の職員など、25人の新人が参加しました。
午前中は長野経済研究所の小沢廣行さんが講師を務め、社会人には積極性・責任性・規律性が大切だとして、新社会人に必要な心構えなどについて話しました。
午後は長野経済研究所の小賀阪知美さんを講師に実技研修が行われました。
参加者はグループに分かれて、電話応対などを練習しました。
開講式では、南箕輪村商工会の田中秀明会長が、「技術だけでなく、それぞれの職業に応じた道徳や常識を考え、最善を尽くして下さい」と話しました。
加藤久樹副村長は、「人も手を加えることで変わっていきます。人材の“材”の字が財産の財の字に変わるように頑張ってください。」と訓示しました。
南箕輪村商工会では、年2回新人研修を行っていて、10月にはフォローアップ研修として行われることになっています。 -
ご当地キャラ 広報啓発活動大使に任命

伊那警察署は10日、管内のご当地キャラクターを、安心安全なまちづくりを進める「広報啓発活動大使」に任命しました。
10日は、伊那警察署で任命式が行われ田中泰史伊那警察署長から任命書が送られました。
任命されたのは伊那市の「イーナちゃん」
辰野町の「ぴっかりちゃん」
箕輪町の「もみじちゃん」
南箕輪村の「まっくん」です。
これは地域住民に安心安全な街づくりに向け、地域の安全活動の普及を図ろうと任命したものです。
伊那署によると、キャラクターへの委嘱は県内の警察署で初めてということです。
4市町村のキャラクターは意気込みを横断幕で表明しました。
任命式の後、4市町村のキャラクターはそれぞれ地元の大型店などで啓発活動を行いました。
任期は来年の3月31日までとなっていて、振り込め詐欺や地域安全運動などで啓発活動を行うことになっています。
222/(日)
