-
宮田観光ホテルで14日に初のディナーショー、完売状態に
村長が社長職を兼務し、経営改革に着手している宮田村の第3セクター宮田観光開発は14日、創業以来初となるディナーショーを運営する宮田観光ホテルで開く。地元のほか、歌手目当てに全国的にもチケットが売れ、完売状態。長期債務などで村民から厳しい目が注がれる同社だが、今年度からマレットゴルフの日帰りパックを始めるなど、徐々にだがサービスに変化も生まれつつある。
「ディナーショーは地元の人にも数多くホテルを利用してもらう商品として企画した。おかげさまでほぼ売りきれ」と同ホテルの担当者。
若手歌手が出演することで、そのファンクラブへの販売効果もあったが、今後に向けて手応えもつかむ。
今年5月から社長を務める清水靖夫村長は「今までと同じではダメ。村民の皆さんにも変わったと実感してもらい、利用してもらわなければ」と話す。
同じく今年から始めた日帰りパックは、近くの村マレットゴルフ場でコンペを開き、ホテルで昼食、入浴を楽しんでもらう商品。
2回開き1回は悪天候に見舞われたが、愛好者を中心に村内外の多くの人が楽しんだ。
近年は近くの駒ケ根高原に新しいホテルができるなど、周辺の宿泊施設は競争も激化。今年は7月の豪雨の影響も重なり取り巻く環境は厳しいが、ディナーショーも活性化の一助として位置付けていく考えだ。 -
起業チャンピオン賞表彰式

創業者を対象にした「創業塾」(伊那商工会議所・上伊那地域チャレンジ起業相談室主催)の起業チャンピオン賞表彰式が8日、伊那商工会館であった。実現性が高いビジネスプランとして、市内高遠町の守屋豊さん(54)に贈った。
守屋さんは来年4月上旬、高遠町内に高遠そばの店をオープンする予定。
高遠そばは辛み大根、焼きみそ、刻みネギを合わせたからつゆで食べる伝統食で、地元産ソバを使い、自らで粉をひいて打つ。1人前を2回に分けて出し、ゆでたてを味わってもらえるよう工夫する。
「リスクがあっても悔いのない生き方をしたい」と定年を前に仕事を辞め、東京の専門学校に通ってそば打ちの基本を学んだ。開業に向けて準備中で「高遠そばは、素朴で豪快な味。いずれはソバを作るところから取り組みたい」と意気込みを語った。
表彰式で、伊藤正専務理事代行は商売繁盛を祈り、今後もフォローアップに努めるとした。
創造塾は9縲・0月の5回開き、経営コンサルタントや弁理士からマーケティング戦略や資金繰りの考え方、事業計画書の作成などを学んだ。会社員、主婦ら30縲・0代の19人が受講し、6人がプレゼンテーションした。受講生のうち、すでに2人が製造業、リンパセラピーを開業している。 -
池上明さん(50)飯島町南仲町

「地域ごとにいい味が出た。1年後がどんな味になるか楽しみ」-。上伊那8市町村がそれぞれのネーミングで12日発売する伊那谷産芋焼酎「伊那八峰」の仕掛け人である。
上伊那8市町村で焼酎に最適なこがねせんがん(1部紅あずまも)が栽培され、飯田市の酒造メーカーでし込まれ、蒸留したての10種類の芋焼酎ができ上がった。試飲し「それぞれ個性がある。熟成するともっとよくなる」と成功の手応えを感じている。
1956年町内の池上酒店の3代目に生まれ、人が集い、酒と文化の香りの中で育った。高校卒業後、カーボーイに憧れ渡米、テキサスの大学で経済学を修め、そこで妻のジェニーさんと知合い「ブラウンの目、薄茶の髪、外国人らしくない」というのが第一印象。「小柄で控えめ、大和ナデシコにアメリカで出会った」と衝撃の出会いから2年後に26歳で結婚し、帰国した。
町起しに関心が高く、商売を通して地域起しができればと 13年前からお陣屋行燈市に関わった。「昔はイベントで客を呼んだが、今は商売につながらないのが課題」とか。
飯島産の酒米を使ったオリジナルの地酒「アルプスの風」も手掛け「ふくよかな味わい、香り華やか、飲み飽きない」と、同店のロングベストセラーになっている。
ソバ栽培が盛んな同町、ソバを使って、特産品づくりをと、飯田市の酒造メーカーに依頼し、蒸留したのがそば焼酎「そばのかおり」。
8年前、宮田村新田のマルスウイスキーで、たくさんの原酒(モルト)が貯蔵されている倉を見学「宝物発見!、早速6樽開けてもらい、日本一アルコール度の高い山岳シリーズを企画した」。
芋焼酎に注目したは3年前、「伊那谷では好きな芋焼酎が手に入りにくい、それなら自分で作って見よう」がきっかけ。仲間に呼びかけ、芋づくりの助っ人「くつろぎ応援団」を組織「地域起しには子どもが一緒の方が効果的」と、飯島小学校に働き掛け、4年生の協力で完成した伊那谷初の芋焼酎「穆王(ぼくおう)」。この焼酎をきっかけに、上伊那8市町村に広がりを見せ「伊那八峰」誕生と続いた。
「次のテーマはリンゴ、ひょう害やカメ虫被害で売れなくなったリンゴを使い、酸やカルシウムを加え、健康的な飲物ができないだろうか」。米からソバ、芋、リンゴと町起しの種はつきないようだ。
現在妻と2人暮らしで、子ども3人はアメリカに留学中。将来、米国に日本酒と焼酎の酒屋を開くというワイルドな夢も持つ。 -
塚田理研用地取得契約

めっき製品製造の塚田理研工業(本社・駒ケ根市赤穂太田切、下島康保代表取締役)は本社敷地に隣接する駒ケ根市土地開発公社所有の大田原工業団地の土地約3960平方メートルを新たに取得した。6日、市役所を訪れた下島代表取締役が契約書に調印し、中原正純市長と握手した=写真。下島代表取締役は「業績も伸びてきて工場が手狭になっていたところで、今回の話はタイミングが良かった。業務拡大に備えての取得だが、当面は緑地として活用していきたい。将来は工場と従業員の駐車場としたい」と話した。市は条例に基づき用地取得額の10%、530万円を補助する。04年3月に販売を開始した同団地(総面積12万1900平方メートル)はトーハツ、トヨセットに続く今契約で完売となった。
同社は1963年創立。資本金3千万円。06年度の予想売上は42億1千万円。 -
SPF種豚センター分娩離乳舎がしゅん工

中川村片桐の種豚「ハイコープSPF・F1」を生産するJA長野経済連SPF種豚センターの分娩離乳舎が完成、7日、現地で経済連やJA上伊那、県、村、地元など関係者24人が出席し、喜びのしゅん工式を行なった。稼働開始は1月初旬の予定。
木造平屋建て、面積1077・8平方メートル、南北14・2メートル、東西79メートル、分娩房、離乳房、飼料庫、機械室など。電熱ヒーターや送風設備、自動給餌、給水システムを備えた。分娩房は妊娠末期の親豚66頭収容、踏み潰しなど事故防止のため子豚と分離。帝王切開で取り出した子豚は生後24、25日で離乳させ離乳房へ。雌雄を分け、雌は離乳房で約2カ月飼育された後、前期、後期育成豚舎で育成し、約5カ月体重百キロ前後で種豚として、県内外の農家や施設に出荷される。出産は年約2・5回。SPFとは「特定の病原菌のいない」の意味。
同センターは92年に全国初の「ハイコープSPF・F1種豚」の生産供給施設として建設されたが、02年11月に豚舎2棟を焼失。05年8月残存施設で事業再開。今年4月、全農肉豚150万頭構想を踏まえ、事業拡大が決定した。
) -
コニカミノルタの重合法トナー生産増強のための第3工場が南信パルプ跡地でしゅん工

コニカミノルタビジネステクノロジーズ(木谷彰男社長、本社・東京都)の投資を受けて新工場の建設を進めていた生産子会社・コニカミノルタサプライズ(本社・山梨県甲府市、原田義明社長)の第3工場が4日、辰野町の南信パルプ工場跡地にしゅん工した。
電子複写機用資材やレーザープリンター用資材などの製造・販売で世界展開をしている同社は2000年、高速機などでも高密度・高画質な印刷を可能とする「重合法トナー」新らたに開発。山梨県の第1、2工場で生産を進めてきた。しかし、市場拡大に伴い両工場の最大年間生産能力である約8千トンに需要が近づき、今後の需要増も見据えて昨年9月から新工場の建設に着手。水資源が抱負で第1、2工場や八王子市の開発拠点から距離が近い辰野町を選んだ。 投資規模は約75億円。土地面積は約4万5500平方メートル、延べ床面積は6418平方メートル。主には、今後事業拡大を狙う軽印刷市場で導入を進める「新開発重合法トナー」の生産を担う。操業開始時の従業員は約30人で、約3分の1は地元者を採用している。技術移転の期間は甲府工場の従業員が行き来し、その後も、技術、保全、生産管理機能などを最大限共通利用することで人員の効率化を図る。
本格的な量産開始は来年1月の予定。 -
山ぶどうワイン祭りに500人余

宮田村の特産品山ぶどうワインの新酒解禁を祝う「中央アルプス山ぶどうワイン祭り」が3日、新田区の本坊酒造であった。この日発売の村内産の山ブドウ「ヤマソービニヨン」で造ったヌーボータイプワイン「紫輝(しき)」が無料で振舞われ、来場者は出来たての新酒の味と香りを堪能した。品種名のヤマソービニヨンを記した新ラベルの披露もあった。
好天に恵まれ、村内外から500人余の家族連れが訪れ、マスのくんせいやチーズ、焼き鳥など村内の各種団体や有志が用意したおつまみを食べながら、新酒を心ゆくまで味わった。
祭りは栽培農家や村、醸造元の本坊酒造などでつくる「山ぶどうの里づくり推進会議(会長・清水靖夫村長)」が主催。「紫輝」の解禁に合わせ毎年開き、今年で7回目。
清水会長は「7月の天候不順の影響が心配されたが、酸味と糖度のバランスの良いワインになった。多くの人に飲んでほしい」とあいさつした。
村内から訪れた男性は「山ブドウ独特の味、香りもいい」と話していた。
「紫輝」は上伊那を中心に約6000本出荷。酒販店で1本(720ミリリットル)1900円で販売。 -
新・ス名物丼・スのふるさとCMが入賞

県内各地から93作品の応募があったふるさとCM大賞NAGANO(長野朝日放送主催)の最終選考が3日行われ、宮田村商工会青年部が名物丼開発をコミカルに演出収録した「信州宮田・ス丼ぶり物語・ス」が企画賞を受賞した。一昨年大賞の飯島町が演技賞、駒ケ根市も味覚賞を獲得するなど、16の入賞作品のうち3作品を伊南地域で占めた。
村民からアイデアやレシピを募り、名物丼の開発に取り組む宮田村商工会青年部。
2日に新名物丼「鶏の山ぶどう酒煮丼」を発表したばかりだが、そのPRも兼ねようと、3年ぶりにふるさとCM大賞に応募した。
CMには、丼をアピールしようと誕生した「どんぶりレンジャー」が出演。部員が自ら演出、カメラをまわし、名物丼の誕生を楽しく伝える内容に仕上がった。
3日に長野市で開かれた最終選考には、部員扮するどんぶりレンジャーが新名物丼とともに会場へ。
CMを見てもらうだけでなく、審査委員で作家の内田康夫さんらに試食してもらった。
味、映像、パフォーマンスいずれも好評で、委員のひとりで辛口評論で有名なやくみつるさんも絶賛。
審査委員全体からも「周辺の丼に負けないという意気込み、企画がCMによく現れている」と評価を受けた。
前林裕一部長ら青年部員は「名物丼にもさらに弾みがつく」と大喜びした。
飯島町の作品は「おそるべし越百の水」。3人の子どもたちが主人公で「子どもたちが頑張り、演技、演出ともに良かった」と評価を受けた。
両町村と駒ケ根市の「くせになりそー」の3作品は、来年1月下旬から8月にかけて長野朝日放送で30回放映。34作品による最終選考の模様は1月8日午後3時半から放送する。 -
商工会青年部歳末慈善パーティー

宮田村商工会青年部(前林裕一部長)は2日夜、第41回歳末慈善パーティーを村民会館で開いた。約300人が集まり、恒例のオークションや抽選会。2人の人気お笑い芸人によるモノマネショーもあり、年末の忙しさを一時忘れて楽しんだ。
会場には新名物丼・ス鶏の山ぶどう酒煮丼・スをはじめ、美味しい料理などで青年部員が来場者をもてなした。
多彩なものまねでおなじみのホリさんとイジリー岡田さんは楽しいショーを展開。
2人は引き続き開いたオークションにも登場し、会場を爆笑の渦に巻き込んだ。
楽しみながら競り落とす来場者に、鋭いツッコミも。「来年もぜひ呼んでほしい。テレビですきがあれば、宮田って叫びます」とも話し、会場を喜ばせた。
同青年部はパーティ収益金のうち33万8600円を、村へ寄付する。 -
宮田の名物丼は・ス鶏の山ぶどう酒煮丼・スに決定

宮田村商工会青年部(前林裕一部長)が村民から幅広くアイデアやレシピを募り、半年かけて選考した同村の・ス名物丼・スに、「鶏の山ぶどう酒煮丼」が決定した。10月の村商工祭で行った食べ比べ投票の結果を基に選び、2日開いた青年部歳末慈善パーティーで披露。今年度中に青年部所属の数ヵ所の飲食店で発売する予定で、今後はさらに拡大し、名実ともに村の名物として広めていく考えだ。
村内産の山ぶどうワインをふんだんに使い、鶏肉にしみ込む味わいが絶妙な酒煮丼。数回の選考の後に行われた「地ビール丼」との食べ比べでも、試食した地域の人たちの支持を受け、公募169点の頂点に立った。
アイデアを考案した町1区の学生、池上智絵さん(20)は「ボリューム感と、他にはないものとして村の名物ワインを組み合わせてみた。これを契機に、宮田の味が広がれば」と期待を寄せる。
慈善パーティでは今までの経過を報告し、華々しく発表。来場者がさっそく試食し、新名物の誕生を祝った。 -
伊那商工会議所で情報化の実態を把握
伊那商工会議所は、情報化の実態を把握するアンケートの結果をまとめた。それによると、メール活用は全体で74%であることが分かった。
アンケートは商業、建設、工業、観光接客など全会員1800人が対象で、150人が回答した。
アンケートは、会社で利用している情報機器や活用状況など4項目。商議所から会員への情報伝達の手段は封書やファクスだが、新しい手段で情報を迅速に提供したり、メール活用が可能な環境を構築できるかどうかを探った。
メールの利用状況は情報通信業、工業、理財部会がほぼ100%だが、観光接客業、商業は50縲・0%にとどまり、業種や従業員数によって差が出た形。利用しない理由としては▽必要がない▽使い方が分からない▽パソコンを持っていない竏窒ネどが挙がった。
また、商議所からの情報配信について「メールでよい」が半数以上を占め、10%に満たなかった「よくない」を上回った。「どちらでもない」は40%近くで、メールの利便性を理解してもらうことで、上昇するとみている。
来年1月中旬には、県経営者協会上伊那支部と一緒に、インターネットやメール活用のための研修会を開く。情報化の推進に役立て、事業効果を上げる。
経協が昨年度、調査したブロードバンドやITシステムの構築・活用状況の結果から「上伊那の企業のIT(情報技術)利用に対する「現状満足度」は県内トップで、高い関心を示している結果と同じだった。 -
ワークショップ経営セミナー(5)
県経営者協会上伊那支部情報委員会など5団体は24日、飯田市の飯伊地域地場産業振興センターで経営改善研究会「第5回ワークショップ経営セミナー」を開いた=写真。
ワークショップ経営は、方針や目標の管理を小単位の「ショップ」に任せ、生産性の向上や採算性の改善などを図り、企業の体質強化につなげる方法。
下伊那の中小企業5社、10人余が出席し、伊那テクノバレー地域センターコーディネーター明石安弘さんから、部下を統率して経営目標を達成するショップ長の職務遂行能力基準の位置づけや賞与との関連など説明を受けた。
明石さんは「実力主義を強化しなければ、不公平感が出て、企業の活力の低下を招く」と社員教育の重要性を含め、成果が人件費を上回る人事制度の考えを示した。
また、参加企業が作成した「職務能力基準」(試案)の紹介もあった。
参加した飯田精機=下伊那郡喬木村=の林敏郎社長は「ショップ経営は成果があると判断している。収支状況を把握し、部門ごとに改善を進めたい」と話した。
セミナーは、経協の会員事業所を対象に、ITを活用した経営改善アンケートの結果を受け、経営改善の実践に生かそうと初めて企画。製造業の経営者や製造現場の責任者など6社が参加し、7月から5回、現場を視察したり、ショップの編成方法などを学んだりした。
セミナーは今回で終了するが、飯伊地域地場産業振興センターは12月、下伊那の参加企業を対象に、経営改善研究会を立ち上げる。各企業の実態に合わせ、ショップ経営を取り入れた経営改善を進める。
経協などは、ソフト開発など支援の必要があれば協力するという。 -
石田忠義さん(39

4月29日オープンしたほんもの体験型オートキャンプ場、「キャンプファームいなかの風」の管理人を務める。「オープンから半年余、今までに千人以上が利用した。リピターも多く、半年間に10回も来ていただいた人もいる」と盛況ぶりを。
1967年横浜市生まれ。結婚して東京で生活していたが「田舎暮らし」に憧れ、妻の友人が駒ケ根市に住んでいることや、伊那市長谷に親せきがあることなどから、Iターンを希望し、長野県を中心に、求人、不動産情報を調べた。駒ケ根高原のこまくさ橋からの景観がすっかり気に入り、駒ケ根市近辺を集中的に探した。
「自然の中で働きたい」という希望にぴったりのキャンプ場管理人の仕事を見つけ、4月1日、同キャンプ場を開設、運営する辰巳屋建設環境事業部に入社し、オープン準備を進めた。
オープンから半年余。利用者は愛知県が半分、県内は10%程度。「いなかの風」のHPや、アウトドアブランド「スノーピーク」のHPに「いなかの風」が紹介された反響も大きかったという。
また、1度利用した人が、友人や知人、職場の同僚に紹介したりと、口コミで知り、訪れる人が多いのが最近の傾向とか。
来場者は自然の棚田を利用した広大なキャンプサイト、息をのむ中央アルプスの眺めに感嘆の声を上げ、設備の清潔さにも感心するという。
「キャンプ場には風呂はいらないというイメージがあったが、展望露天風呂、ドラム缶風呂が好評で、町内の入浴施設の割引券を出しているが、利用はほとんどない」。
里山の自然体験として、米づくりやマウンティーンバイク、モトクロッサー、ダッチオープンでパンづくり、ストーンペイントなど14プログラムを用意。特にファミリーに人気があるのはモトクロッサー。2時間もあれば、初めての子どもでも乗れるようになる。家族連れからカップルまで幅広い利用者に好評なのが、ダッチオープンを使ったパンづくり。中にはパンを作っている間に、生のコーヒー豆を焙煎し、本格コーヒーを入れて、パンと一緒に楽しむ人もいるとか。
10月8、9日は30人余が稲刈り体験し、来年は田植えから1年間を通じての米づくりを計画する。
キャンパーズファームにはナスやトマト、、キュウリ、インゲンと15種類の夏野菜が育ち、無料で提供される。地元の人から柿など果物の差し入れもあり、思いがけないプレゼントが利用者を喜ばせている。
「このすばらしい景観の中で仕事ができ、訪れた人たちといろいろな話ができて楽しい。地元の人たちもなにかと気を配っていただきいている。こんな素敵なキャンブ場はほかにない」。
妻と2人暮らし(大口国江) -
飲酒運転防止に夜間バス検討を
宮田村商工会と同村議会との懇談会は27日、商工会館で開いた。商工会側は、飲酒運転防止と地域活性化の両面から、夜間に村内でバスを運行できないか提案。村や議会などと一緒に研究していきたいと投げかけた。
夜間バスの運行は、以前に同商工会で研究しようと試みた経緯がある。
当時は夜の中心商店街を活気づける観点だったが、最近になり飲酒運転が全国的な社会問題として大きく取り挙げられ、懇談会で再び議題に乗せた。
「経費面など単純に結論が出る話ではない」(関係者)が、懇談で前林善一商工会長らは商工会としても前向きに研究していきたい考えを示し、村側の協力も求めた。
懇談会は商工会役員、村議会産業建設委員会の約30人が出席。商工会各部会が各業種の厳しい現状を説明したうえで、村や議会に理解と協力を要請した。
建設部会は「工事数が減り続け厳しい。国や県の補助を積極的に活用して、新規の公共事業を充実してほしい」と要望。
商業部会は権兵衛トンネル開通による村の経済活性化策、工業部会は新製品開発の支援などを求めた。
他に、「村が物品などを購入する場合、村内業者が受注に参加できるよう配慮を」と意見も。商工業にとらわれず、若者の結婚対策、地域活性化のための住民組織強化なども提案した。 -
ニシザワ文芸コンクール表彰式

ニシザワ(本社伊那市、荒木康雄社長)の第3回文芸コンクール表彰式が26日、伊那市生涯学習センターであった。小・中学生の部の優秀賞以上にそれぞれ表彰状と副賞の図書カードを手渡した。
コンクールは、同社が書店として創業、04年の80周年を記念して原点に戻ろうと始まったもの。小・中学生を対象に、読書感想文を募集したところ、今回は640点(小学生の部376点、中学生の部264点)が集まった。「命」を題材にしたものが多かったという。
小・中学校の教諭らが▽本の内容が分かりやすく表現されているか▽読んで参考になったことが書かれているか竏窒ネどを基準に審査。小学生の部で最優秀賞2点、優秀賞8点、佳作29点、中学生の部でも2点、6点、31点を選んだ。
表彰式で、荒木社長は「本を読みながら感じる心を相手に伝えるものだった。コンクールを機に、本を好きになって心が豊かになることを祈念する」とあいさつした。
入賞者は次の通り。
◇小学生の部▽最優秀賞=佐々木杏菜(赤穂2)池田真由子(赤穂東6)▽優秀賞=小牧知世、田路悠太(富県6)水上朝比(赤穂東2)花木彩香(赤穂東4)久保田慧(伊那東6)斎藤咲恵、白崎莉玖(赤穂2)秋山龍矢(箕輪東3)▽佳作=おおくぼあかね、伊藤真衣(伊那3)小松航(伊那北5)山岸裕也、諸田千鶴、杉本結衣(伊那北6)中村可奈(西箕輪5)寺沢徳子(新山5)平岩なつみ(富県6)有賀千佳(西箕輪3)宮下昇也(赤穂南5)宮下しゅうへい(赤穂東2)有馬優衣、平沢奈津美、北原紗良、六波羅理子、平沢壮太郎、唐沢拓也(伊那東5)小町谷たくみ(赤穂2)小山田好希、原田佑佳(赤穂3)園原綾菜、芦部さやか(赤穂5)横前ひかる(箕輪中部2)上條しょうた(箕輪東3)辰野茜(宮田5)やましたのえ(長谷1)市村渉(飯島4)城田理香(飯島6)
◇中学生の部▽最優秀賞=若林麻衣(東部2)松崎伸哉(赤穂3)▽優秀賞=山岸将暉(東部1)大島優佳(宮田2)神航平(西箕輪3)森田貴裕(伊那1)井口悦美(駒ケ根東3)内堀麻由美(箕輪3)▽佳作=翁大次郎、中村瑞穂(東部2)広田安優美、田代宗一郎、高橋優莉亜、樋屋真莉菜、馬場和香子(東部1)藤原弘樹(東部3)池上真奈、田辺澄、小田切ひかり、伊藤俊一(宮田3)下村沙希(宮田)桐山明日香、米山陽子(宮田2)石井那苗、沢田理沙、飯島啓介、矢沢優(宮田1)浦野森音、唐沢慎二(西箕輪2)唐沢彩佳、浦野あおい、鳥羽定徳(西箕輪)小島のどか(西箕輪1)久保田はるか(伊那2)泉祥衣(伊那)竹村瞳(駒ケ根東3)山内さなえ(駒ケ根東2)鈴木里彩(南箕輪3)倉田萌(南箕輪2) -
伊那食品工業がグッドカンパニー大賞を受賞

伊那市西春近の伊那食品工業(塚越寛代表)がこのほど、経済的、社会的に優れた成績を上げている中小企業として中小企業研究センターの「グッドカンパニー大賞」に選ばれた。塚越会長は「全国で1社しか選ばれない賞に選ばれたことは伊那谷にとっても名誉なこと。利益だけでなく、社員を大切にする姿勢や教育やまちづくりに貢献する事業展開などが総合的に評価されたのだと思う」と喜びを語った=写真。
今年で40回目となるこの賞は、歴史と実績のある中小企業の栄誉を称えるために1967年から始まったもの。経済産業省、文部科学省、商工会議所、中小企業投資育成会社の推薦をもとに、年に一度、全国の中小企業の中から大賞1企業と、優良企業賞、特別賞などを選出する。これまでに選出してきた約500社の中には、京都セラミック(現在の京セラ)をはじめ、有力企業に成長した企業も多い。
寒天で国内市場の8割、世界市場の2割を占める同社は▽無理な成長を避けた安定的成長基盤の実現▽社員を尊重した会社運営竏窒ネどに取り組んでいる。また「人を幸せにすることが企業の役割」として、環境整備、メセナ活動の実施、教育支援などに積極的に取り組み、地域貢献を果たしている。 -
高遠町商工会優良従業員表彰式

伊那市の高遠町商工会(森本光洋会長)は26日、優良従業員表彰式を高遠さくらホテルで開き、町内の事業所へ長年勤める従業員などを表彰した。
町の商店街の活性化に貢献している町内での勤務者に、今後の励みとしてもらうことなどを目的して5年に1度ずつ行っている取り組み。今年は、商工会に所属する11事業所の38人が表彰を受けた。
森本会長は「みなさんは高遠の商店や高遠町にとって大切な存在。町と商店を明るくするために、今後も力添えをしてほしい」とあいさつ。その後、各企業の代表者が前に進み、表彰を受けた=写真。
表彰は次のみなさん。
春日三郎、前田裕敏、田中喜美子(以上仙醸)猪俣治、藤木秀康、小岩井由道(以上ウッドレックス)伊東さち子、森本千史(以上森本洋品店)福沢初子、古旗勝美、内山久子、草野留美子(以上赤羽菓子店)北原順一、西沢正勝、柳田六十四、塩原努、藤原彰二、滝沢進、松浦昭雄、北原忠三(以上阿部組)竹内治、伊東忍、向山三人女(以上北條商店)池上美枝子、伊藤里美、兼子透(以上山高産業)田辺照美(北條商店)伊藤いく子、守屋育郎(以上丸繁木材)湯沢房子(タスマン伊那高遠工場)伊藤さだ子、北原光治、北原興四郎(以上山一建設)遠藤覚、有馬久司、山崎芳文、小松武、北野智子(以上ヒットビジネス) -
「きもの着方教室&ランチ」を企画 牧田広利さん(43) 伊那市
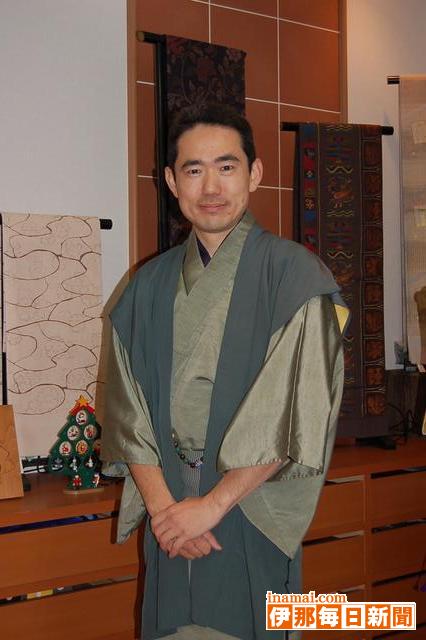
00年に父が亡くなり、1924(大正13)年に創業した染織店を継いだ。03年11月には、伊那市の駅前再開発ビル「いなっせ」のオープンと同時に、大型店から「いなっせ」1階へ店舗を移した。
大学卒業後、東京都の大手呉服ナショナルチェーンで6年間、販売を中心に修業。いかに売るかが求められた。商売をする上で大事なことだが、多くの人にきものを楽しんでもらいたいという思いがあった。
「女性に『きものは好きですか』と尋ねると『好きです』と答える。『着ますか』と聞くと『着ません』という」。その理由は▽着方や手入れ方法が分からない▽きものを着て、出かける場所も、機会もない▽礼儀作法を知らない▽ヘア、メイクがめんどくさい竏窒ネど。それを1ずつ取り除き、自宅に眠っているきものを楽しむ機会を作ろうと「きもの着方教室&ランチ」を企画した。
05年5月からこれまでに36回開き、延べ120人が参加。上伊那を中心に、郡外からも申し込みがあるほどの反響だ。年齢層は若者、子育て中の母親、年配者らと幅広く「きものを着るのは成人式以来」「きものは母、祖母のもの」…という女性が集う。
講師の美容師に手伝ってもらいながら、参加者一人ひとりが自宅から持ち寄ったきものを自分で着る練習をする。季節に応じ、浴衣も指導。中には、10回通い「徐々に着られるようになった」と喜ぶ参加者もいる。
きものを着たあとは、周辺の飲食店で昼食を食べる。きもの姿で街中を歩くだけで、華やか。地域の活性化にも一役買っている。
「きものは簡単に変身することができ、気分転換にもなる。同じまちも違って見えると思う」と話す。
「きものは値段が高いというイメージがあるけど、安くても楽しめる方法はある。礼装に比べ、カジュアルはブローチを付けるなど個人の感性で着こなしができる」と提案。きものを気楽に、気軽に楽しんで着る習慣のきっかけになることを期待する。
男性にも、きものを着る機会を設けたいと考える。
また、正月に成人式を開く高遠町・長谷と合併したことを機に「成人式を正月に開いて、きものを着てほしい」と住民から気運が盛り上がるよう願っている。
(湯沢康江) -
南箕輪村商工会女性部40周年記念式典

設立40周年を迎えた南箕輪村商工会女性部は23日、記念式典を商工会で開き、40年の歩みを振り返り、節目を祝った。
女性部は講演会、一人暮らしのお年寄りに手作り弁当の配布やマレットゴルフ交流、サツキ植樹作業、簿記や帳簿の勉強、料理健康の研修、趣味講座、パソコン勉強会など熱心に活動してきた。
記念事業は、記念誌をパソコン教室が作成し、式典会場は絵手紙など趣味の講座の作品を展示、祝賀会料理は料理・漬け物教室が準備するなど、これまでの活動を取り入れ手作りした。
記念事業の柴親子実行委員長は「自分を磨くため、女性部が女性部であるため、頑張っていきたい」、女性部の後藤幸子部長は「これから40年、今日からまた皆さん一緒に歩み始めましょう」とあいさつした。
記念事業で「歌のつどい」も村民センターで開いた。歌手として活動する神谷ありこさんを招き、南箕輪小学校と南部小学校の合唱部も参加し、ふるさとの歌をうたって交流を深めた。 -
まちじゅう美術館表彰式

伊那市内の保育園児を対象にした「第5回まちじゅう美術館」(伊那商工会議所・商業連合協議会主催)の表彰式が23日、商工会館であった。市内49店舗で12月25日まで、応募作品691点を飾っている。
「まちじゅう竏秩vは、商店街に園児の絵を飾る取り組み。「わたしの好きなお店」「わたしの家族」をテーマに、高遠町・長谷を含む32保育園・幼稚園の年長児が伸び伸びと書いた作品が集まった。
式で、会頭賞5点、副会頭賞10点、部会長賞20点の入賞者を一人ずつ表彰。
向山公人会頭は「権兵衛トンネル開通で、木曽の人にも見てもらえるのではないかと思う」とあいさつし、元気なまちづくりへの参加を呼びかけた。
応募作品は飲食店、理・美容店、衣料品店などのウインドーや店内に飾られ、歩道からも見ることができる。園児が絵のある店に行くと、メダルなどがプレゼントされる。 -
ソースかつ丼売上寄付

10、11月に下諏訪町で開かれたイベント「しもすわうまいもん市」に参加した駒ケ根商工会議所青年部(倉田勇会長)は21日、イベントで販売したソースかつ丼などの売上の一部1万5千円を駒ケ根ソースかつ丼会(下平勇会長)に寄付した=写真。倉田会長はイベントでのソースかつ丼の売れ行きについて「すごく好評でびっくりした。ほかのテントには客がいないのに、うちだけ長い行列ができたほどで、たちまち売り切れで困った。駒ケ根名物としての認知度も高く、今後の展開にも大きな期待が持てる」などと報告し、ソースかつ丼会の会員らを喜ばせた。
-
南箕輪村「まっくんファーム」設立総会
集落営農組織の南箕輪村「まっくんファーム」の設立総会が20日、村役場であった。加入者505人のうち450人の出席で、組合規約承認、役員選任など14議案を原案通り可決し、設立した。
「まっくんファーム」は加入者505人、加入面積274ヘクタール(水田265ヘクタール、畑9ヘクタール)。役員に組合長、副組合長、会計、監事を置き、専門部として総務、企画、作業の各部を設ける。11支部あり、組合員10人前後で班を編成。それぞれ支部長、班長を置く。
主な事業は、組合員が供した農用地での稲作、麦作、大豆、ソバ作などの農業。組合員はこれまで同様に自分の農地は自分で経営する。経理は一元化。出資は1人当たり千円。
06年度事業計画は、組合の体制作り、07年産麦作の共同事業など。06年度は種の小麦栽培面積は23ヘクタール。
組合長に選任された倉田庄衛さんは「皆さんのお知恵をいただき、スムーズにまっくんファームが進むよう一緒にやっていきたい」とあいさつした。
役員は次の皆さん。
▽組合長=倉田庄衛▽副組合長=原英雄、木下尊英、田中実▽会計=征矢誠之▽監事=唐沢俊次、五味一廣 -
三洋グラビア人事
三洋グラビア(本社・伊那市)は21日、臨時株主総会を開き、新役員を選任した。
営業、生産、管理、経理、経営企画の責任体制を拡充、各工場の製造部長級には執行役員制を導入し、責任と権限を強化した。
同社では「新体制により、顧客ニーズに従来以上に俊敏に対応できる生産体制を構築し、さらなる飛躍を図る」としている。
新役員は次の通り。
▽代表取締役会長=原章▽代表取締役社長兼営業本部長=原敬明▽常務取締役兼生産本部長=和久田佳秀▽常務取締役兼管理本部長=矢野和雄▽常務取締役兼経理本部長=原貴子▽取締役経営企画室長=鈴木弘男▽取締役営業部長=中村秀人▽執行役員第一製造部長=有賀達彦▽執行役員第二製造部長=薮原芳信▽執行役員第二製造部長=田畑義幸▽執行役員第三製造部長=小松道雄 -
勝山織物飯島きぬの里、志村明代表(53)、

飯島町飯島の勝山織物飯島きぬの里は、代表の志村明さんを中心に、釜田友紀さん、秋本賀子さん、永長ゆう紀さんの4人で、養蚕から、製糸、織まで一貫して、絹織物を生産する全国的にも、ほかに類をみない工房だ。
きぬの里が町内の空家を借り、生産をスタートしたのは4年前。 4人の出会いは、さらに数年遡り、志村さんが10年間、講師を務めた愛媛県野村町(現西予市)の野村シルク博物館の染織講座、繭からの糸づくり、染色、手機織りまでに全工程を習得し「シルクにかかわる仕事をしたい」と、意気投合した。
野村町はかつて西日本有数の養蚕地帯だったが、湿度が高いため、糸の節が上がりやすく、絹織物生産には最適とは言えなかった。 自然環境のいい場所で絹織物を続けようと、場所を探した。湿度が低く、歴史的に良質な繭が生産されていた蚕飼いの里、伊那谷に着目し、飯島町の空家を借り、生産拠点を構えた。空家は改修が必要なため、京都西陣の勝山織物の資金提供を受け、3年前から本格稼働を開始した。蚕を飼い始めたのは2年前から。かつて養蚕地帯だった飯島町も、繭価格の低迷や後継者不足、安価な輸入品や化学繊維との競合に勝てず、養蚕農家は激減、今では1軒だけ。
「このままでは、最高品質の繭を生産する日本の養蚕の技術、道具など全てが無くなってしまう。まず、自分たちが使う、良質の繭を自分たちで生産しよう」と、県新規就農里親研修制度を利用し、以前、養蚕をしていた宮沢八千代さんに指導を受けた。
赤坂で桑園4アールと蚕室用にハウスを借り、春、夏、秋の3回、合わせて7箱を飼育、成長、脱皮を繰り返し、約8センチに生育、体が透き通ると、まぶしに入れる。糸を吐き出し、数日で繭になる。
生産した繭は冷蔵したり、長期保存するために約1週間塩漬けした後、座繰器を用い、糸を引き出し、枠に巻き取る。天然染料で染め、経糸の長さをそろえ、機に掛け織り上げる。
織り上がった布は、湯通し、天日干し、さらに木槌で叩いて風合いを出す。製糸から仕上げるまで、最低でも1カ月から1カ月半かかるとか。
秋本さんは「蚕の個体差が大きく、おやといなどのタイミングが難しいが、繭は節が上がり難く、格段に品質の良い繭が出来た」と話す。
代表の志村さんは「着物産業が縮小する中で、素材を重要視し、最高品質の物を作りたい、需要は少ないが、必ずある。日本から養蚕がなくなることは、日本では最高級の絹織物が出来なくなること。『なくしていいのか』という危機感もあった。養蚕から、織りまで全工程を行なうことで、時代の変化を回避できるのでは」と話す。 -
歳暮商戦 12月第1、2土・日曜日がピーク

12月を控え、大型店などで歳暮商戦が繰り広げられている。
ベルシャイン伊那店は1階に特設コーナーを設け、ふるさとギフト(漬け物、そば関係)、ハム、食用油、菓子、酒、洗剤などカタログ分を含め1200点と昨年並みの品数を用意。「安心・安全ギフト」では、国産原料などにこだわった米、しょうゆなどをそろえている。
人気の商品は、地元の農家と契約したリンゴ「サンふじ」をはじめ、食用油、コーヒー、ハム、新巻鮭など。売れ筋は4千円前後で、中元に比べて高めという。
ピークは12月の第1・2土・日曜日の見込み。
平日でも、夫婦などが「慌しくなる前に」と来店し、豊富にそろった商品を品定めしている。
歳暮は、正月祝いの準備を始める12月13縲・0日ごろに贈るといわれるが、11月下旬から贈る人もいるそうだ。 -
えびす講青空市
宮田村の仲町商栄会と村商工会は19日、恒例のえびす講青空市を津島神社境内で開いた。宝投げやくじ引きのほか、商店主協力による露店も盛況。歳末商戦に向けて弾みをつけた。
商工会青年部が始めたのがきっかけで、30年ほど続く青空市。この日は小雨も降る天候だったが、多くの人が・ス商売繁盛・スを祈願するえびす講の雰囲気を味わおうと訪れた。
熊手など縁起物を求めたり、くじ引きで運試ししたり。露店めぐりも楽しんでいた。 -
光の街並み今年も
中心商店街、店主らが飾り付け
宮田村の中心商店街が来年の2月3日まで光のイルミネーションに包まれる。宮田村商工会商業部会(宮下進八郎部会長)、同夢づくり委員会(中谷俊治委員長)の主催。仲町、河原町、駅前の数百メートルに及び、19日夕の一斉点灯を前に各商店主らが飾り付けに追われた。
冬場の街並みを明るくし、商店街を活気付けようと毎年企画。街路樹などに100本を超えるイルミネーションを施した。
協力して作業に汗を流した商店主たちは「地域の元気につながれば」と話した。 -
未来技術セミナー

地域の産業を支援する県テクノ財団伊那テクノバレー地域センター(向山孝一会長)は17日、21世紀未来技術セミナーを駒ケ根市の駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた。南信各地の金属加工企業経営者や技術者など約50人が集まり、「鍛造・金属プレス加工の最新技術動向」をテーマにした講演2題を聴いた。参加者は時折メモを取ったりしながら、専門的な内容の講義に真剣な表情で耳を傾けていた=写真。
独立行政法人産業技術総合研究所デジタルものづくりセンターの加工応用技術研究チーム長で工学博士の大橋隆弘さんは「鍛造・金属プレスに関連する技術戦略と新加工技術の動向について」話した。大橋さんは経済産業省の指針などを示しながら「日本の製造業の国際競争力向上のためには、大企業を支えている中小企業のものづくり技術の高度化が不可欠だ」と訴えた。
山梨大大学院工学総合研究部助教授で工学博士の吉原正一郎さんは「マグネシウム合金の将来予測とプレス加工」について話した。 -
旭松食品中間決算
旭松食品(本店・飯田市)は16日、07年3月期中間決算を発表した。
納豆部門が好調に推移したことから連結売上高は87億1千万円(前年同期比2・4%増)、経常利益は固定費削減などで前年同期より30・1%増の5700万円。中間純利益は300万円となった。
部門別売上高は、凍み豆腐部門が21億9600万円(前年同期比3・4%減)、加工食品部門が20億4400万円(同5・3%増)、納豆部門が35億6700万円(同5・5%増)など。
通期予想は、売上高183億円、営業利益、経常利益ともに2億7千万円、当期純利益1億2千万円を見込む。 -
まちじゅう美術館の審査で入賞35点決まる

伊那商工会議所・商業連合協議会は16日、伊那商工会館で「第5回まちじゅう美術館」の審査会を開いた。会頭賞をはじめとする入賞作35点を決めた。
まちじゅう美術館は、商店街に市内の保育所・幼稚園年長児から募集した絵を飾る取り組み。「私の好きなお店」「私の家族」をテーマに、32保育園・幼稚園から691点が集まった。市町村合併で、高遠町・長谷にも呼びかけたため、前回より115点多かった。
審査には主催者役員、地元の洋画家須沢重雄さんの10人が当たり、子どもらしく伸び伸びと表現できているかを基準に見て回った。
「好きな店」は食べ物屋さんが人気で、ふわふわのおいしいパン、赤やオレンジ、黄など色鮮やかな花、棚にずらりと並んだ本など個性あふれる作品がそろった。クレヨンや絵の具などのほか、折り紙をはり付けた作品もあった。
表彰式は23日、伊那商工会館で開く。
応募作品は23日縲・2月25日、伊那地域の中心商店街に展示。例年、年末年始にかけていたが、各店で正月の飾り付けがあるため、クリスマス商戦までとした。
主催者は「子どもたちのかわいい絵が並ぶ。美術館めぐりをしながら、買い物や飲食を楽しんでほしい」と呼びかけた。
入賞者は次の通り(敬称略)。
▽会頭賞(5人)=うしくなおと「ぼくのすきなおみせはほんやさん」(富県北部)ふくよちさき「かぞくでたのしいおふろだよ!」(緑ケ丘)ふくざわはるや「かぞく」(上の原)とのうちたくと「かわいいあかちゃんがたのしみなかぞく」(西春近北)たばたかすみ「わたしのすきなケーキやさん」(富県南部)
▽副会頭賞(10人)=いずみみゆう(伊那北)ゆざわゆう(高遠第四)みやじままき(つくしんぼ)こばやしゆうすけ(伊那西部)ほんだりかるどきよし(上の原)のじゆき(緑ケ丘敬愛)こまつものか(西春近南)すずきももこ(伊那)きゃくのふう(天使)なかむらさゆき(東春近中央)
▽部会長賞(20人)=かにさわけいた(大萱)まきたとしあき(手良)みさわまゆう(伊那北)みやざわりく(美篶東部)はしづめしえみ(西春近中央)かわしまやまと(西箕輪南部)きりやまゆりこ(西箕輪北部)おおぐちめい(長谷)おのとぎそういちろう(竜南)ほそのしゅんいち(伊那東)いのうえまゆか(新山)むかいやまあやめ(竜北)くさのゆうじ、あおきやまと(竜東)はしもとさき(美篶西部)ふくはらたつや(高遠第一)きたはらひろゆき(高遠第二)(竜東)やまぎしゆりな(美篶中央)たなかみゆき(東春近南部)ながたげんき(竜西)
262/(木)
