-
箕輪町経営研究会が新春講演会
サブプライムローンを学ぶ
経営者などでつくる箕輪町経営研究会は20日夜、新春講演会を開き、世界同時不況の発端となったサブプライムローンについて約45人が学んだ。
講演会は毎年企画されているが、今年は世界同時不況の発端となったアメリカの低所得者向け住宅ローン「サブプライムローン」について学ぶため、八十二銀行の伊那支店長滝澤亮さんを講師に迎えた。
滝澤さんは、サブプライムローンの焦げ付きが、どうして世界経済に影響を与えるまでになってしまったかを説明し、一番の原因は「ヘッジファンドが小さい資本で大きいリターンを得るために動いた結果、ものとマネーがかい離してしまったことにある」と話した。
また打開策としては、「短期的には公共投資によって市場の流れを強制的に作り出すことが大切。しかし、長期的には実態経済を正常化する取り組みが重要」と話した。
講演会を主催した研究会では、世界的な経済状況を踏まえながら、この不況を乗り越えたい竏窒ニしている。 -
ふるさと就職面接会

3月に卒業を控えた学生などを対象とした上伊那地域合同就職面接会が23日、伊那市のプリエキャスレードで開かれた。会場には、3月卒業予定の学生のほか、一般求職者など150人ほどが集まった。
この時期の参加事業所は例年40ほどだが、今年は不況のあおりを受け、3割ほど少ない27の事業所が参加した。
特に製造業は、前年の20社に対し6社の参加となった。
参加した高校3年生は、「製造業で仕事を探しているが、なかなか見つからない。4月までに就職を決めたいので、業種の幅を広げて考えるつもりです」と話していた。
また会場には、長野県新規就農相談センターなどが開く就農相談のブースが、初めて設置された。
これは、農業人口を増やすとともに、雇用拡大につなげよう竏窒ニ開かれた。
この相談コーナーは、伊那のほか県内3カ所で開かれる就職面接会にも設置される。 -
子どもたちの自然エネルギー活用コンテスト初開催、大賞に赤穂東小エコ委員会

伊那谷の企業20社でつくる伊那テクノバレーリサイクルシステム研究会(会長・向山孝一KOA社長)は24日、環境活動を幅広く浸透させようと初めての「KIDS自然エネルギー活用コンテスト」を伊那市役所で開いた。自然にやさしい活動を熱心に展開する上伊那の6小学校が参加。ペットボトルに入れた水を太陽熱で温めて清掃に利用するなど、年間数十万円の節電を全校児童あげて実践している駒ヶ根市の赤穂東小学校エコ委員会を大賞に選んだ。
同小では4年前の5年生が愛知万博を訪れ、環境問題に関心を寄せたことを契機に取り組みを開始。エコ委員会が中心となって全校の省エネ活動を推進するほか、反射板を使った太陽熱利用装置も児童自らが手づくりし、各学級で清掃時のお湯として使っている。
審査委員長も務めた向山会長は「校内のみならず家庭や地域社会にも活動の輪を広げ、世界にも目を向けたボランティア活動にもつながている。深く感銘した」と講評した。
残る5校の取り組みも高く評価し、それぞれ特別賞を贈った。参加した小学校の取り組みは冊子にして、伊那谷の全小中学校に配布。コンテストは来年度も学校、家庭などに幅広く呼びかけて行う予定だ。 -
あるしん中小企業景気動向
アルプス中央信用金庫は、去年10月縲・2月の伊那谷の経済動向をまとめた。それによると今年の見通しについて、9割の企業が自社の業績悪化を予想していることがわかった。
これは、あるしんが年に4回行っている定期的な景気動向調査によるもの。
今年の見通しについては、ほぼ100%の企業が「景気は思わしくない」と回答している。
自社の業績の見通しについては、「普通」「回復へ向かっている」と答えた企業が1割にとどまり、9割の企業で業績悪化を予測する結果となった。
売り上げ額の伸び率については、8割の企業が「減少する」と回答し、特に製造業・建設業・卸売業では、「減少する」との回答が去年の3割から今年は8割へと増加していて、悪化傾向が強まり厳しさが増す見通しとなっている。
自社の業績が好転する時期については、今年中に「良好感が出る」と回答した企業が3割だが、製造業・建設業・卸売業では、半分の企業で業績が上向くのは2年以上先と予測している。
サービス業では半数を超える企業が「業績改善の見通しがたたない」と回答している。
あるしんでは、「景気回復や中小企業支援の政策が急務であり、今年も厳しい景気の状況となる見通し」としている。 -
障害者就職支援セミナー

障害者の就職を支援しようと22日、伊那市のいなっせで就業支援セミナーが開かれた。会場には障害のある人や支援者、企業経営者など約100人が集まった。
このセミナーは、地域全体で障害者の就業を促進しようと、南信障害者就業支援ネットワークが開いた。
宮城県で会社を経営する大場俊孝社長が講師を務め、「障害を乗り越えて働くために」という演題で講演した。
大場社長は、全社員の2割にあたる10人の精神障害者を雇用している。
障害者の雇用が難しいという現状について大場さんは、「家族、支援機関が、無理をさせられないという思いから就職をあきらめている場合が多い」と話した。
また企業側も受け入れに不安があることから、「訓練制度を利用して職場環境や仕事への適応を進め、雇用につなげることが大切」と説明した。
大場さんは、「障害者が職場に定着するにはお互いの理解が必要。現在の環境をそれぞれ見つめ直して理解を深めてほしい」と呼びかけていた。 -
合同就職面接会に前年13社下回る27社、求人減に対して求職者倍増

伊那公共職業安定所(ハローワーク伊那)は23日、上伊那地域合同就職面接会を伊那市西町のプリエ・キャスレードで開いた。参加企業は前年同期に開いた面接会を13社下回る27社だったのに対し、職を求めて訪れた人たちは前年の倍近い153人。特に現場製造職の落ち込みは激しく、前年の面接会に61人もあった求人はわずか1人にまで激減した。働いていた職場の経営悪化に伴い解雇や雇い止めされた人の姿もあり、厳しい雇用情勢を如実に示した。
製造業で正社員として働いていたが不況の影響で解雇されたという上伊那郡内の30歳男性は、企業との面接を終えて「やはり厳しい」と唇をかんだ。製造の職を求めて求職活動の毎日だが「ひとつの求人に対して10倍や20倍の競争率が普通になっている」とも。実家で暮らすため何とか生活をつなぐが「今後もあたるだけ、あたるしかない」と続けた。
同じく製造現場の仕事をしていたという伊那市内の40代男性は、この日の会場に足を運んだものの希望職種の求人がなく面接を受けなかった。「技術力があるとか、手に職があるとか必要になっていて難しい。若くもないですから」ともらした。
面接会には数社の製造業が参加したが、大半は技術専門職。ある製造業の採用担当者は「現場の製造職は募集する状況にない。高い専門的な能力がある人に限って採用している」と話す。
製造の求人が激減する一方で、目立ったのが介護や看護職などの求人。ある福祉施設の担当者は「製造業の派遣などで解雇された人からの求人問いあわせが急激に増えている」と説明する。「中途で入った人は経済が立ち直った時に再び転職されてしまうのではと不安もあるが、この不況が私たちにとって労働力を確保する絶好機であることもたしか」と話し、求職者との面接に臨んでいた。
また、会場には農業法人への就職や就農を考えている人たちの相談窓口も設けられ、若者らが熱心に担当者から説明を受ける姿もみられた。
生産工程管理の仕事をしていたという伊那市内の男性(31)は「不況だが自分をもっと試したいと思い会社を辞めた。今日の面接を受けに来ている人の数を見ても厳しいと感じるが、適正をみながら長く働ける職場をあわてずに探していきたい」と語り、食品業界に勤めながら職を探している上伊那郡内の男性(30)は「このような時でも自分にあった仕事があるはずなので、求職活動を続けていきたい」と話した。
同安定所の野口博文所長は「今日の面接会でも切迫感の高さが伝わってきたが、今までと違った職種、企業に入るチャンスであるとも言える。幅広く考えてほしい」と語った。 -
春闘上伊那地区連絡会結成総会
雇用確保に重点
2009春季生活闘争上伊那地区連絡会の結成総会が19日、伊那市で開かれ、取り組みについて組合員の雇用確保を重点に置くことなどを確認した。
この日は、関係者約80人が参加した。
上伊那地区連絡会は、連合長野上伊那地域協議会や上伊那地区労働組合会議などで構成している。
総会の中で連合上伊那地域協議会の竹内啓剛議長は、「年末に始まった景気後退はとどまることなくウイルスのように日本列島を覆ってしまった。安心して暮らしていけるよう理想を高く元気に闘っていきたい」とあいさつした。
具体的な取り組みとして、組合に加入していない人やパート労働者のための相談ダイヤルを周知し強化していく考えという。
2月5日に闘争開始宣言集会、3月9日に総決起集会を開催する予定。 -
人材育成の拠点熱望、県工科短期大学校誘致の意見も

大学や短大などに進む高校卒業者のうち、約85%が県外に進学している長野県。そのまま都市圏で就職し、県内に戻らないケースが多いとみられ、上伊那の経済関係者も若い人材の流出に頭を悩ませている。県議会と南信の経済、行政のトップが意見を交わした「こんにちは県議会」が20日に伊那市で開かれたが、伊那関係の代表者らは県工科短期大学校の南信誘致を熱望。培った技術力を継承し、さらに発展させるためには育成機関が地元に必要と強調した。
席上、川上健夫伊那商工会議所副会頭は「これからは高度化に対応できる開発力と総合的なマネジメント力のある人材育成が求められる。若者を育てられる工科短大校を南信に設ければ、この地域の競争力も高まる」と語気を強めた。
上田市にある県工科短大校の卒業生の大半は県内に就職しており、伊那市選出の木下茂人県議は「地元に密着している点で効果が高い。しかし、県内は広く1校ではカバーできず、南信からは通学できず縁遠い存在」と指摘。
小坂樫男上伊那広域連合長も「工科短大校レベルの養成機関を設置してほしい」と要望し、県伊那技術専門校の充実で対応する案も示した。
伊那市選出の向山公人県議は、地域で踏み込んだ議論が必要と指摘。地域と経済界、行政が一緒になって県へ提案していくべきと述べた。 -
28社が参加して上伊那地域合同就職面接会23日に
伊那公共職業安定所(ハローワーク伊那)は23日午後2時から、上伊那地域合同就職面接会を伊那市西町のプリエ・キャスレードで開く。一般求職者と就職先が未定の今春新規学卒者が対象で28社が参加を予定。未曾有の不況の影響で参加企業は昨年同時期に開いた面接会に比べて12社減っているが、「各企業と直接話ができる貴重な機会」と求職者に呼びかけている。
昨年11月の上伊那地方の有効求人倍率は0.87倍。2002年12月以来6年ぶりの低水準で、雇用情勢は年明け後も一層の厳しさに。今回の面接会でも製造業の落ち込みを受けて現場生産職の求人が減少する一方で、介護職など福祉分野や営業系の割合などが強まっている。
「職種の転換も含め、現実を重視しながら仕事をどのように考えていくかが就職のカギを握っている」と同職安の担当者。面接会は午後4時(受け付けは同3時20分)まで。参加費や事前申し込みは不要で、問い合わせは同職安0265・76・1000。 -
伊那市景気動向調査結果
伊那市が行った景気動向調査の結果、「来年度新規採用をしない」と答えた事業所が80%以上に上っていて、一層厳しい雇用情勢が懸念されている。
これは伊那市が、商工会議所や商工会の協力を得て昨年12月に実施した調査から明らかになった。
調査事業所を業種別に無差別に抽出し、製造業・建設業は112事業所、商業・サービス・飲食業などは96事業所から回答を得た。
それによると、「来年度の新規採用を行わない」としたのは、製造業・建築業で83%、商業・サービス・飲食業などで87・2%に上っている。
製造業・建設業関係では、66・1%の事業所が、前の年の同じ時期に比べ、「受注量が減少した」と答えている。
また、今後も受注量が減少すると見ている事業所は77・4%に上った。
派遣社員を雇用している28事業所のうち、15事業所(53.6%)が「人員を削減した」、あるいは「今後削減する」と答えていて、派遣社員が雇用を調整する役目を負っている様子がうかがえる。
伊那市では、緊急経済・雇用対策本部を設置している期間中、この景気動向調査を半期に一度行なうという。 -
上伊那高卒者の就職内定状況
伊那公共職業安定所は、昨年11月末現在の高校新卒者の求人、就職状況をまとめた。
それによると11月末現在の就職内定率は、前の年を3.4ポイント上回る90・9%となっている。
これは、県平均の81・1%を10ポイント近く上回っている。
この要因について伊那公共職業安定所では、「各企業とも中途採用はしなくなっているが、新卒者は人材育成の一環として別扱いしているケースが多いのではないか」と話している。
ただ、内定率は高いものの製造業などの求人者数は前の年より7・8ポイント低くなっている。 -
ジョブカフェ信州に緊急雇用相談窓口
急激な景気低迷による雇用情勢の悪化に対応するため県商工労働部は15日から、主に若者の仕事探しを支援しているジョブカフェ信州に緊急雇用窓口を開設。年齢関係なく離職を余儀なくされた人たちの相談に幅広く応じ、きめ細かな就職アドバイスや求人検索、職業紹介などを行っている。
松本センター(松本市深志1-4-25松本フコク生命ビル1、2階、)の受付時間は午前8時半から午後6時半。長野分室(長野市新田町1485-1もんぜんぷら座4階)は午前9時から午後5時15分。いずれも月縲恚燉j日で当分の間開設する。 -
新たな部長に平澤賢司さん、宮田村商工会青年部が次期役員承認

宮田村商工会青年部は14日夜に臨時総会を開き、新たな部長に平澤賢司さん(小松屋商店)、副部長に春日真一さん(春日商会)、北原貴明さん(宮田自動車工業)ら次期役員を選任し全会一致で承認した。任期は4月から2年間。厳しい不況に部員たちは直面しているが、地域の活力源でもある部の伝統を協力して受け継いでいく。
平澤さんは「このような厳しい時だからこそ、青年部魂を持ち全員で力をあわせて取り組んでいきたい」とあいさつ。2年間務めてきた小田切等部長は新体制にエールを送りながら「厳しい状況だが、私たちには若さと行動力がある。先輩のアドバイスも受けながら力をつけ、生き抜いていこう」と話した。
同青年部は多彩な活動を展開し、毎年テーマを持ちながら歳末慈善パーティーを開催。名物丼やどんぶりレンジャー、よさこいソーランなど地域が元気になる取り組みも次々と打ち出してきた。
総会席上、前林善一商工会長は「このような時だからこそ、前をみすえて宮田村の元気の発信源になって」と部員たちに呼びかけた。
新役員は次の皆さん。▽部長=平澤賢司(小松屋商店)▽副部長=春日真一(春日商会)北原貴明(宮田自動車工業)▽常任委員=濱田聖(パブリックレコード)綿内信幸(信光設備)馬場誠(理容アルプス)、間瀬令理(間瀬製作所)酒井豊典(サカイ家電)、清水正康、近藤浩紀(ジョイ・アクトコンドウ)伊藤康晃(太陽堂)酒井大介(白木屋商店)春日孝昭(ラスタデザイン)清水邦浩(千代田)鈴木貴久(トノムラヤ薬局)三澤敏昭(エムテイクリーンサービス)▽監査委員=太田豪敏(レストハウスおおた)下井明人(下井ばね製作所)▽直前部長=小田切等(長野ユーシン) -
上伊那のレギュラーガソリン価格前月比13.9円安の108.8円に
上伊那地方の1リットルあたりレギュラーガソリンの価格は13日現在108.8円で、先月8日の調査に比べて13.9円値下がりしたことが県企画部の調査で分かった。ハイオクガソリンは120.7円で前月比13.8円安、軽油は105.1円で同10.1円安。灯油も18リットルあたり1158.7円で148.5円値下がりした。
県内78店舗を対象に電話による聞き取りで調査した。県平均のレギュラーガソリン価格は前月比12.7円安の106.8円。価格急騰によりピークだった昨年8月と比べて80円近く安くなっており、5カ月連続で下落した。ハイオクは118.1円(前月比12.6円安)、軽油は103.2円(同11.2円安)、灯油は1159.4円(158.5円安)だった。 -
失業者、離職者に低金利で融資する勤労者生活資金緊急融資制度創設、15日から受付開始
長野県は倒産やリストラなどで離職、失業した県内居住者を対象に緊急的な生活資金を低金利で融資する「勤労者生活資金緊急融資制度」を創設。15日から県労働金庫窓口で受付を開始する。限度額は1世帯あたり100万円で、返済期間は10年以内。年利1%(別途保証料1.2%)で貸し出す。
県内に1年以上居住し、同一事業所に1年以上勤務していた20歳以上が対象。県税に未納がなく、失業後も求職活動を続け、保証機関の保証が得られ、雇用保険受給用件が満たされていることなどが条件。受付、問い合わせは県労働金庫の本店、各支店などで、上伊那では伊那支店0265・72・7266、伊那支店伊北出張所0265・70・6880、ローンセンター伊那0265・77・0023、駒ヶ根支店0265・82・6555が窓口となる。 -
緊急経済対策で20%のプレミアム商品券発行へ、宮田村が商工会事業の助成で独自策
宮田村は緊急経済対策として村内消費を促進するため、村商工会が発行するプレミアム商品券事業への助成を16日の村議会臨時会に提出する本年度補正予算案に盛り込む。補助金により額面を20%上乗せするもので、一般家庭の生活支援策としても位置づけながら村内経済の活性化に結びつけたい考えだ
1000円券12枚を1万円で1000セット販売予定。同商品券は発行額の2%が事業主負担のため、村は残る18%分の180万を補助する。村内の加盟65店舗で利用でき、2月初旬の発売を予定。短期間に需要を見込もうと3月末までの使用期限と設定する方向だ。
同商工会は通年で5%のプレミアム商品券を販売するほか、毎年秋の商工祭では20%に上乗せした商品券を400縲・00セットの限定で発売して人気を集めている。
村はこのほど開いた村緊急経済対策雇用対策会議の専門部会で商工会側に説明した。村産業建設課は「厳しい経済情勢の中で村内の景気刺激と一般世帯の生活助成の両面につながる施策」としている。 -
来春学卒の就職活動本格化、信大農学部でも合同企業説明会

景気低迷による雇用情勢が悪化する中、2010年3月卒業予定の学生を対象にした就職活動が本格化している。10日には信州大学農学部(南箕輪村)で39社の参加により合同企業説明会が開催。厳しい情勢を受けて来春の採用計画を現段階で明確に打ち出せていない企業もある一方で、「こんな時だからこそ優秀な人材を獲得する好機」と話す採用担当者の声もあった。学生たちは不安を抱えながらもより多くの企業の話しを聞こうと熱心に行動する姿がみられた。
食品、製薬、建設などから流通、ITシステムまで幅広い業種の企業が参加。学生たちは各企業のブースを訪れ、担当者から企業概要や求めている人材などの説明を受けた。応用生命科学科の大学院生鹿島温さん(23)は「不況の実感はまだないが、手探り状態のなかでもやれることは全てやっていきたい」と話し、次のブースへと向かった。
信州大学キャリアサポートセンターによると、年末段階までに寄せられた求人企業は同大学全体で400社にのぼり例年並み。しかし、厳しい雇用情勢から「今年10人であったのを5人にするなど採用人数を絞り込んでくる企業もあるのでは」と話す。
この日の説明会に参加した東京が本社の大手食品関連メーカーの採用担当者は「まだ採用人数は未定」と説明。そのうえで「前向きに行動できる学生を採用していきたい」と話した。
一方である中小企業の担当者は「不況の影響は大いにあるが、このような時だからこそ良い人材を積極的に採用したい」と語気を強めた。
学生が売り手市場だった昨年までは人材を確保するのが難しかったともいうが、それだけに逆境の今こそが成長する好機ととらえる企業があることも伺わせた。 -
中小企業の経営実態まとまる
最近の経済情勢における上伊那地域の中小企業の経営実態がまとまった。
70%を超える企業で売り上げが減少していて、今後更に人員削減が進められることが懸念されている。
これは、昨年12月に長野県が行った中小企業の経営実態調査から、上伊那地方事務所が地域独自の結果をまとめたもの。
調査は、上伊那地域の中小企業78事業所を対象に行った。
それによると、昨年10月から11月は、56の事業所(全体の71.8%)が、前年の同じ時期と比べ売り上げが減少したと答えている。
特に影響が出ているのは製造業で、90%の事業所が売り上げが減少したと回答している。
県全体では75%が減少したと答えていることから、上伊那地域への影響が大きいことがうかがえる。
県によると、上伊那地域は製造業が産業の中心になっていることや、製造業が車産業にシフトしてきた傾向により、長野県全体よりも上伊那のほうが経済危機の影響を受けているという。
こうした状況の中で、上伊那で11月までに人員削減を行った製造業は18.5%。
今後、売り上げが減少すると予想している事業所が多いことから、今後更に人員削減が進められることが懸念されるという。
長野県では、中小企業の支援策として金融融資など総額58億円の補正予算案を、13日の臨時議会に提出する考え。 -
未曾有の逆境の中で商工会新年祝賀会

宮田村商工会は9日、新年祝賀会を商工会館で開いた。会員ら約100人が出席。未曾有の景気悪化の影響が大きく影を落す新年となったが、社会構造の大きな転換期ととらえ踏ん張っていこうと前を見据えた。
前林善一会長は「大変厳しい年明けとなった。この難局を一致して乗りきろうと論ずるのが本来の政治であるはずなのに、国は何も打ち出していない。官と民には大きな温度差がある」と指摘。一方で社会構造や価値観が大きく転換する時でもあるとして「商工会が沈静化すれば地域も沈む。ここを踏ん張って地域を引っ張っていきたい」と続けた。 -
県内中小企業の14%が人員削減、今後も2割が予定
長野県が県内中小企業578事業所を対象に行った緊急経営実態調査で、人員削減について14.2%が10月から11月にかけて実施し、今後3月までにさらに22.3%が行う予定であると回答していたことが分かった。特に製造業の削減が目立ち、同業種の4割にのぼる91事業所が今後の削減を示唆している。全体の6割が資金繰りの厳しさを訴えており、必要な施策としては47.8%が金融支援をあげた。
調査は昨年12月8日から19日にかけて、県職員による聞き取りで実施。10、11月の売上高が昨年同期と比べて減少した事業所は68%にのぼり、10縲・0%減が29.1%で最も多かった。今後についても7割は減少すると答え、そのうち37.7%は10縲・0%を見込み、1割は「予想できない」答えた。
資金繰りでは「最近特に苦しくなった」と20.8%が回答。受注減などで先行きを不安視する声が寄せられており、7割が今後3月までの売上げも落ち込むと予想している。金融機関との取引状況は11.4%が「変化あり」とし、「借入時の審査、返済条件が厳しくなった」「「融資姿勢が後ろ向きとなったようにみえる」といった声もあった。
新規採用については2009年4月採用は25.8%で、2010年4月採用は25.1%が予定している。 -
県中小企業融資制度資金に緊急借換対策枠
急激な経済情勢悪化をを受け長野県は2月1日から、県中小企業融資制度資金の中小企業振興資金の中に新たに別枠で「緊急借換対策枠」を設ける。3月末までの取り扱いで、貸付利率は年2・5%で期間は7年以内、限度額は3千万円。詳細は今後県のホームページなどで告知する。問い合わせは県商工労働部経営支援課026・235・7200。
-
上伊那の有効求人倍率0・87倍に
昨年11月の上伊那の有効求人倍率は、前の月を0・12ポイント下回る0・87倍となり、依然として厳しい状況が続いている。
これは、伊那公共職業安定所がまとめたもので、職安によると、世界的な経済危機のあおりを受け、上伊那ではすべての職種で新規の求人が減っていて、前の年の同じ時期より4割ほど減少しているという。
一方、就職を希望する求職者の数は2割ほど増加していて、職安ではしばらくこうした状況が続くと見込んでいる。
有効求人倍率が0・87倍まで落ち込んだのは、2002(平成14)年の12月以来、実に6年ぶり。
派遣や契約の打ち切りを理由に失業した人の数は、昨年の倍以上となって、事業主の都合で解雇される失業者の数が増加傾向にあるという。
派遣、契約社員として働いていた外国人労働者の相談も増加しているという。 -
企業も仕事始め

多くの企業では5日が仕事始めとなった。
伊那市に本店のあるアルプス中央信用金庫でも5日が仕事始めとなり、窓口を担当する本店営業部では、開店前に朝礼が行われた。
本店営業部の酒井茂部長は職員を前に、「今年は景気の後退など厳しい年と予想される」と話し、「こういう時こそ地域密着型の金融機関として、どういうことが出来るか提案し、着実に前進していくことが大切」と話していた。
あるしんによると、大手企業の生産調整などにより、受注が半分以下に減っている所もあり、昨年からの景気の後退はまだ底が見えていない状況ということで、去年にもまして厳しいことが予想される。 -
各地に緊急経済対策相談窓口
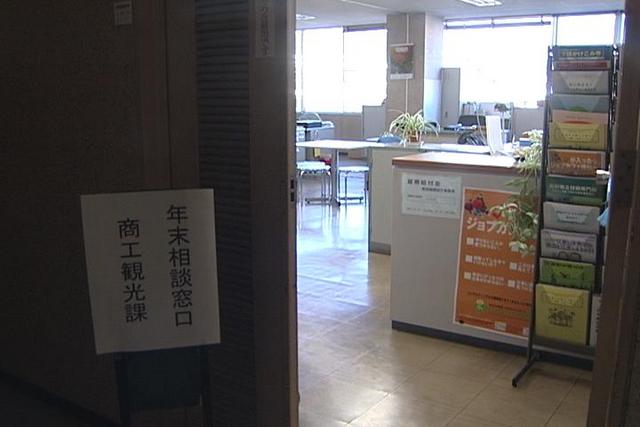
厳しい経済状況が続く中、上伊那各地の行政機関では、年末年始の期間中、緊急経済対策相談窓口を設置している。
上伊那地方事務所の商工観光課には、中小企業の資金や経営を中心とした相談窓口が24日から設置されている。
これまでにあった相談は合計3件で、すべて企業経営に関する相談だったという。
商工観光課によると、上伊那地域の企業では今のところ倒産した企業はないということだが、金融機関が営業している30日までは予断を許さない状況だという。 -
伊那ケーブルテレビが年末年始に上伊那の経済を考える特番放映

伊那ケーブルテレビジョンは、年末年始にかけて上伊那の経済を検証する特別番組2本を放送する。年末29日から31日まで放送するインタビュー番組「伊那谷の経済を振り返る」は、伊那食品工業の塚越寛会長やニシザワの荒木康雄社長、アルプス中央信用金庫の大澤一郎理事長、上伊那農協の春日州一常務理事らが登場。新入社員や新たに伊那市に進出してきた企業の経営者も出演する。新春1日から1月の週末に放送する「伊那谷経済展望」は小坂樫男伊那市長、向山公人伊那商工会議所会頭、滝沢亮八十二銀行伊那支店長が座談会形式で語り合った。製造業が多い伊那谷も急激な不況の波に飲み込まれ厳しい状況だが、だからこそ各企業が原点に立ち戻って自社の技術、サービス力を見返す時でもあると多くの出演者は声をそろえ、さらに一歩を踏み出すため異業種交流や人材育成などの歩みを止めてはならないと強調した。
「伊那谷経済展望」で小坂市長は輸出産業が円高などで厳しい局面に立たされていることも踏まえ、食品、環境、医療が今後の伊那谷の産業振興を図るキーワードになると指摘。滝沢支店長も同様の考え方を示し、今まで培ってきた地域の製造技術をどう活かしていくかもポイントになると挙げた。
そのうえで各企業の技術を持ち寄る必要性を示し、向山会頭も「各企業の得意分野を持ち寄れば世界に発信できる技術を掘り起こせる可能性も高い」と語り、地域にある資源、技術力を見直し連携も強めるなかで地域経済が停滞しない努力が必要と説いた。
工科短期大学校の誘致など人材育成や観光と産業の連携、リニアモーターカーへの期待など、厳しいながらも将来を見据えて熱く意見交換。厳しさを乗り越えた時に、次に進むための体制や条件などを今のうちに整備しておく必要性も指摘した。
「伊那谷の経済を振り返る」は29日午後11時、30日午前7時、午後2時、31日午後7時の計4回放送。
「伊那谷経済展望」は1日正午、午後10時半、4日午後9時と、4日以降の土曜日午後2時、同9時20分、日曜日正午に放映する。 -
ネクストエナジーが太陽光発電装置のレンタル開始

太陽光発電装置を販売・施工するネクストエナジー・アンド・リソース(駒ヶ根市、伊藤敦社長)は、イベントなどへの利用を見込んで太陽光発電装置のレンタルを始めた。短時間で容易に設営可能。環境への関心の高まりから要望も強く、既に諏訪郡原村のイルミネーション会場や県内の工事現場で使われている。同社は装置の中古販売なども手がけており、その独自性を生かしてレンタルに着目した。利用機会を増やすことで、太陽光発電の普及拡大にもつなげていきたい考えだ。
基本セットは、60ワットの太陽光発電パネル2枚とバッテリー、家庭用電源への変換インバーター、設置スタンドが一式。蓄電により100ワットの機器を約3時間使用可能で最大出力350ワットまで対応する。利用が見込まれる屋外イベントでのマイクやアンプの電源として「十分対応できる」と同社の南澤桂営業マネージャーは説明する。
コンセントに電源をつなげておけば、バッテリーに残量がなくなった場合にも自動的に通常の電力に切り替わるシステムも採用。
通常、同様の装置を購入した場合は4,50万円ほとかかるというが、同社のレンタル料金は基本セット4日間で4万9800円に設定し、さらに太陽光パネルなどを増やす時にはオプションで対応する。
問い合わせは同社0265・87・2070。 -
上伊那地方事務所が県営住宅の緊急相談窓口を設置

上伊那地方事務所は24日、解雇などで住居を失った人のための緊急相談窓口を県伊那合同庁舎2階の建築課内に設置した。
これは、今年10月1日以降に解雇され、来年1月末までに住む場所がなくなってしまう人に対し、県営住宅の一次使用を認めるもの。窓口では、解雇により、社員寮や社宅から退去せざるを得ない人や住宅手当が貰えず、家賃が支払えない人などを対象に相談を受け付ける。
県営住宅は駒ヶ根市や飯島町、宮田村など5つの団地の7世帯分が充てられる。
窓口は30日まで。
また、中小企業の資金融資に関する相談についても、年末休み期間中、伊那合同庁舎3階の商工観光課で受け付けている。
県営住宅の入居に関する相談、資金融資に関する相談の休み期間中の窓口設置は、27日から30日までで、時間は午前8時30分から午後3時15分までとなっている。 -
味工房のテナントに城山決まる

南箕輪村開発公社が募集していた大芝高原味工房内の喫茶軽食コーナーのテナントに、南箕輪村の株式会社城山が出店することが決まった。
地域食材の加工や販売をおこなっている味工房は現在、建て替え工事が進められている。味工房を運営する村開発公社ではこれに伴い、喫茶軽食コーナーを民間に業務委託することにし、業者を募集していた。
応募は城山1件で、公社の審査基準に合格したことから、出店が決まった。城山は主に県内外のイベント会場などで飲食コーナーを出店していたが、地元での募集ということと、これまでの経験を活かすことができるとの考えから、味工房での出店を決めた。
城山の小林和秀社長は「地元に根を張り、大芝高原のPRにも一役かいたい」と話している。 -
伊那市緊急経済年末相談窓口設置伊那市役所
伊那市は27日から、中小企業の融資に対する相談、解雇により住まいを失った市民の相談に応じる年末の相談窓口を設置する。
窓口では▽中小企業を対象にした緊急保障制度に関する認定▽市の制度資金の利用▽解雇により住まいを失った市民を対象に住宅や生活竏窒ネどについての相談に応じる。また、必要に応じて、ポルトガル語通訳の派遣もする。
市によると、これまでに解雇による居住の問題についての相談は寄せられていないという。
設置期間は30日までの4日間で、市役所3階の商工振興課で受け付けている。 -
雇用維持と安定に緊急メッセージ
急激な景気悪化に伴う雇用不安に対し24日、長野県と労働局、経済、労働団体は共同で雇用安定に向けた緊急メッセージを発表した。村井仁県知事、小池國光長野労働局長、安川英昭和県経営者協会長、近藤光連合長野会長の4者連名。県内企業に雇用維持と安定に向けて最善の努力を求めた。
262/(木)
