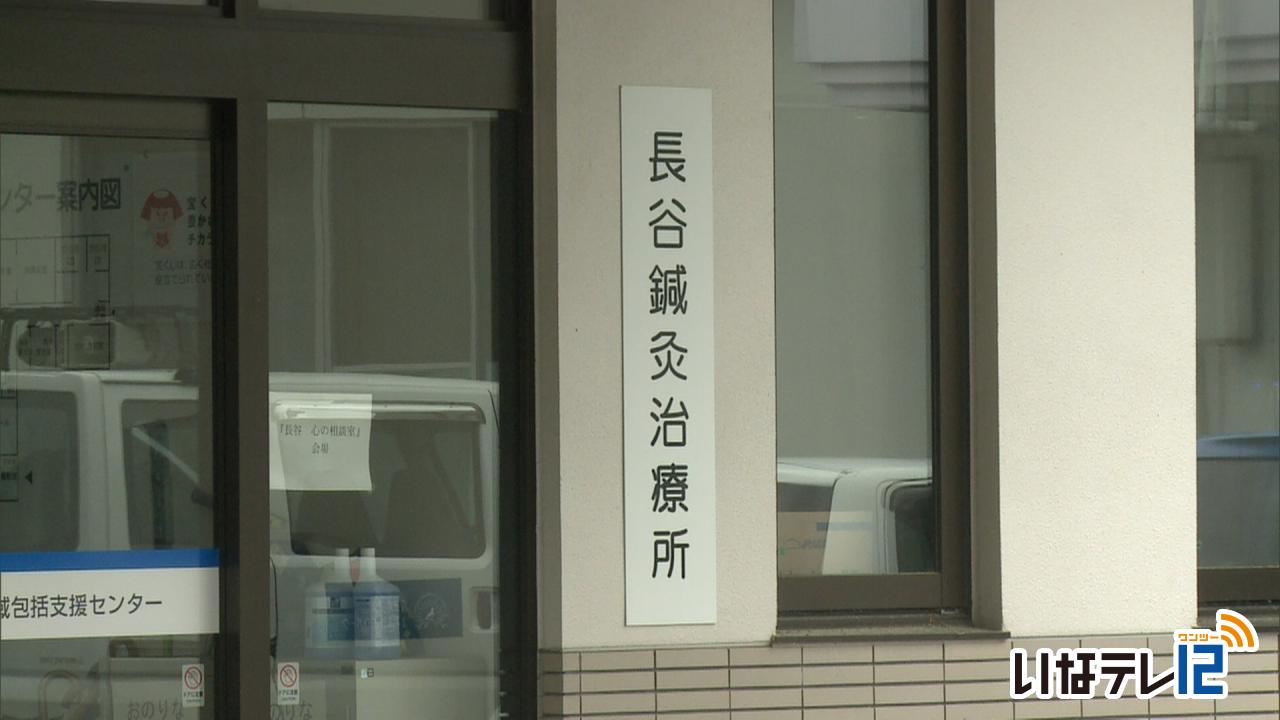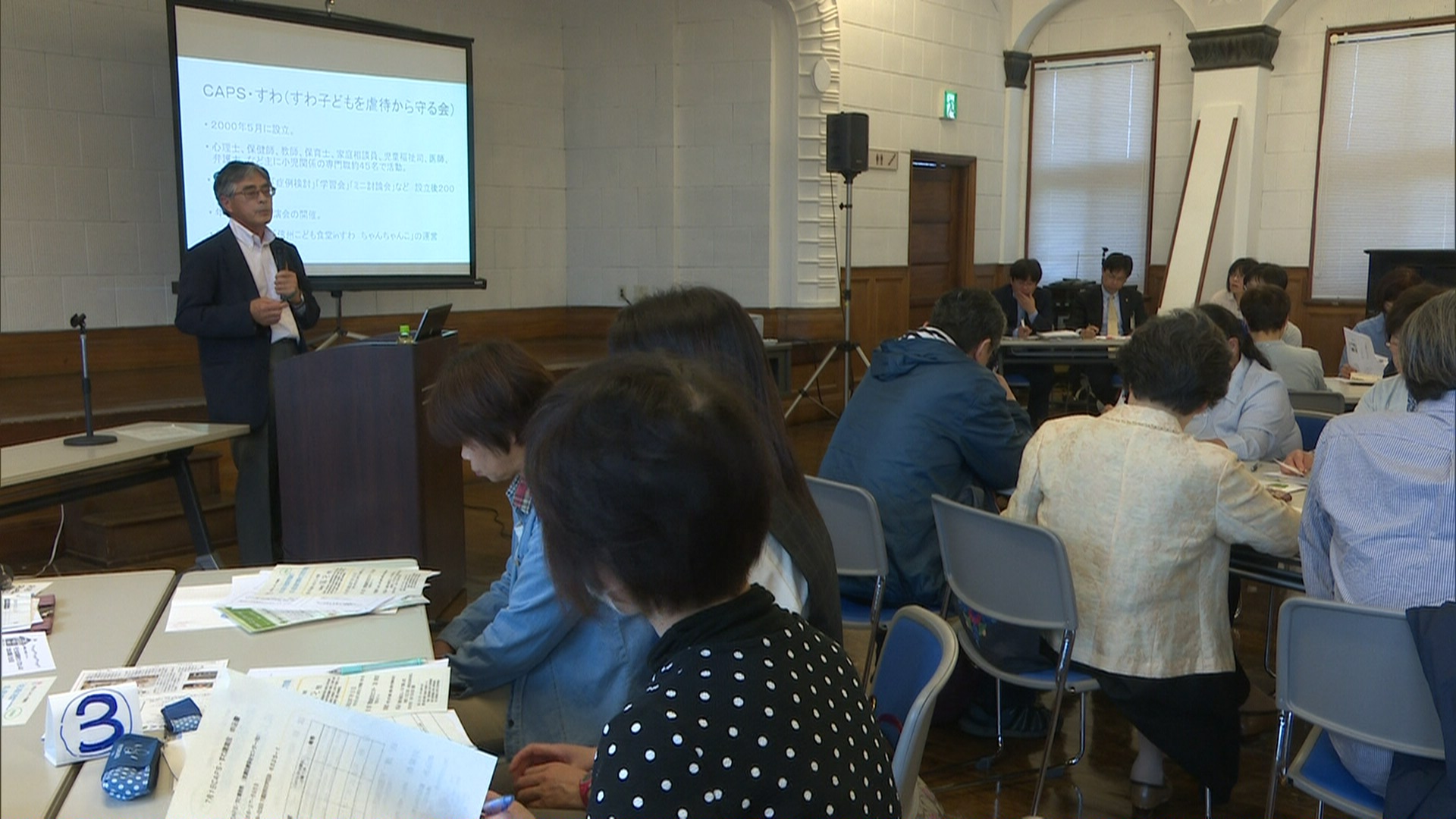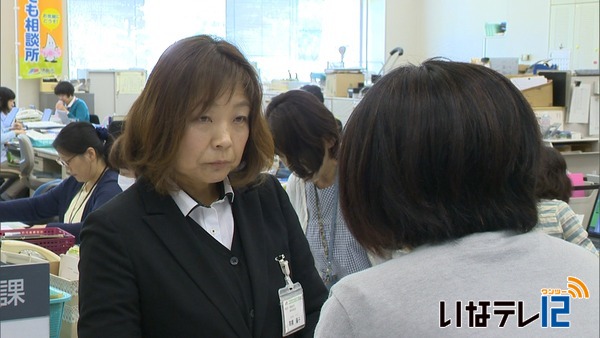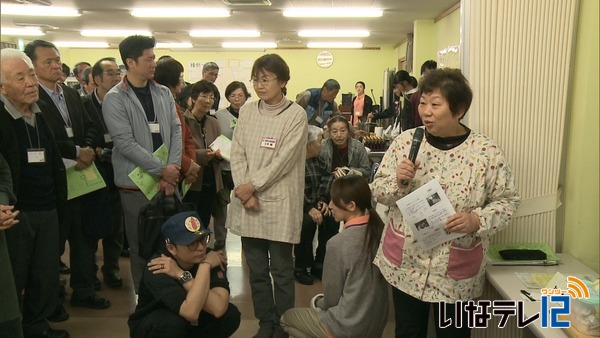-
歯科医師会がアンサンブルで健診
上伊那歯科医師会のメンバーは伊那市西箕輪の知的障がい者就労支援施設アンサンブル伊那を20日訪れ利用者の歯科健診を行いました。
伊那市と南箕輪村の歯科医師3人がアンサンブル伊那を訪れ、利用者の歯科健診を行いました。
上伊那歯科医師会の地域保健部は障がい者の口腔機能の維持・向上をサポートし、自立支援につなげようと2007年から毎年アンサンブル伊那での歯科健診を行っています。
この日は18歳から40代までの利用者90人に対して、虫歯はないか、歯茎が腫れていないかなどをチェックしました。
自分自身で口の中のケアをしづらい利用者もいるという事で、アンサンブル伊那では「普段目が行き届かない部分を見てもらえるので助かっています」と話していました。 -
歯科医師会が障がい者の歯科健診
上伊那歯科医師会のメンバーは伊那市西箕輪の知的障がい者就労支援施設アンサンブル伊那を20日訪れ利用者の歯科健診を行いました。
伊那市と南箕輪村の歯科医師3人がアンサンブル伊那を訪れ、利用者の歯科健診を行いました。
上伊那歯科医師会の地域保健部は障がい者の口腔機能の維持・向上をサポートし、自立支援につなげようと2007年から毎年アンサンブル伊那での歯科健診を行っています。
きょうは18歳から40代までの利用者90人に対して、虫歯はないか、歯茎が腫れていないかなどをチェックしました。
自分自身で口の中のケアをしずらい利用者もいるという事で、アンサンブル伊那では「普段目が行き届かない部分を見てもらえるので助かっています」と話していました。 -
長谷鍼灸治療所 閉所検討へ
伊那市は長谷鍼灸治療所を閉所する方向で検討を進めています。
これは15日開かれた市議会6月定例会で白鳥孝市長が議員の質問に対し答えたものです。
白鳥市長は「最終決定ではない」としながらも「閉所の方向で動きたい」と答えていました。
長谷鍼灸治療所は平成16年に旧長谷村が村営で開所し、合併後も市営として運営してきました。
伊那市では毎年赤字が続いている事や、市内に同様な鍼灸所が20業者ある事などから閉所の検討を進めています。
平成29年度の利用者数は1,331人で、収支は470万円の赤字でした。
伊那市では、次回開かれる長谷地域協議会で意見を聴き、検討を進めたいとしています。
-
伸和コントロールズ たかずやの里応援チャリティコンサート
伊那市高遠町上山田に長野事業所がある伸和コントロールズ株式会社は、東春近の児童養護施設たかずやの里を応援するチャリティコンサートを、2日に信州高遠美術館で行いました。
地域貢献の一環として、しんわの丘ローズガーデンのバラ祭りに合わせてコンサートを毎年行っています。
今回は児童養護施設たかずやの里を応援するためコンサートの売り上げの全額を寄付する事にしました。
会場には募金箱も設置されました。
コンサートでは、東京を拠点に全国で活動するプロの音楽家7人が、クラシックなどを演奏しました。
伸和コントロールズは、毎年たかずやの里に寄付を行っているという事で「コンサートを通してより多くの人たちに施設を知ってもらいたい」と話していました。
500円で販売された約140人分のチケット代と募金は、6月末までにたかずやの里へ届けられるという事です。
-
水道週間 高齢者宅を無料点検

6月の水道週間に合わせ、高齢者世帯を対象にした水道の無料点検が1日伊那市内で行われました。
水道の無料点検は6月1日から6月7日の水道週間に合わせて毎年伊那市水道事業協同組合が行っています。
今年は、組合加入業者23社が希望のあった30世帯を分担して点検をしました。
水道事業者はパッキンを変えたり蛇口部分を点検したりしていました。
伊那市水道事業協同組合では、「この活動も今年で22年目です。毎年、お年寄りの方たちにも喜んでいたただいている。今後も継続して活動していきたい」と話していました。
-
「こども食堂」地域で学ぶ研修会
子ども達に食事の提供や学習支援などを行う「こども食堂」を推進している上伊那地域子ども応援プラットフォーム運営委員会は、広く活動を知ってもらおうと初めての一般むけの研修会を伊那市内で、5月30日に開きました。
研修会には、上伊那地域の一般やNPOなどから50人ほどが参加しました。
講師は、2016年から諏訪市で「信州こども食堂inすわ」を運営している宮原規夫さんがつとめました。
毎月第三土曜日に近くの寺を借りてこども食堂を開設していて、1回の平均利用人数は子どもが13.6人、大人が8.8人、ボランティアなどのスタッフが17.6人だという事です。
宮原さんはこれまでの活動で子ども同士の繋がりができたこと、片づけを積極的に行うなどコミュニケーション能力が向上したこと、親同士の情報交換の場になっている事などをあげました。
上伊那地域子ども応援プラットフォーム運営委員会では、子どもの居場所づくりを地域で進めていくために今年度研修会をあと4回開く予定です。 -
遺志引き継ぎ給水所で中学生を応援
伊那市の東部中学校の強歩大会が29日に開かれました。
大会が始まった54年前から休まず給水所を設置している伊那市手良の桐山さん宅では、この家に住んでいた桐山さん夫婦の遺志を引き継ぎ、親族や近所の住民が今年も給水所を設置しました。
午前9時半頃、3年生の男子が、続いて2年生の男子が東部中のグラウンドをスタートしました。
2・3年生の男子が走る、最長13.5キロのコースの折り返し地点に桐山さんの家があります。
給水所を通過する生徒たちは、水を飲んだり、頭にかけたりしながらゴールを目指していました。
この給水所で生徒たちの走りを見守ってきたのは、桐山慶二さん・八重子さん夫妻です。
おととし慶二さんが亡くなり、去年は八重子さんが寝たきりになりながら慶二さんの遺志を引き継いで生徒たちを応援しました。
その八重子さんも去年亡くなりましたが、姪の桐山みどりさん夫婦や、近所の住民が二人の遺志を引き継ぎ給水所を設置しました。
姪の桐山みどりさんは「応援してみて中学生から力をもらうことができ、おじさんやおばさんが毎年続けてきた気持ちがわかった。私も出来る限り協力していきたい」と話していました。
小松雅人校長は「ご親族の協力で給水所を続けていただくことができ本当にありがたいです。地域の人たちの協力があって大会を続けることができる」と感謝していました。
大会には生徒およそ780人が参加し、2・3年生女子と1年生男子は8.4キロ、1年生女子は5キロを走りました。 -
伊那市境区 運動会で防災意識を高める
伊那市の境区は楽しみながら防災意識を高めてもらおうと負傷者の搬送の体験や防災グッズを学ぶ競技を取り入れた運動会を、27日に開きました。 毛布で作った簡易担架で人形を運びます。 負傷者が足にけがを負っているとの想定でコース途中で止血を行います。 止血の処置が終わると再び搬送を始めゴールを目指します。 この競技は楽しみながら防災意識を高めてもらおうと毎年開いている区民運動会の中で初めて行われました。 体育館の中央に懐中電灯や軍手、水などが並べられました。 防災グッズの名前が書かれたくじを全員が引きます。 こちらの競技は常会対抗のリレーです。 1チーム4人がそれぞれくじで指定された防災グッズを見つけて運び一番早くゴールしたチームが1位となります。 境区では、上伊那広域消防本部の講習を受けた「応急手当普及員」でつくる普及員会を平成15年に立ち上げました。 現在メンバーは6人いて、区民らは普及員から簡易担架の作り方などの指導を受けていました。
-
返礼品「墓地清掃」 就労・自立支援にも
伊那市は、去年7月から墓地の清掃をふるさと納税の返礼品として取り入れています。 作業は、障害者就労支援施設の利用者が行っていて、自立への一端も担っています。 22日には、伊那市美篶笠原にある墓地で作業が行われました。 施設利用者と伊那市社会福祉協議会の職員、あわせて7人で掃き掃除や墓石の水拭きなどを行いました。 墓地清掃は、去年7月に伊那市のふるさと納税の返礼品に登録されたサービスです。 納税額2万円で年1回、6万円で年3回依頼できます。 利用者は、自分や家族の出身地が伊那市の人がほとんどです。 今回は、東京都在住の70代男性からの、父親の墓の清掃の依頼です。 作業にあたった就労支援施設の利用者らは、枯れ葉を掃いたり、草取りをしたりしていました。 ある施設利用者は「きれいに掃除をすれば喜んでくれると思う。そういう作業ができてうれしいです」と話していました。 サービスを提供している市社会福祉協議会では、依頼者に喜んでもらうだけでなく、施設利用者の就労や自立にもつながっていく事業だと話します。 市社協の竹松幸人さんは「作業が障害者の人たちのやりがいにもつながっている。これが自立につながっていけばうれしい」と話していました。 依頼者は取材に対して「これまでは自分でやっていたが、年を取り作業も難しくなってきた。父の地元に納税できることに加え、墓の掃除をしてもらえるのはとてもありがたい」と話していました。 市社協では、依頼があれば墓地の清掃作業を行っていて、1回4千円から利用することができます。
-
ガールスカウトが福祉体験
伊那市と南箕輪村の団員が所属するガールスカウト長野県連盟第26団は、13日に、福祉体験会を伊那市福祉まちづくりセンターで開きました。 13日は、保育園の年長から小学校6年生までの団員およそ20人が、車いす体験などを行いました。 福祉体験会は、ガールスカウトの活動を通して障がいを持った人と接することが多くなってきたことから、相手の気持ちを知る機会にしてもらおうと開かれたものです。 子ども達は、エレベーターへの乗り降りや坂道の上り下りなどのコツを、伊那市社会福祉協議会の職員から教わっていました。 ガールスカウト長野県連盟第26団では、5月26日に入団式を、6月9日には花壇の整備をそれぞれ予定しています。
-
障がい者就労事業所に理解を
障がい者就労事業所について一般の理解を深めてもらうイベントこころん春まつりが18日と19日の2日間、伊那市東春近で行われています。 伊那市東春近の障がい者就労継続支援事業所信州こころんでは利用者手作りのポシェットや農作物を販売し訪れた人たちが買い求めていました。 イベントは地域住民との交流を深め事業所の活動を知ってもらおうと行われたものです。 利用者が野菜や花を栽培している近くの畑ではミニコンサートも開かれました。 信州こころんは県の指定を受け障がい者の自立、自活への道を支援していて25人ほどが利用しています。 花や野菜、きのこなどを育てて販売しているほか、今年からブルーベリーの栽培も始めるということです。 こころん春まつりは19日も行われ手打ちそばの販売やミニコンサートなどが予定されています。
-
箕輪町内の施設利用者が参加 風船バレーボール大会
箕輪町内のデイサービスセンターなどに通う利用者が参加する風船バレーボールの大会が15日、ながたドームで開かれました。 風船バレーボール大会には、町内5つの施設に通う利用者125人が参加し、7チームに分かれて対戦しました。 試合は、椅子か車いすに座り1チーム10人で対戦します。 トーナメント方式で行われ、制限時間5分の間に5点先制したチームが勝ちとなります。 相手のコートに風船を落としたら1点入ります。 この大会のために日頃から練習をしてきたところもあり、利用者は日ごろの成果を披露していました。 それぞれお揃いのハチマキやバンダナを身に着け、チームに声援を送っていました。 決勝戦は、グレイスフル箕輪と生協デイケアBの対戦となりました。 試合の結果、5対3で生協デイケアBが優勝しました。 大会は、町の福祉の活性化と施設間の連携を図ろうと平成24年から行われていて、今回で5回目です。 主催した箕輪町福祉施設事業所連絡会では「風船バレーボールは自然と手が動いたり普段使わない筋肉を使うので良い運動になる。利用者の生き生きとした表情が見られてよかった」と話していました。
-
多機能型事業所「ほっとジョイブ」開所 パン等の販売も
障害者の就労支援や生活介護を行う、南箕輪村久保の多機能型事業所「ほっとジョイブ」の開所式と内覧会が12日行われました。 施設では、利用者が製造したパンとバームクーヘンを販売するほか、喫茶コーナーも営業します。 南箕輪村の国道153号沿いに開所した多機能型事業所ほっとジョイブは、鉄骨平屋建て、延べ床面積は930平方メートルです。 ほっとジョイブは、箕輪町大出の「ほっとワークスみのわ」を移転新築したものです。 施設の老朽化や、利用者が増加し手狭だったこと、また、工賃アップにつなげようというねらいです。 就労支援として近隣の企業から受託した作業の他、パンとバームクーヘンの製造を行います。 施設内に店舗を設け販売するほか、今後は飲み物などを提供する喫茶スペースを設置します。 また、施設では重度の障害がある人の生活介護を始めます。 利用者は、作業の補助や創作、リハビリをして過ごします。 車いすの人でも入浴できる設備もあります。 運営する社会福祉法人長野県社会福祉事業団の和田恭良理事長は、「この地域に根付き愛される施設にしていきたい」と挨拶しました。 パンとバームクーヘンの販売は15日(火)から、平日のみ行われます。 喫茶の営業は6月以降だということです。
-
看護週間に合わせて 骨密度など測定するイベント
12日までの「看護週間」に合わせて、骨密度や体脂肪などを測定するイベントが10日、伊那市の伊那中央病院で行われました。 伊那中央病院1階売店前のスペースには、血圧・骨密度・体脂肪を無料で測定できるコーナーが設けられ、来院者が利用していました。 5月12日はナイチンゲールの誕生日にちなんで「看護の日」に制定されていて、伊那中央病院では7日から12日までを看護週間に定めイベントを行っています。 骨密度の測定では、機械に足を乗せて測り、終わると看護師がアドバイスをしていました。 伊那中央病院では「看護週間を通して看護を身近に感じてもらい、理解を深めてもらいたい」と話していました。 なお、初日から行われている看護の日をPRするグッズの配布は、11日にも行われます。
-
14日から早期がん発見の検診
伊那市の伊那中央病院で早期のがんを発見するPET―CT検診が今月14日から始まります。 検診が始まるのを前に最新の検査機器PET―CTが8日報道関係者に公開されました。 PET―CTはがん細胞が正常な細胞に比べてより多くのブドウ糖を取り込む性質を利用して、がんを見つけるPET検査と内臓の形や大きさを映像化するCT検査を同時に行うことができる検査機器です。 PET―CTを使った検診は地域がん診療連携拠点病院に指定されている伊那中央病院が、がんの早期発見を目的に導入したもので上伊那では初めての検診メニューとなります。 検査室は去年10月に竣工した北棟に作られました。 PET―CT検診は今月14日から始まり完全予約制となっています。 電話で予約することができ実施日は祝祭日を除く月水金それぞれ1名で料金は税込9万9,900円となっています。
-
伊那中央病院で看護週間
7日から始まった看護週間に合わせ伊那市の伊那中央病院では、5月12日の看護の日をPRするイベントが行われています。 初日の7日は、看護師が病院を訪れた人に看護の日をPRするクリアファイルやティッシュなどを手渡していました。 看護の日は、ナイチンゲールの誕生日の5月12日で、今年は、7日から12日までが看護週間となっています。 伊那中央病院では期間中イベントを企画していて9日には正面玄関前で献血が行われます。 10日には、1階売店前で骨密度や体脂肪の測定、栄養相談などが計画されています。 伊那中央病院では「イベントを通じて看護を身近に感じてもらいたい」と話していました。
-
医療・介護従事者の悩み解決へ 相談所開設
在宅高齢者の支援を行う、医療・介護従事者などの相談支援窓口が、1日から伊那市役所に設置されました。 窓口が設置されたのは、市役所1階の高齢者福祉課です。 在宅医療や介護連携について悩みを抱える、市内の医療機関や介護保険事業所、地域包括支援センターの関係者の相談に、看護師の職員が応じます。 市によりますと、医療依存度が高く家族の受け入れが難しいことから在宅介護に切り替えられない、認知症で薬の管理ができず自分で飲むことができないなど、少ない時でも月に4、5件の相談があるということです。 窓口の設置で、看護師が常駐することになり、これまでよりも充実した相談支援ができるようになりました。 伊那市では「今までは体制が十分でなかったため、相談したくてもできない人もいたと思う。これからは気軽に相談に来て欲しい」と話しています。
-
伊那中央病院で消火訓練
今年度採用された医師や看護師などを対象にした消火訓練が26日、伊那市の伊那中央病院で行われました。 訓練には、今年度の新入職員や異動してきた職員およそ70人が参加しました。 伊那中央病院では、毎年春と秋に防災訓練を行っていて、春は火災に関する訓練を実施しています。 職員は、水の入った消火器を使って火に見立てた的に放水していました。 指導した伊那消防署の木下広志署長は、「消火器に触れる機会は少ないので積極的に体験してもらい、日ごろから防災意識を高めてもらいたい」と話していました。 伊那中央病院内の通路には、20メートルに1本消火器が設置されているということです。 万が一火が出た場合は、センサーですぐに場所が特定され、院内に瞬時に情報が伝わるようになっているということです。
-
ナイスハートバザール 自主製品販売で工賃アップを
上伊那にある障がい者就労支援事業所の利用者が製作した商品などを販売するナイスハートバザールが、伊那市日影のベルシャイン伊那店で開かれています。 木工製品に力を入れている伊那市山寺の伊那ゆいまーるは、プランターを販売しました。 箕輪町松島の煌めきティユールは町のふるさと納税の返礼品にもなっている人気商品、無添加石けんを販売しました。 会場には上伊那を中心とした14の施設のブースが並び、手作りの小物や農産物加工品などの自主製品を販売しています。 ナイスハートバザールは、施設利用者の工賃アップや製品のレベル向上などを目的に、NPO法人長野県セルプセンター協議会が毎年開いているものです。 伊那市での開催は6年目で、年々商品のグレードがあがり種類も増えているという事です。 ナイスハートバザールは15日も午前10時から午後4時まで開かれ午後2時からは東部中学校吹奏楽部によるステージイベントが行われます。
-
伊那市下水道指定工事店組合 市社協に寄付
昨年度末で解散した伊那市下水道指定工事店組合は、解散時の組合費の残金4万円あまりを、伊那市社会福祉協議会に、4日に寄付しました。 鈴木正比古組合長代行が福祉まちづくりセンターを訪れ、市社協の伊藤隆会長に4万円あまりを手渡しました。 伊那市下水道指定工事店組合は、下水道の普及と広報活動、技術者の養成などを目的に平成5年に発足しました。市の指定工事店58社が加盟し一般家庭の下水道接続工事などを行ってきましたが、下水道普及率が一定の水準になった事から昨年度末で解散しました。 鈴木組合長代行は「これまでお世話になった地域の方のために使って頂きたい」と話していました。
-
箕輪町消防団 新しい団長に松島の伯耆原信さん
箕輪町消防団の任命式が1日に行われ、新しい団長に松島の伯耆原信(ほうきばら まこと)さんが任命されました。 任命式では白鳥政徳町長から伯耆原さんに任命書が手渡されました。 続いて伯耆原団長から階級が移動する団員60人と新入団員に任命書が手渡されました。今年は16人が新しく入団しました。 伯耆原団長は「団長という責務の重大さを感じ身の引き締まる思いです。新入団員の皆さんは幅広い年代の人と絆を深めながら早く慣れて先輩団員と共に活躍してもらいたい」と訓示しました。 箕輪町消防団は団員数の不足などから、今年度、定数を450人から400人に変更しています。
-
伊那市富県の国保新山診療所 閉所式
医師確保が困難な事などから今年度末で廃止となる伊那市富県の国保新山診療所の閉所式が、28日に行われました。 新山診療所は昭和29年に開所し63年あまり地域の医療を支えてきました。 現在の建物は昭和56年に建て替えられたものです。 これまで15人の医師が診療に携わりました。 平成7年からこれまで診療は週1回の1時間のみで、ここ最近は新山地区の4人が通院していたという事です。 新山集落センターで行われた閉所式で新山区長会長の石原信行さんは「この地域になくてはならない診療所だった。担当医師を始めこれまで地元で支えてくれた人たちに感謝したい」と話していました。 通院していた4人のうち3人は富県地区の別の医院に通う事になっていて、伊那市では、バスの路線変更や交通費の補助を行うという事です。 診療所の後利用については、地元北新区と上新山区から移住定住策を進めるための施設として活用したいとの要望があるという事です。
-
箕輪町とフクロヤ家具が園児の避難場所に関する協定締結
箕輪町と有限会社フクロヤ家具総合センターは、災害時の木下北保育園の避難場所の提供に関する協定を26日に締結しました。 白鳥政徳町長とフクロヤ家具の唐澤修一社長が覚書を交わしました。 木下北保育園は、住宅密集地にあり、周囲に避難できる場所がありません。 近くにあるフクロヤ家具は、床面積が900平方メートルと広く、災害時には全園児が避難できることなどから協定を結びました。 これまでも保育園の雪かきや大雨のときの防災対策などで協力をしてきたということです。 唐澤社長は「地域企業としては当たり前のことだが、この他のことでも園から要請があれば出来る限りの協力はしていきたい」と話していました。 白鳥町長は「これまで同様、協力をお願いします」と話していました。 事業所が町内の保育園と避難場所の提供に関する協定を結ぶのは今回が初めてだということです。
-
小規模多機能施設4月1日オープン
伊那市西箕輪の老人保健施設はびろの里に、新たに小規模多機能施設が増設され4月1日にオープンします。 23日はケアマネジャーなどを対象にした見学会が開かれました。 小規模多機能はびろの里は利用者の希望により「通い」「宿泊」「訪問」といったサービスを組み合わせて、自宅で継続して生活するために必要な支援が行われます。 総事業費はおよそ6,300万円で延床面積は225平方メートル、キッチンや洗面台、テーブルなどがある多機能ホールは利用者の団欒の場として活用されます。 宿泊できる部屋は6室ありベッドが備えられています。 風呂場は2人が同時に使えるように設計されています。 通所定員は18人、宿泊定員は6人、利用料は基本料金で要介護1の場合1か月1万320円からとなっています。 利用は伊那市在住者が対象でオープンは4月1日です。
-
介護センター花岡 伊那店新店舗が完成
諏訪市に本社を置く、福祉用具のレンタル・販売などを行う「介護センター花岡」の伊那店の新店舗が完成し、20日に披露会が開かれました。 新しい店舗は、伊那市役所近くに建てられました。 鉄骨4階建てで延床面積はおよそ4,000平方メートルです。 1階は販売エリアがあり、実際に車椅子やベッドなどを体験することができるようになっています。 また、レンタル用具を消毒・洗浄するためのシステムが導入されています。 2階は事務所、3階、4階は商品の倉庫になっています。 伊那店は、中南信の支店にレンタル福祉用具を配送する拠点の機能も兼ね備えています。 花岡剛成社長は「サービスをさらに充実させて、よりいっそう社会貢献していきたい」と話していました。 介護センター花岡伊那店の新店舗は24日にオープンします。
-
「まちの縁側」 取り組みを紹介する見本市
伊那市社会福祉協議会が進める、地域の人の交流の場「まちの縁側」の取り組みを紹介する見本市が22日、伊那市福祉まちづくりセンターふれあい~なで開かれました。 この日は、会場内にブースが設けられ、これから取り組みを始めようとしている人や興味がある人を対象に、それぞれの縁側の代表者が取り組みを紹介しました。 「まちの縁側」は、縁側のように少人数で集い、交流を通して居場所づくりを進めようと、伊那市社会福祉協議会が平成27年から始めた取り組みです。 これまでに39か所が認定されていて、今年度は6か所が新たに認定されたということです。 市社協では「高齢者だけでなく、幅広い世代の人が集えるような場所も今後は掘り起こして認定していきたい。」としています。
-
保険代理店アシストエース 社協に6万円寄付
伊那市の保険代理店「アシストエース」は、交通遺児の教育や生活に役立ててもらおうと、伊那市社会福祉協議会へ6万円を16日寄付しました。 16日はアシストエースの伊藤正明社長らが社会福祉協議会を訪れ、伊藤隆会長に寄付金を手渡しました。 アシストエースでは、継続的な地域貢献をしていこうと、自動車等の自賠責保険の手数料の一部を交通遺児の為に役立ててもらおうと寄付する事にしましました。 今回は3年前から積み立てた200件分6万円を社協に渡しました。 伊藤社長は「困っている人の為に役に立ててもらいたいです」と話していました。 社協の伊藤会長は「継続的な取り組みをしていただいてありがたいです」と話していました。
-
新人看護師・准看護師対象 技術研修会
4月から上伊那の病院で働く看護師や准看護師を対象にした技術研修会が、15日、伊那市の伊那中央病院で開かれました。 研修会は、働き始める前の新人看護師や准看護師に基本的な知識・技術を身につけてもらおうと、伊那中央病院が行ったものです。 4月から上伊那の各医療機関で働き始める23人が参加し、日本看護協会の認定看護師から技術を学びました。 研修では、6つのカテゴリーごとに分かれて体験しました。 このうち、患者の気道に溜まった分泌物を取り除く「吸引」の演習では、実際に医療現場で使用している機器を使って体験していました。 看護師は「吸引を始める前に必ず患者に吸引することを伝えてください。苦痛が伴うので、常に患者の状態をみながら行ってください。」とアドバイスしていました。 伊那中央病院では、「技術の習得と同時に、実際に働き始めるときは根拠や理由を考えながらケアしてもらいたい。」と話していました。
-
伊那市消防団音楽隊 第7回定期演奏会
音楽を楽しみながら消防団を身近に感じてもらおうと伊那市消防団音楽隊は3日、伊那市高遠町で7回目となる定期演奏会を開きました。 伊那市消防団音楽隊41人が、アニメソングなどを披露しました。 音楽隊は、平成元年に発足し今年で30年となります。 地域の祭りやイベントでの演奏活動を通して防火・防災の啓発活動を行っていて、定期演奏会は今年で7回目になります。 1年間で起きる火事のうち6割近くが1月から5月に起きているという事で今の時期は土手焼きが原因となる林野火災に特に注意して欲しいと呼びかけていました。
-
インフルエンザ注意報レベルに
14日発表された上伊那の1医療機関当たりのインフルエンザ患者数は22.13人で、前回の警報レベルの30.25人からは減少しましたが依然として注意報レベルの10人を超えています。 県の発表によりますと、上伊那の3月5日から3月11日までのインフルエンザ患者数は1医療機関あたり22.13人でした。 前の週の30.25人の警報レベルからは減少しましたが、依然として注意報レベルの10人を超えています。 学級閉鎖は、14日現在、伊那市の小学校で1校1クラス、中学校はなし、箕輪町の小学校で1校1クラス、中学校はなし、南箕輪村の小中学校はありません。 伊那保健福祉事務所では、警報基準を下回ったものの完全には収束していないので、引き続き手洗いやうがい、不要な外出を避けるなど感染拡大に注意するよう呼び掛けています。
122/(木)