-
上伊那公立病院の連携検討会議発足
上伊那地域の伊那中央病院・昭和伊南総合病院・辰野総合病院の3つの公立病院の連携促進について検討する会議が17日、発足した。
医師の不足や地方自治体の財政難などにより、公立病院の経営は非常に厳しい状況にある。
そういった中、上伊那地域では、医師の確保や経営改善などといった課題に直面しているとして、連携について検討する組織を立ち上げた。
会議は、病院が設置されている地区の伊那市長・駒ヶ根市長・辰野町長のほか、各病院の病院長、県など9人で組織している。
上伊那地域公立病院連携促進検討会議では、連携により医療提供体制を維持、また強化していく方策を検討していくという。 -
6億7500万円の一般会計補正予算案
市議会最終日に提出伊那市議会経済建設委員会協議会は17日、伊那市役所で開かれ、第4回補正予算案が示された。
これは国からの地域活性化・経済危機対策臨時交付金として、伊那市に5億7千万円が交付されたことから追加された。
市ではこの交付金を地球温暖化対策、少子高齢化社会への対応などに充てる。
主な事業は小黒原産業適地周辺道路の整備に1億2100万円、浄水管理センター屋上への太陽光発電装置設置に7700万円、デイサービスセンター春富ふくじゅ園の増改築に1100万円など。
補正予算案は交付金のほか、国庫補助金を加え総額6億7500万円を追加することにしていて、議会最終日の22日に提案される。 -
箕輪町共同作業の家新築を検討
箕輪町の平澤豊満町長は、箕輪町共同作業の家の施設整備について、新築の方向で検討していることを明らかにした。16日開いた箕輪町議会一般質問で答えた。
共同作業の家は昭和61年に建設され、62年に開所した。
建設から23年が経過して建物が古くなり、一部に痛みが生じているという。
平澤町長は、「今後できるだけ早い時点で新築を考えている」とし、建設場所については「今、建物がある沢の周辺が一番いいと考えているが、保護者などと検討したい」と話した。 -
上伊那新型インフルエンザ対策協議会会議
「冷静な対応」呼びかけ
新型インフルエンザの2例目の県内発生を受け16日、上伊那地方本部と8市町村の担当者との合同会議が開かれた。地方本部長の宮坂正巳上伊那地方事務所長は、「まだ上伊那管内で発生はないが、今後の展開にも注目し、正確な情報に基づいた冷静な対応をお願いしたい」と呼びかけた。
会議では、県や上伊那での対応が報告された。
それによると上伊那では、指定医療機関となっている伊那中央病院のほか4つの病院が協力病院となっていて最大で1日700人の外来診療の受け入れが可能、入院は182人分の病床が確保されているという。
また、飯田で感染が確認された男性が、熱が出る前の今月13日、飯田で開かれた保育フェスタに参加していたことを受け、各市町村が独自に調査した結果を報告した。
報告によると、駒ヶ根市と中川村で親子1組、飯島町で保育士3人、宮田村で保育士5人がフェスタに参加していたという。
いずれも、今のところ発熱などの症状はなく、県の指示に従い、園児は登園せず自宅待機、保育士や保護者は自宅待機のほか、マスクを着用しての出勤などの対応をとっているという。
伊那保健福祉事務所では、上伊那でもフェスタ参加者がいることから、電話対応時間を15日夜から24時間体制にしている。
これまで、参加者からの相談が寄せられたが、感染を疑うような例はなかったという。
電話相談は伊那保健福祉事務所(TEL76-6837)へ。 -
新型インフルエンザ冷静な対応を
県内で初めて新型インフルエンザ感染者が確認され、長野県は冷静な対応を求めている。
市町村でも、「感染拡大の危険性は低い」と見て、従来通りの体制を維持する中で、冷静な行動を住民に求めている。
13日に飯田市で新型インフルエンザに感染した患者が確認されたことを受け、翌14日は県の相談窓口に200件を超える相談が寄せられた。
その大半が、感染したのではないかと心配する内容だった。
しかし県では、患者が限定されていて、接触した人も限られていることから、現時点では感染が広がるような状況にないと判断し、冷静な対応を求めている。
学校行事や事業の自粛要請などは行わない方針。
伊那市や箕輪町でも14日、対策会議が開かれ、県の判断に従い、これまで通りの対応を行っていくことを確認した。南箕輪村も同様の方針という。
上伊那の新型インフルエンザの相談窓口は、伊那保健福祉事務所(TEL76竏・837)で、対応時間は午前8時半から午後5時15分まで。急な発熱などに関する相談は時間外でも対応する。 -
箕輪町ごみ資源化事業
モデル地区は木下区箕輪町は本年度、生ごみの資源化推進のためモデル地区を設定して事業を行う。
生ごみの資源化は、各家庭から出た生ごみを集めて処理し、堆肥を作るもので、箕輪町は本年度予算に200万円を盛り込んでいる。
15日開いた箕輪町議会一般質問で平澤豊満町長は、木下区の区会議員の了解を得たとして、「区内の常会をモデル地区に選ぶ」と話し、「生ごみは収集するごみの4割を占めている。削減につながるよう期待したい」と話した。
具体的な方法について町では、収集と堆肥化を業者に委託する方法と、地域に大型の生ごみ処理機を設置する方法を想定しているが、住民と共に考え、取り組みやすく続けていける方法をとりたい竏窒ニしている。
作った堆肥については、農地や家庭菜園で使用してもらう予定。
実施時期は未定だが、地区が決定したらできるだけ早く実施したい竏窒ニしている。 -
伊那市議会がBルート実現求める

伊那市議会交通対策特別委員会は15日、伊那市役所で開き、市議会としてリニア中央新幹線のBルートの実現を求める意見書の提出などを検討していくことを確認した。
13日に伊那市で開かれたJR東海の説明会に出席した矢野隆良委員長は、「JRからルートに関する話はなかったが、民間会社はコストを下げなければ利益を出せない。全額自費で工事を行うなど、暗にCルートを想定したようなニュアンスだった」とした上で、議会として「あくまでBルート実現を意思表示しなければならない」と話した。
委員会には各派の代表8人が出席。市議会として6月定例会最終日の22日に、議長名で国と県にBルート実現を求める意見書を提出するか、決議する方向で調整を進めることにしている。 -
子育て中の保護者支援
相談員設置の考え示す南箕輪村の唐木一直村長は15日、子育て中の保護者を支援する相談員を新たに設置したい考えを示した。村議会6月定例会の一般質問の中で答えた。
これまでは、義務教育中の子どもやその保護者を対象にした教育相談員を設置していた。
最近は、幼児教育や就学支援など総合的な相談も増えてきたことから、新たに相談員を設置し、教育相談員とともに活動する。
これにより「保護者からの相談に幅広く対応しいきたい」としている。
また唐木村長は、長引く不況により所得が激減した国民健康保険の加入者に対して、税を減額する措置について検討したい考えも示した。
実施時期は未定だが、早急に取り組みたい竏窒ニしている。 -
リニア中央新幹線 JR東海が上伊那地区で説明

首都圏と中京圏を結ぶリニア中央新幹線の2025年開業を目指すJR東海は13日、上伊地区建設促進期成同盟会の関係者らを対象に伊那市役所で説明会を開いた。
説明会には、上伊那8市町村の市町村長や議会議員、商工団体の関係者ら約180人が出席した。
JR東海は先月、松本市で県内5地区の期成同盟会に対して初の説明会を開催。席上、各同盟会から地元での説明会開催の要望を受け、上伊那や諏訪など県内4会場で説明会を計画した。
上伊那地区期成同盟会会長の小坂樫男市長は、「リニアは地域振興を含めた国の一大プロジェクト。単に首都圏や中京圏を結べばいいものではない」と話し、「長野県は、伊那谷を通るBルートで一本化されている。今日はいい機会なので、Bルート実現に向け強くお願いしたい」とあいさつした。
JR東海の関戸淳二担当課長は、「リニアの技術的な面などに理解を深めて頂き、早期実現を目指し、支援と協力をお願いしたい」とあいさつした。
会は冒頭を除き非公開で行われた。出席者によると、JRの担当者が開発の経緯や山梨県の実験線の施設概要など基本的な事柄について説明。質疑では、出席者から伊那谷を通るBルートでの建設を求める声が相次いで出ていたという。 -
伊那市が国保税減免要綱制定へ
伊那市は、長引く不況のため所得が激減した国民健康保険加入者に対して、税を減額する減免要綱を制する。
11日の市議会一般質問で小坂市長が明らかにした。
減免の対象となるのは、年間所得が500万円以下の国保加入者で、今回の不況により離職をよぎなくされるなどの理由で平成20年中の所得に対して現在の所得が5割以上減少している市民。
これまでにも条例はあったが、より具体的な救済措置として要綱を制定する。
要綱は15日に告示予定で、今年の納付から適用する。 -
南原保育園建て替え工事起工式

老朽化に伴い建て替えられる南箕輪村の南原保育園で11日、起工式が行われた。村長をはじめ地元関係者、業者などが出席し、神事を行って工事期間中の安全を祈願した。
新しく建設する園舎は、木造平屋建てで、大芝高原の間伐材などを利用する。
自然エネルギーを活用するため、村内の公共施設では初めて太陽光発電システムを取り入れるほか、ペレットボイラーによる床暖房設備も整える。
現在の駐車場部分も利用し、建築面積は約1200平方メートル、総事業費は約3億300万円。
唐木一直南箕輪村長は、「現在地での建て替えなので、工事の安全には万全を期していきたい」とあいさつした。
新園舎は、来年3月1日の竣工を目指す。 -
小坂樫男市長は地裁伊那支部の移転建て替え「非常にハードルが高い」
県弁護士会などが別の場所への建て替えを要求している伊那市西町の長野地裁伊那支部について、伊那市の小坂樫男市長は、「非常にハードルが高い」と述べ、移転建て替えが困難だとする見解を示した。
12日の伊那市議会6月定例会の一般質問で議員の質問に答えた。
東京高裁は本年度、老朽化した地裁伊那支部の建物建て替えを計画しており、建設場所は現在の場所を想定している。
しかし、現在の場所は駐車場や前の道が狭いことから、県弁護士会などが移転建て替えを要求している。
小坂市長は、「裁判所の要請を受け、市も用地交渉をしたが、実現しなかった」と話した。
また、敷地面積が2500平方メートル以上であること、駅から近いことなどが条件となっていることを説明し、「非常にハードルが高い。移転する場合、6月中に場所を決めなければ、新年度の予算で予算化できないとしている。現地建て替えは、すでに国の予算がついているので、現地での改修で話が進むと思う」と述べた。 -
伊那市が長谷浦に携帯電話の電波塔設置
本年度伊那市は、長谷の浦地区に携帯電話の電波塔を設置する。11日開いた伊那市議会一般質問の答弁で、小坂樫男市長が明らかにした。
現在伊那市内には、携帯電話の電波が届かない地区が5箇所ある。
その一つが浦地区で、市では国の補助を利用して電波塔を設置する方針。
小坂樫男市長は、「浦は人口が少ないが、鉄塔を建てると南アルプスの遭難者救出にも有効ではないかと考えている」と話した。 -
伊那市議会一問一答方式へ

伊那市議会の一般質問が11日始まり、今議会から一問一答方式が取り入れられた。
一問一答は、議員の一つの質問に対して、そのつど理事者が答えていく方式。
議場は、議員と理事者が向き合う形に配置換えされた。
議会活性化委員会や議会運営協議会などで1年間検討を進め、今議会から実現した。
これまで、質問は5回までと決められていたが、今後は、議員一人の発言時間30分の中で何度も質問することができる。
一般質問初日の感触として中村威夫議長は、「細部にわたり答弁できるので、議会の果す役割が高まったのではないか」と話し、当初の目的は果せたとしている。
また小坂樫男市長は、「思ったより時間がかかる」としながらも「市民に対してわかりやすくなったのではないか」と話していた。
一部の理事者からは、「新しい方式になり、質問する側も更に工夫が必要になるのではないか」との意見もあった。
傍聴に訪れた女性は、「無駄がなくなり、わかりやすくなった」と話していた。
伊那市議会6月定例会の一般質問は、12、15日も行われる。 -
さくら祭り号 来年から平日も
高遠城址公園の桜の見ごろの時期に花見客を運ぶ電車とバス「高遠さくらまつり号」について伊那市は、専用路線の確保と平日運行の実施を検討している。
さくらまつり号は、一昨年から運行していて、松本駅を出発する臨時電車が伊那北駅まで直行する。
伊那北駅から臨時バスが運行しているため、高遠城址公園までの移動時間が短縮できることをメリットとしてきた。
しかし、今年のさくらまつり号の利用者は330人で、前年の690人の半分以下に留まった。
これは、ETCシステムの導入車両に対する高速料金の値下げの影響と見られ、自家用車での来園者増加のため、城址公園に向かう道は大渋滞となった。
さくらまつり号も、伊那北駅から城址公園まで2時間以上かかったという。
そのため伊那市では来年度、こうした臨時バスの専用路線を確保したいと考えている。
また、これまでさくらまつり号は、城址公園の桜が一番見ごろとなる4月の土日曜日4日間のみ運行してきたが、平日に運行することも検討している。
混雑の緩和と、より多くの観光客を誘客することを目的としている。
11日の伊那市議会一般質問で白鳥孝副市長は、「平日の電車を組むことを前向きに検討することになった。桜以外の何かと組み合わせることで、平日運行も十分可能かと思う」と話した。 -
箕輪町保育課題検討委員会 答申

箕輪町の保育園の運営形態や施設整備などについて検討してきた委員会は11日、「民間の保育園等の誘致や、保育園数の削減などの検討が必要」と、平澤豊満町長に答申した。
箕輪町保育課題検討員会の松下勲委員長が、検討結果を平澤町長に答申した。
委員会は、昨年9月に箕輪町から諮問を受け、10回にわたり町の保育サービスについて検討を進めてきた。
答申ではまず、運営形態については保護者の多様化するニーズに応え、サービスを向上させるために、民間の保育園や幼稚園等の誘致が必要としている。
また施設整備については、老朽化に伴う園舎の建て替えに合わせ、統廃合も検討することが必要としている。
このうち町内の2つの園については、統合も視野に入れた計画的な検討が必要としている。
松下委員長は、「子どもたちが、これからの社会の中で柔軟な変化に対応できる資質を身につけられるよう保育サービスの充実を図ってほしい」と要望した。
平澤町長は「答申の趣旨に従い、具体的な検討を進めていきたい」と述べた。 -
伊那市に求職者支援センター設置
長野県は、雇用情勢の悪化を受け、伊那市に「緊急求職者総合支援センター」を設置する。
センター設置は、県内でも求人倍率の低い伊那市と上田市。
センターでは、離職を余議なくされた人を支援するため、伊那公共職業安定所と協力し、就職や職業訓練と合わせて、住宅など生活に関する相談に専門の相談員が対応する。
予算額は、伊那市と上田市の2カ所合わせて約2300万円で、補正予算案が6月定例県議会に提出される。
県では、可決され次第準備にとりかかり、今年秋までには設置したい竏窒ニしている。 -
箕輪町で出張職業相談
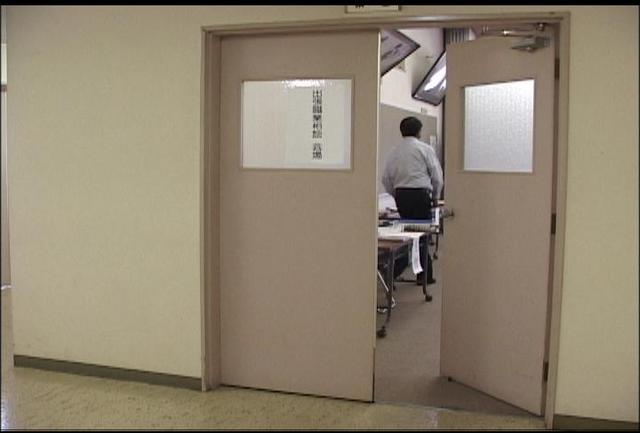
箕輪町役場で9日、伊那公共職業安定所による出張職業相談があった。
雇用対策の一環として箕輪町が初めて、伊那公共職業安定所の協力を得て行った。
午前9時から正午までの相談時間に49人が訪れ、専門相談員1人が対応にあたった。
1月から求職中という女性は、「今後、情報提供してもらえるというので少し目の前が広がった」。50代の男性は、「家から近い役場で相談をやってもらえてありがたかった」と話していた。
町では、「少しでも待ち時間が短縮できて、住民の役に立てれば」と話している。
出張職業相談は7月7日にも開く。 -
箕輪町議会6月定例会開会
共同作業の家を障害者就労支援センターへ移行
箕輪町議会6月定例会は9日開き、箕輪町共同作業の家を障害者就労支援センターに移行する条例案が提出された。
この条例案は、国の法律に基づいて、障害者が通っている共同作業の家を、就労継続支援施設に移行するというもの。
共同作業の家は現在、町の委託で箕輪町社会福祉協議会が運営している。
就労支援センターに移行された場合、委託から指定管理者制度に変わる。
今まで通り、通所者が工賃を得るための作業訓練などを行うが、通所者の仕事の場を増やすなど、より積極的な取り組みをするという。
この条例案は、今議会で可決されると10月1日から施行となる。
6月定例会の会期は22日まで。一般質問は15、16日。 -
南箕輪村議会6月定例会開会

南箕輪村議会6月定例会が8日開会し、村側から予算案件など4議案が提出された。
一般会計補正予算案は、総額1億2千万円で、全会一致で原案通り可決された。
主な事業は、西部保育園の耐震改修工事費用等に4千万円、8月に発行を計画している総額2400万円のプレミアム商品券の印刷代や、プレミアム部への補助に500万円など。
任期満了に伴う副村長の選任は、現職の加藤久樹さんを再任した。
6月定例会の会期は17日まで。一般質問は15、16日。 -
新型インフルエンザ相談体制変更
新型インフルエンザに関する相談が少なくなってきていることを受け、長野県は6日から、県内の保健福祉事務所などに開設している電話相談窓口の対応時間を短縮した。
県では、4月末から県庁などに電話相談窓口を開設していて、上伊那でも伊那保健福祉事務所に設置している。
国内で感染者が確認された5月16日以降、多いときは1日に500件以上の相談が寄せられたこともあったが、6月に入り相談件数は100件前後まで減少している。
また、新型インフルエンザの発生地域に滞在した人からの相談はほとんどないことから、相談時間の変更を決めた。
変更後は午前8時半から午後7時までとなる。
急な発熱などの緊急時は、引き続き時間外の対応も行っていくという。 -
伊那市保育料統一で23人に影響

伊那市は旧3市町村の保育料を一元化するため段階的に保育料徴収基準を改定し、今年7月から統一料金にする。保育料体系の一元化に伴い保育料が値上げとなる人数は高遠町と長谷に住む23人で、影響額は年間合計で83万2800円となる。
5日夜、伊那市役所で開いた伊那市保育園運営協議会で報告された。
階層区分は現行の21階層から13階層に統合し、それにより高遠町と長谷の23人の保育料が値上げとなる。
最高は月額5千円の値上げで該当者は5人、4600円が7人などとなっている。
伊那市では該当者に対し、料金改定について説明し理解を求めていくことにしている。
運営協議会ではほかに、同じ世帯から3人以上が保育園に通っている場合、3人目以降は保育料を無料とする報告もあった。
これは国の保育料軽減措置によるもので、今年度は市内で17人が対象となり、年間の合計影響額は約60万円。
上伊那での3人目以降の無料化は箕輪町と南箕輪村で実施している。
また協議会では今年度、伊那東保育園と伊那北保育園の整備について検討していくことを確認した。 -
伊那市議会開会
伊那市議会6月定例会が4日開会し、市が予算案件など5件を提出した。
提出されたのは、条例案件2件、予算案件など合わせて5件。人事院勧告による特別職や一般職の給与を減額する条例の専決処分は承認された。
会期は22日まで。一般質問は11、12、15日。今議会から一問一答方式で一般質問を行う。 -
災害発生時初動対応職員研修会

伊那市は2日、災害発生時に避難所となる小中学校の鍵を開けるなど初動対応する職員を対象とした研修会を市役所で開いた。
初動対応職員に指定されている50人ほどが出席した。
伊那市では、市内の小中学校すべてを災害時の中心的な避難場所に指定しているが、平成18年7月豪雨災害の際、避難所の開設に時間がかかった場所があった。
それを教訓に、体育館の鍵を開けるなど初動対応する職員を指定し、19年度から研修会を開いている。
指定されている職員は、学校まで歩いていける距離に住む職員。
研修会では、初動対応職員がけがなどをすれば避難所が開設されないため、「地震止めをタンスに設置するなど、日ごろからの心がけが大切」と説明があった。
また災害時は、時間によっては飲酒している人も多く、トラブルが発生する可能性があるとして、「職員がパニックにならず冷静に対応することが必要」としている。
伊那市では、初動対応職員を対象に、開設時のトラブルを想定したゲームでの訓練を7月中に行いたいとしている。 -
伊那市行革効果は2億8千万円

伊那市がまとめた平成20年度の行政改革効果は、2億8千万円に上ることが分かった。
平成20年度、伊那市行政改革大綱に基づき推進した項目は、窓口サービスの向上や補助金の見直し、自主防災組織の充実など90項目。
このうち、一部実施も含め実施したのは84項目で、予定通り進んでいるのが50項目、予定より進んでいるのが31項目、予定より遅れているのが9項目だった。
それによる効果額は、給食業務の見直しや民間委託の推進などによる削減額が2億3500万円。企業誘致や不要な公有財産の売却などによる収入額が4500万円。合計で2億8千万円の効果があったとしている。
これらの評価は、これまで市の職員自らが行なってきたが、今年度伊那市は、より客観的で信頼性があるものにしようと外部評価制度を導入する。
3日市役所で開いた本年度第1回の行政改革審議会で承認された。
審議会の委員13人が、20年度に実施した事業の中から抽出したものについて、より充実させるか、現状維持か、廃止すべきかなどを評価する。
評価時期は、8月から10月までの3カ月で結果を市長に報告する。
審議会長の伊藤泰雄市議会副議長は、「改革は痛みを伴うが財政難の中避けては通れない。最小の経費で最大の効果をあげるよう委員の知恵を借りたい」とあいさつした。 -
上伊那のごみ処理基本計画見直し
上伊那広域連合は本年度、上伊那のごみ処理方針などを示した基本計画を見直す。今回の見直しでは、これまで課題となっていた最終処分場などの施設整備についても、具体的な方針を盛り込むことを見込んでいる。
ごみ処理基本計画推進委員会の第1回会議は2日開き、事務局が新たな計画の素案を示した。
今回見直す「ごみ処理基本計画」は、上伊那のごみ処理の方法やごみ減量化の方針を示している。目標年度は平成35年で、5年ごとに見直しを行っている。
現在上伊那では、上伊那圏域内に最終処分場がないことや、資源ごみや不燃物を処理するリサイクルセンターの老朽化が進んでいることなどが課題となっている。
そのため広域連合では今回、具体的な施設整備の方針を盛り込むことで、施設整備を進めていきたい考え。
最終処分場については、箕輪町の八乙女最終処分場を再生活用する方針を盛り込みたいとしている。
また、リサイクルセンターについては現在、箕輪町、伊那市、駒ヶ根市の3カ所にあるが、比較的新しい箕輪町の「クリーンセンター八乙女」に一本化し、八乙女が古くなった段階で新しい施設を整備する竏窒ニしている。
広域連合では委員会からの提言を計画に反映し、来年1月末ころまでに新しい計画を確定したい竏窒ニしている。
新たな計画は、来年度から適用する予定。 -
国会議員が天竜川激特事業視察

地元選出の国会議員は31日、平成18年7月豪雨以降行われている天竜川激特事業の状況を視察した。
辰野町から伊那市中央区までの激特事業の進ちょく状況を、地元選出の宮下一郎衆議院議員と吉田博美参議院議員が視察した。
地元中央区の宮下政男区長は、「工事が始まってから、地域に流れる古川という湧き水が冬の間枯れるようになった。地域の農業用水、防火用水として利用している大切な川なので復旧してもらいたい」と訴えた。
天竜川上流河川事務所によると、工事に伴って浅い井戸などの水位が低下したり、渇水するなどの恐れはあり、古川も工事が原因で渇水した可能性があるという。
宮下議員らは、「天竜川を安全な川にしていく必要がある。国・県・市と連絡を取りながら、予算の確保に取り組んでいきたい」と話していた。
天竜川激特事業は、平成18年から5年間の計画で行っている。
川底を掘り下げ、根固め工を施していて、18年と同じ規模の出水があっても0.5メートルほど水位を下げられるという。 -
公売のバイク55万円で落札
伊那市がインターネット公売に出品したバイクの落札価格が55万円に決まった。
公売に出品したバイク「カワサキメグロSG」は、伊那市が公用車として使っていたが、ここ10年ほどは使われずに車庫に眠っていた。
市では公売により財源の足しにしようと予定価格5万円で出品したところ、マニアには人気のバイクだということで愛好者などから101件の申し込みがあり、2日に落札価格が55万円に決まった。
市では「どれくらいの値がつくか予想がつかなかったが、高額の落札価格となり驚いている。収入については有効に使っていきたい」と話している。 -
上伊那ごみシンポジウム

新しいごみ中間処理施設の建設を計画している上伊那広域連合は31日、ごみ処理施設の安全性を健康面から考え、理解してもらおうとごみシンポジウムを開いた。
ごみ処理施設の安全対策・環境対策については、日本環境衛生センターの秋月祐司さんが講演。
「焼却施設で各種対策措置をとることで、ゼロにはならないがダイオキシン類の削減が図れる。ダイオキシン類の摂取の大部分は食物からで、大気中濃度増加の影響はほとんどない」と語った。
また、パネルディスカッションでは、信州大学医学部の野見山哲生教授が「関心を持ち続けることが大切」
と話したほか、用地選定委員会委員長を務めた伊藤精晤信州大学名誉教授は、「施設のマイナス面を話し合いでプラスに転じさせて欲しい」と語った。
また、伊那商工会議所女性会の小林旬子会長は、「今後、施設を受け入れた住民に感謝の気持ちを持たないといけない」と述べた。
コーディネーターをつとめた上伊那広域連合ごみ処理基本計画推進委員会の小澤陽一委員長は、「お互いの理解と信頼を得るためには勉強を重ね正しい情報を入手して理解を深めることが大切」とまとめた。
この日のシンポジウムには約280人の市民が訪れた。 -
リニア新幹線 JR東海が初の地元説明会

首都圏と中京圏を結ぶリニア新幹線の2025年開通を目指すJR東海は29日、松本市内で、県内5つの建設促進期成同盟会に対して初めての地元説明会を開いた。
説明会には、上伊那や諏訪など県内5つの期成同盟会からおよそ60人が出席した。
JR東海は、今年の2月から4回にわたり県と勉強会を開いている。
県は、沿線地域との情報共有をJR側に求めていて、この日初めて地元説明会が開かれた。
冒頭で、JR東海東海道新幹線21世紀対策本部の増田幸宏対策本部長は、「皆さんに説明できる貴重な機会。理解を深めてもらえれば幸い」と挨拶した。
この日の説明会は非公開で行われた。出席者によると説明会では、リニア開発の経緯や、山梨の実験線の施設概要と延長工事、駅の構造イメージなど基本的な内容について説明が行われ、県内の通過ルートについては触れられなかった。
建設促進上伊那地区期成同盟会の代表として説明会に出席した、伊那市の酒井茂副市長は、今後新たな情報がある場合は沿線自治体にも情報提供をするようJR側に要望し了解を得た、と話した。
1都5県をまたぐリニア新幹線の計画地域で、県以外に対してJRが説明会を開くのは、今回が初めて。
262/(木)
