-
高校生対象の就職面接会

この春卒業を迎える高校生を対象にした就職面接会が28日、県下で初めて伊那市のいなっせで開かれた。
就職面接会は、ハローワーク伊那と伊那職業安定協会が、県下で始めて開いたもの。
この日は、上伊那を中心に6校から15人が参加した。
ハローワーク伊那などが管内の400社ほどに呼びかけたところ、幅広い業種から、15社が集まった。
上伊那では、主力となる製造業で求人が多かったため、高校生の求人倍率も県下で高い水準を保っていた。
しかし、景気の低迷で、求人数が、前年の6割近くに落ち込んでいる。
高校生が就職せず進学に切り替えた事などから、去年12月末現在の就職内定率は89.3%と、前の年の同じ時期に比べて3.7%のマイナスまで持ち直してきている。
しかし、就職を希望していても現時点で、まだ就職が決まらない高校生を支援しようと今回の面接会は開かれた。
会場では制服やスーツ姿の高校生が、企業の人事担当者から、企業の概要などの説明を受けていた。
ハローワーク伊那では、面接会などを通して、就職を希望する全ての高校生の内定につなげたいと話している。 -
上伊那教育会 研究発表会

郷土の自然や風俗などについての研究結果を発表する、上伊那教育会研究発表会が23日、いなっせで開かれた。
会場には上伊那地域の教職員など約100人が訪れた。
上伊那教育会では、地域の変化を広域的に調査し、記録していこうと31年前から専門委員会を設置して分野ごとに調査を行っている。
23日は自然の部と人文の部に分かれて、各分野の委員がそれぞれの研究結果を発表した。
昔見られた鳥がなぜ現在見られなくなったかを調べた野鳥班は「農薬の空中散布や温暖化により地域からいなくなった」と発表した。
美術班は、伊那市出身の彫刻家、中村喜平(きへい)についての研究結果を発表した。
やさしい作風の作品が多いことに着目し、「作家スタート時は貧しく、家族をモデルにすることが多かったのが要因ではないか」とした。
ある参加者は「教育指導者として研究意欲を忘れずに、勉強する気持ちを持ち続けたい」と話していた。 -
ハイブリッドカー技術研修会
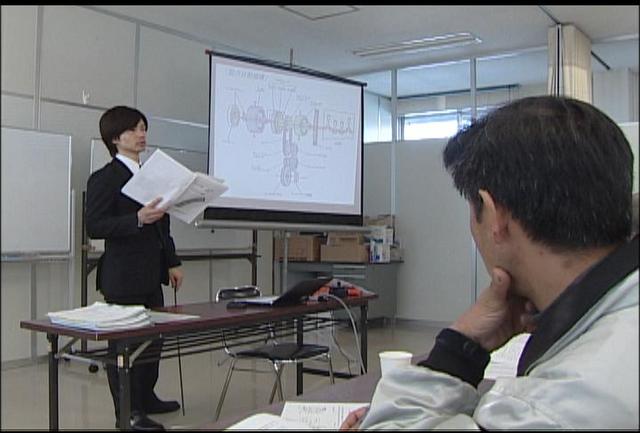
自動車の販売修理を行なうJAグルーブの株式会社オートパル上伊那は、伊那市上牧のオートパル伊那でハイブリッドカー技術研修会を27日開いた。
研修会には、南信地域7つのオートパル所属の工場で働く20人が参加し、自動車の構造に詳しい専門家からハイブリッドシステムや特徴などを聞いた。
オートパル伊那では、国産の全ての車種を取り扱っているが、最近ハイブリッドカーの販売が伸びていることから、修理などをディーラーでなくても積極的に取り扱っていこうと研修会を開いた。
新車の販売台数に占めるトヨタのプリウスやホンダのインサイトなどのハイブリッド車の割合は上昇を続けている一方で、整備を専門とする業者は、「ほとんど入庫がなく、まったくハイブリッド車に触れたことがない」という状況となっていて、今回の研修もこうした現状を打破する意味合いもある。 -
この春の花粉飛散 開始時期例年並み 量は少なめ

飯田保健福祉事務所は27日、飯田・下伊那地域の今春の花粉飛散予測をまとめた。
飛散開始の時期は、例年並み、飛散量は、例年より少なめとしている。
飯田保健福祉事務所によると、今年春の飯田・下伊那地域のスギ花粉の飛散が始まる時期は、去年の2月14日より遅く、例年並みの2月下旬と予測している。
今後の気象状況によっては、飛散開始時期が早まる事も考えられる。
また、スギ・ヒノキの花粉飛散量は、去年より少なく、例年より少ないとしている。
今年の1平方センチメートルあたりの花粉の数は、974個と予測していて、去年の6158個、例年の3488個に比べて少なくなっている。
飯田保健福祉事務所では、花粉症の人は、医療機関や薬局に相談するなど、早めの予防対策を行うよう呼びかけている。 -
上伊那医師会 会長に北原敏久さん

上伊那医師会は25日夜、伊那市で臨時総会を開き、新しい会長に伊那市高遠町の北原内科院長の北原敏久さんを選出した。
上伊那医師会では2年に1回臨時総会を開き役員を選出している。
3月31日の任期満了に伴い、上伊那医師会の新しい会長や副会長などを選出した。
会長は伊那市高遠町の北原内科の院長北原敏久さん。 副会長は伊那市西町の野沢医院の院長野沢敬一さん、伊那市東春近の河野医院の院長河野宏さんの2人に決まった。
上伊那医師会の役員任期は2年。 -
ごみ処理基本計画案まとまる

上伊那広域連合ごみ処理基本計画推進委員会が25日、伊那市のいなっせで開かれ、新たなごみ処理基本計画案のまとめをした。
広域連合では5年ごと、ごみ処理方針を定めた計画の見直しを行っている。
この日は、4回目の会合が開かれ、ごみ処理基本計画案のまとめをした。
平成19年度の試算では、平成25年度における新ごみ中間処理施設の整備規模は、一日あたり149トンとしている。
しかし、今回の基本計画に沿って、家庭系や事業系のごみの減量化、資源化が進められた場合、平成30年度での整備規模は一日あたり139トンと試算された。
また長期計画として、新ごみ中間処理施設の稼働に合わせ、上伊那圏内のごみをクリーンセンター八乙女で最終処分し、完結型の廃棄処理を目指すことなどが盛り込まれている。
今回検討した計画案は、来月、広域連合長に報告される。 -
高齢者ワクチン前倒し 健康成人の日程決まる
長野県は25日、新型インフルエンザワクチンの高齢者の接種時期を前倒ししたほか、健康な成人の接種日程を発表した。
県によると、国からの国内産のワクチンが追加供給されたことなどから、高齢者の接種時期を前倒しした。
また、高齢者などの優先接種対象者の予定数量が確保できる見込みとなったため、健康な成人の接種を始めるとしている。
65歳以上の高齢者は、日程を2週間ほど前倒しし、1月26日予約開始、29日から接種を始める。
健康な成人は、2月1日から予約を受け付け、接種を開始する。
県はこれにより、すべての希望者の接種が可能となる竏窒ニしている。 -
高校生対象の料理教室

高校生を対象にした料理教室が、23日、伊那市の伊那公民館であった。
伊那市食育推進会議は、「健康的な生活を送る為には、どんな食事が必要なのか」を考えてもらおうと初めて料理教室を企画した。
高校生たちは、「鮭の香味ソース グラッセ添え」、「タラコとマヨネーズをあえたサラダ」、「具だくさんの味噌汁」の3品を作った。
生徒達は、野菜の切り方や料理の手順等のアドバイスを受けながら調理を進めていた。
今回料理教室に参加したのは、野球部のマネージャーや、将来、栄養士を目指す2年生、4月から短大に進学し一人暮らしを始める3年生など様々。
管理栄養士の北原和恵さんは、「一人暮らしをすると、コンビニのお弁当を買う機会も多くなると思うが、サラダや総菜などを一品加える事で、バランスのとれた食事になる」とアドバイスしていた。
料理を作り終えると、参加した生徒達は、早速、出来たての料理を味わっていた。 -
花粉飛散予測発表
環境省は22日、今年春の花粉の飛散予測を発表した。
県内の飛散量は例年の半分程度、飛散開始時期は2月中旬となりそうだ。
環境省によると、今年長野県のスギやヒノキの花粉の飛散量は、例年の半分、昨年の3分の1程度の量になる見込み。
これは、昨年6月縲・月にかけ、日照時間が短く、降水量が多かったことが影響したためだという。
また、花粉の飛散開始時期については、例年に比べ数日から1週間程度早くなり、県の南部では、2月中旬頃になる見込み。
環境省では、今年の花粉総飛散量は、全国的に花粉症を発症するレベルだとして、早めの花粉症予防対策が必要と呼びかけている。 -
伊那谷経済動向 水面下で持ち直し傾向
上伊那地域の去年10月から12月の業況は、依然として深刻な状況ながら、水面下で持ち直しの傾向が見られた。
アルプス中央信用金庫は、去年10月から12月の経済動向をまとめ発表した。
それによると、上伊那地域の業況については、好転企業割合から悪化企業割合を差し引いた数値がマイナス54・6と、7月から9月の数値より14・8ポイント改善した。
業種別では、製造業がマイナス56・0、建設業がマイナス30・3、卸売業がマイナス80・0、小売業がマイナス60・0、サービス業がマイナス63・7、不動産業がマイナス66.7で、すべての業種でマイナス領域となっている。
7月から9月の調査と比べて製造業、建設業、小売業、サービス業で改善がみられた。
中でも建設業はマイナス72・2から41・9ポイント上昇し大幅に改善した。
信金では、依然として全ての業種で深刻な状況に変わりはないものの、総じて改善の兆しが見られ、水面下ながら持ち直しの傾向が見られる竏窒ニしている。 -
南信地区の高卒就職内定率86.3%
県教育委員会は21日、今年3月の公立高校卒業予定者の就職内定状況を発表した。
南信地区の内定率は86・3%。
この日発表の就職内定状況によると、南信地区の男子は、 就職希望者数が531人で内定者は474人、内定率は89・3%で前年同期比で1・6ポイントの減となっている。
また女子は就職希望者数が
313人で内定者は254人、内定率は81.2%で10・1ポイントの減。
男女合計の内定率は86.3%で4.7ポイントの減。
県全体では内定率が81.5%で3.6ポイントの減。
厳しい就職内定率を受け今後県教委では、全ての県立高校に就職支援の相談窓口を整える方針。 -
JA上伊那農業振興大会

これからの農業のありかたを考えようと21日、JA上伊那農業振興大会が伊那市で開かれた。
大会は毎年この時期に開かれていて、この日は、集落営農組織や地区組織の代表など260人が出席した。
宮下勝義代表理事組合長は「不況で農業も大変な状況だが、食糧生産は人の命を育むもの。持続可能で、地域が元気になる農業を目指し、営農指導に取り組みたい」と挨拶した。
大会では、来年度から始まる国の戸別所得補償制度についての説明や、山形県で行われている観光農業の事例について発表があり、参加者が今後の農業振興策について理解を深めた。
また、JA上伊那で現在策定が進められている、H22年度から3年間の中期計画が説明された。
中期計画では、多様な担い手の育成、生産の共同化によるコスト削減、農商工産学官連携による地域振興などが目標として盛り込まれている。
大会の最後には、農業情勢の好転と今年の豊作などを願ってダルマの目入れが行われた。 -
高校入試後期選抜追試験実施なし
高校入試の新型インフルエンザ対応について、長野県教育委員会は21日開いた1月定例会で、後期選抜の追試験は実施しないことを決めた。
追試験を実施しない理由として、中学3年生全員分のワクチンが確保できたこと、新型インフルエンザの患者数が減少傾向にあることなどを挙げている。
新型インフルエンザにかかっている受験生については、別室を用意して当日試験が受けられるようにするという。
また受験会場には、消毒用アルコールや予備のマスクを用意し、試験当日に発熱や咳の症状がある受験生にはマスクの着用を指導するという。 -
新型インフルエンザ発生状況 上伊那地域減少
長野県は20日、先週の新型インフルエンザ発生状況を発表した。
それによると、上伊那地域は1医療機関あたりの患者数が先々週の18人から10人に減少した。また全県では2週連続で10人を下回った。
しかし県ではまだ終息状況とは判断できないとして、インフルエンザ警報は解除せず、引き続き手洗いやうがいなど感染予防策を実施するよう呼びかけている。 -
AFS留学生お別れ会

南信地区の高校に留学していた外国人高校生のお別れ会が17日、伊那市のいなっせで開かれた。
今年2月に帰国する留学生6人と、その友人などが集まり、お別れパーティーが開かれた。
6人の留学生は、高校生の留学を支援している民間団体AFSの制度で、昨年3月から南信地区の高校で学んできた。
上伊那では、デンマーク出身のディッテ・ミケルスンさんが伊那北高校へ、ドイツ出身のジュリア・バンバッハさんが伊那弥生ケ丘高校へ留学し、地元の高校生と一緒に学校生活を送ってきた。
また、2月カタールで開かれる高校生の英語ディベート世界大会に出場する伊那北高校英語クラブの激励会も行われ、出場メンバーに拍手が送られていた。 -
上伊那広域計画を答申

上伊那広域計画策定委員会は15日、平成22年度から26年度までの上伊那広域行政の指針となる広域計画を小坂樫男広域連合長に答申した。
小池喜志子副委員長が伊那市役所を訪れ、小坂連合長に広域計画を答申した。
策定委員会は、昨年10月から3回にわたり広域連合が示した計画案について審議を行った。
広域計画は、ごみ処理や医療に関することなどについて17分野にわたりまとめられている。
小坂連合長は、「地域医療再生計画や新ごみ中間処理施設建設など上伊那広域としても重要案件が増えている。答申案を尊重して仕事を進めたい」と話していた。
この広域計画は、2月の広域連合議会に提案される。 -
大学入試センター試験始まる

平成22年度大学入試センター試験が16日から全国一斉に始まった。
上伊那地域では南箕輪村の信州大学農学部と、駒ヶ根市の長野県看護大学の2校を試験会場に試験が行われ、このうち信州大学農学部では、入口付近に高校の教諭らが立ち、試験会場に向かう生徒達にエールを送っていた。
今年の大学入試センター試験の志願者数は、県全体で1万221人となっていて、昨年よりも218人多くなっている。
また上伊那地域の試験会場2校では1383人が受験している。
今年は新型インフルエンザの流行が拡大していることから、追試験の実施期日を例年よりも2週間遅らせた。
また例年は全国2カ所で実施している追試験の会場を、今年は全都道府県に設置している。
大学入試センター試験の追試験は、30日、31日に行われる予定で、長野県では信州大学松本試験場で行われる。
なお、「世界史A」の中で問題文に一部訂正があったが、試験前に発覚したため、文章を訂正し通常通り試験を行ったという。
上伊那2会場は、初日の日程を無事終了した。 -
伊那消防組合の消防士らが意見発表会

消防士らが消防・防災について意見や提案を述べる意見発表会が15日、箕輪町の地域交流センターであり、伊那消防署の春日崇広さんが最優秀賞に選ばれた。
意見発表会は日頃の業務で感じた問題点などについて意見・提案し、今後に生かしていこうと行われている。
この日は伊那消防組合の各消防署から7人の消防士が意見発表をした。
そのうち最優秀賞を受賞した春日崇広さんは「小さなヒーロー」をテーマに話し、子ども向けの体験学習などをもっと企画し、早くから災害に対する知識と技術を身につけてもらうことの必要性を指摘した。
春日さんは、2月18日に駒ヶ根市で開かれる県の意見発表会に出場する予定。 -
スケッチ旅行作品美術展

上伊那美術教育研究会OB有志9人によるスケッチ旅行作品の展示会が、伊那市のいなっせ2階ギャラリーで開かれている。
作品展が開かれるのは、おととし以来2回目。
スケッチ旅行は、平成2年に始まり、国内外各地に、年に2回ほど訪れている。
メンバーは、温泉宿に泊まり、交流を楽しみながらスケッチに励んできた。
今回は、近年訪れた旅行で描いた作品のうち、それぞれ5縲・点を持ち寄った。
このスケッチ旅行作品展は、19日(火)まで、伊那市のいなっせで開かれている。 -
高校生の新型インフルワクチン接種時期決まる
長野県は8日、高校生と65歳以上高齢者の新型インフルエンザワクチン接種の開始時期を発表した。
高校生は1月29日から、65歳以上は2月12日からとなっている。
国の方針見直しに伴い、高校生と65歳以上の高齢者は、国産の新型インフルエンザワクチンが接種できる対象となった。
県では、高校生について、予約の受け付けを14日から19日まで、ワクチン接種の開始日を29日としていて、予定対象者数全員分のワクチンが確保できる見込み。
また65歳以上は2月1日から予約の受け付けを始め、2月12日からワクチンの接種を開始する。
また、長野県の発表によると、12月28日から1月3日までの一医療機関あたりの上伊那のインフルエンザ患者数は、前回の41・88人から21・5人となった。 -
高校入試志願者数第2回調査 発表
来年度の県立高校入学志願予定者数の第2回の調査結果が、8日、発表された。
辰野高校は、普通科前期、64人の募集に対し58人、後期、96人に対し97人。商業科前期、20人の募集に対し30人、後期、20人に対し40人が志願している。
上伊那農業高校は、各科、前後期とも20人の募集で、生産環境科、前期40人、後期58人。園芸科学科、前期42人、後期 50人。生物工学科、前期49人、後期 53人。緑地工学科、前期39人、後期 47人が志願している。
高遠高校は、普通科前期48人に対し88人、後期72人に対し114人が志願している。
伊那北高校は、普通科前期36人に対し83人、後期204人に対し261人。理数科前期36人に対し53人、後期4人に対し46人が志願している。
伊那弥生ヶ丘高校は、普通科前期84人に対し151人、後期196人に対し298人が志願している。
赤穂高校は、普通科前期48人に対し91人、後期112人に対し155人。商業科前期40人に対し79人、後期40人に対し103人が志願している。
駒ヶ根工業高校は、3つの学科一括で、前後期ともに60人の募集で、前期77人、後期108人が志願している。
多部制の、箕輪進修高校は、普通I部前期、20人に対し33人。普通II部前期、20人に対し23人。普通III部前期、20人に対し5人。普通I・II・III部の後期は一括で60人の募集に対し91人。工業I部は、前後期ともに20人の募集に対し、前期16人、後期 15人が志願している。
なお、高校入試前期選抜は2月9日、後期選抜は3月10日に行われる。 -
上古田スケート場 9日オープン

箕輪町上古田の町営スケート場が9日オープンする。
上伊那地域では数少ない天然リンクで、氷の厚さが10センチを超え、予定通りのオープンを迎える。
9日は、午前7時から10時まで、平日は、午後6時からナイターも楽しめる。
昨シーズンは、1月15日から29日までの11日間滑走可能となり、のべで2,177人が利用した。
今シーズンは、地元の箕輪西小学校が授業で使用するほか、町郷土博物館による下駄スケートの体験会も計画されている。 -
井月映画「ほかいびと」クランクイン

幕末から明治にかけて伊那谷を放浪した俳人・井上井月の映画、「伊那の井月 ほかいびと」の本格的な撮影が始まった。
このほどは、主人公の井月を演じる俳優の田中泯(たなかみん)さんがクランクインし、井月が「鉢たたき」に出会うシーンの撮影をした。
「鉢たたき」とは、鉢や瓢箪などを叩きながら、念仏を唱えて歩いた半俗の僧侶のこと。
監督は、伊那市出身の映像作家・北村皆雄さん。
また、主人公の井月を演じる田中泯さんは、映画「たそがれ清兵衛」で最優秀助演男優賞を受賞している。
クランクアップは、井月の命日である来年の3月10日で、映画の公開は来年9月頃を予定している。
映画の制作は、井上井月顕彰会が顕彰事業の一環として取り組んでいる。制作費はおよそ3800万円を見込んでいて、企業や個人からの協賛を募集している。 -
寅年生まれの県内人口 17万3200人
長野県は、来年、年男・年女となる寅年生まれの人口をまとめた。
それによると来年、年男・年女となる県内の寅年生まれの人口は17万3200人。総人口に占める割合は8%で十二支の中では9番目。
内訳では、最も多いのは昭和25年生まれの60歳で、最も少ないのは大正3年生まれの96歳。 -
中央高速バスで「ひとりだけシート」試行

中央高速バスを運行する伊那バス株式会社など6社は、隣り合った2席分のまとめ売りを試験的に始めた。
これは、中央高速バスの「新宿から伊那・飯田」まで、隣りあった2席分を一人に対し、まとめて販売するというもので、その名も「ひとりだけシート」。
隣の人を気にすることなくゆっくりと乗車してもらおうと、中央高速バスを運行する6社が企画した。
ひとりだけシートは、通常の高速バス代にプラス千円の追加料金で購入することができる。
対象路線は新宿線で、乗車券は各バスターミナルなどで購入でき予約は1カ月前から行っている。
この乗車券が使えるのは12月29日から1月3日までを除く平日のみ。
ひとりだけシートが設定されている便は、上りの伊那バスターミナルを午前4時55分発と午後2時25分発、下りの新宿を6時50分発と午後12時30分発のみ。
ひとりだけシートは3月まで試験的に行い、それ以降については検討していくという。 -
上伊那の小中学校で2学期の終業式

今年も残すところわずかとなり、上伊那の小中学校では25日から2学期の終業式が始まった。
このうち伊那市の富県小学校では、全校児童138人が体育館に集まり終業式が行われた。
式の中で、1年生、3年生、5年生の児童が2学期に取り組んできた事を発表した。
このうち5年生は、環境について学習してきた。
学習では、新聞紙でエコバックを牛乳パックで小物入れを作ったということで、児童たちは苦労したことなどを発表していた。
赤羽康・ス(やすのり)校長は、「休み中は家の掃除などのお手伝いをがんばって、楽しいお正月にしてください。休み明けは元気な顔で登校してください」と話していた。
伊那市によりますと、25日市内の小中学校で終業式が行われたのは8校で、ピークは28日という。 -
上伊那11月の求人倍率0.39倍
ハローワーク伊那は、11月の上伊那の月間有効求人倍率が0.39倍だったことを発表した。
5ヶ月連続で上昇しましたが、企業の求人が減るなど、依然として厳しい状況となっている。
11月の上伊那の月間有効求人倍率は、0.39倍で、10月の0.38倍より0.01ポイント上昇した。
県平均は0.44倍で、上田の0.35倍、佐久の0.38倍に次いで3番目に低い地域になっている。
新規求人数は、671人で、10月に比べ15%、前の年の同じ時期に比べ27%、減少した。
一方、新規求職者数は、3カ月ぶりに900人台を割り込む821人となった。
11月中に就職した人の数は317人で、10月より15%、去年の同じ時期より34%増加した。
ハローワーク伊那では、「極端に悪くなることもないが、改善することもない状況」として、依然として厳しい雇用情勢が続くとみている。 -
上伊那の来春高卒者の内定率 84.4%
上伊那の来春高校新卒者の、11月末現在の求人・求職の状況が25日発表された。
就職内定率は、84.4%で、前の年の同じ時期に比べ、6.6%のマイナスとなっている。
これは、ハローワーク伊那がまとめたもので、11月末現在、求人数は238人で、前の年の同じ時期の574人に比べ58.5%の減、また、求職者は256人で前の年が375人だったのに対し31.7%少なくなっている。
就職内定率は、長野県全体の内定率73.4%を上回る84.4%で、前の年の90.9%と比べて6.6%のマイナスとなっている。
ハローワーク伊那によると、伊那職業安定協会や高校など各機関と連携しながら、求人開拓をしてきた成果があり、ここにきて就職内定率が例年並みに持ち直してきたという。
また、今年の厳しい就職状況をみて、高校生が就職から進学に切り替えたことも、持ち直してきた要因とみている。
ハローワーク伊那では、「ここからの活動が重要になる。来年1月に開く、高校生就職面接会を始め、危機感を持って、高校と協力しながら100%の就職内定率を目指したい」と話していた。 -
高校生の就職面接会 初開催へ

ハローワーク伊那は、かつてない厳しい高校生の就職状況を受けて、高校生のみを対象とした就職面接会を来年1月28日に初めて開く。
11月に上伊那の高校や市町村、商工団体などの関係機関が参加し開かれた高等学校雇用対策会議で、開催の要望があったことなどからハローワーク伊那が初めて計画した。
大学生や一般に、高校生も加わっての面接会は県内の他地域にもあるということだが、高校生のみを対象としたものは県内でも初めてだという。
ハローワーク伊那によると、9月末現在、上伊那の就職内定率は48・6%で、前年同時期に比べ23%のマイナスとなっている。
10月から11月にかけて、内定率は例年同様80%ほどに持ち直してきているということだが、求人数が、いつもの年より6割減となっているなど厳しい情勢が続いている。
ハローワーク伊那では、面接会に参加する企業について、製造業を中心に10社ほどの参加を見込んでいるが、高校生に出来るだけ多くの選択肢を持たせられるように、引き続き参加企業を募集している。
来春卒業予定の高校生を対象とした就職面接会は、来年1月28日にいなっせ5階で開かれる。 -
上伊那農業若人のつどい
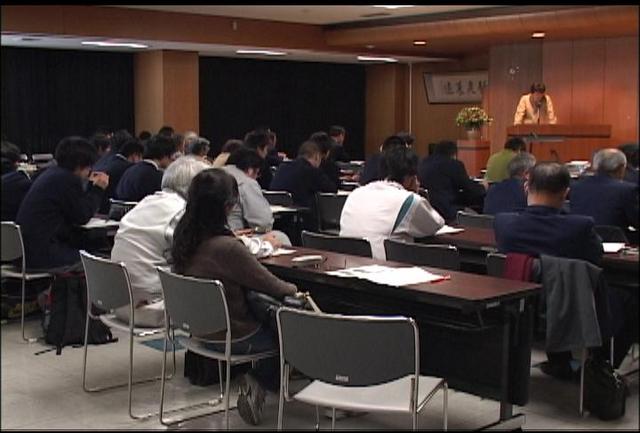
農業に携わる青年たちが互いに学びあう上伊那農業若人のつどいが22日、伊那合同庁舎で開かれた。
20代から30代の青年農業者や上伊那農業高校の生徒など約60人が集まった。
上伊那農業若人のつどいは、情報交換や交流の場がほしいという農業者からの要望を受け今回、17年ぶりに開かれた。
つどいでは、参加した農業者から活動事例発表があった。
このうち、伊那市で米を栽培している唐木千尋さんは、無化学肥料・減農薬栽培に取り組んでいることを話した。
唐木さんは、「安心安全な米づくりが目標。責任をもった米の生産販売を行っていきたい」と話していた。
会場には、伊那市や箕輪町、南箕輪村などの青年農業クラブが活動内容を記した模造紙や農産物も展示されていた。
1912/(金)
