-
伊那市美篶の青島堤防の桜並木に学ぶ

伊那市の伊那小学校6年勇組(北條由美教諭、33人)は14日、同市美篶の三峰川右岸にある青島堤防の桜並木などを観察した。地元の桜並木を保護する「青島堤防桜保存会」(橋爪正昭会長)から桜の管理方法を学んだ。
総合学習で4年生時から同小学校の桜の治療に取り組み、活動を市内全域に広げる勇組。青島堤防の桜並木については昨年4月、約40本の桜を写真に納めた「桜地図」や、児童1縲・人が一本一本を担当して診断したカルテを作ったりもしている。
「樹齢60縲・0年が寿命」といわれているソメイヨシノの木が約90年経っても残る青島堤防。児童たちは治療方法などの活動内容を会員から探り、約1年振りとなる健康診断をして、気がついた点を会に報告した。
児童たちは「枯れ枝を切らないと雨でどんどん腐ってしまう」「あそこにアリの巣があった」「枝を整理しないと日光が当たらない」などと助言。会員と一緒に桜の木を一本づつ見て回り、互いの情報を交換し合った。
橋爪会長は児童たちが桜の病気や、治療するための塗り薬の名前などを詳しく知っていることに驚きの表情。「子どもたちから教わることも多かった。指摘されたことに十分注意しながら今後の管理に役立てたい」と話した。
勇組はこの日、高遠城址(し)公園(高遠町)、非持諏訪神社(長谷)などのコヒガンザクラやエドヒガンザクラも観察。また、国土交通省・天竜川ダム統合管理事務所から昨年6月に任命を受けた、美和ダム(長谷)周辺にある桜を治療する「桜守」に、今年度も再任命された。 -
花のパッチワーク&世界の刺繍(ししゅう)展

宮田村の刺繍(ししゅう)教室・オリジナルT刺繍と駒ヶ根市のパッチワーク教室・マルコミコットンクラブの受講者などの作品が並ぶ「花のパッチワーク&世界の刺繍展」が14日から、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まった。世界各国の伝統的な刺繍や、鮮やかなパッチワークが施されたベッドカバーやタペストリーなど約200点が、訪れた人の目を楽しませている。
作品展は宮田村の刺繍作家・竹中理恵子さんの教える2教室の受講者は、ほとんどが女性。最高齢者は85歳で、高齢の人も多いという。
昨年フランス研修に訪れた竹中さんは、立体的な刺繍「スタンプワーク」を習得。今回の展示は、その手法を披露する場ともなっている。そのほかにもノルウエーやインドなど、各国の特徴ある刺繍が施されている。 -
みはらしで福足しまつりはじまる

伊那市西箕輪の農業公・みはらしファームの春イベント「春らんまんのみはらしまつり」を前に14日、当日の福足し抽選会に参加できる補助券の配布が始まった。
地元農産物、産地直送の海産物などが並び、餅つき大会やスタンプラリーなどが催されるみはらしまつりは、春の恒例。
10日間の間、園内の各施設で500円分の利用につき1枚が配布される「福足し補助券」を手に入れると、当日実施する空クジなしの抽選会に参加できる。
景品は、羽広荘のペア宿泊券や「伊那華の米」、みはらしいちごようかんなど、園内で販売しているものが中心。昨年は約3千人が抽選に参加したという。
券の発行は当日の午後3時まで。抽選はみはらしファーム体験施設前広場の抽選会場で午前9時縲恁゚後4時。 -
桜の名所が次々と満開

伊那市内の桜の名所で、花見を楽しんだり、写真に収めたりする観光客やカメラマンの姿が目立つ。高遠町勝間のシダレザクラなどはこれから見ごろとなるが、伊那区域では桜の花が開く。
市天然記念木指定の伯先桜は14日、満開を迎えた。樹齢200年余、高さ10メートル、幹の太さ6メートル。儒医中村伯先(1756縲・820年)が幼少のころ、自宅の庭に植えたとされる。
西春近の城倉三喜生さん宅が所有するシダレザクラは樹齢100年余。三分咲きで、16日ごろが見ごろ。「例年8日にウグイスが鳴くが、今年は鳴かず、桜の開花予想(9日)も遅れた」という。
枝のはりが見事で、道路沿いに根を張った桜の枝が垂れ下がり、カメラマンがシャッターを切る。
また、天竜川近くにある見通し桜も見ごろ。洪水のために大きく川筋を変える天竜川の測量基点としていた。
訪れた人たちは「きれいだね」としばらくの間、ピンク色の桜を見上げた。 -
かんてんぱぱツツジ

伊那市西春近の伊那食品工業では、早咲きのツツジが咲き始めた。
本社社屋の隣で淡い紫色の花を咲かせているのはエゾムラサキツツジ。4縲・月に開花し、開花後に葉が繁るのが特徴。主には北海道などに分布している。
広域農道の反対側にあるかんてんぱぱガーデンでも、ミツバツツジ、クリーム色のヒカゲツツジなどが見ごろ。
5月前には、朱色やピンク色をしたヤマツツジも咲き始めるため、さまざまな色の移り変わりが楽しめるという。 -
【登場】伊那北高校校長
千村重平さん(58)
相手を信頼し、自分も相手から信頼されなければ本音で話すことはできない。人と人との信頼関係が一番大切竏秩B
初任地は地元の木曽高校。松本県ヶ丘、長野西などで教鞭(べん)をとり、県教育委員会の教学指導課へ。その後、松本蟻ヶ崎で校長を務め、教学指導課の係長をとなった。専門は理科。
勉強にしても部活にしても、生徒と共に過ごし、何も飾らずに向き合うことができる日々は楽しく、天職だと実感した。部活動では、山岳部の顧問も務めた。最初は全く知らなかった山登り。一切合切を教えてくれたのは生徒たちだった。マイナス20度にもなる3千メートル級の冬山など、死と隣り合わせの世界。だからこそ、いつも一生懸命な生徒たちの姿がそこにあった。
自分たちの思いを伝えたい竏窒ニ昨年の文化祭で田中知事に自分たちの思いのたけをぶつけた伊那北高校の生徒たちについては「こういうことは若い人にしかできない。若さとしての特権はどんどん主張してほしいし、ぼくらはそれをバックアップしたい」と期待をかける。
「教育というと『教え込む』というイメージがあるが、そうでなくて本人が持っている無限の可能性をいかにして引き出してあげるか。喜びを共に分かち合うだけでなく、悩んでいる生徒がいるなら、一緒になって悩む。それが必要なんです」。
松本市在住。家族は妻、娘2人。現在は伊那市へ単身赴任中。 -
新伊那市かるたを発売へ

伊那市書店組合(小林史麿組合長、4人)は今月下旬、「新伊那市かるた」を発売する。子どもから大人までが楽しめるかるたで、3千セットを用意。市内の書店で注文を受け付けている。
新市誕生記念の冠イベントの一つ。3月31日の高遠町・長谷村との合併を機に、誇り高きふるさとを知ろうと制作した。
読み札は五十音の46札に「新・伊・那・市」の4文字を加えた。中央・南アルプス、高遠城址公園コヒガンザクラ、孝行猿、伊那部宿、ザザ虫などが題材。「あ 朝夕に駒・仙丈を仰ぎ見て」「い いっせいに駆け出す春よ、やきもち踊り」…と詠んだ。絵札はオールカラー。解説書とかるためぐり地図付き。
市外から注文も入り、反響の大きさをうかがわせる。
小林組合長は「かるたを通じて身近な郷土の歴史や自然、行事などを知り、訪ねることで、心の融和が図られるのでは」と話す。
価格は2千円。
注文はコマ書店(TEL78・4030)、上条書店(TEL72・2028)、小林書店(TEL72・2685)、草思堂書店(TEL94・2080)、ニシザワデパート(TEL78・3811)などへ。 -
業務上過失致死罪の男性 禁錮2年6月
横断歩道を渡ろうとしていた女性=当時(75)=を車ではね、死亡させた罪に問われていた伊那市西春近、無職溝上康時被告(81)に対して地裁伊那支部は13日、執行猶予3年、禁錮2年6月(求刑禁錮2年6月)の判決を言い渡した。
起訴状によると、普通貨物自動車を運転していた溝上被告は昨年10月8日午前9時55分ころ、宮田村の県道交差点を駒ヶ根方面から伊那方面へ直進している時、女性をはねた。この事故で女性は脳挫傷などのけがを負い病院に搬送されたが同月14日午後5時05分ころ、死亡した。
同被告は横断歩道の前方約57メートル地点で女性が歩道脇に立っている姿を確認しているにもかかわらず、女性が横断しないものと思い、時速30キロで直進。折から横断を開始した女性を前方約7メートル地点に迫ってからようやく認め、ブレーキをかけたが、車両左前部を衝突させ、路上に転倒させたもの。 -
書道家 池上信子さん(74) 伊那市日影

伊那公民館で隔週開いている書道教室の講師を26年間務めている。2年ごと新しい生徒を迎える同教室では、これまでに約400人以上の教え子が卒業している。
「生徒たちのとの出会いはすばらしい。生徒数は年々少なくなっているが、むしろ少ない分、心のつながりが出てきている。一人休めば『今日はさみしいね』という感じ。生徒さんと出会うのが私の生きがいになっている」
教室の2年間は筆の持ち方、線の書き方、墨のすり方などの基本を3カ月間、丹念に学ぶことからはじまる。文字を書きはじめるのはそれからとなる。
教える文字は、流れがあって、全体的に見た時に優美さがあるという「かな」が中心。日本にしかない、かな文字を伝承していかなければ竏窒ニの思いで伝え続けている。
これまでに12期生が巣立っていった。まだまだ勉強したい竏窒ニ、各期ごとのメンバーでつくるグループの学習の面倒も見ている。
「一つの方向に向かって頑張ろうと自分を高める姿。心も豊かに、身体的にも成長していく生徒たちを見ていけることはうれしい」
書道との出合いは弥生ヶ丘高校時代。担任が、かなを得意とする書道の教師だった。「実用的な字が書けなくはいけない」と毎週、自分の住所・氏名、学校名などを習字紙に記す宿題で、細字を嫌というほど書かされたという。
「字に対する教えは厳しかった。でも、厳しい分やった分の努力は認めてくれたことがうれしかった」
高校を卒業して、中学校の体育教諭になったが、習字の心得があると赴任先の校長に見初められ、生徒たちに書道も教えるはめに。指導する立場になるのでもっと勉強しなければと、書道塾へ通うようにもなったと振り返る。
本格的に学ぶようになったのは、同じ教師だった夫と結婚して退職してから。長野市で一緒に暮らしていた6年間や地元に帰ってきてからも、多くの師の下で勉強。子育てで忙しい時期も「書きたい。書きたい…」という思いは強かったという。
自分のやりたいことを認めてくれていた夫との思い出がよみがえる。器用な夫は退職後、表具師として作品を表装に仕立ててくれていたという。しかし、自分を支えてくれていた夫は61歳の若さで亡くなった。最期まで作品を仕立てようとしていたという。残った表装は7縲・本。宝物になっている。
自分を支えてくれているのは「仏になった夫」や、生徒など周りの存在。「残された人生の中で、自分の作品を多く残していきたい。書きたいものも、まだまだ沢山ある」と意欲をみせる。
現在は書道教室の生徒や卒業生らによる展示会(5月19縲・1日・県伊那文化会館)の作品づくりの指導に追われている。初心者から20年間以上続けているベテランまでの総勢70人余が出品。「一つのことに協力して取り組める教え子たちばっかり」と作品を添削する筆が生き生きと滑っている。 -
伊那北小学校で交通安全教室

伊那市の伊那北小学校で13日、2・4年生を対象とした交通安全教室があった。2年生は通学路を歩きながら、4年生は自宅から持ってきた自転車を用いて交通マナーを学び、交通安全の意識を高めた。
4年生は校庭で、地元の交通安全協会員やPTA、学校教諭らから、自転車の発進、停止方法、道路の横断方法などを学習。「右側を車が通るので、停止後は地面に左足からつく」「右左折や横断時は自転車を降りて渡る」などの注意を受けながら練習に励んだ。
校庭での模擬練習を終えるとさっそく、学校近くの車道を走行。児童たちは教わった通りに「ペダルに足を乗せて、左右の安全を確認」などと声に出して、一つひとつの動作を確認しながら、安全運転を心がけた。
2年生は安協女性部員などと、自分の地区の通学路を歩き、交通量が多い道路などの危険箇所も皆で確認。横断歩道を渡る時は「よく見て、よく手を上げて渡る」と教わっていた。
地元安協・北部地区会長の三澤勝美さんは「今日学んだことを思い出して、交通ルールを守って事故にあわないように」と児童たちに呼びかけた。 -
上下水道使用料納入通知書のバーコードを変更
伊那市は、上下水道使用料納入通知書のバーコードを4区分から1区分に変更した。コンビニエンスストアで使用料を納入する際、待ち時間を短縮することによって住民の利便性を図る。また、高遠町、長谷でもコンビニでの収納が可能となった。
バーコードは、3月検針分料金(2、3月使用量分)から変更。これまで地区、氏名、金額など必要事項を区別していたが、伊那市・高遠町・長谷村との合併を機に、1区分に切り替えた。上伊那では初めての採用で、契約会社を通し、コンビニでのバーコード読み取りテストを済ませている。
収納業務は市役所、総合支所のほか、金融機関、郵便局でも対応。コンビニは02年10月から旧伊那市で取り組みを始めた。受け付け時間に限られない、自宅の近くで支払えるなど利用者は年々増加。現金納付に対し、コンビニは02年度の17%から、04年度には27%に上がった。05年度は30%を超える見込み。
市は、コンビニなどで納入できることを知らない人がいるため、市報などで広くPRし、徴収率アップにつなげたいとしている。
使用料は高遠町が5月から隔月検針、隔月徴収とし、長谷が偶数月に検針、奇数月に徴収する。 -
桜の木の下で伊那節まつり
伊那市中央区の伊那公園にある石碑「伊那節発祥之地」前で12日、第47回伊那節まつりがあった。伊那節を後世に伝えようと、咲き始めた桜をバックに、伊那節保存会員14人が伊那節を踊った。
まつりには、伊那商工会議所議員、桜愛護会員ら約40人が参加。
向山公人会頭は、権兵衛トンネル開通、伊那市・高遠町・長谷村との合併を新たな交流のスタートと受け止め、伊那節が歌い継がれるよう願った。
伊東義人市長職務執行者も「高遠城址公園、伊那公園、春日公園を結びつけるなど、全市でつながりを持ち、通年観光にしていくべき」と述べた。
そのあと、着物姿の伊那節保存会員が「伊那の華」と題した振り付けで伊那節を披露。太鼓や三味線、歌に合わせて踊り、公園内に訪れた夫婦連れなどの目を楽しませた。
石碑は60(昭和35)年4月、伊那節発祥の地を広く知ってもらおうと市・伊那商工会議所が建立。昨年、石碑の文字が薄れたことから刻み直した。
※ ※
伊那公園桜愛護会(伊藤一男会長)は16日午前11時縲恁゚後4時、伊那公園で「太鼓演奏を聴き・カラオケを楽しむ会」を開く。
当日は午前11時から、太鼓演奏で、地元の小出太鼓、伊那太鼓、創龍太鼓が出演。午後1時からはカラオケを楽しむ会で、飛び入り参加できる。
市によると、公園内にソメイヨシノ約270本があり、見ごろは18日と予想している。 -
伊那市美篶の上川手区 「地域の子どもを守り育てる会」発足

伊那市美篶の上川手区(北原伍区長)は11日夜、地元公民館で地域の園児、児童、生徒の登下校時の安全などを見守る「地域の子どもを守り育てる会」(春日照子会長)の発足式を開いた。会場に集まった約100人の地域住民は、子どもたちが健やかに育つ環境をつくっていくことを決意した。
同会はパトロールという管理的な取り組みではなく、区民総参加で「普段着のスタイルで子どもの安全を見守る雰囲気づくり」などを目的に活動。具体的には、登下校時間帯に合わせて区民が・ス子どもたちの見える場所で・ス農作業や散歩などをして安全を確保する。
美篶地域では昨年末、笠原地区で初めて「地域の子どもを守り育てる会」が発足。同会会長で美篶青少年育成会の畑房男会長は「他地域では学校ごとにパトロール隊を立ち上げているが、美篶の場合は住民が立ち上がり、美篶全体に広がっていけばと考える」と呼びかけた。
あいさつに立った美篶小学校の片山寛教頭は「美篶地域の12地区が一体となり、自分の地区はぜったい安全に通学させてやるという、連帯感をつくってほしい。それが世の中を変えるきっかけになる」と期待した。 -
諏訪形寿健康体操クラブ本年度活動開始

伊那市西春近の「諏訪形寿健康体操クラブ」(会員25人、野溝弘文会長)は12日、本年度の活動を開始した。
市の高齢者介護課の「高齢者向け筋力向上トレーニング教室」として04年に開講。市の教室指導修了後も参加者の要望にこたえ、地区活動の一環として継続している。
高齢者や軽度の障害を持つ人のうち、簡単な筋力トレーニングで日常生活の維持・改善が期待できる人を対象とし、平均年齢は約75歳。参加者は年々増加している。4月縲・1月に活動している。
初日は、伊那保健センターのインストラクターの指導のもと、筋力トレーニングや有酸素運動を組み込んだ体操に挑戦。仲間と共に、体力づくりを楽しんだ。
昨年12月にあったアンケートでは、約75%が体操を始める以前より「体調が良い」と回答。楽しいので継続したい竏窒ニする意見も多かった。 -
かんてんぱぱガーデンカタクリ咲く

伊那市西春近のかんてんぱぱガーデンでは、春の山野草が咲き始めた。約200株あるカタクリは、このところの暖かさで一気に開花し、見ごろを迎えている。
今年のカタクリは、開花が例年より1週間から10日ほど遅かったため、ほかの山野草と開花時期が重なった。 現在見ごろを迎えているのは、ミズバショウ、ワサビなど。青紫色の花をつけるタツタソウ、葉がうちわに似ているイワウチワなども咲き始め、園内は春の色彩で溢れている。
同園には80種類以上の山野草があり、今後は、シラネアオイ、ニリンソウ、クロユリなどが、徐々に咲いていく。1週間ほどすれば、別の種類の花が咲き始めるという。 -
伊那ビジネス専門学校で入学式 目標に向かってまい進

伊那市狐島の伊那ビジネス専門学校(三沢岩視理事長)で12日、06年度の入学式があった。上伊那を中心に飯田市から生徒5人が入学し、それぞれの学校生活をスタートした。
入学生代表で堀内志織さん(18)=辰野町=が「自覚と誇りを持って校則を守り学業に専念する」と宣誓。三沢理事長は「すばらしい職場に就職できることを期待する」と式辞し、三沢清美校長は「大きな目標に向かってまい進してほしい」と訓辞を述べた。
新入生5人は情報経理学科(2年制)に2人、OAビジネス学科(1年制)に3人が入学。
伊那ビジネス専門学校は個性を重視しながらビジネスマナーを心得た社会人を育成することが理念。少人数教育でパソコンや簿記などを学び、就職に有利な各種資格を習得することができる。 -
アフガニスタンで教育支援などに取り組む女性を招いた報告会

アフガニスタンにある教育の現状を知り、自分たちの教育のあり方を改めて考えてほしい竏窒ニ5月28日、女性や子ども医療、教育、自立支援に取り組むアフガン女性・ソハイラさんを迎えた対話会が、伊那市駅前ビル・いなっせである。
ソハイラさんは、アフガン女性の自立を目指して1977年に発足した「アフガニスタン女性革命協会(RAWA)」の一員で、現在は戦禍や貧困に追われた子どもや女性の教育支援をしている。
会の主催する尾崎真理子さん(24)は、日本からRAWAの支援するグループに所属しており「自分の地元の人にもアフガンの話を聞いてほしい」と今回の対談を企画した。
大学卒業後、アフガニスタンへのスタディーツアーに参加。米軍の侵攻と共に一時的に集中した各国のNGOは現地から徐々に撤退し、現地には再び貧困に困窮する人たちがいた。お金だけではない、支援の形があるのではないか竏窒サう考え、発展途上国での教育支援にも携わってきた。
尾崎さんは「アフガンの現状を通して、そもそも教育とは何のためにあるのかなどを考えてもらえるような対談にしたい」と話す。
対談は市民団体の交流イベント「市民バザール」の中で実施する予定。現在は対談の企画・運営をする実行委員も募集している。
問い合わせは伊那国際交流協会(TEL72・7706)、または(TEL090・3536・3211)尾崎さんへ。 -
みはらしファームでアスパラ狩り開始

畑に生えた新鮮なアスパラの収穫を楽しんでもらおう竏窒ニ11日、伊那市西箕輪の農業公園・みはらしファームは、観光客を対象としたアスパラ狩りを始めた。愛知県から訪れた15人は、ハウスの中で大きく成長したアスパラを袋いっぱいに詰め込んだ。
アスパラ狩りは、6月下旬までのイチゴ狩りに代わる収穫体験イベントとして企画。本年度はツアー客を中心に7月まで続ける。ツアー客の要望にこたえ、アスパラ狩り体験を実施したことも過去にあったが、本格的な導入は本年度が初めて。
400円で8センチ×30センチの袋いっぱい詰め込むことができる。アスパラ狩りのほ場は8つ。約1週間のサイクルで新しいものが生えてくるという。
この日は、アスパラの試食も準備され、参加者は「甘い」「新鮮だから香がいい」などと話しながら味を楽しんでいた。
アスパラは今が旬。上伊那産は甘味があって柔らかく、さまざまな調理方法で楽しむことができる。 -
旧井澤家に花の写真で春を演出 「青葉の会」が展示会

ペアーレ伊那の写真講座生徒の有志でつくる青葉の会(中澤二郎会長)の展示会「花の写真展」は20日まで、伊那市西町の旧井澤家住宅で開いている=写真。
新伊那市誕生を記念した企画で、同所での展示は初めて。桜のシーズンに合わせ、会員16人が一人一点づつの花の写真を出品。色彩豊かな作品のそれぞれが、会場をあでやかな雰囲気にしている。
ウズイスカグラ、クリスマスローズ、セツブンソウ、ザゼンソウ、コブシなどの写真を展示。桜の写真が多く、駒ヶ根市東伊那や中川村美里のシダレザクラ、伊那市高遠町のタカトオコヒガンザクラなどの名所で撮影した作品がある。
会員は伊那市を中心に上伊那から集まる60代前後の男女。ペアーレ伊那の写真講座では、松本大学研究員の建石繁明さん(71)=同市西町=を講師に招き、週一回の学習を通して技術を磨いている。
建石さんは「写真を見てもらい、春が到来した感じを味わってもらえれば」と話している。
火曜日休館。午前9時縲恁゚後5時。入館料は大人(高校生以上)200円、小中学生100円。 -
伊那郵便局 赤バイクで交通安全パレード

伊那坂下区の伊那郵便局(藤原良明局長)は11日朝、「春の全国交通安全運動」(6竏・5日)に合わせ、赤バイク(郵便配達用バイク)による交通安全パレードをした=写真。
前年に続いて2回目となるパレードは、伊那署管内の郵便局で唯一。同署の協力でパトロールカーを先導に、交互2列に隊を組んだバイク22台が小雨が降る中、同局を発着点に伊那北駅から伊那市駅までの間(約2キロ)を走り、地域住民に交通安全を呼びかけた。
局は04年度、4件の交通事故を起こしてしまったのを契機にパレードをはじめた。前年度は局員の交通に対する安全意識が向上され、事故は0件に抑えられたという。
パレード前の出発式で藤原局長は「交通事故を発生させないという意気込みで市内をパレードしてほしい」とあいさつ。伊那署の小嶋惣逸署長は「地域の安全パトロールなど、皆さんが日ごろから総力をあげて取り組んでくれていることがありがたい」と感謝した。
同局貯金保険課の宮下豊文総務主任は「絶対に交通事故を起しません。子どもが安心して通学できる環境をつくることを誓います」と決意表明した。 -
パンジーや芝桜などの苗を販売

伊那観光協会は11日、駅前再開発ビル「いなっせ」多目的広場で花の苗を販売した。地域の活性化を図る「花の路(みち)プロジェクト」の一環。
観光協会は04年から、花を植えたプランターの設置などに取り組んでいる。独自で事業を進める自治区も出始め、花づくりを広げようと一般向けに販売した。
苗はパンジー、芝桜、ペチュニアなど5種類の870個を用意。雨降りにもかかわらず、販売開始時刻から女性らが訪れ、黄や紫、オレンジなど色とりどりの苗を買い求めた。
上荒井の女性は、色違いの花を選び「ちょうど花を植えようと思っていたところ。プランターで飾りたい」と話していた。 -
伊那市の西春近公民館のコヒガンザクラ見ごろ

地元では伊那市内でも早咲きと知られる桜の名所、西春近公民館南児童公園のコヒガンザクラが七分咲きとなり、見ごろになっている。夜はぼんぼりに光がともり、幻想的な風景が広がっている。
公園には樹齢80年くらいとなるコヒガンザクラの古木2本など、計8本が植えられている。本年は前年より4日ほど早い、3月30日に開花した。
花の色は濃いピンク色で、枝はしだれ桜のように垂れているのが特徴。窓から毎日眺めている公民館関係者らは「心豊かに仕事をさせてもらっています」と笑顔。天候がよい日は、近くの園児や子ども連れの家族が立ち寄るという。
ライトアップは連日午後5時30分縲・時30分、観桜期中は続く。公民館では「今週の土・日曜日ごろには満開になるのでは」と、多くの人が花見に訪れることを期待している。 -
地域福祉推進セミナー
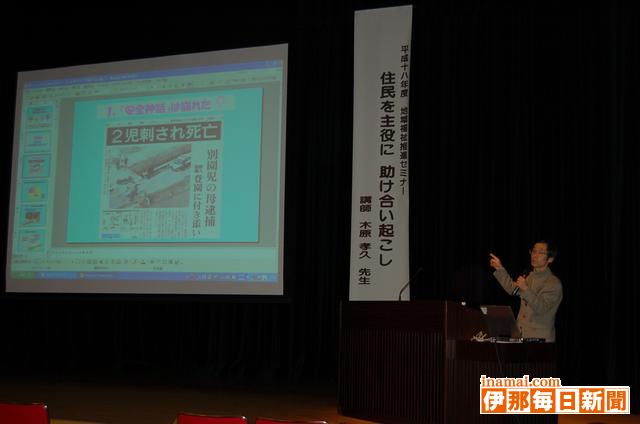
ご近所同士の助け合いから地域福祉を考えよう竏窒ニ8日、05年度地域福祉推進セミナーが伊那市駅前ビル・いなっせであった。地区社協やボランティア関係者、民生児童委員など約50人が集まり、防災、防犯、予防介護につながる助け合いの重要性を学んだ。市社会福祉協議会主催。
講師の木原孝久さん(住民流福祉総合研究所主宰)は、近隣住民の面的つながりが被災者救済や防犯に果たす効果を示し「こうした被害に遭いやすい要支援者を近所で支えることが重要」と指摘。 しかし介護保険導入以降は「対象者への対応はプロがすべき」という流れがあり、高齢者が近所から疎遠となってしまっている現状を語った。
一方、近所の地域サロン、趣味の場などで認知症高齢者を受け入れている事例を紹介し「その人がやりたい事をし、行きたい場所へ行けることは『その人らしい人生』をおくることにもつながる」とし、生きる意欲や介護予防への効果を示した。
しかし、住民同士の助け合いは『助けて』という当事者の声を受けて発生するため「助けられる側も周囲へ困っていることを発信していくことが重要」と呼びかけた。 -
青島堤防桜保存会が「さくら功労者」で表彰
伊那市美篶青島の三峰川右岸堤防沿いに植わる桜並木を守る青島堤防桜保存会が、財団法人日本さくらの会から桜の保存や愛護運動などに功績のあった「さくら功労者」として表彰を受けた。
堤防沿いの桜は、洪水時の堤防決壊防止などのため、大正時代に約1800本が植えられたが、昭和後期に砂利採取の車両道路に使用することから大半が撤去されたという。現在はソメイヨシノ約40本だけが残っている。
同保存会は96年、青島区全92戸の区民で発足し、病害虫防除や施肥、せん定などの手入れをして管理に当たり、桜の保護活動に尽力。観桜期には見事な花を咲かせ、多くの人に親しまれている。
橋爪正昭会長(62)は「先代が育てた桜を区民全員で守り、その努力が表彰されてうれしい。これからも保存はもちろんだが、増やしていくこともしていけたら」と話している。 -
マレットゴルフの季節「大芝高原」「はびろ」今季オープン

南箕輪村の「大芝高原マレットゴルフ場」と伊那市西箕輪の「マレットパークはびろ」が9、10日、それぞれ今季の施設運用を開始した。
村開発公社が運営する大芝高原マレットゴルフ場では9日、村を代表する愛好者グループ「南箕輪マレットゴルフ同好会」ら約80人を招き、オープンセレモニーをした。
式典で村開発公社の山崎文直常務理事が「コース上ですばらしい快音が聞こえることを願う。皆さんが仲良くプレーできることを期待する」とあいさつ。同好会の池上辰夫会長は「自分たちで遊ぶマレットゴルフ場なので、自分たちできれいに使っていきましょう」と呼びかけた。
山崎常務理事と池上会長が始球式で快音を響かせると、会員らはさっそくオープニング大会を開いた。
大芝高原マレットゴルフ場は「赤松」(18ホール)、「桧」(18ホール)、「白樺」(9ホール)の3コース。プレー料金は一日200円。年間券は4千円。道具貸出料金は300円(ボール100円、スティック200円)。営業時間は午前8時30分縲恁゚後5時。
昨年度は4月12日縲・2月4日まで営業。利用者は2万9873人。年間券購入者は410人だった。
マレットパークはびろは「天竜」(18ホール)、「仙丈」(18ホール)の2コース。プレー料金は一日300円。年間券は5千円。道具貸出料金は1セット100円(ボール、スティックどちらか一方でも)。営業時間は午前8時30分縲恁゚後6時。
昨年度は4月上旬縲・1月下旬まで営業。利用者は2万1530人。年間券購入者は237人だった。
同好会オープニング大会の結果は次に通り。
▽男性 (1)戸塚久雄83(2)池上辰夫、萩原文博86(3)伊東幸人、羽生剛88(4)倉田喜隆、松本孝志89(5)池上安雄90(6)福田岩雄、三沢一二三、小倉孝一91
▽女性 (1)北沢ヒデ子86(2)伊藤茂美87(3)伊藤久子、倉田さだ子、武村八千江89(4)原幹子、大槻キサエ93(5)深見フサエ94(6)根橋栄、小沢かおる95
ホールインワン 酒井精治、山口実子 -
若年者を対象とした就職相談室「サロン・ド・お仕事」を開設
ニート、フリーター問題を解消し、地域労働力の確保につなげよう竏窒ニ伊那市は11日から、若年者を対象とした就職相談室「サロン・ド・お仕事」をいなっせ4階の402会議室に開設する。
県、NPOなどが連携する松本市の就職相談室「ジョブカフェ信州」の派遣アドバイザーと市役所職員が常駐し、若年者の仕事に関する不安や悩みが解消されるよう、相談を受ける。職業紹介へとつながる状況になった場合は、ハローワーク伊那と連携して担当職員を配置するなどして相談しやすい環境づくりを進める。
県内でもいくつかの市町村でこうした取り組みを進めているが、相談実績は年々増加しているという。
対象は30代程度までの若年非定職者。開設は毎月第2火曜日の午後1時縲恁゚後4時半。 -
伊那部宿を考える会 旧井澤家に桜植樹

伊那部宿を考える会(田中三郎会長)は9日、伊那市西町の旧井澤家住宅敷地内に、新伊那市誕生を祝った記念事業として、エドヒガンザクラなどの苗木3本を植樹した。会員約10人が、小さな苗木が大きな幹に成長することを願いながら丁寧に植えた。
旧井澤家住宅近くにある、40年ほど前までは桜の名所として知られていた「尾花ヶ崎」の花の再現も目的とする。会員によると、同所は約650年前の南北朝時代に活躍した宗良親王が歌を詠んだ場所としても有名だという。
エドヒガンザクラはタカトオコヒガンザクラに似ていて、花びらは小さく、ピンク色が濃いのが特徴。苗木の大きさは3メートルほど。高遠町で桜の苗木を育てている人から譲り受けた。
会員の一人は「花が見られるのは3年後かな。せっかく植えたのだから、良い木に育って皆でお花見でもできればうれしい」と話していた。 -
伊那市身体障害者福祉協会・合併創立総会

伊那市・高遠町・長谷村の3市町村合併により統合した伊那市身体障害者福祉協会は9日、市福祉まちづくりセンターで合併創立総会と記念式典を開いた。式典には会員ら約90人が出席。新会長に選ばれた竹松猛会長=日影=は、新体制になった身障協への協力を呼びかけた。
式典で竹松会長は「3市町村合併により、身体障害者手帳の交付者は約2300人を超えた。会員は増えたが、入会率は32%と厳しい状況。これからは事業を活発化させ、魅力ある協会にしなければ。皆さんと支えあって、伊那市が全国一住み良い街と言われるように頑張っていきたい」とあいさつした。
伊東義人市長職務執行者は「合併により、今までの福祉(サービスの質)が落ちないよう、協力していきたい。今後、市でも重点的に支援していきたい」と話した。
総会では役員選出や、会員相互の親ぼく会や障害者スポーツへの積極的参加などの本年度事業計画など3議案を承認、可決。役員は副会長に西村周市さん=高遠町上山田=、加藤伸一さん=原新田=、下島忠孝さん=中央区=らが選任された。 -
県無形文化財・ス奇祭・ス「やきもち踊り」16日

・ス奇祭・スとして知られる山寺区上村の白山社八幡社合殿の例祭「やきもち踊り」(16日)を控えた区民約30人は9日、御神木に巻かれた古くなったしめ縄を作り直した。
毎年、例祭の約8日前にしめ縄を作り替えるのが風習。この日は区、氏子総代会、やきもち踊り保存会から参加者が集まり、長さ11メートルのしめ縄、5本のしめ子などを協力して制作した。
わらの束をねじりながらなっていく作業はひと苦労。参加者は「そーりゃ」と掛け声を合わせて気合を充てん。なうメンバーを交代しながら、約2時間で縄を完成させた。
氏子総代会長の笠松保さんは「区民にとってしめ縄作りは、一つの風物詩になっているね。例祭を終えてから、皆田んぼの仕事を始める」と話した。
県無形文化財である「やきもち踊り」は、酒盛りと踊りを繰り返し、踊りが終わると鳥居から一気に走り出す…。江戸時代、伊勢参りに行った人たちが習い、例祭で踊ったのが始まりと伝えられている。
しめ縄は10日、伊那北地域活性化センターきたっせで、例祭に用いる道具などと一緒に厄払いをして一時保管。例祭前日の15日、市指定天然記念物のケヤキの御神木に巻かれる。例祭は16日正午から。 -
天竜川や商店街にこいのぼりを飾りつけ
伊那商工会議所商業連合協議会は10日、恒例事業「まちいっぱいこいのぼり」を展開している。天竜川にかかる伊那市の大橋上流などにこいのぼりを取り付け、花見などで訪れる観光客らを楽しませる。5月9日まで。
本年は権兵衛トンネル開通、新伊那市誕生で、例年以上に県内外から観光客が来ると見込まれ、新市のPRや商店街のにぎわいを演出する。
天竜川では、花火のナイアガラ用ワイヤを活用。入舟駐車場から対岸の中央区までの220メートル区間に、黒や赤、青など大小さまざまのこいのぼり45匹が連なる。
中心商店街(通り町縲恃ェ幡町)にもミニこいのぼり約300匹を飾り付けた。
91/(金)
