-
国際ボランティアに参加した人達の写真展

大学を休学したり仕事を辞めるなどして国際ボランティアに参加した人達の写真展が13日から、南箕輪村の信州大学農学部で開かれています。
ボランティアは、世界各地で合宿型のボランティアを行っているNGO、NICEが主催したもので、全国から16人が参加しました。
信州大学農学部4年生の古川博一さんもその1人です。
古川さんは、大学3年の夏から7か月間、インドとアメリカに渡りました。
現地では、飲み水を確保する為のタンクを作ったり、ダムを作る作業をしました。
写真展は、活動について知ってもらおうと開かれているもので、会場には16人が現地で撮影した写真およそ600枚が展示されています。
写真展は、15日木曜日まで信州大学農学部で開かれています。 -
地震の影響で飯田線に遅れ
13日午後1時頃、岐阜県を震源とする地震がありました。
この地震で、JR飯田線が天竜峡、七久保間で徐行運転となり上下線の一部で20分以上の遅れがでました。
JR東海によりますと、地震の影響で、天竜峡、七久保間が徐行運転となり、上下線の一部で20分以上の遅れがでました。
14日午後1時1分に発生した地震は岐阜県美濃東部を震源とするもので、震度は、伊那市と箕輪町で3、南箕輪村が2となっています。
各市町村、消防によりますと、この地震による被害はなかったという事です。 -
インフルエンザ流行し始め 長野県注意呼びかけ
長野県は、インフルエンザが流行し始めたとして感染の拡大防止につとめるよう呼びかけています。
県の発表によりますと、先週5日から11日までの一医療機関あたりのインフルエンザ患者数は、県全体で1.16人となっています。これは、流行開始の目安となる1人を超える数となっています。
県では、発熱などの症状がみられたら早めに休養をとる事、外から帰ったらうがい、手洗いをする事、マスクを着用する事など、感染拡大防止に努めるよう呼びかけています。
また、県は14日、ノロウイルス食中毒注意報を発令しました。
ノロウイルスは主に冬に流行する事から、感染予防として、手洗い、食材の十分な加熱などをするよう呼びかけています。 -
伊那北高生と留学生が交流

オーストラリアやタイなどの留学生が、14日伊那市の伊那北高校を訪問し、生徒と交流しました。
留学生は、公益財団法人AFSが行っている東アジアの青少年交流で日本を訪れました。
オーストラリアやシンガポール、ニュージーランド、タイの15歳から17歳の高校生です。
9日に日本に到着し、飯田、下伊那などでも高校生と交流してきました。
14日は、伊那北高校を訪れ、授業を見学したほか、ゲームで交流を深めました。
全員が自己紹介したあと教室の中央に幕を張り、降ろした瞬間に相手の名前を呼び合うゲームで楽しみました。
この事業は東アジアの連帯を図る土台づくりのほか、好意的な対日感情を持ってもらおうという狙いもあります。
留学生は15日、駒ヶ根市を訪れその後帰国する事になっています。 -
江田慧子さん伊那市に絵本を寄贈

絶滅危惧種に指定されている蝶のオオルリシジミの研究をしている信州大学大学院博士課程2年の江田慧子さんは13日、伊那市に絵本を寄贈しました。
13日は、江田さんが伊那市役所を訪れ久保村清一教育長に絵本30冊を手渡しました。
江田さんは絶滅危惧種に指定されている蝶、オオルリシジミの生態について研究しています。
その生態について多くの人にしってもらおうと絵本を 今年9月に出版しました。
寄贈した絵本は「ちょうちょのりりぃ オオルリシジミのおなはし」です。
主人公のりりぃが困難にあいながらも成長していく物語です。
久保村教育長は「自然に興味をもってもらえる絵本。活用させていただきたい」と話していました。
寄贈された絵本は、市内の小中学校や図書館などに贈られることになっています。 -
雇用・生活支援ワンストップサービス
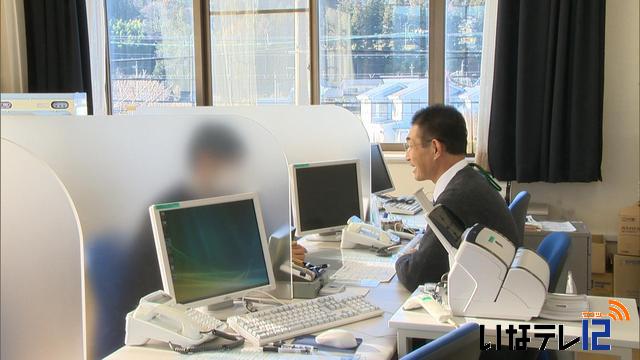
年末年始を前に伊那保健福祉事務所は13日、生活困難な人達を対象としたワンストップサービスを行いました。
雇用、生活支援ワンストップサービスは、仕事の紹介に加え、生活保護や住宅手当に関する相談など仕事を失った人への生活支援を行うもので、県内5か所で行われています。
伊那市のサンライフ伊那内にある伊那緊急求職者サポートセンターには相談者が訪れていました。
この他、生活福祉資金貸付や多重債務などの相談も行っています。
ワンストップサービスは12月15日も伊那緊急求職者サポートセンターで行われます。
時間は午後1時30分から午後4時30分までとなっています。 -
劇制作に向け聞き取り調査

JR飯田線伊那北駅開業100周年に合わせ、伊那市の伊那小学校の児童が飯田線にまつわる劇の制作に取り組んでいます。
12日は地元の人から当時の話の聞き取り調査をしました。
劇の制作に取り組んでいるのは伊那小学校6年孝組の児童達です。
孝組では、地域の人達に喜んでもらおうと孝組座として劇やダンスなどを毎月発表しています。
伊那北駅開業100周年に合わせ、劇を制作し発表する事になりました。
12日は、班に分かれて伊那北駅周辺に住む人達から昔の伊那北駅などについて話を聞きました。
このうち、伊那市で洋服店を営む尾崎晃一さんの店には5人の児童が訪れました。
尾崎さんは「60年前、伊那北駅から乗りきれないほど多くの人が乗車した」など、子どもの頃の思い出を話し、昔と今の伊那北駅の移り変わりを写真で説明していました。
伊那小6年孝組座は、12月21日に伊那市のきたっせで劇を発表します。 -
伊那西部保育園 休園へ

伊那市は、伊那西部保育園の来年度の入園希望者が定員の半数30人に満たなかったため、来年度から休園することを決めました。
これは13日開かれた伊那市議会社会委員会協議会で報告されたものです。
伊那市では今月、7日付で地元の区長をはじめ保護者会などに保育園休園の方針を文章で送りました。
伊那市によると11月30日まで行った伊那西部保育園の入園希望者数は来年度の進級園児を含む12人でした。
市では、定員の半数の30人を下回り、健全育成や効率的な保育運営などが困難とし休園を決めました。
市では、今後5年間、入園希望者が30人以上にならなければ廃園とする方向です。
伊那西部保育園の在園児7人については来年度から入園する保育園の希望をとっているということです。
議員からは、「伊那西小学校との連携についても考えていく必要がある」などの意見が出されました。
伊那市では16日に、保護者を対象とした説明会を開く予定です。 -
満光寺で雪吊り作業

本格的な冬の訪れを前に伊那市高遠町の満光寺で13日、境内の松を雪から守る雪吊り作業が行われました。
満光寺の境内には、一目みるだけで極楽往生できるといわれている樹齢500年の松があり、13日はその松を含む3本に、雪吊りが行われました。
作業は、長さおよそ8メートルの支柱を松に対して垂直に立てます。
支柱の上部からおよそ100本の縄をらせん状に垂らし、松に結び付けていきます。
作業にあたった人達は、ロープが絡まないよう、1本1本確かめながら作業を進めていました。 -
グレイスフル箕輪「社員の子育て応援宣言」の登録企業に

箕輪町の社会福祉法人サン・ビジョングレイスフル箕輪は、企業が従業員の仕事と子育ての両立を支援する県の「社員の子育て応援宣言」の登録企業となりました。
13日は、南信労政事務所の増田隆司署長が、グレイスフル箕輪と辰野の施設長3人に登録証を手渡しました。
社員の子育て応援宣言は、従業員の仕事と家庭の調和を図ることで安心して働ける職場の環境作りを進めていこうと、県が平成19年度から取り組んでいる事業です。
グレイスフル箕輪では、有給休暇取得率の目標を80%にしている他、育児休業を取りやすい環境づくりを進めています。
今回登録した企業9社を含む南信労政事務所管内の登録企業数は16社で、県全体では162社となります。 -
JA上伊那などが援助米を発送

JA上伊那などは14日、飢餓で苦しむアフリカのマリ共和国へ援助米、690キロを発送しました。
14日は、JA上伊那の職員など、およそ10人が伊那市美篶にあるJAの倉庫前で援助米をトラックに積み込みました。
JA上伊那では平成11年から飢餓で苦しむマリ共和国に援助米を送る国際協力田運動に参加しています。
送られる米は下川手青壮年部や農業団体労働組合のほかJA上伊那あぐりスクールが休耕田を利用して栽培してきたものです。
今年は、県下15のJAがこの運動に参加し合わせておよそ6.5トンの援助米が集まる見込みです。
援助米が送られるマリ共和国には、サハラ砂漠があり、国土のおよそ7割を占めています。
農業が産業の中心ですが干ばつにより収穫量が少なく、慢性的な食料不足が続いているということです。
援助米は衣類や缶詰などほかの支援物資と一緒におよそ40日かけて船で運ばれるということです。 -
新山山草等保護育成会が奨励賞受賞

伊那市新山でハッチョウトンボなどの保護育成活動を行っている新山山野草等保護育成会は、優れた地域活動を表彰する「中部の未来創造大賞」で奨励賞を受賞しました。
14日は、会員で事務局の筒井弘さんと武村輝雄さんが伊那市役所を訪れ酒井茂副市長に授賞の報告をしました。
会は、伊那市新山で国内で最も小さいハッチョウトンボの保護活動などを行っています。
会員らは、ハッチョウトンボが生息している一帯に木橋をつくることで一般の人たちがトンボの観察をしやすくしたり、草刈りをするなど整備に努めてきました。
中部の未来創造大賞は国土交通省中部地方整備局が実施する地域づくり活動応援事業で、会の活動が特色があり活発なことが評価されました。 -
助産師鹿野恵美さん 母子保健奨励賞受賞

伊那市富県の助産師、鹿野恵美さんが、全国各地で母子保健の発展のために活躍している人を表彰する第33回母子保健奨励賞を受賞しました。この賞の受賞は、長野県からは7年ぶりです。
12日、鹿野さんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞の報告をしました。
この賞は、財団法人母子衛生研究会が、全国各地で母子保健の発展のために活躍している個人を表彰するもので、毎年15人に贈られます。
鹿野さんは、助産師として伊那中央病院に勤務した後、自治体の保健師になりました。
平成20年に助産所を開業した鹿野さんは、「妊婦の気持ちに寄り添いながら、その人らしいお産、安心安全なお産のお手伝いをしている」と話していました。
また、命の出前講座で子どもたちに命の大切さも伝えています。 -
12年間伊那市議会議員を務めた伊那市美篶の・ス嶋利春さん 旭日単光章を受章

昭和62年から12年間伊那市議会議員を務めた伊那市美篶の・ス嶋利春さんは、旭日単光章を受章しました。
12日は、・ス嶋さんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝伊那市長から表彰状が伝達されました。
・ス嶋さんは、大正12年生まれの88歳。
昭和62年から平成11年まで3期12年間に渡り、市議会議員を務めました。
任期中、経済委員会の委員長として、地域経済の発展と観光振興に取り組みました。
平成7年に完成した三峰川右岸農道の開通に貢献し、翌年には伊那市西箕輪のみはらしの湯の建設に尽力しました。
白鳥市長は、「これからも体に気をつけ、地域の為に活躍されることを願います」と話しました。 -
第49回技能五輪全国大会

青年技術者の技能レベルを競う第49回技能五輪全国大会が12日から始まりました。
技能五輪全国大会は、ものづくりや技能の大切さを実感してもらうことを目的に、昭和38年から開かれているものです。
静岡県を中心に行われている今年の技能五輪全国大会には、40種目におよそ1,000人が参加しています。
このうち、フライス盤の競技が南箕輪村の伊那技術専門校で行われました。
競技は、自動車や家電製品の部品を作るのに使われるフライス盤で、4種類の金属部品を作ります。
決められた時間の中で、品質、スピード、見た目などを競います。
会場には、出場者の家族や会社の同僚が訪れ、作業を見守っていました。
技能五輪全国大会は19日月曜日まで開かれます。 -
子ども達が昔の遊び楽しむ

お手玉やコマまわしなど昔懐かしい遊びの体験会が11日、箕輪町の木下公民館で開かれました。
体験会は、木下区青少年健全育成会が毎年開いているもので、今年で11年目です。
会場には、子どもからお年寄りまでおよそ100人が訪れ、お手玉やコマまわし、折り紙など11種類の遊びを楽しみました。
折り紙のコーナーでは、小学生が、大人に折り方を教えている姿もありました。
体験コーナーでは、やしょうま作りが行われ、子ども達は作り方を教わりながら形を整えていました。
木下区青少年健全育成会の木下実会長は「昔の遊びを後世に伝えていきたい」と話していました。 -
皆既月食 伊那でも観察会

満月が地球に覆われる皆既月食が10日、全国各地で観測されました。
伊那市の伊那東小学校の校庭では、伊那天文ボランティアサークル「すばる星の会」が観測会を開きました。
時折雪が舞う中、およそ50人の親子が訪れ望遠鏡を使って月が欠けていく様子を観測しました。
皆既月食は、太陽と地球、それに月が一直線に並び、満 月の状態の月が地球の影に完全に覆われる現象です。
グラウンドでは会代表で伊那東小学校の野口輝雄教諭がスライドを使って説明しました。
午後11時5分から午前0時前まで全て隠れる皆既状態となり火星のような赤い月が見られました。
訪れた人たちは夜空で繰り広げられる天体ショーを楽しんでいました。 -
みろくそば祭り

地元産のそば粉を使った手打ちそばをふるまう、弥勒そばまつりが11日、伊那市高遠町の弥勒多目的集会施設で開かれました。
弥勒そばまつりは、地区内の遊休農地で育てたそばを多くの人に味わってもらおうと地元有志でつくる弥勒そばの会が開いているものです。
会場には、高遠そば伝統の焼き味噌と辛み大根が用意され、訪れた人たちが独自の風味を味わっていました。
弥勒そばの会ではは「多くの人たちに弥勒で獲れたそばを味わってもらえてうれしい」と話していました。 -
年末の交通安全運動はじまる
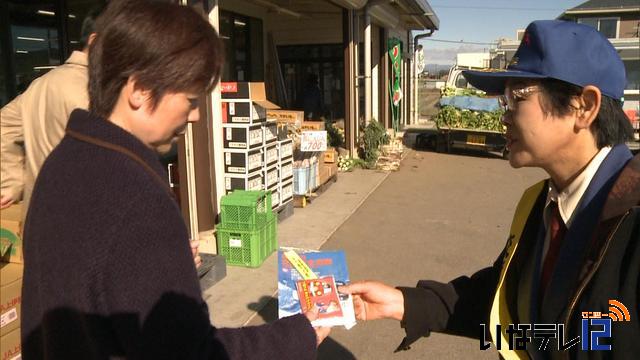
11日から年末の交通安全運動が始まりました。
南箕輪村では交通安全協会や警察など20人が交通安全を呼びかけました。
南箕輪村のファーマーズあじ縲怩ネでは、交通安全協会のメンバー達が買い物客に交通安全を呼び掛けるチラシなどを配っていました。
メンバーたちは、チラシを配りながら「安全運転でお願いします」と呼びかけていました。
伊那警察署管内では、今年1月から昨日までに12件の死亡事故が発生しています。
前の年に比べて5件増となっていて多くが高齢者による事故ということです。
年末の交通安全運動は今月31日にまでとなっていて、高齢者の事故防止、飲酒運転の根絶などを重点目標としています。 -
お天気キャスター森田さん講演
テレビやラジオで活躍しているお天気キャスターの森田正光さんが10日、伊那市の伊那文化会館で講演しました。
森田さんは、フリーのお天気キャスターとしてテレビなどに出演しているほか、講演や執筆活動にも取り組んでいます。
講演は、JA上伊那の生活部会が年1回行っている女性まつりの中で行われました。
異常気象と環境問題をテーマに講演した森田さんは、「異常気象は、30年に1回起こる現象のこと。30年前に比べると異常気象は3倍に増えている」と話しました。
近年増えているゲリラ豪雨については、温度が上がると大雨が降るため、「温暖化が進むとゲリラ豪雨が増える」と説明しました。
さらに、「急速な温暖化が進むと生態系が崩れる」と問題を指摘していました。 -
伊那市消防団東春近分団第3部詰所完成

伊那市消防団の東春近分団第3部の新しい詰所が完成しました。
詰所は、東春近原新田に伊那市が建設しました。
10日、地元区や伊那市、消防団関係者ら38人が集まり、完成を祝いました。
第3部にはこれまで車庫しかなく、老朽化していたことから、今回詰所が建設されました。
木造2階建て、延べ床面積はおよそ89平方メートル、事業費はおよそ1200万円です。
1階は車庫で、オーバースライダーのシャッター、車両の排気ガスを屋外に排出するためのホースなどがあります。
2階は団員が利用する詰所で、物入れや流しが備えられています。
第3部は原新田、榛原、木裏原、暁野の4つの区がエリアで、現在団員は29人です。
完成した詰所は10日から利用するということです。 -
この冬一番の冷え込み

10日の伊那地域は最低気温-5.6度を記録し、今季一番の寒さとなりました。
朝8時、部活などで高校に向かう生徒たちが白い息を吐きながら登校していました。
この寒さは、日本上空に入り込んだ寒気によるもので、冬型の気圧配置となり寒い一日になりました。
伊那地域でも-5.6度を記録し、今季一番の寒さとなりました。
長野地方気象台によりますと、11日以降は、これほどの冷え込みはないものの冬型の気圧配置が続きそうだということです。 -
箕輪町人権啓発講演会

箕輪町人権啓発講演会が10日、箕輪町地域交流センターで開かれ、参加者が高齢者の人権について考えました。
これは、人権のありかたについて理解を深めてもらおうと箕輪町が開いたもので、会場にはおよそ50人が訪れました。
信濃毎日新聞社の論説委員、畑谷史代さんが講師を務め「生き方を受け止める」と題して講演しました。
畑谷さんは、介護現場の取材での体験談を中心に、高齢者の人権について話しました。
東日本大震災で被災した介護施設を取材した畑谷さんは「被災したのは避難できなかった災害弱者。災害弱者への理解を深め、地域でどう支えるかが大切だと感じた」と話していました。
認知症患者への差別については「認知症は恥ずかしいというのは偏見。家族も地域も認知症を正しく理解し、普通に接する必要がある」と話していました。
畑谷さんは「杓子定規でものごとを測ってはいけない。自分はどう老いるのか、身の回りの人権問題とつなげて考えてほしい」と話していました。 -
南箕輪村議会12月定例会開会
南箕輪村議会12月定例会が6日開会しました。
今議会には、5400万円を減額する一般会計補正予算案など5議案が提出されました。
補正予算案減額は国の子ども手当の制度改正により、補助金減額などによるものです。
南箕輪村議会12月定例会は14日、15日に一般質問、16日に委員長報告、採決が行われ閉会する予定です。 -
菓匠Shimizu 清水慎一さんが講演
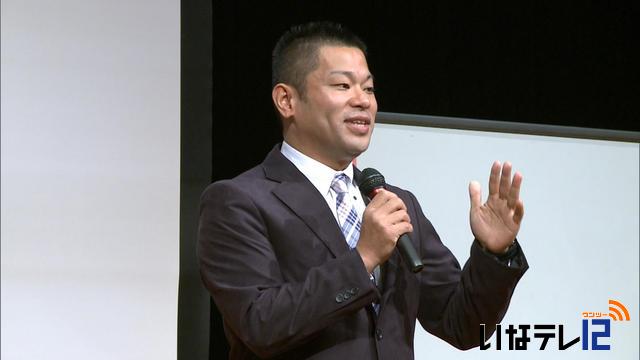
伊那市上牧の菓匠Shimizuシェフパティシエの清水慎一さんが6日、まほら伊那市民大学で講演しました。
清水さんは、昭和50年生まれの36歳です。東京やフランスで修業を積んだのち29歳の時に実家のShimizuを継ぐために、伊那へ戻りました。
菓匠Shimizuでは、子供の夢の絵をケーキにして無料で配る「夢ケーキ」の取組を6年間おこなっています。
家族で夢について語りあうきっかけにしてもらいたいと始めたもので、最初は9件だった申込は一昨年850件になりました。
清水さんは、お菓子を通じてひとつでも多くの家庭に幸せになってもらいたいとの思いで仕事をしているという事です。 -
伊那市地域づくり大賞の最優秀賞に末広財産区環境を守る会

地域の環境整備や福祉活動、伝統芸能の伝承などに取り組んでいる個人や団体に贈られる伊那市地域づくり大賞の最優秀賞に、末広財産区環境を守る会が選ばれました。
6日は、伊那市役所で表彰式が行われ、受賞した9団体と個人1人に白鳥孝伊那市長から表彰状が手渡されました。
守る会の塩原啓治会長は「今後も地域一丸となって取り組んでいきたい」と話していました。
最優秀賞に選ばれた「末広財産区環境を守る会」は、160年ほど前に作られた「六道の堤」の環境保全に取り組んでいます。
会では、雑草や雑木などが生い茂り荒れ果てていた六道の堤の環境を取り戻そうと、間伐や水仙の栽培などを8年前から行っていて、今年度は新たに、桜の苗木を62本植えました。
白鳥市長は「今後も活動を地域に広げ、継続していただきたい」と話していました。 -
クリスマスを前にオーナメント作り

クリスマスを前に、オーナメント作りの教室が9日、伊那市のいなっせで開かれました。
9日は、市内外から女性6人が参加しました。
日用雑貨に色を塗って楽しむトールペイントの講師、幸村淳子さんが、指導しました。
参加者らは、木の板に青や茶色の絵具をぬり、その上にツリーなどの絵を貼り付けていました。
幸村さんは、クリスマスは子どもだけでなく大人もワクワクするもの。小物1つで雰囲気が変わるので飾ってみて下さい」と話していました。 -
まっくん日本一人気のないキャラに

南箕輪村のキャラクターまっくんが日本一人気のないゆるキャラとなり、注目を集めています。
まっくんは、平成6年に大芝高原のキャラクターとして誕生。平成17年から村のキャラクターとしてイベントなどで活躍しています。
ゆるキャラサミット協会が主催するゆるキャラグランプリには、全国各地や、海外から349種類のキャラクターが出場しました。
グランプリはインターネット投票で行われ、1位は熊本県のキャラクターでおよそ28万票、まっくんは68票で最下位でした。
村ではこの結果を受け、ホームペ竏茶W上に特集ページをつくり、今回の結果についてのコメントやまっくんの仲間について紹介しています。
村では、「日本一人気のないキャラクターを売りに、村内外にPRしていきたい」と話しています。 -
寒天作り始まる

冬の寒さを利用した信州の特産品寒天づくりが、伊那市東春近の小笠原商店で始まっています。
伊那市東春近の小笠原商店では、朝早くから寒天づくりに追われていました。
小笠原商店は、10年前に富士見町から伊那市に移り、「糸寒天」と呼ばれる細長い寒天をつくっています。
寒天づくりは、テングサをトコロテン状にし、夜のうち凍らせ日中は太陽にあてて溶かし、水分を抜いていきます。
この作業を何度も繰り返し、完全に水分が抜けたら完成です。
朝の伊那地域は、最低気温0.5度と冷え込み、時折雪が舞う中、従業員およそ10人が作業にあたっていました。
小笠原寿房社長は、「伊那谷の気候は日中と朝晩の気温差がちょうどよく、寒天づくりに適している」と話します。
作業は、3月下旬まで行われ、完成した寒天は都内の和菓子屋などに出荷されるということです。 -
上農生がAEDの使い方学ぶ

AED自動体外式除細動器に関する知識や使い方を習得するための講習会が6日、上伊那農業高校で行われました。
講習会は毎年1年生を対象に行われていて6日は生徒およそ30人が参加しました。
上農は近くの伊那中央病院と連携協定を結んでいることから講師には、中病の医師や看護師を招きました。
講習会ではまず心臓マッサージのほか、倒れている人に大きな声で呼びかけることや近くにいる人に救急車を呼んでもらうことなど、初期対応について学びました。
次にAEDの使い方について指導を受けました。
講師からは、電極パッドを肌に直接貼ることや、倒れている人から離れてボタンを押すなど使い方の説明がありました。
県内では平成13年度から全ての公立高校にAEDが設置されていて、上農では「万一の際、対応ができるようにしておきたい。」と話しています。
52/(木)
