-
長野地裁伊那支部・伊那税務署建て替え
県弁護士会など移設求める
県弁護士会などは18日、伊那市西町の長野地裁伊那支部と、その向かいに位置する伊那税務署の移転建て替えを求める市民集会を開き、集会宣言を採択した。
集会を開いたのは、県弁護士会のほか、納税関係団体など14団体でつくる「税務署・裁判所の明日を考える会」で、この日は関係者や市民ら約100人が集まった。
会では、現在伊那税務署と地裁伊那支部のある場所は道幅が狭くアクセスしづらいことや、双方の建物も敷地面積が狭く十分な駐車場が確保できていないことを挙げ、「市民の交通の安全などが十分に補償されていない」と主張している。
地裁伊那支部は、建設から今年で50年となることから今年度、庁舎の建て替えが予定されているが、事業の実施主体である東京高裁は、現地での建て替えを計画している。
これに対し、発起人の中村威彦弁護士は、「どうせ建て替えをするなら、利用者がアクセスしやすい、障害者などに優しい施設とするべき。これは皆さんにかかわること。市民の皆さんにも考えていただき、行動に移していただきたい」と訴えた。
こうした動きに対し東京高裁は、「伊那支部の庁舎建設はすでに予算措置がとられており、現時点では計画通りの建て替えを計画している」としている。
伊那支部の工事は本年度中に着工し、来年度完成の予定。
会では、今後も働きかけを続け、より利便性の高い場所へ双方の施設の移設を求めていくという。 -
はらぺこでみそ造り

伊那市東春近の保育園、山の遊び舎はらぺこの園児20人は13日、みそ造りに挑戦しした。
はらぺこでは、昔ながらの方法で作ったみそを味わおうと、毎年味噌を手造りしていて、今年で5年目。
これまでは電動式の機械で大豆をつぶしていたが、今年は保護者の家から借りた手押し式の機械ですりつぶすことにした。
子どもの力では少しハンドルが重いようで、周りからは応援の掛け声が上がっていた。
10キロの大豆を全てつぶすと麹と塩を混ぜ、みそ玉を作る。
このみそ玉はワラの上で1週間ほど寝かせた後、たるに入れ、10カ月ほど寝かせて完成する。
はらぺこでは来年の4月ころ、このみそを使ってみそ
汁などの料理を作る計画という。 -
ヒメギフチョウ 住民と行政が保護へ

伊那市長谷の鹿嶺高原に生息する貴重なチョウ「ヒメギフチョウ」を住民と行政が協働で保護する活動が始まる。
春の訪れを知らせる蝶と呼ばれているヒメギフチョウは、環境省から絶滅の恐れのある生物に指定されている。
伊那市では3カ所で生息が確認されているが、いずれもその数は多くない。
生息地の一つ、伊那市長谷の鹿嶺高原でも年々その数は減ってきているという。
伊那市東春近の窪田勝好さんは、日本鱗翅学会会員で、16年前から鹿嶺高原でヒメギフチョウの生息調査を行っている。
窪田さんは、ヒメギフチョウを保護するためには、「幼虫の時のエサとなる植物ウスバサイシンを守ることが大切」と話す。
このウスバサイシンは、高原の開発に加え、シカなどの食害により減少してきている。
長年にわたり鹿嶺高原でヒメギフチョウの調査をしてきた窪田さんは、「この場所をヒメギフチョウが舞う貴重な生息地とし残していきたい」と話している。
伊那市では、ヒメギフチョウの幼虫のエサとなるウスバサイシンの分布調査を23日に、またシカなどの食害から守るための柵の設置作業を24日に計画していて、それぞれボランティアを募集している。 -
高尾神社例大祭

伊那市山寺の高尾公園で16日、高尾神社の例大祭とツツジまつりが行われた。
高尾神社は、77年前に山梨県の神社からのご神体を祀ったのが始まりで、それ以来、商売繁盛を願い、毎年例大祭を行っている。
例大祭では、地元山寺区の小学5・6年生8人が、浦安の舞を奉納した。
舞は、扇を使うものと鈴を使うものの2種類あり、子どもたちは緊張した表情で厳かな舞を披露していた。
また、花の見頃に合わせたツツジまつりでは、ゲーム機などがあたる福引きに、多くの子どもたちが列を作っていた。
公園内に植えられているツツジは現在見頃で、20日頃まで楽しめるという。 -
中条公民館で盆栽山野草展

伊那市の中条山野草盆栽クラブの展示会が17日まで、伊那市西箕輪の中条公民館で開かれている。
中条公民館で活動する山野草盆栽クラブが毎年この時期に開いているもので、今年は約300点の山野草や盆栽を展示している。
展示会は、愛好者にも人気が高いアツモリソウが多いことが特徴。
北海道の礼文島に自生し、絶滅危惧種に指定されているレブンアツモリは、ほかのアツモリソウと異なり淡いクリーム色をしている。
赤紫色で花が大きい釜無ホテイアツモリは、南アルプスにも自生しているが、ニホンジカの食害で野生種はほとんど見られなくなっているという。
また盆栽も、樹齢100年を超える松など、見ごたえのある鉢が多く並んでいる。
白鳥昭平会長は、「会員の育てた成果を大勢の人に見てもらいたい」と話していた。
展示会では即売も行われている。 -
伊那市消防団のホームページ完成
伊那市消防団の活動紹介や年間スケジュールなどを掲載したホームページが、このほど完成した。
消防団の活動を広く知ってもらうとともに、団員に活動スケジュールなどを漏れることなく伝えるために作成された。
ホームページには、日々の活動の記録が写真付きで紹介されているほか、組織の紹介、防災、防火のための準備や心得などを掲載している。
伊那市消防団の伊藤仁団長は、「市民のみなさんには、消防団の活動を知ってもらい、その必要性を理解してもらいたい」と話していた。
今後は、各分団を紹介するページを設けたり、分団の垣根を越え、団員たちが交流できるページを作成する予定。 -
春の河川一斉パトロール

河原などに捨てられているごみの実態を把握するための県内一斉パトロールが14日、行われた。
パトロールは、県の呼びかけで市町村や警察署などが参加して毎年行っている。
上伊那では、8市町村の天竜川、三峰川など11の一級河川で行われた。
伊那市高遠町の三峰川・山田河原では5人が作業にあたり、ペットボトルやタイヤのホイールカバー、板きれなどの一般ごみが回収された。
上伊那全体では356キロで、去年の秋に比べ100キロほど減少した。
ごみは、橋のたもとや人が集まりやすい場所に多くあるということで、関係者は、「きれいな川になるよう、一人ひとりが気をつけ、意識を高めていってもらいたい」と呼びかけていた。 -
伊那エンジェルス隊などでつくるキャラバン隊が車上狙いなどへの注意を啓発

上伊那をはじめ中南信地区で、昨年末から車上狙いや自転車盗難などの街頭犯罪が多発していることを受けて15日、防犯ボランティアグループ・伊那エンジェルス隊と伊那警察署、伊那市の3者が、防犯啓発を呼びかける企業訪問をした。
これは、会社の駐車場で対策をとってもらうとともに、社員を通してその家族にも防犯意識を持ってもらおうと今回初めて行われた。
そのうち、西春近の伊那食品工業では、車上狙いや振り込め詐欺防止についての要請書と、チラシの入ったポケットティッシュを手わたし、犯罪防止を呼びかけた。
駐車場を管理する総務人事部の小口知彦部長は「駐車場をきれいにすることが防犯につながると聞いた。防止策を社員に徹底していきたい」と話した。
伊那署管内では4月末現在、車上狙いが42件発生しており、昨年同時期の約2倍となっている。
また、伊那署など5つの警察署は、松本市や白馬村で窓ガラスを割るなどして車上荒しをした疑いで、ブラジル人4人を逮捕している。 -
16日から信州みのわ山野草クラブの山野草展

信州みのわ山野草クラブによる春の山野草展示会が16日から、箕輪町の木下公民館で開かれる。
信州みのわ山野草クラブは、7年前に木下公民館のクラブ活動の中で発足した。
今回は寄せ植えや季節の山野草など約200点をそろえた。
会長の白鳥征男さんは、「育てていると愛情が湧いてくる。珍しいものもたくさんあるのでぜひ観に来てほしい」と来場を呼びかけていた。
展示会は17日まで。16日には女性会員による自慢料理が振る舞われる。 -
温暖化対策病院協議会で情報交換

長野県内の医療機関が省エネルギーなどについて情報交換する県温暖化対策病院協議会が14日、伊那市の伊那中央病院で開かれ、県内の43医療機関から70人が参加した。
県では、温暖化防止県民計画に基づいて、家庭や企業でさまざまな対策を進めている。
その一つとして県内の病院にも呼びかけ、省エネなどの取り組みについて情報交換を行う協議会を昨年設立した。
今年度1回目の協議会では、伊那中央病院の省エネの取り組みなどが報告された。
報告によると、伊那中央病院では、省エネルギー推進委員会を平成18年6月に設置している。
外光を取り入れ電気使用量を減らしたり、適度な空調を保つことなどにより、増床や増築が行われているにもかかわらず、エネルギー使用量は横ばいを保っているという。
協議会では、今年度の事業計画として、6月に二酸化炭素の排出量の調査を行うほか、県内各医療機関の事例について研修していく予定。 -
すくすく絵本の会
親子が読み聞かせ楽しむ
南箕輪村の未就園児の親子を対象にした子育て支援施設「すくすくはうす」で12日、親子が絵本の読み聞かせを楽しんだ。
毎月行われている絵本の会で、すくすくはうすのアドバイザーが絵本や紙芝居を読んだ。
絵本の会は去年まで図書館の職員に依頼して行っていたが、今年からアドバイザーが受け持つことになった。
今会がその初回で、集まった子どもの年齢に合わせた絵本を読み聞かせたり、パネルシアターを披露した。
パネルシアターでは、子どもたちも動物の絵をパネルに貼るなどして楽しんでいた。
アドバイザーの高橋美奈さんは、「お母さんと子どもが絵本を読むきっかけになればうれしい」と話していた。
絵本の会は毎月第2火曜日の午前10時半から、すくすくはうすで開く。 -
公売オートバイ人気

伊那市がインターネット公売に出品したバイク「カワサキ メグロSG」が人気を呼んでいる。
このバイクは以前、伊那市が公用車として使っていたが、ここ10年ほどは使われず車庫に眠っていた。
市ではこのバイクを財源の足しにしようと、インターネットによる公売に出品したところ4月14日から締切となった5月12日までに約300件の入札参加仮申し込みがあった。
バイクのエンブレムにあるメグロは40年ほど前にあったエンジンメーカーの名称で、カワサキと業務提携した。
このバイクは1964(昭和39)年から5年間販売され、マニアの間では人気があるという。
仮申し込みが済んだ人を対象とした入札は26日から始まり、6月2日に落札者と価格が決まる予定。 -
辰野町の管轄伊那警察署へ
長野県警は、辰野町を岡谷警察署の管轄区域から伊那警察署の管轄へ変更するなどとした組織再編計画案をまとめた。
県警では辰野町の管轄変更により、広域連合の区域と整合が図られ、住民と協働した防犯活動や交通安全活動が進めやすくなるほか、裁判所管轄区域と整合し、事件送致業務や護送業務の効率化が図られる竏窒ニしている。
なお辰野町交番には所長以下8人の警察官が配置されていて、従来通りの運用になるという。
再編案については、説明会などを開いて住民の意見を聞き、県議会での議決を経て来年4月からの実施を予定している。 -
恩徳寺のクロユリ見ごろ

南箕輪村の恩徳寺で、クロユリが可憐な花を咲かせている。
恩徳寺では、2株のクロユリを50年かけて増やしてきた。
今年は例年並みの5月3日ころから咲き始め、約250株咲いている。
訪れる人々に楽しんでもらおうと、花が咲きそろったプランターは本堂の前に並べられている。
花は今週いっぱい楽しめるという。 -
高尾公園でふれあい広場開催

地域の交流や活性化につなげよう竏窒ニ、伊那市山寺の高尾町社会福祉協議会は10日、「ふれあい広場」を高尾公園で開いた。子どもからお年寄りまで、多くの人が訪れ、世代を超えた交流を深めてた。
公園内の社務所では、紙芝居の愛好家グループによる上演があり、訪れた人たちは懐かしい紙芝居を楽しんでいた。
紙芝居が始まると、子どもたちはおしゃべりをやめ、紙芝居の世界に引き込まれていた。
また、5年ぶりにバザーのコーナーを設置。会員が栽培した野菜や、自宅で不要になった衣類などが販売された。
バザーの売り上げは、地域の花壇整備や福祉活動に活用する予定。
高尾町社会福祉協議会の中谷操会長は「顔見知りになり、交流することで、いざという時に地域で助け合える環境ができる。これからも地域の交流の場として続けていきたい」と話していた。 -
青空の下で童謡・唱歌を楽しむイベント 箕輪町で

青空の下で童謡や唱歌を歌うイベントが10日、箕輪町のみのわ天竜公園であった。約100人が集まり、自然に囲まれた園内に、歌声を響かせた。
イベントは、町内の音楽愛好家でつくる実行委員会が「自然の風を受けながら歌を楽しんでもらおう」と企画したもの。昨年は雨で中止となったが、今年は青空に恵まれ、参加者は童謡や唱歌など37曲を歌った。
また、イベントの途中で、町内の太極拳愛好家らが、「箕輪町の歌」に合わせて太極拳を披露。訪れた人は歌を歌いながら、体を動かしていた。
山口栄一実行委員長は「屋外では強風によるハプニングもあるが、半分遊びという気分で歌と自然を楽しんでほしい」と話していた。 -
結婚体験談表彰式

伊那市の結婚相談窓口「いなし出会いサポートセンター」が募集していた結婚体験談の入賞作品が決まり、12日、伊那市高遠町のさくらホテルで表彰式が行われた。
表彰式には受賞者やその家族など約10人が集まった。
結婚体験談は独身の人たちに家庭を築くためのきっかけづくりにしてもらおうと、出会いサポートセンターが応募したもので、全国から9点が寄せられた。
このうち最優秀賞には岡谷市出身で京都に住んでいる破田野智美さんの作品が選ばれた。
破田野さんは32歳。5年前に結婚し、現在初めての子どもを妊娠中で、夫とともに表彰式に駆けつけた。
破田野さんは体験談で、「舞散る桜の花びらをつかむと幸せになれる」とつづっている。
体験談にはほかに、「結婚は2人の“ずっと”を公に認めてもらえ、周囲に守ってもらえる。思いたったときこそが適齢期です」と記されている。
この体験談は、今週末に伊那市のホームページで公開される。
現在出会いサポートセンターには、20代から70代まで160人ほどが登録していて、10組が交際中だという。 -
ザ・シワクチャーズ伊那が韓国で交流演奏会
市長に帰国報告
1日から4日まで韓国南原市を訪れていた伊那市の女声合唱団ザ・シワクチャーズ伊那のメンバーが12日、小坂樫男伊那市長に帰国報告した。
北沢理光代表とメンバー2人が伊那市役所を訪れた。
シワクチャーズのメンバーは伊那市と交流がある南原市を訪れ、南原春香合唱団と交流演奏会を開いた。
シワクチャーズは伊那市の歌などを作曲した名誉市民の故高木東六さんの遺志を継ごうと2年前結成された。
南原の訪問は高木東六さんが制作したオペラ「春香」の舞台となっていることが縁で決まったもので、交流演奏会では、それぞれが歌声を披露したほか、合同で合唱もした。
北沢さんらは、「南原の合唱団と同じステージに立つことができ感動しました。音楽は言葉に関係なく、どこの国の人たちとも通じあえると実感しました」と感想を話していた。 -
美和ダムで洪水に備えたダム管理演習実施

大雨などによる美和ダムの洪水に備えたダム管理演習が11日、伊那市長谷非持にある国土交通省の美和ダム管理支所で行われた。
演習は、大雨などによる洪水時、美和ダムから安全に放流するため、毎年この時期に行われているもの。
この日は、三峰川流域の6ヵ所に設置されたサイレンを鳴らし、電光掲示板で川に近付かないよう、呼びかけた。
また、今年は初めて中川村にある天竜川ダム統合管理事務所と光ケーブルで結び、テレビ電話でお互いの状況を確認し合った。
美和ダムでは通常、2つのゲートを開けて水量を調節している。しかし、容量の8割を超え、治水容量の1340万トンを超えると予想される場合、3つ目のゲートを開けて洪水調節を行う。
3つ目のゲートを開けなければいけない洪水は、昭和34年の建設以来、50年年間なかったという。
神野祐一支所長は「地域の安全のため、情報を適切に伝えていきたい」と話していた。
演習は明日も行われる。 -
母の日に贈るトピアリー作り

南箕輪村公民館で9日、母の日に贈るプレゼント作りがあった。
子どもや保護者約30人が参加し、南箕輪村沢尻の伊藤瑞枝さんから造花でつくるアレンジメントフラワー、トピアリーの作り方を教わった。
村公民館では、母の日に手作りの贈り物をプレゼントしてもらおうと、毎年講座を開いている。
参加した人たちは、花の色や形を選びながら、発泡スチロールのボールに挿しこんでいた。 -
箕輪町国際交流協会 交流会

箕輪町国際交流協会の定期総会と交流会が7日夜、町産業会館で開かれた。
国際交流協会のメンバーや町在住の外国人ら約60人が参加した。
交流会では、外国人によるスピーチが行われ、中国出身の金千雪さんが日本での生活について発表した。
金さんは現在、箕輪中部小学校の5年生。北京では、7縲・時間授業があり、英語も毎日勉強していたといい、「日本は、学校の外に行く授業もあって楽しい」と話していた。
箕輪町には現在、1300人の外国人がいる。
箕輪町国際交流協会では、日本語教室を開いているほか、交流事業、海外研修などを行っている。
世界的な不況の中、日本語が話せない外国人は就職が難しく、日本語教室に通う外国人が増えているという。
協会ではこうした状況の中、本年度はビジネスマナーの講座などの開催も考えている。 -
母の日に贈る音楽会

10日の「母の日」にちなんで、伊那市のいなっせで9日、小さい子どもを持つ母親に気兼ねなく音楽を楽しんでもらうための音楽会が開かれた。
NPO法人クラシックワールドが毎年開き、今年で11回目。幼い子どもの入場が制限されるコンサートが多い中、母親にもコンサートを楽しんでもらおうと開いている。
バイオリンやフルート、アルパなどの地元奏者が、クラシックの名曲を披露したほか、地元の母親でつくる合唱団が子どもたちと一緒に合唱曲を披露した。
訪れた親子は、会場に響く歌声や楽器の音色を存分に楽しんでいた。 -
西駒山草会 山野草展

葉に模様が入ったものなど、こだわりの山野草が並ぶ西駒山草会の山野草展が9日、南箕輪村の南原公民館で始まった。
会場には会員10人が丹精込めて育てた山野草100種類、400鉢が並んでいる。
西駒山草会では、育てていた山野草が突然変異し斑入りになったことをきっかけに、斑入りの山野草にこだわった展示会を開くようになった。
緑と白がくっきり分かれた刷毛込み斑、砂のような模様の砂子斑、白・黄緑・濃い緑の三色に分かれた三光斑など、さまざまな斑入りの山野草が並んでいる。
網野幸治会長は、「これだけ斑入りの山野草が並ぶ展示は珍しい。ひと味違うものが見られるのでぜひ足を運んでください」と来場を呼びかけていた。
西駒山草会の山野草展は10日まで。 -
秋葉街道整備

静岡県浜松市の秋葉神社まで続く古道、秋葉街道で9日、冬の間に落ちた枯れ葉などを取り除く作業があった。
伊那市高遠町の的場から始まり長谷、大鹿村を通って静岡県へ通じる秋葉街道は、江戸時代から明治にかけて、神社へ参拝する信仰の道として、また生活物資の輸送路として利用されていた。
平成19年から2年間かけて、住民有志でつくる「秋葉街道道普請隊」が古道を復活させようと、間伐や道の修復などを行い、去年11月に開通した。
この日は、新緑の季節を迎えてから初めての作業で、隊員17人が4つの班に分かれ、長谷黒河内から大鹿境の分杭峠までの約6キロメートルを整備した。
メンバーらは、冬の間に落ちた枯葉を取り除き、道の崩れている所を直して歩きやすいようにした。
また、森の中に自生する多年草のヒトリシズカなどを見つけると、踏まれないように石で囲った。
道普請隊隊長の高坂英雄さんは、「古い歴史のある道に、県内外から多くの人に来てもらい、豊かな自然も楽しんでもらいたい」と話していた。 -
ふれあい看護ながのin南信
看護への理解深める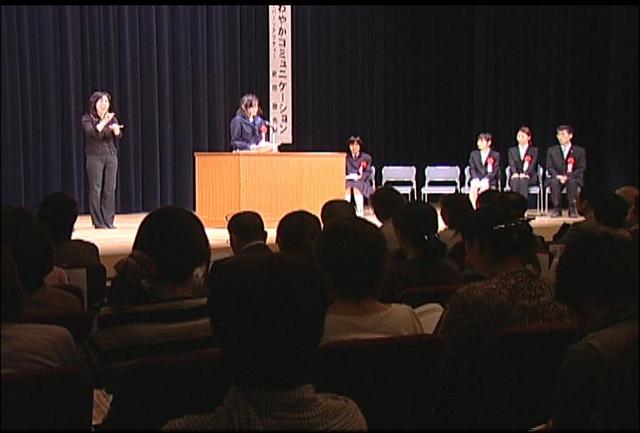
看護への理解を深める「ふれあい看護ながのin南信」が9日、箕輪町文化センターであった。
看護への理解を深めてもらうことと、看護従事者の人材確保を目的に、長野県看護協会が毎年県内を巡回して開いている。
看護士や地域住民ら約400人が参加。中学生や高校生が、それぞれ看護体験を通じて感じたことを発表した。
伊那市長谷中学校の中山沙紀さんは、「楽しいことばかりではなかったが、看護した患者さんの笑顔がとてもうれしかった」と話した。
また岡谷市の岡谷東高校の平出理沙さんは、「患者さんへの気遣いがとても多く大変だったが、やりがいのある仕事だと思った」と話した。
会場の外では、看護や健康に関するブースが設けられ、訪れた人たちがフットケアの体験や健康相談をしていた。 -
ミツバチの分蜂始まる

伊那地域では、女王蜂が働き蜂を連れて巣から別れる「分蜂」が始まっている。
9日、伊那市美篶青島の矢島信之さんが飼っているミツバチが分蜂した。
新しい巣が見つかるまでの間、働き蜂が女王蜂を守るため仮の巣を作り木の枝に群がっているもので、分蜂蜂球と呼ばれる。
蜂を飼っている人が多い伊那地域では、この状態の蜂の群れを取り込み、巣箱に入れ、新しい巣として増やしていくことを楽しみにしている。
分蜂は、一つの巣に新しい女王蜂が生まれたとき、古い女王蜂が働き蜂を連れて集団で巣から別れることをいい、ミツバチが群れを増やす方法として重要な役割を果たしている。
分蜂は午前10時から午後2時の間くらいに多く行われるが、蜂を飼っている人でも見逃してしまうことが多いという。
蜂を取り込むことに成功した矢島さんは、「観察していると蜂がかわいく思えてくる。これから大きな巣を作ってもらいたい」と話していた。 -
ルネッサンス西町の会と園児が春日公園に桜を植樹式

伊那市西町の住民有志らでつくるルネッサンス西町の会が8日、今年も地元春日公園に桜の苗木を寄贈した。
この日は遊具がある三の丸西側の広場で、近くの保育園児を招いて植樹式を実施。ルネッサンス西町の会では、桜の名所を後世に伝えていこうと毎年さくらの苗木を寄贈しており、今年で5年目。今回は、3年生のヒガンザクラを7本贈った。
植樹式に参加した園児らは「大きくなあれ」と掛け声をかけながら、桜の根元に土をかぶせてた。
春日公園には現在、ソメイヨシノ150本、ヒガンザクラ50本植えられているが、樹齢50年を越す老木が増えてきているという。
西町の会のある会員は「高遠城址公園に負けないようにがんばっていきたい」と話していた。 -
かんてんぱぱくぬぎの杜で9、10日に山野草展

信州伊那野草会は9日、10日、伊那市西春近のかんてんぱぱくぬぎの杜で山野草大展示会を開く。
8日は、野草会のメンバーが、展示会に備えて準備を進めていた。
会場には、シラネアオイやサンカヨウなど、この時期に見頃を迎えている山野草、200種類、350鉢が整然と並べられている。
飯島隼人会長は「会員たちが心のよりどころとして丹精込めて育てたものばかり」と話し、多くの来場を呼びかけている。
信州伊那野草会は、上伊那を中心に25人の会員がいて、随時会員を募集している。
この山野草大展示会は、9日、10日、かんてんぱぱガーデンより南に1.2キロのくぬぎの杜で開かれる。 -
伊那市西箕輪中条で花まつり

伊那市西箕輪中条で8日、釈迦の誕生を祝う花まつりが行われた。
中条地区では、花が咲く時期に合わせ、地区住民が一カ月遅れで花まつりを行っていて、昔から公民館が会場になっている。
3年前からは、近くの西箕輪南部保育園の園児が参加していて、この日も年少から年長の園児60人ほどが訪れた。
手を合わせた後、ツツジや八重桜、チューリップなどで飾った小さなお堂に向かい、釈迦像に甘茶をかけた。
地域のお年寄りは、「行事を通して触れ合うのは、お互いに楽しいこと。大人になるまで忘れないでいて、行事を受け継いでもらえたらうれしい」と話していた。 -
糸鋸亭ナルカリさんが糸鋸寄席

「こどもの日」の5日、伊那市では電動のこぎりを使って木のおもちゃを作る糸鋸亭ナルカリさんのパフォーマンスが披露された。
このパフォーマンスは、伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームの工房Cooのイベント「昔あそび」に併せて行われた。
ナルカリさんは、木曽で木を使ったおもちゃを制作していて、この日は集まった人たちからのリクエストに答えて鳥や動物などを即興で作った。
集まった人たちからは、ナルカリさんの鮮やかなパフォーマンスに歓声が起こっていた。
この日は、こま回しなど昔なつかしい遊びのコーナーが設けられ、大人から子どもまで遊びに夢中になっていた。
32/(火)
