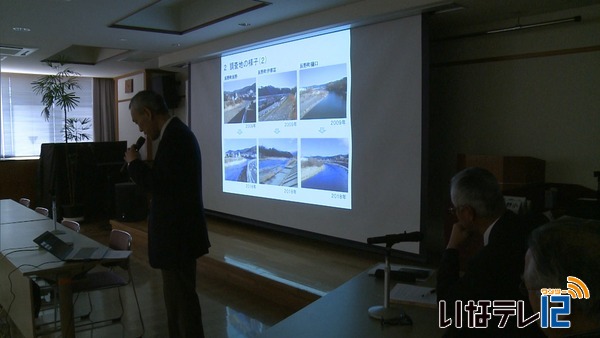-
公立高校前期選抜 県内4,229人に春
県内の公立高校前期選抜試験の合格発表がき15日に行われ合格した4,229人の受験生に一足早く春が訪れました。 前期選抜試験は、7日に実施されました。 上伊那の公立高校では594人が受験し404人が合格しています。 後期選抜試験は3月7日に行われ、合格発表は16日の予定です。
-
高遠高校 地域体験型学習の活動発表会
伊那市高遠町の高遠高校で行われている、地域体験型学習の活動発表会が8日に行われました。 高遠高校では、学校を核に教育機関や行政機関、文化施設などと連携して実習を行う「高遠学園構想」の取り組みを進めています。 この日は、その取り組みを知ってもらおうと学校評議員などを招き、初めて学習活動発表会を開きました。 情報ビジネスコースの生徒は、去年の秋に行われた高遠城址公園紅葉祭りのアンケート調査の結果を発表しました。 祭り期間中に訪れた197人を対象に、訪れたきっかけや高遠の印象などを聞いたということです。 生徒は「観光パンフレットを配ったり周辺の情報提供をすることが、また訪れてもらえるきっかけに繋がると思う。」と話していました。 高遠高校では、高遠学園構想の取り組みを市内全域に広げていきたいとしています。
-
弥生器楽クラブ定期演奏会
伊那弥生ケ丘高校器楽クラブの第10回定期演奏会が11日伊那市のいなっせで開かれ、めりはりの効いたやわらかくあたたかな音色が会場に響きました。 弥生の器楽クラブは、ギターマンドリン音楽を演奏するクラブで、昭和37年創部。55年の歴史があります。 11日は、1・2年生27人が、映画音楽やポップス、アニメソングを交えながら日頃の練習の成果を披露しました。 去年11月の県大会では、県知事賞を受賞し、7月の全国大会に出場するほか、8月の全国高校総合文化祭にも県代表として参加するなど全国レベルのクラブです。 この日は、OB・OGを交えての演奏も含め16曲を披露しました。
-
伊那市の西箕輪小学童クラブ 移転改築工事が完了
去年9月から進められてきた伊那市の西箕輪小学校学童クラブの移転改築工事がこのほど完了し開所式が7日に行われました。 新しい西箕輪小学校学童クラブは隣接する西箕輪中学校東側に建てられました。 以前校長の住宅として使っていた建物を改築したもので、木造平屋建て延べ床面積は180平方メートル総事業費は3,900万円です。 腰板には伊那市産のアカマツが利用されています。 きょうは、伊那市教育委員会など関係者が出席し開所式が行われました。 西箕輪小学校の竹松寿寛校長は「この地区に住む子供たちを大切に育てる環境が整ったことに感謝したい」と話していました。 学童クラブでは共働きなどで放課後、家庭に保護者がいない児童を預かります。西箕輪小学校では1年生から5年生の52人が対象となっていて、新しい施設は2月5日から利用が始まっています。
-
南箕輪村の大泉まんどの会 「子供の会」が発足
お盆の伝統行事「振りまんど」を伝えていこうと活動している南箕輪村の大泉まんどの会は、子ども達が自主的に活動できるようにと小学生でつくる会を立ち上げました。 10日に発足式が行われ多数決で会の名称を「子供の会」に決めました。 会長は南箕輪小学校5年生の増澤俊太郎君が、副会長は同じく南箕輪小学校4年生の原和花さんが務めます。 大泉では伝統の振りまんどを後世に伝えようと住民有志でつくる「大泉まんどの会」が主体となって活動しています。 昭和10年代頃までは、地域の子供たちが主体となって振りまんどの行事を行っていたという事で、自主的な活動をする機会をつくろうと小学生を対象とした会を立ち上げる事にしました。 この日はこのほか休耕田で振りまんど用に育てている大麦の麦踏み作業を行いました。霜で浮き上がった麦を土へ戻す作業です。 去年10月に種をまき、収穫は6月を予定しています。 大泉には106人の小学生がいますが、現在子供の会の会員は9人です。まんどの会の唐澤俊男会長は「会員を増やしながら、いずれは自分たちで麦の栽培計画を立て、行事を企画していけるようになってほしい」と話していました。
-
伊那西高校 1年間の成果を披露「芸術フェスティバル」
伊那市の伊那西高校の文化系クラブがこの1年で制作した作品を披露する芸術フェスティバルが、かんてんぱぱホールで10日から始まりました。 会場には、美術クラブ、書道クラブ、折り紙・工芸クラブ、写真クラブ、家庭科クラブのほか、保育の授業で制作した作品、合せて190点が展示されています。 茶華道クラブは訪れた人にお点前を披露しました。 伊那西高校の芸術フェスティバルは1年間の活動の成果を地域の人たちに発表する場として毎年開かれていて今年で11回目になります。 写真クラブ2年生の蟹澤悠月さんは、去年宮城県で開かれた全国高等学校総合文化祭で最優秀賞の文化庁長官賞を受賞した作品を展示しています。 生徒たちは来年の活動に活かすため、訪れた人たちの感想を大切にしているという事です。 伊那西高校の芸術フェスティバルは伊那市のかんてんぱぱホールで13日(火)まで開かれています。
-
高遠だるま市 人形飾りを園児が見学
伊那市高遠町の商店街には11日のだるま市に訪れた人たちを出迎える人形飾りが並べられています。 9日は高遠町内の園児が人形飾りを見学しました。 人形飾りはだるま市に訪れた人たちに楽しんでもらおうと作られたものです。 今年は7団体が人形飾りを展示していて高遠保育園では、だるまを作りました。 高遠第2第3保育園は木にまつぼっくりなどをつけて人の顔を作りました。 いろは堂薬局は、ドラえもんを作りました。 アルプス中央信用金庫と八十二銀行はスターウォーズにちなんだ作品です。 春日医院は戌年にちなんだ作品となっています。 グループホーム桜は高遠の四季を貼り絵で表現しました。 伊那市職員だるま市を盛り上げる有志の会は去年開催されたドローンフェス・イン・イナバレーにちなんだ作品となっています。 だるま市は11日に高遠町の鉾持神社参道を中心に行われます。
-
上伊那岳風会伊那地区 初吟会
上伊那の詩吟愛好家でつくる上伊那岳風会伊那地区の初吟会が4日、伊那市のJA上伊那本所で行われました。 上伊那岳風会は、伊那市・駒ヶ根市・箕輪町に支部があり、この日は伊那地区の今年最初の吟会が行われました。 伊那地区には16の教室があり、小学校5年生から87歳まで、およそ70人が会員となっています。 この日は全員が1人ずつ吟じる「独吟」という形式で発表しました。 高校生は、去年12月に須坂市で行われた、第42回全国高等学校総合文化祭のプレ大会で披露した合吟と剣舞を行いました。 上伊那岳風会伊那地区では「緊張感がある中で良い声が出ていてよかった。今後も活動を続けていくために、若い世代の育成にも力を入れていきたい。」と話していました。
-
長谷中学校 内藤とうがらしの活動で最高賞を受賞
伊那市長谷の長谷中学校は、自然体験活動のアイデアを全国の小中学校から募集する、第16回トム・ソーヤースクール企画コンテストで、最高賞を受賞しました。 7日は、3年生の生徒や田中祐貴教諭らが市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞を報告しました。 トム・ソーヤースクール企画コンテストは、ユニークな自然体験活動のアイデアを全国の小中学校から募集するもので、今回で16回目です。 長谷中学校は、地元で採れる伝統野菜「内藤とうがらし」を使った地域の活性化に取り組みました。 3年生の生徒を中心に内藤とうがらしを栽培し、乾燥させて一味唐辛子やラー油を作りました。 過疎化する地域の活性化に貢献した点などが評価され、今回最高賞にあたる文部科学大臣賞に選ばれました。 賞金の100万円は、唐辛子の製粉機や鍋などの購入費に充てたということです。
-
高校入試前期選抜
高校入試の前期選抜試験が7日、県内一斉に行われました。 午前8時頃、上伊那農業高校では受験生が続々と会場に向かっていました。 上伊那の公立高校では、伊那弥生ヶ丘高校を除いた7校で前期選抜試験が行われました。 上農高校では4つの学科合わせて128人が志願していて、倍率は1.6倍となっています。 県内全体では6,889人が志願しています。 長野県教育委員会によりますと、入試にかかわるトラブルはなかったということです。 前期選抜の合格発表は15日の予定です。
-
伊那市高遠町の旧馬島家住宅 雛人形の飾りつけ
伊那市高遠町の旧馬島家住宅で、雛人形の飾りつけが7日に行われました。 高遠町内の女性でつくる「高遠をこよなく愛する会」のメンバーが200体ほどの雛人形を飾り付けました。 以前は3月に飾り付けを行っていましたが、だるま市に訪れた人にも見てもらおうと去年から2月に行っています。 会場では様々な時代のものを一堂に見る事ができます。 一番古いものは300年前、江戸時代中期の享保雛です。享保の改革で倹約を推し進めていた幕府により、大型の雛人形の製作や売買が禁止されていた時代に作られました。 このほか、江戸時代後期に作られた押絵雛のほか、明治、大正から現代のものが展示されています。 愛する会のメンバーは「趣のある雰囲気の中で様々な人形を楽しんでほしい」と話していました。 雛人形の展示は、あすから高遠城址公園の花見シーズンが終わる頃の4月24日まで行われます。 また3月10日には、抹茶の提供や着物の着付けを無料で行うイベントを開催する予定です。
-
西春近北小 2分の1成人式で節目の歳を祝う
成人の半分、10歳を記念した「2分の1成人式」が5日、伊那市の西春近北小学校で行われ、4年生が将来の夢を発表しました。 この日は、4年欅(けやき)組の児童26人が、将来の夢やこれまでの歩み、両親への感謝を発表しました。 ある男子児童は「お父さんのうなぎを焼くのを見て格好良いと思ったので店を継ぎたい」、ある女子児童は「料理を作った時にみんなが喜んで食べてくれて嬉しかったのでパティシエになりたい」と発表していました。 西春近北小学校では、感謝の気持ちや自分の成長を10歳の節目に感じてもらおうと、平成21年から毎年、2分の1成人式を行っています。 4年生は和太鼓の演奏も披露しました。 大日野昭美(おおひのあきみ)校長は「家族や地域の人たちが優しく、時には厳しく接してくれるから学校に来ることができています。改めて感謝をしましょう」と話していました。
-
伝統の高遠だるま市 人形飾り・オリジナルだるまで盛り上げ
11日に行われる、伊那市高遠町の恒例行事「高遠だるま市」を盛り上げようと、人形飾りの準備や、オリジナルのだるまの販売が行われています。 高遠町総合支所では連日、市役所の職員でつくる「だるま市を盛り上げる有志の会」が人形飾りづくりをしています。 伊那市で活用が進むドローンをもっと多くの人に知ってもらおうと、ドローンに乗ったゲームキャラクターを製作しています。 展示を直前に控え作業は大詰めを迎えていて、5日夜は発泡スチロールでつくった部品を組み立てていました。 人形飾りは、だるま市に訪れた観光客を商店街に呼び込もうと、100年以上前から続いていると言われています。 高遠町内の商店や実業団など多い時には20団体近くが出展していましたが、手間がかかることなどから出展団体は徐々に少なくなり、現在は7団体となっています。 職員有志の会は、人形飾りの伝統を残していこうと15年ほど前に発足し、飾り作りを始めました。 有志の会の山下隆さんは「人形飾りを見て喜んでもらって、少しでもだるま市を盛り上げられたらうれしいです」と話していました。 飾りは7日から総合支所の駐車場で見ることができるということです。
-
東みのわ保育園サッカー教室
箕輪町の東みのわ保育園サッカー教室が、6日ながたドームで開かれました。 東みのわ保育園の年長と年中の園児およそ30人がサッカーを楽しみました。 指導したのは、町内のサッカーチームの指導者で作る一般社団法人箕輪町サッカー協会の会員です。 協会では、町内の保育園でサッカー教室を開いていて、東みのわ保育園では今年度4回目です。 園児たちは、ドリブルに挑戦したり、ミニゲームを楽しんでいました。
-
これからの図書館 「集い」と「地域学習」
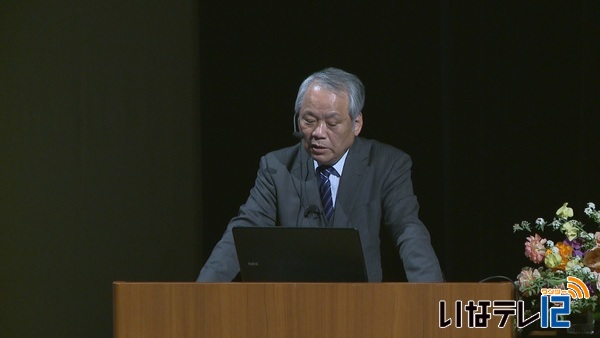
箕輪町図書館の開館40周年記念の講演会が4日町文化センターで開かれ、長野県立歴史館の笹本正治館長が「図書館が担う知の地域づくり」をテーマに話をしました。 講師の笹本さんは元信州大学副学長で平成28年度からは長野県立歴史館の館長を務めています。 講演会は、箕輪町図書館の開館40周年を記念し、これからの図書館に求められる役割やサービスについて考えるきっかけにしようと開かれました。 笹本さんは「今の図書館にはだれもが訪れやすい空間や、調査や学習をさらに支援する体制が求められている」と話していました。 また、図書館の充実を図る事で「住民が地元の文化や歴史について知識を深めるきっかけとなり、それが地域づくりに繋がる」と話していました。
-
伊那西小学校6年生 地域住民と「伊那西冬祭り」
伊那西小学校の6年生は地元の保育園が休園となっている伊那西地区を盛り上げようと地域住民を学校に招いて「伊那西冬祭り」を3日に行いました。 魚釣りや射的、輪投げなど子ども達が考えた5種類のゲームを訪れた住民らが楽しみました。 伊那西小学校の6年生17人が、去年12月から準備を進めてきました。 6年生は、伊那西部保育園が休園となる前の最後の卒園生です。 去年4月から保育園の活用について考えたり、地域をもりあげようと伊那西地区の魅力をみつける活動などを行ってきました。 秋に保育園を使って祭りを行い好評だったという事で、小学校卒業を前に活動のまとめとして最後の冬祭りを企画しました。 この日の祭りには、地域住民や保護者など約70人が訪れたという事です。
-
公立高校前期選抜試験 志願者数発表
-
西部地区活性化へ 伊那西小6年生が冬祭りを開催
伊那西小学校の6年生17人は、地域の保育園が定数に足りず休園となっていることから、伊那市西部地区を盛り上げようと2月3日、伊那西小冬祭りを開催します。 30日は、児童が準備とリハーサルを行いました。 当日は、子ども達がつくった射的や釣り、缶積み、輪投げなどのゲームで、集まった人たちと楽しい時間を過ごす計画です。 6年生は、現在休園中の伊那西部保育園の最後の卒園児です。 授業で保育園に関する新聞記事を読み、自分たちも何かできないかと、去年4月から保育園の活用について考えたり、掃除をするなど取り組みを始めました。 9月には保育園を使って伊那西小秋祭りを開催し、90人近くの地域住民を集めました。 このことから、卒業を前に、小学校に新しくつくられた地域の集いの場「多目的室」を使って冬祭りを行うことを決めました。 ある男子児童は「僕たちが通っていた保育園が休園になっているということを聞き、まだ建物はあるから何かできないかとみんなで考えてイベントを企画しました。好評だったので今回も計画しました」と話していました。またある女子児童は「地域に人が集まって、保育園や小学校にも人が増えてくれればうれしい」と話していました。 伊那市は、来年度から伊那西小学校を地域の特性を活かし、市内全域から入学、または転学することができる小規模特認校に指定することを決めています。 現在入学・転学の希望者を募っていて、伊那市によりますと、検討している家庭が数件あるということです。 二木栄次校長は「子ども達の伊那西地区への愛情を感じるし、伊那西地区の未来にもつながる活動だと思う」と話していました。 冬まつりは今週末、2月3日土曜日の午前10時から伊那西小多目的室で開催されます。
-
旧満州の孤児焦点に講演会
終戦後、旧満州に取り残された満蒙開拓団の孤児達を引き取った中国養父母に焦点をあてた講演会が30日、伊那市役所で開かれました。 満蒙開拓平和祈念館の副館長で中国の養父母支援団体と繋がりがある寺沢秀文さんが講演しました。 寺沢さんは「終戦直後、ソ連軍から責められていた日本人は、子どもが泣くと居場所がわかってしまうため、山の中に置いてきたり、現地の人達に預けてその場を去ってしまった」と当時の状況について説明しました。 また、寺沢さんは中国のある養母から聞いた体験談について「日本人憲兵にお腹を蹴られ流産した中国の女性が日本人から子どもを預けられ育てたという話を聞いた。日本人がこの現状を知らなくてはいけない」と話していました。 講演会は、長野県日中友好協会が市役所で開いている展示に合わせて開いたもので、会場にはおよそ50人が集まりました。
-
まちなかJapan+演奏会
東京を中心に活動する若手邦楽演奏家のグループ「まちなかJapan」の初めての地方演奏会が、28日、伊那市のいなっせで開かれました。 まちなかJapanは、舞台から飛び出して不特定多数の人たちに邦楽に親しんでもらおうと活動している若手グループです。 今回は、地元の邦楽演奏家も加わり、まちなかJapan(じゃぱん)+(ぷらす)として演奏会を開きました。 正派副家元の中島 一子さんは、「伊那と新宿は友好都市であり、その絆を深めながら東京オリンピックにむけて盛り上げていきたい」と話していました。
-
上伊那教育会郷土研究部 1年間の研究成果を発表
上伊那教育会の郷土研究部が行っている地域の自然や歴史の研究成果について報告する年に1度の研究発表会が伊那市のいなっせで27日に開かれました。 自然の部と人文の部にわかれ、この1年の研究の成果を発表しました。 このうち箕輪西小学校の宮澤良友教諭は、郷土研究部の野鳥班が20年間毎月1回行ってきた、天竜川でのサギとカモの出現状況について発表しました。 調査の結果、2003年以降毎年観察されるダイサギは2014年以降繁殖が確認され、今後も個体数を増やしていくのではないかという事です。 またカモ類では、川に潜って魚を食べる潜水性の種類が増加傾向にあり「天竜川の魚類への影響が心配される」と話していました。 上伊那教育会では、上伊那誌自然篇の改訂増補版の刊行を予定しています。 この日発表された内容も盛り込まれるほか、本に掲載しきれなかった詳しい資料はウェブ版としてデータ配信する計画です。 改訂増補版は6月末までに上伊那の小中学校や高校、図書館などに無料で配布され、希望者には有料でも配布されます。1冊4,500円で、2月末まで伊那市創造館内の郷土研究室で申し込みを受け付けています。
-
第9回 南信一水会展
南信の一水会の出品者の作品が集う第9回南信一水会展が、伊那市のかんてんぱぱホールで25日から始まりました。 会場には、15人が出品した作品が並んでいます。100号の大作は26点あります。 一水会は、昭和12年に東京で始まった展覧会で、南信一水会はその南信の出品者で組織しています。 去年までは上伊那を中心とする一水十日会として活動していましたが、南信地域で統合し今回、展示会を開きました。 大作は去年9月の展覧会に出品したものと、今年出品するものの2点を展示している人も多くいます。 去年のものは完成していますが、今年のものは制作途中です。 関係者は、「絵の好きな人から感想を聞くと、制作のヒントになるので見た感想を聞かせてほしい」と話していました。 また、チャリティコーナーも設けられています。 実費を除いて日本赤十字社に寄付するもので会場には、赤十字から感謝を込めて贈られた盾もあります。 南信一水会の展示会は、2月7日まで伊那市のかんてぱぱホールで開かれています。
-
山の遊び舎はらぺこでラーメン作り
伊那市東春近のNPO法人山の遊び舎はらぺこで21日、日曜開放日に合わせてラーメン作りが行われました。 ラーメン作りには、はらぺこの園児のほかその活動に興味を持つ親子8組約25人が集まりました。 園児らは野菜を炒めるなどしてラーメン作りを手伝っていました。 スープのベースとなる醤油は、手作りしたものが使われました。 はらぺこは2005年に開園し自然との関わりを中心とした保育が行われています。
-
高遠高校音楽専攻 卒業定期公演
伊那市高遠町の高遠高校芸術コース音楽専攻の卒業定期演奏会が、20日信州高遠美術館で開かれました。 演奏会には、音楽専攻の生徒や、合唱部、吹奏楽部などが出演し22曲を披露しました。 卒業定期演奏会は、3年間の集大成として、また1,2年生の発表の場として毎年開かれています。 全学年の合同演奏では、3年生が琴、2年生がキーボード、1年生が歌を担当し、息の合ったハーモニーを披露していました。 ある3年生は「これまでの感謝の気持ちや、3年間歌に取り組むことができた喜びを伝えられたと思います」と話していました。 会場には、保護者やOBなどおよそ100人が訪れ演奏に耳を傾けました。
-
親子ふれあいトンカチ教室
伊那市の手良小学校で、親子で木工を体験するふれあいトンカチ教室が今日開かれました。 教室には、1年生から6年生までの児童とその保護者、およそ140人が参加しました。 西箕輪産のスギを使って収納箱を作りました。 指導したのは手良地区の建設業者でつくる手良建設労働組合の組合員9人です。 教室は、ものづくりを通して親子のふれあいを深めてもらおうと、手良小学校PTAが開いていて、今年で21年目になります。 PTA会長の竹中康仁さんは、「親子で協力して一生懸命作る姿が見られてよかった。長く続く行事なのでこれからも続けていきたい」と話していました。
-
大人の話を聞き「生き方」考える
大人の話を聞くことで「生き方」について考える大人と語る会が19日、南箕輪村の南箕輪中学校で開かれました。 大人と語る会では上伊那在住で職種や出身、年齢など様々な大人16人が講師を務めました。 キャリア教育の一環として行われたもので1年生約150人がグループに分かれて仕事や家庭、趣味などについて話を聞きました。 「どんな時に楽しいと感じますか」という質問に製造業の男性は「子どもと遊んでいるとき」と答えていました。 「仕事をしていて幸せだと思うのはどんなときですか」という質問に農家の女性は「お客さんが喜んでくれたとき」と答えていました。 大人と語る会は生徒自身が実行委員となりどんな大人を呼びたいか、どうすれば質問や発言をしやすいかなどを考えてきたということです。 2年生になった5月には職場体験が予定されていて仕事について考える機会にしていくということです。
-
園児に伝統の羽広の獅子舞披露
伊那市の西箕輪保育園で、地域に伝わる羽広の獅子舞が19日披露されました。 羽広の獅子舞保存会のメンバー12人が保育園を訪れ伝統の舞を披露しました。 保存会では、子ども達に獅子舞を近くで見てもらおうと、毎年この時期に地元の西箕輪保育園と西箕輪南部保育園を訪れています。 羽広の獅子舞は、15日周辺の小正月に仲仙寺で奉納されていて、市の無形民俗文化財に指定されています。 400年以上の歴史を持ち、勇壮に舞う雄獅子と静粛に舞う雌獅子の舞い合わせが特徴で阿吽の舞とも呼ばれています。 クライマックスの悪魔払いでは、子どもたちの間近に獅子が行き、舞いを披露しました。 保存会では、「子どものうちから獅子舞に親しんでもらい、将来は伝統を受け継ついでもらいたいです」と話していました。
-
箕輪中2年生 発砲スチロールでアート展
箕輪町の箕輪中学校の2年生が発泡スチロールで作った立体のアート展が、町文化センターで開かれています。 会場には、2年生235人が制作した立体アートが並んでいます。 天竜公園にこんな彫刻があったらいいなと想像して、制作したということです。 待ち合わせ場所や、子どものあそび場・町のシンボルになるようなアートを目指しています。 発砲スチロールを電熱線で文字の形などにカットして、色付けしました。 制作には3か月ほどかかったということです。 箕輪中学校の美術担当教諭によると、「デザインからどう立体にしていくか苦労しながら作った。見る角度によって形が変わるのが魅力だ」と話していました。 作品展は18日までとなっています。
-
地域の安泰や五穀豊穣を願い 獅子舞披露
伊那市高遠町上山田引持に伝わる引持の獅子舞が13日、地域住民に披露され集まった人たちが家内安全や五穀豊穣を願いました。 引持の獅子舞は、昔は地区住民が徹夜で酒を酌み交わしながら日の出を待ち、地区の安泰を願う「お日待ち」の行事で行われていたという事です。 今は地域住民でつくる引持獅子舞保存会が毎年行っていて会場にはおよそ60人が集まりました。 前は獅子を後ろはひょっとこの面をつけた2人が会場狭しと舞を披露し獅子が体についたノミを食べるユニークな仕草もありました。
-
箕輪中生8人が全国大会へ
箕輪中学校のスケート部、技術部、家庭科部の生徒が15日に町役場を訪れ、白鳥政徳町長に全国大会出場を報告しました。 この日はスケート部、技術部、家庭科部の生徒8人が役場を訪れました。 スケート部からは、3年生の浅川華(はな)さんが1500メートルと3000メートルに、同じく3年生の河野菜々穂(ななほ)さんが500メートルと1000メートルに出場します。 技術部からは、木工チャレンジコンテストの製作部門に3年生の松田惇平(じゅんぺい)くんが出場します。 アイディア部門はすでに審査が終わっていて、3年生の池田啓太くんが産業教育教材振興協会長賞を受賞しています。 また、作品コンクール部門に3年生の藤森深海(しんかい)くんと1年生の丸山春輝(はるき)くんの作品が県代表として出品されます。 家庭科部からは、豊かな生活を創るアイディアバックコンクールに2年生の備前ゆき恵さんと1年生の太田結衣子(ゆいこ)さんが出場します。 白鳥町長は「頑張ってきてください。結果を楽しみにしています」と激励していました。 スケートは2月3日から長野市で、木工チャレンジコンテストと豊かな生活を創るアイディアバックコンクールは1月20日から東京都で開催されることになっています。
99/(火)