-
御柱祭学習で里引き体験

総合的な学習の時間で御柱祭について学習している伊那市の東部中学校の生徒が12日、柱の里引きを体験しました。 御柱祭について学習しているのは東部中の3年3組の生徒33人です。 クラスの保護者が所有する伊那市手良の山のモミの木が使われ東部中学校までのおよそ8キロを引きました。 モミの木は先月切られたもので太いところで直径28センチ、長さが10メートルあります。 3年3組では11月に校内合唱コンクールで御柱をテーマにした曲「御山出し」を歌うことにしていて曲のイメージをつかむため御柱祭について学習しています。 生徒らはこれまでに諏訪大社を訪れ御柱を見学したり、諏訪地域の木遣り保存会から木遣りを習ったりしてきました。 一番の難所となる急な上り坂では全員が声を掛け合いながら力を合わせて柱を引いていました。 柱はおよそ8時間かけて目的地の東部中学校に運ばれました。 3年3組では運んできた柱を校内に建てる建御柱も計画しています。
-
歴博講座 研究成果を発表
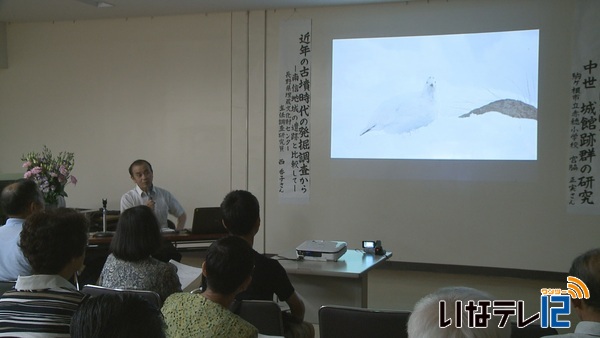
地域の研究者や県の専門職員が研究の発表を行う「歴博講座」が、11日、伊那市の高遠町歴史博物館隣の地域間交流施設で開かれました。 歴博講座は、夏と冬の年2回開かれています。 上伊那教育会の会員と長野県埋蔵文化センターの専門職員の合わせて4人が発表しました。 このうち、駒ヶ根市の赤穂小学校の飯澤隆校長と伊那中学校の大木島学教諭は、山の日に合わせて「南アルプスのライチョウの生息状況」について話しました。 飯澤さんは、「北岳のライチョウの縄張りの数は30年前に比べて7分の1ほどに減った。原因として、温暖化による気温の上昇でキツネやカラスなど低地の生き物が高山帯に進出したことと、ニホンジカの食害による植生の変化があげられる」と話していました。 歴史博物館では、「高遠は歴史や民俗などへの関心が高い地域。新しい研究や調査結果に触れる機会をつくっていきたい」と話していました。
-
上農伝統盆花市 15分で完売

上伊那農業高校伝統の盆花市が12日、伊那市のいなっせ北側などで開かれ、会場は行列ができる賑わいとなりました。 生徒の掛け声と共に販売が始まると、集まった100人ほどの人たちは盆花を買い求めていました。 上農の盆花市は60年以上続く伝統行事です。 今年は、暑い日が続いた事などから早く花が咲いてしまい、去年より100束少ない160束が用意されました。 一束500円で小菊、トルコギキョウ、カーネーションなど8種類入っています。 いなっせ北側では、販売開始から15分で完売となりました。
-
ミヤマシジミの観察会

伊那市のますみヶ丘平地林で環境省の絶滅危惧種に指定されているミヤマシジミの観察会が7月24日に開かれました。 ますみヶ丘平地林の鳩吹公園周辺では、ミヤマシジミが生息しています。 信州大学名誉教授の中村寛志さんが会長をつとめるミヤマシジミ研究会が、幼虫のえさとなるコマツナギを植樹して保護する活動をしています。 この日は、市内の親子、20組50人が虫取り網を手に観察会に参加しました。 観察会は、子どもやその親にミヤマシジミの希少性などを理解してもらおうと伊那市と研究会が開きました。 鳩吹公園近くの保護区では、コマツナギの周辺にミヤマシジミが多数みられます。 子どもたちは、網で捕まえ、観察したり写真を撮り終えると逃がしていました。 ミヤマシジミは、環境省のレッドリストで絶滅危惧種に指定されているほか13の県で指定されています。 長野県版では、準絶滅危惧種に指定されていて、研究会では、「信州から全国へ保護を提唱していきたい」としています。
-
七夕の奇祭 さんよりこより

伊那市の三峰川をはさんで北の美篶川手天伯社と南の富県桜井天伯社で、毎年8月7日の七夕に行われる奇祭「さんよりこより」が7日に行われました。 さんよりこよりを2日後に控えた5日、美篶川手天伯社には、上川手と下川手の住民が集まり、高さ15メートル以上ののぼりを建てます。 のぼりは、川手天伯社の東側に上川手が、西側に下川手がそれぞれ2本ずつ建てますが、両地区が助け合いながら作業は進められます。 昔から伝わる建て方で建てるため、すんなりとはいきませんが、1時間ほどで4本ののぼりが建ちました。 7日は、正午からの神事のあと、ご神体を乗せた神輿の下を地域の子どもたちが3回くぐり、無病息災を祈願します。 その後、神社脇の公園でさんよりこよりが行われました。 三峰川に洪水を引き起こす鬼役の大人2人が笠をかぶって太鼓をたたくのを中心に、七夕飾りを手にした川手の子どもたちが輪になって囲みます。 子どもたちは、「さんよりこより」と唱えながら3周した後、鬼をめった打ちにし、これを3回繰り返し鬼を退治します。 300年続くといわれているこの行事は、その昔、高遠の藤沢にあった天伯様が大洪水で流されて桜井に流れ着いた後、ふたたび流されて対岸の川手に流れ着いたとされ双方に天伯社が祀られたと言い伝えられています。 三峰川を天の川に見立て神輿が渡るさまは、七夕の織姫と彦星の年に一度の逢瀬になぞらえられています。
-
箕輪で恐竜の模型づくり

夏休みを利用した講座やワークショップが4日伊那市や箕輪町で開かれました。 箕輪町文化センターです。 箕輪町図書館主催で恐竜の模型をつくる講座が開かれました。 作ったのは、首としっぽが長い恐竜の総称「カミナリ竜」です。 京都府在住の恐竜造型家荒木一成さんが講師をつとめました。 ただの模型でなく、骨や筋肉にこだわり復元を目的にしています。 この講座は、箕輪町図書館の人気講座で今年で4年目。 町内を中心に20組40人が参加しました。 参加者たちは、芯に粘土をつけていき、胴体部分をふくらませたり、骨をイメージしながら前足や後足をつくっていました。 箕輪町図書館では、「子どもたちに人気の恐竜づくりを入口に、図鑑や化学の本に興味を持ってもらいたい。」と話していました。
-
じゃがいも収穫で交流

伊那市の長谷中学校と東部中学校の生徒が22日、じゃがいもの収穫体験で交流しました。 22日は長谷中の1年生と東部中の1年5組の生徒合わせておよそ50人が長谷中学校の畑でじゃがいもを収穫しました。 両校はこれまでに情報通信技術ICTを活用した遠隔合同授業で交流してきました。 遠隔合同授業は同年代の交流を広げることで小規模校の活力ある教育につなげようと行われているものです。 今回は実際に顔を合わせて作業をすることでさらに交流を深めようと長谷中の生徒が育てたじゃがいもの収穫体験が企画されました。 東部中の生徒は学校近くに畑がなく農作業の体験があまりないということで楽しみながら作業にあたっていました。 両校は「互いのメリットを活かしながら交流の可能性を広げていきたい。」と話していました。
-
地域の史料に触れ 歴史を学ぶ

伊那市高遠町の歴史博物館で、市内の中学生を対象に見て触れて学ぶ講座「地域の実物史料から日本の歴史の流れをとらえよう」が3日から始まりました。 講座は、授業で習った歴史についてさらに理解してもらおうと開いているもので今年で3年目です。 講座は3日から5日まで開かれ、市内の6つの中学校の生徒が日替わりで参加する予定です。 講師は、高遠町歴史博物館の笠原千俊館長や博物館の学芸員が務めました。 生徒たちは、始めに歴史博物館や伊那市で保有している縄文・弥生時代の土器を実際に触って違いを感じていました。 博物館の学芸員は、「土器や陶器を高温で焼く技術が発達するにつれ、薄く丸びをおびた形に変化していった」と話していました。 笠原館長は「博物館の史料と中学校の指導が双方向的に関わることで、博物館が地域の学習センターとしての機能を担いたい」と話していました。
-
井月さんまつりを宣伝カーでPR

9月3日と4日に伊那市で開かれる第四回千両千両井月さんまつりをPRする宣伝カーが完成しました。 1日、伊那市役所で、平澤春樹実行委員長らが宣伝カーをお披露目しました。 軽トラックは実行委員の矢島信之さんのもので、妻の美代子さんが作った切り絵を拡大した勘太郎の絵が飾られています。 まつりでは、「井月と伊那の勘太郎―アウトローへのまなざし―」をテーマにしたシンポジウムを行う事から、この絵をモチーフにした宣伝カーを製作したという事です。 行燈をイメージした作りで、中に照明を入れ、1日から祭り当日まで市内を毎日走ってPRします。 第四回千両千両井月さんまつりは、来月3日と4日にいなっせを会場に行われます。 初日はシンポジウム、2日目は信州伊那井月俳句大会が行われるほか、伊那旭座では「ほかいびと-伊那の井月-」と昭和27年公開の「勘太郎月夜唄」のアンコール上映が予定されています。
-
ソフトテニスでインターハイ出場

伊那北高校の漆戸大さんと木村海夢さんの2人はソフトテニスでインターハイに出場します。 21日2人は箕輪町役場を訪れ白鳥政徳町長にインターハイ出場の報告をしました。 漆戸さんは3年生で同じ伊那北高校の3年生とペアを組み64ペアが出場した県大会で優勝しました。 木村さんは2年生で同じ伊那北高校の2年生とペアを組み県大会で3位に入りました。 ソフトテニスのインターハイは8月1日から岡山県で開かれます。
-
弥生器楽クラブ 全国3位

伊那弥生ヶ丘高校器楽クラブは今月26日と27日に大阪で開かれた全国高等学校ギター・マンドリン音楽コンクールで全国3位に相当する全国知事会賞を受賞しました。 29日伊那弥生ヶ丘高校の終業式で受賞報告と演奏が行われました。 今回演奏したトレピック・プレリュードという曲はマンドリン独特の、音を小刻みに演奏する技法が多く取り入れられています。 音楽コンクールには全国から60の高校が集まり伊那弥生ヶ丘高校は3位相当の全国知事会賞を受賞しました。 器楽クラブはおよそ55年の歴史がありその中で最も優秀な成績だということです。 クラブ員は3年生11人、2年生29人、1年生14人の合わせて54人で、週に6日基礎練習を大切に活動しているということです。 クラブのメンバーは「これまでの努力が報われて嬉しく思います。 みんなが目標に向かって一つになれたことが良かったです。」と話していました。
-
夏休みの小学生対象 大芝こども未来塾

夏休み中の子どもたちを対象にした南箕輪村公民館が主催する3日間の体験教室「大芝こども未来塾」が、28日から始まりました。 この日は、南箕輪村の大芝高原みんなの森で未来塾が開かれました。 子どもたちは、桜やホウノキの枝を使って弓と矢を作り、友達と競って矢を放っていました。 中には、トカゲを見つけて捕まえた子どももいました。 みらい塾は、7年前から夏休みの小学生を対象に、南箕輪村公民館が開いている人気の講座です。 募集受付開始5分で定員に達してしまう人気ぶりで、今年は、2回に分けて開催することにしました。 前半の今回には、村内の小学校の1年生から6年生まで35人が参加しました。 弓の練習を終えると、子どもたちに宝の地図が手渡されました。 地図には、目的地の目印や、ミッションが書いてあります。 5つの班に分かれて、子どもたちは相談しながら、目的地を目指します。 こちらの班の目的地にはクマの写真が飾ってありました。 ミッションは、全員が的に矢をあてることです。子どもたちは順番に矢を放っていました。 前半は30日までで、28日は南箕輪村公民館に宿泊するほか、川遊びや魚のつかみ取りなどが予定されています。
-
園児と高校生がフェイスペインティングで交流

高遠高校の芸術コースの2年生5人は27日、学校近くの高遠保育園を訪れ、顔や体に専用の絵具で絵を描くフェイスペインティングをして交流しました。 顔や体には無数の色が塗られています。 女の子は猫になりきっています。 使うのは、専用のクレヨンや絵具です。 生徒たちは園児からのリクエストを受けると、顔や腕などに絵を描いていきました。 芸術コースでは、これまで美術館のアシスタントや小学校の写生大会で児童に絵のアドバイスをするなど芸術分野を活かした、学習活動を行ってきました。 今回は、子供たちに絵を描く楽しさや面白さを、芸術とは違う手法で伝えようと、フェイスペインティングを企画しました。 最初は腕や顔に描いてもらっていましたが、中にはお腹に描いてもらう子もでてきました。 10分程すると、お腹の絵も完成です。 園児たちもしばらくすると、専用のクレヨンを手に取り、鏡をみながら、自分の顔や体に絵を描いて楽しんでいました。 高遠高校では、生徒たちが学校外で学ぶ体験型学習活動をこれまでの高遠町や長谷地域から伊那市全域に広げていくことにしています。
-
フェンシングで全国 競泳で北信越

南箕輪中学校の赤羽正輝君がフェンシングで全国大会に、また加藤幸磨君が競泳で北信越大会に出場します。 21日2人は南箕輪村役場を訪れ原茂樹副村長に出場の報告をしました。 赤羽君は3年生で小学6年生以来2度目の全国出場となります。 8位までが全国大会に出場できる予選の県少年フェンシング大会で3位となりました。 全国大会は22日から東京で開かれます。 加藤君は2年生で北信越大会は初出場となります。 県総合体育大会200メートル平泳ぎで3位入賞し北信越大会出場を決めました。 北信越大会は来月5日に富山県で開かれます。
-
山の日制定記念展「山岳の詩」

山の日制定を記念した写真展「山岳の詩」が伊那市長谷の南アルプスフォトギャラリーで開かれています。 会場には南アルプスと中央アルプスまたそこに咲く高山植物の写真35点が展示されています。 山岳地帯の雄大な景観や動植物の営みのほか季節の移り変わりが撮影されています。 写真展を開いている津野祐次さんは日本山岳写真協会南信支部支部長で主に中央アルプス、南アルプスをフィールドとしています。 塩見岳を写した作品「塩見岳山群」は荒川岳から撮影したもので山が険しいことからシカが入れず高山植物が今も残っています。 「仙丈ヶ岳」は雪が残る仙丈を写したもので雪解け水がやがて麓で暮らす人間に恵みを与えてくれることを表現しています。 写真展でテーマとしている山の日は、山に親しむ機会を得て山の恩恵に感謝しようと制定されたものです。 日付は8月11日で祝日の一つとなります。 写真展「山岳の詩」は8月31日まで伊那市長谷の南アルプスフォトギャラリーで開かれています。
-
新山小で伊那節踊りの練習

伊那市の新山小学校で伊那まつりの市民踊りに向けて、伊那節と勘太郎月夜唄の踊り練習が20日に行われました。 伊那節振興協会会員で踊りインストラクターの池上龍子さんが指導しました。 新山小学校の体育館には、全校児童が集まり、池上さんの踊りをまねながら練習しました。 新山小では、毎年この時期、伊那まつりの市民踊りに全員が踊ることができるようにとダンシングオンザロードのドラゴン踊りや伊那節、勘太郎月夜唄の踊り練習をしています。 池上さんは、動作がおおげさにならないようになどと児童たちに話しながら、伝統の伊那節の踊り方を教えていました。 池上さんは、「遠くに行ってふるさとを思いだす時、大人になった時にこの踊りがきっと役に立つので、しっかり覚えてください。」と児童に呼びかけていました。 新山小の児童は、8月6日の伊那まつり市民踊り当日は、富県連として参加することになっています。 さらに伊那節は、9月の運動会でも披露することになっています。
-
弥生高 久保田同窓会長が激励

伊那弥生ヶ丘高校の全国大会に出場する選手を久保田裕子同窓会長が20日激励しました。 高校の校長室では、これから開かれる全国大会に出場する故人やクラブの代表者が集まり、久保田同窓会長の激励を受けました。 杉崎あおいさんは、全国高校総合文化祭小倉百人一首かるた部門に出場します。 同じくリーダーズコール部門には、音楽クラブの6人が出場します。 全国高校ギター・マンドリン音楽コンクールには、器楽クラブの54人が出場します。 このほか、男子ソフトボール部と小林愛海さんが全国大会に出場します。 小林さんは、少林寺拳法です。 それぞれ代表者が、「去年よりいい成績で、まず1勝」などと決意表明しました。 久保田同窓会長は、「大会に出場できる幸せをかみしめながら、実力を発揮し、楽しんできてほしい」と激励しました。 大会は、7月下旬から8月上旬にかけて、広島や大阪、岡山で開かれます。
-
長野地区少年少女詩吟大会

詩吟教室に通う子供たちが稽古の成果を披露する、長野地区少年少女詩吟大会が18日飯島町で開かれました。 大会は、技術向上や交流を目的に毎年この時期に開かれていて、県内各地から170人が出場しました。 コンクールは、一人で行う独吟の部と、3人一組で行う合吟の部で行われ、小学生から高校生が学年ごとに発表しました。 大会は、詩吟の岳風流を教える日本詩吟学院が開いているものです。 学院では、子供たちに詩吟を通じて礼儀作法や文化を学んでもらい、吟道を究めてほしいと話していました。
-
中島副知事 信州型自然保育視察

長野県の中島 恵理副知事が、県の信州型自然保育に認定されている伊那市の高遠第2・第3保育園を視察し、保護者や地域住民と意見交換しました。 19日は、中島副知事が高遠第2第3保育園を訪れました。 園児たちがいつも遊んでいる裏山へ中島副知事も一緒に行きました。 園児たちは、園舎が見下ろせる山へどんどんと登っていきました。 第2・第3保育園は、自然環境や地域資源を取り入れた保育を行う団体を県が認定する「信州型自然保育認定制度」に、去年認定されました。 活動を視察し、住民と意見交換してもらいたいと、高遠第2・第3保育園と地域の未来を考える会が、副知事を招きました。 19日遊んだ場所は、子どもたちが作った小屋のある場所です。 子どもたちは、昆虫を見つけたり木の実を拾ったりして自然に親しんでいました。 保育園の活動を視察した後、会場を、荒町公民館に移して、中島副知事の講演と、地域住民との意見交換が行われました。 中島副知事自身も、富士見町の自然保育で子どもを育てた経験から、自然体験が豊かな子どもほど自己肯定感が強く、生きる力を養うことができると話しました。 意見交換会では、「自然保育は少人数ならではだと思うが、統廃合し、こどもを1か所に集める政策がすすめられている」といった意見や、「保育だけの支援では移住しづらい。定職のサポートも検討してほしい」などの要望がありました。 中島知事は、「農山村で暮らしていくための支援を検討したい」と答えていました。 長野県内では現在、72の園が信州型自然保育に認定されていて、うち、伊那市では高遠第2・第3保育園を含め3園となっています。
-
哲学者内山節さんが伊那市の食育を視察

哲学者で田舎暮らしを実践している内山節(たかし)さんが、伊那市の保育園や小中学校の学校給食や農業体験の取り組みを、14日視察しました。 内山さんは、東京と群馬県上野村を往復しながら、田舎暮らしを実践している哲学者です。 今日は、伊那市教育委員とともに市内の保育園や小中学校、4か所を訪れました。 そのうち、長谷保育園では、年間を通して、地域の住民から協力を得て農業や食について学んでいると説明を受けました。 そのあと、園舎の隣にある、今年から保育園が借りている畑を視察しました。 畑は、地域住民が管理していて、栽培された野菜は、子どもたちが収穫したり、給食として提供されています。 伊那市教育委員会では、市内のすべての小中学校で給食や食・農業を学ぶ体験事業を実施していて、今後も事業に力を入れていくとしています。
-
荒井区少年少女消防クラブが夏季訓練

伊那市の荒井区少年少女消防クラブの夏季訓練が16日に行われ、小学生が消火活動を体験しました。 小学1年生から6年生まで8人が参加し、小型ポンプを使った消火活動を体験しました。 荒井区少年少女消防クラブには区内の小学生29人が所属しています。 年間を通して規律訓練や火災予防の啓発活動などを行っていて、毎年7月に夏季訓練を実施しています。 子ども達は消防署員の指導を受けながら2人一組で放水を行いました。 荒井区では、「自分たちの安全は自分たちで守るという意識を子どものうちからもってもらいたい」と話していました。 次回は10月に、整列や行進の仕方などを学ぶ規律訓練を行う予定です。
-
木下北・南保育園の統合後の候補地「北城地区」

木下地区保育施設整備検討委員会は8日箕輪町役場を訪れ木下北保育園と木下南保育園の統合後の建設候補地を北城地区とする意見書を提出しました。 8日は木下区の馬場恭平区長ら4人が町役場を訪れ白鳥政徳町長に意見書を提出しました。 検討委員会は去年10月に設置され建物の老朽化で整備が必要な木下北と南保育園について統合を前提に建設候補地の選定に取り組んできました。 候補地として11か所があがりその中から北城地区に絞り込んだものです。 候補地の選定理由として保護者の送り迎えの安全確保や区民の理解を得るため区の中心付近としたことなどをあげています。 白鳥町長は「農業振興地域で課題もあるが検討していきたい。」と話していました。 町では保育園整備計画に基づき平成32年度までの完成を目指したいとしています。
-
元Jリーガー小針さんが南箕輪小学校で夢授業

産学官が連携して進めるキャリア教育の一環で、14日、南箕輪小学校で元Jリーガーを招いての特別授業が行われました。 夢授業と題し行われた特別授業では、元Jリーガーで、現在は帝京大学サッカー部のコーチをしている小針清允さんが先生を務めました。 この日は、5年生がこの授業を受けました。 南箕輪村では、今年度から小学校でもキャリア教育を進めていくことになりました。 全国各地の小学5年生を対象に、「JFLこころのプロジェクト」を展開している公益財団法人日本サッカー協会に村が依頼し、「夢授業」が実現しました。 前半は、全員で手を繋いでゴールを目指すゲームを行いました。 この後教室では、小針さんの幼少期からプロのサッカー選手になるまでの話を聞きました。 7歳でサッカーを始め、9歳の時にテレビで観た選手のプレーに魅了されてプロへの道を決意したということです。 小針さんは「これまで2回の挫折を味わいサッカーを辞めようと思ったこともあったが、自分の熱い想いを持ち続け行動に移すこと、両親や友人の励ましの言葉があってプロのサッカー選手になれた」と話しました。 夢教室は15日も開かれる予定で、元女子バスケットボール選手の岡里明美さんから話を聞きます。
-
芸術、文化団体が交流

箕輪町の芸術文化団体が一堂に集う芸術文化のつどいが箕輪町の松島コミュニティセンターで開かれました。 催しでは、町内で活動している太鼓や舞踊、音楽サークルなど、17のグループが発表をしました。 みのわ太鼓ジュニアは小学生から中学生のメンバーが力強い演奏を披露しました。 また、歌声喫茶で演奏を披露しているアンサンブルドルチェは、歌謡曲を演奏し、会場の人たちと一緒に歌を楽しんでいました。 この催しは、町内で活動する文化団体の交流や親睦を深めようと毎年開かれています。 主催するみのわ芸術文化協会の大槻武治理事長は、「自分たちの世界に留まることなく、別の団体と協力して、活動の活性化を図っていってほしい」と話していました。
-
伊那市の菓匠Shimizu 清水慎一さんが講演
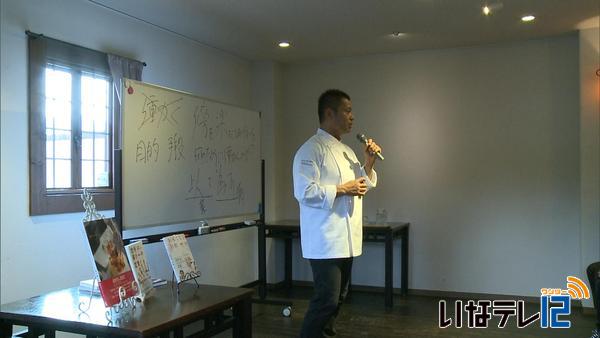
伊那市上牧の菓子店、菓匠Shimizuの清水慎一さんとザ・リッツ・カールトンホテルの前の日本支社長、高野登さんの講演会が2日、伊那市内で開かれました。 講演会は、小布施町に本社を置く出版社、文屋が開いたものです。 清水さんは、2014年に文屋からレシピ本「縁(えにし)」を出版しています。 菓子作りにかける想いや社員の様子のほか、取引先の農家がレシピと共に紹介されています。 清水さんは、「菓子づくりという手段を通して社員や地域の人を幸せにしていく事が私の仕事であり目的です」と話していました。 同じく文屋から本を出版した高野さんは、「自分の欲のためではなく人のために行動する事が会社の一体感につながる」と話しました。 文屋では、本の書き手、作り手、読み手の交流と学びの場として東京や長野市で年に4回ほど講演会を開いていて、この日は読者60人ほどが訪れました。
-
伊那市長賞に吉澤さん

第19回伊那ビデオクラブ作品コンクール表彰式が3日に伊那市のいなっせで行われました。 伊那市長賞には、地元の御柱を描いた作品吉澤豊さんの作品「福地の神様お願いだ」が選ばれました。 「福地の神様お願いだ」は、吉澤さんの地元伊那市富県北福地の御柱の様子を5分にまとめた作品です。 地元目線でとらえた区民の表情やテンポの良い編集技術が評価されました。 伊那ケーブルテレビ賞は、前田耕一さん、映画監督の後藤監督賞には、河野恆さんの作品が選ばれました。 今回のコンクールには、16人の会員から26作品の応募がありました。 伊那ビデオクラブの赤羽仁会長は、「生涯学習をビデオを通じ実践している。地域に役立つ作品をこれからも作っていきたい。」とあいさつ。 コンクールを共催している伊那ケーブルテレビの向山公人会長は「放送に協力いただき番組の充実につながっている。」と感謝していました。 なお、伊那ケーブルテレビが日ごろ放送している放送部門賞の表彰もあり、3人に賞状が手渡されました。 今回のコンクール入賞作品は、後日ご覧のチャンネルで放送します。
-
伊那西高校文化祭 第32回西高祭

伊那市の伊那西高校の文化祭第32回西校祭が2日から始まりました。 今年のテーマは「Sparkle!~フレッシュに駆けぬける甘ずっぱい夏」で、今を自分たちらしく輝き、駆け抜けていきたいという思いが込められています。 校内では、各クラスやクラブによる出店や展示が行われています。 3年1組は、ありがとう伊那西と題し、校舎のジオラマを制作しました。 5月から制作をはじめ、発砲スチロールを使って校舎を再現しました。 1年1組は、お祭りをテーマにした展示を行っています。 ヨーヨー釣りや輪投げなどがあり、まつりの雰囲気を楽しむことができます。
-
駒ヶ根工業高校コマレンジャー同好会が小学生と紙飛行機作る

地域への奉仕活動の一環で駒ヶ根工業高校の生徒が2日、箕輪町の箕輪中部小学校を訪れ、子ども達に紙飛行機の作り方を指導しました。 箕輪中部小学校を訪れたのは駒ヶ根工業高校の文化系クラブ「コマレンジャー同好会」の生徒6人です。 地域に出向き、環境や防犯に関する啓発活動や、ものづくりの魅力を伝える活動を行っていて箕輪町で活動するのは今回が初めてです。 A4サイズの紙に印刷された図の通りに切り取って翼を作り、割りばしを胴体にする紙飛行機の作り方を指導しました。 この日は箕輪中部小学校の授業参観の日で2年生94人が保護者と一緒に体験しました。 紙飛行機は1時間ほどで完成しました。 子ども達はどこまで飛ぶか友達と比べながら何度も飛ばして楽しんでいました。
-
地域ぐるみで10年後を見据えた人材育成

10年後を見据えた人材育成の取り組み、伊那谷人材育成ラボが1日伊那市の伊那中学校で行われました。 伊那谷人材育成ラボは産学官が協働して地域の人材育成を図ろうと行われたもので学校や企業、行政からおよそ20人が集まりました。 この取り組みは経済団体や教育機関、上伊那広域連合などで構成し地域の未来について考える活動を行っている郷土愛プロジェクトの取り組みとして行われたものです。 人材育成ラボでは、学校、企業ともに人を育てる場所であり、互いに学びあうことが地域の力になるとしています。 今日は企業から伊那中を訪れた社員が授業や掃除の様子を見学しました。 ほかには学活の時間に社員が話をしました。 学校の様子を見学した社員は「今やっている勉強が社会に出てから知識の肥やしになります。知識を得て成長することで個人そして地域全体が成長します。」と話していました。 伊那谷人材育成ラボではこの取り組みを地域を担う人材育成のモデルにしていきたいとしていて次回は企業の現場の視察を計画しています。
-
選挙の意義や1票の大切を理解

選挙の意義や1票の大切さを理解してもらう18歳選挙の啓発が1日、伊那市高遠町の高遠高校で行われました。 これは7月10日投開票の参院選から選挙年齢が18歳以上に引き下げられることを受け開かれたものです。 まず伊那市選挙管理委員会の春日州一さんが「大事な1票を棄権することなく行使してください。」と投票を呼びかけました。 また上伊那地方事務所の土屋晴香さんが選挙権を持つ意味などについて話をしました。 土屋さんは「18歳、19歳の皆さんは自ら考え判断する能力を持っています。政治への関心や参加意識の高まりに期待しています。」と話していました。 参院選の選挙は7月11日までに18歳になる人が対象で伊那市内ではおよそ1500人があらたに有権者となります。
201/(火)
