-
「芝田会」発足20周年記念「郷土をささえた書画展」始まる

上伊那の美術愛好者で作る「芝田会」は、発足20周年を記念した書画展を、11日から伊那文化会館で開き、伊那市出身の日本画家小坂芝田の作品を中心に展示しています。 会場には、小坂芝田の作品を中心に、中村不折や池上秀畝などの作品163点が展示されています。 芝田会は、個人の家で眠っている貴重な作品を多くの人に見てもらおうと平成6年に発足し、現在は80人ほどの会員がいます。 今回は発足20周年を記念した書画展となっていて、初日の今日は、芝田の四男で彫刻家の小坂昇平さんが、東京から訪れテープカットを行いました。 小坂芝田は、明治5年に伊那市小沢で生まれ、16歳の時に絵を始めました。 中国絵画の技法「南宗画」から影響を受けた、日本画の画法のひとつ「南画」を描き、大正6年に45歳で亡くなりました。 今回の書画展では、伊那市の文化財に指定されている「十六羅漢図」なども見る事ができます。 芝田会発足20周年記念「郷土をささえた書画展」は17日(土)まで伊那文化会館で開かれています。
-
芝平石灰岩採掘場跡の環境整備

昭和50年代に集団移住した伊那市高遠町芝平の元住民でつくる「芝平会」は、4日、伊那谷遺産に今年3月に追加登録された「芝平石灰岩採掘場跡」の環境整備作業を行いました。 この日は、芝平会のメンバー16人が参加し、立木の伐採を行いました。 ここは、かつて土壌改良のための肥料となる石灰岩が豊富に産出されました。 盛んに採掘が行われていたのは幕末から明治37年までの間で、昭和20年頃まで続いていたということです。 採掘場跡では、石灰岩の露頭が確認できます。 その周辺には、切り崩した石灰石を運ぶために敷かれたトロッコの道、焼いて粉状の石灰にするための窯の跡などがあります。 窯の周辺には、石灰石がまだ残されていました。 伊那谷遺産は、天竜川上流河川事務所などが取り組むプロジェクトで、土木、暮らし、自然にまつわる先人たちの足跡を残していこうと、これまで98件が登録されています。 子どもの頃、採掘場での作業を見たことのある北原厚さんは、採掘場と共に伊那谷遺産に登録された「芝平集落」の800年の歴史と、採掘作業に携わってきた先人へ、思いをはせていました。 芝平会では、今後、年に1回程度整備作業をする計画で、歴史の勉強をするために子ども達にも見に来て欲しいと話していました。
-
電気機関車 公開

箕輪町郷土博物館は、5日博物館前に展示している電気機関車の内部を公開し、訪れた子ども達が運転士気分を味わっていました 電気機関車「ED19」は、昭和35年に飯田線に導入され、引退するまでのおよそ15年間活躍しその後、郷土博物館前に展示されています。 子ども達は運転席に座ると国鉄OBなどでつくる電気機関車保存会のメンバーから運転の仕方を聞き、母親らは子供達の様子を写真に撮ったりしていました。 館内では、博物館オリジナルのED19のペーパークラフト作りや鉄道模型の運転体験コーナーが設けられ、訪れた親子づれは鉄道の魅力の一端に触れていました。
-
中村不折の書簡を御園の御子柴家が寄贈

伊那市御園の御子柴家に伝わる、書家で画家の中村不折の書簡が、1日、高遠町歴史博物館に寄贈されました。 寄贈されたのは、29歳の中村不折が、従兄弟の御子柴 琴治郎に宛てたものです。 寄贈したのは、伊那市御園の御子柴 錦さんです。 琴治郎は、錦さんの夫・文孝さんの祖父の弟で、中村不折とは従兄弟の関係になります。 まだ、画家として大成する以前・鈼太郎(さくたろう)の名で、東京で暮らしていた不折が、故郷の母の面倒を御子柴家に頼んだもので、不折の若い頃の状況を知ることができます。 その他、不折からのハガキ2枚、江戸時代の辞書・「頭書字彙(とうしょじい)」12巻、御子柴家伝来の裃(かみしも)が寄贈されました。 ハガキは、不折の絵を使用した絵葉書です。 ほかに、江戸時代の御園村に伝わる古文書や古地図52点が、寄託されました。 御子柴さんは、「不折の若い頃の研究に役立てて欲しい」と話していました。 高遠町歴史博物館では、寄贈・寄託された資料の整理を行い、2016年の中村不折・生誕150周年特別展などで一般公開していきたいとしています。
-
美篶の洞泉寺で大般若会の法要

伊那市美篶の洞泉寺で30日、600巻の経典「大般若経」を読み上げる大般若会の法要が行われました。 本堂では、13人の僧侶による力強い読経の声が響き渡っていました。 虫干しの意味あいもある大般若会では、経典を上から下へと落とす「転読」という方法で、経典を読み上げます。 大般若経はおよそ1,400年前、三蔵法師が釈迦から受け取り、中国へ伝えたものと言われ、仏教の基本思想の一つが書かれています。 経典を読む時に起きる般若の風に当たると、一年間の無病息災や家内安全などのご利益があると言われています。
-
学力テスト 結果公表は市単位で

伊那市教育委員会は今回行われた、全国学力・学習状況調査における結果の公表について28日、去年までと同じ市単位での発表とすることを決めました。 文部科学省が去年11月に今年度の全国学力・学習状況調査結果の公表について、教育委員会の責任で学校名を明らかにした結果の公表が出来ることになりました。 28日は伊那市教育委員会4月定例会で協議が行われ、学校名を明らかにせず去年と同じ市単位での発表を行うこととしました。 参加者からは、「しっかりとした配慮があれば、結果は学校単位で発表した方が良い」「学校名を出すことで序列や過度な競争が生まれる」などの意見が出ていました。 協議の結果、市単位でこれまで通り全国平均との比較で公表することが決まりました。
-
南部小2年生が信大でどんぐり植え

南箕輪村の南部小学校2年生の児童が、去年大芝高原で拾ったどんぐりを28日、信州大学農学部の畑に植えました。 南箕輪村は大芝高原の松クイ虫対策などで、針葉樹から広葉樹への樹種転換を計画していて、その一環で行われたものです 28日は、南箕輪南部小学校2年生32人が参加しました。 子どもたちが去年の秋、大芝高原で拾ってきたどんぐりは信大農学部の畑で発芽させ、大きくなったら大芝高原に植樹する計画です。 どんぐり4つをひとかたまりにして土の中に埋めていきました。 畑で指導したのは信大農学部の小林元准教授と、信大生8人で、植えたどんぐりの水やりなどの管理をしていきます。 どんぐりは、1週間ほどで発芽して、来年の秋には大芝高原に植樹される予定です。
-
南ア50周年に向け合唱曲「讃歌-長谷」披露

伊那市長谷小学校の児童は5月24日の南アルプス国立公園指定50周年記念式典に合わせて作られた合唱曲「讃歌-長谷」を23日市の関係者に披露しました。 讃歌-長谷は、南アルプス国立公園指定50周年を記念し、今年の3月に作られた合唱曲です。 長谷小学校の音楽専科の小口稔子(としこ)教諭が作詞と作曲をしました。 これまでは、学年毎に練習を行ってきましたが、全校で合わせて歌ったのは今日が初めてという事です。 小口教諭は「子供達に、長谷の自然や歴史、災害での教訓などを後世に伝え、地域の愛唱歌となってほしいと」と話していました。 歌は1番と2番があり1番は長谷の自然や風景を、2番では、四季の移ろいを表しています。 小口教諭は、本番までに高音と低音のバランスを調整したいと話していました。 長谷小学校の児童が出演する、南アルプス国立公園指定50周年記念式典は来月24日伊那市の伊那文化会館で開かれる事になっています。
-
端午の節句飾りと古い写真

伊那市西町の旧井澤家住宅で、端午の節句飾りと古い写真の展示会が開かれています。 端午の節句飾りコーナーには、旧高遠藩士の鎧や兜など40点が並んでいます。 当時名主だった東條家に伝わる裃は、高遠城に行く際に羽織っていったものとされていて、土蔵には一緒に刀も保管されていました。 鑑定により、江戸時代後期のものとわかり、高遠城の当時の殿様から与えられたものと推察されています。 一方、昔の写真コーナーには、幕末から昭和までのもの50枚が展示されています。 当時の有力者が所有していたもので、人物や風景が当時の様子を今に伝えています。 旧井澤家住宅を管理している伊那部宿を考える会では、「生活環境が変わってきて、ゆとりもない時代。ゆったりと眺めてもらい、当時の雰囲気にひた浸ってもらいたい」と話しています。 この展示は、5月6日まで西町の旧井澤家住宅で開かれています。
-
全国学力テスト 一斉に実施
全国のすべての小学校6年生と中学校3年生を対象にした「全国学力テスト」が22日、全国一斉に実施されました。 このうち、伊那市・箕輪町・南箕輪村の合わせて30の小中学校では、およそ2,100人がテストを受けました。 全国学力テストは、全国的に子ども達の学力状況を把握する目的で、平成19年度から文部科学省が行っています。 テストは、国語と算数・数学の、基礎知識を問う問題Aと、知識の活用力を問う問題Bに分けて実施されました。 全国学力テストは、今回から各市町村の教育委員会が、一定の条件を満たせば学校別に成績を公表できることになっています。 伊那市・箕輪町・南箕輪村の各教育委員会では、公表するかどうかについて今後検討して決めていくということです。 テストの結果は、文科省が8月頃発表する予定です。
-
伊那東大社例大祭で浦安の舞奉納

伊那市の伊那公園にある伊那東大社の例大祭が20日行われ、地元の小学校6年生16人が浦安の舞を奉納しました。 浦安の舞は、近代神楽の一つで昭和15年に全国各地で奉納されたのが始まりです。 浦安の浦とは心を示す古語で、安らかな心で平和を祈る意味があります。 扇を使う扇舞と鈴を使う鈴舞があり、舞の途中で持ちかえます。 伊那東大社では、昭和15年から欠かすことなく奉納しています。 集まった氏子総代や区の役員を前に、児童16人は雅楽の音色に合わせて舞を披露しました。 伊藤光宣宮司は「20日集まった保護者の中にも経験した人は多いと思う。大人になった時に自分の子どもにも地域に伝わる伝統を引き継いでいってほしい」と話していました。
-
ギャラリートーク&コンサート 豊の宴
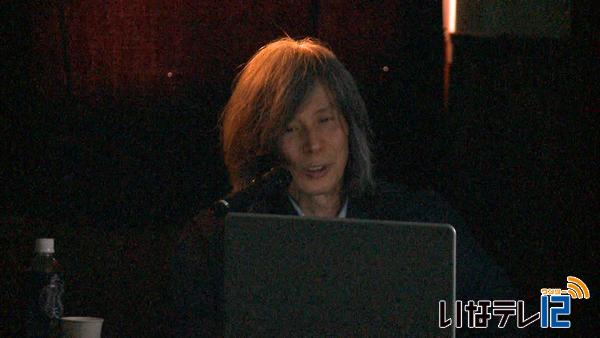
伊那市創造館で縄文土器の写真を展示している写真家、滋澤雅人さんとシンガーソングライター葦木美咲さんのギャラリートーク&コンサート「豊の宴」が19日、伊那市創造館で開かれました。 伊那市創造館では、縄文土器をテーマにした滋澤雅人さんの写真展が開かれています。 19日のギャラリートークとコンサートは、これにあわせ開かれたもので、およそ40人が訪れました。 滋澤さんは東京都在住の写真家で、2002年から12年間、縄文土器を撮影しています。 滋澤さんは、撮影の際、土器が制作された当時の光を再現することに力を注いでいると話します。 滋澤さんは、「土器に光を当てると、表情が浮かび上がってくる。縄文の人たちは、光に関してとても繊細な感受性を持っていたことは間違いない」と話していました。 一方、葦木さんは松本市出身で、全国の遺跡や史跡でコンサートを行っています。 葦木さんは富山県に伝わる民謡「こきりこ節」を披露しました。
-
長谷中学校南アルプスジオパークについて学ぶ

南アルプスの世界自然遺産登録を目指すジオパーク協議会が今年度から実施する、南アルプスを授業に取り入れた教育プログラムの第1弾が18日、地元伊那市長谷の長谷中学校で開かれました。 これは、地域の子ども達の郷土教育に南アルプスの授業を取り入れようと今年度からジオパーク協議会が開くものです。 講座は、総合学習の時間で、恵まれた自然との関わり方を考えるきっかけにしようと開かれたもので、今日は全校生徒32人が講座を聞きました。 講師は、伊那市世界自然遺産登録推進室の藤井利衣子さんが務めました。 藤井さんは、ジオパークや南アルプスのつくりについて話しました。 「人々の暮らしや歴史、動植物などは、地形に大きく関わっている。その関係を知りながら楽しく学習してほしい」と話しました。 講座の最後には、生徒が1人ずつ中央構造線を構成する層を記入してつくりを学びました。 長谷中学校では、今年度総合学習で3つのコースに分かれて長谷地域について学びます。 そのうちの1つ、ジオパークについて学ぶ「自然探索コース」では、パンフレットや案内看板などの制作を検討しているということです。
-
刻字教室の崇嶺会が作品展

伊那市を中心に活動している刻字教室、崇嶺会の作品展が、17日から伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで始まりました。 崇嶺会は伊那市と箕輪町の4会場で、週に1回教室を開いています。 会場には、29人の作品90点が並んでいます。 毎年テーマを決めて作品を展示していて、今年は、歌の歌詞やことわざ、俳句などを題材にしました。 刻字はもともと漢詩を題材にしていますが、平仮名を使って誰でも読める作品を作ろうと、このテーマにしたということです。 会では「カラフルでインテリアとしても楽しむ事ができる。色使いなどそれぞれの個性を楽しんでほしい」と話していました。 第34回崇嶺会刻字展は、20日(日)まで、伊那市のいなっせで開かれています。
-
伊那谷まあるい学校 プレオープン

公立の学校に通いながら自然の中で自分のやりたい事を見つけるもう1つの学校、オルタナティブスクール「伊那谷まあるい学校」が15日、伊那市高遠町のポレポレの丘にプレオープンしました。 この日は、伊那谷まあるい学校に通う予定の子どもとその保護者合わせて8人が集まりました。 学校の代表は、元公立小学校教諭で伊那市上新田の濱大輔さんです。 濱さんは、去年まで公立小学校の教諭を務めていましたが、その時に子ども達1人1人のペースに合った授業ができないという壁に当たり、今回オルタナティブスクールを開校しました。 オルタナティブスクールとは、公立の学校に通いながら、個性を重視した教育制度の中で学ぶ学校です。 伊那谷まあるい学校は、子ども達のやりたい事を引き出してあげることを1番の目的としています。 この日は、市内と山梨県に住む2歳から9歳までの子どもと大人が参加し、輪を作り今後どんなことがやりたいかを話し合いました。 子ども達からは「どろんこ遊びがしたい」「校舎を建てたい」といった意見が出ました。 伊那谷まあるい学校は、毎週火曜日水曜日土曜日日曜日に伊那市高遠町のポレポレの丘で開校しています。 4月26日と5月18日に、高遠町高齢者生きがいセンターで学校説明会を開く予定です。
-
山寺伝統の「やきもち踊り」奉納

県の無形民俗文化財に指定されている伊那市山寺の「やきもち踊り」が、13 日、白山社・八幡社合殿で奉納されました。 羽織、袴姿で、足を高くあげ、飛び跳ねるようにして踊る「やきもち踊り」。 このユーモラスな踊りは、県の無形民俗文化財に指定されています。 この日は、伊那市山寺にある白山社・八幡社合殿で、地元住民でつくる保存会、およそ30人が踊りを奉納しました。 踊りは、前踊り、中踊り、後踊りがあり、その合間には酒盛りが行われます。 踊り手たちは、キセルで刻み煙草を吸いながら、アユの串焼きを肴にどぶろくを酌み交わしました。 最後の酒盛りを終えると、下駄を境内の外に出し、後踊りが行われます。 踊りが終わると、踊り手たちは一斉に逃げ出します。 逃げ遅れると厄病にかかると言い伝えられていて、先を競って鳥居の外に駆け出しました。
-
諏訪ー伊那峠のサミット

歴史や文化をキーワードに、伊那地域と諏訪地域の交流がスタートしました。 13日は、伊那市と茅野市の境にある国道152号の峠の茶屋で、諏訪―伊那峠のサミットキックオフミーティングが開かれました。 諏訪地域からは、25人、伊那地域からは15人が参加しました。 峠の茶屋の展望台で、八ヶ岳山麓を望み鳥獣たちの成仏を祈る神事 原山遥拝です。 平安時代から江戸時代に至るまで、諏訪地域には、狩猟と肉食に関する免罪符的なものがあり、その神事を再現しました。 特に鹿は、特別な存在で、ある神職は、「鹿なくては御神事すべからず」とまで書き残しています。 神にささげた鹿の供物。 伊那市長谷ざんざ亭の長谷部晃さんが、独自の解釈で作り奉納しました。 内容は、鹿肉のローストと脳みそ、パテ、レバーペースト、血のペーストです。 これを参加者が味わいました。 さらに、キーワードとなる鹿肉を使った弁当を参加者が味わいました。 鹿肉のそぼろ、レバーペースト入りのキッシュなど、鹿肉の風味を活かしながら臭みを感じさせない仕上がりになっていました。 今回の峠のサミットは、伊那地域の高遠ぶらりプロジェクトと諏訪地域の歴史を研究しているスワニミズムなどが開いたもので、両地域の地質や信仰についても理解を深めました。 前の高遠高校校長で、この春諏訪清稜高校の校長に就任した石垣正志さんは、「伊那を知らずして諏訪は理解できないし、伊那を掘り下げれば必ず諏訪に突き当たる」と話しています。
-
クロスペンアカデミー 山岸淳子さん講演会
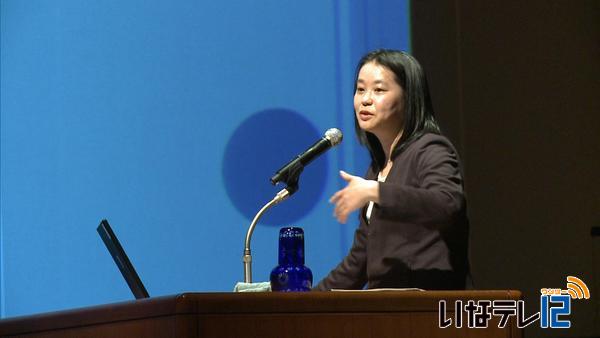
伊那北高校の今年度の薫ヶ丘クロスペンアカデミーが12日に開かれ、伊那市出身で日本フィルハーモニー交響楽団の山岸淳子さんが講演しました。 12日は全校生徒や保護者など、およそ700人が参加しました。 講演会では、山岸さんが自身の体験を振り返り、進路について話しました。 山岸さんは、伊那北高校卒業後、東京芸術大学音楽学部楽理科に進学し、現在は日本フィルハーモニー交響楽団の特命担当として新規事業の開拓などに携わっています。 高校生の時、山岸さんは進路に悩んでいたといいます。 音楽の道に進みたいと考えてはいましたが、人前で演奏するのが好きではなかったためです。 現在の道に進んだきっかけは、ピアノ教室の先生が「音楽の理論を学ぶ楽理科の存在を教えてくれたこと」だといいます。 薫ヶ丘クロスペンアカデミーは、生徒に広く社会を知り、将来について考えてもらおうと同窓会やPTAなどが毎年開いています。
-
中尾歌舞伎春季定期公演中止に

中尾歌舞伎保存会は、4月29日に予定していた春季定期公演を中止にすることを10日決定しました。 中尾歌舞伎の稽古と発表の場所となっている伊那市長谷の中尾座です。 4月29日の春季定期公演もここで行われる予定でした。 保存会では、指導者の西村清典さんの死去により、春季定期公演の実施について検討を重ね、実施する方向で進めていました。 しかし、会の大きな柱で指導者だった西村さん急逝の影響は大きく、本番までに仕上げられないとの判断からやむなく中止を決断しました。 保存会では、11月の秋季定期公演で、西村さんが亡くなるまで指導に携わり春の公演で予定していた演目「一谷嫩軍記 熊谷陣屋の段」を披露する予定です。
-
上伊那工芸会30周年記念展

上伊那の工芸家でつくる上伊那工芸会による30周年記念展が9日から伊那市の伊那文化会館で開かれています 上伊那工芸会は上伊那の工芸作家有志が集まり昭和60年発足し現在は21人が所属しています。 会では、定期的に作品展を開いていて、今回は30周年記念展として会員20人と物故者3人から68点が寄せられました 会場には 人形や鍛金、陶磁、染織など、会員の近作や代表作品が並んでいます。 訪れた人達の中には、作家から金属の加工方法や工程など直接説明を受ける姿も見られました。 会では、「この30年で互いに刺激を受け上達し、新たな時代を作ってきた。 今後も活動を通じて次の世代を担う作家を育てていきたい」と話していました。 この作品展は13日(日)まで、伊那市の伊那文化会館で開かれています。
-
伊那技術専門校 16人入校

南箕輪村の伊那技術専門校の今年度の入校式が8日行われ、16人の入校生が技術習得への第一歩を踏み出しました。 今年度、伊那技術専門校に入校したのは16人で、そのうち15人は上伊那出身です。 訓練期間が2年間のメカトロニクス科に8人、情報システム科に6人、訓練期間が半年間の機械科に2人が入校しました。 吉川一彦校長は「初心を忘れることなく自分自身を厳しく鍛え上げる時間として過ごしてください」と式辞を述べました。 新入生を代表して、南箕輪村出身の宮坂翔吾さんが誓いの言葉を述べました。 なお、伊那技術専門校は平成28年4月から県工科短期大学校南信キャンパスとして開校されることになっていて、今年度入学した2年制の学生は、伊那技術専門校最後の入校生となります。
-
富県小1年生に交通安全傘贈呈

伊那市の富県交通安全協会は7日、富県小学校の1年生全員に黄色い交通安全傘をプレゼントしました。 この日は富県安協の牧田稔会長らが富県小学校を訪れ、1年生21人に傘を贈りました。 富県安協では、子どもの事故防止につなげようと4年前から新1年生に傘を贈っています。 傘は黄色の生地の一部が透明になっていて傘をさしても前が見えるようになっています。 また、傘のふちに夜光反射材が縫い付けられています。 牧田会長は「登下校の際には車に十分注意して欲しい」と子どもたちに呼びかけていました。 富県小では「地域のみなさんに子ども達の安全を見守っていただきありがたい」と感謝していました。
-
桜守佐野藤右衛門さんのコレクションと小松華功さんの陶芸

伊那市高遠町の高遠城址公園の花見シーズンに合わせて、京都府在住の桜守佐野藤右衛門さんのコレクションと、陶芸家小松華功さんの作品を並べた展示会が5日から、信州高遠美術館で始まりました。 佐野さんのコレクションは、自身が所蔵する掛け軸や漆工芸品など、桜に関する作品78点です。 京都府在住の佐野さんは、祖父、父と親子三代にわたる桜守で、展示品は全国各地から集めたものです。 特に、江戸時代中期から後期にかけて活躍した画家の作品が多く並んでいます。 衣笠山桜図屏風は、江戸時代後期のもので、枝が折れても次の花を咲かせる生命力の強さが表現されています。 他にも、室町時代につくられた陶磁など様々な分野の桜に関する作品が並べられています。 小松さんの作品は、桜に関する陶芸作品30点です。 辰野町出身で京都府在住の小松さんは、20年前に佐野さんと出会い、指導を受けながら桜を燃やした灰を釉薬として使用しています。 佐野さんと小松さんによる展示会は、来月25日日曜日まで、信州高遠美術館で開かれています。
-
伊那弥生ヶ丘高校吹奏楽クラブ定期演奏会

伊那弥生ヶ丘高校吹奏楽クラブの第24回定期演奏会が、このほど、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 演奏会では、1・2年生、42人が11曲を披露しました。 第1回から演奏されている定期演奏会の伝統曲「アルメニアンダンス・パートⅠ」やパート紹介をかねたアンサンブルなどが演奏されました。 第2部ではももいろ人気アイドルグループの代表曲が演奏され、観客を巻き込んで盛り上がっていました。 会場には、保護者など300人が訪れ、生徒たちの演奏に聞き入っていました。
-
上伊那一斉に入学式

上伊那8市町村の全ての小学校と中学校で4日入学式が行われ、小学校では1,750人、中学校では1,870人が新たなスタートを切りました。 このうち箕輪町の箕輪西小学校には、13人が入学しました。 入学式で、新一年生は、在校生や保護者の拍手に迎えられて入場しました。 松島ゆかり校長は、「箕輪西小の自慢は、あいさつと仲良し。あいさつは魔法の言葉でみんなと仲よくなれます」と話しました。 このあと児童会長の唐澤依織里さんが「学校にははじめてのことがたくさんあります。わからないことがあったらいつでも聞いてください」と新入生たちに呼びかけていました。 新1年生たちは、保育園で練習してきた歌を元気に歌い、学校生活をスタートさせていました。 式の後、教室では、担任から名前を呼ばれると元気に返事をしていました。 担任からは、交通事故にあわないよう気をつけることや規則正しい生活のリズムを習慣づけるよう話がありました。 4日は、上伊那8市町村全ての小学校と中学校で入学式が行われ、小学校には1,750人が、中学校には、1,870人が入学しました。
-
5年ぶり再開の新山保育園で入園式

園児数の減少により平成21年度から休園となっていた伊那市富県の新山保育園で3日、5年ぶりに入園式が行われ、18人の園児達の新しい生活がスタートしました。 晴天に恵まれた3日、園児18人が保護者に手を引かれながら元気よく式に臨みました。 新山保育園は、園児数の減少により平成21年度に休園。平成27年度までに再開できなければ、平成28年度に廃園になることが分かっていました。 新山から保育園をなくしたくないという思いから、住民有志でつくる新山の保育園・小学校を考える会が中心となって保育園再開に向け取り組んできました。 再開条件となっていたのは、定員40人の半数の20人で、2月時点で21人の保育希望者を確保し、再開が決まりました。 田中文代園長は「みんなが来てくれて地域の人は喜んでいます。お散歩したり、トンボを見たり野山を駆け回っていっぱい遊びましょう」と挨拶しました。 式では、全員で富県・新山保育園の歌を歌いました。 新山保育園では、4日から通常保育が始まります。
-
絵画教室の作品展「八本の絵筆展」

宮田村を拠点に活動している絵画教室の作品展「八本の絵筆展」が、3日から、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 伊那、駒ヶ根、箕輪、宮田に住む10人の作品、41点が展示されています。 講師の小木曽章八さんの名前から「八本の絵筆」という会の名前を付けました。 絵画の全国コンクールなどへの出品に挑戦している仲間で、全員の作品を集めて展覧会を開くのは今回が初めてです。 伊那市西箕輪に住む三澤栄さんは、足跡をテーマにした作品を展示しました。目には見えない人の足跡を空想の世界で表現したということです。 箕輪町長岡に住む柴光子さんは、畑でみかけた蝶々をテーマにした作品を展示しました。地球は全ての生き物のためにある事を表現したということです。 八本の絵筆ではそれぞれが自由に題材を選んで制作していて、「一人一人の個性を楽しんで欲しい」と話していました。 八本の絵筆展は、8日(火)まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。
-
平澤真希さんのCDが「特選」

伊那市出身のピアニスト平澤真希さんのCDオマージュ・ア・ショパンがクラッシック音楽専門誌「レコード芸術」の4月号で特選に選ばれました。 平澤さんは伊那市出身で伊那北高校卒業後、東京音楽大学に進学。 その才能を認められポーランドのショパン音楽大学に特待生として留学し演奏活動を続けてきました。 レコード芸術は音楽論評の権威者が執筆にあたっていて国内のクラッシク音楽批評では最も信頼のおけるものといわれています。 器楽曲や交響曲など部門別に批評が行われ、平澤さんのCDは器楽曲の部門で最高賞の特選に選ばれました。 CDは2月19日に発売されショパンのほかオリジナル作品も収録されています。 今回のCDはこれまでの活動の集大成と位置づけられていて、平澤さんは特選受賞を喜んでいます。 平澤さんは現在国内を中心に音楽活動をしていて、今後はオリジナル曲の制作にも力を入れていきたいと話しています。
-
高遠石工守屋家三代の作品展示会

高遠石工の第一人者として高く評価されている守屋貞治と祖父、父の三代にわたる作品を納めた写真展が29日まで、伊那市の伊那図書館で開かれています。 会場には、貞治の祖父貞七と、父親の孫兵衛、貞治本人の作品を納めた写真およそ40点が展示されています。 江戸城の石垣は高遠石工が作ったとの記録が残っていて、芸術的で高度な作品を生み出していたとされています。 守屋貞治は、その高遠石工の第一人者として評価されています。 写真展は、守屋家が作った作品について広く知ってもらおうと上伊那郷土研究会が開きました。 こちらは、中川村で見つかったとされる貞治の作品「青面金剛像」です。 貞治が残した細工帳には記載されていないということですが、像のまわりの舟形が貞治の作品に似ていることから、研究会では「川の氾濫で流された祖父貞七の作品の変わりに貞治が無償で作ったのではないか」と推察しています。 29日は、守屋家の作品に関する講演会が開かれ、伊那市文化財審議委員会の竹入弘元委員長と、駒ヶ根市立博物館の田中清文専門調査員が話をしました。 竹入さんは残されている資料から「当時石工がもらっていた給与について」話しました。 田中さんは、親子3代の作品の違いについて「貞七と孫兵衛の作品を比べると、貞七は顔の奥行きが広く、目は上まぶただけで表現している。それに対し、孫兵衛は顔の横幅が広く、目は上下のまぶたで表している。貞治が最初に作ったとされる作品は、父孫兵衛のものに似ていることから、貞治は父親から技術を教わったのではないか」と話していました。 展示は、29日まで、伊那図書館1階ギャラリーで開かれています。
-
作家デビュー 東さんサイン会

伊那市在住で5日にデビュー作の文庫本「ひぐらし神社、営業中」が発売になった東朔水(あずま・さくみ)さんのサイン会が21日に伊那市のTSUTAYA伊那店で開かれました。 「ひぐらし神社、営業中」は、ユーモラスで心温まる内容の文庫本で5日にポプラ社から発売されました。 東さんは、伊那北高校の卒業生で伊那市高遠町在住です。 サイン会には、多くの人が列をつくり、握手をしたり、一緒に写真を撮ったりしていました。 中には、中学時代の同級生や高校時代の恩師もかけつけ、東さんを激励していました。 本は、一冊620円(税抜)で、TSUTAYA伊那店などで購入できます。
212/(土)
