-
自衛隊OBが上伊那招魂社でボランティア清掃

伊那市などに住む自衛隊OBのメンバーは、11日、伊那公園西の上伊那招魂社でボランティア清掃を行いました。 自衛隊OBでつくる長野県隊友会南信地区支部連合会のメンバーなど21人が作業を行いました。 隊友会は、2011年に公益社団法人になった事をきっかけに、毎年この時期にボランティア清掃を行っていて今年で4年目になります。 この日は、西南戦争から太平洋戦争までで亡くなった約5,700柱の霊が祀られている上伊那招魂社周辺の草刈りや生け垣の剪定を行いました。 隊友会では、戦没者の遺族の高齢化が進む中、こういった活動をこれからも続けていきたいと話していました。
-
寒晒蕎麦 販売始まる

江戸時代に高遠藩が将軍に献上したとされる寒晒蕎麦の販売が、18日から、伊那市高遠町のそば店3店舗で始まりました。 高遠そば組合では、新たな地域おこしにつなげたいとしています。 寒晒蕎麦は、高遠そば組合が地域おこしにつなげようと3年前に復活させ、去年試験的に提供しました。 今年は本格的に販売しようと、去年の倍のおよそ90キロのそばの実が用意され、各店舗限定150食を提供します。 組合によりますと、そばの実を冬の冷たい水や風にさらすことで風味や保存性を高める効果があるということです。 また、アクが抜け甘みが増しモチモチとした食感が特徴ということです。 3連休初日の今日は、県内外から観光客が訪れ、普通のそばと食べ比べていました。 寒晒蕎麦は、ますやの他に華留運と壱刻でも提供されています。 価格は、3店舗共通で1人前1,200円となっています。
-
伊那部宿を考える会 発足20周年特別講演会

伊那市の伊那部宿を考える会は、発足20周年を記念した特別講演会を18日、旧井澤家住宅で開きました。 講演会には、地域住民などおよそ30人が集まりました。 伊那部宿を考える会は、旧伊那街道の宿場跡を活かした地域づくりと歴史・文化の継承を目的に、平成7年に発足しました。 18日は、伊那市教育委員会学芸員の大澤佳寿子さんを講師に招き、「高遠藩内藤家武具奉納と春日神社」をテーマに話しを聞きました。 大澤さんは「明治4年に内藤家から春日神社に鎧が寄進された。これまでに市内20か所あまりの神社を調査したが、3点そろっているのはここも含めて2か所しかない。地域で大切に管理してきた証」と話していました。 会場には他に、会員が30年ほど前に購入し初めて展示したという東海道五十三次歌川広重の復刻版展示会も開かれていて、期間は24日金曜日までとなっています。
-
上牧で蝶を観察するイベント

地域に生息している蝶を観察するイベントが、11日、伊那市上牧で行われました。 イベントには、保育園児と小学生、その保護者の合わせて25人が参加しました。 里山の資源利用や保全を行っている上牧里山づくりが企画したものです。 参加者は、3つのグループに分かれると虫捕り網を持って蝶を捕まえていました。 公民館に戻ると、蝶の種類を図鑑を見て調べていました。 伊那北小学校周辺では、国蝶「オオムラサキ」を捕まえるなど、3つのグループ合わせて11種類が確認されました。 上牧里山づくりでは、「様々な体験を通して里山に目を向けてもらいたい」と話していました。
-
富県で高齢者が集い唱歌や歌謡曲を歌う「歌の幼稚園」

高齢者が集い唱歌や歌謡曲を歌う会、「歌の幼稚園」が16日、伊那市富県の北福地で行われました。 60代から80代の高齢者43人が集まり、15曲を唄いました。 この会は、北福地に住む会社役員、平岩高嶺さんが、年に4回開いています。 9年前に北福地社協の会長をつとめた事をきっかけに、高齢者が楽しく集える場所を作ろうと始めました。 子どもに戻ってみんなで楽しく唄おうと「歌の幼稚園」と呼んでいます。 平岩さんは歌の幼稚園の「園長」として進行役をつとめます。 歌の合間には、日本の財政状況などを学ぶ時間もあります。 この日は平岩さん宅の庭先で唄う予定でしたが、雨のためビニールハウスが会場となりました。 平岩さんは、「いつも多くの人が参加してくれる。これからも皆で楽しく唄い続けたい」と話していました。 歌の幼稚園は次回10月15日に北福地集落センターで開かれます。
-
台風11号まとまった雨に注意

大型で強い台風11号により、県の南部にはまとまった雨が降る予想で、長野地方気象台では注意を呼び掛けています。 大型で強い台風11号は、午後2時45分現在、室戸岬の南を北北西に向けて進んでいます。 この影響で、南部では、断続的に雨が降っていて、場所によっては1時間に40ミリの雨が降っています。 長野地方気象台では、あすの夕方まで、南部はまとまった雨が降る予想なので、河川の増水や土砂災害、竜巻や突風、降雹などに注意するよう呼びかけています。
-
最高気温 今年最高33.1度

15日の伊那地域の最高気温は33.1度とこの夏一番の暑さとなりました。 上伊那地域は6日連続の真夏日となり、上伊那広域消防本部によりますと、15日、熱中症とみられる搬送が2件あったという事です。 15日の伊那地域は日中、強い日ざしが照りつけ厳しい暑さとまりました。 長野地方気象台によりますと、日中の最高気温は、33・1度と、この夏一番の暑さとなりました。 上伊那消防広域本部によりますと15日午後3時現在、熱中症とみられる搬送が2件あったということです。 16日は台風11号の影響で最高気温も平年並みの28度前後となる見込みですが、消防では油断せずこまめな水分や塩分の補給など熱中症予防に努めるよう呼びかけています。
-
みのわ祭り「会場変更」意見多数

来年以降のみのわ祭りの在り方について検討する、2016みのわ祭りの未来を考える委員会が9日地域交流センターで開かれ、出席した各種団体の代表からは、会場の変更を求める意見が相次いで出されました。 委員会は、みのわ祭りの運営やイベント参加団体等で構成され、昨夜はおよそ40人が出席しました。 今年5月に初めての委員会が開かれ、来年以降のみのわ祭りの会場や運営について実行委員会から諮問されました。 みのわ祭りの会場は、平成10年以降バイパスや中心市街地、現在の松島の工業団地と4回変更しています。 出席者からは、「現在の場所では狭く、祭りに一体感が無い」といった意見が出され、中心市街地や役場周辺、松島駅東側など新たな会場案が出されました。 運営については「町や区の積極的な関与が必要」「手筒花火をもっと全面に押し出しては」などの意見が出されていました。 次回の委員会は8月に開き、今回出された会場案について検討を行います。
-
園児が中心市街地駆け抜ける

園児が伊那市の中心市街地を駆け抜けるちびっこ駅伝が12日行われました。 ちびっこ駅伝は、ぎおん祭りの歩行者天国に合わせて行われています。 この日は、市内の保育園や幼稚園から52チーム、485人が参加しました。 スタートのいなっせ前からゴールの八幡町までのおよそ800メートルを、8人でリレーします。 商店街には多くの保護者が応援に駆けつけ懸命に走り抜ける子ども達に声援を送っていました。
-
大﨑さんバスケットでSO出場

7月25日からアメリカのロサンゼルスで開かれるスペシャルオリンピックス夏季世界大会に伊那市の大﨑克哉さんがバスケットボールで出場します。 14日は、大﨑さんらが市役所を訪れ白鳥孝伊那市長に出場を報告しました。 スペシャルオリンピックスは知的障害者の自立や社会参加などスポーツを通じて支援する国際組織で、4年に1度夏と冬に世界大会を開いています。 大﨑さんは健常者がパートナーとなり試合をするユニファイドスポーツバスケットボールに日本代表として出場します。 大﨑さんは伊那養護学校の高等部からバスケットを始めました。 現在は市内の会社で働いていて毎週日曜日は高等部時代の仲間たちと練習をしています。 大﨑さんのポジションはフォアードだということで、「良い所にパスを出すのが得意」と話していました。 白鳥市長は、楽しんで頑張って欲しいと激励し、イーナちゃんピンバッチをプレゼントしていました。 スペシャルオリンピックスは7月25日からロサンゼルスで開かれることになっています。
-
高遠北小全校児童が「高遠そば」を学ぶ

伊那市高遠町の高遠北小学校の児童は、1年間、地元の名物「高遠そば」について学習します。 14日は、そばつゆに入れる焼き味噌用の大豆の苗を植えました。 この取り組みは、伊那市教育委員会が今年度進めている「暮らしの中の食」事業の一環で行なわれたもので、高遠北小学校では全校児童が高遠そばについて学習しています。 高遠そばは、麺つゆに辛み大根をおろしたものと焼き味噌を混ぜた辛つゆで食べるのが特徴です。 高遠北小学校では、1~2年生が大豆、3~4年生辛み大根、5~6年生がそばなどを栽培します。 14日は、1~2年生が学校近くの畑に焼き味噌用の大豆の苗を植えました。 6月の中旬に1度苗を植えましたが鹿や猿にほとんど食べられてしまいました。 そのため、防護ネットを先月下旬に設置しました。 児童たちは、スコップを使って穴を掘り、30センチ間隔で苗を植えていました。 14日植えた大豆は秋に収穫し味噌をつくる予定です。 また、6年生は薬味の内藤とうがらしの苗を植えていました。 伊那市教育委員会では、今年度、市内全小中学校で自分たちが育てたものを味わう「暮らしの中の食」事業に力を入れていきたいとしています。 高遠北小では秋に食材を収穫しそば打ちをして味わうということです。
-
今日も真夏日 2人が熱中症疑いで搬送
14日の伊那地域の最高気温は31.9度で、5日連続の真夏日となりました。 上伊那広域消防本部には、14日午後5時現在までに、熱中症と疑われる搬送が2件入ったということです。 消防では、こまめな水分や塩分の補給、適度な休憩を呼びかけています。
-
南箕輪村戦没者慰霊祭

太平洋戦争で戦死した南箕輪村の戦没者の霊を慰める慰霊祭が、14日、村公民館で行われました。 14日は、遺族など100人ほどが参加し、戦没者に花を手向け冥福を祈りました。 慰霊祭は、太平洋戦争で命を落とした南箕輪村の戦没者170柱の冥福を祈るものです。 南箕輪村と村社会福祉協議会が毎年主催して行っています。 唐木一直村長は、「凄惨を極めた戦争から70年が過ぎた。節目の年にあたり、さらなる平和な社会の実現のために、決意を新たにしていかなければならない」と祭祀を読み上げました。 村遺族会の山口一男会長は「明日にでも安全保障関連法案を採決するという情勢でこれからどうなっていくのか。二度と戦争を繰り返さないという状況を強く求め守っていきたい」と話していました。
-
消防技術水上の部 県代表が成果披露

消防救助技術関東大会水上の部に県代表として出場する上伊那広域消防本部の署員3人が13日県看護大学のプールでこれまでの訓練の成果を披露しました。 関東大会水上の部に出場するのは伊南北消防署に所属する3人です。 溺れている人に浮き輪を渡し引き上げるもので速さと正確さを競います。 救助に向かう人は溺れている人から目を離さないように常に顔をあげて泳ぐなどの基準があります。 関東大会は17日に埼玉県で開かれることになっていて18チームが出場します。
-
最高気温32.9度 2日続けて真夏日
伊那地域の11日の最高気温は、この夏1番の32.9度で、2日続けての真夏日となりました。 11日の伊那地域は、午後3時53分に最高気温32.9度を記録しました。 今季1番の暑さとなった32.1度の昨日を更新しました。 南箕輪村の大泉所ダムでは、家族連れなどがバーベキューや水遊びをして楽しんでいました。 上伊那広域消防署によりますと、午後5時現在管内で熱中症により搬送された人はいないということです。
-
最高気温32.1度で真夏日 今年1番の暑さ

10日の伊那地域の最高気温は32.1度の真夏日となり、今年1番の暑さとなりました。 伊那市役所のせせらぎ水路では、親子連れが水遊びを楽しんでいました。 このところ雨模様の天気が続いていましたが、10日の伊那地域は梅雨の晴れ間が広がり、最高気温は32.1度と今年1番の暑さとなりました。 長野地方気象台では、最も暑い時期を上回ったとしています。 11日以降もしばらく晴れの日が続く予想で、午前を中心によく晴れ10日と同じような暑さになるとみています。 関東甲信地方の梅雨明けは毎年7月21日頃で、今年も平年並みになると予想しています。 上伊那広域消防によりますと、午後4時半現在、管内で熱中症により搬送された人はいないということです。 気温の高い日が続くため、消防ではこまめに水分補給をすることや体調管理に気を付けるなど熱中症の予防を呼びかけています。
-
これはなんじゃ?第14回写真展なんじゃもんじゃ 開催

見た人が「これはなんじゃ?」と不思議に思う写真が並ぶ「第14回写真展なんじゃもんじゃ」が、伊那市の伊那図書館で開かれています。 会場には、伊那市境のカメラ店「カメラのキタハラ」に通う小学生から80代までの作品60点が並んでいます。 作品展の名前は、ヒトツバタゴ別名なんじゃもんじゃの木から命名したもので、見た人が「これはなんじゃ?」と不思議に思うような作品を展示しています。 去年から展示している人形をモデルに使った「ドールフォト」は、出展者が去年の作品よりも力を入れて撮影したということで今年の目玉の一つとなっています。 ある会員は「腕自慢の作品展ではなく身近な被写体を写してユーモアを表現しているので子どもから大人まで多くの人に楽しんでもらいたい」と話していました。 「第14回写真展なんじゃもんじゃ」は、19日(日)まで伊那市の伊那図書館で開かれています
-
伊那友の会 夏の家庭料理講習会

夏野菜を使った料理講習会が、9日伊那市日影の伊那友の家で開かれ、参加者が、身近な食材で作る事ができる家庭料理を学びました。 講習会には、伊那友の会の会員や一般など25人が参加しました。 会員が講師となり、ちらし寿司や鳥もも肉のロースト、水ようかんなど、夏野菜を中心に使った5品を作りました。 伊那友の会は、昭和5年に創刊した雑誌「婦人之友」愛読者でつくる会で、上伊那の30代から80代まで、50人の主婦が会員となっています。 一般も参加できる料理講習会は年1回開かれています。 会員らは、野菜の切り方や美味しく見える盛り付け方などを一般参加者にアドバイスしていました。 伊那友の会リーダーの有賀みづきさんは、「男性も女性も、料理を含めて家事ができる事は人生を豊かにする上で大切なこと」と話していました。 次回は、11月に家計簿のつけ方を学ぶ講習会を開く予定です。
-
木下北保育園 七夕送り

箕輪町の木下北保育園で8日、七夕送りの行事が行われました。 木下北保育園では、7月に入り、願い事を書いた短冊などを飾りつけた笹を、七夕飾りとして園内に飾っていました。 この日は、園児96人で七夕送りの行事として笹を燃やしました。 七夕飾りに火がつけられると、園児達は短冊に書いた願いが叶うよう、手を合わせていました。 山下いち子園長は「昔から続く行事を大切に、子供達に伝えていきたい」と話していました。
-
箕輪町で子ども用品リユース会開催

使わなくなった子ども用品を再利用してもらうリユース会が7日、箕輪町の松島コミュニティセンターで開かれました。 箕輪町では、子育て世代の経済的な負担や環境への負担を減らそうと毎年リユース会を開いています。 会場には、衣類やおもちゃ、ベビーカーなどおよそ2,000点が並びましたが、開始から30分程でほとんどの物が無くなったということです。 子ども用品リユース会は、秋にも開かれる予定です。
-
東部中の生徒がブロッコリー収穫

伊那市の東部中学校の生徒は、給食の食材で使われるブロッコリーを7日、収穫しました。 東部中の2年1組の生徒33人は、去年から総合学習の一環で食育について学習しています。 地元農家の山岸さんに協力してもらい、5月に生徒たちがブロッコリーの苗植えをしました。 山岸さんの畑では、アスパラやスイートコーンなどを栽培していて、市内の小中学校などの給食で使われています。 生徒たちは、去年も苗植えから収穫までを体験しています。 山岸さんによると、今年は天候にも恵まれ、形がよく甘みがあって美味しいものが出来たということです。 生徒たちは、カマを使って茎を切り、その後まわりの葉を落としていました。 7日は、およそ40キロを収穫しました。 収穫したブロッコリーは8日と9日にサラダなどにして給食で提供されることになっています。
-
鹿肉を使ったドッグフード販売へ

鹿肉を使った料理を伊那市長谷で提供している長谷部晃さんは、鹿肉のドッグフードを商品化しました。 長谷部さんは、「新たな産業につながれば」と期待しています。 長谷部さんが考えた鹿肉のドッグフードです。 鹿肉を使った料理を提供するざんざ亭を経営し、狩猟体験や解体見学ツアーなども行っています。 知人から鹿でドッグフードを作れないかと問い合わせがあり、先月から仕事の合間を見て作りました。 肉は、解体処理場から仕入れ、人が食べるには処理がしづらい筋肉や前足の肉などが使われています。 ひき肉にして、燻したレバーと合わせました。 犬だけではなく人も食べる事が出来るということです。 試食品の、モニターをしてもらった所好評だったということです。 モニターをした、長谷の松尾みゆきさんは「犬が喜んで食べている」と話していました。 長谷部さんは、「鹿肉は、鉄分やたんぱく質が豊富で、食欲がなかったり、アレルギーの犬には良い食べ物」と話しています。 鹿肉を使ったドッグフードは8月中旬からざんざ亭で販売する予定で、値段は30g600円です。
-
県老人クラブ連合会会長に池上さん就任

伊那市高齢者クラブ連合会の池上弘祥会長は、今年度長野県老人クラブ連合会の会長に就任したことを、白鳥孝市長に報告しました。 この日は、県老人クラブ連合会会長に就任した池上さんが伊那市役所を訪れ、白鳥市長に就任の報告をしました。 池上さんは平成23年から4年間、長野県老人クラブ連合会の副会長をつとめ、今年4月、会長に就任しました。 県老人クラブでは、会員の増強運動を実施していて、平成26年度は目標値に対して達成できたのは、県全体で6市村だけでした。 伊那市老人クラブは、108人増の目標に対し209人で、目標人数を101人上回り、達成しています。 池上さんは、「65歳から入会できるので多くの人たちに入ってもらいたい」と話していました。
-
春富中七夕コンサート

伊那市の春富中学校で、3日、七夕コンサートが開かれ、タレントのなるみさんが歌を披露しました。 コンサートは、PTAでつくる「いぶきの会」が毎年七夕に近いこの時期に開いているもので、生徒や保護者などおよそ230人が集まりました。 地域で音楽活動をしている個人やグループを毎回招いていて、今回は春富中出身のなるみさんがゲスト出演しました。 コンサートでは、生徒がなるみさんの歌に合わせて手拍子をしたり振付けをまねるなど盛り上がっていました。 また、この日が誕生日だったなるみさんにサプライズで歌が贈られました。
-
社会を明るくする運動 上伊那北部地区大会
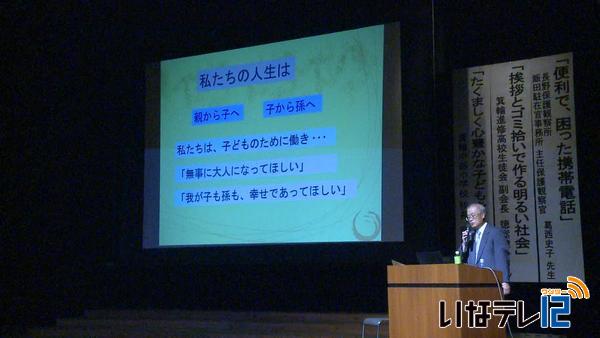
第65回社会を明るくする運動・青少年健全育成推進上伊那北部地区大会が5日、箕輪町文化センターで開かれました。 大会には、箕輪町や辰野町からおよそ180人が参加しました。 この大会は、箕輪町と辰野町の関係団体でつくる青少年健全育成推進委員会が開きました。 昨年度の県の作文コンテストで優秀賞を受賞した箕輪北小5年の松見すみれさんが、作文を朗読しました。 また、大会では、箕輪中部小の岡田誠校長が講演しました。 岡田さんは、「心豊かな良い子を育てるためには学校・家庭・地域が連携し、子どもを勇気づけたり、成長を共感しあうことが必要」と話していました。
-
メイクやクラフト体験「新しい出会い」

上伊那のメイクサロンやクラフト教室などが出店した新しい出会いと題したイベントが5日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。 このイベントは、それぞれの活動について知ってもらおうというもので、会場には、小物作り、メイク講座など、13のブースが設けられました。 伊那市や箕輪町でクラフト教室などを開いているストロベリーファームは、お菓子をかたどったアクセサリーやガラス瓶のペイントのブースを出展し、にぎわっていました。 実行委員長で、伊那市狐島でメイクサロンを営む城取ゆかりさんは、「それぞれの仕事を活かし、家族や友達で楽しめるイベントをこれからも開いていきたい」と話していました。
-
新山でミヤマシジミ生息確認

伊那市富県新山の和手上地籍で、環境省のレッドリスト、長野県の準絶滅危惧種に指定されている蝶、ミヤマシジミが生息していることが確認されました。 近くに住む伊澤敏明さんの案内で、現地に向かい、カメラがその様子をとらえました。 羽を広げた長さが3センチほどで、500円玉よりひとまわり小さい大きさです。 雄の羽の表面は、青紫色をしています。 この場所は、新山の和手上地籍で、ミヤマシジミのえさとなるコマツナギが群生しています。 幼虫もみつかりました。 伊澤さんは、去年から観察を続けていて、今年は、ここ何日かで幼虫がみられるようになったということです。 伊澤さんは、今後も仲間たちと保護育成活動を続けていくことにしています。
-
夢縁日フェスティバル

県内各地の44の店舗が出店する夢縁日フェスティバルが、伊那市西春近の住まいDEPOショールームで5日まで開かれています。 会場には、飲食店やエステサロン、自動車販売店などが出店した44のブースが並んでいます。 夢縁日は、伊那市内の飲食店や建築業の経営者でつくる実行委員会が、地域の人たちに県内の様々な業種を知ってもらおうと開いているもので、今年で2回目です。 飲食や物販の他、工作や占い、ボディペイント体験などのブースがあり、訪れた人たちは、それぞれのコーナーで楽しんでいました。 夢縁日フェスティバルin伊那は、5日まで伊那市西春近の住まいDEPOショールームで開かれています。 5日はヨガ体験や、地元出身のアイドルグループパラレル☆ドリームのライブも行われます。
-
伊那市西春近 酒井花枝さん宅であじさい見頃

伊那市西春近沢渡の酒井花枝さん宅の庭であじさいが見ごろとなっています。 酒井さん宅の庭では、いろとりどりのあじさいが見ごろとなっています。 96歳になる酒井さんが、20年ほど前から家の裏にある竹林で育てはじめ、徐々に数を増やしていったということです。 娘の茂美さんは、「あじさいは母の生きがいになっている。今年は特に花が大きく、きれいに咲いたのでぜひ見に来てほしい」と話していました。 花は2週間ほど楽しめるということです。
-
伊那西高校文化祭「西高祭」4日と5日一般公開

伊那市の伊那西高校の文化祭「西高祭」の一般公開が、4日と5日の2日間の日程で始まりました。 31回目となる今年の西高祭のテーマは「ヒロイン~弾けろ!最強のteenager~」です。 西高祭を通じて、1人ひとりが主人公になり輝いてほしいという願いが込められています。 4日は、午後1時から一般公開が行われ、玄関前の屋台は生徒や保護者、一般の来場者で賑わっていました。 校内では、伊那西高校の教員をパネルにして一緒に写真が撮れる「妄想フォトシアター」や、4月に行った沖縄修学旅行をテーマにした展示など、各クラスの工夫を凝らした企画が用意されています。 3年3組の教室では、スーパーマリオの世界観を体感することができます。 他にも、茶華道クラブによるお点前披露など、クラブの体験コーナーも用意されています。 一般公開は5日も行われ、時間は午前9時30分から午後3時までとなっています。 講堂では、演劇クラブや英語研究クラブなどによるステージ発表も行われます。
82/(日)
