-
箕輪町無量寺 立像2体が県宝指定

箕輪町北小河内の無量寺の阿弥陀堂にある仏像2体が、来月にも県の宝「県宝」に指定されます。
4日県庁で開かれた県の文化財保護審議会で県宝に相応しいと答申されました。
国の重要文化財にも指定されている阿弥陀如来坐像の両脇にある木造観音菩薩立像と木造地蔵菩薩立像の2体で、来月にも、県宝に指定される見込みとなりました。
阿弥陀如来坐像は、平安時代の後期に制作されたとされていて、両脇の2体も、同じ時期に、同じ作者が制作したものと見られています。
また、観音菩薩と地蔵菩薩の組み合わせは、あまり例がなく珍しいことなどが評価されました。この無量寺の仏像は、県教育委員会の定例会で県宝に指定される見込みです。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
伊那西保育園児が野菜畑探検

伊那市の伊那西保育園の園児は、4日、野菜畑探検をしました。探検したのは、伊那西保育園に野菜を提供している小池農園の畑です。
小池農園の小池満さんの子供が伊那西保育園に通っていることもあり、この野菜畑探検は、去年から行われています。
最初に、葉っぱからどんな作物が取れるかを当てるクイズがありました。
子供達は、ニンジンや大根、ナスなどを見事に当てていました。
そのあと、カボチャのトンネルをくぐって畑に出ました。
そこには、丸い物体がごろごろ転がる不思議な光景が広がっていました。
丸い物体は、スイカでした。
小池さんから叩いていい音がするものがおいしいと聞いて、子供達は、スイカの音を確かめていました。
また、実際に半分に割って、本当にいい音のスイカがよく熟しているかを確認しました。
そのあと、ジャガイモ畑に移動してイモ掘りを体験しました。
子供達は、「大きい。たくさんある」と話しながら、ジャガイモを掘っていました。
小池さんは、「この地域の子供たちなので、野菜の収穫を体験したことのある子どもが多いが、みんなで収穫すると、また一段と楽しいと思う。」と話していました。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
上伊那教育財政懇談会、開催

上伊那の教育関係者が県への要望事項について話し合う、上伊那教育財政懇談会が4日、伊那市の信州伊那セミナーハウスで開かれました。
会場には教育委員会や学校長、PTAなど、およそ80人が集まり、地元の県議会議員と上伊那の教育課題について協議しました。
懇談会では、上伊那の高校募集定員数ついて、ある中学校の校長から「今年度の中学校卒業生2千人に比べ、上伊那8校の募集定員が千5百人と少なすぎる。もっと高校の募集定員を増やしてほしい」と要望が出されました。
また、高校の募集定員が少なく、上伊那から近隣地域に流出する中学生が多くなっている現状を受け、ある保護者からは「通学距離が長くなれば危険も増えるし、親の負担も大きくなる。安心・安全のためにも地元高校に通わせたい。」と意見が出されました。
これらの意見に対して地元県議からは、「高校の募集定員数の増員について、県がやるべきことはどんなことなのか、具体的な施策を挙げて要望した方が良い」と話していました。
今回協議された内容は、再検討したのち、10月中に県の教育委員会などに要望する予定です。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
箕輪町保育課題検討員委員会 発足

箕輪町の保育園のあり方を協議する検討委員会の初会合が2日夜箕輪町役場で開かれました。
委員会では、保育園の統合、幼稚園の誘致なども視野に入れ検討を進めていきます。
発足した委員会は、保育園に通う前の子供を持つ保護者や、民生児童委員、町関係者など15人で構成されています。
2日夜は平澤豊満町長が、松下勲(いさお)委員長に検討内容を諮問しました。
内容は、大きく分けて2項目です。
(1)保育サービス向上のため、町内9つの保育園の統合・民間委託、私立幼稚園の誘致を含んだ運営形態の検討、(2)それらを踏まえた町全体の保育施設の整備について竏窒フ2つを協議し、来年3月をめどに町長へ答申します。
現在箕輪町では、「一味ちがう箕輪の子ども育成事業」として、運動あそびや英語遊び、読育を積極的に取り入れていますが、保育園運営の行政コストが割高になっている事や、施設の老朽化などが課題となっています。
委員長は「箕輪の次代を担う大事な子供達のため、検討に力を注いでいきたい」と話していました。
委員会では、まず近隣市町村を含めた保育園の視察を行って現状を把握します。その後、約10回の協議の中で結論を出し、来年3月中には町長に答申する計画となっています。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
美篶小にグアテマラから手紙の返事

伊那市の美篶小学校3年2組の児童が、7月に南米の国グアテマラの子どもたちに書いた手紙の返事が、今日、届きました。
手紙を届けたのは、アマランサスの栽培や、日本の農産物直売所のノウハウを普及・指導するためにグアテマラを訪れていた信州大学農学部の根本和洋(かずひろ)助教です。
3年2組の子どもたちは、今年、総合学習でアマランサスを育てています。その指導を根本さんがしていることが縁で、グアテマラの子ども宛に、アマランサス栽培などについて手紙を書きました。
根本さんは、アマランサスの栽培状況などの視察に8月にグアテマラを訪れ、西部にあるタブロン村の子どもに手紙を渡しました。
そして、その返事を持ち帰り、今日、子どもたちに渡しました。
子どもたちは、手紙を受け取ると、早速開き、友達と交換しながら、翻訳された手紙を読んでいました。
手紙には、アマランサスの絵や、栽培を手伝っていること、家族のことなどが書いてありました。
子どもたちは、「海の向こうから手紙が来ると思うとドキドキした」「グアテマラからの手紙は夢みたい」と感想を話していました。
根本さんは、「喜んでもらえて嬉しい。いつかは、国際中継システムを使って、お互いに顔を見る機会を作ってあげたい」と話していました。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
県伊那文化会館で県展公開始まる

長野県出身者や在住者による美術展「県展」の展覧会が、県伊那文化会館で開かれています。
会場には、受賞作品と中南信の入選作品など444点が展示されています。
例年作品が多いため、今年から会場ごとに作品を減らして展示しているということです。
今年の県展は、伊那で審査が行われ、日本画・洋画・彫刻・工芸の4部門、559点が入選しました。
展覧会は、上田・松本でも順次開かれることになっています。
伊那会場での展示は、7日(日)まで県伊那文化会館で開かれています。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
長谷中花壇、県の中央審査へ

先月上伊那で行われた、学校花壇コンクールの地方審査の結果、伊那市の長谷中学校が県の中央審査に進む事が決まりました。
長谷中学校は、ここ数年、毎年中央審査に進む常連校となっています。
今回行われた秋の審査では、(1)夏の気象条件が悪かったものの、見事な花を咲かせ管理も行き届いている事、(2)地域に、花を提供して一緒に育て、学校以外でも環境整備を行っている事などが評価されました。
県の中央審査は9日(火)から行われる事になっています。【伊那ケーブルテレビジョン】 -
高遠高校兜陵祭 30、31日一般公開

伊那市の高遠高校で文化祭、兜陵祭が、30・31日の2日間の日程で一般公開されています。
このうち。体育館下のスペースでは、書道コースと書道部の生徒らによる、巨大書道の実演が行われました。
生徒達は、畳2枚程の大きさの紙に、高さが腰まである筆を使い、漢詩の一説を書きました。
皆、全身を使い、力強い文字を書いていました。
また、美術コースと美術部の生徒達の作品を並べた教室では、紙で作った家の模型や、自由なテーマで描かれた油絵などが並べられています。
高遠高校の文化祭、兜陵祭は、明日も午前10時から一般公開される予定です。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
長谷の民話、切り絵にした作品展

伊那市長谷に伝わる民話や地元の風景などを切り絵にした作品展が、30日から伊那市の信州高遠美術館で開かれています。
作品展を開いたのは、長谷の民話をテーマに紙芝居をしているグループ「糸ぐるま」代表の久保田文子(フミコ)さんです。
久保田さんは、30年前から長谷の民話をテーマに切り絵で紙芝居を作っていて、信州高遠美術館では、初めて作品展を開きました。
今回は、紙芝居で使用したものの中から、特に気に入っていると言う作品20点が出展されています。
銃で撃たれた親猿を、介抱する3匹の子猿から、親子の絆の大切さを伝える「孝行猿」や、絵馬に書かれた馬が、夜になると畑を荒らす、「お宮の絵馬」などの民話を題材にした作品が並べられています。
久保田さんは、「紙芝居のいい場面を選び展示した。じっくりと見てもらい、民話や切り絵に親しんでほしい」と話していました。
この作品展は、9月23日まで開かれています。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
地域ぐるみで子どもを育てるフォーラム

教育の現状や課題について考え、地域ぐるみで子育てを行っていこうと30日、伊那市の伊那合同庁舎でフォーラムが開かれました。
会場には、伊那市内の学校の職員やPTA、子育て支援団体など、およそ170人が集まりました。
フォーラムは、子育ての現状と課題を考え、地域で子どもを育てていく意味や価値を確認してもらおうと、伊那教育事務所が開きました。
講演では、国立信州高遠青少年自然の家の、松村純子さんが講師を務めました。
松村さんは、子どもの現状を、空間、時間、仲間、遊びの方法の4つに分け説明しました。
このうち時間では、習い事や塾など個人の時間が増えたために、大人数で遊ぶ機会が少なくなったと説明し、過剰な個人学習による子どもの孤独化を危惧していました。
また遊びの方法については、大人が遊びに介入しすぎて、今の子ども達は新しい遊びを考える創造力が乏しくなっていている。子ども同士で遊びの方法やルールを考えさせるようにしてほしい。」と話していました。
松村さんは、「子ども達は、自分で考えることで感性や自己判断力、リーダーシップなどを身につけていく。大人がその環境づくりの手助けをしてあげることが大切。」と呼びかけていました。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
伊那小の恒例バザー、今年も

伊那小学校PTAによるバザーが30日、小学校の体育館で開かれ、会場は多くの人でにぎわいました。
バザーは、各家庭で使われなくなったものや、子ども達が総合学習で作ったものを販売する場として、毎年開かれているものです。
PTAバザーでは、日用品や雑貨など、学年ごとに違った種類のものを出品していて、スキー板やグローブなど、スポーツ用品も出されていました。
児童の店では、クラスごとにバザーに向けて準備してきたものが販売されました。
6年順組では、自分たちで育てたソバを使った料理を販売しました。
かけそばだけでなく、ソバを切る中で余った端の部分を使った「耳揚げ」や、中にあんこを詰めた「そば団子」など、趣向を凝らした料理が並んでいました。
店の前には人の列ができ、300食以上用意したかけそばも、完売に近い状態でした。
PTA会長の織井つねあきさんは、「子ども達に楽しんでもらいながら、お金を稼ぐにはどんな苦労が必要なのか学んでもらいたい。」と話していました。
今回の売上げは、学習用品の購入や、活動費に充てられるということです。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
県展の彫刻の部、伊那市の中山隆文さん知事賞受賞
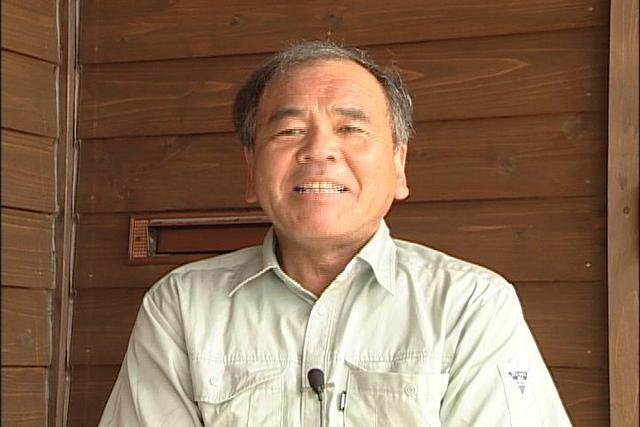
第61回県展の彫刻の部で、伊那市西春近の中山隆文さんが最高賞となる知事賞を受賞しました。
彫刻の部には、65作品が出品され、中山さんの作品が見事知事賞を受賞しました。
県展審査員で彫刻の部の審査長を務めた渋谷修平さんは、「黒みかげ石を生かして重量感と配置を活かした新しい方向を目指した作品」と講評しています。
中山さんは、西春近で石材業を営む傍ら、15年にわたり石の彫刻を制作していて自宅周辺の庭にも作品が見られます。県展には今回初めての出品で、知事賞受賞となりました。
中山さんの知事賞受賞作品、「群れるII(ツー)」は、31日の伊那会場を皮切りに9月の上田会場、10月の松本会場とすべての会場で展示されることになっています。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
長谷保育園で「おはなしの里」

伊那市の長谷保育園で、29日、園児と保護者を対象にした読み聞かせ会「おはなしの里」が開かれました。
今日は、園児と迎えにきた保護者などおよそ70人が、未満児から年長の4クラスに分かれおはなしを聞きました。
長谷保育園では、旧長谷村時代に、お話に親しむイベントを定期的に行ってきました。
今回の読み聞かせ会はそれを引き継いだもので、絵本やお話を通して、楽しさを共有し親子のふれあいを深めてもうらおうと、初めて開かれました。
年少のチューリップ組では、女の子が電車に乗って、駅ごとにいろいろな動物に出会うという絵本「でんしゃにのって」を読みました。
園児や保護者は、絵本の世界を楽しんでいました。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
県展審洋画の部、上伊那で8作品hが受賞

第61回県展のトップ会場は伊那市。その伊那市にある県伊那文化会館で、すべての作品の審査が行なわれました。4つの部門の中で一番作品数の多い洋画の部では、26の受賞作品のうち、伊那支部の作品が9つを占め、伊那支部のレベルの高さが目立つ結果となりました。
結果発表のまとめによりますと、日本画の部には110点、洋画の部には635点、彫刻の部には65点、工芸の部には127点のあわせて937点が搬入され、受賞作品は43点、入選作品は611点、選外が283点でした。
伊那ケーブルテレビ放送エリア関係分では、
日本画の部で、箕輪町の内田三智子さんの作品がJA長野中央会賞を受賞しました。
洋画の部では、伊那市の唐澤弥生さんの作品が県教育委員会賞、南箕輪村の前田博さんの作品が信州美術会賞、伊那市の北原恵子さんの作品が八十二文化財団賞、南箕輪村の丸山栄一さんの作品がSBC賞、伊那市の千田俊明さんの作品がNBS賞、伊那市の小林修一郎さんの作品がNBS賞、伊那市の伊東圭太さんの作品がTSB賞を受賞しました。
伊東さんは、高遠高校3年生です。
彫刻の部では、伊那市の中山隆文さんの作品が知事賞、伊那市の酒井勉さんの作品が信毎賞を受賞しています。
工芸の部では、箕輪町の中澤達彦さんの作品が県教育委員会賞を受賞しました。
第61回県展の伊那会場は、8月31日から9月7日までの日程で一般に公開されます。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
子育て学級が野菜収穫体験

未就園児とその保護者を対象にした伊那市西箕輪公民館の子育て学級「わんぱく親子塾」27日、自分達で育てた野菜の収穫をしました。
今日は30組の親子が参加し、城取茂美公民館長から、収穫の方法を教わりました。
わんぱく親子塾では今年5月に、みはらしファームの一角に畑を借り、トウモロコシやスイカの苗を植えました。
管理は、5つのグループに分かれて自主的に草取りや水やりをしてきたという事です。
子供達は、お母さん手をかりながら大きなトウモロコシを選んで収穫していました。
白取館長は「最近は、農業体験をした事がない母親も増えている。親子そろって野菜を育てる貴重な経験になったと思うと話してました」
わんぱく親子塾では10月にもサツマイモの収穫をし、焼き芋パティーを行うという事です
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
記憶に残そう「聖職の碑」 遭難の碑に花

箕輪中部小学校の児童は、27日学校玄関前にある遭難の碑に花を手向け、西駒ヶ岳登山の犠牲者の冥福を祈りました。
児童が持ってきた花を遭難の碑に手向け、手をあわせていました。
西駒ヶ岳登山の遭難は1913年大正2年の8月26日に今の箕輪中部小学校、当時の中箕輪尋常高等小学校で引率していた教師や児童37人のうち11人が犠牲になりました。
遭難の碑は大正13年に建立されたもので校内には他に登山で亡くなった同級生がたてた、像もあります。
この像は児童らがたくましく育つようにとの願いでたてられたということです。
この遭難事件を題材にした新田次郎の小説で有名な「聖職の碑」は、上伊那教育会が西駒ケ岳の稜線上に建立したものです。
箕輪中部小学校では遭難事故が風化しないよう後世に語りつぐとともに、子どもたちの安全を守るための教訓にしていきたい、と話しています。 -
学校花壇コンクールの地方審査行われる

学校花壇の出来ばえを評価する、学校花壇コンクールの地方審査が28日、上伊那地域の小中学校で行われました。今日は伊那教育事務所や上伊那地方事務所の職員が、対象となっている小中学校11校を訪れ、審査を行いました。
コンクールは、学校環境の美化と、情操教育に役立てていこうと、毎年春と秋の2回行われています。
審査は、花壇の配色や生育状況、また校外の美化活動への協力など、大きく分けて5つの項目、合計100点で評価をします。
伊那市西箕輪の伊那養護学校では、南箕輪村の上伊那農業高校で花を育ててもらい、それを養護学校の生徒たちが植えるという、対象校では珍しい2校協同の花壇となりました。
また高遠中学校では、全校生徒で夏休みの花壇の水やりや草取りをするなど、伝統ある学校花壇を復活させようと活動してきました。
審査員は、花の咲き具合や色のコントラストなど、入念にチェックをしていました。
地方審査は明日も行われ、審査の結果で上位校は、県内を対象にした中央審査に進むとことになっています。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
伊那市で食育推進会議設置

伊那市は、食育をより効果的に推進するため伊那市食育推進会議を設置しました。25日夜、今年度初めての会議が市役所開かれました。
伊那市は国で定められた食育基本法を基に昨年度、伊那市食育推進計画を策定しました。この、計画に沿って食育推進活動の実施や計画の進捗状況を確認していくため食育推進会議を設置しました。
25日は、学校や保育園、食に関係のある団体をはじめ公募の市民など20人に小坂樫男市長から委嘱書が手渡されました。
会議では、推進計画の策定までの経過などが報告された他、事業計画などについて意見を交わしました。
今年度の事業計画では食生活・健康ジャーナリストの砂田登志子さんによる食育講演会が予定されています。
また食育を推進するため、食育推進会議の中から食育応援団を結成します。
食育応援団は、地域との連携をとりながら企業や外食産業への協力の呼びかけ、保育園や学校への出張食育講座などの食育の普及啓発活動を行います。
応援団は早ければ来年4月から実施する計画です。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
写真サークル「彩」の作品展、かんてんぱぱホールで

駒ヶ根市の赤穂公民館の写真サークル「彩(いろどり)」の作品展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。
会場には、四季折々の植物を撮影した作品54点が並んでいます。
サークル「彩(いろどり)」は、駒ヶ根市を中心に伊那市から松川町までの24人が参加しています。
会員は花などの植物が好きで、その綺麗な姿を残したいという思いで、植物を被写体にしています。
初めのうちは大勢で撮影に出かけていたということですが、結成15年ほどとなった最近は、撮影のコツをつかんできて、少人数ので出かけることが多いということです。
ある会員は、「花の気持ちを考えながら一番いいところを捉えるのが難しい。写真を見て、花の表情や思いを感じてもらえたら嬉しい」と話していました。
このサークル「彩(いろどり)」の写真展は、31日(日)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
県美術展、作品審査会始まる

今月31日から始まる、第61回県美術展の作品審査会が26日から、県伊那文化会館で始まりました。
61回となる今年は、県内在住・出身者から937点の応募がありました。審査は、今年の展覧会が伊那会場から始まることから伊那で行われました。
作品は、洋画・日本画・彫刻・工芸の4つの部門毎に審査され、26日は、635点と応募のおよそ7割を占める洋画の審査が行われました。
審査員は、展覧会を主催する信州美術会の会員や外部審査員が務めます。
会場に作品が運ばれると、札を上げ、一作品毎に点数をつけていきました。
審査は28日まで行われ、知事賞・県教育委員会賞など13の賞が決定します。
県美術展は、今月31日(日)から9月7日(日)まで、伊那市の県伊那文化会館で開かれ、その後上田、松本の会場でも開かれます。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
日本大会前に、タヒチアンダンスを披露

タヒチアンダンスチーム「ティアレ・ヘイプア長野支部」は23日、南箕輪村村民センターで公開練習をおこないました。
主婦らで集まる、ティアレ・ヘイプア長野支部は、伊那市を拠点に活動しているグループです
今月31日に東京都でタヒチアンダンスの日本大会があることから、家族や、お世話になっている人達に、日頃の練習成果をみてもらおうとステージで発表しました。
タヒチアンダンスはお祝いの時など感謝の敬意を表す踊りです。
打楽器のリズムに合わせて踊り、腹筋や背筋など全身を使います。
メンバーは、赤や黄色などの華やかな衣装を身にまとい独特なダンスを笑顔で披露していました。
会場には、友人などおよそ140人が訪れ大きな拍手を送っていました。
長野支部からは、即興で振付をするソロ部門に5人・団体部門に1組が出場します。
メンバー達は上位を狙えるよう頑張りたいと話していました。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
千葉市の子供たち 長谷に農山村留学

千葉市の子どもたちが自然の中で過ごす、農山村留学が22日から始まり、伊那市長谷で入村式が行われました。千葉市の2つの小学校の6年生121人が、伊那市長谷の入野谷に到着しました。
千葉市では、6年生を対象に夏休みを利用して、人や自然と触れ合う体験事業を行っていて、長野県内18ヵ所に希望者およそ千人が訪れています。
開村式で、伊那市長谷総合支所の中山晶計支所長は、「自然や動物、地域の人が長谷の宝物。多くのものと触れ合って、楽しい思い出を作ってください」と歓迎しました。
子どもたちは、早速川に入り、長谷の自然を満喫していました。
子どもたちは、長谷地域の民家に宿泊したり、長谷小学校の児童と交流するなどして、4泊5日を過ごします。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
大芝まつりステージ練習に熱
8月23日土曜日の大芝高原まつりステージ発表に出演する保育園児が南箕輪村大芝高原の大芝湖上に設置された特設ステージで練習に励んでいます。
22日は中部保育園の年長児が鳴り物を手に本番に向け、練習していました。
練習で園児らはステージの広さや並ぶ順番、立ち位置などを確認していました。
ステージ発表は大芝高原まつりのイベントのひとつで今年は、キッズダンスや太鼓演奏など28団体が出演します。
当日は南箕輪村内を中心に、上伊那地域のほか、木曽や、塩尻からの参加もあります。
ステージは午前10時から午後7時半までおこなわれ、南箕輪村最大のイベント、大芝高原祭りを盛り上げます。 -
旧井澤家住宅で和紙ちぎり絵作品展

和紙ちぎり絵 しゅんこう伊那教室の作品展が、伊那市の旧井澤家住宅で開かれています。
会場には、伊那教室に通う生徒16人の作品30点が展示されています。
しゅんこう伊那教室は、伊那市の中村早恵子(さえこ)さんが開く3つの教室の1つで、旧井澤家住宅での展示は、今回が2回目です。
教室では、手すきの和紙を素材にしていて、ちぎる、そぐ、貼るといった手法で作品を仕上げていきます。
和紙の魅力もあって、初心者でも見栄えのする作品を制作できるということですが、和紙を薄く剥がす事で濃淡を生み出し、遠近感を表現できるようには時間がかかるという事です。
中村さんは、「ちぎり絵の一番の魅力は、絵がかけない人でも作品を作れるということ。井澤家住宅の雰囲気と一緒に楽しんで欲しい」と話していました。
このしゅんこう伊那教室和紙ちぎり絵作品展は、25日(月)まで、旧井澤家住宅で開かれています。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
北海道犬が児童の登校見守る

伊那市の野生動物追い払い事業で活躍が期待されている北海道犬が、子供達の安全確保にも一役買っています。
21日朝も、平沢地区から伊那西小学校へ通う子供達の集合場所には、北海道犬の姿が見られました。
伊那西小学校の周辺で、17日、18日と熊の目撃情報が相次いだ事から、小学校では、保護者に送り迎えしてもらうなどの対応をとっています。
北海道犬は、勇敢で、熊などをみると追いかける性質を持っていることから、子供達は、昨日から、北海道犬と通学しています。
同行しているのは、保護者の網野嘉彦さんと、メスで生後6ヶ月の北海道犬チョコです。
通 学路の中には、動物が食い散らしたトウモロコシ畑などもありました。
2・5キロの道のりを、およそ30分かけて学校に到着しました。
この北海道犬との登校は、今週いっぱい続けられるという事です。
【伊那ケーブルテレビジョン】 -
伊那市 大萱で百八灯

伊那市西箕輪の大萱地区で16日、108つの火の玉をつるす送り盆の伝統行事、百八灯が行われました。
この日は会場となった大萱グラウンドに多くの地区住民が集まり、盆踊りや振りまんどを楽しみました。
イベントが終わると、会場を囲むようにつるされていた布製の玉に火がつけられました。
百八灯は、盆の送り火として、また無病息災や害虫駆除を願って、除夜の鐘の数と同じ108つの玉に火をつけるものです。
会場はつるされた108つの火の玉によって、幻想的な雰囲気に包まれていました。 -
伊那市天竜川で 精霊流し

灯篭を流して霊を供養する、精霊流し大法要が16日、伊那市坂下区の天竜川沿いで行われました。
精霊流し大法要は、伊那仏教会が亡くなった人たちの霊を供養しようと、坂下区商工会と協力して毎年行っているものです。
この日は伊那市内の新盆の家族を中心に、先祖代々の霊や戦没者の霊を供養しようと、およそ250人が集まりました。
参加者らは法要を行ったあと、それぞれ思いを込めた灯篭を天竜川へと流しました。
流された灯篭は静かに川を下っていき、参加者らはその様子をずっと見つめていました。 -
箕輪町で無形文化財「おさんやり」
箕輪町の南小河内区に伝わるお盆の伝統行事で、町の無形民族文化財に指定されている「おさんやり」が、16日に行なわれました。
おさんやりは、区内を流れる、「大堰」(おおせぎ)が天竜川とは逆に流れている為、疫病や災いの原因とされ、その厄を払う目的で始まったといわれています。
夕方、白い服を身に纏った、地区の男達が、およそ600キロの舟を担ぎ上げると、お舟の巡航がはじまります。地区の災いを舟にのせ、地区外へ運び出すものとされ、2時間かけ地区内を練り歩きます。
日が沈み、暗くなると、おさんやりもクライマックスを迎えます。
男達は、広場に置かれた、舟を担ぎ上げると、木の回りを3周し、その後、左右に揺らしながら、舟を壊しました。
舟の破片は、玄関に飾ると、厄除けになると言われ、集まった人達は1年間の無事を祈りながら、破片を拾い集めていました。【伊那ケーブルテレビジョン】 -
美篶三峰川で水生生物調査
川の生き物を通して水質を調べる水生生物調査が17日伊那市美篶の三峰川で行われました。
これは子どもたちに、水環境に関心を持ってもらおうと、川の環境保護活動などに取り組む、三峰川みらい会議が行ったものです。
17日は市内の子どもたちやその保護者などおよそ40人が集まり川にはいって、そこに住む生き物をつかまえていました。
子どもたちは網を使って生き物をつかまえると、きれいな水に住むもの、少しきたない水に住むものなど4種類に分けていました。
調査の結果、ヒラタカゲロウやヘビトンボなど、きれいな水に住む生き物が多くみつかり、三峰川はきれいな水ということが確認されていました。
この調査は、三峰川のほか天竜川やその支流でもおこなわれていて、国土交通省が結果を冊子にまとめる予定です。
三峰川みらい会議では、秋には魚のつかみ取りなどをおこなうことにしていて、子どもたちに、川に親しんでもらうことにしています。 -
伊那市で助産婦呼び子育て相談会
伊那市の竜南子育て支援センターで今日、助産師による子育て相談が行われました。
市内5つの子育て支援センターでは、今年に入って定期的に助産師による子育て講座を開いています。
今日は竜南保育園に、伊那市富県の助産師 鹿野(しかの)恵美(えみ)さんが訪れ、3人の母親から子育てに関する相談を受けました。
「なかなか離乳食に切りかえられない」との相談に鹿野さんは、「おやつでも、オニギリやパンをあげると自然に食べるようになる」とアドバイスしていました。
ある母親は、「近くに相談できる両親がいないので、とても参考になる。本には書いてない事もたくさんあるのでびっくりした」と話していました。
次回、助産師による相談は 10月23日(木)富県子育て支援センターで行われる事になっています。
2810/(火)
