-
救命救急センター指定へ中病視察

長野県救急医療機能評価委員会は、来年4月に、救命救急センターの指定を目指す、伊那中央病院のセンターとしての機能が十分備わっているかを、24日視察しました。
この日は、長野県救急医療機能評価委員会の委員6人が、伊那市の伊那中央病院を視察しました。
伊那中央病院では、9月26日に、センター指定への申請依頼を県に提出しました。
これを受け、機能評価委員会は、施設や設備などのハード面や、受け入れ体制などのソフト面が、センターとして十分な機能があるか現地調査を行いました。
委員らは、病院担当者から説明を受けた後、平成25年に運用を開始予定の、新しい救命救急センターの建設地などを視察しました。
視察した報告書は、11月下旬頃、県に提出される事になっているということです。 -
上伊那農業高校 チェーンソー講習会

上伊那農業高校緑地工学科の生徒は19日、箕輪町でチェーンソーの実習を行いました。
箕輪町木下の民有林で講習を受けたのは、上農高校緑地工学科の2年生39人です。
これは、林業の後継者育成を目的に国が行っている事業の一環で、上農高校ではこの助成を受けて平成18年から毎年行っています。
生徒はグループに分かれ、持ち方や姿勢などの基本から実際の伐採まで、林業士から学んでいました。
上農高校では、チェーンソーを扱える生徒を増やすことで、手が行き届かずに荒れてしまっている、地域の森林整備ができる人材を育成していきたいという事です -
みのわ健康アカデミー卒業生の集い

箕輪町が2005年からシニア世代を対象に行っている健康教室「みのわ健康アカデミー」の卒業生の集いが19日に開かれ、継続的な健康づくりのための活動が紹介されました。
卒業生の集いは、教室終了後も継続して健康づくりをしていこうと「みのわ健康アカデミーフェスティバル」と題して毎年行われていて今年で3回目になります。
これまで273人が卒業し、この日はこのうち115人が参加しました。
卒業後も自主的に健康づくりを行っているグループも多く、その活動の輪を広げようと事例発表が行われました。
活動を発表した1期生のグループは、週に2回集まってウォーキングを行い、今年の秋には赤そば畑を歩くウォーキングイベントを開きました。
誰でも気軽に来てもらえるように、申込や受付をなくしたところ、卒業生以外の一般も含め60人以上が参加したという事です。
町では、教室終了後も自主的な健康づくりの輪を広げ、健康、長寿の町づくりをしていきたいという事です。 -
上伊那消防 大災害の消防活動に限界

伊那消防組合は、今の上伊那の消防体制では、大災害が発生した場合、出動体制や保有する車両に制限があり、消防活動に限界があると、17日、報告しました。
17日、伊那市役所で開かれた、伊那消防組合議会全員協議会の中で、示されたものです。
上伊那の消防体制については、今年5月より、伊那、伊南の消防本部を一つにする、広域化について研究が始まっています。
この日は、広域化に向け、上伊那地域の消防の現状と課題について、報告がされました。
伊那消防組合は、事実上市町村単位で消防署を運営管理していて、本部機能が一元化されていません。
一方、伊南行政組合では、本部機能は一元化されていますが、管轄人口が、およそ6万人と小規模で財政面などでの課題があります。
これらの事を踏まえ、今の上伊那の消防体制では、大災害発生時に、出動体制や保有する車両に制限があり、消防活動に限界があるとしています。
議員からは、地域の防災の要となる消防団からも意見を聞くべきなどの意見が出されていました。
また、伊那消防署の庁舎建設の候補地については、現在、4地域で検討が進められているとの説明がありました。
組合では、「具体的な場所については、現在は公表できないがある程度絞り込んだ段階で公表したい」と話していました。 -
木下南保育園園児がイナゴ取り

箕輪町の木下南保育園の園児が13日、保育園近くの田んぼでイナゴ取りをしました。
イナゴ取りは、稲刈りが終わったこの時期に行っている恒例行事です。
年少から年長までの園児65人がイナゴ取りをしました。
この日は園児の父親が保育に参加する日で、父親も一緒に田んぼを訪れました。
園児は、田んぼの中や土手を歩き、眼を凝らしてイナゴを探していました。
園児が取ったイナゴは、保育園の調理室で煮て、給食で味わうということです。 -
子ども神輿 お披露目

箕輪町の福与諏訪社の例大祭本祭りにあわせ、9日子ども神輿がお披露目されました。
子ども神輿は、全長3メートル、高さは1メートルほどです。
地元の有志でつくる「福与と人を元気にする会」が、住民参加による地域起こしを進めようと区内の子どもたちからデザインを募集し1ヶ月半かけて製作しました。
9日は、午前8時30分に福与公民館を出発し、諏訪社までの1キロのみちのりを1時間半かけて練り歩きました。
沿道では、地区住民たちが子どもたちに声をかけていました。
諏訪社の例大祭は、2007年まで約80年にわたり青年会による演芸が続いていましたが、会員不足により途絶えていました。
2月に発足した元気にする会は、まずできることからと神輿を活用した地域の活性化に取り組むことを決め、今日お披露目しました。 -
箕輪町青色パトロール隊

箕輪町の防犯ボランティア、箕輪町青色パトロール隊が、警察庁の「現役世代の参加促進を図る環境づくり支援事業」実施団体の指定を受けました。
この事業は、40歳代以下の世代に防犯ボランティアへの参加促進を図ろうと警察庁がおこなっているものです。
箕輪町青色パトロール隊が、この事業に応募したところ、町ぐるみで行っているセーフコミュニティへの取り組みが認められ今回、県下で唯一指定を受けました。
指定を受けたことから、警察庁から青色回転灯や、車両用マグネットシート、パトロールベスト、青色LED懐中電灯が貸与されました。
箕輪町青色パトロール隊は60歳代以上を中心に今年3月に結成されました。
15人の隊員が自分の車に青色回転灯を装着し子どもの登下校時のほか夜間や休日にパトロールを行っています。
隊では、今回の指定を機に現役世代の参加者を募り、その活動を広げていきたいとしています。 -
伊那市・箕輪町から技能五輪全国大会へ

次世代のものづくりを担う技能者がその腕を競う「技能五輪全国大会」の長野県選手団がこのほど発表されました。
伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは、2事業所から2人が出場します。
伊那市の菓匠Shimizuで働く圃中智穂さん22歳。圃中さんは木曽高校を卒業後、2年間愛知県の専門学校に通い、現在の仕事に就きました。
圃中さんはアメ細工やマジパン細工、ケーキを作る洋菓子製造の部門に出場します。
仕事が終わった後、先輩に教わりながら大会に向け練習をしているということです。
圃中さんは「普段やらないアメ細工が課題。先輩に教わりながら作り方を勉強しています。大会で学んだ技術や経験を持ち帰り、お客さんによりよいサービスが提供できるようにしたいです」と話していました。 -
上古田保育園の園児が栗拾い

箕輪町の上古田保育園の園児は11日、保育園近くの栗園で栗拾いを楽しみました。
栗拾いをしたのは、上古田保育園の未満児から年長までの園児およそ50人です。
箕輪町木下で大根などを栽培しているわかば農園が、子ども達に喜んでもらおうと無料で開放しました。
広さ30アールの園内には栗の木が70本以上あり、園児らはいがの中に入っている栗を上手に取り出していました。
栗園を管理する下平洋八さんは「園児たちの姿を見て元気をもらった。喜んでもらえてうれしいです」と話していました。
拾った栗は、家に持ち帰る他、給食で栗ごはんにして食べるということです。
園児達は、ビニール袋いっぱいになった栗をリュックサックにつめていました。 -
第5回天竜健康ウォーク

さわやかな秋晴れに恵まれた9日、第5回天竜健康ウォークが箕輪町で開かれました。
大会には、上伊那を中心に県内外からおよそ1,000人が参加しました。
参加者の健康と体力づくりを目的に実行委員会が5年前から毎年開いているものです。
参加者は、天竜川護岸を歩く5キロコースと田園風景を眺めながら歩く9キロコース、もみじ湖を通る13キロコースに分かれ、みのわ天竜公園をスタートしました。
絶好のウォーキング日和となった9日は、参加した家族や仲間同士、天竜川の景色を楽しみながら歩いていました。
実行委員会では「ウォーキングはお金がかからず誰でも気軽にできる。健康づくりのためにも、この大会がウォークングを始めるきっかけになればうれしい」と話していました。 -
旧井澤家住宅で木彫教室作品展

箕輪町在住の木彫作家、中澤達彦さんの木彫教室に通う生徒の作品展が9日から伊那市西町の旧井澤家住宅で始まります。
作品展は、旧井澤家住宅を管理する伊那部宿を考える会のメンバーが、古い木造建築と木彫が合うのではないかと中澤さんに話を持ちかけて実現したものです。
会場には中澤さんの伊那地区の教室に通う20人と中澤さんの作品、90点が並んでいます。
教室では生徒が創作で思い思いの作品作りをしていて、会場には仏像やレリーフなど様々な作品が展示されています。
中澤さんは「古い木造住宅と木彫で物によってはミスマッチなものもあるけど、逆にそこが良い。作品と住宅の融和した雰囲気を見てもらいたい」と話していました。
作品展は9日から16日まで旧井澤家住宅で開かれています。 -
学校給食アイデア料理コンテスト審査会

箕輪町の小中学生が学校給食の献立を考えるアイデア料理コンテストの審査会が7日夜、箕輪町保健センターで開かれました。
コンテストは箕輪町の食育推進事業の一環で、今年で4年目です。
秋の献立を募集し、町内の中学校と5つの小学校から248人の応募がありました。
同日は、書類による1次審査で入賞作品に選ばれた6点から最優秀賞を選ぶ2次審査が行われました。
献立を考えた児童と生徒が、「野菜がたくさんとれるようにした」「和風、洋風、中華風といろいろな味を楽しめるようにした」などと、献立について発表しました。
その後、栄養士や役場職員ら15人が、季節感、色どり、味、オリジナル性などを考え、試食審査していました。
最優秀賞は来週決定する予定で、表彰は学校で行われます。
入賞した6つの献立は、それぞれの学校で、実際に給食で提供されるということです。 -
箕輪進修高校定時制III部 「進修祭」で太鼓の演奏を披露

箕輪町の箕輪進修高校定時制III部の生徒は、10月14日から開かれる文化祭「進修祭」で太鼓の演奏を披露します。
6日夜は、箕輪町文化センターで2回目の練習が行われました。
箕輪進修高校の定時制III部は、地元のみのわ太鼓保存会の協力を得て、毎年進修祭で太鼓を演奏しています。
指導するのは、みのわ太鼓保存会の三澤興宣代表です。
6日夜は、1年生から4年生までのおよそ40人が、進修祭で演奏する予定の3曲を練習しました。
三澤さんは「太鼓には強と弱、長と短しかない。この4つをいかに表現するかが大切。太鼓はチームプレーなので息を揃えて1つの音を出すように」などとアドバイスしていました。
進修祭では、14日と16日の2回演奏を行うということです。 -
消火・通報コンクール

伊那防火管理協会に加入している企業などが参加する消火通報コンクールが7日伊那市内で行なわれました。
競技は、消火器操法と屋内消火栓操法で行なわれ、消火器操法には、8社から10チームが参加しました。
中央区自主防災会は初めてオープン参加しました。
火災を確認し消防署へ通報する役割の人と、主に消火を担当する人の2人ひと組で競技は行なわれ、消火や通報の速さ、正確さを競います。
今日は、風が強く、参加者たちは苦労しながら消火器で火を消していました。
審査の結果、中部電力株式会社伊那営業所が優勝しました。 -
MAながた会発足10周年記念展

箕輪町の日帰り温泉施設ながたの湯で絵画や書の作品展をしている「MAながた会」の発足10周年記念展が1日から、箕輪町文化センターで始まりました。
MAながた会は2001年に発足し、現在、箕輪町に暮らす9人と2つのサークルが所属しています。
会員はそれぞれ油彩、水彩、日本画、染色、書に取り組んでいて、ながたの湯ロビーで1か月交代で個展形式の展示をしています。
年1回はチャリティー展を開き、収益を町社会福祉協議会に寄付しています。
今回の10周年記念展では、会員が1人1点出品し、元会員の遺作も含め16点が展示されています。
ながたの湯では展示できない大作や、中央の展示会で入賞した作品など、それぞれ思い入れのある1点を展示したということです。
MAながた会発足10周年記念展は8日まで、箕輪町文化センターで開かれています。 -
箕輪町 新しい副町長に選任された白鳥一利さんの就任式

箕輪町の新しい副町長に選任された白鳥一利さんの就任式が3日、箕輪町役場で行われました。
就任式では、平澤豊満町長から白鳥さんに辞令が手渡されました。
白鳥さんは「40年の間に多くの人と出会い多くの事を学んだ。それらを活かし、平澤町長が掲げる活力溢れる元気な箕輪の町づくりの実現にむけ、職員と町民の皆さんと一緒になってがんばっていきたい」と抱負を述べました。
平澤町長は「副町長が一人制になり新たな形での組織運営が必要となる。副町長を中心にこれまでとは違った白鳥カラーで、職員一丸となってがんばってほしい」と話しました。
副町長の任期は、10月1日から平成27年9月30日までの4年間となっています。 -
交通安全優良運転者らを表彰

交通安全に尽力した個人や団体に対する表彰の伝達式が29日、伊那警察署で行われました。
関東管区警察局長と関東交通安全協会連合会会長の連名表彰など伊那警察署管内の受賞者に表彰が伝達されました。
連盟表彰では、運転者の模範となり安全運転に功績のある優良運転者として、伊那交通安全協会副会長の野口啓士さんと、元高遠地区交通安全協会藤沢支部女性部長の一ノ羽勝江さんが表彰を受けました。
交通栄誉章緑十字銅章の伝達では、交通安全功労者など14人が表彰されました。
受賞者を代表して野口啓士さんは「地域の安全安心を守るため、受賞を契機に一生懸命、交通安全に携わっていきたい」と謝辞を述べました。 -
上古田赤そば花まつり

箕輪町上古田地区で栽培されている赤そばの見ごろに合わせて1日から「赤そば花まつり」が上古田公民館で始まりました。
会場には朝から多くの人たちが訪れ、打ちたてのそばを味わっていました。
これは、地域で獲れたそばの味を楽しんでもらおうと、上古田区が毎年開いているものです。
赤そばは普通のそばに比べて収量が3分の1程度と少ないため毎年普通のそばを提供していますが、今年は初めて先着100人に限り赤そばのそばが提供されました。
埼玉県から訪れたという男性は「打ちたてのそばが食べたくて毎年来ている。こしがあっておいしい」と話していました。
赤そば花まつり実行委員会の唐沢幸道委員長は「地区のそば打ち職人が一生懸命そばを打っているのでぜひきてもらいたい」と話していました。
赤そば花まつりは2日にも上古田公民館で行われる予定で、時間は午前10時から午後3時までとなっています。 -
桑沢・永岡副町長退任式

任期満了に伴い9月30日付で退任した箕輪町の桑沢昭一副町長と永岡文武副町長の退任式が9月30日、箕輪町役場で行われました。
退任式には職員130人が出席し、花束などが送られました。
桑沢さんは昭和37年4月に役場に入り税務課長、総務課長などを経て平成15年10月に助役に、平成19年から総括副町長を務めました。
永岡さんは、平成15年6月ににオリンパス光学工業(株)を退職後、助役に就任し、平成19年から特命副町長を務めました。
桑沢さんは「今日まで5人の町長、大勢の職員、地域の人と一緒に仕事をさせていただいた。貴重な財産をつくることが出来た」と話していました。
永岡さんは「行政も民間も仕事を進めていくのは人。今まで以上に一人一人が自己責任、自己決定の理念のもと仕事に取り組んでほしい」と話していました。
式で平澤豊満箕輪町長は「2人はリーダーとしての能力が高く、多くの成果が生まれた。今後の町の発展の確たる礎になる」と8年間の実績をたたえました。
この後、2人は職員に見送られ役場を後にしていました。
1日から、副町長に前の総務課長の白鳥一利さんが務めます -
第39回ふきはら祭

箕輪町の箕輪中学校の文化祭、第39回ふきはら祭が30日からの2日間の日程で行われています。
今年のふきはら祭のテーマは「3thankyou9」縲怩りがとうの気持ちを伝えよう縲怩ナす。
初日の30日は、ステージ発表が行われ各学年の代表者が総合的な学習の時間に学んだ事を発表しました。
1年生は伊那市高遠町で行ったキャンプについて「自分たちで作った夕食のカレーは、文句を言いたくなるような味だったが、みんなで食べれば不思議と美味しかった」と話しました。
2年生は、福祉施設でのお年寄りとの交流について「自分たちが普段当たり前のようにしていることでも、お年寄りにとってはすごく大変なことが多いということが分かった」と話しました。
3年生は進路学習について「仕事をしている人はその仕事に誇りをもっていることが分かった。自分の夢に向かって1日1日を大切に過ごしたい」と話しました。
ふきはら祭は1日も行われ、生徒会は多くの来場を呼び掛けています。 -
信州みのわ山野草クラブの秋の展示会

信州みのわ山野草クラブの秋の展示会が、24日と25日の2日間、箕輪町の木下公民館で開かれています。
会場には、季節の花や盆栽などおよそ200点が並んでいます。
今年は、花が少なめですが、葉の表面に白い模様のある斑入りの物が多く楽しめます。
クラブは、箕輪町を中心に辰野町から伊那市までの会員18人でつくられています。
毎年展示会を開いていて、近年は県内各地からの来場者も増えているということです。
山野草展示会は、25日まで木下公民館で開かれています。 -
第23回平和のための信州・戦争展in箕輪町

平和の尊さと戦争の悲惨さを後世に伝える「第23回平和のための信州・戦争展in箕輪町」が24日から、箕輪町地域交流センターで開かれています。
会場には、戦争の悲惨さを伝えるパネルや写真、当時の軍服などが展示されています。
戦争展は、県内4地区が持ち回りで開いていて、上伊那では6回目、箕輪町では初めて開かれました。
戦争展を主催する平和のための信州・戦争展実行委員会では、上伊那地域での戦争に関する展示を行おうと、陸軍伊那飛行場に関するパネルの他、辰野町に実際に投下された爆弾の破片などを展示しています。
他にも、スパイ戦に必要な資材や機材の研究開発のために上伊那各地でつくられた登戸研究所に関する資料なども展示されています。
訪れたある70代の女性は「戦争については小さい頃で詳しいことは覚えていないが恐かったことだけは覚えている。展示を見て戦争の悲惨さを改めて実感した」と話していました。
戦争展は25日まで箕輪町地域交流センターで開かれていて、25日は登戸研究所に関する講演などが行われます。 -
台風15号 上伊那で果樹被害3500万円

非常に強い台風15号の影響で上伊那地域は中川村を中心に果樹で3500万円余りの被害がありました。
台風15号は、21日の夕方県内に最接近しました。
一夜明けた22日朝は、箕輪町上古田の果樹農家が、強風により落下した梨を処理する作業に追われていました。
中込さんは、4縲・日後には出荷予定だった梨を拾い集めては捨てていました。
JA上伊那によると、上伊那全体では果樹で、5%が落下・品質が低下するなどの被害がありました。
被害が大きかったのは、辰野町から伊那市の伊那西部地区で、20%ほどが落下しました。
上伊那全体でりんごは160ヘクタール・1千万円、梨は60ヘクタール、2500万円の被害がありました。
米、そば、大豆などは、風により倒伏したり、水に浸かるなどの被害がありました。
伊那市では、人畜や家屋の被害はありませんでしたが、11箇所で倒木がありました。
22日午後4時現在、伊那辰野停車場線と伊那駒ケ岳線が片側交互通行となっています。
箕輪町では、人畜・家屋の被害はありませんでしたが、20箇所で倒木があり、町道などが通行止めになったほか、農業ハウスや東屋の屋根が飛ばされる被害などがありました。
南箕輪村では、特に被害はありませんでした。 -
伊那中央病院 平成22年度決算 2年連続黒字
伊那中央病院の平成22年度決算は純利益が1億4,800万円と、2年連続で黒字となりました。
これは21日に開かれた伊那中央行政組合議会で報告されたものです。
開院後初めての黒字になった平成21年度に続き2年連続の黒字で黒字額は1億4,800万円となっています。
これは、診療報酬の増額や、入院収益が病名ごとの包括支払になったこと、交付税の増額、薬品費や診療材料費の経費抑制によるものとしています。
年間のべ患者数は、外来で185,824人で前の年に比べ858人、率にして0.5%増加しました。
ただ、2年連続の黒字となったものの、里帰り出産の制限、内科、整形外科、産婦人科では、初診は紹介状がある事を条件としていて、引き続き医師確保と収益増に努めるとしています。
また、この日の議会で、伊那中央病院料金条例の一部を改正する事が決まりました。
美容外科での新たな患者ニーズにこたえるもので、スキンケア料金の引き下げのほか、乳がん手術後の乳頭再建手術などが新設されました。
伊那中央病院では、美容外科開設から半年が経過し、患者数は月平均80人と、収益も順調に推移しているという事です。 -
箕輪町議決経ていない損害賠償約282万円

箕輪町で、平成18年度から今年度までに議会の議決を経ていない損害賠償事例が35件、およそ282万円あったことが分かりました。
これは20日開かれた箕輪町議会全員協議会で報告されました。
道路不備による損害賠償は20件、およそ115万円、公用車による物損事故は15件167万円でした。
損害賠償金はすべて保険会社から支払われたということです。
平澤豊満町長は、「地方自治法の認識が甘かった。お詫び申し上げる」と陳謝しました。
箕輪町議会は今回の報告を受け、町が行う損害賠償について、今後町長の先決処分とする議員発議の提出に向け内容を検討していくということです。 -
副町長に白鳥一利さん

箕輪町の新しい副町長に現在の総務課長の白鳥一利さんが就任することが20日、決まりました。
現在総務課長の白鳥一利さんは58歳。
昭和46年3月に辰野高校を卒業後、その年の4月に箕輪町役場に勤めました。
平成18年10月から保健福祉課長を、平成21年10月から総務課長を務めています。
白鳥さんは「町民の目線に立ち、職員の良き理解者として誠心誠意努力したい」と挨拶しました。
箕輪町では平成15年10月から副町長2人体制をとっていて、 現在の桑沢昭一さんと永岡文武さんは9月30日に任期満了となります。
20日の町議会9月定例会には副町長を一人とする条例改正案と白鳥さんを副町長とする人事案件が提出されどちらも全会一致で可決されました。
白鳥さんは10月1日付で副町長の職務につくことになっていて任期は4年間、平成27年9月30日までとなっています。 -
箕輪町上古田の赤そば色付き始め

箕輪町上古田の赤そば畑では、そばの花が赤く色付き始めています。
赤そばはネパール原産で、日本でも育つように品種改良され、高嶺ルビーと名付けられています。
箕輪町上古田の赤そばの里は標高およそ900メートル、広さは4.2ヘクタールで赤いそばの花が一面に広がっています。
18日、箕輪町上古田で赤そば里開きが行われ、関係者がテープカットなどで祝いました。
この畑を管理しているのは、上古田の区民有志95人でつくる古田の里赤そばの会です。
会では8月におよそ200キロの種をまき、順備を進めてきました。
赤そばの里は箕輪町の観光スポットとなっていて、この時期、県内外から観光客や、写真愛好家が訪れます。
赤そばの見ごろは、今月下旬から来月上旬までで来月10日まで地元産の野菜や果物などの直売所が設けられています。
また10月の1日と2日は、上古田公民館で、手打ちそばの試食ができる、赤そば花まつりが開かれる予定です。 -
箕輪町職員が災害対応訓練

箕輪町は、町職員を対象にした、災害対応訓練を16日に行いました。
訓練は、職員が、被災地や避難所などで、迅速かつ的確に行動できるよう行われました。
町では、東日本大震災や各地で発生した豪雨災害を受け、これまでの避難を中心とした訓練から、今年は、より実践的なものにしました。
参加した職員は、発電機や放射能測定器など町が所有する機器の使用方法を理解すると共に、どのう作りなどを行いました。
放射能測定では、防護服を着た職員が、「電源を入れてから機器が安定するまで2分30秒待つ事」や、「同じ場所で30秒毎、5回測定するなど」基本的な使い方を説明していました。
箕輪町では、防災の原点にもどり、今後、設備や職員の行動などについて見直しを行いながら、災害に強い街づくりを目指していくといしています。 -
蓄音機の音色楽しむ 箕輪町郷土博物館でミニ講座

箕輪町の郷土博物館で16日夜、蓄音機の音色を楽しむミニ講座が開かれました。
これは、普段忙しい大人にも博物館に親しんでもらおうと開かれたミニ講座で、5人が参加しました。
蓄音機は、昭和8年に発売されたもので、2年前に町民から郷土博物館に寄贈されました。
講座は、蓄音機の音色を楽しんでほしいと初めて計画され、博物館が所蔵するレコードおよそ300枚の中から状態の良いものを選び、昭和20年代後半から30年代初期の歌謡曲と童謡合わせて10曲を聞きました。
参加した人たちは、蓄音機から流れる歌に合わせて口ずさむなどして楽しんでいました。 -
箕輪町防災講演会
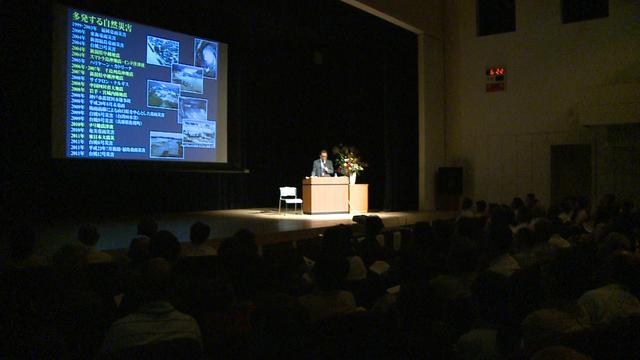
箕輪町は、住民の防災意識を高めようと「想定外を生き抜く力についての防災講演会」を15日、箕輪町文化センターで開きました。
講演会は、東日本大震災の教訓から、災害に備えることの大切さを再認識してもらおうと、箕輪町が開いたものです。
会場には、住民およそ450人が集まりました。
群馬大学大学院工学研究科教授の片田敏孝さんが講師を務め、「想定外を生き抜く力」をテーマに、話をしました。
片田さんは、平成16年から岩手県釜石市の防災アドバイザーとして、地震発生時の避難などについて、市内の小中学校で指導してきました。
今回の震災では、釜石市は津波の被害を受けましたが、学校に登校していたおよそ3,000人の小中学生全員が避難することができました。
片田さんは「▽想定にとらわれるな▽最善を尽くせ▽率先避難者たれ」と、自身の考える避難3原則について話しました。
他に、「想定外を生き抜くためには、ハザードマップや過去の経験などの想定にとらわれてはいけない。その状況下で最善の策を尽くすことが大切」などと話していました。
なお、伊那市教育委員会では市内の全小中学校を対象に東日本大震災発生時の避難行動について調査しました。
その結果、「自主的に避難行動をとった」という児童や生徒は、小学校で57%、中学校で42%となっています。
他に、「教師が即座に避難行動の指示を出した割合」は、小学校で61%、中学校で67%となっています。
教諭が気付いた点として、「▽地震が起きた際、児童はすでに机の下に避難していて、日頃の訓練が活かされていること▽今後も自主的に避難行動をとれるよう訓練を重ねていくこと」などを挙げています。
202/(金)
