-
ニュージーランドの林業学ぶ

林業先進地ニュージーランドの林業・林産業についての講演会が10日南箕輪村の信州大学農学部で開かれました。 講師は、ニュージーランド在住の林産業・木材コンサルタントの松木法生さんです。 東京農工大学農学部林学科卒業後、ニュージーランドにわたり、林業に関するコンサルタントをしています。 講演会は、林業先進地の状況を聞くことで、日本林業再生のヒントを見出そうと開かれました。 ニュージーランドは、日本と気候が似ていますが、林産物が輸出の3位で、主要な産業に位置付けられています。 30年で成木になるラジアータ松を効率的に生産していて、中国への輸出が飛躍的に伸びているということです。 松木さんは、「杉は、成木になるまでに60年から80年かかるが、30年サイクルのラジアータ松は、効率的な林業のモデルケースと言える」と話しました。 ある参加者は、「どんな木をいつ植えていつ切って何に使うかをもっと考えるべきと感じた」と話していました。
-
信州大学農学部 山ぶどうワインの販売始まる

南箕輪村の信州大学農学部の学生が育てた山ぶどうを醸造して作ったワインの販売が、14日から始まりました。 食料生産科学科の3年生が今年の春から夏にかけて栽培し、2年生が10月に収穫した山ぶどうを使ったワインです。 今年は1.6トンを収穫し、伊那市美篶の伊那ワイン工房で醸造しました。 すっきりとして飲みやすく、爽やかな酸味が効いた仕上がりになったという事です。 山ぶどうワインは720ml入りが2,200円、360ml入りが1,300円です。それぞれ1,200本、200本の数量限定で信大農学部の生産品販売所で購入できます。
-
い~な雑穀フェスタで料理教室

様々なレシピを知ってもらう事で雑穀の普及につなげようと、伊那市長谷で10日「い~な雑穀フェスタ・料理教室」が開かれました。 アマランサスを良く熱したフライパンでポップさせます。タルトの上に温野菜をのせて食べる「ベジデコケーキ」のトッピングになります。 料理教室は、伊那地域アマランサス研究会や伊那市などでつくる、い~な雑穀ネットワークが、毎年この時期に行っている「雑穀フェスタ」の一環で開かれました。 この日は市内を中心に32人が参加し、雑穀クリエーターの梶川愛さんのレシピを学びました。教室では、アマランサスをトッピングするベジデコケーキのほかに、もちきびともちあわ入りの冬野菜スープ、粉状にしたしこくびえと米粉でつくるガレットの3品を作りました。 梶川さんは、炒めたり、茹でたり、粉状にするなどして食感に変化がつくようレシピを工夫したという事です。 い~な雑穀ネットワークでは、栄養価の高い雑穀のより良い取り入れ方を知ってもらい普及に繋げていきたいとしています。
-
特産品に手紙を添えて町をPR

箕輪町のリンゴや長いもなどの特産品に、小学生が地域を紹介した手紙などを添えた「ふるさと便」の発送作業が9日、JA上伊那箕輪果実選果場で行われました。 「ふるさと便」は、地域の特産品を、子ども達のメッセージとともに県内外に発信してもらおうと、箕輪町観光協会が行っているもので、今年で30年目になります。 この日は観光協会の職員がメッセージの箱詰め作業にあたりました。 注文数は毎年増えていて、今年は、リンゴ5キロ入りが118箱、10キロ入りが73箱、長いも5キロ入りが117箱の注文があったということです。 注文のほとんどが町内の人で、県外にいる家族や友人にお歳暮として送っている人が多いということです。 町観光協会では「子ども達のメッセージとともに、箕輪の味を楽しんでもらいたい」と話していました。
-
年越しそばと年明けうどんの贈答用セット発売

JA上伊那のオリジナルブランド「伊那華シリーズ」で、年越しそばと年明けうどんの贈答用セットが、8日から限定販売されます。 「伊那華の年越しそば 年明けうどんセット」は8日から販売が始まります。 7日、南箕輪村のファーマーズあじ~なで、JA上伊那の神子柴茂樹組合長らが試食販売をし、商品をPRしました。 そばは上伊那産のそば粉を使い、そば殻を入れて風味を引き立てました。 うどんも上伊那産の小麦ハナマンテンが使われていて、コシが強いのが特徴です。 年越しそば 年明けうどんセットは、贈答用に去年からシリーズ化し今年で2年目です。 そば、うどんは人気が高く、伊那華シリーズの売り上げの半分を占める主力商品だという事です。 そば、うどんそれぞれ4人前がセットで価格は2,160円です。 8日からJA上伊那管内のAコープや直売所などで販売が始まります。 限定2,000セットとなっています。
-
地産地消セミナーで豆腐作り

農村女性ネットワークいなが主催する地域の食材を活用した地産地消セミナーで、参加者が、豆腐作りに挑戦しました。 セミナーは、伊那公民館で開かれ、35人ほどが参加しました。 今回は大豆から豆腐を作りました。またおからのサラダとドーナツも作りました。 農村ネットワークいなは、農家の女性たちで作るグループで、年に2回こうした料理講習会を開いています。 手作りの豆腐は家庭ではなかなか作る機会がないということもあって今回は募集人数を超える参加がありました。 農村ネットワークいな代表の白鳥 あき江さんは、「野菜を作っている私たちにとって地産地消はうれしいことです。みんなで楽しく料理を学んで、家庭に持ち帰ってほしい」と話していました。 次回の講座は、来年2月で雑穀を使った料理に挑戦する予定です。
-
雪と冷え込みでリンゴに影響

上伊那地域では、先週の雪と低温の影響で、リンゴなどの農作物に被害が出ています。 伊那市西箕輪でリンゴオーナー園を営む重盛正さんは、リンゴを地域の福祉施設の利用者に食べてもらうことにしました。 傷んではいますが味に問題はないということで、28日に福祉施設の職員と共にもぎ取り作業をしました。 伊那地域では、24日に14センチ雪が積もり、その翌日には11月の観測史上最低となる、-7.2度を記録しました。 その影響で、リンゴの上に積もった雪が翌日の低温で氷り、果肉が柔らかくなってしまったり、割れてしまう被害が出ました。 重盛さんは「昭和58年にここで農園を始めてからリンゴに雪が積もったり、こんなに寒くなるのは初めてのこと」と話していました。 箕輪町木下のJA上伊那果実選果場では、先週の雪や低温の影響で、リンゴの持ち込みに遅れが出ているということです。 例年、凍っても融ければ売り物になるということですが、今回は強い冷え込みの影響で、リンゴの芯まで凍ってしまい、外見だけでは被害が確認できず、出荷の判別が難しい状況だということです。 JA上伊那の果樹広域担当の唐澤良忠さんは「ここまでの冷え込みはこれまでに経験がないので、どんな被害が出るかわからないし、被害があるかどうかもわからない」と話していました。 収穫作業が遅れていることから箕輪果実選果場では、30日を予定していた受け入れ期間を、来月4日まで延長して対応することにしています。
-
天竜川で大きなアマゴを 本流に初めて放流

天竜川本流で大きいアマゴを釣り上げて楽しんでもらおうと、天竜川漁業協同組合は25日、初めて本流にアマゴを放流しました。 天竜川本流への放流は、現在の川の状況を知り、アマゴが釣れる環境か確認しようと、漁協が試験的に行ったものです。 2月の解禁以降どこで釣れたかわかるように、集まった漁協の組合員10人ほどが、アマゴの脂ビレを切り落としていました。 アマゴは、川を下り、成長してから生まれた場所まで遡上して産卵する魚です。 天竜川漁協によりますと、昔は海まで下ったアマゴが、サツキマスと呼ばれる大きいサイズになって天竜川に戻っていたということです。 海から天竜川を遡上した大きいアマゴを「天竜差し」と呼び、多くの釣り客がこれを目当てに訪れていたということです。 現在はダムができ、遡上が難しいことから、天竜川の支流に放流し、本流から支流に遡上したアマゴを釣るのが主流になっています。 一方、本流で大きな竿を使ってアマゴを釣りたいという釣り客の要望も多く、今回初めて放流しました。 支流とは違い、水温が安定していることや、餌となるザザムシが豊富なことから、アマゴの成長が早く、釣果も期待できるということです。 小野文成組合長は「釣り客のみなさんに楽しんでもらえるよう今回企画した。釣り人だけでなく、多くの人に親しんでもらえる天竜川を作っていきたい」と話していました。 漁協の組合員らは、20センチほどのアマゴおよそ1,300匹の脂ビレを切ると放流していました。 天竜川での釣りは2月16日に解禁される予定で、天竜川漁協では「脂ビレのないアマゴが釣れたら、どこで釣れたか連絡してもらいたい」としています。
-
家畜の霊を慰める畜魂祭

家畜の霊を慰めるJA上伊那の畜魂祭が21日、伊那市のJA上伊那本所で行われました。 JA上伊那畜産部会協議会が毎年この時期に行っているもので、上伊那の畜産農家など関係者およそ70人が出席しました。 JA上伊那の1年間の出荷頭数は、豚3,500頭、牛300頭などとなっていて、ここ数年間は横ばいとなっています。 出荷額は肉牛が2億5千万円、豚が1億7千万円ほどとなっています。 JA上伊那によりますと、全国的に肉牛の出荷頭数が減少しているため、出荷価格が高騰しているということです。 JA上伊那の牛山喜文専務は、「御霊に感謝するとともに、畜産事業の発展のため決意を新たにしてほしい」と農家に呼びかけていました。
-
上農生と南部保育園の園児がチューリップ球根植え

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒と南部保育園の園児が21日、大芝高原内の花壇にチューリップの球根を植えました。 球根植えは、園児と高校生の交流を深めてもらおうと村内の住民有志でつくる南箕輪村花いっぱい推進協議会が毎年行っているもので、1200個が用意されました。 上農高校の園芸科学科の3年生13人と、南部保育園の年長園児35人が大芝の湯駐車場入り口の花壇に球根を植えました。 高校生は、球根の尖っている方を上にして植えるよう園児に教えていました。 草取りなどの世話は協議会が行い、花は来年の春から夏にかけて咲くということです。 余った球根は村内の保育園に配るということです。
-
JA上伊那あぐりスクール 育てた米をマリ共和国へ贈る

小学生が農業体験を行うJA上伊那のあぐりスクールは、9月に収穫した米を、食料不足に悩むアフリカのマリ共和国へ贈りました。 19日に伊那市内で贈呈式が行われ、あぐりスクールの代表児童がJA上伊那の神子柴茂樹組合長に米を手渡しました。 東春近の田んぼで5月に田植えをして育てたコシヒカリで、60キロを贈ります。 米袋には「このお米が役立ちますように」などと現地の言葉でメッセージが書き添えられました。 JA上伊那では平成18年から毎年マリ共和国へ米を贈っていて、今年で11年目になります。 県内の各地域にあるJAでもこの取り組みを行っていて、来月中にJA長野中央会を通じてアフリカのマリ共和国へ届けられる予定です。
-
アルストロメリア 出荷作業本格化

上伊那が出荷量日本一を誇る花「アルストロメリア」の出荷作業が、年末の需要期に向けて本格化しています。 伊那市東春近の花卉農家 酒井弘道さんのハウスでは、アルストロメリアおよそ80万本を栽培していて、年末に向けた出荷作業が本格化しています。 ちょうど花が綺麗な頃店頭に並ぶよう咲き始めのものを選んで収穫しています。 アルストロメリアは南アメリカ原産の多年草で、花束やフラワーアレンジに使われるなど、汎用性の高い花として重宝されています。 JA上伊那管内では、およそ60軒の農家が、東京・愛知・大阪の主要都市を中心に年間1200万本を出荷していて、全国で最も出荷量の多い地域となっています。 上伊那では、常に良い状態で買ってもらえるよう特殊なダンボールを使用したり、冠婚葬祭などにも使われることから夏の時期に出荷するなど、生産地日本一のブランドを維持するために様々な工夫をしています。 JA上伊那花卉部会アルストロメリア専門部会の部長も務める酒井さんは「もちろん日本一の生産地というものを自負している部分もあるが、常に良いものを出荷し続けるという意味では苦労も多い」と話していました。 酒井さん宅では1年間出荷をしていますが、これから最盛期を迎える5月頃まで忙しい時期が続くということです。
-
羽広菜かぶ 漬け込み作業

「信州の伝統野菜」に認定されている羽広菜かぶの漬け込み作業が、伊那市西箕輪のみはらしファームで16日から始まりました。 この日は、90キロのかぶの漬け込み作業が行われました。 機械にかけ洗浄した後、包丁で大きさを整え、粕漬けに加工していきます。 伊那市西箕輪の農業公園みはらしファーム内にある農産物加工場では、朝から羽広菜生産加工組合のメンバー5人が作業に追われていました。 羽広菜は、西箕輪羽広を中心に昔から栽培が行われてきたもので、普通のかぶより歯ごたえがあるのが特徴だという事です 粕漬けは、縦に2つに切ったあと、酒粕と味噌、砂糖などを混ぜたものに漬け込み20日から30日ほど熟成させます。 組合では、地区内に畑を借り毎年2トンの羽広菜かぶを加工しています。 作業は12月上旬まで行われ、かぶ漬は来年3月頃までみはらしファームや南箕輪村のファーマーズあじ~な、ニシザワなどで販売されます。 価格は、250グラム入り330円となっています。
-
貝付沢に獣害防止ネット設置

伊那市有害鳥獣対策協議会は、野生鳥獣対策モデル事業として、伊那市西春近諏訪形貝付沢に獣害防止ネットを12日設置しました。 12日は、伊那市や西春近自治協議会、諏訪形区を災害から守る委員会など25人が参加し、貝付沢に獣害防止ネット500メートルを張りました。 諏訪形区では平成18年の豪雨災害を機に、根が張りやすく倒れにくい広葉樹の植栽を行ってきましたが、野生鳥獣による食害が問題となっていました。 伊那市有害鳥獣対策協議会では、伊那西部山麓地域へのニホンジカの進出を食い止めようと、昨年度から諏訪形でモデル事業を行っています。 昨年度はおよそ1キロの長さのネットを張ったほか、今年6月から8月にかけ林道沿いにセンサーカメラ2台を設置しました。 その結果、ニホンジカ6体、イノシシ21体などが確認されました。 協議会では、今後効果を検証し、他地域の有害鳥獣対策や里山の利活用につなげていきたいとしています。
-
JA上伊那まつり

農産物の収穫に感謝するJA上伊那まつりが12日、13日の2日間、JA上伊那本所で行われています。 JA上伊那本所では、上伊那産の農産物が販売され、訪れた人たちが買い求めていました。 JA上伊那まつりは、農産物の収穫に感謝し、地域の人たちに農業に親しんでもらおうと毎年行われていて、今年で21回目です。 今年は酪農を盛り上げていこうと、バターづくり体験が行われました。 訪れた人たちは牛乳と生クリームをボトルに入れて振り、バターを作っていました。 JA上伊那まつりは13日も行われることになっていて、午前10時からと午後3時30分からは大宝投げが行われます。
-
上伊那の主力野菜 白ネギ出荷本格化

上伊那地域の野菜農家の主力品目、白ネギの出荷が本格化しています。 11日は南箕輪村のJA上伊那広域集出荷場に白ネギが集められ皮をむいたり、箱詰めする作業が行われていました。 白ネギは県内では上伊那と松本が産地でアスパラガスやブロッコリーと並びJA上伊那が出荷する野菜の主力品目の一つです。 今年は秋に雨が多かったことが影響し例年より細いものが多く収量も落ちているということです。 去年のJA上伊那の年間販売額は全体でおよそ140億円で品目別にみると1位は米で36億円、白ネギは6位の4億3000万円でした。 今年は年間で1,320トンを生産し販売額は3億9,000万円を見込んでいます。
-
信大生が育てた低農薬の米 販売

南箕輪村の信州大学農学部の学生が低農薬有機栽培で育てた米の販売が始まっています。 信州大学農学部では、植物資源科学コースの学生が実習の一環で米の栽培を行っています。 販売するのは、新米のコシヒカリで、低農薬で栽培したものです。 田んぼの広さはおよそ2.5ヘクタールで、今年は、平年並みの12.5トンを収穫しました。 価格は、はざかけしたものが10キロで4,500円、はざかけしてないものが3,900円です。 米は、信大病院や大芝高原の施設で提供されているということです。 信州大学農学部の学生が育てた米は、生産品販売所で購入できます。
-
信州の伝統野菜 羽広菜かぶ収穫

長野県の「信州の伝統野菜」に認定されている伊那市西箕輪の羽広菜かぶの収穫が始まっています。 羽広から望む西山の山頂付近は8日の夜降った雪により紅葉から一転、雪化粧に変わり冬の訪れを感じさせます。 伊那市西箕輪羽広の西村勇一さんの畑では羽広菜かぶの収穫作業が9日の朝も行われていました。 西村さんは、5年ほど前から自宅用とは別に出荷向けの栽培をしています。 現在はサラダや浅漬け用にみはらしファームの直売所に出荷しています。 西村さんによりますと「羽広菜かぶ」は種を蒔く時期や天候により出来が大きく変わるため、リスクを減らす為に時期をずらして栽培しています。 今年は9月の天候不順によりその出来が心配されましたが、影響も少なくまずまずの出来だという事です。 収穫は漬物作業が始まる11月下旬から12月上旬にかけてピークを迎えるという事です。
-
県内4農業共済組合統合へ

南信農業共済組合の臨時総代会が10月26日に開かれ、来年4月に県内の農業共済組合を一本化する合併案が可決されました。 県内の農業共済組合は、農家の減少や、国が進める「1県1農業共済組合」を受け来年4月に合併し、これまでの県内の4共済組合から一本化する予定です。 農業共済制度は、自然災害の時に農家の損害を共済金で補う仕組みです。 組合員の農家が支払う、掛け金は、合併後3年は現在の水準が維持されます。 また、事務費は県内4つの組合のうち最も低い組合の金額となります。 南信農業共済組合の組合員数はおよそ3万4千人で、県内全体では12万9千人となります。
-
ふじ出荷前に査定会

晩生のりんご・ふじの出荷を前に、伊那市東部地区の農家を対象にした今年の出来をみる査定会が、31日、高遠町の東部ライスセンターで開かれました。 ふじは、上伊那のりんごの中では出荷量の37%を占めるりんごです。 この日は高遠町と長谷の東部地区でふじを生産している農家から15人ほどが査定会に参加しました。 今年は、春先の暖冬の影響から開花も早くふじの出荷も早まり、11月4日から本格的な出荷が始まります。 農家は、色や傷などによる等級分けなどについて説明を受けました。 ふじの出荷は来月4日から、12月中旬まで予定されています。
-
伊那市ソーシャルフォレストリー都市宣言 キックオフ
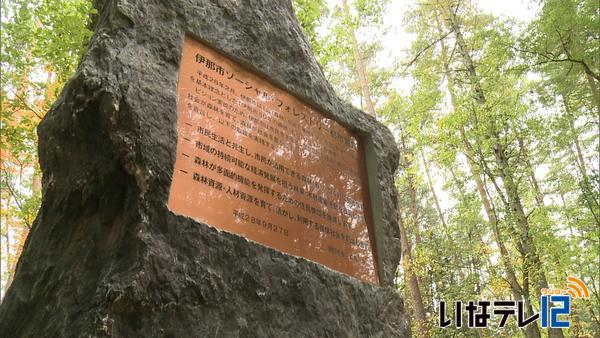
伊那市は、森林を活用した経済発展や雇用創出を目指す「50年の森林(もり)ビジョン」を進めています。 ビジョン実現に向けて30日、「ソーシャルフォレストリー都市宣言」のキックオフイベントが、ますみヶ丘平地林で行われました。 この日は、林業関係者や小学生、高校生などおよそ100人が参加して、記念碑の除幕や記念植樹が行われました。 植樹では、カエデやコナラなどの広葉樹およそ200本を、参加者全員で植えました。 市は「山が富と雇用を支える50年後の伊那市」を基本理念に「伊那市50年の森林(もり)ビジョン」を今年2月に策定しました。 このビジョンの実現に向けて、市民を主役とした自立的な経済の循環を構築し、社会が森林(もり)を育て、森林(もり)が社会を豊かにする―としたソーシャルフォレストリー都市を宣言しました。 伊那市は市内の50,000ヘクタールを超える森林を活用して、持続可能な林業・木材産業の発展の推進や、森林資源・人材資源の育成・活用・利用による循環社会の創出など「林業都市」という新しいモデルを作っていきたい考えです。 白鳥孝伊那市町は「50年に渡る事業をスタートすることができた。環境も十分にあるので、人材を育成していけば色々な事業をやっていける」と、今後の活動に期待していました。 伊那市では今後、間伐材を建築材として活用していくことを検討している他、地元の木材を使った建築への補助なども予定しています。 なお、この取り組みには、国から地方創生推進交付金として、およそ1,000万円が交付されています。
-
南箕輪小1年生がどんぐり拾い

南箕輪小学校の1年生は28日、樹種転換の活動で、大芝高原みんなの森でどんぐり拾いをしました。 この日は、南箕輪小の1年生およそ140人と信州大学の教授や学生がどんぐりを拾いました。 南箕輪村は、信州大学農学部の協力のもと、大芝高原の松くい虫対策として大半を占める針葉樹林を広葉樹林に変える樹種転換を進めています。 どんぐり拾いはその一環として行われたものです。 子ども達は、コナラやクヌギなどから落ちたどんぐりを、しゃがんで探しながら拾い集めていました。 子ども達は「なかなか見つからない」、「根っこが生えてる」と声をあげながらどんぐりを探していました。 信州大学農学部の小林元准教授は「拾うだけでなく、植えるところまで体験してもらう。種から木にになっていく過程を子ども達に学んでもらいたい」と話していました。 今回拾ったどんぐりは、来年春に信大農学部の畑に植えられ、3~4年後に育った苗木を大芝高原に植えることになっています。 コナラやクヌギがどんぐりを落とすようになるまでには20年ほどかかるということです。
-
森林づくり県民税 活用の現場を視察

長野県森林づくり県民税を使った里山整備について考える「みんなで支える森林づくり上伊那地域会議」は26日、里山整備の現場を視察しました。 この日は、林業関係者や建築士など、委員10人が箕輪町三日町の現場で間伐作業の様子を視察しました。 視察は、支援金が使われた現場を見て、適切に税金が使われているかを確認するものです。 視察した林は、三日町の御射山三社が所有する社有林で、現在間伐した木材を搬送するための林道を整備しています。 伐採された木材は、加工されたあと東北復興支援材として活用されるということです。 ある委員は「実際に現場を見ることで適切に使われているということが実感できた」と話していました。
-
5週連続そばイベント第2弾 信州伊那新そばまつり

「信州そば発祥の地伊那」をPRする5週連続秋の新そばイベントの第2弾、「信州伊那新そばまつり」が22日伊那市西箕輪のみはらしファームで行われました。 まつりでは、かけそば、せいろそば、行者そばが1人前500円で提供されました。 お昼時には訪れた人たちが長い列を作り、注文していました。 伊那市産のそば粉を使い、信州伊那そば打ち名人の会が打ちました。 このまつりは、信州そば発祥の地伊那をPRしようとみはらしファームが行っているもので、今年で5回目です。 また、そば粉を違う形で味わってもらおうと、ファーム内の体験交流施設では今年初めてそばガレット作りが行われました。 そば粉を使った生地を焼き、中に野菜や肉を包み込んでいました。 体験した人たちは自分たちが作ったガレットを早速味わっていました。 みはらしファームの州伊那新そばまつりはあすも行われることになっていて、そばは2日間でおよそ4000食が提供されます。
-
「富玉会」が箕輪町富田で玉ねぎの苗植え

箕輪町富田で玉ねぎを栽培している「富玉会」は、地域の子ども達と一緒に玉ねぎの苗植えを22日に行いました。 会長の向山勝一さんが子ども達に玉ねぎの苗の植え方を指導しました。 富玉会は休耕田で玉ねぎを育てる事で遊休荒廃農地の解消に取り組んでいる住民有志のグループです。 会の活動は今年で7年目で、毎年地元の子ども達と苗植えと収穫を行っています。 玉ねぎは来年6月末に収穫しカレーを作って味わう予定です。
-
家畜伝染病の発生に備えて 防疫演習

鳥インフルエンザなどの特定家畜伝染病の発生に備えた防疫演習が20日、伊那市の伊那合同庁舎で行われました。 演習は、渡り鳥の時期が本格的に始まる前に、鳥インフルエンザなどの家畜伝染病が発生した場合に備えようと上伊那地方事務所などが行ったものです。 今回初めて、上伊那と諏訪の地方事務所が合同で行い、この日は市町村関係者などおよそ80人が参加しました。 演習では、防疫服の着脱訓練が行われました。 防疫服を2枚着用し、ウイルスの感染を防ぐためガムテープで足元や袖を留めます。 防疫服の着脱訓練は、上伊那で行うのは3年ぶりです。 参加者はお互いに服装を確認しながら着用していました。 上伊那では今年2月1日現在、卵を産むための鶏を中心に95戸でおよそ20万羽が飼育されています。 万が一鳥インフルエンザが発生した場合、確認から24時間以内に殺処分を、72時間以内に埋めることが求められています。 上伊那地方事務所では「ウイルスの感染が確認された場合、とにかく初動対応が重要になる。万が一の時に迅速に対応できるよう備えていかなければならない」と話していました。
-
上農生が商品化「みたらしアマ団子」

南箕輪村の上伊那農業高校生産環境科作物班の生徒が商品化に取り組んできた、雑穀アマランサスを活用したみたらし団子が、このほど完成しました。 11日、伊那市の和菓子店大西屋で商品のお披露目会が開かれました。 上農高校生産環境科作物班では、雑穀の栽培や活用・普及に取り組んでいます。 雑穀アマランサスの活用について考えている、伊那地域アマランサス研究会で大西屋社長の小池保彦さんと知り合ったのがきっかけで、みたらし団子の開発が始まりました。 商品名は「みたらしアマ団子」で、ラベルも生徒が考えました。 団子に使われているのは、アマランサスの水煮です。 水を吸っている分、粒が大きくなり、歯ごたえを感じやすいのが特徴です。 作物班の藤原未有希班長は「みなさんが好きな食べ物にアマランサスを入れて、美味しいと言っていただければうれしい。」と話していました。 大西屋の小池保彦さんは「若い人たちの発送で新しい商品が完成した。これからもその感性で新たな商品を作って欲しい」と話していました。 「みたらしアマ団子」は、16日の上農祭一般公開で販売されることになっています。 価格は、1カップ5個入りで200円となっています。
-
マツタケ博士に学ぶ マツタケ教室

伊那市新山のマツタケ博士藤原儀兵衛さんから山の手入れ方法を学ぶマツタケ教室が8日、藤原さんが管理している新山の山林で行われました。 教室には市内を中心に14人が参加し、山の整備方法を学びました。 藤原さんは、山の一部に、マツタケの菌糸とアカマツの根が一緒になった塊「しろ」を作っていて、しろにそってマツタケが生えています。 アカマツの根を切ると新しい根が出て、マツタケの胞子がつきやすいということです。 教室は、マツタケの生産技術向上につなげようと伊那市が夏と秋の年2回開いています。
-
園児がもち米を収穫 農作業を体験

伊那市の西春近北保育園の園児は7日、園近くの田んぼでもち米の収穫を体験しました。 7日は園児およそ90人が保育園近くの田んぼで稲刈りや、はざかけを体験しました。 これはJA上伊那が、子どもたちに農業に触れてもらおうと地元のJA青壮年部西春近支部と協力して行ったものです。 園児らは鎌で稲を刈ったり、束ねたものを運んだりしていました。 保育園では11月に収穫したもち米を使ったもちつき大会を計画していてJAの職員や青壮年部のメンバーを招待することにしています。
-
JA上伊那フォトコンテスト 向山世男さんが最優秀賞

「農のある暮らし」や「魅力ある風景」をテーマにJA上伊那が行ったフォトコンテストの審査会が9月30日に開かれ、伊那市荒井の向山世男さんの作品が最優秀賞に選ばれました。 向山さんの作品は、最優秀賞のJA上伊那組合長賞を受賞しました。 JA上伊那青壮年部西箕輪支部のメンバーが遊休農地で育てたヒマワリ畑の様子を、今年7月に撮影したものです。 今年のフォトコンテストには、上伊那をはじめ千葉や埼玉など県外も含めた48人から169点の応募がありました。 審査は季節感のあるものか、農業の明るい未来を感じるものかなどの基準で行われました。 入賞作品は11月12日と13日のJA上伊那まつり本所会場に展示されるほか、JA上伊那の広報誌「る~らる」の2017年1月号に掲載される事になっています。
252/(水)
