-
富県さつき会会長
伊那市富県
橋爪謙司さん
玄関前をはじめ車庫や庭に、美しい色合いの見事なサツキの鉢がずらりと並ぶ。その数約100鉢。さらに盆栽も100鉢ある。
「サツキは咲き分けがある。真っ白の花の中に赤い花が咲いたり。それがいいじゃんかね」
20年ほど前、サツキの好きな弟が苗木を送ってくれたのがきっかけ。「やみつきになっちゃった」。定年退職後、本格的にサツキを育て始めた。
苗木を購入したり、挿し木をするなどして増やしてきた。品種は、山の光、日光、煌陽、大盃、華宝、翠扇などがあり、花色も白、朱、とき色などさまざま。単色もあるが、咲き分けの美しい鉢が多い。
管理で大切なのは、根が張って木が弱るのを防ぐための植え替えと、花が咲いた後の摘み取り。あとは水かけと肥料さえやれば咲くという。
「花の後の摘み取りが大変。全部しっかり取らないと、次の年に咲かない。来年咲くのが楽しみだから」と精を出す。
「サツキは花を楽しみ、その後は盆栽として楽しむ。2度楽しめるのがいいところ」。枝ぶりにもこだわり、枝が棚になるように小さいうちに針金で固定するなどして成形する。咲き分けでピンク色などが咲いた枝は、間違えて切らないように目印のテープを巻くなど注意を払い、大事に育てるという。
昨年は、霜の被害で上手く花を咲かせることが出来なかった。そのため今年は、「飲んで帰ってきても天気予報をよく聞いといて、霜の予報が出たら霜除けをして慎重に育てたよ」。そのかいあって、「今年は大きくて本当にいい花が咲いた」と満足気だ。
6月5日から4日間、富県さつき会の展示会を開いた。鉢は丹念に油で磨き上げ、盛りと咲き誇るサツキを出品。来場者250人を楽しませた。
これから咲く遅咲きのサツキを楽しみに、花が終わり始めた早咲きの鉢の手入れが始まる。それと同時に盆栽の手入れも怠らない。「サツキをやってたら盆栽にも興味が沸いてきて、めた増やしちゃって」。五葉松、錦松、ブナ、アケビ、柿など数えればきりがない。
「道楽ってもんだ。仕事は嫌だけど、これはごしたくない。農業しながら暇見ちゃやる。好きじゃないと出来ないね」。道楽とはいえ、全部で200鉢もの手入れ。「サツキでも100鉢くらいないとやる気にならない。熱が入らないからね」。そう言って楽しそうに笑った。(村上裕子) -
エコシャンプーで環境推進に一役

宮田村町三区の美容室スピックサロン駒ケ原店は5月に、従来品よりも節水できる環境にやさしいシャンプーを提供する「エコシャンキャンペーン」を展開。客に意識の啓もうを図りながら、売り上げの3万円を環境推進活動にと同村へ寄付した。経営するアトリエシミズの清水光枝社長、清水博行同店長は「少しでも多くの人に環境について考えてもらうきっかけになれば」と話した。
2人は11日に村役場を訪れ、清水靖夫村長にキャンペーンの取り組みを報告。「マイバックの普及など環境推進に役立てて」と、売り上げを手渡した。
今回用いたシャンプーは本来、首に負担をかけず頭皮にもやさしいとして開発されたもの。使用する水の量を最小限にできる特徴があり、清水店長は中越地震の時に被災地でシャンプーボランティアをした実績もある。
そのような経験から「エコシャンプーとして環境面の取り組みにもなるのでは」と同店が独自に着眼。
売り上げは地元の環境推進に役立てることを念頭に、5月の約20日間を特別価格のキャンペーンで提供した。
「我々の業界も環境は避けて通れない。地域とともに意識を高め、協力していきたい」と清水社長ら。
排水などが課題のパーマの環境対策にも乗り出しており「温暖化の中でドライヤーのことなども考えたい」と話す。 -
根強い人気、可れんなウチョウラン

花の中央頭部が烏(カラス)の頭に似ているから「烏頂蘭」、舌弁が羽を広げた蝶のようだと「羽蝶蘭」とも書く、ラン科の小型ラン。中川村小渋峡の急斜面の林の下や岩場に数十万株と咲いていたというウチョウラン、乱獲され、ほとんど姿を消してしまったが、村の人々は「イワユリ」と呼んで親しみ、村花にもなっている。20数年前、上伊那では一大ブームが起き、銘花、稀少花が数万円で取り引きされた。その後、バイオ技術で大量生産が可能になると、「高嶺のユリ」から庶民の花に。花の時期には飯島町や中川村など各地で展示・即売会が開催され、愛好家でにぎわう。今回は飯島町七久保の道の駅、花の里いいじまで開催中の「天竜うちょうらん愛好会」のウチョウラン展に展示されている銘花や珍花を紹介し、同会の山本知善会長や、小渋産の山採りウチョウランを繁殖させる中川村の「村花うちょうらんを育てる会」の宮下明芳さんから、育て方や繁殖法、魅力についてお聞きした(大口国江)
◇銘花、珍花など丹精込めた200鉢を展示、即売品も多数、天竜うちょうらん愛好会
同会は駒ケ根市と宮田村の愛好家6人で組織。会場にはポピュラーな紫花から白花、ふ入りの「白紫点」「紅一点」のほか、舌弁が大きい「仁王系」、舌弁が開かない玉咲き、いくつもの花が固まって咲く「子宝咲き」、斑入り葉など銘花がずらり。
開催日は14、15、28、29日。即売は500円から5千円位まで多数用意。
◇開花時期が長く、花色、花の形も多彩、山本知善会長
駒ケ根市赤須東町のガラスハウスで3千鉢を育てる。自家採りの種を蒔いたり、極小の球根を植えつけて育てるが、開花までに4年かかる。「1万本に1本位、突然変異の花が出現することがある。これが1番うれしい」とか。
用土は鹿沼土を主に、山ゴケを混ぜる。鉢は朝日が当り、夕日が当らない場所に置き、乾燥気味に育てるのが失敗しないコツ。「根の周りに寒天状の保水膜があり、乾燥に強いが、過湿に弱い」
「開花時期は1カ月余と長く、花の色も白から濃い紫までと多彩。花の形も変化に富む」と魅力を。
◇小渋産のウチョウランは「派手さはないが清楚で可れん」
中川村発足50周年記念協賛事業として開催される「うちょうらん展示・即売会」は22日午前9時から午後5時まで、中川村片桐のショッピングセンターチャオ特設会場で開く。「村花うちょうらんを育てる会(中飯寿勝会長)」の会員がウチョウランを多数展示、販売する。国道を挟んで西側のJAたじまファームでも、今月末ころから、小渋産の展示即売会も予定。小渋産のウチョーランは園芸種のような派手さはないが、色は淡紫色、清そで可れんとか。
◇岩ヒバの中で自然に繁殖、「育てる会」の宮下明芳さん(大草飯沼)
自宅前庭のイワヒバ群生の中や、ざっと百年物のイワヒバとの寄せ植えの大鉢の中にも小渋産のウチョウランが咲いている。「昔、桑原の山中に、ウチョウランが赤紫色のじゅうたんのように咲いていたのを見た。バイオで銘花が量産されるようになり、魅力も薄れたが、それだけに、小渋の自生のウチョウランが貴重になった」。
イワヒバの中で自然に繁殖しているが、シュンランやモジズリなどラン菌のある鉢に種まきをすると、成績がよいとも。
了) -
伊那街道駕籠立場現地見学研修
伊那部宿を考える会
伊那部宿を考える会は7日、伊那部宿と関係する史跡の一つ、伊那街道「駕籠(かご)立場跡」などの現地見学研修を開いた。会員16人が、当時の面影を残す伊那街道を通って駕籠立場跡や恩徳寺跡などを巡り、江戸の時代に思いをはせた。
伊那の古文書研究会長の久保村覚人さんが案内。説明によると、天保9年5月、幕府の巡見使(江戸幕府が地方に派遣した監察使で、領内の事情を視察し幕府に報告する)が伊那地方を訪れ、一行115人が伊那部宿に到着し昼食をとった。地元では183人を動員して接待。巡見使一行はその後、眼田(まなこだ)村(現西春近沢渡上段)木浦ヶ原の「駕籠立場」で休息し、地方の情勢を聴取したという。
研修では、今も道祖神が並ぶ眼田坂下の辻、眼田坂、駕籠立場跡、恩徳寺跡と恩徳寺坂を巡った。
駕籠立場跡には、1966(昭和41)年に伊那公民館沢渡分館が立てた案内がある。久保村さんは、「駕籠立場は社会科の勉強のためにも残さないといけない。駕籠立場を含む伊那街道千メートルは、原形をとどめるとても貴重な街道」と話した。
駕籠立場跡は、文化財候補として伊那市文化財審議会に申請されているという。 -
劇団メタボ公演、メタボレンジャー初登場

箕輪町の箕輪北小学校で6日、町内の元保健補導員らでつくる「劇団メタボ」(関奈保子会長)の寸劇の公演があった。劇中では町職員がげんき体操を広めるために生み出したキャラクター「メタボ撲滅もみじ戦隊メタボレンジャー」が出演。同キャラクターの初披露となった。
劇団メタボは、メタボリックシンドロームへの注意を促す内容を盛り込んだ劇を保育園や小学校で上映し、子どもたちへ生活習慣病予防を呼びかけている劇団。昨年6月に結成し、現在団員は14人が在籍している。
箕輪北小学校では昨年に続き2回目となる公演。前回は5、6年生のみだったが、今回は全校児童が劇を観賞した。
劇は小学生の「ケンちゃん」が、学校から帰ったらおやつをたくさん食べ、ゲームばかりしているという生活をしていたため体調を崩してしまうというストーリー。医者から野菜をしっかりと食べ、外に出て運動しないとメタボは治らないと言われ、「僕にできるかな」とつぶやくケンちゃん。児童たちから「できるー」と声援が飛んだ。
ケンちゃんを誘惑する悪魔が現れると、赤、青、緑のメタボレンジャーが登場。もみじのマークが入ったヘルメットをかぶり、体操服にバスタオルのマントを羽織ったメタボレンジャーに、児童は大喜び。メタボレンジャーは見事、悪魔を撃退し児童にメタボリックシンドロームにならないための「早寝早起き」「きちんと食事」「運動」の3つを教えた。 -
新山小6年生記念植樹 トンボの楽園で
伊那市富県の地域住民らでつくる「新山山野草等保護育成会」(中山智会長)は8日、新山小学校6年生と一緒に地元にあるトンボの楽園で、オオヤマザクラの記念植樹を行った。児童たちは、早く桜が花を咲かせることを願いながら苗木に土をかぶせていった。
地域での思い出をつくってあげたい竏窒ニ、5年ほど前から始まった記念植樹。同小6年生10人を対象に8人が参加した。苗木は高さ50センチほどで児童と担任教師ら計12本を用意。子どもたちは、植樹作業に参加できなかった仲間の分も丁寧に植えていった。
児童会長の橋爪栞奈さん(11)は「緑に囲まれたこの場所に、ピンク色の桜の花が鮮やかに咲くのがイメージできる。自分で植えた苗木を時々、見にきたい。今からわくわくする」と話していた。
また、この日は、世界最小といわれるハッチョウトンボの生息地「トンボの楽園」で会員ら約30人が草刈りなどの環境整備作業を行った。関係者によると、ハッチョウトンボの発生ピークは6月中旬縲・月下旬で、7月13日には恒例の観察会を開く予定だ。
小学校の思い出に桜の苗木を記念植樹する児童たち -
木下五郎彫鍛金展

日展会員の木下五郎さん=駒ヶ根市=による「SILVA MATER 森は母 木下五郎彫鍛金展」は15日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開いている。40点余もの作品を紹介する展覧会は約10年ぶりで、日展初入選以降、約20年間に制作した作品を展示している。
伊那食品工業創立50周年企画展。日展、日本現代工芸美術展出品作品が中心で、最も大きな作品は300号。最近制作した小品もある。
主に銅を使い、ステンレスやアルミ、真ちゅうなどを併用。色は銅の複雑なさびで表現している。「じわっと素材から出てくる天然の色なので、安らぎを与えてくれる。金属は工業的イメージがあると思うが、絵のように表現できるところを見てほしい」という。
今回は、伊那食品工業が建設した研究棟(R&Dセンター)に設置した「漲盈」(縦190センチ×横240センチ×厚さ10センチ)も発表。「大自然が健康であることが、そこに生存する生き物の健康につながる。地球も宇宙も健康でありたいというエネルギッシュなものを表現した」と話している。
午前9時縲恁゚後6時。入場無料。 -
伊那市の中央区救助支援隊が土のう作り

伊那市の中央区(横森孝心区長)の住民らでつくる中央区救助支援隊(高沢勝隊長)は8日、万一の水害に備えて土のう約300袋を作った。隊員や区の役員など約30人が同区公民館に集合。スコップやじょれんなどを使って砂を次々に袋に詰めた。作業は手際良く進み、予定よりも早く約1時間で終了した。
出来上がった土のうは同区公民館駐車場の一角に保管。緊急の際、トラックの荷台に素早く積み込めるよう、地面から一段高い場所にきちんと整頓して並べた。
横森区長は「災害は起きてほしくないが、備えは必要。土のうは数年前に作ったものがあったが、袋が傷んで砂が漏れるようになっていたので、今年新しく作ることにした。万一、河川のはん濫などの水害が起きた場合に被害を最小限に抑えるために役立てたい」と話した。
救助隊の活動は、3月に地震を想定した防災訓練を行ったのに続いて今年2回目。 -
【記者室】園児の元気パワー
老人ホームを訪れた保育園児たちが、手遊びや歌を元気いっぱいに披露した。園児の発表を見ていつも思うことは、そこまで…と感じるほどの一生懸命さだ▼声が出なくなるのでは-と心配になるくらい大きな声で歌い、踊りも精一杯に手を振り足を振り、その頑張りが伝わってくる。たまには、ちょっと休憩しているのかなという子も見受けられるが、全体としては、やはり子どもの元気パワーに圧倒される▼お年寄りは、子どもと一緒に手遊びしたり、歌声に拍手したり。園児の姿に涙する姿さえあった。純粋な子どもたちの歌声、計算ではない一生懸命さが、お年寄りの心に響くのだと思う。世代を超えた交流、施設訪問は、子どもたちの元気お届け便なのだろう。(村上裕子)
-
ミヤマシロチョウを保護
県の天然記念物に指定され、絶滅が危ぐされるミヤマシロチョウ保護のため、伊那市は6日、入笠山にメギの木の苗木100本を植樹した。地元の高遠、高遠北の2小学校4年生ら50人余が協力した。
ミヤマシロチョウの減少は、乱獲やメギの木の伐採が要因の一つに考えられることから、自然環境保全の学習を兼ね、ミヤマシロチョウの幼虫が葉を食べるメギの木を植えている。5年目の取り組み。
児童たちは面積600平方メートルの決められた場所に、とんがで穴を掘って肥料や水を与え、高さ30センチほどの苗木を植えた。
高遠小の伊藤朗君(9つ)は「僕の植えた木が一番大きくなって、ミヤマシロチョウが増えてくれたらいい」と話した。
植樹に先立ち、県自然観察インストラクター征矢哲雄さんが講話。「南アルプスにいるチョウは7種類。ミヤマシロチョウは霧ケ峰、入笠、鹿嶺高原でいっぱい見ることができたが、00年の入笠山調査では数匹を確認しただけ」と生態を交え、保護を促した。
ミヤマシロチョウは標高1800縲・500メートルに生息する高山チョウ。羽は白く、翅脈が黒色。羽化後、集団生活するのが特徴。征矢さんは「ゆくゆくは幼虫を放したい」と話した。 -
駒ケ根高原で杜の市開催

さまざまな人、モノと出会えるわくわくする空間を提供しよう竏窒ニ、全国からさまざまなクラフト作家らが集う「くらふてぃあ杜の市手作り工芸展in駒ケ根」が7、8日、駒ケ根市の駒ケ根高原菅野台、駒ケ池の特設会場で開かれている。木工、陶芸、ガラス工芸など、多彩な作品が並んだブースが軒を連ね、ここにしかない掘り出し物を買い求めようと訪れた来場者でにぎわっている=写真。
「杜の市」は例年、地元のクラフト作家らでつくる実行委員会(松本卓委員長)が企画し、開催しているもので、今年で12回目。出店者の半数以上は県外のクラフト作家が占めており、出店を希望する申し込みは年々増加傾向にあるという。
また、来場する側も普段の店ではなかなか見られないようなオリジナルのクラフトを目当てに地元以外訪れる人もおり、会場を訪れた人たちは各ブースを見て回り、「面白いものがたくさんあるね」などと話しながら楽しんでいた。
8日の開催時間は午前10時縲恁゚後5時。雨天決行。 -
水源祭で1年間の水の安全供給などを願う

6月の水道週間に合わせて市内の水道指定事業者21社でつくる駒ケ根市水道指定組合(山浦速夫組合長)は7日、「水源祭」を北原浄水場で開いた=写真。組合関係者や市職員などが集まり、この1年間の水の安全供給や安全などを願った。
水源祭は水の恵みに感謝するとともに水に関する災害や事故がないことを願い、毎年開催している。
例年は切石浄水場で開催していたが、現在同浄水場は更新のための建設工事中であるため、今年は切石浄水場にある水源碑を北原浄水場に移し、神事を行うこととなった。
神事に先立ち山浦組合長は「中国四川省の大地震では、想像を絶する被害に見舞われているが、私たちの地域でも同様の被害が起こりかねない。災害時、市民のライフラインである水道水を確保することが水道指定店の使命であり、今日は安心、安全を祈願したい」と語った。
駒ケ根市は現在、太田切川、箕輪ダムを水源として1日約1万2千トンの水を供給している。現在浄水場は市内3カ所にあるが、将来的には切石浄水場に一元化していく予定。 -
伊那フォーラム

伊那青年会議所(唐沢幸利理事長)は7日「2008伊那フォーラム 輝く夢」の1日目を伊那市の生涯学習センターいなっせで開いた。「輝く人が地域を元気にする」をテーマに、ベストセラー『てっぺんの朝礼』の著者で居酒屋チェーン「てっぺん」社長の大嶋啓介さんによる基調講演「夢をもてば人は輝く」と、NPO法人茨城県経営品質協議会代表理事、鬼沢慎人さんをコーディネーターとするパネルディスカッション「愛とやる気とチームワーク」が開かれた。
大嶋さんは店での朝礼で「できない」「だめだ」などのマイナスの言葉を使うと罰金を取るルールを10年間続けていると紹介し「人間の心や脳の働きは言葉、動作、表情で良くも悪くも変わる。何事にもプラス思考で取り組めば、夢は必ずかなう」と呼び掛けた。
8日は県伊那文化会館で「輝く企業が人をつくる」をテーマに基調講演とパネルディスカッションが行われる。講演はネッツトヨタ南国の会長、横田英毅さんの「人を輝かせる経営」。パネルディスカッションは「人と経営研究所」所長の大久保寛司さんをコーディネーターに、伊那食品工業会長の塚越寛さんら3人が「輝く人、輝く企業、そして地域が輝く」をテーマに論じる。 -
富県桜井の公園化事業整備 花壇作りなど
伊那市富県の桜井区でつくる「桜井郷づくり委員会」(広瀬明代表)は8日、区内にある観浄寺の休耕田で、花壇作りとサツマイモの苗植えをした。区民の交流を目的とした行事で7年目。園児からお年寄りまでの約80人が集まり、早朝から気持ちのよい汗を流していた。
同区で管理する観浄寺の公園化事業の一環で、花壇作りなどは同寺近くの休耕田約5アールで行った。花の苗はマリーゴールド、ヒマワリの計350本、サツマイモの苗は200本を用意。本年はジャーマンアイリス250本も加え、植え付けていった。
服が汚れるのも構わず作業する子どもたちの姿を大人たちは、優しく見守った。広瀬代表は「区民が交流する機会が減ってきているので、親ぼくのきっかけになればと始めた。毎年、多くの人が参加してくれているのでうれしい」と話していた。
休耕田は標高約750メートルの高台にある。花壇などは、区民が当番で水やりや、草取りなどの維持管理を行う。11月にはサツマイモを収穫し、焼きいも大会を開く予定だ。
花の苗を植えていく区内の子どもたち -
高遠長谷保育園年長交流会

伊那市の高遠長谷地区保育園の年長交流会が6日、高遠第1保育園であった。普段は別々の園で過ごす園児57人が、新しい友達と混合のグループでゲームやカレー会食を楽しんだ。
交流したのは高遠第1、第2・3、第4、長谷保育園の4園。年長交流は恒例行事で、本年度は4回計画し、季節によって各園を会場に、その地域ならではの体験なども取り入れて交流を深める。
この日は本年度第1回で、自己紹介で1人ずつ名前や好きな遊びを発表した。動物や乗り物のまねをするゲームなどで、初めて会った友達とも少しずつ慣れたあと、園庭に出て、自分の園にはない遊具に挑戦したり、砂場で川を作ったり、ままごとをしたり、皆夢中になって遊んでいた。
高遠長谷地域は、小学校でも高遠小、高遠北小、長谷小の3校交流があり、保育園での交流から小学校までの流れができ、いい連携ができているという。 -
上伊那華道会50周年記念いけばな展

上伊那華道会(春日セツ子会長)の50周年記念いけばな展が6日、伊那商工会館イベントホールで始まった。9日まで前期後期に分けて会員317人全員出瓶という華道展。50年の節目に思いを込めて生けた見事な作品に、来場者は関心を寄せ見入っている。
上伊那華道会は1958年に13流派87人で始まり、現在は13流派317人で構成する。
ササユリ、アジサイ、バラ、テッセン、ヒマワリ、タケノコ、ゼンマイなど、さまざまな花材がある。各流派によって異なる趣があり、それぞれの良さが味わえる。
「50年歩み続けてきた記念の行事。伝統文化の良さが忘れられてきているが、伝統を守る精神を感じ取ってもらいたい」と同会。諸流の先生との交流の場でもあり、会員が一堂に会して一つの目的のために生ける意義深い行事でもあるという。
会員は、教授者の資格を持つなど条件があり、各流派からの推薦で入会。例年の華道展では、会員が多いため出瓶は1年おきで、1回に半数を展示している。
記念華道展は前期7日まで、後期8縲・日。時間は午前10時開始、終了は7、9日午後5時、8日午後6時。 -
高遠町商店街で花のプランター設置
伊那市高遠町の中心商店街の活性化を目指し、住民らでつくる町商店街発展の会(米山祥一会長)と、高遠景観形成会(柳沢秀一会長)は6日、同商店街の街路にサフィニアの花の苗を植えたプランターを設置し始めた。作業は8日にもあり、2日間で約100人が参加する。
取り組みは「高遠・花の商店街づくり事業」で、市の08年度「地域づくり活動支援金事業」として採択された新規事業。2団体それぞれに50万円の支援金があり、両会ではカラマツ製のプランター(100個)とサフィニアの苗(200株)、肥料の費用に充てた。
プランターは、高遠町に本社工場を構える木工メーカー「ウッドレックス」に特注した、城下町の同商店街にあう茶色に色を塗ったカラマツ製を使用。花は長く楽しめるよう、花期時期が10月までの一年草、サフィニア(紫色、すみれ色の2色)に決めた。
この日は、両会員から50人の人手が出て、42個のプランターをメーン通りなどに飾った。景観形成会の柳沢会長は「お客さんに和んでもらえればうれしい。もう一度、高遠町に来てみたいと思ってもらえる町づくりを目指したい」と話していた。
高遠町の中心商店街に花のプランターを設置するメンバー -
「信州花街道のながたの丘にアサギマダラを呼ぶ夢追人」発足
箕輪町の西部地域住民による「西部花街道をつくる会」の会員有志らが、グループ「信州みのわ花街道のながたの丘にアサギマダラを呼ぶ夢追人」を結成した。日本本土から南西諸島などへ長距離を移動するチョウ「アサギマダラ」が好むフジバカマ(秋の七草の一つ)を近日中に、ながた荘周辺の林に植樹し、箕輪への飛来を期待する。
グループ発足のきっかけは、フジバカマを栽培している町内沢の唐沢英行さんから「西部花街道をつくる会」に、苗40株を提供するいう申し出があったことから。唐沢さんの畑にはアサギマダラが1匹、飛来したこともあるという。
仲介をした西部花街道をつくる会副会長で信州みのわ花街道推進協議会長の唐沢荘介さんは「このチョウが来るか来ないか、わからない。そんなロマンを求めて、子どもたちに夢を見てほしい」との思いから箕輪西小学校にも話を持ちかけた。同校も「ぜひお願いしたい」と趣旨に賛同。試みに参加することになり、学校敷地にフジバカマの苗を植える。
【解説】アサギマダラは日本全土から朝鮮半島、中国、台湾、ヒマラヤ山脈まで広く分布している大型のチョウ。夏に日本本土で見られ、秋になると南西諸島や台湾まで南下し、繁殖。子孫が春に北上し、日本本土に再び現れる。1500キロ以上移動した個体や、1日あたり200キロ以上の速さで移動した個体もある。 -
信州みのわ花街道推進協議会総会
箕輪町の企業や住民団体などでつくる信州みのわ花街道推進協議会は5日、箕輪町上古田の西部ふれあいサロン(西部診療所)で総会を開いた。協議会を構成する団体の代表者らが出席し、08年度の事業計画案や予算案を承認した。
同会は県道与地辰野線の6キロ区間を中心に、同線やその沿線地域を花桃や赤ソバなどで花満載の景観にする「信州みのわ花街道」を推進するために町内の12団体が集まり設立した。
今回、新しく「赤そばの里」を町の委託を受け管理している上古田地区住民有志による「古田の里 赤そばの会」(唐沢清光会長)が所属。
08年度の事業は▽花もも育樹事業▽花壇整備事業▽あんず育樹事業▽ヘブンリーブルー鑑賞提供事業▽先進地研修視察竏窒ネど。
また観光客などに向けて「信州みのわ花街道」の周辺の観光スポットなどを紹介する街道マップの作成の準備も始める。
信州みのわ花街道推進協議会所属団体は次のみなさん
◇西部花街道をつくる会、これからの農業林業を考えるEグループ、みのわ振興公社、信州伊那梅園、NPO法人伊那ハーレンバーレンパカパカ塾、箕輪西小学校、あんず生産組合、橋爪製作所、社会福祉法人サンビジョングレイスフル箕輪、北山ラベス、古田の里赤そばの会、長野県伊那建設事務所、箕輪町 -
悪質落書き、子どもたちの想いふみにじる

宮田村役場近くの国道153号を横切る地下歩道で5日朝、側壁にスプレー塗料で落書きされているのが見つかった。5月末にも同様の落書きがあり、管理する県は悪質と判断し6日、駒ケ根署に被害届を提出。落書きされた近くには、地元の宮田小学校児童が描いた絵なども飾ってあり、関係者は「子どもたちの想いもふみにじる行為」と憤っている。
5日に見つかった落書きは、先月28日と同じ赤色の塗料。稚拙な印象も強く、同一人物の可能性も高い。
地下歩道には2001(平成13)年度の宮田小卒業生が絵を飾り、以来快適に通行してほしいという願いは後輩の子どもたちにも受け継がれてきた。
絵などに落書きはされなかったが、県伊那建設事務所の竹村喜由管理係長は「このような行為に子どもたちも悲しむ。せっかくきれいにしようと取り組んでくれているのに」と絶句する。 -
伊那防火管理協会総会

伊那防火管理協会(唐沢可昭会長)は28日、08年度定期総会をJA上伊那本所で開き、08年度事業計画案などを承認した。伊那防火管理協会長表彰もあった。
第21回長野県危険物安全大会は6月13日、伊那市の高遠さくらホテルである。主な事業は危険物取扱者試験準備講習会、危険物取扱者試験、防火管理者取得講習会、第17回消火通報コンクール、小学生防火作品募集など。会員数は534事業所。
唐沢会長は、「いざ災害が発生してしまったときの初期対応が災害の大小を決める。防災体制の確立をもう一度考え、安全の確立を図ってほしい」とあいさつした。
伊那防火管理協会長表彰の受賞者9人を代表し扇屋石油の菊池健一さんは、「決意を新たに防火のためさらなる精進をする覚悟」と謝辞を述べた。
08年度表彰の関東甲信越地区危険物安全協会連合会長表彰、長野県危険物安全協会長表彰は、第21回長野県危険物安全大会で行われる予定。
表彰は次の通り(敬称略)。
◇関東甲信越地区危険物安全協会連合会長表彰(1事業所)=伊那食品工業
◇長野県危険物安全協会長表彰(1事業所)=コトブキ石油
◇長野県危険物安全協会長表彰(優良取扱者6人)=清水厚(上伊那農業協同組合)黒川雄二(伊那中央石油)村上通孝(村上石油)田中正樹、酒井文一(北山ラベス)堀内幸二(積水フィルム信州高遠工場)
◇伊那防火管理協会長表彰(優良者9人)=原一郎(上伊那農業協同組合)細田博(ミスズ工業箕輪工場)三上博史、河村奈緒(北山ラベス)池上稔(KOA箕輪工場)菊池健一(扇屋石油)久保村八朗、久保田哲朗、飯島弘樹(伊那燃料) -
蒼華会「手描き染め教室」作品展

伊那市御園の宮下梨花(久子)さんが主宰する蒼花会の「手描き染め教室」による作品展が1日から、みはらしの湯ロビーで始まった。30日まで、愛らしい花などを描いたTシャツやブラウスなどを展示している。
描いただけで簡単に染まる特殊染料を使った手描き染め。染料は赤、青、黄の3原色のみで、それを調合して色を出す。綿や絹、ポリエステルなど布であれば何にでも、塗り絵手法で簡単に描くことができる。
今回は、伊那教室と駒ヶ根教室の生徒10人が出品。Tシャツやブラウスのほかクッション、傘などもある。宮下さんの図案を基に応用してデザインを決め、独自の色で仕上げた作品で、カラー、アヤメ、スズラン、カトレア、ユリなどさまざま花が淡い色合いで描かれている。
宮下さんは、「素材と図案のマッチング、独自の色合いを見ていただきたい」と話している。作品希望者には展示会終了後に相談に応じる。 -
辰野ほたる祭り キャラバン隊によるPR
21日から始まる「第60回辰野ほたる祭り」に向け、同祭り実行委員会は5日、キャラバン隊によるPR活動を行った。隊を2つに分け、諏訪・伊那方面と塩尻・木曽方面の近隣計10市町村で周知。上伊那地方にはキャラバン隊が伊那市、箕輪町、南箕輪村を訪れた。
南箕輪村役場には、副町長の赤羽八洲男副大会長ら6人が訪れた。町によると、ホタルの名所・松尾峡で実施したゲンジボタルの上陸調査では過去最高の1万6千匹余を確認しており、赤羽副大会長は「ここ2、3年は発生数が少なかったが節目の今年は期待できそう」と笑顔で話した。
ホタルの発生は気象状況に左右されるが、20日ごろを発生ピークと予想。雨が降っていたり、気温が低かったりするとホタルの乱舞を見ることは難しく、月明かりがなく、蒸し暑く、風がない状態が好条件といわれている。時間帯は午後8時前後。
祭り初日は、JR飯田線辰野駅周辺で地元小学生の太鼓演奏や鼓笛隊パレードのほか、ちんどん屋や笠踊りなどのパフォーマンスを展開。祭り期間中の土、日曜日は松尾峡周辺の駐車場利用状況をホームページで情報提供する。祭りは29日まで。
南箕輪村役場を訪れたキャラバン隊のみなさんと村関係者 -
昭和伊南総合病院で赤ちゃん相談始まる

赤ちゃんの不安を解消してもらおう竏窒ニ、駒ケ根市の昭和伊南総合病院で5日、小児科外来の助産師・看護師による「赤ちゃん相談」が始まった。この日は他院で出産し、地元へ戻った伊南地区在住の母子4組が訪れ、授乳のことなどを助産師に相談した=写真。
産婦人科の常勤産科医師が不在となった同院では、お産の取り扱いができない状態が続いており、これまで産婦人科でしてきた産後のケアも十分できないでいた。そんな中、何かと心配ごとの多い出産後の赤ちゃんとお母さんに小児科外来を開放し、看護師や助産師が相談に応じる今回の試みを企画した。
この日、生後20日の赤ちゃんを連れて相談に訪れた駒ケ根市に住む34歳の母親は「急に母乳を飲んでくれなくなって相談にきた。親身になって話してくれ、ありがたかった。また何かあったら来たい」と話していた。
相談に当たった松尾睦助産師(48)=駒ケ根市中沢=は「産後は自分で運転することもできないし、遠くまで通うのも大変だと思う。いろんな所に窓口があれば、お母さんたちの不安も解消できると思い、今回の試みをみんなで考えた。相談が増えれば、日数や時間を増やしていきたい」と話していた。
相談会は毎週木曜の午後2時縲恁゚後3時。
問い合わせ・予約は昭和伊南病院(TEL82・2121)へ。 -
箕輪南小6年22人「セーフティーリーダー」に委嘱
伊那署は6日、子どもの防犯意識の向上を図るための施策「わが家のセーフティーリーダー」に、箕輪南小学校(北原文雄校長、100人)の6年生22人を委嘱した。全校児童が見守る中、篠田彦雄署長から委嘱証が入ったネックストラップを児童一人ひとりが受け取った。
篠田署長は「犯罪や交通事故について考えるための学校、家庭の代表として委嘱した。活動を通じ、仲間や兄弟の模範になってほしい」とあいさつ。児童代表の森川知生君は「非行や犯罪について話し合い、少しでも被害がなくなるようこれから役目を果たしたい」と誓った。
地域の非行防止、防犯活動などへの参加を促すため01年度から始まった事業で、委嘱は同署管内の小学校を毎年、指名している。これまでの学校では、通学路の危険箇所の確認や、「こどもを守る安心の家」への訪問、家族や下級生に対する防犯などの啓発活動竏窒ネどを行ってきた。
箕輪南小のほか伊那署管内では本年度、伊那市の高遠小6年生35人が委嘱を受けている。
篠田署長から委嘱証を受け取る児童ら -
美篶中央保育園が老人ホーム訪問

伊那市の美篶中央保育園(春日由美子園長)は5日、養護老人ホーム「みすず寮」と特別養護老人ホーム「みすず寮」を訪れ、園児42人が歌を披露するなどしてお年寄りと交流した。
ふれあいを通してつながりを持ち、お年寄りを大事にする気持ちを養うと同時に、お年寄りにも元気になってほしいとの願いを込め、毎年施設を訪問している。
老人ホームみすず寮では、広間に集まったお年寄りの前で、園児が「風はともだ」「さんぽ」などの歌を大きな声で元気いっぱいに歌った。ワニの手遊びを発表すると、見ていたお年寄りも一緒になって手を動かして楽しんだ。
最後に、園児が折り紙で作った朝顔のペンダントを一人ひとりがおじいさん、おばあさんにプレゼント。ペンダントを首にかけ「お元気で」と声をかけると、うれしそうに「ありがとう」と答え、涙ぐんで握手するおばあさんもいた。
同園は、年2回の訪問を計画し、2回目は秋ころを予定する。 -
高遠さくらホテルで特製ランチ始める
伊那市高遠町にある市観光株式会社「高遠さくらホテル」内レストランは14日から、バラをイメージした特製ランチのコースメニューを始める。7月21日までの期間限定で、期間中はランチと同施設の「ばら風呂」のイベントで利用客を持て成す。
イベントは、本年初の市などが主催する「高遠しんわの丘ローズガーデン」バラ祭りに合わせた企画で、施設の総支配人で料理長の丸山拓さんがメニューを考案。内容は「スモークサーモンのバラ飾り縲怎Tラダ仕立て縲怐v「春キャベツと野菜のスープ縲怎oジル風味縲怐vなど6品で2千円となる。
バラの庭園をイメージしたという、前菜のサラダは、ライスペーパーと食用バラを加え彩り鮮やか。食用バラはデザートのクレープにも入っている。メーンは魚料理と肉料理のどちらかで、「牛『バラ』の煮込み玉野菜添え」は、仕込みに1週間を掛けた濃高なソースが特徴となる自信作だ。
ランチの注文は前日予約が原則。バラの花びらを飾った露天風呂の入浴とのセットは2500円となる。問い合わせは、高遠さくらホテル(TEL94・2200)へ。
バラ祭りに合わせた期間限定の特製ランチ -
自治体消防制度60周年記念長野県大会で箕輪町消防団表彰

5月30日に長野市で開かれた自治体消防制度60周年記念長野県大会で箕輪町消防団が表彰された。4日、平沢久一団長と小松孝寿副団長が箕輪町役場を訪れ平沢豊満町長に報告した。
表彰は06年7月の豪雨災害時の団の活躍に対する水防功労で、村井仁長野県知事から表彰状が贈られた。
平沢団長は「これから梅雨の時期を迎えるので気を引き締めていきたい」と話していた。 -
【日韓親善伊那谷の会運営委員長 鄭康雄(てい・やすお)さん】
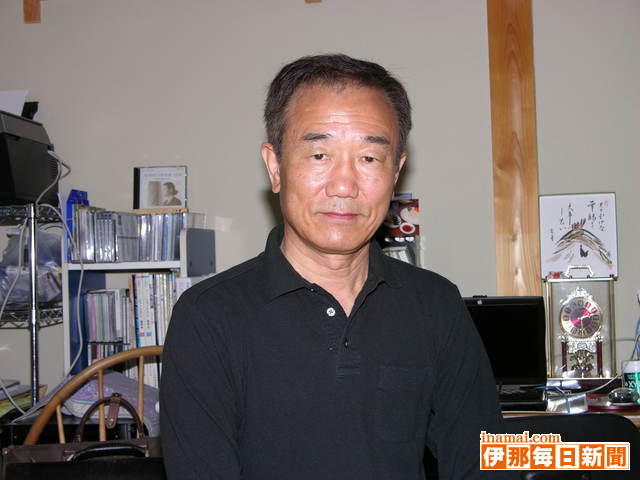
・ス今来人・ス(いまきびと・いまきのひと)は古代、大陸から渡来した人たちを指す語。
「彼らは文化や技術を持って日本にやって来た。私も現代の今来人でありたい」
◇ ◇
大阪で生まれ、5歳まで日本で暮らしたが、当時の記憶はほとんどない。早稲田大での留学を終えた父とともに韓国に移り、高校卒業までを過ごした。父と同じく日本で学ぼうと18歳で来日したが、経済的な事情などから大学入学は果たせず。韓国大使館の広報官として働く一方、力道山門下でプロボクサーとして数年間を過ごした。その後韓国の新聞の記者に。
「それまで自身では特に差別などを感じたことはなかったが、記者になったことで在日韓国人の体験や思いなどを知り、いろいろな問題に目を向けるようになった」
その偏見や差別を痛切に思い知ることになったのは結婚後。子どもが小中学校でひどいいじめに遭ったのだ。暴力的ないじめが繰り返され、ついには殴られて目を傷めたために手術する事態にまでなった。
「子ども同士のけんかということにしてその場は収めたが、あの時は本当につらかった。日本は韓国に対してひどいことをしてきた歴史的な経緯もあるというのに、さらにこんな仕打ちをする日本への反感が高まった」
そのころ、伊那で戦争展が開催された。その中で、戦争に反対して投獄され、死んだ人が伊那にもいたことを知り、ショックを受けた。
「日本は国民みんなの意志で戦争をしたと思い込んでいたのに、そうではないと初めて知った。この事実は韓国にも知らせる必要があると思いました」
90年、アニメ映画『キムの十字架』の上映実行委員会として発足した日韓親善伊那谷の会(キムの会)に中心的に参画。両国の相互理解と親善のための活動を始めた。当初は日本人のみならず、韓国人からも冷ややかな目で見られた。「面子やプライドはないのか」と後ろ指を指されたりもした。
「そんなことを言われたら立つ瀬がない。しかし、過ぎ去ったことをいつまでも言っていても仕方がないでしょう。両国は地理的にも近いし、民族としても同じで切っても切れない関係にある。過去は過去。歴史を教訓として、将来に向けて考えることが大切。両国の関係を改善するためには、間に入って中和する人も必要だと考えてやってきました」
その後の18年で国民感情はずいぶん変わった。日韓ワールドカップもあり、日本ではヨン様をはじめとする韓流ブームも起きた。
「今は差別の例はほとんど聞かない。本当に良かった」
◇ ◇
韓国は祖国だが、これから韓国で暮らそうとは考えていない。生まれた国である、この日本で生きていくと腹を決めている。
「自分に質問したんです。民族とは何か。国家とは、国民とは竏秩B結論は、私は私だということ。人間は一人では生きていけない。だから集まって社会をつくって生きる。その中で一番大事なのは家族です。家族が住むこの伊那谷が大事、この日本が大事。だから今住んでいるここが故郷なんです。その意味では国家というものはあまり意味がない。たまたま日本に住んでいるというだけのこと。この大事な故郷をもっと住み良い所にするための一環としてキムの会もある。その一員として、これからも自分がやれることを精いっぱいやっていきたい」
(白鳥文男) -
駒ケ根山岳会が池山清掃登山を開催

本格的な夏山シーズンを前に、中央アルプス池山で1日、駒ケ根山岳会(林文博会長)が主催する「池山清掃登山」があった。同会のメンバーや駒ケ根市内の家族連れなど25人が集まり、初夏の池山を楽しみながらごみを拾いに励んだ=写真。
登山清掃は長野県勤労者山岳連盟がこの時期県下一斉に開催している取り組み。同連盟に所属する駒ケ根山岳会では、36年前から池山清掃登山を開催してきた。近年は遠方から引っ越してきた人などが参加するケースも多く、この日、今回家族で参加した松崎孝子さんは「昨年、子どもたちに山を体験させてあげたいと参加して、良かった。今年も山を楽しみたい」と話していた。
林会長(60)=南割=は「池山も毎年いろんな形で変化している。ごみを拾うことが山の動植物の育成にもつながる。今日参加してくれた子どもたちが、今後も池山を守り続けてくれれば」と話していた。
最近は登山者のマナー向上に伴ない、登山道のごみは減ってきている一方、車が山の中腹まで入り込めるようになったことに伴ない、林道などにごみを捨てる人が増えているという。
22/(月)
