-
大田切区ソフトバレー
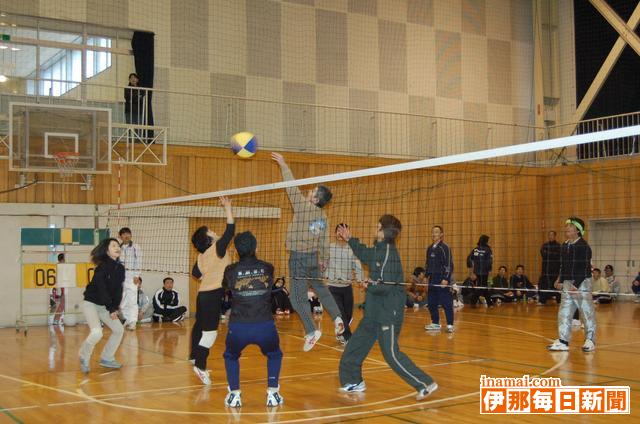
宮田村大田切区の班対抗親ぼくソフトボール大会は12日、農業者トレーニングセンターで開かれた。
20代から高齢者まで幅広い年代層の約百人が参加。8班が親ぼくを深めながら、班の団結を強めた。
結果は次の通り
▽優勝=5班(2)4班(3)2班、6班 -
天竜川渇水対策支部の解散
天竜川上流河川事務所は14日、少雨に伴う渇水を警戒して設置していた天竜川渇水対策支部を解散した。
同事務所は、先月14日から情報収集や節水の呼びかけを行う支部を設置してきた。
しかし、2月後半から断続的な降雨が続いており、2月は平年の約1・5倍の降雨量を観測。天竜川の流量も回復し、今後しばらくは流量が危機的な状況にならない程度までの回復があったため、支部の解散に至った。 -
みはらしの湯で伊那市、高遠町、長谷村の名所写真を展示

伊那市、高遠町、長谷村の合併まで2週間余り。伊那市西箕輪の日帰り温泉施設「みはらしの湯」は、3市町村の歴史や文化、自然などをとらえた写真50点を、ギャラリーに展示している=写真。
3月31日には新伊那市が誕生するが、合併する他市町村の代表的な文化や名所を知らない人もいることから「今後、足を運ぶときのの参考にしてもらおう」と今回の写真展を企画した。
写真の提供はそれぞれの市町村に依頼。高遠町のコヒガン桜や長谷村の中尾歌舞伎など、各市町村のさまざまな写真を見た入浴客からは「こんなところもあるんだね」などと話す声も聞こえてくるという。
唐澤壽男支配人は「地元の人には自分の地域の名所を改めて見直してもらえれば」と話していた。
31日まで。 -
わんぱくスクール活動のまとめ

飯島町社会福祉協議会のわくぱくスクールは12日、今年度の日程を終了し、うどん打ちなどして活動をまとめた。
文化館で行った最終回のスクールには、22人が参加し、堀越康寛さんを講師に手打ちうどんづくりをした。
中力粉に水を混ぜ、力を込めて、よくこねた。しっかりこねた生地を足で踏んで、うどんのこしを出した。
薄く伸ばして、4-5ミリの幅に切りそろえ、ゆでて、出来上がり。
参加者はゆでたてのうどんを口に運びながら、1年間の活動を振り返った。
わんぱくスクールは学校週5日制実施に合わせ、03年から始めた事業。今年度は2歳縲恟ャ学生6年生30人余が参加。5月開校し全11回開催。
ホタル観察や手話の練習、農業体験、たこづくりなどを多彩なカリキュラムで体験学習をした。 -
東中3年生を送る会

今週末に卒業式を迎える3年生に残り少ない中学校生活の思い出を贈ろうと駒ケ根市の東中学校で生徒会主催の3年生を送る会が開かれた。生徒会役員と1・2年生らが感謝と激励の気持ちを込めてそれぞれ歌や発表などを披露し、3年生の卒業を祝いながらも迫った別れを惜しんだ。3年生と向かい合った在校生らが全員で『喜びの歌』など、思い出の歌を思いを込めて合唱した=写真。誘われるように一緒に歌い出した3年生の中には感極まってあふれる涙を何度もぬぐう女子生徒の姿も見られた。
生徒会役員らは3年生へに対して行ったアンケートの結果をプロジェクターで発表。星座や血液型、好きな給食などについてグラフで示しながらユーモアたっぷりに紹介した。1・2年生はダンスや漫才を交えた呼び掛けをしたり、歌を歌ったりして先輩たちへの感謝の気持ちを表した。
同校の卒業式は17日に行われる。 -
バスケットチーム全国大会出場

赤穂高校OBらが中心になって6年前に結成された男子バスケットボールチーム「すずらんクラブ」(松崎吉文監督、16人)は1月に行われた県予選大会に優勝し「第32回全日本クラブバスケットボール選手権大会」(3月18縲・0日、長野市)への初出場を決めた。13日夜、松崎監督のほか、駒ケ根市在住の野口輝幸さん=北割一区、上野平二さん=北割一区=の2選手が市保健センターを訪れ、中原稲雄教育長らの激励を受けた=写真。松崎監督は「練習は週2回だけしかできないが、初めての全国大会なので一生懸命やって良い成績を挙げたい。市民の期待に応えられるよう頑張る」、野口さんは「良いプレーをしたい。まず1勝が目標」上野さんは「悔いの残らないよう頑張りたい」とそれぞれ決意を述べた。
同チームは結成直後から県大会で優勝するなど強豪として知られる。平均身長は170センチ台と上位チームの中では低い方だが、スピードと技を生かしたチームワークには自信を持っている。 -
差損額は約3億9千万円
開会中の駒ケ根市議会3月定例会で14日、一般質問が行われた。2日の議会全員協議会で示された駒ケ根市土地開発公社の第2次経営健全化計画に関連して、公社が保有する土地の簿価と時価の差額について共産党の大沼邦彦議員が質問したのに対し中原正純市長は「05年度末に公社が保有するすべての土地(簿価48億4200万円)が処分できたと仮定した場合の簿価と時価の差額は約3億9千万円」と答弁し、売却に伴って大幅な差損が想定されることを明らかにした。第2次経営健全化計画では06年度から10年度に生じる売却損の2分の1は市が補助するとしていることなどから大沼議員が「このような事態を招いて市長としての責任をどう取るつもりか」と重ねて答弁を求めたのに対し中原市長は「資産価値の下落は全国的なもの。まちづくりにとって今後も重要な役割を果たす公社の運営に市長として全力を尽くすことが使命と考える」と述べ、引き続き健全化に向けて努力していきたいとする姿勢を示した。
新風会の塩澤崇議員が有害図書の自動販売機設置問題に関連して青少年健全育成条例の制定に対する考えをただしたのに対し中原市長は「市単独での制定より県全体での取り組みが必要」として、市としては条例制定は行わず、県に働きかけていきたいとする方針を示した。 -
本郷地区伊南バイパス沿道景観形成等住民協定調印

伊南バイパス本郷地区住民らが工事着工を前に、無秩序な開発を抑制し、自然豊かな田園風景と地域環境、優良農地の保全を目的に「本郷地区伊南バイパス沿道景観形成・土地利用住民協定」の調印式が13日夜、本郷公民館であった=写真。協定者20人が出席し、協定書の内容を最終確認し、それぞれ調印した。
調印に先立ち、本郷地区対策委員会の中村満夫委員長が「地域の景観を守り、優良農地の保全に向け、昨年9月、委員会を立ち上げ、協定の準備を進めてきた」と経過に触れ「対象者の総意で協定が締結されるように」とあいさつ。
協定区域は南は本郷ふるさと農道・国道交差点、北は与田切橋南までの約680メートル、バイパス敷地から両サイド60メートル以内で、面積約6・88ヘクタール、協定者は協定区域内の土地所有者と建築物の所有者、並びに賃借人で対象者は107筆、33人。
土地利用基準は建築物、屋外広告、自販機、土木構造物などそれぞれに基準を設けた。具体的には▽建物は高さ12メートル以内、容積率百%以内、建ぺい率60%以内▽野立て看板は原則禁止▽自販機は景観、環境を阻害するような物品の販売機は設置しない-など。
今後のスケジュールは近日中に、県に「景観形成住民協定認定申請」を行う。 -
3年生を感謝して送り出す

中川中学校生徒会は13日、体育館で3年生を送る会を開き、1、2年生が心を込めたメッセージや歌のプレゼントで、旅立つ3年生に感謝の気持ちを伝えた。
在校生の拍手の中、入場した3年生79人を前に、安富穂澄会長は「在校生はいろいろとお世話になった3年生に、感謝の気持ちを込めて発表しよう。3年生の最後の思い出になるように良い会にしよう」とあいさつ。
役員会企画ではスライドで、1年の宿泊学習、2年の西駒登山、3年の修学旅行、文化祭などを振り返り「まぶしすぎるほど、輝いていた3年生。それぞれの道を歩むことになるが、壁にぶつかることがあっても、中川中の輝いていた3年間をほこりに自分の道を歩んで」と呼び掛けた。
続いて、3学年の担任教諭らが「太鼓を通じて、密度の濃い時間が持てた」「いろいろやってくれたオレのクラスらしいクラス」「自分のことを二の次にし、他人のために頑張れた」と3年間の生徒の姿を振り返り「卒業おめでとう」と祝福した。
学年発表では1年生は「学校をよくしようとする姿、忘れません。自分たちの夢をかなえてください」とメッセージを伝え、歌「旅立ちの朝」をプレゼントした。
2年生は生徒会活動での3年生の頑張りに触れ、校歌を歌って、門出の3年生を激励した。
在校生の温かい贈り物に感激した3年生は堂々と「流れゆく雲を見つめて」を体育館いっぱいに響かせ、別れと門出の歌にした。 -
職員の地区担当制の機能強化を村長答弁
宮田村の清水靖夫村長は14日の村議会一般質問で、「機能していない」と指摘が挙がっている職員の地区担当制について答弁。「今後は地区に密着し、抱えている問題や住民の要望など、入り込んで情報収集する」と説明した。
担当制は住民と行政の協働の柱として、昨年度に導入。しかし、役割が不明瞭で、現状では多くの区が活用に苦慮している。
また英語指導助手(AET)設置の考えについて聞かれた新井洋一教育長は、宮田中学校に早期に配置したいと説明。
児童、生徒の学力意欲向上にむけた私案として、小、中学校の教師を入れ替える特別授業なども検討したい考えを示した。 -
【記者室】駒ケ根を想うブログ
インターネットをのぞいていたら市民が駒ケ根の市政を論じているブログが目に留まった。いったいどこで情報を仕入れているのか分からないが、相当深くにまで踏み込んだ鋭い指摘が多数あって感心させられる▼ブログ(ウェブ・ログ)とはインターネットを利用した日記風のホームページのこと。自身の考えを居ながらにして瞬時に世界に向けて発信できる。もちろん読む人がいなければ自己満足で終わってしまうが、このブログは読んだ人からの書き込みも多く、一方通行で終わっていない▼批判を向けられる市の当事者にとっては耳の痛い話も多かろうが、市政について真剣に考える市民の貴重な意見として、ここは真摯(しんし)に耳を傾ける必要があるだろう。(白鳥記者)
-
箕輪町議会一般質問
箕輪町は06年度、文部科学省に町職員1人を派遣する。これまで県、市町村の職員交流はしているが、国への派遣は初。
平沢豊満町長が13、14日の町議会3月定例会一般質問で、職場外研修についての唐沢荘介議員、浦野政男議員の質問に答えた。
派遣で期待することは、「中央省庁のほうが理論的なアプローチは上手。論理的な考え方、物の見方を身につけてもらう」とした。派遣期間は4月1日から1年間。
人事院から今年採用の新人研修で自治体研修の申し入れがあり、町が6月ころに3人程度受け入れる予定も示した。
市町村の派遣は06年度は町から辰野町に派遣し、南箕輪村からの派遣を受け入れる。「できるだけ幅広く研修に出す」との考えで、海外研修も継続し、民間の外部主催の研修にも職員を出す方針。 -
手紙作文コンクで南箕輪中3年生2人が入賞
日本郵政公社が主催する第38回手紙作文コンクールの手紙・作文部門で、南箕輪中学校3年の有賀美陶さん(15)が信越支社長賞、木本遥香さん(15)が佳作を受賞した。14日、南箕輪郵便局の大沼悟局長が同校を訪れ伝達した。
コンクールは昨夏に、全国の小中学生から公募し、同部門には1万8700人が応募。有賀さんは「尊敬すべき母さんへ」と題し、母親に向けた感謝の気持ちや普段言葉にできない思いをつづり、木本さんは「あの日の君へ」とし、2年ほど前に「母親が猫に食べられてしまうと拾ってきた」(木本さん)スズメのひなと過ごした3日間を振り返った。
大沼局長は「手紙文化が薄らいできている」なかでの受賞をたたえ、賞状のほかに有賀さんにはトロフィ、木本さんには盾を手渡した。普段手紙や作文を書くことが少ないという2人は「ただ驚いた」としながらも、喜びをかみしめていた。 -
箕輪東小学校1年ゆめっこ組

元気いっぱいに歌い、踊り、演奏し、オペレッタを熱演した箕輪町の箕輪東小学校1年ゆめっこ組(31人、松崎まさえ教諭)。1年間の学習のまとめとして挑戦したオペレッタの公演は、大きな拍手とともに大成功のうちに幕を閉じた。
生活科で取り組んだ蚕の飼育学習に加え、日常の中で大きな声で話す、語りや暗唱、合奏、音楽の時間のほかに朝と帰りの学級の時間に歌うなど、「自分を表現しよう」と学習してきた。学びの集大成として取り組んだオペレッタ。辰野町の「第6回オペレッタフェスティバル・イン・たつの」(2月5日、辰野町民会館)の出演を目標に、昨年11月末から活動が始まった。
絵本が大好きなゆめっこ組。オペレッタの題材は絵本から選び、公演が冬という季節も考えて「てぶくろ」を選んだ。台本、せりふ、動きを皆で考え、おじいさん、イヌ、ネズミ、ウサギ、カエル、クマなど配役も自分たちで決めた。
ネズミのせりふをどうするか、どのように動いたらいいか、ポーズは…。役になった児童が考え、友達に見てもらう。「ウサギに見えないよ」「クマはもっとこんな感じ…」と、試行錯誤を繰り返した。劇中歌は、これまでに習った曲を替え歌にし、楽器演奏を入れた。体を動かして歌うことが好きなので、皆で振り付けも加えた。
舞台の背景は学校長に描いてもらった絵にゆめっこ組が色を塗り、雪だるまのセットは皆で作った。こうしてゆめっこ組のオリジナル作品が完成した。
オペレッタの練習は待ち遠しく、「何回やっても楽しい」時間。家でも歌の練習に励んだ。特にお風呂の中はオン・ステージで、歌い、友達の役の分もすべてせりふを言い、お母さんに公演の流れを見せてあげる児童。「毎日、ゆだってしまう」。そんな保護者の声があったほど、オペレッタに夢中だった。
フェスティバル当日、松崎教諭お手製の衣装に身を包み、大舞台でライトを浴び、大勢の観客を前に熱演した。ビデオやカメラで撮影され、「俳優さんになった気分」。緊張していた松崎教諭をよそに、ゆめっこ組は「楽しかった」「気分がよかった」と大満足だった。
オペレッタフェスティバルの出演をきっかけに、保育園から公演依頼があり3月、東小体育館で2回目のステージにも立った。
「自分で成長を確信させたい」。オペレッタには松崎教諭の願いがあった。「大きな声で発表して、これまでつけてきた力ができるようになった。一人ひとりが充実感を味わって大切なことを学び、見違えるほど大きく成長した。お陰です」。
オペレッタの練習を通して一歩一歩成長したゆめっこ組。演技を互いに評価し合ってきたことで、普段の生活の中でも「○○ちゃん、すごかったね」と友の良さを認めたり、助け合う姿が自然に見られるようになってきた。表情が豊かになり、皆の前でハキハキと話せるようにもなった。
「次は何やる?」
ゆめっこ組の心に新たな夢が大きく膨らんでいる。
(村上裕子) -
南箕輪中3年生が卒業前にスクールバス清掃

卒業間近の南箕輪中学校の3年生が14日、感謝の気持ちを込めて3年間利用したスクールバス3台を掃除した。
学びやへの奉仕活動として、生徒たちが事前に挙げた清掃場所を分担。バスの掃除はその一環で、利用者を中心に10人余が担当した。活動は毎年恒例だが、バスの掃除は初めてという。
スクールバス(29人乗り)は、村が伊那広域シルバー人材センターに委託し、南原と沢尻、神子柴の一部に在住する生徒を対象に、1日4便を運行。3年生は148人のうち24人が利用している。
生徒たちは約1時間にわたって、寒さでかじかむ手を擦りながら、雑巾やモップを使い、高い場所は脚立に上ったりして、バスの内外を隅々まできれいにした。
バスを利用している田島郁美さん(15)は「毎日乗せてもらっているから、最後にこういった形で恩返しさせてもらえてよかった」と話していた。 -
園芸福祉学ぶ アルプスバラ会1周年で講演会

バラを育てる上・下伊那の愛好者でつくる「アルプスバラ会」(春日千定会長)はこのほど、設立1周年を記念した公演会を伊那市のJA上伊那フラワーパレスで開いた。元信州大学教授で県園芸福祉研究会長の藤田政良さんが園芸活動の効用と福祉について話した=写真。
会員や一般住民など約50人が集まり、藤田さんが「ガーデニングと園芸福祉」と題した話しを聴講。園芸については「人間と植物の関わり。手をかけ、世話をすることで自分も癒される」と説明し、高齢者が園芸作業で元気を回復した事例を映像など交えて紹介した。
藤田さんはガーデニングテクニックを会員らに助言。類似色や反対色での配色や同一植物での組み合わせがある竏窒ニ実際の庭の映像を見せながら話し「自分の洋服を選ぶのと同じ感覚で考えるとよい」と述べた。
講演会後の総会では世界バラ会議への参加、バラ作り技術講習会の開催、研修日帰り旅行などの来年度事業計画を承認した。 -
長谷村 ボランティア連絡協が総会

長谷村のボランティア連絡協議会の年一回の総会が12日、村保養センター「仙流荘」であった=写真。今年度事業の報告のほか、正副会長の選出があり、伊那市・高遠町との合併による3市町村の社会福祉協議会合併(10月)までの任期として、加藤二葉会長と伊藤博子副会長が再任した。
村内のボランティアグループ9つなどから約70人が参加。加藤会長はメンバーの一年間の功労に感謝。上伊那ブロックボランティア研修会で災害ボランティアの立ち上げ訓練に参加した教訓として「村にいつ災害が発生するか分からないので、日ごろから心がけて」と呼びかけた。
各ボランティアグループの代表が公園の除草作業、花壇づくり、トイレ清掃などの今年度の活動内容の報告、来年度事業の計画などを話し合った後、メンバー同士の交流を深めるためレクリエーションもあった。 -
親子で力合わせておやき・五平もち作る

信州名物のおやきと五平もちの料理教室が12日、町福祉センター「やますそ」であった。園児縲恷剴カの8人や保護者ら約20人が協力して調理した。文部科学省推進の地域子ども教室事業「遊びの寺子屋」を高遠町で展開する運営委員会(丸山宏一委員長)主催。
五平もちは丸い形に成形したご飯の固まりを串に刺して調理。串は壊れた唐傘の骨を使う伊那谷に古くから伝わる方法で実施したため、子どもたちや保護者ら目を丸くして驚きの様子だった。
おやきにはナスや菜っ葉、キムチなどを包んで料理した。参加者らは生地を練り上げる、力を必要とする作業に一苦労。高遠小学校3年の伊藤七海ちゃんは「皆で力を合わせておいしいおやきを食べたい」と、生地づくりにも力が入っていた。
遊びの寺子屋は児童たちの放課後の遊びを支援するため、高遠小学校校庭で週一回のレクリエーションをしているほか、毎月1、2回の親子で楽しめるイベントを企画。今年度は手作り楽器やキノコ狩り、もちつき大会などに参加者らが挑戦してきた。 -
高遠町の弥勒を語る会・景観整備

高遠町弥勒の歴史学習や環境美化活動に取り組む住民の集まり「弥勒を語る会(弥勒塾)」は12日、弥勒諏訪社周辺の景観整備をした=写真。約30人の会員が早朝から集まり、やぶ掃除やヒノキの枝打ちなどの作業に汗をかいた。
御神木の周りに植林した木の枝などが伸び、風通しが悪く、日光も行き届かなくなっているのを解消するために以前から計画。伊那市・長谷村との合併記念事業で町が進める環境美化活動に合わせて今回実施した。
この日は小雨が降り、風も強く吹きつける悪天候。急斜面に生える雑草や竹を除去したり、はしごを使って高い位置の枝枝打ちをするなどの作業はただでさえ危険な仕事だったが、一人ひとりが無理をせず、皆の力を合わせて一つの目標に取り組んだ。
伊藤啓仁会長(69)は「先祖が残してくれた地域のことを自分たちが振り返るように、子どもたちが大きくなったときに振り返ってもらえるような活動したい」と話していた。
弥勒を語る会は昨年2月に有志らで発足し、毎月一回の勉強会で弥勒の歴史を学んできた。今後は地域防災をテーマにした学習や、弥勒諏訪社周辺にモミジを植林しようと考えている。 -
伊那北小で「安全見守り隊」発足

伊那市の伊那北小学校よりよい教育環境協議会は14日、児童の登下校の通学路を巡視する「地域・子どもの安全見守り隊」の発足会を同校で開いた。地域のお年よりなど約50人の地域住民が集まり、児童の安全を守ることを決意した。
同見守り隊は、子どもたちの通学路の安全を確保するため、地域ボランティア約80人で結成。メンバーらは児童の登下校時に合わせて通学路に立って見守る。
今回の同協議会の呼びかけに賛同した隊員のなかには積極的に「子どもを守る安心の家」に登録。発足前の8件から発足後は46件に増加した。
発足会で同協議会の萩原昇吾会長は「発足したからといって完全に犯罪がなくなる保証はない。つねに自分たちの安全は自分たちで守ることを心がけて」と注意を促しあいさつとした。 -
やまびこ会がシメジを使った菓子を研究
伊那市の菓子店有志でつくる「やまびこ会」(橋都喜三郎会長、9人)は13日夜、市内でシメジを使った創作菓子を持ち寄った。メンバーがおこわまんじゅうなど4品を提案、改良を加えながら商品化する。
会は、地元産の米や農産物などを使った創作菓子を開発し、将来的に「地域ブランド」として売り込もうと、50代を中心に組織。
試作品は、おこわまんじゅう、おやき、パン2種類の4品。洋菓子はシメジをマヨネーズで混ぜたり、パンの上にチーズと一緒に乗せたが、和菓子の場合はシメジの水分が出たり、食感を残したりするのが難しいという。
試食したメンバーは、具の味付けや歯ごたえ、皮のふっくら感など熱心に意見交換。これまで職人の技術は門外不出だったが、酒を飲みながら、和・洋がアイデアを出し合い、商品開発への思いを熱く語った。
メンバーの一人は19日、春の高校駅伝に合わせ、駅前再開発ビル「いなっせ」で開く屋台横丁でおこわまんじゅうとおやきを販売する。 -
小さな親切運動上伊那支部車いすを贈呈

小さな親切運動上伊那支部は13日、設立10周年を記念して伊那市社会福祉協議会に車いす2台を寄贈した=写真。
あいさつをすること、困っている人がいたら手伝ってあげる竏窒ネど、小さな親切を進めることで青少年の豊かな心を育成することを目指す「小さな親切運動」は、約40年前にはじまり、全国展開されている。
その上伊那支部(会員99人、山田益支部長)は、設立10周年を迎えたため、記念事業を計画。会員から集めた会費で、上伊那地区10社協に総数12台の車いすを寄贈し、上伊那37小学校と各教育委員会に2種類のオリジナル紙芝居を寄贈することにした。
車いすを受け取った御子柴龍一会長は「長期高齢者社会を迎え車いすの需要も増えている。学校の授業の中で使われることもあり、各方面で利用させてもらいたい」と感謝の言葉を述べた。
これで上伊那支部は全25台の車いすを寄贈したことになる。 -
キジの放鳥

上伊那猟友会(田辺一清会長)は14日、箕輪町の萱野高原でキジ60羽(オス30羽、メス30羽)を放鳥した。
駆除・増殖を通してに鳥獣数を管理している同会は、個体数維持を目的としてキジの放鳥を例年管内でしている。本年度は箕輪町で行うことになり、町猟友会(小林弘人会長)のメンバーや鳥獣保護員、箕輪南小学校の3、4年生34人などが参加した。
小林会長は、雌雄の違いや特徴を児童に話し「オスは獲ってもいいがメスは獲ってはいけないことになっている。メスはたくさんヒナを育てるように放す」と語った。
児童らは、会員などと一緒に放鳥。力強いキジに戸惑いながらも「きれい」「かわいい」と話しながら飛び立つ姿を見送った。
オスには足缶が付いており、狩猟したときに生息範囲が把握できるようになっている。萱野高原は禁猟区で、高原内での狩猟はできない。 -
JC小中高生との交流会

子どもたちとの間にある壁を取り除こう竏窒ニ13日、伊那青年会議所(伊那JC)の青少年委員会(唐澤幸恵委員長)は、小中高生との交流会をした=写真。11歳から40歳までの参加者が、日ごろ考えていることや感じていることなどを話し合いながら親ぼくを深めた。
青少年育成事業としてウミガメの放流体験を通じた活動に取り組んでいる同委員会だが、一緒に活動していく子どもたちとの間に「見えない壁」があると感じ、お互いのことを分かり合うきっかけとして交流会を企画。これまでJCの活動に参加した小学生から高校生までに声がけしたところ、25人が集まった。JCからは約20人が参加。
話し合いのテーマは「学校は面白いか」「家族との関係はどうか」などさまざま。「バレンタインチョコをもらったことはあるか」と質問されたり「父親ととても仲が良い」と話す女子高生などに、JCメンバーの方が戸惑っている様子だった。
同委員会は4月3日縲・8日に、ウミガメ放流体験会の小学生リーダーとして活動する参加者を募集し、体験会のプランや事前交流会などを一緒に計画していきたいとしている。
問い合わせは伊那JC事務局(TEL78・2328)青少年委員会へ。 -
「とんぼの楽園」パンフレットできる
伊那市は、新山に生息するトンボを紹介したパンフレット「とんぼの楽園」を5万7千部作った。日本一小さいといわれるハッチョウトンボの全国有数の生息地で「自然豊かな地域を知ってほしい」と活用を促している。
調査は昨年、日本蜻蛉(とんぼ)学会会長の枝重夫さん=松本市=に依頼。その結果から、準絶滅危ぐ種のモートンイトトンボ、希少種のヒメアカネ、ネキトンボなど29種類を確認した。
パンフレットはA3判の二ツ折。費用は30万円。トンボ図鑑のほか、トンボの目録、トンボの一生などカラー写真入りで紹介している。
また▽木道から湿地へ降りない▽昆虫や植物を採取しない竏窒ネどを呼びかける。
子どもにも読めるよう、漢字にふりがなをつけた。
パンフレットは市役所生活環境課、新山荘などに置いている。
新山の生息地では、観察できるように木道などを整備中で、今月下旬には完成。5月ごろからハッチョウトンボを見ることができ、市は学校などで環境学習をする際、案内人を派遣するという。 -
すまいの安全セミナー
上伊那地方事務所は13日、伊那市役所で「すまいの安全セミナー」を開いた。建築士や地域住民ら約90人が出席。講師の信州大学工学部助教授・五十田博さんが耐震診断と耐震補強の推進を促した。
セミナーは、建築物の耐震化の促進を図るため、震災対策への関心を深めてもらおうと開いたもので、テーマに「大規模地震、あなたの建物は安全ですか」を掲げた。
五十田さんは▽老朽化によって耐震が弱くなる▽建築年数がほぼ同じ建物で、耐震補強したものに比べ、しないものは崩壊しやすい竏窒ネど木造住宅を使った実験を映像で映しながら説明。阪神淡路大震災で亡くなった8割以上が住宅の倒壊による圧死だったことを踏まえ、いつか来るだろう地震に備え、倒壊を防ぐ補強の必要性を挙げた。また「補強工事は新築より難しい。施主のプランを入れながら、メニューを作れば普及が図られるのではないか」と話した。
会場には家具転倒防止器具、非常持ち出しリストなどが展示された。 -
黒河内さん初の個展

宮田村南割区出身で東京工芸大学芸術学部デザイン学科1年の黒河内志保さん(19)が、地元宮田村の宮田郵便局で17日まで初の個展を開いている。鮮やかな色づかいや大胆な筆致が評判。来客者の目を楽しませている。
春休みの帰郷を兼ねて、母親のすすめもあり実現。伊那弥生ケ丘高校在籍当時に描いた油絵から、現在課題で取り組むデザイン画まで20作品を出品した。
詩から自分のイメージをふくらませ、和紙と墨だけで表現したり、広告や包装紙の切り抜きをコラージュにするなど、多彩な作品の数々。
高校までとは、全く違うデザインの世界にもまれながら、新たな分野を吸収した意欲的な力作が揃う。
「初めての個展だが、多くの人に見てもらえてうれしい。大学でも課題をこなしながら、自分の作風を確立していきたいですね」と黒河内さんは話していた。 -
係に係員の配属はしない
中川村の曽我村長らは14日、村議会一般質問で、機構改革に触れ「係間の協力、協調に向け、係に係員の配属をしない」などの考えを示した。
富永和典議員と村田豊議員が「機構改革の一環として、大課制を導入する考えはないか」と質問。
曽我村長は「機構改革は大課制を前提とせず、現組織の問題点を探り、対策を講じていく」とし、具体的に▽係間の協力・協調体制を構築するために、係員の係配属をなくす▽下水道事業業務の減少を受け、水道課と建設課を統合し、事務室を改修し、農村環境改善センターに移転する▽教育委員会の4係を学校教育と社会教育の2係に統合する▽複数の課によるプロジェクトに対応するために、課長の役割を拡大する▽係長の課長補佐的役割を担うことを検討する▽1階フロアーの各課配置を変更をする-などの方針を示した。時期は事務所の配置替え、改修などをのぞき、4月1日から実施の方向。 -
箕輪北小6年生が薬物防止の学習

箕輪町の箕輪北小学校6年生は10日、薬物防止の学習をした。覚せい剤やシンナーなど薬物が人間の脳や人格を破壊する恐ろしさ、絶対に薬物に手を出してはいけないことを学んだ。
6年生はビデオで、覚せい剤、アヘン、コカインなど薬物の種類、覚せい剤などを使用すると脳を破壊する、幻覚や幻聴に襲われる、依存症になる、治療しても症状は簡単には治らない-ことなどを学び、その人の人生だけでなく家族や周囲にも大きな負担を与えることを知った。
学校薬剤師の千葉胤昭さんは、シンナーをかけると発泡スチロールが溶ける様子を実験で児童に見せ、「シンナーを袋に入れて吸っている人がいるけど、絶対にしてはいけない。薬物が簡単に手に入る時代。誘惑の場所、機会がいくらでもある。ちょっと手を出すと止められなくなる。絶対に手を出さないで」と強く呼びかけた。
児童は「覚せい剤の怖さがわかってよかった」と感想を話した。 -
もちつきボランティア交流会

駒ケ根市ボランティア協議会の「もちつきボランティア交流会」は12日、駒ケ根市ふれあいセンターであった。同協議会に所属するボランティア35団体の150人余が参加し、もちつきを楽しんだ。 今回は22キロのもち米を4基のうちでつきあげ、あんこやきなこ、大根おろしで味わった。
始めの会で飯島美佐子会長は「大勢の元気な声と明るい笑顔に会えた。多くの人と交流を深め、心にいっぱい、ビタミンを蓄えて」とあいさつ。
参加者はつきたてのもちを味わったり、ステージに繰り広げられる踊りや歌などの発表を楽しみ、交流を深めた。
1910/(日)
