-
みはらしファームで羽広かぶ入りパンを発売

権兵衛峠通路「トンネル」の開通を記念して、伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームは2月4日から、地元の特産品「羽広かぶ」を生地に練りこんだパンを発売する。
トンネルを通して木曽が身近になるため「みはらしファームとして何か独自の商品ができないか」と検討。みはらしファーム「麦の家」が、地元ならではの食材「羽広かぶ」を使ったパンの開発を進めてきた。
パンは2種類。米の粉の生地に細かく刻んだカブを入れた「かぶンパ!」(130円)と、フランスパンの生地を使った「かぶdeフランス」(120円)。ほかにも、サンドイッチの間にかぶを挟んだ「羽広菜かぶサンド」(100円)も発売する。
米粉の方はもちもちした食感、フランスパンの方は新しい風味が楽しめ、カブの塩気と生地の甘味が「意外にもおいしい」という。
みはらしファームのとれたて市場や麦の家などで販売する予定。 -
JA上伊那営農資材伊那竜東店改装工事安全祈願祭

上伊那農業協同組合(JA上伊那)は18日、これから改修工事を始める伊那市にあるJA上伊那美篶手良支所で、これから改修工事へと入る美篶資材店と東春近資材店の安全祈願祭をした=写真。
JA上伊那は、事業改革と収益性の改善を目的として、04年度から06年度までの中期3カ年計画を立て、昨年から経済事業の店舗整備を実施。上伊那の資材店を10店舗まで統合することを決めた。
今回の改装は竜東エリアの店舗整備で、美篶、東春近の資材店を整備して、伊那、手良、富県の3店舗を閉店する。
10店舗構想の中で伊那市には、昨年7月にオープンした「JAファームいな竜西店」と、竜東エリアに1店舗を整備する予定だったが、竜東地区で2店舗を整備することとなったため、上伊那全体で11店舗へと整備されることのなった。
改修店舗では、規模の拡大、品揃えの充実を図る。また、昨年上半期からは、本所に配送センターを設けて配達事業もはじめており、統合後の不備が生じないよう、整備が進んでいる。
東春近店は3月18日に、美篶店は同月25日開店する予定。 -
飯島町福祉有償運送協議会を設置、

飯島町は18日、町福祉有償運送協議会を設置。役場で開いた初会議で、町社会福祉協議会が申請、審査した結果、全会一致で承認された。社協は近日中に長野陸運支局に、上伊那第1号となる有償運送許可申請をする。
会の冒頭で、高坂町長は社協やタクシー事業者、移動困難者、知識経験者などの代表、9人に委員を委嘱し「国土交通省が黙認し、社協が実施してきた白タク的送迎サービスが、4月から許可が必要になった。福祉有償運送の安全確保、円滑、円満に事業を進めるために協議を」と、同協議会設置の目的に触れてあいさつ。
引き続き、協議会設置要綱、申請指針などのほか▽運送条件▽対象者の要件▽運行範囲▽使用車両▽運転者▽運送対価-などを盛り込んだ判断基準を確認した。
この後、町社会福祉協議会が業務計画や運行規約、料金表、運転者名簿、移動困難者等の状況など必要書類を添付し、申請した。
委員からは「安全運転の徹底を」「運転手の研修を」「車両管理の十分に」などの意見、要望が出されたが、全会一致で承認、推薦することを決めた。
町社会福祉協議会の04年度実績は利用者15人前後、年間利用数119件。駒ケ根市内の病院への通院が中心。 -
有害図書自販機早期撤去に向け、看板を製作
飯島町田切の田切地区青少年安全対策会議(山田治男会長)は17日夜、田切公民館で、第2回会議を開き、有害図書自販機撤去活動について状況報告を受け、今後の取り組みを協議した。同会議は昨年末、区役員や春日平耕地役員、育成会、防犯女性部ら約30人で組織した。
今後の取り組みとして▽有害図書撤去署名活動開始(17日縲・1日)▽有害図書撤去立て看板作成、設置(17縲・8日)▽長野地裁伊那支部へ有害図書等自動販売機撤去土地明け渡し仮処分命令申請(申請10日、第1回審尋23日)▽自販機看視パトロール活動▽防犯パトロールステッカー車貼付活動-などを確認した。
議事終了後、立て看板作り。幅90センチ、高さ180センチの両面看板3基を製作し、「有害自販機早期撤去を」「防犯カメラ作動中」などを赤と黒のペンキで書き込み、翌18日朝、春日平の現地や広域農道沿いに設置した。 -
中川西小のスキーそり教室

中川村の中川西小学校は17日、駒ケ根高原スキー場でスキー・そり教室を開いた。
5、6年生66人はすずらんコースでスキーを、1、2年生40人はそり滑りを楽しんだ。
5、6年生は学年別、習熟度別に班分けし、中ア山ろくスキー学校のインストラクターの指導を受けながら、、板の装着やストックの持ち方など基本を確認した後、それぞれの力量に合った滑りでスキーを楽しんだ。
1、2年生は舟型やスプーン型のそりで、1人乗り、2人乗り、後ろ向き、時にはつながって滑ったりと、歓声を上げながら、そり遊びに熱中した。
この日のゲレンデは積雪1メートル、パウダースノーでコンディションは最高。同校のほか、南箕輪小学校、南箕輪南部小学校もスキー教室とあって、ゲレンデは小学生で貸し切り状態だった。 -
オリジナル体操で転倒・骨折予防健康に
高遠町は介護予防事業の一環として来年度から、各地区ごとに転倒・骨折予防の体操教室を開く。オリジナル体操を作って高齢者を中心に普及させ、健康増進を図る。これに先立って、体操の創作と教室のサポーターを養成する「いきいきサポーター講座」が今月始まり、第2回の17日から、50縲・0代の町民22人が創作に取りかかった。
講師に迎えた町出身の健康運動指導士・藍早瀬さん(59)=東京都調布市=の案を基に、参加者が意見を出し合って改良。3月中旬まで9回の講座で完成させ、老人会の役員会などで発表する。
町健康福祉課は「高齢者が多いからこそ、取り組みやすいオリジナルの体操を考え、健康で元気に暮らしてもらいたい」とし、普及に期待を寄せている。
オリジナル体操は音楽に合わせて、ストレッチ、柔軟、バランス、筋力など数種類を織り交ぜた約10分間の内容を2セット作り、最終的に約20分間で構成する。
第2回講座は、いすに座って腕を伸ばしたり、上半身を左右に曲げたりしたほか、浮かせた足で「たかとお」と宙に描くなど、藍さんが提案した体操を実際に体験し、意見や動きの案を出し合った。
藍さんによると、要介護になる原因は高齢による衰弱や、転倒・骨折が多い。30分程度の運動を週2回定期的に続けることで筋肉量が増加し、予防につながる。
参加した小原の女性(73)は「全身を動かせてよかった。普段は特別運動もしていないから健康のために続けたい」と話していた。 -
UJIターン者優先 児童・園児の確保期待
高遠町が定住対策の一環として、山室久保に建設を進めていたUJIターン者優先の町営住宅(2棟2世帯分)が完成し19日、しゅん工式があった。
過疎地域への設置により小学校、保育園の児童・園児の確保を目指して01年から進めている事業で、山室は2カ所目の建設となった。
木造平屋建てで、延床面積はそれぞれ93平方メートルの3LDK。敷地内には家庭菜園も備える。事業費は2棟合わせて約3600万円。
式には関係者約20人が出席。伊東義人町長は「建てることが目的でなく、子どもがいる人に入居してもらうことが最重要であり、目的の達成である」とし「過疎地域の人口の減少が食い止められ、三義地区の活性化につながれば」と期待した。 -
JAがのぼり旗20本を寄贈

JA上伊那は18日、伊那商工会議所にキノコ入りローメンとギョーザを宣伝するのぼり旗を10本ずつ寄贈した=写真。物産展や権兵衛トンネル開通などのイベントで活用する。
昨年の商工祭やJAまつりなどで、上伊那特産の「スーパーやまびこしめじ」を使ったローメンとギョーザを販売。地元農産物のPRにとJA全農長野の支援を受けて旗(縦180センチ、横60センチ)を作った。
旗は黄地に「きのこローメン」、赤地に「伊那谷餃子(ギョーザ)」の文字が入り、それぞれキノコのデザインが描かれている。
贈呈式で、征矢福二組合長は「キノコの消費拡大として、さらに花が咲き、実を結ぶよう旗を契機づけにしてほしい」とあいさつ。
向山公人会頭は「農作物を活用することで、農工商がスクラムを組み、地域振興につながる」と寄贈に感謝した。 -
木下北保育園で収穫祭

箕輪町の木下北保育園は16日、野菜づくりでお世話になった地域の人を招いて収穫祭を開き、収穫した大根を使った給食を一緒に味わった。
同保育園は毎年、園近くの井上武雄さんの畑3アールを借り園児が野菜栽培を体験している。本年度はジャガイモ、サツマイモ、大根を作り、畑を耕したり、苗の植え方を教えたり、肥料などの管理まで南部営農組合、上伊那農協、町役場産業振興課が協力した。
収穫祭は、お世話になった人への感謝の気持ちを込めて、未満児から年長児までが昨年12月の生活発表会でやったリズムダンスや鉄棒、縄跳びなどを元気いっぱいに披露した。
給食は、大根が入った煮物、大根の漬物のほか、ごまときなこのおはぎ、ギョウザ、サラダ、イチゴの特別メニュー。年長児が地域の人と一緒のテーブルでお昼を食べた。園児は、畑のことなどを話ながら「おいしい」「楽しい」と笑顔だった。
南部営農組合の柴正人組合長は、「毎年、収穫祭を開いて招待してくれる。園児の発表を見ていると童心にかえったようでいいね」と話していた。 -
東伊那子どもを守る会発足

小学生の安全を地域で守ろうと駒ケ根市の東伊那地区で小学校が中心となって「東伊那の子どもを守る会」が発足した。17日夜、小学校教諭、PTAなどのほか、子どもを守るサポート隊、子どもを守る安心の家、警察、消防など約60人が東伊那小に集まって発足式が行われ、今後の活動方針などについて確認した。
児童の安全について学校などに対して指導・助言するスクールガード・リーダーの小出光恵さんはあいさつで「子どもたちの下校時にはメモ用紙とペンを持ち歩き、不審な人や車を見たらすぐにメモして通報してほしい」と呼び掛けた=写真。
同会の会員は小学校職員、PTA、警察のほか、正副区長、各自治組合長、民生児童委員、青少年育成委員、高齢者クラブ、子どもを守るサポート隊、子どもを守る安心の家、消防団第5分団長など多岐にわたる。今後、学校、PTA、地域が互いに連携を取りながら通学路のパトロールなどを地域ぐるみで行っていく。 -
ヤングドライバークラブ交通事故防止コンクール表彰

県安全運転管理者協会主催の第16回ヤングドライバークラブ交通事故防止コンクールの入賞者に対する表彰状の伝達式が17日、駒ケ根警察署で行われた。優秀クラブに選ばれた飯島セラミックヤングドライバークラブ(原田哲会長・67人)と、交通安全メッセージの部佳作に選ばれたタカノヤングドライバークラブの小笠原いづみさん(21)が県安全運転管理者協会の小林紀玄副会長らから表彰状を受け取った=写真。
飯島セラミックヤングドライバークラブは3回目の受賞。会社周辺の道路で通勤者のシートベルト着用や速度などをチェックしたり、新入社員を対象にした交通安全講習や標語募集などを実施しているほか、交通KYTで危険予知の訓練を行うなどの活動が評価された。
免許を取って3年目という小笠原さんは、運転中にヒヤッとすることもあった竏窒ニの思いから「初心者マークはもう外してしまったけれど、いつも心に初心者マークをつけていたい」などとするメッセージを書いた。 -
国際教育実績発表会
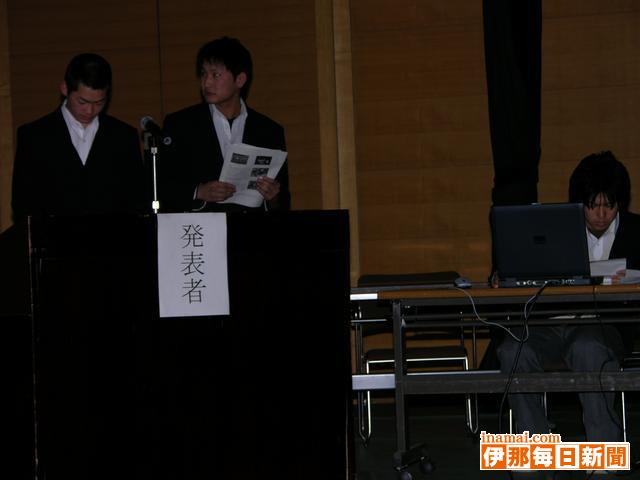
高校生が海外研修や国際協力などの体験を発表する県国際教育実績発表会が17日、駒ケ根市の文化会館で行われた。県国際教育研究協議会主催。上伊那農業高校をはじめ、県内6校の生徒約30人が参加し、意見発表の部、記録・研究発表の部に分かれてそれぞれの思いや成果を発表した。
上伊那農業緑地工学科2年の武田英太君、古川智君、竹村大志君は林業専攻国際交流研修会でインドネシアを訪問した時の体験について「現地での炭焼きや植林を通じて日本と異なる文化や環境について学んだ。今後の人生に生かしていきたい」などとスライド写真を使って発表した=写真。会場からの「どんなことが大変だったか」との質問に対して「インドネシアはとても暑くて汗が止まらなかった」などと笑顔で答えていた。
審査結果は次の通り。
▽県教育委員会賞=大塚麻美(須坂園芸2年)▽国際協力機構駒ケ根青年海外協力隊訓練所長賞=高橋彩夏(北佐久農業1年)▽JA長野中央会長賞=御子柴すみれ・有賀大地(上伊那農業)▽県高等学校国際教育研究協議会長賞=ウィアンロー・ウォーラワット(北佐久農業2年)▽伊那ライオンズクラブ会長賞=吉田知宏・塩原章太・太田覚・瀧澤まなみ(南安曇農業) -
南箕輪村輪の会がリンゴの調理実習
農業フォーラムでリンゴ料理紹介
農業や食に関心を持つ南箕輪村内の女性でつくる「南箕輪村輪の会」は、第20回南箕輪村農業フォーラム(27日、村民センター)で、リンゴの消費拡大のためリンゴ料理を紹介する。17日、会員ら10人が村公民館で調理実習をし、フォーラム参加者に試食してもらうリンゴ料理を決めた。
フォーラムでは、地産地消事業の一環として村内で生産量の多い「リンゴ(ふじ)」の消費拡大コーナーを設け、リンゴジュースの試飲やリンゴをプレゼントする。リンゴ料理も紹介しようと、主催の営農センターが「輪の会」に協力を依頼した。
「輪の会」は、家庭や地域の伝統料理のレシピ集作りを主な活動とし、信州大学農学部の学生とも交流している。今回のフォーラム参加のような対外的な活動は初。
調理実習には会員、上伊那農業高校教員、信大農学部の学生らが参加。リンゴ40個を使い、リンゴ農家に教わったり、ホームページなどで調べたレシピで「リンゴの天ぷら」「リンゴおこわ」など9品を作った。
「リンゴは甘いのでおかずのような使い方ができるという意識がなかったが、違和感なく食べられる」「いろいろなメニューができることがわかった」と会員も新たな発見があり、試食の結果、食べやすさや珍しさなどから、試食用に「りんごの簡単パイ」「りんごじるこ」の2品を選んだ。
当日は約100人分用意する。「ちょっと変わった卵焼き」「りんごが入った人参ゼリー」も展示紹介する。 -
俳人
南箕輪村
酒井昌好さん
南箕輪村大芝高原の大芝荘ロビーで、「身近な花々の写真と俳句縲恊l々の心をいやすひととき縲怐vと題し、自らが撮影した花の写真とその花を詠んだ俳句を展示している。
全国俳句誌「河」「みすゞ」「欅」の各同人。元上伊那俳壇会長でもある。
「俳句は優しいようですが、鑑賞するときに難しく感ずるときがある。初心者もどのような俳句作りがいいのか考えるもの」。そこで始めたのが、花の写真と俳句を一緒に飾る展覧会。一つの句に二つの事柄を詠む手法に似て、一つの作品に俳句と写真という二つのものを並べる。
「俳句と写真は本質は違うようだが、二つを並べると、イメージが多彩にふくらみ、見る人、読む人に深い印象を残す。俳句は花鳥風詠という。展示を参考にし、花と俳句に親しみを持っていただきたい」という。
俳句を始めたのは、今から50年前にさかのぼる。20歳のころ、「みすゞ」の初代主宰、中村六花さんに街角で偶然に出会った。伊那北高校時代に教えを受けた化学の先生でもある中村さんに、「俳句をやってみないか」と誘われ、「みすゞ」に入った。「あの時、先生に会わなければ、俳句はやっていなかったと思う」。
家業を手伝った後、石川島播磨重工業の関連会社に就職し、定年まで勤めた。社内報の編集長を10数年務め、自分の俳句を名前を隠して掲載したこともある。
中央で開く、大手企業の社内報編集長の会議で、社内報を作る意義について意見を交わしたときのこと。たどり着いた答えは「やっぱり“愛”。愛を感じ、愛を育てよう」。“愛”は、俳句の世界にも共通する。「俳句から、人間生活に必要な優しさ、いたわりの心をなるべく感じてもらいたい」と願う。
俳人の中村六花さんと森澄雄さんを尊敬し、俳句を作る。会誌に出す句は毎月25首ほど。そのために50首を作り、発想段階も含めると100首近くになる。歩きながら自然に浮かぶこともあるが、「集中力が大事。役者が芝居を演じるときと同じで意識を高めることが大切。そうすることで感覚が鋭くなる」。作ろう-という気持ちが大きな要素になる。
“世界を見る目”も重視する。在職中は、仕事でパリやロンドンを毎年訪れた。「とにかく世界を見なければ日本は語れない」。“世界を見る目”は、俳句で自然や花を見つめる目にもつながるという。
「森羅万象、あらゆるものが俳句になる」。それゆえに、いろいろなことを知ったうえで、俳句を作らなければいけないと考える。
「俳句は日本の昔からのもので、大切にしないといけない。国際的にも認められ、俳句の根本にある詩の心が理解されて、『はいく』が国際語になっている。世界を見ながら国際的な俳句の広がりを見守り、豊かさを求めていきたい」
伊那市西箕輪羽広の仲仙寺に96年、「みすゞ」の初代、2代、3代の句碑が並ぶ後ろに、句碑が立った。「伊那部宿を考える会」の会員でもあり、集会所に自詠の句が飾られている。 -
高遠町・長谷村・西春近商工会 06年度から合併に向けた連携
高遠町・長谷村・伊那市西春近の商工会は年度内に、合併・統合に向けて06年度から連携するための調印を交わす。西春近商工会新年祝賀会の席上、野溝和男会長が明らかにした。
県は商工団体への補助金を抑制する点から、1市町村に1商工団体を原則としている。「補助金を受けての商工会。減額されると運営できない」(野溝会長)と今後の方向性を検討。3月31日の新市発足に伴い、1商工会議所3商工会を1つするのは容易でないことから、まず3商工会が広域的に連携することとし、各商工会の理事会で決定した。
連携によって、税務や経営などの経営改善普及事業を1本化。各商工会が中心となっているイベントなど地域振興事業はそれぞれで取り組む。06年度は高遠町商工会が監事を務める。
各部会の事業内容などが異なるため、連携を取りながらまとめ、07年度の3商工会合併に向ける。さらに助走期間を置き、09年度に伊那商工会議所と統合したいとする。
06年度は補助金や職員数に変動はない。07年度に合併すると、補助金は06年度までの80%を確保できるという。
西春近商工会によると、会員から合併・統合を望む一方、経営指導体制などきめ細かなサービスが行き届かなくなると危ぐする声もある。
伊那商工会議所の向山公人会頭は「会議所として即統合ということは決めていない。会員の合意を取り、成果が上がるように論じることが大切」と述べ「商工会と共通事業があれば、力を合わせて取り組みたい。一つの生活圏、経済圏で、同じ目的を持つものがまとまるのが望ましい」と西春近商工会と話し合いの場を作りたいとした。 -
飯沼棚田産美山錦を使った「今錦おたまじゃくし」が完成

中川村大草の米沢酒造(米沢博文社長)が、飯沼棚田の美山錦だけを使ったオリジナル新酒「おたまじゃくし・おり酒、原酒」が完成、18日の新発売を前に、17日夜、JA中川支所で試飲会があった。来賓の村、商工会、JAをはじめ、酒米を栽培した飯沼農業活性化研究会、米沢酒造、南部酒販組合ら関係者約50人が参加、しぼりたての原酒、おり酒を口に含み「香り高く、きりっとした、濃い味わい」に、地域活性化への期待を膨らませ、完売を確信した。
米沢社長は「30俵を12月に仕込み、厳しい寒さが続き、酒づくりには最高な環境の中、ベテランから若手まで蔵人が気持ちを1つに、蔵付きの酵母菌の力を得て醸造した」と経過に触れ「小さなオタマジャクシが大きなカエルに変身できるように、温かい支援を」とあいさつ。
この後、発酵中のおり酒を互いに注ぎあって、乾杯した。
飯島町で酒店を営む池上明さんは「ほかに類のない個性溢れる、どぶろくのような酒。しとやかな香り、米つぶが残っている感じが楽しい。これはすごく売れる」と話していた。
生原酒の限定販売は25日から、特別純米酒は5月上旬を予定。 -
伊那商工会議所が市に要望

伊那商工会議所は18日、市役所を訪れ、小坂市長、三沢岩視市議会議長あてに06年度事業に対する補助金・委託金の要望と事業提案をした=写真。
事業は地域総合振興事業、小規模事業経営支援事業、雇用対策事業を柱とする14項目。空き店舗を活用したにぎわいのまちづくりを含む商店街活性化イベント事業、伊那北駅周辺整備・空き店舗対策検討支援、仕事に必要な知識の習得や能力の向上を目的とした「トータルビジネス創造学院」事業などにも力を入れる。それらの事業にかかわる要望額として2900万円(前年比400万円増)の交付を要望。
市への事業提案は▽市街地にぎわいルート開拓・案内標識の設置調査▽権兵衛トンネル出入り口付近への駐車場設置と羽広のウォーキングコースの整備調査▽ローメンに次ぐ新たな健康志向型の「食」資源調査竏窒ネど5点を挙げた。
向山公人会頭ら4人が来庁し、要望事項を説明。向山会頭は「市街地活性化は各店が本気で取り組むことを前提に進めている。産業集積地の充実を図るよう成果を上げたい」と理解を求めた。
小坂市長は「合併を控えているので、新規事業は6月の補正となる。権兵衛トンネル開通、合併と大きな変化に対する施策を考えていかなければならない」と述べ、商工会議所の意見を聞く場を設けていきたいとした。 -
JA上伊那の七久保宅幼老所起工式

JA上伊那(征矢福二組合長)は飯島町七久保の七久保支所旧資材店舗を利用し、仮称JA七久保宅幼老所を開設する。18日現地で、大規模改造の安全祈願祭を行い、工事の無事と期限内完成を祈った。3月末しゅん工、4月中旬の開所を目指す。
高齢者福祉事業に取り組むJA上伊那が、遊休施設の有効活用を図りながら、小規模地域密着型の介護施設として、また、学童を含めた地域全体の拠り所として初めて整備する。運営は生活部ふれあい事業課がかかわる。
建設面積は160・75平方メートル、約37平方メートルの食堂・機能訓練室、相談室(4平方メートル)、静養室(6平方メートル)、休憩室(10平方メートル)のほか、事務所、ちゅう房、浴室、トイレなどを整備する。
事業は介護保険通所介護事業「一般型」(生活指導・機能訓練・介護サービス・送迎・給食・入浴サービス・筋力向上トレーニング)、町委託の身体障害者デイサービスのほか、自主事業として障害児(者)のタイムケア、高齢者の地域交流、学童保育-など。
利用定員12人。
職員体制は常勤換算5人、内訳は管理者兼生活相談員1人、看護職員1人、介護職員2人、調理職員1人、送迎運転手1人。
営業日は月曜日縲恣y曜日、午前9時縲恁゚後4時30分、延長あり。
実施地域は飯島町、中川村、駒ケ根市、宮田村。 -
宮田中学校で入学説明会

宮田村の宮田中学校で17日、4月入学の新1年生と保護者を対象に入学準備の説明会を開いた。会に先だって、入学前に授業や学校を知っておこうと、児童や保護者が授業参観もした。
児童らは学級担任の引率のもと、学校内や先輩が学ぶ授業の様子を見学、保護者らも我が子が春から通う中学校に理解を深めていた。
約1時間の授業参観の後、児童と保護者は分かれて説明会へ。
児童に向けては、入学までの心構え、中学校の生活全般について話しがあった。
保護者を対象した説明では、同校の特色、学習教科、時間割のほか、生徒会活動、学級活動、部活動、給食、定期テスト、学校行事など詳しく説明した。
このほか、辞典や楽器、体育の運動着など1年次に個人で購入する学用品などにも触れた。 -
高校改革プラン推進委員会(15)

第3通学区高校改革プラン推進委員会(池上明雄委員長)が18日、南箕輪村民センターであり、各委員から募った考えを池上委員長らがまとめた最終報告書素案が示された。委員は20日までに、素案にそれぞれ検討を加えて事務局に提出する。それを考慮し、改めて報告書をまとめ、30日の最終委員会で正式な了承を得る。県教育委員会への答申は今月中に行う構えだ。
池上委員長は冒頭、統廃合案が確定していなかった諏訪につき「岡谷東と岡谷南の統合」という過去に諏訪からでた案を改めて提示。諏訪の委員は、地域での合意形成の時間を設けるなど、なんらかの配慮を付記することを条件としながらも、案の決定を受け入れた。
最終報告書の素案は▼25校から22校にすること▼岡谷東、岡谷南の統合▼箕輪工業の全日制廃止▼飯田長姫と飯田工業の統合竏窒軏{とし、多部制・単位制の設置や、定時制高校の統廃合を示している。
「削減ありき」という結論が強調され、魅力論の言及が希薄化している竏窒ニ考える委員も多く、具体的な魅力論に踏み込むことを求める声もあり、付記事項で各委員が考える魅力論を充実させることとなった。
一部の委員からは、20人学級や教員の加配などで定時制と同等の環境を多部制・単位制に確保してほしい竏窒ニの要望もあったが、県教委は「あくまでも40人学級の枠で充実を図りたい」とした。 -
【寄稿】豪雪災害現地視察を終えて(下)
長野県議会土木住宅委員長 向山公人
飯山市の千曲川近くの視察(前号参照)に続いて、農業施設の状況ということで、大規模農業経営をされている花卉ハウスや畜産団地を視察したが、除雪作業に追われている現況では、被害状況など掌握できない状況であった。
黒岩地籍に従来あったスキー場の跡地は、過去雪崩を数回起こし下段の集落に犠牲者が出ていることから、県では防止施設を昨年設置したが、将来的には植樹していく必要を感じた。
国・県道は除雪により車の通行は確保されてきているが、脇道や町村道については通行の確保が進んでおらず、土木部として、11日から排雪作業の応援にロータリー車、バックホー、ダンプカーなどをオペレーター付きで4グループ、各市町村に出すことを決定した。
北信地方事務所管内の5市町村において、弱者世帯といわれている世帯は約700世帯あるようだが、早急に屋根などの除雪作業に着手するよう要望すると同時に除雪支援を求めることを約束した。
飯山市から栄村へは、「1里1尺」という昔からの言い伝えがあり、4キロ行くと30センチ雪が増えると言われるが、屋根の雪や道路脇の雪の高さがそのことを物語っていた。
毎年これから本格的な雪のシーズンを迎える時期なので、除雪作業計画は気を許せない日々がまだ続いており、地域の人たちの大変さが身に染みて理解できた現地調査であった。
それ以前に知事が飯山市を訪れたが、たった10分ほどいただけで栄村に向かったことについて、住民の一人は「あんな短時間で的確な状況判断ができるのだろうか」と不満を漏らしていたが、いかにもパフォーマンス知事を表わしている一面と感じられた。
毎日の除雪作業に励む人々が「地域の中でお互いに助け合う信頼感や団結が強まるのはうれしいですけどね……」と語った言葉が特に印象的だった。
災害など緊急を要することは現地の状況を的確に捉えた対策が重要と改めて感じて帰路に着いた。
視察前日17時現在の被害状況は、死者が飯山市1人、栄村で1人。重傷者が中野市、飯山市、など5市町村で11人。視察当日、体育館が倒壊した。
視察後の13日、県議会正副議長と土木住宅委員長の3人で、19日に国土交通省に除雪作業への支援の要請に赴くことが決まった。 -
正月遊びに夢中
長谷小学校(三沢久夫校長)で18日、正月遊び集会があり、児童たちが羽子板や百人一首などを楽しんだ。
日本の伝統文化の継承を目的とした児童会主催の恒例行事で、96年にかるた遊び集会が始まり、6年前から多種類の遊びを取り入れている。全校児童のアンケートで、こま回し、すごろく、トランプなど10種類ほどの遊びを計画した。
児童たちは希望するものを選び、学年関係なく仲良く遊んだ。こま回しでは、手のひらに乗せる高度な技術を披露する児童もいて、「今は綱渡りができるように頑張ってる」と張り切っていた。
児童会長の松村響君は「自分たちが家族に教わったと同じように、大人になってから子どもたちに教えたい。それが目的の一つだし、下級生にも伝統行事として引き継いでやっていってほしい」と話していた。 -
高遠町上山田引持で伝統の悪魔払いの獅子舞
高遠町上山田引持の祭事連とそのOBが17日夜、地区集会所で一年間の無病息災を祈る伝統の悪魔払いの獅子舞を披露し、子どもからお年寄りまで地域住民40人余が鑑賞した。
かつて、酒を飲みながら日の出を待ち、夜明けとともに願いごとをしたとされる「お日待」の日(17日)の恒例行事。
前獅子とひょっとこの面を付けた後舞の2人で操る獅子は、笛の音に合わせて、御幣と鈴を持って舞台を幾度か回り、身を清める仕草をした後、鈴を振って激しく再び舞台を舞った。気迫に満ちた勇壮な舞に住民からも盛大な拍手が起きた。
祭事連は、30歳未満の跡取りでつくり、現在は4人。人数の減少によってここ数年は、OBの協力を得ている。来年は2人となり、伝統芸能の継承が危ぶまれるなか、「郷土芸能保存会を立ち上げたい」(平岩國幸常会長)という動きも出ている。 -
議運が対面方式採用を提案
宮田村議会運営委員会(片桐敏良委員長)は、定例会一般質問で議員と理事者らが向き合って質疑する対面方式を採用するなどの議会改革案をまとめ、17日の全員協議会に提案した。一方でやり方を変えるだけでは質の向上につながらないと異論も挙がり、近く再議論することになった。
一昨年の議会改選後から改革の検討が始まり、特に一般質問のやり方について議論。
既に質問回数の制限緩和などを実施したが、一問一答方式の採用も検討してきた。
議運は一問一答の導入について時期尚早と判断。経過措置として、質問を1項目ごと対面によって質疑する案をとりまとめた。
案では項目ごとの質問回数を3回までとしたほか、ひとりあたり40分以内の持ち時間制を採用している。
片桐委員長は議運案について「質問のレベルアップも考慮に入れた」と全協で説明したが、時間制の採用などに異論の声も。
また、「形を変えるだけで、質問の中味が大きく変わるとは思わない。レベルアップを図るためには(現状でも)改善の余地がある。もっと総合的な研究をすべき」と、慎重な対応を求める声もあった。 -
村土の利用計画13年ぶりに改定
国土利用計画に基づく宮田村の村土利用計画が13年ぶりに改定され17日、村議会全員協議会に示された。引き続き土地活用が・ス虫食い状態・スにならないよう、用途ごとの集積化を図っていく。
目標である人口1万人達成を想定し、2015年には住宅地が25ヘクタール、工業用地が15ヘクタールそれぞれ増加すると目標規模に設定。一方で農用地は52ヘクタール減少すると見込んだ。
既存の土地用途を基本にして、住宅地域、工業地域、農業地域などをある程度すみわけし、有効活用を図る。
村土の利用に関して行政上の指針となる同計画は2001年に改定する予定だったが、合併問題の浮上により中断していた。
昨年7月に庁内に委員会を設け策定作業に着手。県との調整も行なってきており、3月定例会に議案上程する。
この日の全協では、住民委員らで構成する審議会がまとめた村の第4次総合計画後期基本計画案についても説明。内容について意見交換したが、再度全協を開いて理解を深めることになった。 -
インフルエンザ 郡内小学校で集団発生
伊那保健所に18日、上伊那郡内の小学校からインフルエンザ様疾患の集団発生の報告があった。同保健所によると、当該小学校の4年生1クラス27人のうち、16人が高熱、咳などの症状を訴え欠席。同小は19日から20日まで、同クラスを学級閉鎖する。
上伊那では今季、インフルエンザの集団発生、学級閉鎖はいずれも初。県内では学級閉鎖は2校目。
感染症発生動向調査第2週(1月9日縲・5日)のインフルエンザ患者届出数は、県全体で定点当たり7・55人で、増加傾向にある。伊那保健所は、今後もさらに患者数の増加が心配されることから、感染予防のための注意を呼びかけている。
インフルエンザの感染予防対策は、▼よく食べる▼よく寝て、休養を取る▼よく「うがい」「手洗い」をする竏窒ネど。「インフルエンザにかかったな」と思ったら、早めに医療機関で受診することが必要だという。 -
優しく、温かく、患者和ませて

南箕輪村の上伊那農業高校のクラブ「国際研究班」(池上あゆみ部長、4人)が作ったアメリカンキルトが1月末まで、伊那市の中央病院4階ラウンジに飾られている=写真。ラウンジに集まる利用者たちは、優しくて温かみのある作品を見て和んでいる。
昨年8月、新しく着任した米国出身のAETの先生と交流を図るため、秋の文化祭に向けてアメリカンキルトを製作。より多くの人に見てもらおう竏窒ニ今回、生徒たちが同病院に申し入れた。
作品は、縦120センチ、横90センチ。購入した布や各自が自宅から持ちよった古布で作った。クラブ活動や放課後の時間など、2カ月の製作日数が注ぎ込まれている。
出産を控えた箕輪町の30代女性は「とってもじょうず。毎日、ラウンジを利用して和んでいます」と笑みを見せていた。 -
カウンセリングを学ぶ会の公開講演会

上伊那子どもサポートセンターは14日、「不登校の諸君と共に」をテーマとした公開講座を伊那市立図書館で開いた。子どもとの向き合い方に悩む母親など約10人が参加。不登校や引きこもりに悩む子どもの心理的不安やストレスに、親としてどう付き合っていけばよいのかなどを学んだ。
講師は「のぞみ学園」園長の北澤康吉さん。ロジャーズ流カウンセリングで不登校や引きこもりの子どもたちを支援している。月に1度、上伊那子どもサポートセンターで開く「カウンセリングを学ぶ会」(コープ倶楽部主催)の講師も務め、今回はその会の公開講座とした。
北澤さんは「登校拒否は安全反応である」として、精神的にも身体的にも不安を感じるようになった現代では、しばらくその姿を大切にしてあげる必要があると説明。
また、受験などを控えた子どもは、だれよりも自分の将来について不安を感じており、親が言及して追い詰めるのでなく、自分から自発的に相談してくるまで待つことも必要竏窒ニ話した。 -
社会福祉関係知事表彰

県は19日、高齢者・障害者支援などに取り組むことを通して、地域の社会福祉充実に貢献した個人・団体を知事表彰する。
上伊那は、まちのバリアフリー化を提言して地域のまちづくりに積極的に活動した人や、児童擁護施設に食事を提供したり調理実演をするなどのボランティアに取り組む飲食店経営者らでつくる団体など、4個人2団体が表彰を受ける。次のみなさん。
◇障害者福祉=久保田元次(駒ヶ根)、西島米子(飯島)
◇高齢者福祉=駒ヶ根市上赤須高齢者クラブ(駒ヶ根市)
◇更生保護=渕井光久(箕輪)
◇ボランティア=一の会(伊那)、矢島忠夫(箕輪町) -
上伊那岳風会駒ケ根地区初吟会

上伊那岳風会駒ケ根地区の初吟会が15日、赤穂公民館であり、市内18教室の160人が参加、約100プログラムで鍛錬した喉を披露した。
全員で「富士山」を吟じて幕開け。堀内岳茂会長が朗朗ときよめ吟を行った後、独吟や教室単位の合吟で漢詩、漢文の1節、和歌、新体詩などを吟じた。
また、勇壮な剣舞、扇をかざして舞う扇舞などが舞台を新春らしく華やかに彩った。
45/(日)
