-
書道家 池上信子さん(74) 伊那市日影

伊那公民館で隔週開いている書道教室の講師を26年間務めている。2年ごと新しい生徒を迎える同教室では、これまでに約400人以上の教え子が卒業している。
「生徒たちのとの出会いはすばらしい。生徒数は年々少なくなっているが、むしろ少ない分、心のつながりが出てきている。一人休めば『今日はさみしいね』という感じ。生徒さんと出会うのが私の生きがいになっている」
教室の2年間は筆の持ち方、線の書き方、墨のすり方などの基本を3カ月間、丹念に学ぶことからはじまる。文字を書きはじめるのはそれからとなる。
教える文字は、流れがあって、全体的に見た時に優美さがあるという「かな」が中心。日本にしかない、かな文字を伝承していかなければ竏窒ニの思いで伝え続けている。
これまでに12期生が巣立っていった。まだまだ勉強したい竏窒ニ、各期ごとのメンバーでつくるグループの学習の面倒も見ている。
「一つの方向に向かって頑張ろうと自分を高める姿。心も豊かに、身体的にも成長していく生徒たちを見ていけることはうれしい」
書道との出合いは弥生ヶ丘高校時代。担任が、かなを得意とする書道の教師だった。「実用的な字が書けなくはいけない」と毎週、自分の住所・氏名、学校名などを習字紙に記す宿題で、細字を嫌というほど書かされたという。
「字に対する教えは厳しかった。でも、厳しい分やった分の努力は認めてくれたことがうれしかった」
高校を卒業して、中学校の体育教諭になったが、習字の心得があると赴任先の校長に見初められ、生徒たちに書道も教えるはめに。指導する立場になるのでもっと勉強しなければと、書道塾へ通うようにもなったと振り返る。
本格的に学ぶようになったのは、同じ教師だった夫と結婚して退職してから。長野市で一緒に暮らしていた6年間や地元に帰ってきてからも、多くの師の下で勉強。子育てで忙しい時期も「書きたい。書きたい…」という思いは強かったという。
自分のやりたいことを認めてくれていた夫との思い出がよみがえる。器用な夫は退職後、表具師として作品を表装に仕立ててくれていたという。しかし、自分を支えてくれていた夫は61歳の若さで亡くなった。最期まで作品を仕立てようとしていたという。残った表装は7縲・本。宝物になっている。
自分を支えてくれているのは「仏になった夫」や、生徒など周りの存在。「残された人生の中で、自分の作品を多く残していきたい。書きたいものも、まだまだ沢山ある」と意欲をみせる。
現在は書道教室の生徒や卒業生らによる展示会(5月19縲・1日・県伊那文化会館)の作品づくりの指導に追われている。初心者から20年間以上続けているベテランまでの総勢70人余が出品。「一つのことに協力して取り組める教え子たちばっかり」と作品を添削する筆が生き生きと滑っている。 -
高遠城址公園タカトオコヒガンザクラの開花宣言

全国有数の桜の名所、伊那市高遠町の高遠城址公園で13日、タカトオコヒガンザクラの開花宣言が出された。平年並みで、昨年より2日遅く、週明けごろに見ごろを迎えそうだ。
ここ数日の冷え込みなどの影響で予想より遅れていたが、公園南口から徐々に咲き始め、全国各地から訪れている花見客らは記念撮影をするなどし、歓声をあげている。
さくら祭りが開幕した6日から12日までの有料入園者数はツアー客を中心に約1万5千人が訪れた。ピークは15、16日となる見通しで、2日間で8万人の人出を見込む。
同日からライトアップも始まったほか、期間中は、高遠ばやしの巡行(17日)、商工会女性部による桜茶のサービス(18日)、高遠まんじゅうの大食い大会(21日)などのイベントを予定している。 -
新伊那市かるたを発売へ

伊那市書店組合(小林史麿組合長、4人)は今月下旬、「新伊那市かるた」を発売する。子どもから大人までが楽しめるかるたで、3千セットを用意。市内の書店で注文を受け付けている。
新市誕生記念の冠イベントの一つ。3月31日の高遠町・長谷村との合併を機に、誇り高きふるさとを知ろうと制作した。
読み札は五十音の46札に「新・伊・那・市」の4文字を加えた。中央・南アルプス、高遠城址公園コヒガンザクラ、孝行猿、伊那部宿、ザザ虫などが題材。「あ 朝夕に駒・仙丈を仰ぎ見て」「い いっせいに駆け出す春よ、やきもち踊り」…と詠んだ。絵札はオールカラー。解説書とかるためぐり地図付き。
市外から注文も入り、反響の大きさをうかがわせる。
小林組合長は「かるたを通じて身近な郷土の歴史や自然、行事などを知り、訪ねることで、心の融和が図られるのでは」と話す。
価格は2千円。
注文はコマ書店(TEL78・4030)、上条書店(TEL72・2028)、小林書店(TEL72・2685)、草思堂書店(TEL94・2080)、ニシザワデパート(TEL78・3811)などへ。 -
中川村バスロケーションシステム、本格運行

中川村は村内巡回バスの現在位置や「複雑でわかりにくい」と言われる路線、ダイヤなどをCATV画面で見やすく表示するバス情報システム「中川村バスロケーションシステム」を構築、4月から本格運用している。
同システムは▽村内全世帯の住民が自宅のテレビ画面で情報が見られる▽携帯電話とインターネット網による安価なシステム▽バス位置情報に留まらず、路線、乗り換え、次発便の情報、文字情報など総合的バス情報をシステムとして一体化する-など全国的にも類を見ない画期的なシステム。
モニターが設置されているショッピングセンターやみなかた診療所では、バスの利用者がモニターを見て、バスの現在地やルート、近くの停留所の発着時刻を確認している。
同村のバスロケーションシステムは、昨年11月、国交省や県、村、交通事業者など交通利用者代表による検討委員会を立ち上げ、3月末まで2回の検討会、試行運行、利用者アンケートなどを行い、調整、修正を加え、本格運行にこぎつけた。 -
桜満開でカメラマンどっと
中川村の大草城址公園や坂戸橋など桜の名所や1本桜の名木が見ごろを迎え、県内外から多くのカメラマンが訪れ、花の下に三脚を据え、ファインダーをのぞき、次々とシャッターを切っている。
数10本のソメイヨシノが桜のトンネルを作る坂戸橋には、大阪のカメラ教室のグループが樹間に流れる天竜川、山のりょう線をバックに、構図に工夫を凝らす。
樹齢百年余の下平のしだれ桜も満開。道路いっぱいに枝を伸ばし、花天井の下をドライバーはゆっくりと通り抜ける -
1年生の給食始まる

入学式から1週間、飯島町の2小学校で12日から、新1年生の給食が始まった。
このうち、七久保小学校1年生(小野岳司教諭、25人)は、白衣、白の帽子、マスクと身支度を整え、パンのケース、おかずが入った平缶、汁ものの缶、牛乳びんの入ったカゴなどを持ち、小野教諭を先頭に隊列を組んで、慎重に教室まで運んだ。
牛乳びんやデザートのヨーグルトを配る人、パンやおかず、スープを盛り付ける人、配る人など手分けで、配膳を進めた。
この日の献立は、パン、串カツ、サラダ、ワカメとタマネギのスープ、ヨーグルト、牛乳。
配膳が済むと、小野教諭は「パン、次ぎにおかず、汁物と少しずつ代わる代わる、ゆっくりよく噛んで、食べるように」と三角食べを指導した。
当番の児童が「手を合わせて下さい」と声を掛け、「いただきます」で一斉に食べ始めた。
1年生は「パンがおいしい」「野菜もりもり食べるんだ」「ナスもピーマンも食べられる」と、おう盛な食欲を見せて、料理を平らげていた。
小野教諭は「保育園でしっかり指導していただいているので、配膳も手際よく、行儀もりっぱ」と話していた。 -
【登場】伊那北高校校長
千村重平さん(58)
相手を信頼し、自分も相手から信頼されなければ本音で話すことはできない。人と人との信頼関係が一番大切竏秩B
初任地は地元の木曽高校。松本県ヶ丘、長野西などで教鞭(べん)をとり、県教育委員会の教学指導課へ。その後、松本蟻ヶ崎で校長を務め、教学指導課の係長をとなった。専門は理科。
勉強にしても部活にしても、生徒と共に過ごし、何も飾らずに向き合うことができる日々は楽しく、天職だと実感した。部活動では、山岳部の顧問も務めた。最初は全く知らなかった山登り。一切合切を教えてくれたのは生徒たちだった。マイナス20度にもなる3千メートル級の冬山など、死と隣り合わせの世界。だからこそ、いつも一生懸命な生徒たちの姿がそこにあった。
自分たちの思いを伝えたい竏窒ニ昨年の文化祭で田中知事に自分たちの思いのたけをぶつけた伊那北高校の生徒たちについては「こういうことは若い人にしかできない。若さとしての特権はどんどん主張してほしいし、ぼくらはそれをバックアップしたい」と期待をかける。
「教育というと『教え込む』というイメージがあるが、そうでなくて本人が持っている無限の可能性をいかにして引き出してあげるか。喜びを共に分かち合うだけでなく、悩んでいる生徒がいるなら、一緒になって悩む。それが必要なんです」。
松本市在住。家族は妻、娘2人。現在は伊那市へ単身赴任中。 -
JA伊南地区杯マレット

第49回JA上伊那伊南地区杯マレットゴルフ大会が12日、宮田村マレットゴルフ場で開かれた。伊南各地区から108人が出場。シーズン初めの大会で腕を競った。
今季のオープンをしたばかりの同マレットゴルフ場で、出場者はプレーを満喫。新緑に包まれた久しぶりの競技会に、自慢の腕も鳴った。
地元宮田村の唐沢治男さんが2位に2打差をつけて優勝。今季開幕の主要大会を制した。
上位の結果は次の通り。
【総合優勝】唐沢治男(宮田村)109
【男子】(1)斉藤昭二(中川村)111(2)倉田東亜(宮田村)112(3)森田孝司(同)113
【女子】(1)山口ひで子(駒ヶ根市)112(2)山本かね子(同)112(3)小田切宏子(宮田村)115
【混合】(8)下島一男(飯島町)114(9)宮崎忠雄(中川村)115(10)村井敏雄(駒ヶ根市)115
【ホールインワン】倉田東亜、宮崎勝司、尾形正 -
ゲートボールリーグ戦開幕

球春到来‐。宮田村ゲートボール協会主催のリーグ戦(加納義厚会長)は13日、中央グラウンドで開幕した。昨季と同じ6チームが参加。10月まで熱戦を繰り広げる。
開幕式では加納会長があいさつ。白鳥剛公民館長は「冬に積んできた練習の成果を存分に発揮してください」と激励した。
さっそく試合開始。最高齢は90歳を超えるが、元気にプレーを楽しんでいた。
昨季は大田切が5年ぶりに優勝。今季も半年に及ぶ長丁場で50試合を予定しており、仲間との絆、健康増進を深めつつ勝利を目指す。 -
高遠の桜のにぎわい報じる70年前の地元紙見つかる

駒ヶ根市赤須東の小松茂郁さん(64)の自宅から、戦前に上伊那で発行していた信濃民友新聞の1933年(昭和8年)4月14日付号が見つかった。高遠の桜の開花状況や賑わいなどが紙面を飾っており、「70年余りも前の昔から、高遠の桜は変わりがないんですね」と、偶然見つけた貴重な資料に小松さんは目を細めている。
きのう13日は高遠の桜の開花宣言があったが、見つかった73年前の信濃民友新聞は「日増しに赤味を帯びて来り開花期も近づいて来た」と報じている。
「高遠も宣伝に大童(おおわらわ)の有様」という見出しで紹介し、町商工会が観桜客を呼び込もうと関東、関西方面に大々的な宣伝を行ったと掲載。
また、伊那電気鉄道(現JR飯田線)が下伊那からの観桜団体ツアーを募集しているとも記している。
この新聞は小松さんが自宅の片づけをしていた所、祖父で赤穂郵便局長も務めた今朝弥さんの持ち物の中から見つかった。
「ちょっと古い新聞だと思ったら、地元のことが書いてあった。掲載広告には今も続いている商店などがあって、ちょっと熱を入れて探してしまいました」と小松さん。
同新聞のその日の紙面には「一家6人心中」「人妻がネコ自殺」など気になる事件、事故も載っているが、サクラも含めて当時の民衆の様子を克明に伝えている。 -
特別純米酒「おたまじゃくし」が21日から発売開始

中川村大草の米沢酒造(米沢博文社長)は21日、飯沼棚田産の酒米「美山錦」を使った特別純米酒「今錦おたまじゃくし」を新発売する。
米生産者と地元酒造会社が協力し、地域活性化を目指す「今錦おたまじゃくし」シリーズは、1月発売、即完売したおり酒、生原酒に続く、第3弾。
今回発売する特別純米酒は、3カ月間、蔵の中でじっくり熟成させ、香り高く、コクのある酒にし上がったという。
販売数は720ミリ600-700本、1・8リットル300本。価格は720ミリリットル1386円、1・8リットル2730円(税込)。中川村・飯島町を中心に上伊那の酒店で販売、予約受付中。 -
高遠高1年生「進徳ゼミ」
高遠高校(福沢務校長)の旧高遠藩校「進徳館」にちなんだ総合的な学習「進徳ゼミ」で、新1年生121人が13日、講師を招いて高遠の歴史を学び、桜が開花し始めた高遠城址公園で花見を兼ねてごみ拾いをした。
高校のある高遠の歴史や文化を学び、体感して素晴らしさを再認識するとともに、清掃活動による地域貢献を目的に、1年生の恒例行事。
生徒たちは、前信州高遠美術館長の堀井英雄さんを講師に、高遠の歴史などについて学び、実際に進徳館を見学。また、観桜客でにぎわう城址公園のごみ拾いもした。
園内の桜は一部が開花しているだけだったが、友達同士で散策したり、開花した桜を携帯電話のカメラに収めるなど、有意義な時間を過ごした。 -
【記者室】通年観光に結びつける機会に
桜の話題が紙面を飾る。桜の名所として知られる高遠城址公園。待ちに待った開花宣言が出され、18日ごろに見ごろを迎えるという。連日、全国各地からツアー客などが訪れ、駐車場は満車状態が続く▼観光客の誘導や駐車場整理、料金徴収など1日に市職員らおよそ200人が当たっている。また高遠へ来てもらえるようにと観光客への対応は徹底している。ボランティアで参加する中学生にも観光案内ができるよう講座を開くほどだ。地域に根づく「もてなしの心」に頭が下がる▼本年は権兵衛トンネル開通などによって、32万人の人出を見込む。「高遠の桜」にとどまらず、より合併した地域の資源を知ってもらい、通年観光に結びつける機会としてとらえたい。(湯沢記者)
-
みのちゃんバス利用状況まとめ
箕輪町は町内循環「みのちゃん」バスの05年度利用状況をまとめた。04年度に比べ乗車人数が24%増加し、町民の足として活用されている結果になった。
05年度の乗車人数は3万936人。前年度より5908人増えた。前年度と比べ最も利用が増えたのは12月で913人増、次いで多かったのは2月で649人増だった。
年間を通して利用者が増えているが、中学生や冬場の利用が特に増加したという。 -
「まっくん」の刺しゅう作品展示

南箕輪村の大芝荘に、91歳のおばあちゃんの手による村のキャラクター「まっくん」の刺しゅう作品が飾られている。
伊那市にある介護老人保健施設辛夷園を利用しているおばあちゃんが楽しみに縫ったもの。新しいデザインのまっくんで、「まっくんと桜」「まっくんと松」の図柄。一針一針丁寧に刺しゅうしている。
希望者には1枚300円で販売。すでに桜の作品を購入した人もいるという。 -
理容生活衛生同業組合総代会
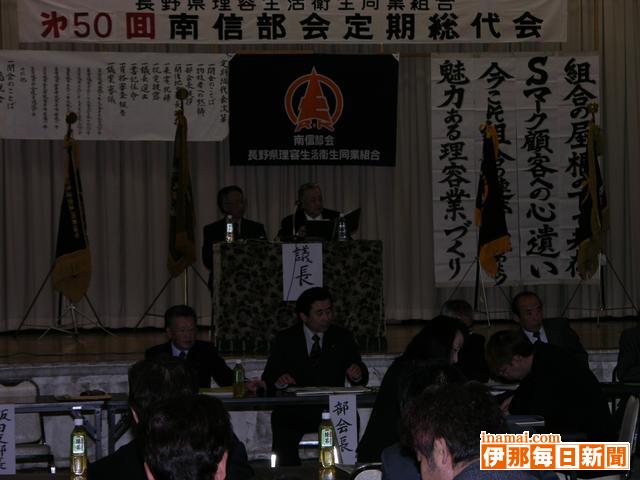
県理容生活衛生同業組合南信部会は10日、第50回定期総代会を駒ケ根市のアイ・パルいなんで開いた=写真。諏訪から飯田の7支部の総代約60人が出席し、05年度事業・決算報告、06年度事業計画・予算案を承認したほか、06年度役員を選出した。
新役員は次の皆さん。
▽県常任理事=松澤光洋、菅沼一弘▽県監事=唐木寛武▽南信部会長=中村文明▽同副部会長=辻村章▽南信部会監事=太田正夫、唐澤満男▽同会計=下島善三▽県教育部委員=池上喜郎▽県総務部委員=藤木益男▽県文化広報部委員=下島善三▽県事業厚生部委員=樋口眸、志賀良雄▽県共済部委員=辻村章▽県組織部委員=桜井智明 -
みのわ振興公社
講演会で従業員研修
箕輪町のみのわ振興公社は11日、従業員研修で雑誌「KURA」編集長の市川美季さんの講演を聞き、もてなしの心得を学んだ。
市川さんは、「抜本的に視点を変えてできることから始めることが大事」とし、日本5大観光地の1つだった“高原の信州”のネームバリューが下がっていること、高度成長期に作った観光のひな型がそのまま残り現在は人が来なくなっていること-などを挙げ、「発想の転換」の必要性を指摘した。
宿泊施設の印象は「予約の電話とチェックインの応対で決まる」とし、泊まってよかったと思える施設に、その土地をよく知っているスタッフの多さを挙げた。「自分の言葉で語れるサービスをどれだけ自分の中に貯められるかを大事にしてほしい。箕輪にしかないこの景観を自慢して。自慢は来た人には素晴らしいガイドになる」と語った。
権兵衛トンネル開通による観光への影響は、長野県の観光がダイナミックになり県外客が来やすくなった-とし、「観光客が滞留するエリアではなかったが今度は1泊するようになる。観光シーズン本番になると、太い帯になって客が来る流れを強く実感すると思う」と話した。 -
危険交差点に反射材設置

交通事故多発交差点の安全対策の一環として駒ケ根署と伊南交通安全協会駒ケ根支会、駒ケ根市交通安全推進協議会は12日、駒ケ根市内の2カ所の交差点に高輝度反射材約50個を設置した。安協役員ら13人が同市赤穂北割二区下の坊と南割区の交差点に出向き、反射材を一つ一つ接着剤で縁石に取り付けた=写真。
反射材は横9センチ、高さ6センチのゴム製。両面が車のライトなどの光に反射して明るく輝くことにより、ドライバーに交差点の存在を知らせるとともに進入速度を抑制させる効果がある。 -
共同募金高額寄付者に感謝状

県共同募金会は駒ケ根市の高額寄付者3人と2団体に感謝状を贈った。12日、代表者ら3人が駒ケ根市役所を訪れ、同会駒ケ根支会長の中原正純市長から感謝状を受け取った。中原市長は「多くの浄財の寄付に感謝する。募金は80%が駒ケ根支会に還元される。社協を通じて市民福祉増進のために使いたい」と感謝を述べた。
感謝状を贈られたのは次の皆さん。
太田秋夫(町四区)竹内寿一(上穂栄)久村良助(小町屋)駒ケ根ライオンズクラブ、駒ケ根ロータリークラブ -
「ぐるっと駒ケ根花めぐりバス」スタート

駒ケ根市内の花の見所をバスで巡る「ぐるっと駒ケ根花めぐりバス」が12日、運行を開始した。早太郎温泉開湯10周年を記念する温泉郷感謝祭の企画として今年初めての実施。前日からの雨の影響などでキャンセルがあり、初日の乗客は1人と少々寂しいスタートとなったが、晴天の下、大沼湖のザゼンソウやミズバショウ、光前寺や吉瀬のシダレザクラなど6カ所を約5時間かけて回った=写真。
バスは週2縲・回、11月19日まで60本運行する予定。サクラが見ごろを迎える4月下旬にかけては予約が集中している日もあるため、市観光案内所は早めの予約を呼び掛けている。
記念事業実行委員会の宇佐美宗夫委員長は「1年目はまず花めぐりバスを知ってもらうことが大事。じっくり育てて来年以降も継続して運行していきたい」と話している。
問い合わせは市観光案内所(TEL81・7700)へ。 -
壮年ソフトボール大会開会式
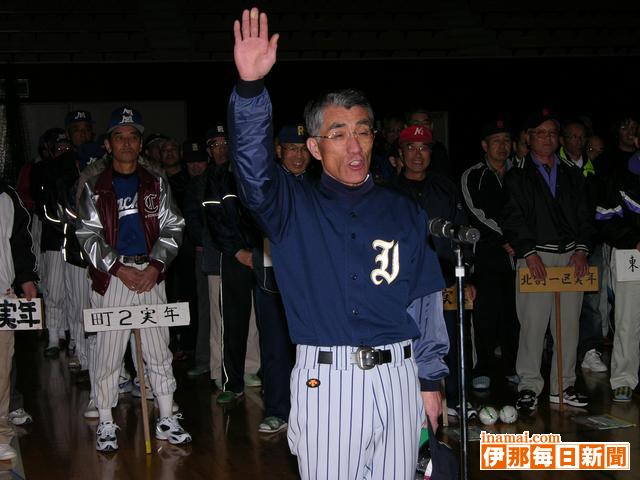
壮年、実年、シニアの3クラスで優勝を争う第24回駒ケ根市壮年ソフトボール大会の開会式が11日夜、駒ケ根市民体育館で開かれた。選手ら約200人が出席し、シーズンの開幕を祝った。選手代表の谷村文敏さん(飯坂実年)は「スポーツマン精神にのっとってプレーし、試合後の慰労会ではとことん反省することを誓う」と宣誓して選手らの爆笑を誘った=写真。主催者を代表して市壮年ソフト連盟の松崎勝治会長はあいさつで「待望の季節がやって来た。勝敗にこだわりつつ年齢、体力に応じて悔いのない元気なプレーが展開されることを期待する」と激励した。
あいにくの雨で予定されていた始球式と開幕試合はお流れ。いきなりの予定変更で今後の試合日程の調整を心配する声も聞かれた。
出場するのは壮年(40歳代)14チーム、実年(50歳代)14チーム、シニア(60歳代以上)12チームの計40チーム。市内4会場で10月まで6カ月の長丁場を戦う。 -
宮田小交通安全教室

宮田村の宮田小学校は12、13日、交通安全教室を開いている。各学年ごと歩行や自転車で路上に出て、正しいルールを再確認。事故に遭わないよう、判断力なども養った。
学校周辺を巡るコースで、1、2年生は歩行、3年生以上は自転車で走行した。
そのうち初めて路上の自転車走行が許される3年生は、基本的な乗り方から学習。村駐在所の雨宮則彦所長から、発進、停止、方向指示の出し方などについて説明を受けた。
実際に自転車に乗って練習。ブレーキのかけ方など不慣れな姿もみられ、教諭や雨宮所長からアドバイスを受けていた。
3年生には今後、保護者の許可を得て免許証が改めて交付される。 -
手づくり弁当広げて、桜の下で春を満喫

宮田村の心の病と向き合う当事者グループ「さくら」と村福祉作業所の30人は12日、中川村の大草城址公園に足を運び、花見を楽しんだ。出発前に全員で弁当を手づくり。咲きほこったサクラの下で舌鼓を打ち、春を満喫した。
ビンゴゲームなど楽しみながら、バスで到着した一行。ピンクに染まった木々の鮮やかな姿に「きれいだねぇ」と目を輝かせた。
さっそくシダレザクラの下に陣取り、宴(うたげ)を開始。自分たちでつくったおにぎり、唐揚げ、卵焼きなど色鮮やかな弁当を広げた。
花をめでながら、食欲もモリモリ。ポカポカ陽気にも包まれ、時間を忘れて談笑していた。
さくらは毎年花見を行っているが、弁当持参は初めて。「いつか桜の下でお弁当広げたいね」と話し合っていただけに、今回の花見は格別な様子だった。 -
みやだ夏祭り7月16日に決定
今年で17回目を迎える宮田村の「みやだ夏祭り」の開催日が、例年通りに祇園祭翌日の7月16日に決まった。11日夜に関係者が集まって確認し、慣例に従って大会長は村長、実行委員長は商工会長が就くことも決定した。
村長、助役、議長、農協、商工会、区長会、むらおこし事業実行委員会、祇園祭総代ら関係者が懇談した。
今まで参加団体や区長会などで話し合ってきた内容を説明。
踊りが主体の祭りについて、将来的な活性化の注文はあったが、今回は従来通りの日程で継続することに意義はなかった。
今後は4月下旬に実行委員会を立ち上げて、細部を煮詰める。
また、活性化に向けて実行委メンバーを新たに公募するほか、新規の参加団体も積極的に募る考えで、近く全戸にチラシを回覧する。
同夏祭りは前回2年前から隔年開催になるなど、変化もみられるが、実行委員会事務局の村産業建設課は「若者などより柔軟な発想、意見を吸いあげていきたい」と幅広い参画を求めている。
問い合わせなどは同課85・5864まで。 -
伊那ビジネス専門学校で入学式 目標に向かってまい進

伊那市狐島の伊那ビジネス専門学校(三沢岩視理事長)で12日、06年度の入学式があった。上伊那を中心に飯田市から生徒5人が入学し、それぞれの学校生活をスタートした。
入学生代表で堀内志織さん(18)=辰野町=が「自覚と誇りを持って校則を守り学業に専念する」と宣誓。三沢理事長は「すばらしい職場に就職できることを期待する」と式辞し、三沢清美校長は「大きな目標に向かってまい進してほしい」と訓辞を述べた。
新入生5人は情報経理学科(2年制)に2人、OAビジネス学科(1年制)に3人が入学。
伊那ビジネス専門学校は個性を重視しながらビジネスマナーを心得た社会人を育成することが理念。少人数教育でパソコンや簿記などを学び、就職に有利な各種資格を習得することができる。 -
タカトオコヒガンザクラ今日にも開花宣言
「天下第一の桜」とうたわれる伊那市高遠町の高遠城址公園に植わるタカトオコヒガンザクラは、ここ数日の冷え込みなどの影響で予想より開花が遅れていたが、13日にも開花宣言が出される見込みで、町観光協会は週明けごろが見ごろとみている。
城址公園には連日、全国各地からツアーバスが訪れ、12日には城址公園下のバス専用駐車場(80台収容)は午前10時ころから満車状態が続いたが、開花状況によって日程を設定できないツアー客からはため息がもれる状況となっている。
茨城県から訪れた女性(60)は「知り合いから高遠の桜は素晴らしいと聞いて今回初めて来たが、咲いていなくて本当に残念。また、来年を楽しみにしています」と話していた。
それでも園内では、つぼみの桜の木をバックに記念撮影をするグループや、ゴザを敷いて食事を楽しむ家族連れなどの姿が見られた。 -
かんてんぱぱガーデンカタクリ咲く

伊那市西春近のかんてんぱぱガーデンでは、春の山野草が咲き始めた。約200株あるカタクリは、このところの暖かさで一気に開花し、見ごろを迎えている。
今年のカタクリは、開花が例年より1週間から10日ほど遅かったため、ほかの山野草と開花時期が重なった。 現在見ごろを迎えているのは、ミズバショウ、ワサビなど。青紫色の花をつけるタツタソウ、葉がうちわに似ているイワウチワなども咲き始め、園内は春の色彩で溢れている。
同園には80種類以上の山野草があり、今後は、シラネアオイ、ニリンソウ、クロユリなどが、徐々に咲いていく。1週間ほどすれば、別の種類の花が咲き始めるという。 -
諏訪形寿健康体操クラブ本年度活動開始

伊那市西春近の「諏訪形寿健康体操クラブ」(会員25人、野溝弘文会長)は12日、本年度の活動を開始した。
市の高齢者介護課の「高齢者向け筋力向上トレーニング教室」として04年に開講。市の教室指導修了後も参加者の要望にこたえ、地区活動の一環として継続している。
高齢者や軽度の障害を持つ人のうち、簡単な筋力トレーニングで日常生活の維持・改善が期待できる人を対象とし、平均年齢は約75歳。参加者は年々増加している。4月縲・1月に活動している。
初日は、伊那保健センターのインストラクターの指導のもと、筋力トレーニングや有酸素運動を組み込んだ体操に挑戦。仲間と共に、体力づくりを楽しんだ。
昨年12月にあったアンケートでは、約75%が体操を始める以前より「体調が良い」と回答。楽しいので継続したい竏窒ニする意見も多かった。 -
箕輪町町道 落石で1・3キロの全面交通止めに

11日、箕輪町東箕輪の町道で落石があった。同日午後9時ころ、現場を通りかかった町消防署員の通報で分かった。町では危険性があるとして午後10時から12日午前9時30分までの間、同町道の箕輪ダム入口付近から長岡区イベント広場入口の約1・3キロを全面交通止めにした。落石によるけが人はいない。
町などは12日午前8時ころから、道路に広がった落石を取り除き、落下場所には「落石注意」の看板を設置した。
落石は道路に面した斜面の約50メートル上方にある、土留のための石垣(幅5メートル、高さ1メートル)の一部が崩れたのが原因。石の大きさは直径約30センチで、15縲・0個が落下。町職員によると長い間の雨で地盤がゆるんでいたのではないかという。 -
伊那市美篶の上川手区 「地域の子どもを守り育てる会」発足

伊那市美篶の上川手区(北原伍区長)は11日夜、地元公民館で地域の園児、児童、生徒の登下校時の安全などを見守る「地域の子どもを守り育てる会」(春日照子会長)の発足式を開いた。会場に集まった約100人の地域住民は、子どもたちが健やかに育つ環境をつくっていくことを決意した。
同会はパトロールという管理的な取り組みではなく、区民総参加で「普段着のスタイルで子どもの安全を見守る雰囲気づくり」などを目的に活動。具体的には、登下校時間帯に合わせて区民が・ス子どもたちの見える場所で・ス農作業や散歩などをして安全を確保する。
美篶地域では昨年末、笠原地区で初めて「地域の子どもを守り育てる会」が発足。同会会長で美篶青少年育成会の畑房男会長は「他地域では学校ごとにパトロール隊を立ち上げているが、美篶の場合は住民が立ち上がり、美篶全体に広がっていけばと考える」と呼びかけた。
あいさつに立った美篶小学校の片山寛教頭は「美篶地域の12地区が一体となり、自分の地区はぜったい安全に通学させてやるという、連帯感をつくってほしい。それが世の中を変えるきっかけになる」と期待した。
2010/(月)
