-
小学生の税についての書道作品を審査

伊那地区納税貯蓄組合連合会(坂井武司会長)は18日、伊那市の伊那公民館で、上伊那の各小学校から募集した、税についての書道作品を審査した=写真。租税教育の一環で、88年から続く同連合会独自の事業。4年生以上を対象に募り、37校から5270点(前年比72点増)が集まった。
連合会や税務署などの関係者18人が審査し、各校ごと金賞1点、銀賞1縲・点(出品数100点ごと1点)を選出した。連合会女性部長の大石節子さんは「字のはねや止め、バランスや力強さの部分を審査する。昨年よりも応募数が増えてうれしい」と話した。
課題は学年ごと異なり、4年が「ぜいきん」、5年が「税金」、6年が「納税」。夏休み中の宿題として児童たちは取り組んだという。入選作品は、11月中旬の「税を考える週間」に合わせ、各市町村ごと伝達表彰、展示する予定。
各小学校ごとの結果は次の通り。
◆辰野南▽金賞=尾坂裕司(6年)▽銀賞=穂苅祐奈(6年)◆辰野西▽金賞=野沢志帆(6年)▽銀賞=丹羽まどか(6年)畑瑠衣菜(5年)◆辰野東▽金賞=石倉佳奈(5年)▽銀賞=有賀麻依(6年)小松勇樹(5年)◆川島▽金賞=小沢瑞樹(6年)▽銀賞=根橋真那(6年)◆両小野▽金賞=丸山恵夢(6年)▽銀賞=飯嶋雪乃(4年)小沢夏子(6年)◆箕輪中部▽金賞=今井南貴(6年)▽銀賞=濱中愛美(4年)中林美夏(5年)大沼尚平(5年)北條隆祐(5年)◆箕輪北▽金賞=唐沢桜(6年)▽銀賞=山崎久樹(4年)児玉貴之(5年)◆箕輪西▽金賞=釜屋良美(5年)▽銀賞=小嶋穂乃花(4年)◆箕輪南▽金賞=中谷昭太郎(6年)▽銀賞=渡部優太(4年)◆箕輪東▽金賞=柴知世(5年)▽銀賞=原すずか(4年)◆南箕輪▽金賞=春日美緒(6年)▽銀賞=有賀睦(5年)原風音(6年)原志門(5年)戸田あやな(4年)◆南箕輪南部▽金賞=林真言(6年)▽銀賞=斉藤優香(4年)福田一貴(6年)◆伊那▽金賞=北沢隆三(6年)▽銀賞=小林佳奈(6年)中村詩穂(5年)飯島史歩(5年)小松晃(4年)◆西箕輪▽金賞=吉江ひかり(5年)▽銀賞=岩谷咲奈(4年)有賀有理(6年)◆伊那西▽金賞=網野ゆたか(5年)小池真里奈(5年)◆伊那東▽金賞=小木曽巧朗(6年)▽銀賞=赤羽真弥(4年)井上愛実香(5年)近江鮎香(6年)高橋美朱樹(6年)◆伊那北小▽金賞=里見はるか(5年)▽銀賞=渡辺彩葉(4年)猪川美知恵(6年)松沢梨沙(6年)◆富県▽金賞=伊沢桃(6年)小牧薫(4年)◆新山▽金賞=寺沢徳子(6年)▽銀賞=六波羅聡美(6年)◆美篶▽金賞=白鳥満帆(5年)▽銀賞=若林千秋(4年)渋谷友里乃(6年)◆手良▽金賞=荒井実季(6年)▽銀賞=西沢彩(6年)◆東春近▽金賞=下平晴彦(5年)▽銀賞=笹谷恵莉(4年)大脇愛菜(6年)◆西春近南▽金賞=小田切柚(5年)▽銀賞=北林末希(4年)◆西春近北▽金賞=中谷梨沙(6年)▽銀賞=竹内杏希望(4年)小田部空(5年)◆高遠▽金賞=小松みか(6年)▽銀賞=竹松祐子(4年)◆高遠北▽金賞=伊藤佳央(6年)▽銀賞=北原綾佳(6年)◆長谷▽金賞=伊藤千夏(6年)中島大希(6年)◆宮田▽金賞=下平まどか(6年)▽銀賞=倉田光輝(5年)市瀬里緒(6年)吉水梨紗(4年)斉藤輝(6年)◆赤穂▽金賞=坂佳純(6年)▽銀賞=竹沢萩野(6年)山林安優美(5年)芦部瑞穂(6年)唐沢里菜(4年)◆赤穂東▽金賞=今井美月(6年)▽銀賞=松崎瑠音(4年)長島花奈(5年)勝又文香(6年)◆赤穂南▽金賞=芦部夢乃(6年)▽銀賞=青木崚(6年)森岡里奈(5年)◆中沢▽金賞=下平真美(5年)▽銀賞=林華夏子(6年)◆東伊那▽金賞=福沢弘樹(5年)▽銀賞=赤羽佳子(6年)◆飯島▽金賞=初崎采佳(6年)▽銀賞=熊谷真希(6年)山谷聖也(5年)袖山慎二郎(4年)◆七久保▽金賞=上原杏奈(6年)▽銀賞=上山千夏(4年)◆中川西▽金賞=荒井麻有(6年)▽銀賞=丹羽優花里(6年)◆中川東▽金賞=高木香代(6年)▽銀賞=三石有貴(6年) -
伊那市の女子ソフトボールチーム「サンフラワーズ伊那」
伊那市のソフトボールチーム「サンフラワーズ伊那」(野溝和男監督)は、22竏・5日、青森県三沢市で開かれる、第20回全国スポーツ・レクリエーション祭の女子ソフトボール競技に県代表として出場する。スポレク祭への参加は8年ぶり5回目となる。
「サンフラワーズ伊那」は、本年で創部33年目。監督の野溝和男さん、妻で現役選手の和子さん=ともに西春近=が発足した市内の古豪チームだ。これまで「レディース」(18歳以上)「エルダー」(35歳以上)「エルデスト」(50歳以上)のほか、スローピッチなど各種大会で活躍してきた。
ソフトボール経験者から入部後に競技を始めた人までの18縲・2歳の約20人で構成し、週2回の練習でチームワークを磨いている。ここ2、3年で10縲・0歳代の若手選手が加わり、チームは活性化した。中には、親子でバッテリーを組んでいるメンバーもいるという。
72歳で現役の野溝和子さんは「チーム名のサンフラワー(ヒマワリ)の花言葉のように強くて、明るいチーム。チームワークはよく、最近は粘り強さも出てきた」。
全国スポーツ・レクリエーション祭は、勝敗のみを競うのではなく、気軽にスポーツを楽しみ、交流を深めることが目的。1988(昭和63)年から各都道府県持ち回り方式で毎年開催される生涯スポーツの一大祭典だ。
女子ソフトボール競技は、35歳以上(エルダー)の選手が対象。「サンフラワーズ伊那」は、本年5月中旬にあった県エルダー大会で上位成績を収め、県協会の推薦により5回目の出場を決めた。48縲・2歳のメンバー11人が参加する。
競技は各都道府県代表が集まり、予選リーグ、決勝トーナメントを繰り広げる。「サンフラワーズ伊那」は初戦、高知県と茨城県の勝者と対戦する。
主将の渡辺久栄さん(52)=東春近=は「攻守のバランスが取れたチーム。コントロール重視のエースを中心とした堅実な守備と、上位から下位までまとまって打てる打線が特徴。参加する以上は優勝する意気込みで頑張ってきたい」。
また、「サンフラワーズ伊那」は、10月12縲・4日、伊那市内6球場である、50歳以上の選手による「第6回全日本エルデスト大会」に県代表として出場する。全国から38チームが集まり、トーナメントを展開。初戦は青森県代表「青森ねぶた」と戦うことが決まっている。 -
第117回秋季北信越高校野球県大会 22日開幕
第117回秋季北信越高校野球県大会は22日に開幕し、県営上田野球場、長野オリンピックスタジアム、小諸南城公園野球場の3会場である。県内4地区の各予選を勝ち抜いた計16校が、上位3校が出場できる北信越大会(10月13竏・6日・福井県)を目指して戦う。
組み合わせ抽選会は18日、県校野連事務局の屋代高校であり、別表の通りに決まった。地球環境(東信3位)、小諸(東信4位)が初出場のほか、久々の県大会となる学校もある。
3季ぶり優勝、2季連続の出場となる辰野の初戦は小諸が相手。勝ち進めば松本美須々(中信3位)と飯山南・飯山(北信2位)との勝者と戦う。南信3位で4季ぶりの出場を決めた伊那北は、松本工業(中信2位)と対戦。勝てば中野西(北信4位)と佐久長聖(東信1位)の勝者と顔を合わせる。
24日休養日、27日予備日の日程で繰り広げ、順調に消化すれば25日に準決勝、26日に決勝と3位決定戦がある。 -
駒ケ根市町二区市政懇談会

駒ケ根市の町二区(柏原孝従区長)は18日夜、中原正純市長や市の職員らを招いての市政懇談会をふれあいセンターで開いた。区民約50人が参加し、市政に対して日ごろ感じている疑問や要望などをぶつけた=写真。
自治会への未加入者が多い現状と今後の加入促進対策について質問が出たのに対し清水亀千代総務部長は、町二区の1323世帯中、未加入は941世帯で加入率は71・1%竏窒ニ説明した上で「市全体としても大きな課題。現在、転入者に対してチラシを手渡したり口頭で加入を強く呼び掛けるなどの対応をしている。策定中の『まちづくり基本条例』では市民の責任を明確に示したい」と述べた。
給食費の滞納が上伊那の中でも多いといわれる問題についての質問に対し滝沢修身教育次長は「滞納率はともかく金額は確かに多い。教育委員会として滞納整理に当たっているが、今後は一度滞納したら現金で支払ってもらうこととしたい。給食費は税金ではないので差し押さえなどはできないが、収納率を上げる体制を整えていきたい」と回答した。 -
伝統工芸士作品コンクール特賞

1910(明治43)年に創業し、伊那紬(つむぎ)のブランドで全国に知られる駒ケ根市の久保田織染工業(久保田治秀社長)の着物作品「夕暮霧雨」=写真=が、9月に行われた第7回関東伝統工芸士会作品コンクール(関東伝統工芸士会主催)で最高賞に次ぐ特賞に選ばれた。同社の作品は昨年の同コンクールで初入賞を果たしたが、特賞の受賞は初めて。
「手技の夏」をテーマに行われたコンクールには関東地区の紬産地から31点が出品され、作品の出来栄えが審査された。「夕暮霧雨」は、霧雨の降る湖が次第に暗くなってゆく夕暮れの様子を表現したという。久保田社長は「織り方や糸の作り方にもこだわって仕上げた柔らかい手触りと風合いこそが、よそにはないうちの品の特徴。化学染料とは違う草木染めの色も深みがある。さらに良い作品を作って、来年は最高賞を狙いたい」と話している。 -
伊那中央病院の施設改修の必要性を確認
地域の安定的な医療確保を図るため、医療問題を研究し、解決案を検討する上伊那医療問題研究会の第2回会議が18日夜、駅前開発ビル「いなっせ」であった。医師不足に伴う産科問題対応で、伊那中央病院(伊那市)の施設改修の必要性を確認した。
来年4月、昭和伊南総合病院(駒ケ根市)の常勤産科医がいなくなることから、産科診療を休止せざるを得ない状況で、受け皿として中病が施設整備を検討。陣痛待機室や分娩(ぶんべん)室の増設、監視モニターの設置など病棟改修に加え、パンク状態になっている外来診察室を増築する必要がある。改修費用は1億200万円と試算する。
中病を運営する3市町村以外の市町村関係者から「喫緊の課題。中病の増設をお願いしたい」「住民に不便を来たさないようにしてほしい」など改修を求める声が挙がった。
施設改修に対する県の財政支援はない。費用負担は課題で、中病だけに任せるのではなく、上伊那医療圏の問題として考えることにした。県にも助成を要請していく。
昭和病院は来年4月以降、非常勤医師が検診で対応し、中病で出産する方法を調整中。院内産院設置の可能性も検討しているが「医師がいないと難しい」としている。
委員は公立3病院事務長、各市町村担当課長、上伊那医師会事務長らで、今回から消防組合関係者を加えた。
次回は10月上旬を予定している。 -
07年地価調査結果を公表
県企画局は19日、07年地価調査の結果を公表した。上伊那では、住宅地、商業地とも平均変動率が下落。下落幅が最も大きかったのは辰野町で、住宅地で4・1%、商業地でマ5・5%のマイナスとなった。
調査は07年7月1日を基準日として県内の469地点(上伊那では38地点)で実施。
各市町村の下落率は住宅地で伊那市2・3%、駒ケ根市2・4パーセント、辰野町4・1%、箕輪町2・7%、飯島町1・7%、南箕輪村1・7%、中川村0・2%、宮田村2%、商業地で伊那市5・4%、駒ケ根市4・6%、辰野町5・5%、箕輪町4・8%、飯島町2・7%、南箕輪村4・5%(基準地のない中川村と選定替を行った宮田を除く)竏秩B県平均は住宅地2・3%、商業地3・1%の下落となっている。
下落幅が最も大きかったのはマイナス5・5%だった辰野町宮木区の商業地域で、基準値1平方メートル当たりの価格は4万4600円。次いで下落率5・4パーセントとなったのは伊那市山寺区八幡町の商業地域と同市下新田区の商店地域で、それぞれの基準値1平方メートル当たりの価格は6万7900円、5万5900円となっている。 -
三日町の介護予防拠点施設完成
名称「げんきセンター南部」に箕輪町が三日町のデイサービスセンターゆとり荘南側に建設していた介護予防拠点施設が完成し、公募により名称が「げんきセンター南部」に決定した。18日の町議会全員協議会で町が報告した。
名称の応募総数は56件。「げんきセンターは町民へも浸透しており、シンプルでわかりやすく、親しみやすい」という理由で選定したという。
新施設の整備は、06年度地域介護・福祉空間等整備事業。高齢者らの健康を増進するため、体力づくりと寝たきり予防の知識を普及し、高齢者の自立と生活の質を確保し介護予防を推進する目的。
筋力トレーニング機器を配備し、みのわ健康アカデミー卒業生の継続トレーニングと、町民を対象に一般開放し健康づくりの推進を目指す。アカデミー卒業生が「みのわ健康サポート隊」として運動指導をサポートするほか、介護予防についての講座を開く。10月、みのわ健康サポート隊結団式(開所式)を開く予定。
施設の建築面積は241・60平方メートル、鉄骨平屋建て。事業費は5287万9480円(補助4914万円)。
トレーニングルーム、受付・事務室、トイレ、更衣室(男・女)、休憩スペース、倉庫があり、床暖房をトレーニングルーム、ホール、事務室、トイレ、玄関に設置。高度大成分分析システム機器1台、トレーニング用のバイク5台、トレーニングマシン6台などを設置している。 -
宮田観光開発依然として赤字も収益改善
4期連続の赤字から脱却し黒字への転換を目指している宮田村の第三セクター宮田観光開発(社長・清水靖夫村長)は19日、4月から7月までの経常収支が1137万円の赤字だったと明らかにした。一方で赤字額は前年同期に比べ44・7%縮小し、常勤役員報酬の50%カットや購入物品の仕入原価の削減など、収益改善策の効果も現れており、村民を優待するなど、伸び悩む客の獲得へ力を注ぐ。
経営する観光ホテル、温泉施設のこまゆき荘、中央アルプスの山荘の利用客総数は、日帰りが前年同期比約10%増の4763人。しかし、宿泊は6355人と逆に1割ほど減っている。
より客単価が高くなる宿泊客の減少は売り上げ面の苦戦に直結。8月までで観光ホテルは前年同期に比べ548万円売り上げが減っており、こまゆき荘も40万円ほど減らしている。
山荘は815万円ほど増やしており、他の減少をカバーする格好にもなっている。
ただ、7月末から開設したホームページの予約が1カ月余りで150件にのぼるなど好調。
団体ツアーに頼らない個人客の獲得に向けた取り組みも徐々に効果を現しているといい、シーズンオフの誘客も含めて改めてサービスのてこ入れを図る。
また、収益改善を受けて、村民に温泉入浴の割引券を配布し、より地元に親しんでもらう施設運営も目指す。 -
北割区の高齢者死亡の交通事故受けて現地診断

宮田村北割区の広域農道交差点でバイクに乗った近くの女性=当時(88)=が出会い頭にトラックと衝突し死亡した8月9日の交通事故を受け18日、再発防止に向け現地診断が行われた。警察や地元関係者のほか、高齢者の事故という点を重視し、村内の高齢者クラブも参加。身体機能の衰えによる運転自粛など、周囲も含めた自覚と意識の徹底を中心に意見を交わし、安協宮田支会は高齢者への声かけ訪問を全村で実施する考えを示した。
現場は一時停止標識が設置された見通しのよい交差点。バイクの女性は農道を東から西に横切ろうとして、伊那市方面に向っていたトラックと衝突した。
診断で山本修作駒ケ根署長は「高齢の方が自ら決断して運転をやめるのは難しい。これ以上無理だと判断したら家族、地域の人が止めてほしい」と指摘。
県警中南信運転免許センターの小林富勇所長は今年の県下交通事故による死者の半数が65歳以上と報告した。
さらにその半数近くが車やバイクを運転していて事故に遭ったと示し、「今回も県下で多発しているパターンと同じ」と語った。
席上、安協宮田支会の橋爪利夫支会長は21日から始まる秋の交通安全運動期間中に、啓発チラシを全戸配布し、高齢者宅へは各地区の会員が訪問して声かけを行うと説明。
宮田村駐在所は、村内全区長に高齢者参加のミニ集会開催を呼びかけており、今回の事故や免許と身体機能の関係などについて、お年寄りと直接対話していきたい考えだ。 -
公民館ヨガ教室が閉講

宮田村公民館のヨガ教室は19日、8回に渡る本年度全日程を終え閉講した。約30人が3カ月余りに渡って自身の体と向き合ったが「今後も続けていきたい」と好評だった。
国際ヨガ協会伊那学園の三澤裕子さん、壬生美代子さんを迎えて2年目の講座。女性にまじって男性の参加者もあり、呼吸しながら体をストレッチするヨガの世界にふれた。
この日も心地良い汗を流し、最後に三澤さん、壬生さんは「継続が力になる。これからも続けていって」と呼びかけた。
受講者の有志からは、自主サークルをつくって活動を継続しようという話しも。
公民館は来年度も開講を予定している。 -
新設の環境担当係長に浦野氏、地球温暖化対策を強化
宮田村は19日、10月1日付けの人事異動を内示した。地球温暖化対策を強化するため、住民福祉課住民生活係に環境担当係長を新設。浦野康之氏(45)が総務課企画情報係から昇格し、就任する。
村の環境基本計画の策定などを控えており、世界的な問題でもある温暖化対策の責任者として担当。浦野氏は「今までとは違う分野の業務だが、大切な問題であり頑張って取り組みたい」と話した。
その他の異動内示者は次の通り。カッコ内は旧職名。
▽総務課企画情報係=松下宏(住民福祉課住民生活係)▽住民福祉課住民生活係=紫芝恵美(教育委員会付) -
南極の氷が飯島小、中に届く

南極の氷が届いたよ-。飯島町の飯島小学校と飯島中学校に19日、南極観測船「しらせ」が南極から運んできた貴重な南極の氷が届き、子どもたちを喜ばせた。
このうち、飯島小学校では体育館で全校児童に披露。子どもたちはクーラーボックスから取り出された縦10センチ、幅20センチほどの氷の固まりを見て「わあ、すごい!」と歓声を上げた。
氷は町出身で飯島町中町在住の自衛隊長野地方協力本部、伊那地域事務所の松田千眞男さんらが持ち込んだ。
松田所長は飯島町担当の山浦和之さんと2人で訪れ、贈呈を前に、児童らにスライドを使って南極について話した。
この中で、松田所長は「南極観測船『しらせ』は11月に出発し、オーストラリア経由で1カ月掛かって南極の昭和基地に到着する。南極ではオゾン層や地質、生物について研究している」と説明。南極にすむクジラやアザラシ、ペンギンが紹介されると、子どもたちは興味津々の様子で画面に見入った。オーロラの写真には「きれい!」「オーすごい!」と感嘆の声が上がった。
同校ではこの氷は理科の実験などに使う計画。 -
上伊那地域犯罪被害者実務者担当者会議

上伊那地域犯罪被害者実務者担当者会議が21日、伊那市の県伊那合同庁舎であった。県や市町村担当者などが集まり、犯罪被害者などの置かれている状況などについて理解を深めたほか、地域の連携強化について話し合った=写真。
同会議は犯罪被害者の支援に携わる関係機関の連携強化と担当職員の理解増進を目的として県内10地域で開催している。
研修では、犯罪被害者の置かれている状況や犯罪被害者を支援するための国や県の制度や対応についての説明があり、長野県警の女性被害犯罪捜査指導係の藤原久子さんは性犯罪被害者などの傾向から「被害に遭った人たちは事件の後、自分に対する無力感や自責感などから引きこもりがちになってしまう傾向にある」と説明。被害者と接する上では被害に遭った時に感じたような二次被害を与えないよう、被害者に対する思い込みを払拭することが重要であることなどを示した。 -
梅戸神社例祭にぎやかに

)
五穀豊じょうを祈る飯島町の梅戸神社の秋祭りが15日宵祭り、16日、本祭りでにぎやかに行われた。
飯島町飯島の9耕地から子ども、大人合わせて約400人がJR飯島駅前に集合。
高張提灯を先頭に、丸提灯を付けたササを持った子どもたちが続き、広小路を「ピッピ」「ワッショイ、ワッショイ」と練り歩き、提灯が点る参道に。耕地ごと拝殿に向かって、鈴を鳴らし参拝し、万歳三唱をした。
この後、神殿では厳かに巫女による「浦安の舞」の奉納。
また、飯島運動場では花火大会、次々と打ち上げられる大小の花火が夜空を彩った。 -
わが町を花で美しく

秋花壇の主役は鮮烈な黄色のマリーゴールドと真紅のサルビアである。縁取りや模様付けに使われる青紫色のアゲラタムは名脇役、その3種類の花だけで構成した飯島文化館のプランター花壇、今年も金賞に輝いた。マリーゴールドやサルビア、アゲラタム、センニチコウ、インパーチェンスなど色とりどりの花を咲かせる「岩間花の会」は長年の苦労が報われ、初の町長賞に輝いた。飯島町の「わが町は花で美しく」推進機構(花機構)の「花のある風景づくりコンクール」には個人の部5点、地域の部13点、事業所の部3点の合わせて21点がエントリーした。この中から、町長賞、金賞、銀賞、努力賞など受賞花壇を紹介する(大口国江)
##(中見出し)
「わが町は花で美しく」推進機構(花機構)
「花咲く美しいわが家・わが町」運動を展開し、住みよい町、美しい環境の町づくりを進めるとともに、花情報の発信などを通して町の活性化を図ることも目的に94年3月に発足した。事業は「花のある風景づくりコンクール」のほか、8月12日の上伊那で最大規模を誇る「いいじまはないち」、オープンガーデン、花のある絵募集などを行なっている。
##(写真)
【町長賞の岩間花の会】「花の種類が多く、それぞれの性質を考えながら植栽した。雨が降らなかったが、マリーゴールドはきれいに咲いて良かった(羽生冨喜江さん)」
【事業所の部金賞・飯島文化館】「駐車場から正面玄関まで長いので、花のプロムナードという雰囲気で、プランター300個を並べた。各列ごと管理者を決め、責任を持って管理している(唐沢隆さん)」
【地域の部金賞・田切公民館】「植え付け作業には子どもから大人まで百人余が参加した。作業を通じて、世代間を超えた交流の場にもなっている(井口明夫さん)」
【地域の部金賞・北河原耕地福地・街道端耕地】「初期の成長管理や追肥に配慮した。バックのネギ畑とのコントラストにも工夫した」
【個人の部金賞・土村幸子さん】「メーンのゼラニュームは暑さに負け、花数が少なく残念。色々の種類の花を1度に咲かせるのは難しい」
【個人の部銀賞・岩田典さん】
地域の部銀賞・本六老人会育成会】
【事業所の部銀賞・飯島町社会福祉協議会石楠花苑】 -
第35回伊那まつり写真コンテストで蜷川さんの作品が推薦

伊那まつり実行委員会は18日、「第35回伊那まつり写真コンテスト」の審査会を伊那市役所で開き、応募総数88点の中から伊那市の蜷川靖子さんの作品「赤いハチマキ 赤い扇」を最高賞の推薦に選んだ=写真。
昨年は伊那まつりが中止となったため、写真コンテストも2年ぶり。今年の伊那まつりを撮影した作品を一人5点までで募集したところ、上伊那在住の22人の応募があった。
審査には、同委員会総務・広報委員会のメンバーのほか、実行委員長やカメラ関係者など7人が参加。▽伊那まつりであることが分かること▽楽しげな雰囲気が伝わってくること竏窒ネどを見ながら、入賞作品5点、入選作品20点を選出した。
審査に加わったマスダカメラの増田稔さん(46)は「推薦の作品は、あちら側の列の踊りの様子を手前側の列で踊る小学生らが休みながら見学している。構図的にも面白いしバランスもいい」と話していた。
今回の応募作品は25日から10月5日まで市役所1階の市民ホールに展示するほか、入賞作品は来年度のまつり用パンフレットなどに用いられる。
入賞者は次のみなさん。
◇推薦=蜷川靖子(伊那市日影)
◇特選=酒井幸一(伊那市西春近)
◇準特選=加藤平治(南箕輪村田畑)久保田昌弘(伊那市西箕輪)牛山理(伊那市西町) -
第1回日本工業大学マイクロロボコン高校生大会で優勝
箕輪工業高校1年
井上大樹君(16)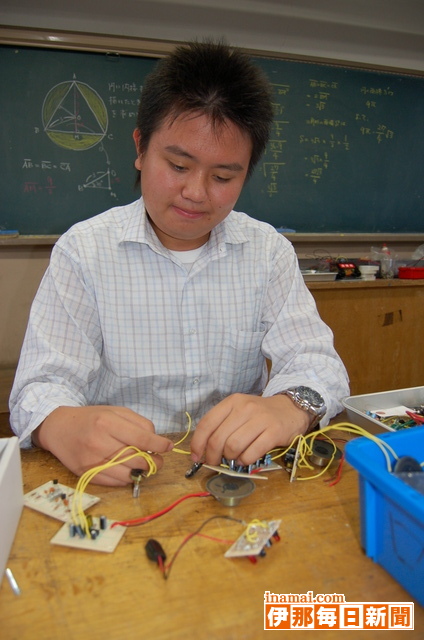
初めてのロボット作りは楽しかった竏秩B
今月1日、日本工業大学(埼玉県)が開催した「第1回日本工業大学マイクロロボコン高校生大会」に自身で製作したマイクロロボット“Robot Industries1号”とともに出場。全国から集まった約100台のロボットを抑えて優勝した。
大会は2・54センチ角しかない“1インチロボット”がコースを周回するタイムを競い合うというもの。競技者は主催者から事前配布されたキットを使ってロボットを製作し、中に組み込むマイクロコンピューターを調節して、黒いケント紙の上に描かれた5ミリ幅の白いラインの上を正確かつ迅速に追跡するようにしていく。
「優勝できるとは思わなかったので、嬉しい」と笑顔を見せる。
◇ ◇
“ロボコン”ってどんなことをやっているのだろう竏秩Bそんな興味から、友人2人を誘って大会へのエントリーを決め、8月上旬からロボット製作を開始した。ロボット製作は初めてだったが、電子工作などではんだ付けなどは経験したこともあり、ほどなくしてロボットは完成した。早速動かしてみようとスイッチを入れたが、動かない。もともと大学から配布されたキットは、ただ組み立てただけでは動かない代物。そこからプログラムを調整する作業が始まった。
最初は動かないロボットを動くようにするにはどうすればいいか、次は少しずつ動くようになったものを早く走らせるには竏窒ニ、考えながら、調整用のコースを何度となく走らせた。
「どう走らせればいいのかということを考えて、プログラムを作るのは初めての経験だった。やっているうちに新しい発見もあり、動くようになるマシーンを見るのが喜びになった」と振り返る。
◇ ◇ -
伊那区域を基準に、上下水道料金を改定
伊那市の上下水道事業運営審議会(福沢良一会長、18人)が18日、浄化監理センターであった。合併に伴う水道料金・下水道使用料の改定について、算定方法の統一と段階調整を諮問。伊那区域に変更はなく、高遠町・長谷区域は伊那区域との差額の2分の1を目安に詰める。答申は10月中旬を予定。
水道料金は、合併協議で「現行のまま新市に移行し、合併後6年目(11年度)から統一料金とする。住民負担の急激な変化を避けるため、段階的に調整する」となっている。昨年度の審議会で、伊那区域の料金を基準に、08、11年度の2回で統一することを確認している。
小坂市長から諮問を受けた委員は諮問内容を協議。上下水道事業の経営状況の報告も受けた。
一般家庭(4人家族)の標準的な使用水量(1カ月約20立方メートル)の上水道料金は伊那が3280円で、高遠町が現行に比べて56円増の3210円、長谷が304円増の2970円とする。伊那区域と同じ算定とするため、高遠町・長谷の基本料金に口径を新たに設けた。下水道使用料は伊那が3100円で、高遠町が118円減の3300円、長谷が78円減の3350円。口径別、使用水量によって増減がある。
06年度実績をもとにした改定後の試算(2カ月分)は、上水道料金が660万円、下水道使用料が500万円の増額をそれぞれ見込む。
高遠町・長谷の地域協議会で水道料金の改定案をそれぞれ説明する。
答申後、市議会12月定例会に条例改正を提案。可決されたあと、住民に周知し、来年4月から施行する。
06年度末の滞納額は1億7500万円。滞納する理由がないなど悪質なものが多い。 -
南信高校新人体育大会陸上競技結果
◆南信高校新人体育大会陸上競技結果(14竏・6日・県松本平広域公園)=1位と上伊那関係分
【男子】
▼100メートル(1)三村瑞樹(伊那北1)11秒21(3)松沢ジアン成治(高遠1)11秒44(4)赤沢侑生矢(駒ヶ根工業2)11秒58(5)唐沢和也(伊那弥生2)11秒62(7)平沢快嗣(伊那弥生2)11秒64(8)村井大介(駒ヶ根工業2)11秒74▼200メートル(1)伊藤圭司(下諏訪向陽2)22秒31(2)三村瑞樹(伊那北1)22秒33(3)唐沢和也(伊那弥生2)22秒80(5)平沢快嗣(伊那弥生2)23秒19(7)安藤太郎(伊那弥生2)23秒41(8)松沢ジアン成治(高遠1)25秒46▼400メートル(1)伊藤圭司(下諏訪向陽2)49秒92(2)唐沢和也(伊那弥生2)51秒32(3)平沢快嗣(伊那弥生2)51秒88(4)大石洋佑(伊那北2)52秒07▼800メートル(1)小林祐作(伊那弥生2)2分00秒71(4)重盛赳男(伊那北1)2分08秒27▼1500メートル(1)村上剛(伊那北2)4分13秒27(3)小林祐作(伊那弥生2)4分15秒60(6)田原直貴(上伊那農業1)4分22秒05(7)山口宏和(上伊那農業2)4分22秒29(8)高橋聡(伊那弥生2)4分22秒86▼5千メートル(1)村上剛(伊那北2)15分51秒72(2)倉沢昇平(高遠2)16分16秒85(3)春日隆大(伊那北2)16分23秒89(4)小林正俊(上伊那農業1)16分26秒69(5)北原弘司(伊那北1)16分35秒00(8)山口宏和(上伊那農業2)16分45秒74▼110メートル障害(1)赤羽巧(伊那北1)16秒77(2)小林圭輔(伊那北2)17秒23▼400メートル障害(1)小林圭輔(伊那北2)58秒36(2)赤羽巧(伊那北1)59秒24(3)森嵩貴(駒ヶ根工業2)60秒56(7)野坂大樹(伊那弥生1)63秒21▼3千メートル障害(1)高橋聡(伊那弥生2)10分07秒17(2)北原弘司(伊那北1)10分09秒00(3)倉沢昇平(高遠2)10分16秒74(6)神航平(伊那北1)10分42秒11▼5千メートル競歩(1)村沢祐二郎(阿南2)28分11秒65(2)浅井順平(伊那北1)30分36秒69▼400メートルリレー(1)伊那弥生(野坂大樹、唐沢和也、平沢快嗣、安藤太郎)44秒77(2)伊那北(春日慧悟、大石洋佑、小林圭輔、三村瑞樹)44秒85(4)駒ヶ根工業(芦部友哉、赤沢侑生矢、森嵩貴、村井大介)46秒68(8)高遠(正木豊、稲垣友樹、矢野祐貴、稲村立吉)48秒83▼1600メートルリレー(1)伊那北(谷川大輔、三村瑞樹、小林圭輔、大石洋佑)3分28秒99(3)伊那弥生(野坂大樹、小林祐作、平沢快嗣、唐沢和也)3分32秒23(6)駒ヶ根工業(村井大介、森嵩貴、芦部友哉、赤沢侑生矢)3分42秒22(8)高遠(正木豊、稲垣友樹、矢野祐貴、稲村立吉)3分53秒71▼走高跳び(1)稲村立吉(高遠2)1メートル80(3)宮崎友宏(赤穂1)1メートル70(5)矢野祐貴(高遠1)1メートル40▼棒高跳び(1)松沢ジアン成治(高遠1)4メートル75=大会新(2)正木豊(高遠1)3メートル90(3)矢野祐貴(高遠1)3メートル30(4)倉田健斗(伊那北1)3メートル10▼走幅跳び(1)松尾雄治(飯田工業2)6メートル41(5)矢島春樹(赤穂2)5メートル80▼三段跳び(1)松尾雄治(飯田工業2)12メートル80(3)稲村立吉(高遠2)11メートル37(4)後藤智耶(駒ヶ根工業2)10メートル62▼砲丸投げ(1)堀井裕介(伊那北2)9メートル99▼円盤投げ(1)勝野英貴(阿南2)39メートル17(2)正木豊(高遠1)31メートル25▼やり投げ(1)涌井洸宜(飯田風越2)54メートル13(5)後藤智耶(駒ヶ根工業2)40メートル35(7)春日信二(高遠2)38メートル63(8)稲村立吉(高遠2)35メートル78▼ハンマー投げ(1)勝野英貴(阿南2)24メートル52=大会新(2)正木豊(高遠1)24メートル18=大会新(8)木下大輔(伊那北2)17メートル99▼8種競技(1)柳沢幸太(下諏訪向陽2)3754点=大会新(2)谷川大輔(伊那北1)3492点=大会新▼対校得点(1)伊那北134点(2)高遠78点(3)伊那弥生70点(8)駒ヶ根工業29点
【女子】
▼100メートル(1)高島理嘉(飯田風越1)13秒01(5)赤羽優希(伊那弥生1)13秒70(7)山崎愛里(伊那弥生2)13秒84(8)小沢彩香(辰野1)14秒04▼200メートル(1)南島彩乃(飯田風越2)26秒39(4)下平侑美(伊那西2)27秒62(6)山崎愛里(伊那弥生2)28秒07(8)鹿野恵理(伊那弥生2)28秒36▼400メートル(1)南島彩乃(飯田風越2)60秒90(5)青木美智子(伊那弥生1)64秒65(6)大久保涼花(伊那弥生2)65秒34▼800メートル(1)池田杏奈(伊那弥生1)2分24秒23(7)山腰絵里(辰野2)2分36秒74▼1500メートル(1)亀山絵未(東海大三2)4分43秒46(5)山腰絵里(辰野2)5分18秒77▼100メートル障害(1)小沢智代(伊那弥生2)16秒95(2)小沢あゆみ(伊那西2)17秒29(3)大場沙奈(伊那弥生1)17秒34▼400メートル障害(1)下島千歩(伊那北1)69秒80(2)中村茜(伊那弥生2)69秒94(3)小沢あゆみ(伊那西2)72秒45(8)山腰絵里(辰野2)77秒80▼3千メートル競歩(1)福沢奈津美(東海大三2)14分44秒05=大会新(3)山岸沙織(伊那西2)17分21秒06▼400メートルリレー(1)飯田風越(南島瑞紀、高島理嘉、宮沢彩実、南島彩乃)50秒58(2)伊那西(小沢あゆみ、青木亜由美、大倉未来、下平侑美)52秒33(3)伊那弥生(大場沙奈、山崎愛里、大久保涼花、赤羽優希)52秒80▼1600メートルリレー(1)飯田風越(原舞美、宮沢彩実、南島瑞紀、南島彩乃)4分10秒42=大会新(3)伊那弥生(大久保涼花、青木美智子、馬場彩香、中村茜)4分16秒28(6)伊那西(小沢あゆみ、渡辺沙愛、沢田帆奈美、下平侑美)4分32秒19▼走高跳び(1)田中恵(諏訪実業2)1メートル50(2)下島千歩(伊那北1)1メートル45(3)下平侑美(伊那西2)1メートル45▼棒高跳び(1)青木亜由美(伊那西2)2メートル80(3)鹿野恵理(伊那弥生2)2メートル70(5)伊藤真夕佳(高遠1)2メートル00▼走幅跳び(1)下平侑美(伊那西2)5メートル21(5)鹿野恵理(伊那弥生2)4メートル56▼砲丸投げ(1)山下弓乃(阿南2)8メートル10(2)マリーニョ アナパウラ(高遠1)7メートル64(3)大場沙奈(伊那弥生1)6メートル17(4)大久保涼花(伊那弥生2)5メートル98(5)沢田帆奈美(伊那西1)5メートル95(6)赤羽優希(伊那弥生1)5メートル04(7)斉藤有季(赤穂1)4メートル42▼円盤投げ(1)青木亜由美(伊那西2)21メートル40(3)マリーニョ アナパウラ(高遠1)19メートル09(5)中村茜(伊那弥生2)15メートル70(6)今井美砂(高遠1)13メートル95(7)伊藤真夕佳(高遠1)13メートル44(8)馬場彩香(伊那弥生2)12メートル47▼やり投げ(1)青木亜由美(伊那西2)33メートル90(2)小沢智代(伊那弥生2)31メートル50(3)マリーニョ アナパウラ(高遠1)30メートル66▼ハンマー投げ(1)田中恵(諏訪実業2)21メートル16(3)山崎愛里(伊那弥生2)12メートル27(4)大倉未来(伊那西2)10メートル32(5)池田杏奈(伊那弥生1)9メートル60(6)山岸沙織(伊那西2)9メートル27小(7)赤羽優希(伊那弥生1)8メートル36(8)渡辺沙愛(伊那西1)4メートル79▼7種競技(1)小沢智代(伊那弥生2)3414点(3)大倉未来(伊那西2)2763点▼対校得点(1)伊那弥生114点(3)伊那西90・5点(8)高遠28点 -
箕輪町議会9月定例会閉会
任期満了副町長2人を再任箕輪町議会9月定例会は18日開き、9月30日の任期満了に伴う副町長の選任で、総括副町長に桑沢昭一氏(63)=沢、行政改革や企業誘致、住宅開発などの特命副町長に永岡文武氏(64)=長岡=の再任に同意した。任期は4年。議員が提出した副町長の定数を現行の2人から1人に改める条例の一部改正案は、賛成少数で否決した。
請負契約、土地の処分、意見書の提出など追加議案5件、条例案2件、07年度一般会計などの補正予算案5件は可決、06年度一般会計などの歳入歳出決算認定7件は認定した。
副町長定数条例の一部改正案は議員2人が提出し、「行政改革の枠組みができ、町長の身辺からリストラし職員に範を示すべき」と提案説明した。討論は賛成1人、反対3人。採決は賛成2人で、賛成少数により否決した。
07年度国庫補助特定環境保全公共下水道管渠埋設工事(1工区)の請負契約は、契約金額5544万円、契約相手方は大槻総業(大槻昭治代表取締役)。工事は沢上桑沢川北側地区で、工期は08年3月26日。
06年度箕輪中部小学校給食室建設工事(建築主体)の請負契約は、契約金額5407万5千円、契約相手方はヤマウラ箕輪営業所(渡辺浩史所長)。工期は08年3月28日。
土地の処分は、南原工業団地の北側を、東信鋼鉄(清水輝美代表取締役)の拡張用地として処分する。面積は1万4798・64平方メートル。処分予定価格は1億7011万366円。
意見書の提出は、「医師不足を解消し、安心できる地域医療体制の確保を求める意見書」、陳情の採択に伴う「『非核日本宣言』を求める意見書」。請願2件▽高齢者の医療制度に関する請願▽6カ所再処理工場の本格稼働に反対し、その中止を求める意見書の決議を求める請願書-は閉会中の継続審査とした。 -
伊那技専から受託の職業訓練修了
宮田村商工会(前林善一会長)運営の宮田ビジネス学院が、県伊那技術専門校から受託した求職者対象のITビジネス応用力養成コースがこのほど、366時間に及ぶすべての日程を終えた。11人の受講者全員が修了し、それぞれ次のステップへ向かった。
閉講式で、石川秀延伊那技専校長が「これからが勝負。努力を重ね、意欲あふれる頼もしい人材になることを期待しています」とあいさつ。一人ひとりに修了証を手渡した。
受講者は20代から50代の女性。年齢もキャリアもさまざまだが、3カ月に及ぶ訓練は全員にとって新たな転機となったようだ。
「若い人たちからいろいろ学ばせてもらった。この頑張りを胸に就職活動に励みたい」などと語り合い、パソコン技術や各種資格を取得するだけでなく、仲間の輪もはぐくんだ3カ月間を振り返った。
##写真
修了証を受け取り3カ月間を振り返った -
東伊那区敬老会

敬老の日の17日、駒ケ根市の東伊那区は07年度の敬老会を東伊那公民館で開いた。招待された75歳以上のお年寄り250人のうち66人が出席し、健康と長寿を祝った。喜寿を迎える人たちには中原正純市長から祝いの記念品が手渡された=写真。地区内の小学生6人が「いつまでも元気で長生きしてください」などと作文を読み上げたほか、演芸会では獅子舞、落語、詩吟、踊りなどが舞台上で次々に披露され、出席したお年寄りを楽しませた。
市村善弘区長はあいさつで「大正、昭和、平成と人生を重ね、懸命に働いてきた皆さんに敬意を表する。その努力のおかげで東伊那も発展し、住み良い地域になった。今後もますます元気で地域のために力添えを」と祝いを述べた。
喜寿を迎えるのは次の皆さん。
春日スエ子、春日藤男、春日マチ子、滝沢ヨシ子、竹村正、山岸清志、伊藤武夫、片桐一嬉、北沢たか恵、木下守寿、坂井愛子、鈴木健司、中村昭梧、福沢昭子、安江弥生、赤羽笑子、久保田康正、下平ひで子、下平テル、鈴木ゆき子、宮下あき子、井口好美、小原正治、福沢文雄、福沢かね子、福沢嘉雄、森田秋子 -
観成園30周年記念式典

伊南福祉会(理事長・中原正純駒ケ根市長)が運営する駒ケ根市の特別養護老人ホーム観成園(米沢長実園長)が今年開園30周年を迎えることから18日、記念式典が同施設内で行われた。中原理事長は「30年の歴史は、先人の大きな努力で重ねてくることができた。利用者が元気で楽しい生活を送れるよう、これからも職員一丸となって努めていきたい」とあいさつした。
利用者の敬老会も併せて行われ、100歳を迎える人などに総理大臣や県知事からの祝い状や花束などが手渡された=写真。
同園は1977年、上穂町で開園。施設の老朽化などにより、昨年12月に北割一区の現在地に新築、移転した。 -
駒ケ根市議会決算特別委員会

駒ケ根市議会の議会改革の一環として9月定例会で初めて設置された決算特別委員会(宮沢清高委員長)は18日、初の決算審査を行った。議員15人のうち議会選出監査委員を除く委員13人とオブザーバーの議会議長が出席し、06年度一般会計など、4日の本会議で付託された13の決算関係議案について審査=写真。担当部課から説明を受け、議案ごとに質疑、討論、採決を行った。日程は20日までの3日間。一般会計決算の討論、採決は委員会最終日の20日に行われる。
委員会での審査結果は議会最終日(28日)の本会議で委員長が報告し、表決に付される。 -
箕輪町・辰野町への風力発電施設建設計画
箕輪町上古田区が反対箕輪町と辰野町の境付近にゼネコンの安藤建設(東京)が建設を検討している風力発電施設で、建設予定地の箕輪町内の関係区のうち、上古田区が臨時区会で建設反対を全会一致で議決していたことが18日、分かった。
風力発電施設は、桑沢山の尾根筋に風車を15基建設する計画。
風の状況を調査するため両町に1カ所ずつ高さ40メートルの測定器を立てる予定だが、箕輪町内の設置予定場所は、上古田区有林と町有林にまたがっている。
上古田区は8月25日に臨時区会を開き、風力発電施設の建設反対を決めた。理由は▽建設予定地が水源の地獄沢の上になる▽区は昨年の7月豪雨災害で土石流や地滑りが発生し被害を受けた▽生態系が崩れる▽景観がよくない-など。取材に対し唐沢光範区長は、「風力発電自体はいい事業なので賛成だが、大きなものが建つと、将来的に災害をもたらす原因になるのではと考え、反対を決めた」と話した。町には口頭で報告したという。 -
実りの秋たわわに、駒ケ原でブドウ農園が開園

宮田村駒ケ原にある平沢秋人さん、明子さん夫妻のブドウ農園が収獲期を迎え、直売やもぎとり体験を始めた。甘さも抜群。夫妻との会話も楽しみつつ、多くの客が実りの秋を味わっている。
敬老の日の17日も「おじいちゃん、おばあちゃんに食べさせたくて」と、買いに訪れる人たちなどで盛況。
中央道の小黒川パーキングエリア売店や村内の温泉施設こまゆき荘へも毎日、朝どりのブドウを出荷し、人気を集めている。
10月初旬まで開くが、期間中は村デイサービス利用者がブドウ狩りを楽しむなど、園内は連日賑やかに。
1キロでナイアガラが500円、マスカットベリーAが600円。問い合わせは平沢さん85・2744まで。 -
議員定数問題20日に決着へ
宮田村議会9月定例会は最終日の20日、一部議員から提出された議員定数を現行の12から10に削減する条例改正案を議事日程に追加する見通しとなり、午後1時半から開く本会議の採決の可否により来春行う村議選の定数が事実上確定する。
同議会は昨年末から議会改革のひとつとして、区長会との懇談や村広報紙に資料を掲載するなど、村民にも投げかけながら定数の議論を深めてきた。
先月22日には議会全員協議会を開催。議会運営委員会が「定数維持」を叩き台として示したが、結論には至らず、「削減派」の議員は条例改正案提出を示唆していた。
自身の考えを私報などを用いて村民に訴えている、ある議員は「村の行く末を決めることでもあり、皆さんに関心を寄せてもらいたい」と話す。
小林茂議長は「分かりやすい形で、来春の選挙に向けてひとまずの決着が図られると思う」と語った。 -
猛暑でバナナがなった?!

中川村葛島のそば処「吉笑楽(榑沢吉男店主)」に植えられたバショウに初めて花が咲き、バナナ状の実が実った。
バショウはチャイニーズバナナと呼ばれ、栽培バナナの仲間。6年前、株分けし、店の前に植えた。毎年は春に芽吹き、たちまち3メートル余に成長し、大きな葉を茂らせている。
9号台風の後、葉が割け、割けた葉を取り除いたところ、先端に薄黄色の雄花をつけ、基部近くには雌花と、7、8センチになったバナナ状の実を発見したという。
以前、防寒して冬越しさせ、花を咲かせたことがあるという榑沢さんは「今回は防寒しなかったが、猛暑のせいで咲いたのでは」と話していた。 -
そばの花見ごろ

日を追うごとに秋めく中、上伊那でも各地にあるソバ畑で白い花が見ごろを迎えている。伊那市西春近にあるソバ畑も満開となり、白いじゅうたんを一面に敷きつめたかのような光景が、見る人の心を和ませている=写真。
上伊那でソバの花が見られるのは8月末から9月下旬。
播種から収穫までの期間が短く、山間部などのやせた土地でも栽培しやすいことから、栽培面積が増えつつある。
新そばが出始める10月には、各地で新そば祭りも催される。
1512/(月)
