-
箕輪ブライトプロジェクト
施策機「順調」
自然エネルギーを活用した廉価な照明装置の開発に取り組む箕輪町の事業者有志による「箕輪ブライトプロジェクト」は10日、第2回定例会を町商工会館で開き、役員や規約を決めた。
会長は小池茂治さん、副会長は市川平和さん、竹内真治さん。これまでに集まったメンバーは22人。
規約には具体的な取り組み事項に▽会員相互の経営資源補完による新製品の企画制作▽太陽光・水力・風力など自然エネルギーを利用し、かつ廉価な照明装置の開発▽装置の試作と天竜川護岸への設置による性能の評価-などを盛り込んだ。
同プロジェクトは9月25日、有志7人で設立発起人会を開き、太陽光、小水力、風力など各部会で照明装置を研究開発することを決定。太陽光発電タイプの試作機を10月7日に町郷土博物館の庭に設置し状況を見ながら研究を進めている。
試作機は周囲の暗さ、またはタイマーにより午後4時に点灯し、午後9時に消える。稼動状況について小池会長は、「順調」とした上で、「さらに高性能、廉価のコンセプトで開発してもらわないといけない」と話した。
試作機は07年3月まで設置し継続調査する。その間、さらに商品開発を進める。 -
池坊伊那支部青年部北部ブロック
ミニ華展
池坊伊那支部青年部北部ブロックのミニ華展が14日、箕輪町のアルプス中央信用金庫いほく支店ロビーで始まった。前期、後期2日間ずつで作品替えをし17日まで開く。
青年部(宮沢京子部長)は上伊那在住の97人。北部ブロックは箕輪町、辰野町を中心に15人いる。年1回のミニ華展で、今回は14人が前期と後期7人ずつで、日ごろのけいこの成果を披露する。
作品は自由花が主で菊、リンドウ、グロリオーサなど身近な花に、秋らしく紅葉した葉を使うなどして生けている。
北部ブロックでは、「今回は身近な花で簡単にでき、自分も家族も和むほほえましい花が多い。ロビーで花を見て一息ついてほしい」と話している。 -
南箕輪村むらづくり委員会
実践に向けた具体策検討へ南箕輪村むらづくり委員会(唐沢俊男会長)は13日夜、村役場で開き、9月下旬に第4次総合計画の基本計画や都市計画マスタープランなどの答申を終えた委員会の今後の活動について協議し、実践に向けた具体策や提案を検討することを決めた。
07年3月まで部会ごとに、基本計画の「ずく出しプロジェクト」の中から優先順位で目標・重点対策を決定し、実践に向けて住民が参加できるような具体策と提案を検討する。
提案後の4月以降は、再度委員会で検討して決めるが、現時点では専門委員会などを設置し▽実践部隊と村の執行部をどのようにつないでいくか▽組織的な連携をどうするか▽外部評価をどうするか-などを検討する予定。 -
【記者室】箕輪町長選…現職再選
箕輪町長選挙。正式な出馬表明は現職のみで無投票ムードも漂う中、住民有志の新候補擁立は続き、最後まで選挙戦突入か否かは微妙な状況だったが、結果は無投票。現職再選で幕を閉じた▼現職は町内全域を網羅した後援会組織で広く支持を集めた。「もう1期やらせてやりたい」。そんな声の一方で、町民の中からは選挙戦を望む声も聞こえた。新たな町政を望んだ住民有志も、ぎりぎりまで動き続けた▼霧雨が降り始めた昼前、西山に虹の橋が架かった。平沢町政の新たな4年間は、町の未来にどんな橋を架けるのか。現職の手法を疑問視し「本当の民意をくんでくれる人」を望んだ住民がいることも心に留めつつ、町民のための町政運営をされることを期待する。(村上裕子)
-
県縦断駅伝18・19日 「上伊那」チーム紹介(上)

第55回記念県縦断駅伝競走大会(県陸上競技協会など主催)は18、19日、長野市から飯田市までの21区間218・7キロのコースで熱戦を展開する。本年は中学生区間を1区間増設したことや、郷土を離れたランナーを活用できる「ふるさと選手制度」の導入が勝負の鍵を握りそうだ。昨年、3年ぶり、33回目の総合優勝を果した「上伊那チーム」は、連覇を目指して激走する。
上伊那は、黄金期を支えた羽生吉浩(養命酒)の調整不良による欠場や、ふるさと選手を使わない布陣となりライバルに苦戦を強いられることが予想されるが、個々の平均的な力には定評がある。メンバーの大きな入れ替えはせず、経験豊富なベテランと昨年の優勝を知る若手選手とが力を合わせ、大会に挑む。
1区にスピードのある小林(信大)を起用し、序盤から好位置を狙う。初日最長距離の4区には、5千メートルを14分台で走り、精神的にも安定感のある注目選手、柳澤(上農高教員)を配置し、1日目を首位で折り返す考えだ。
15回目の出場となる主将・丸山(NEC長野)を7区へ、未だに成長し続けているチーム最年長の守屋(嬉楽Q)を8区へ置くなど初日終盤は、ベテランの力で乗り切る。
2日目の布陣は、若手中心の構成。大学の練習で持久力を増した中塚(亜大)がスタートを切り、佐々木(上農高)へ。中盤の地元区間は、安定感のある大槻、萩原(いずれもジェルモ)、滝澤(駒ヶ根市役所)らが声援を受けて走る。
エース区間の20区には、好調を維持し続けている上島(平井星光堂)が登場。10月の諏訪湖マラソン(21・0975キロ)優勝者の力でたすきを最終区の北原(トーハツマリーン)へつなぐ。最終日の逃げ切り体制は万全といえる。
中学生区間を走る駒ヶ根東の福澤、篠田、宮脇にも注目。11月上旬にあった県中学駅伝大会では男子2位、女子3位と惜しくも涙を飲んだが、上伊那の連覇に全力を尽してくれるだろう。
清水監督(NEC長野)は「他チームのふるさと選手の走りに惑わされず、個々のペースで力を発揮すれば『優勝』の2文字は見えてくる」と意気込む。
2年連続、34回目の総合優勝を賭け「上伊那チーム」が晩秋の信濃路に帰ってくる。沿道からの声援を力に選手たちは「新たな黄金期」へ向け、たすきをつなぐ。 -
上伊那地域景観協議会が発足
地域の特性に合致した広域的景観育成の推進を図る上伊那地域景観協議会が14日、発足した。関係団体や行政担当者などが集まり、本年度の事業方針などを確認した。
県は4月から、景観法に基づく改正景観条例を施行。それに伴い上伊那でも、従来の上伊那地域景観推進会議を発展させ、今回の協議会を設置した。
協議会は本年度事業として▽国道361号の屋外広告物禁止地域における既存不適格広告物の除去▽本年度中に西箕輪地区を景観育成特定指定区域とするための調査、ワークショップの実施▽地域における自律的な景観育成の支援をする景観ヴァンガードの育成及び専門家の派遣竏窒ネどを進めるほか、景観講演会などを行うことも計画している。
屋外広告物禁止地域における既存不適格広告物の除去については、上限を40万円として費用の3分の1を助成する事業を新たに進めており、現在関係する8事業者と協議している。 -
ガールスカウト長野26団 高遠町でウォークラリー

伊那市などの団員らでつくるガールスカウト長野第26団(木部則子団委員長)は12日、一般参加者を募った「子どもたちの居場所づくり事業」の一環として、同市高遠町のホリデーパーク周辺でウォークラリーを開いた。
園児、児童の団員ら23人が参加。4グループに分かれた子どもたちは、同町内の白山橋、歴史博物館、桂泉院、高遠城址(し)公園など6カ所を順番に回り、それぞれで出題される問題に挑戦した。
「橋の長さを自分の歩数で測って距離を割り出す」「大きな木の周りをロープで測る」などの出題をグループごとが力を合わせて正解を考えた。高遠城址公園では落ち葉などの自然物を使って、一人ずつ画用紙に・ス秋・スを表現する工作も楽しんだ。
出発時点では雪が空から落ちてきて肌寒さを感じていたが、次第に日の光りが降り注いでくると、赤や黄色に色づいた周囲の紅葉に目を見張っていた。 -
福澤雅志世会演奏会 輪の音楽の花咲く

伊那市で筝の教室を開く「福澤雅志世会」の2回目の演奏会が12日、同市の伊那北地域活性化センター「きたっせ」であった=写真。伊那三曲協会員による賛助出演など計61人が、11演目を繰り広げた。
同教室の「おさらい会」に、約80人の観客が集まった。出演者全員参加の合奏曲「六段」、教室に通う児童らの「一茶のおじさん」などを披露し、雅な音の世界が会場に広げた。
教室は1971年に、指導者の福澤雅志世(73、本名・靖子=同市山寺=)が開いた邦楽教室。福澤さんが筝を習い始めて60周年の記念に1回目の演奏会をし、今回は68周年の記念となった。
福澤さんは「和の精神をモットーに努力を重ねてきた。ステージにどんな日本の音楽の花が咲くか期待して」と話した。 -
オペラの発展学ぶ 長谷公民館で生涯学習講演会

作曲家、指揮者、ピアニストとして有名な青島広志さんを招いた「生涯学習講演会inはせ」は12日、伊那市の長谷公民館で開いた。市内から約180人が集まり、青島さんのピアノ伴奏に平松混声合唱団長の小野勉さんが声楽(テノール)で参加した演奏を楽しんだ。
長谷地区文化祭に合わせた恒例の講演会。青島さんは「オペラからミュージカルへ」と題して、西洋の娯楽の中心であった舞台芸術のオペラの発展を語るため、年代を追いながら代表曲10曲を演奏し、それらの作曲家や劇内容について説明した。
「昔は宗教に縛られ男性しか出演できなかった」「時代が変るごとに高音が使われるようになった」などの説明の中にも冗談を交えて講話。生誕250年のモーツアルトなども、分かりやすくおもしろい切り口で教授した。
酒井さや香さん(32)=長谷非持=は「オペラについての豆知識を知り、オペラに興味がわいた。とても分かりやすく、楽しい解説だった」と話していた。 -
箕輪町でサッカーフェス

箕輪町サッカーフェスティバルが12日、番場原第2運動場であり、小学生から一般まで約300人が集まってPK合戦やキックターゲットなど各種ゲームを楽しんだ。
少年や社会人のサッカークラブ関係者で9月に発足した箕輪町サッカー協会(小松良輝会長)による初事業。サッカーに親しんでもらうことを目的に企画し、町内の愛好者に参加を呼びかけた。
小学3年生以下を対象にしたPK合戦は、5人一組でゴール数を勝負。小学4年生以上は、ゴール枠内の8枚の的を狙うキックターゲットに挑戦した。10本のポールをジグザグにドリブルしてタイムを競うドリブルタイムトライアルもあった。
キックターゲットは、小、中学生、一般の部門別で競技。5人一組になって的に当てた総数で勝敗を決めた。参加者たちは狙いを定めて集中、的に当たるとギャラリーからは歓声があがった。喜んだり、悔しがったりして和気あいあいと楽しんでいた。
ほかに、協会認定のリフティング検定も計画し、参加者は10級から1級までの取得に向けて挑んだ。目標を掲げて練習してもらうことで、技術向上につなげる狙いがある。
フェスティバルは今後も続けていく考えで、「今回は町内だけだったが、次回以降は広く呼びかけていきたい」と小松会長。
協会は来年度、Jリーグ観戦や町内サッカー大会などを計画している。 -
高遠高校と創造学園大学が連携協定

高遠高校は14日、群馬県の創造学園大学と高大の連携や交流を図る協定を締結した。教育内容の充実、生徒の学習意識や教員の指導力向上を目指す。
高遠高は95年度に芸術や福祉などのコース制を導入し、特色として掲げる。開学3年目の創造大は、創造芸術学部とソーシャルワーク(社会福祉)学部をもち、芸術と福祉の融合をテーマに大学づくりを進めている。
本年度、高遠高は魅力ある高校づくりに向けて設置した高校改革推進調整委員会で、コース制の特色を踏まえ、新たな方向付けとして、同様の専門学部をもつ大学との連携を図ることで意見をまとめ、創造大に投げかけた。双方とも高大の連携は初めて。
協定の締結により、高校側は音楽や美術、福祉の各教科で教育実習生を受け入れる。大学側は専任教員や学生を派遣して特別講義や技術指導をするほか、芸術と福祉コースからの指定校推薦枠を設ける。ほかに、教育に関する調査・研究などに対して協力し合う。
調印式で福沢務校長は「互いに手を携え、未来のためにより高いものを求めていきたい」、堀越哲二学長は「在学中に本大学を訪ねてくださる機会があることを願っている」と述べ、それぞれ協定書を交わした。
連携を記念し、高遠高合唱部と創造大オーケストラによるコンサートもあった。 -
税を知る週間
南箕輪役場で児童・生徒の作品展
南箕輪村は11日から17日の「税を知る週間」に合わせ、書道と標語の作品に応募した村内小・中学生の入選作品展を17日まで、役場ホールで開いている。
村関係分の応募作品数は小学生対象の書道が456点、中学生対象の標語が63点。
作品は期間中に展示替えする。 -
箕輪町長選
今日告示任期満了(28日)に伴う箕輪町長選挙は14日、告示される。町役場講堂で午前8時30分から午後5時まで、立候補の届け出を受け付ける。
立候補予定者は現職の平沢豊満氏(65)=無所属、沢。
平沢氏は午前8時半から西友箕輪店前駐車場で事務所開き兼出陣式をする。
13日現在の選挙人名簿登録者数は1万9997人(男性9862人、女性1万135人)。 -
南みのわわくわくクラブテニスカップ開催

南箕輪わくわくクラブテニスカップ(NPO法人南箕輪わくわくクラブ主催)が12日、大芝公園のテニスコートであり、会員や一般42人がプレーを楽しんだ。
親ぼくと技術向上を目的に、8回目。ダブルスの男女別と混合の3部門で、男子は10組が2グループで総当り戦、1、2位同士で決勝戦をした。女子は5組、混合は6組が参加し、それぞれ総当たり戦で優勝を争った。 -
ミニバスケットボール選手権 上伊那勢7チーム県へ

第31回県ミニバスケットボール選手権中南信地区大会が11、12日、県伊那勤労者福祉センター体育館など4会場であった=写真。上伊那勢は男子の箕輪、駒ヶ根、女子の伊那ミニ、TOSC(伊那市)駒ヶ根、箕輪健全、高遠キャットミンツが12月9、10日、松本市である県大会に出場する。
結果は次の通り(上伊那関係分)。
▽男子(3)箕輪(7)駒ヶ根
▽女子(1)伊那ミニ(2)TOSC(3)駒ヶ根(4)箕輪健全(6)高遠キャットミンツ -
エレベーター内で家事 南箕輪村のマンション
12日午後10時30分ごろ、南箕輪村神子柴のマンション・ハイビスカスのエレベーター内の床を約0・4平方メートル焦がす火事が発生し、約5分後に鎮火した。けが人などは出なかった。
伊那署の調べによると、マンション住人の男性がエレベーター内でビニール袋のようなものが燃えているのを発見し、消防署へ通報したという。
同署では不審火とみて、原因を捜査している。
床を焦がす火事があったマンションのエレベーター -
「遺伝子DNA」講演会
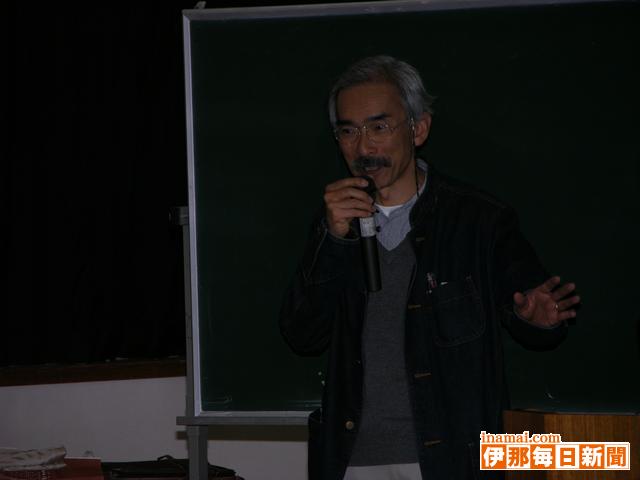
駒ケ根市の赤穂、中沢、東伊那の3公民館でつくる駒ケ根市公民館協議会は駒ケ根ふるさと講座の第2弾として11日、分子遺伝学、分子生物学が専門の信州大理学部長伊藤建夫さんを講師に迎えて「遺伝子DNAは語る竏宙笂`子組み換え食品の問題点」を開いた。市民ら約20人が集まり、普段あまり馴染みのない遺伝子の話に耳を傾けた。
伊藤さんは遺伝子の形と働きなどについて分かりやすく説明した上で遺伝子組み換え食品について「世界の食料事情などの理由から遺伝子組み換え食品が盛んに研究されているが、作物、技術、遺伝子、ヒト、家畜などに対する安全性を慎重に見極めなければならない」と話した=写真。 -
箕輪中学校外国語指導助手
ダンスタン・ヘンダソンさん
箕輪町の箕輪中学校に外国語指導助手(ALT)として今年4月に着任し、半年以上が過ぎた。学校ではディー先生と呼ばれている。
2メートルの長身。校内を歩いていても目を引く。生徒の多くは敬称をつけずにディーと呼ぶ。「外国人なので扱いが違う。でも、先生として尊敬してくれていることを感じている」という。「生徒は元気で好奇心が強い。外国人の考え方の違いなどを質問してくる」と印象を語る。
授業では英語教諭を助けながら、「英語はインターナショナルだから」と、アメリカ人の発音、中国人の発音などの違いを実際に発音して生徒に聞かせる。面白い声で話してみたり、ロールプレイで女の子役を演じたり、時には踊ったり。「先生は驚いている。でも楽しい授業をやりたい。楽しく学んだことは覚えている」。生徒もロールプレイをするが、「恥ずかしがって、発音も棒読みになってしまう。もっと恥ずかしがらずにできたらいいと思う」という。
マレーシアで生まれ、オーストラリアのパースで育った。
日本に関心をもったきっかけは、小さいころに子ども向けのテレビ番組で見た折り紙だった。図書館で折り紙の本を借り、作って遊んだ。日本に行きたいと日本語も勉強した。
高校卒業後、モデルとして働き、イーデス・カーワン大学に進学。コンピューターサイエンスと日本語を専攻し学業に励みながら、モデルの仕事も続けていた。
初来日は4年前。大学を休学し、モデルの仕事で大阪に1年9カ月暮らした。その間、企業でビジネス英語も教えていた。日本料理は好きだが、母親の料理が食べたくなり少しホームシックにもなった。それでも、日本での生活は楽しいことが多かったという。
復学し、大学卒業後はミュージックプロモーターとして働いていたが、大阪では経験できなかった日本の教育システムを学びたいと再来日を決意。ALTとして長野県に来た。
「教育は未来と自由と力をつくる」。日本の教育がどのようにして日本人を形成するかに関心を抱いている。
武士の心、日本人の心にも魅力がある。「日本は強い国だが、日本人の中には日本文化を忘れている人がいる。武士の心は強いけど、今の日本人は知らない」。日本人が武士の心を忘れかけていることを残念に思っている。
日本の自殺者の多さにも驚いた。「すごい問題」と指摘する。女性の地位については、「オーストラリアは女性は強い。日本は女性の心は強いけど、日本文化が女性を抑えている。それは好きではない」という。
母国と日本の文化の違いなどを肌で感じながら暮らす日々。日本に来て花粉症に悩まされ、今度は「超寒い」と長野県の寒さに少しショックを受けているが、生活にも慣れた様子。「日本では教えていないオーストラリアと日本の歴史、世界史も教えたい」と教育現場での次なる課題も見出したようだ。
趣味は極真空手、運動、コンピュータープログラミング、そして折り紙。ビールも大好き。(村上裕子) -
目撃相次ぐ養魚場でクマ捕殺
クマの出没目撃が相次ぐ宮田村新田区の養魚場(天竜川漁協運営)で12日朝、体長120センチほどのメスのクマが捕獲用の檻(おり)につかまった。昨年も捕獲されたクマであることも分かり、県の許可を得て地元猟友会が射殺した。同村内でクマを捕殺するのは一昨年の9月以来。養魚場は民家からある程度離れていることもあり、お仕置き放獣を主体にしてきたが、今後は状況をみて対応する。
クマは推定5縲・歳。捕獲されて再び野に放たれたことを示す赤色の目印が、右耳についていた。
上伊那地方事務所林務課によると、管内では本年度13日現在で20頭を捕殺。そのうち目印がついたクマは12頭にのぼっている。
宮田村林務係は、今後も養魚場内への檻の設置を継続する考え。関係者などによると、一帯には10頭ほどのクマが生息しているとも考えられ、対策に頭を悩ませている。 -
戦後代表する俳人の句碑、遠祖の地宮田村に建立

中世に宮田村北割区の宮田城を拠点に一帯を治めた宮田氏の末えいで、一昨年に90歳で亡くなった戦後を代表する女流俳人・故桂信子(本名丹羽信子)さんの句碑が13日、遠祖ゆかりの地である同城址に近い真慶寺に建立された。「建てるならば宮田の地に」と故人の遺志を受け、300人以上に及ぶ門下が賛同。地元の宮田城址保存会の協力で、刻まれた句の通りに山々を一望する絶好の地に碑は建った。
「信濃全山十一月の月照らす」。桂さんが1960(昭和35)年に信州を旅した時に詠んだ句で生前、「句碑を建てる機会があれば、この句を宮田の地に」と親しい人に話していたという。
門下で現代俳句協会長の宇多喜代子さんらが故人をしのんで建立を計画し、同城址保存会が調整や手配など全面的に協力。南アルプスを一望する高台の真慶寺を場所に選んだ。
この日の建立除幕式には宇多さんや関西の門下でつくる「草樹」の5人が出席。地元からも保存会を含め、多くの参列者があった。
「山々を望む素晴らしい場所で、先生の句が皆さんと一緒に生き続ける。ふるさとに帰った気持ちで天国でも喜んでいるはず」と宇多さん。
保存会の春日甲子雄会長は「お手伝いできて本当にうれしい。今後も一層、宮田城址を村の文化遺産として後世に伝えていきた」と話した。 -
小学生球技大会、河原町ファイト一発が優勝

宮田村の第31回小学生球技大会は11日、宮田小体育館などで開いた。村内12地区から20チームが参加。ドッジボールで熱戦を展開し「河原町ファイト一発」が優勝した。
村青少年健全育成協議会(中原憲視会長)の主催で、各チーム練習を積んできた成果を発揮。優勝を目指して、鍛えたチームワークで挑んだ。
「ファイト一発」は塩沢郁花主将を中心にまとまり激戦を制覇。他チームも一歩及ばなかったが、大会を通じて友情を深めた。
上位の結果は次の通り。
(1)河原町ファイト一発(2)大原へッポコゴリラーズ(3)町二区ドラゴンファイターズ、大田切JrA -
宮田小3年が紙飛行機づくり、駒工生の指導で

宮田村宮田小学校3年は13日、駒ケ根工業高校情報技術科3年の生徒6人から指導を受けて、紙飛行機づくりに挑戦。生徒のやさしい指導で、児童がものづくりの楽しさ、喜びを肌で味わった。
講師を務めた生徒は課題研究として連携授業に取り組む4人と、飛行原理をラジコンから学んでいる2人。
最初は戸惑い気味だったが、児童からは「先生」などと呼ばれ、丁寧に作り方を指南。 寄り添って教える姿も目立ち、つくる喜びを分かち合った。
畑口翼君は「僕たちが普通に使っていても、小学生には理解できない用語もある。指導しながら気付きました」と話した。
さっそく飛ばして楽しみ、空高く舞いあがる愛機に歓声も。みんなの笑顔が広がった。 -
天竜川ふれあい公園(仮称)ワーキンググループが現地視察
中川村中央の天竜川
河川敷に整備する天竜川ふれあい公園(仮称)について整備計画を具体的に検討するワーキンググループは10日、10人が参加し現地調査を行なった。
同公園はチャオ周辺活性化委員会の構想で、多目的芝生広場、親水公園、わんぱく広場、自然観察園、散策路、植栽などが盛り込まれている。
現地調査では、駐車場の位置や国道153号、村道からの進入路、トイレの設置、親水公園のための水路、水量などを見て回った。
調査後の会議で、「芝生広場に日陰がない。植栽が必要では」「芝生広場にサッカーの正式コートは取れるのか」「河川敷にトイレ設置はできるか」「道路周辺の竹林対策も必要」など意見、質問が出された。
ワーキンググループでは12月末までに、整備案を検討し、具体的方針を策定する。
て -
町発足50周年記念、子ども議会

近い将来、町を担う小・中学生と、現在の担い手である大人が一緒になってこれからの町づくりを考える飯島町発足50周年記念事業、「子ども議会(横山今日子議長)」が12日、議場であった。町内3小中学校の代表児童、生徒ら18人が議員になり、理事者や町幹部に質問をした。
質問は環境問題や防災対策、産業振興、財政など町政の広範な課題をはじめ、小・中学生ならではの視点に立った福祉問題を取上げ、率直に質した。答弁に立った高坂町長は、子どもたちに理解できるようにと、言葉を選びながら、丁寧に答弁した。
このうち、自然保護・環境問題は関心が高く、山田菖平君(飯中2年)、大嶋一輝君(七小6年)、堀越咲良さん(飯小5年)、高橋知世さん(飯小5年)がそれぞれの切り口でごみの減量化や、自然を守る方策について質問。高坂町長は「分別収集の徹底や、ごみゼロの日の実施」など具体的に答えた。
また、松村源貴君(飯中2年)は7月の豪雨災害を挙げ「大災害を想定し、どのくらいの備蓄物資があるのか」と質問。高坂町長は米や毛布など品目毎の備蓄数を示し「人口の5%、500人分の備蓄がある」とした。
来春、中学生となる伊藤友梨亜さん(七小6年)は「中学の制服をかわいいデザインにして」と女子ならではの切実な訴えには「そういう意見が多くあれば、検討委員会をつくり検討したい」と優しく答えた。「50周年記念にタイムカプセルの埋設」を提案した久根美奈子さん(七小5年)に対する答弁は「学校で検討してほしい。場所の提供は可能」と前向き答弁をした。
16議員の質問終了後、副議長の松田慧さん(飯小6年)が「笑顔でふれあいがいっぱいのあたたかい町をつくる要望書」を提案、全会一致で採択、閉会した。
この日の子ども議会で出された意見、要望は可能な限り行政運営に生かされる。 -
駒展
駒ケ根市在住の県展出陳作家の力作を集めた「第5回駒展」が26日まで、市博物館で開かれている=写真。
駒ケ根総合文化センター開館20周年記念の同展には、国展で活躍の柴田久慶さんの力強い「MAN」。日展審査員の木下五郎さんの鍛金作品「空寂」。大自然の大切さをアピールする、小木曽章八さんの「汚染、生きる者達」。加納恒徳さんの「鷲ケ峰」、北村昌道さんの染色作品「かたくり」など、洋画、工芸、水墨画、陶芸、漆芸作品約20点を並べた。
いずれも、県展や中央の展覧会、個展で活躍している作家が、渾身の思いを込めた作品だけに、見る人に深い感動を与えている。
また、会場では駒展実行委員である作家の小品作品の展示、入札による販売も行なわれている。収入は全額、市文化財団基金に寄付される。 -
南アルプス世界遺産登録に向け山梨連絡協が来伊

南アルプスの「世界自然遺産登録」を目指し、山梨県連絡協議会(会長・石川豊南アルプス市長)のメンバーが13日、伊那市を訪れ、長野県側の関係自治体による連絡協議会の設置を要請した。小坂市長は「登録されればなお一層、南アルプスの価値がでてくる」と推進に積極的な姿勢を見せた。
南アルプス市が静岡市から登録運動への協力の要請を受けて乗り出すことになり先月、北杣市、韮崎市、早川町との山梨県内関係4市町の首長や議長ら12人で連絡協を発足させた。効果的に推進するための総合調整や、必要な資料の収集、自然環境の保全と地域振興などに関することを協議していく。
当面は、南ア国立公園をもつ長野県の4市町村、静岡県の2市町、山梨県の4市町で各連絡協を設置、年度内に3県全体の推進協議会を立ち上げて、来年度から登録実現に向けた運動を展開していきたい考え。
県内の関係自治体は、伊那市、飯田市、富士見町、大鹿村。石川会長は「長野県側の取りまとめを伊那市にお願いしたい」と求めた。
これに対し、小坂市長は前向きな姿勢をみせつつ、南アふもとの伊那市長谷、大鹿村や下条村に残る歌舞伎など古い民俗芸能を踏まえ、「複合遺産」としての登録を提案。石川会長は、長野県の連絡協で内容を詰め、推進協で検討したい、とした。
山梨県連絡協によると、全体の推進協設置後は、03年に世界遺産の候補地に関する国の検討会で指摘された問題や課題を整理し、南アの学術的な価値を調査・研究するなど、登録に向けた検討を多面的にし、実現への方策を進める。 -
中国料理教室に40人
駒ケ根市社会福祉協議会の「地球人ネットワークinこまがね」は12日、ふれあいセンターで、中国料理教室を開いた。親子ら約40人が参加、宮沢百枝さん=宮田村商工会日本語教室講師=を講師に、中国研修生6人と交流を深めながら、中国の家庭料理、水餃子、葱油餅(チョンヨウピン)づくりを楽しんだ=写真。
参加者は強力粉に湯を加え、よくこね、こね棒で伸ばし、餃子の皮を作った。具は白菜と豚ひき肉、ネギと桜エビの2種類を用意した。
参加者は研修生に教わりながら、手際よく、餃子の皮を作ったり、子どもたちも器用に具を入れて、ひだを連寄せながら包んだ。
宮沢さんは「教室で見せる研修生の表情と違って、生き生きとして、楽しそう」と話していた。 -
県議選 小林伸陽氏が出馬表明

県議小林伸陽氏(61)=日本共産党・箕輪町=は13日、記者会見し、来春の県議選上伊那郡区(定数2)の出馬を表明した。
小林氏は、村井県政について、ガラス張りの知事室閉鎖や陳情が繰り返される現状などを挙げ「一抹の不安を感じざるを得ない。県民の福祉、教育が削られる状況はなんとしても避けたい」と述べ、3期目を目指す。
財政再建は避けて通れない課題で、公約に▽浅川ダムなど無駄な事業の再開は許すべきではない▽福祉の充実▽安心して出産できるしくみづくり▽家族農業の振興と地産地消の促進竏窒ネどを掲げる。
定数減により全体の得票数のかさ上げが必要で「変わり始めた県政の後戻りは許されない」と訴え、支持を広げる。
日本共産党上伊那地区委員会の三沢好夫委員長は、2期8年の実績を踏まえ「住民の暮らしを守る役割を果たせるのは小林県議しかいない」と話した。 -
みのわもみじカップ第1回フェンシング大会開催

みのわもみじカップ第1回フェンシング大会(県フェンシング協会主催)が12日、箕輪町の町民体育館であった。県内では初めての中学生以下を対象とした全国規模の大会で、6府県から8チーム72人が出場した。
これまで協会の大会は、県内選手の交流が中心だったが、全国の少年フェンサーとの交流を通し、技術向上や競技人口の増加を狙って計画。各地に呼びかけ、新潟や岐阜、京都などから参加があった。
小学2年生以下のバンビ、男女別で小学3・4年、小学5・6年、中学生の部門別で、フルーレ個人戦をした。1回戦をプール、2回戦以降をトーナメントで順位を決めた。 -
小黒川渓谷キャンプ場釣り堀感謝祭

伊那市の小黒川渓谷キャンプ場で12日、釣り堀感謝祭があった。エサ代無料などのサービスがあり、多くの家族連れが釣りを楽しんだ。
昨年に続き、2回目。市振興公社が、一昨年の台風被害で迷惑をかけたおわびと、利用者や地域への感謝を込めて計画したのがはじまり。
釣り堀は平均100グラムのニジマスを放し、大きいもので200グラムあるという。釣った魚は通常100グラム180円だが、この日は大小かかわらず1匹100円で提供した。
上伊那各地から午前中だけで約100人が訪れ、見ごろを迎えた渓谷の紅葉も楽しみながら、糸をたらしてじっと当たりを待っていた。午前中は冷え込んだせいもあって魚の食いつきが悪かったが、なかには30匹釣った家族もいた。
市内から家族5人で訪れた会社員の男性(38)は「釣り堀を利用したのは初めて。子どもと一緒に楽しめていいですね。今日は家族みんなで塩焼きにして食べたいと思ってます」と話し、何匹も釣り上げていた。
利用者たちは、釣った魚をその場で、炭火で焼いて味わっていた。
1912/(金)
