-
箕輪町八乙女の夏祭りで振りまんど
箕輪町公民館八乙女分館が主催する区民対象の夏祭りが、15日、地区のグラウンドで行われました。
八乙女地区では、毎年15日にお盆の伝統行事・振りまんどを行っていますが、4年に1度、夏祭りとして盛大にイベントを行っています。
八乙女グラウンドには箕輪太鼓保存会とみのわ手筒会が招かれ、演奏や手筒花火を披露しました。
最後に子供たちによるまんど振りが行われました。
八乙女分館の関 文成分館長は「地域のつながりが減っているので、こうした機会を設けて区民の親睦を図るとともに、伝統を守り引き継いでいってほしい」と話していました。
グラウンドには区民250人ほどが訪れました。
-
服部幸應さん監修バスツアー 来伊
料理評論家でタレントの服部幸應さんが監修するバスツアーの一行がきのう、伊那市内を訪れました。
参加者は、世界的な賞を受賞した食の生産者との交流を通じて、食育について学びました。
バスツアーは、服部さんと一緒に長野県と山梨県を回り食育について学んでもらおうと、阪急交通社が初めて企画したものです。
このうち、横山のカモシカ・シードル醸造所では、一昨年アジア最大の審査会で金賞を受賞したシードルを試飲しました。
他に、シードルにも使われている信州大学農学部が開発した赤い果肉のりんごについて、開発した伴野潔教授から話を聞きました。
次に、富県の有限会社いすゞが製造・販売する天然水「ときわの命水」の施設を訪れました。
ときわの命水は、品質評価を行う国際団体モンドセレクションで、3年連続最高金賞を受賞しています。
織井常和社長は、「この水は老化予防に効果があるという分析結果が出ている」などと説明していました。
ツアーは、首都圏に住む人を対象に18日と19日の2日間の日程で行われ、伊那市の他に飯田市のトマト農家や山梨県のジャム加工施設などを訪れたということです。 -
いなまち盆踊りとよさこい祭り
伊那市の通り町を歩行者天国にして、盆踊りやナイトマーケットを楽しむ「いなまち盆踊りとよさこい祭り」が、15日に行われました。
歩行者天国となった通り町で、初めに地元のよさこいチーム伊那よさこい青龍が踊りを披露しました。
このイベントは、盆踊りの伝統を残していこうと、通り町商店会や伊那節保存会、歌舞劇団田楽座などで作る実行委員会が行っていて今年で3回目です。
今年は祭りを盛り上げたいと初めてよさこい青龍が参加しました。
沿道にも多くの人が訪れ踊りを見学していました。
盆踊りでは、伊那節保存会が生唄を披露し、その周りで住民が踊りました。
商店の前では、飲食などの屋台が並び、100円くじには行列ができていました。
このイベントは、街の活性化につなげ、帰省した人たちが集える場所にしようと行われています。
-
伊那市成人式 719人が新たな門出
高遠町と長谷地区を除く伊那市のお盆成人式が、14日と15日、各地で行われました。
2日間の対象者は、男性367人、女性352人で、合わせて719人が成人を迎えました。
このうち、東部中学校区の竜東地区成人式は伊那公民館で行われました。
同じ東部中学校区の美篶と手良地区は、別会場で開催しています。
新成人たちは、懐かしい顔を見かけると互いに声をかけたり写真を撮ったりしていました。
式では、初めに伊那市の歌の斉唱が行われました。
竜東地区の成人式は、新成人で作る実行委員会が主催して行っています。
対象となる245人のうち142人が参加しました。
白鳥孝市長のビデオレターが上映され、「新産業にも力を入れている伊那で働くことは選択肢として非常に良いことだということを覚えておいてほしい」というメッセージが贈られました。
中学校時代の恩師の塚田 琢磨教諭は「使命という言葉は命を使うと書く。それぞれの人生の使命を果たしながら、どうか幸せになってほしい」と激励しました。
新成人を代表して北澤健汰さんは、「素晴らしいふるさと伊那市の一員であることを誇りに、責任ある社会人として歩んでいく」と決意を述べました。
最後に全員で万歳三唱をして新たな門出を祝いました。
-
南小河内伝統の「おさんやり」
箕輪町南小河内に伝わる厄除けの伝統行事「おさんやり」が、16日に行われました。
16日の夕方、お舟の巡航が行われました。
舟はナラとカラマツで作られていて、重さは600キロあります。
おさんやりは、区内を流れる大堰と呼ばれる用水路が天竜川と逆に流れていることから疫病の原因と考えられ、その厄を払おうと江戸時代から行われてきたとされています。
途中、辻では担ぎ手たちが輪になり歌を歌いました。
夜になると、お舟壊しが行われました。
ナラの木の周りを3周し、その後左右に揺らしながら舟を壊します。
お舟の破片は厄除けになるといわれていて、集まった住民が拾い集めていました。
破片は各戸の玄関に1年間飾られるということです。
-
春富中夏フェス
伊那市の春富中学校の3年生は、地域の活性化を目的としたイベント「夏フェス」を東西春近をつなぐ殿島橋で今日、行いました。
17日は、2005年の夏まで殿島橋で開かれていたどんぴちゃ祭り恒例の綱引き陣取り合戦が行われました。
綱引きは、3本勝負で行われました。
初めに3年生の女子生徒が自分の住む地区側で綱を引き、西春近が勝ちました。
続いて男子生徒による綱引きです。
勝ったのは東春近です。
1勝1敗で迎えた最終戦は、それぞれの地区住民が参加して綱引きが行われ西春近に軍配が上がりました。
イベントは3年生が地域の歴史を学習するなかで2006年の豪雨災害で旧殿島橋の橋脚が崩れ中止になった祭りを復活させ地域を盛り上げようと企画したものです。
生徒たちがポップコーンやかき氷などを販売するブースも設けられました。
会場には、保護者や地区住民が訪れイベントを楽しんでいました。
-
手良で早くも稲刈り
伊那市手良の田んぼでは、早くも稲刈りが行われています。
株式会社中坪ノーサンの田んぼでは、稲が丈夫で倒れづらい、早生種の「五百川」という品種の稲刈りが17日から行われています。
今年は例年よりも梅雨が長く、日照不足が心配されましたが、
梅雨明けの暑さが稲の成長を回復させたということです。
-
若手作家による公募個展25日まで
長野県ゆかりの若手作家3人による公募個展「トライアル・ギャラリー」が伊那市の伊那文化会館で開かれています。
伊那文化会館の美術展示ホールを3つに分け、3人の作家が個展を開いています。
飯田市出身の和全さんは、イラストと書を融合させた作品42点を展示しています。
世界の有名な絵画の一部を漢字に置き換えています。
箕輪町出身の唐澤安伊歌さんは、水彩画を中心に100点を展示しています。
このうちのひとつ「えにし」は、この展示に合わせて書いたということです。
木下北保育園の園庭にあるケヤキや萱野高原から見た街並みが描かれています。
人と人との縁を表現したということです。
駒ヶ根市出身の市岡一恵さんは、空間全体を使った作品を展示しています。
春日公園や伊那文化会館の中で市岡さんが気になったものを簡易的に再現したということです。
18日は、作家による解説も行われました。
若手作家による公募個展「トライアル・ギャラリー」は25日まで伊那文化会館で開かれています。
-
沢区で納涼祭
箕輪町沢区で恒例の納涼祭が14日に行われ、区民が夏の夕べを満喫しました。
納涼祭は、区民の親睦を図ろうと沢公民館が毎年、お盆に行っています。
会場となった公民館前には、フランクフルトや焼きそばなどの屋台が並び無料で振舞われました。
また、子ども達にも楽しんでもらえるようボールすくいや射的のコーナーも設けられました。
この日は、およそ400人が訪れ楽しいひとときを過ごしていました。
沢公民館の平澤正博館長は「毎年楽しみにして来てくれる区民も多い。納涼祭を通し区民の親睦につながればうれしい」と話していました。
-
夏の練習の成果試す
この夏の水泳の練習の成果を試す、上伊那選手権水泳競技大会が18日、伊那市の伊那東部中学校プールで開かれました。
大会には、上伊那地域の保育園児から50代の一般まで、およそ120人が参加しました。
大会は、小学生が夏の水泳の練習の成果を試す「学童泳力テスト」も兼ねていて、水泳教室に通っていない小学生も大会に参加していました。
また、一般の選手が参加することのできる上伊那地域で唯一の大会で、中には中学生と50代の選手が一緒に泳ぐレースもありました。
中学生と一緒に泳いだ50代の選手は「さすがに年齢の差は感じます。地元の50メートルプールで泳ぐことができる良い機会」と話していました。
上伊那水泳協会では「来年は日本でオリンピックが、再来年には長野県でインターハイがある。上伊那から大きな大会に出る選手が育ってほしい」と話していました。
大会の結果、350種目中8種目で大会記録が塗り替えられました。 -
迎え盆の伝統行事「まんど振り」
迎え盆の伝統行事「まんど振り」が13日上伊那各地で行われました。
南箕輪村大泉では親子連れおよそ40人が大泉川堤防に集まり
まんど振りを行いました。
集まった人たちはまんどに火をつけると勢いよく回していました。
まんど振りは祖先の霊を迎える伝統行事で地元有志でつくる大泉まんどの会により受け継がれています。
-
よさこいチーム フェスで演技
よさこいをはじめ、太鼓やチアダンスの演舞演奏を披露する「信州伊那谷よさこい・いな来い・
みな恋FESTA」が17日、伊那市防災コミュニティセンターと市民体育館サブアリーナ・エレコムアリーナで開かれました。
会場では、伊那市西春近を拠点に活動している、伊那よさこい青龍や、岡谷市を拠点に活動している青龍艶舞隊など、6つのよさこいチームが演技を披露しました。
他に、太鼓やチアダンスなどの団体が出演しました。
会場にはご当地料理や、かき氷などの販売ブースがおよそ20店舗並びました。
よさこい・いな来い・みな恋FESTAは、県内を拠点に活動している団体が参加し、今回で
2回目の開催となります。
-
南アルプスで77歳の男性行方不明

先月26日に南アルプスに入山した千葉県の77歳の男性が、下山予定日の30日を過ぎても下山せず、現在も連絡が取れていない状況です。
伊那署の発表によりますと、行方不明となっているのは千葉県鎌ケ谷市の無職 髙橋陞一郎さん77歳です。
髙橋さんは先月26日に南アルプス塩見岳に向けて入山し、下山予定日の30日を過ぎても下山せず連絡がとれないことから、家族が警察に届け出たということです。
警察では17日県警ヘリによる捜索を予定していましたが、天候が悪かったため、行えませんでした。
-
古紙回収箱で火事 不審火か
16日午後0時30分頃、伊那市上の原に設置されている古紙用無料回収ボックスから火が出ました。
この場所では、9日、15日にも火事があり、伊那署では不審火の可能性もあるとみて調べを進めています。
伊那警察署の発表によりますと、火事があったのは、伊那市上の原に設置された古紙用無料回収ボックスで、中に入れられていた段ボールを焼きました。
16日午後0時半頃地域住民から通報があり、火はおよそ10分後に消し止められました。
けが人はいませんでした。
この場所では、9日、15日にも火事があり、当時周辺に火の気はなかったことから、伊那署では不審火の疑いもあるとみて原因について調べを進めています。
-
3年ぶり復活 どろカップ令
田んぼに水をはり泥の中でサッカーを楽しむ「どろカップ令」が17日3年ぶりに伊那市下新田の遊休農地で開かれました。
3年ぶりとなるどろカップには県内を中心に愛知や岐阜などから24チームが参加しました。
試合は1ゲーム5分で、予選リーグと決勝トーナメントが行われました。
伊那商工会議所青年部が主催するどろカップは10回目となる2016年に終了しましたが、再開の要望もあり、青年部が復活させました。
参加者は、泥だらけになりながらもゲームを楽しんでいました。
イベントでは、サッカーのほかに泥綱引きも行われ、白熱している様子でした。
決勝戦は伊那市のスナック繭の常連などで作るチームと、前回優勝の駒ヶ根市の企業に技術研修に来ているベトナム人男性らのチームの対戦となり、2対0でベトナム人男性らのチームが前回大会に続き二連覇しました。
伊那商工会議所青年部では、市民の要望も鑑み、今後の大会開催を検討していきたいとしています。
-
もう一日休みを 盆正月
区の役員宅をバリケードで封鎖してもう1日休みを要求する南箕輪村田畑の伝統行事、盆正月が16日の深夜に行われました。
16日午後10時30分頃、田畑区長の松澤純一さん宅に地域住民が集まりました。
玄関をバリケードで封鎖して盆休みの1日延長を求める、田畑区に伝わる「盆正月」の行事です。
区長宅にあるものをつかって玄関を封鎖していきます。
盆正月は区のPTAでつくる田畑の伝統を守る会が毎年行っています。
子どもたちもバリケードづくりを手伝いました。
最後に、石灰で「お正月」と書いて完成です。
区長の家の飾り付けが終わると、次の標的を目指して出発していきました。
今朝6時。
区長宅には門松や鏡餅が飾られ玄関が封鎖されていました。
松澤さんは、玄関から出られず、隣の家の庭から表へ出てきました。
松澤さんは、区の役員にもう一日休みにすることをスマートフォンで連絡していました。
近所の人たちも今年の出来を見にやってきました。
バリケードは、午前11時頃から5人がかりで片づけたということです。
-
最高気温32.3度 熱中症の疑いで70代女性搬送

17日の伊那地域の最高気温は午後2時12分に、32.3度を記録しました。
上伊那広域消防本部によりますと、午後3時半現在、伊那市の70代の女性が熱中症の疑いで搬送されたということです。 -
箕輪町成人式
箕輪町の成人式は町文化センターで行われました。
対象者は男性158人、女性129人で、合わせて287人が成人を迎えました。
箕輪町の成人式は、新成人でつくる実行委員会が行っています。
式には新成人212人が出席しました。
実行委員会の小平貴男実行委員長は「まだ成人という実感はないが、一日一日を大切に確実に大人になっていきたい」と挨拶しました。
新成人を代表して 大槻裕さんは「未来の道を切り開くために、すべてのことに全力で取り組んでいきたい」、白鳥菜都さんは「学んだことをどう社会に活かしていけるかしっかり考え行動していきたい」と意見発表をしました。
白鳥政徳町長は「みなさんと一緒に未来の箕輪町を作っていく事を楽しみにしている」と挨拶しました。
式では、みのわ太鼓保存会による祝太鼓が披露されました。
保存会に所属する新成人も一緒になって太鼓を打ち鳴らし、記念の節目を祝っていました。
なお、伊那市の高遠町と長谷地区、南箕輪村は正月に成人式を行っています。
-
上農農業クラブ 最後の盆花市
南箕輪村の上伊那農業高校の生徒が盆花を販売する花市が、12日に伊那市のいなっせ北側とJR伊那北駅前で開かれました。
この花市は今回で最後になります。
カーネーションや小菊など、上農生が育てた7種類の盆花が、一束500円で販売されました。
いなっせ北側では、午前9時の販売開始を前に、およそ100人が列を作っていました。
盆花市は1953年(昭和28年)から、地域に感謝の気持ちを表す行事として受け継がれてきました。
しかし、来年度の学科改編に伴う地域活動の見直しにより、盆花市は今回で最後となります。
300束用意された盆花は、30分で完売となりました。
盆花市は今回で最後となりますが、農産物の販売は今後も続けていくということです。 -
山盛りフェスで特別メニュー
国民の祝日「山の日」を盛り上げようと、伊那飲食店組合の13店舗で11日に山盛りフェスが行われ、特別メニューが提供されました。
伊那市上牧の咲来軒では、山盛りつけ麺と山盛り煮カツ丼が提供されました。
山盛りつけ麺は、通常の3倍の麺とトッピングです。
麺は700グラムあります。
特別価格の1200円で提供されました。
山盛り煮カツ丼は、通常提供されている並盛のカツは2倍、ごはんは1.5倍です。
1800円で提供されました。
なんと、山盛り煮カツ丼を注文した人がいました。
山盛りフェスは、伊那谷で山の日を盛り上げようと、伊那飲食店組合を中心に4年前から行われています。
-
大芝高原でマウンテンバイク体験
南箕輪村の大芝高原で11日、初心者を対象にしたマウンテンバイクの体験イベントが行われました。
この日は、村内外からおよそ80人が参加しました。
イベントは、大芝高原やマウンテンバイクに慣れ親しんでもらおうと、村観光協会が開いたものです。
全長3キロのコースは、およそ30分程度で1周できます。
参加者は、自分のペースでコースを走っていました。
このコースは、平坦で危険も少なく森の中を気軽に走ることができるということです。
マウンテンバイクの体験イベントは、来月7日にも予定されています。
-
31日から千両千両井月さんまつり
幕末から明治にかけて伊那谷を放浪し、数々の俳句を残した井上井月をしのぶ、第7回千両千両井月さんまつりが、31日と来月1日の2日間、伊那市のいなっせで行われます。
10日は、伊那市美篶の矢島信之さん宅で記者会見が開かれました。
井上井月顕彰会顧問の宮下宣裕さんをはじめ、会のメンバーがイベントの見どころを説明しました。
31日は、「井月さんが生きた夜明け前の時代」をテーマに、講演会のほか、劇中で伊那が登場し、伊那谷と関連のある島崎藤村原作の映画「夜明け前」の上映会などが予定されています。
また、9月1日は第28回信州伊那井月俳句大会が予定されています。
ほかに、井月にゆかりのある書物の展示も25日から来月1日まで予定されています。
第7回千両千両井月さんまつりは31日と9月1日の2日間、いなっせで行われる予定です。
-
箕輪町の沢公民館で寺子屋教室
箕輪町の沢公民館で10日、寺子屋教室が開かれ、夏休み中の児童が勉強や工作を楽しみました。
この日は、箕輪町沢区の小学生12人が参加し、夏休みの宿題や竹とんぼ作りをしました。
竹とんぼ作りの講師をつとめたのは、伊那市荒井の久保村隆さんです。
児童は、久保村さんにやすりの掛け方や羽の曲げ方などを教わりながら、思い思いの竹とんぼを作っていました。
竹とんぼが完成すると、より遠くに飛ぶよう練習していました。
また、子どもたちはスイカ割りも楽しみました。
子どもたち同士で声を掛けながら、スイカの前まで誘導します。
夏休みの寺子屋教室は、子どもたちに夏休みの思い出を作ってもらおうと、毎年沢公民館が開いています。
-
川上一巳遺作展 17日まで開催
伊那谷の風景や人物を描いてきた、岡山県出身の川上 一巳さんの遺作展が、伊那市のかんてんぱぱ西ホールで開かれています。
会場には、77点の作品が並んでいます。
遺作展は川上さんが死後に従四位・瑞宝小綬章を受章したことを記念し、親族が企画しました。
親族のひとり、三宅由紀さんによると、川上さんは伊那谷の自然に魅了され、毎年春に訪れては風景画を描いてきたということです。
また、自然の中で元気に遊ぶ子どもに魅力を感じたことがきっかけで、子どもをモデルにした人物画も多数描いてきました。
「川上一巳 従四位・瑞宝小綬章受章記念遺作展」は、17日(土)の午後3時まで、伊那市のかんてんぱぱ西ホールで開かれています。
なお、モデルが不明だった2枚の絵のうちの1枚「伊那路の子」は、モデルが判ったということです。 -
経口ワクチン接種率50.8%

長野県は先月散布した野生イノシシに対する経口ワクチンの摂取状況を9日発表しました。
それによりますと上伊那でのイノシシの摂取率は50.8%でした。
豚コレラは豚、イノシシの病気で感染した野生イノシシが移動することにより養豚場のブタへの感染が懸念されています。
経口ワクチンはそれを防ぐためのものでイノシシが摂取すると豚コレラへの免疫力が高まります。
上伊那では伊那市と辰野町の25か所に500個が散布されそのうち254個が摂取されたとみられていて摂取率は50.8%でした。
県内では木曽が53%、南信州が37.3%、諏訪が33%で県平均は46.9%でした。
県は野生イノシシに抗体ができているかどうか今後行う本格散布に併せて検証していくとしています -
自転車観光でサイクルスタンド作り
マウンテンバイクを立てたまま停めることができるサイクルスタンドを作るイベントが10日、箕輪町の箕輪町文化センターで開かれました。
このイベントは観光地が点在する辰野町、箕輪町、南箕輪村を
自転車でつなぎ広域的な観光づくりを目指している上伊那北部観光連絡協議会が開いたもので、地域住民25人が参加しました。
講師を務めたのは辰野町在住の自転車冒険家で地域おこし型サイクリングガイド団体代表の小口良平さんです
参加者は小口さんの指導で木材を組み立てたりロゴマークを付けたりしてサイクルスタンドを作っていました。
マウンテンバイクやロードバイクは軽量化を図るため自転車を立てるスタンドがついていないのが標準でサイクリストが集まる観光施設や飲食店ではサイクルスタンドが必要になるということです。
観光地点を自転車でつなぎ広域的な観光地づくりを目指している
上伊那北部観光連絡協議会ではその第一歩としてサイクルスタンドづくりを計画しました。
上伊那北部観光連絡協議会では今年30基ほどのサイクルスタンドを作り観光施設などに順次設置していくことにしています。
-
上伊那の6月の有効求人倍率
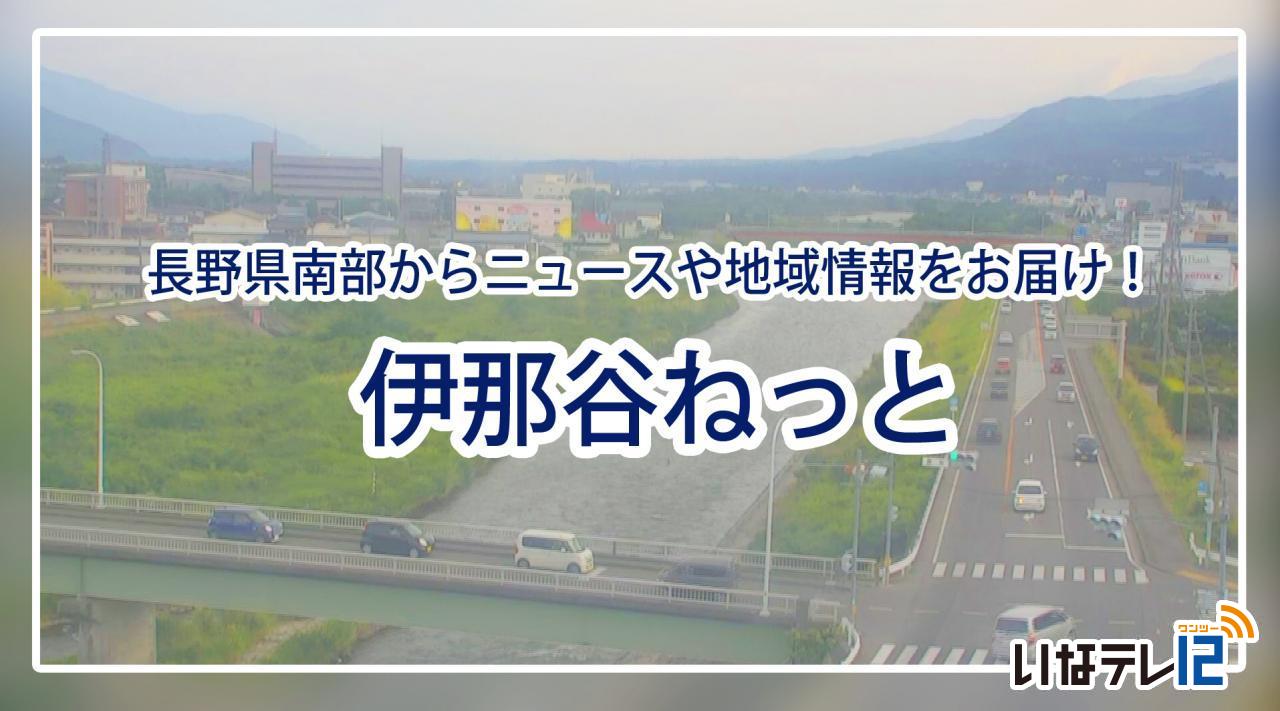
上伊那の6月の月間有効求人倍率は、5月を0.07ポイント下回る1.46倍でした。
月間有効求人数は3,888人、月間有効求職者数は2,660人で6月の月間有効求人倍率は1.46倍でした。
県は1.65倍、全国は1.61倍となっています。
雇用情勢についてハローワーク伊那では「堅調に推移している」として前の月の判断を据え置きました。
-
猛暑日 熱中症で搬送3件

9日の伊那地域の最高気温は午後1時57分に35.5度を記録し、猛暑日となりました。
猛暑日となるのは、この夏7日目です。
上伊那広域消防本部によりますと、午後4時半現在、熱中症の症状による搬送は伊那市野90代の女性、箕輪町の50代の女性、駒ヶ根市の10代の女性の3件だということです。
-
極早生の夏あかり選果
極早生のりんご「夏あかり」の選果作業が、箕輪町のJA上伊那果実選果場で行われています。
夏あかりは、お盆のニーズにあわせてJA上伊那で最も早く出荷されるりんごです。
人の目でキズのチェックを行い、大きさや熟度などを測定する光センサーを通して箱詰めされていきました。
選果は7日から始まり、盆明けの18日頃まで行われます。
夏あかりは、JA上伊那 伊那中央店で主に取り扱われる他、徳島県や中京方面に出荷されるということです。
-
工業高校生が技術を競う
工業高校の生徒が日頃から培った技術を競う「ものづくりコンテスト 電子回路組み立て部門」の県大会が9日、南箕輪村の南信工科短大で開かれました。
コンテストには県内の4つの工業高校から15人が出場しました。
駒ヶ根工業高校からは電気科3年で西箕輪中出身の唐澤雅和さんと、宮田中出身の太田惟尋さんが出場しました。
課題は、2時間30分の時間内に電子回路の製作とプログラムの作成を行い、ランプを点灯させたり数値を表示する装置を作るというものです。
生徒たちは、はんだごてを使い、ハード部分の電子回路を製作していました。
回路がおおむね完成すると、今度はソフト部分にあたる制御プログラムを作成していました。
高校生ものづくりコンテストは、長野県工業高等学校長会が毎年開いています。
コンテストは、旋盤作業や電気工事など6部門があります。
電子回路組み立て部門では、コンピュータ制御システムの構築をテーマに、装置の完成度や技術が審査されます。
審査の結果、松本工業高校と岡谷工業高校の生徒の北信越大会進出が決まりました。
1211/(水)

























