-
温泉のお菜洗い場設置
大芝高原17日、箕輪町長田18日から
箕輪町長田の「みのわ温泉ながたの湯」の西に18日から、恒例のお菜洗い場が開設される。15日、町役場産業振興課が洗い場や看板を設置した。
温泉で温かく作業ができ、お湯で洗うことことでやわらかくおいしく漬かると人気のお菜洗い場。
開設期間は12月17日まで。毎週火曜日は休み。時間は午前8時縲恁゚後9時。無料。
産業振興課は「お菜くずは必ず持ち帰り、順番に仲良く使って」と呼びかけている。
南箕輪村では、大芝高原に恒例のお菜洗い場を設置する。
期間は17日から12月20日まで。午前8時20分縲恁゚後8時。無料。
村開発公社は、お菜くずの持ち帰り、順番を守った使用を呼びかけると共に、「不凍栓は勝手にしようしないで」と話している。 -
狩猟解禁
箕輪町内で安全パトロール箕輪町、伊那署箕輪町警部交番、町猟友会は狩猟解禁日の15日早朝、違法捕獲や事故の防止のため町内をパトロールした。
関係者8人がパトロールに参加。午前6時から約2時間半、東部地区と西部地区の山際、天竜川沿い、狩猟禁止の箕輪ダム周辺などを回った。
午前6時25分の日の出と共にハンターが繰り出し、西部地区のパトロール中に出会ったハンター4人に対し狩猟免許を確認し、安全を呼びかけた。事故や違反はなかった。
町などは「狩猟者は安全確認を徹底して。住民も狩猟期間になったので注意を」と理解を求めている。 -
郷土研究交流の集い 近世上伊那の飢饉などテーマに

上伊那郷土研究交流連絡会(竹入弘元会長)は11日、伊那市荒井区の上伊那郷土館で、「第7回上伊那郷土研究交流の集い」を開いた。会員ら約50人が参加。同館所蔵の資料見学や、小中学校教師らでつくる同館専門委員による研究発表などがあった。
原毅教諭(宮田小)、小野章教諭(西箕輪小)、北林敏文教諭(箕輪中)が研究発表=写真。原教諭は「大久保文書からみた近世上伊那地方の飢饉」と題し、江戸時代に2回あった凶作について書かれた文書の内容を解説した。
説明によると、天明期における野口村(現・伊那市手良)の餓死者は105人で、飢饉は浅間山の噴火による寒冷で農作物が生産できなかったなどが原因とした。
屋根板(樽木)を主な税として納めていた中坪村(現・同)では、森林資源の枯渇も要因の一つにあげ「今後は樽木の生産高の減少と年貢の変遷に伴う中坪村の様子の変化と飢饉の関係を明かにしたい」と話した。
館内見学は、神子柴遺跡(南箕輪村)出土の石器、俳人の野口在色の資料などを担当者が説明した。 -
池坊伊那支部青年部北部ブロック
ミニ華展
池坊伊那支部青年部北部ブロックのミニ華展が14日、箕輪町のアルプス中央信用金庫いほく支店ロビーで始まった。前期、後期2日間ずつで作品替えをし17日まで開く。
青年部(宮沢京子部長)は上伊那在住の97人。北部ブロックは箕輪町、辰野町を中心に15人いる。年1回のミニ華展で、今回は14人が前期と後期7人ずつで、日ごろのけいこの成果を披露する。
作品は自由花が主で菊、リンドウ、グロリオーサなど身近な花に、秋らしく紅葉した葉を使うなどして生けている。
北部ブロックでは、「今回は身近な花で簡単にでき、自分も家族も和むほほえましい花が多い。ロビーで花を見て一息ついてほしい」と話している。 -
【記者室】箕輪町長選…現職再選
箕輪町長選挙。正式な出馬表明は現職のみで無投票ムードも漂う中、住民有志の新候補擁立は続き、最後まで選挙戦突入か否かは微妙な状況だったが、結果は無投票。現職再選で幕を閉じた▼現職は町内全域を網羅した後援会組織で広く支持を集めた。「もう1期やらせてやりたい」。そんな声の一方で、町民の中からは選挙戦を望む声も聞こえた。新たな町政を望んだ住民有志も、ぎりぎりまで動き続けた▼霧雨が降り始めた昼前、西山に虹の橋が架かった。平沢町政の新たな4年間は、町の未来にどんな橋を架けるのか。現職の手法を疑問視し「本当の民意をくんでくれる人」を望んだ住民がいることも心に留めつつ、町民のための町政運営をされることを期待する。(村上裕子)
-
ガールスカウト長野26団 高遠町でウォークラリー

伊那市などの団員らでつくるガールスカウト長野第26団(木部則子団委員長)は12日、一般参加者を募った「子どもたちの居場所づくり事業」の一環として、同市高遠町のホリデーパーク周辺でウォークラリーを開いた。
園児、児童の団員ら23人が参加。4グループに分かれた子どもたちは、同町内の白山橋、歴史博物館、桂泉院、高遠城址(し)公園など6カ所を順番に回り、それぞれで出題される問題に挑戦した。
「橋の長さを自分の歩数で測って距離を割り出す」「大きな木の周りをロープで測る」などの出題をグループごとが力を合わせて正解を考えた。高遠城址公園では落ち葉などの自然物を使って、一人ずつ画用紙に・ス秋・スを表現する工作も楽しんだ。
出発時点では雪が空から落ちてきて肌寒さを感じていたが、次第に日の光りが降り注いでくると、赤や黄色に色づいた周囲の紅葉に目を見張っていた。 -
福澤雅志世会演奏会 輪の音楽の花咲く

伊那市で筝の教室を開く「福澤雅志世会」の2回目の演奏会が12日、同市の伊那北地域活性化センター「きたっせ」であった=写真。伊那三曲協会員による賛助出演など計61人が、11演目を繰り広げた。
同教室の「おさらい会」に、約80人の観客が集まった。出演者全員参加の合奏曲「六段」、教室に通う児童らの「一茶のおじさん」などを披露し、雅な音の世界が会場に広げた。
教室は1971年に、指導者の福澤雅志世(73、本名・靖子=同市山寺=)が開いた邦楽教室。福澤さんが筝を習い始めて60周年の記念に1回目の演奏会をし、今回は68周年の記念となった。
福澤さんは「和の精神をモットーに努力を重ねてきた。ステージにどんな日本の音楽の花が咲くか期待して」と話した。 -
オペラの発展学ぶ 長谷公民館で生涯学習講演会

作曲家、指揮者、ピアニストとして有名な青島広志さんを招いた「生涯学習講演会inはせ」は12日、伊那市の長谷公民館で開いた。市内から約180人が集まり、青島さんのピアノ伴奏に平松混声合唱団長の小野勉さんが声楽(テノール)で参加した演奏を楽しんだ。
長谷地区文化祭に合わせた恒例の講演会。青島さんは「オペラからミュージカルへ」と題して、西洋の娯楽の中心であった舞台芸術のオペラの発展を語るため、年代を追いながら代表曲10曲を演奏し、それらの作曲家や劇内容について説明した。
「昔は宗教に縛られ男性しか出演できなかった」「時代が変るごとに高音が使われるようになった」などの説明の中にも冗談を交えて講話。生誕250年のモーツアルトなども、分かりやすくおもしろい切り口で教授した。
酒井さや香さん(32)=長谷非持=は「オペラについての豆知識を知り、オペラに興味がわいた。とても分かりやすく、楽しい解説だった」と話していた。 -
税を知る週間
南箕輪役場で児童・生徒の作品展
南箕輪村は11日から17日の「税を知る週間」に合わせ、書道と標語の作品に応募した村内小・中学生の入選作品展を17日まで、役場ホールで開いている。
村関係分の応募作品数は小学生対象の書道が456点、中学生対象の標語が63点。
作品は期間中に展示替えする。 -
「遺伝子DNA」講演会
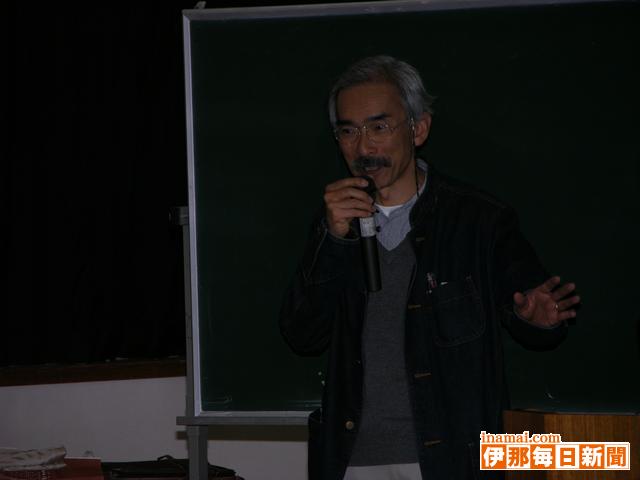
駒ケ根市の赤穂、中沢、東伊那の3公民館でつくる駒ケ根市公民館協議会は駒ケ根ふるさと講座の第2弾として11日、分子遺伝学、分子生物学が専門の信州大理学部長伊藤建夫さんを講師に迎えて「遺伝子DNAは語る竏宙笂`子組み換え食品の問題点」を開いた。市民ら約20人が集まり、普段あまり馴染みのない遺伝子の話に耳を傾けた。
伊藤さんは遺伝子の形と働きなどについて分かりやすく説明した上で遺伝子組み換え食品について「世界の食料事情などの理由から遺伝子組み換え食品が盛んに研究されているが、作物、技術、遺伝子、ヒト、家畜などに対する安全性を慎重に見極めなければならない」と話した=写真。 -
小黒川渓谷キャンプ場釣り堀感謝祭

伊那市の小黒川渓谷キャンプ場で12日、釣り堀感謝祭があった。エサ代無料などのサービスがあり、多くの家族連れが釣りを楽しんだ。
昨年に続き、2回目。市振興公社が、一昨年の台風被害で迷惑をかけたおわびと、利用者や地域への感謝を込めて計画したのがはじまり。
釣り堀は平均100グラムのニジマスを放し、大きいもので200グラムあるという。釣った魚は通常100グラム180円だが、この日は大小かかわらず1匹100円で提供した。
上伊那各地から午前中だけで約100人が訪れ、見ごろを迎えた渓谷の紅葉も楽しみながら、糸をたらしてじっと当たりを待っていた。午前中は冷え込んだせいもあって魚の食いつきが悪かったが、なかには30匹釣った家族もいた。
市内から家族5人で訪れた会社員の男性(38)は「釣り堀を利用したのは初めて。子どもと一緒に楽しめていいですね。今日は家族みんなで塩焼きにして食べたいと思ってます」と話し、何匹も釣り上げていた。
利用者たちは、釣った魚をその場で、炭火で焼いて味わっていた。 -
「はるちかコーロ・フェリーチェ」発表会

伊那市の東春近公民館の女声コーラスグループ「はるちかコーロ・フェリーチェ」の発表会は11日夜、同市の県伊那文化会館で開いた。メンバー32人が家事や仕事を工面して練習に励んできた成果を披露。会場の隅々に広がる美しいハーモニーが約530人の観客を魅了した。
曲は、クラシック、日本の叙情歌や民謡、人気テレビドラマの主題歌など、幅広いジャンルの19曲。練習で苦労したという「こきりこ」「長持唄」「会津磐梯山」などは、民謡を声の重なり合いのある編曲で新鮮に聞かせた。
指揮者の田中真郎さん(箕輪工業非常勤講師)ふんする・スヨンさま・スが登場し「冬のソナタより『はじめから今まで』」の指揮をするなど、時折、笑い声が会場にわくこともあった。
「はるちかコーロ・フェリーチェ」は1989年に発足した、同地区では初めての女声コーラスグループ。地元を中心に40縲・0歳代の主婦らがメンバー。3年に一度の発表会を開き、今回で5回目。
会場に美しいハーモニーを響かせるメンバーら(県伊那文化会館) -
伊那フィル第19回定期演奏会 ハーモニー美しく

伊那フィルハーモニー交響楽団(北澤理光団長)の第19回定期演奏会は12日、伊那市の県伊那文化会館で開いた。バイオリン、チェロ、クラリネットなど数種類の楽器で奏でた音色が約600人の観客を魅了した。伊那毎日新聞社など後援。
プログラムは、メンデルスゾーンの「真夏の夜の夢」の「結婚行進曲」などを演奏した。シベリウスの「交響曲第2番」は今回のメーンで約50分間の演奏。フィンランド生まれの作曲家による、母国の四季を奏でた音楽に惜しみない拍手がわいた。
北澤団長は「来年は20回目の定期演奏会。これまで続けてこれたことが夢のよう。これからも伊那フィルの温かみのある演奏を継続していきたい」と話していた。 -
税を知る週間
箕輪町内小・中学生の税に関する作品展示
11日から17日までの「税を知る週間」に合わせ箕輪町租税教育推進協議会は11日、町内小・中学生の税に関する書道・標語・作文の入選作品展を役場玄関ホールで始めた。展示は17日まで。
同協議会が作品を募集した。応募数は中学生の標語108点、作文27点、小学生の書道709点。 -
駒ケ根市民ネパール訪問団出発

国際協力友好都市協定締結5周年を記念してネパール・ポカラ市を訪問する友好親善市民訪問団(団長・中原正純市長)が11日早朝、駒ケ根市を出発した。市武道館前で行われた出発式で中原市長は見送りの家族や市職員らに対し「所期の目的を果たし、元気で帰って来たい」とあいさつした。
訪問団は33人。中原市長をはじめ、北澤洋市議会議長、駒ケ根青年海外協力隊訓練所の加藤高史所長、ネパール交流市民の会などの団体代表者らが参加したほか、一般市民からの希望者も十数人含まれている。
計画によると訪問団は11日に中部国際空港からバンコクに向けて出発。12日にネパールに入り、13日にポカラ市着。記念式典など公式行事に出席するほか、青年海外協力隊員の活動を視察するなどして19日に帰国の予定。 -
佐野成宏講演会

駒ケ根市の赤穂高校PTAは11日、学校創立90周年を記念する講演会を同校で開いた。イタリアを本拠に世界で活躍するオペラ歌手で同校の卒業生でもある佐野成宏さんを講師に迎えて「夢の在り処」と題した講演を生徒、保護者、同窓会員ら約700人が聴いた。
ステージに上がった佐野さんはまずオペラのアリアを1曲披露=写真。その後も話の合間にオペラ曲やイタリア民謡などを数曲歌った。聴衆は伸びやかでつやのある歌声に感嘆し、大きな拍手を送っていた。
佐野さんは歌手になったいきさつなどについて高校時代の思い出などを交えてユーモアたっぷりに話し「進む道を意外とスムーズに見つけることができた自分は幸せだった。こんな時代だから、などというが夢を持つことは大事。どんなことでもいいからこうしたい、こうなりたい竏窒ニいう夢や希望をいつも頭の片隅にでも持っていてほしい。きっといつかは実現できるのではないか」と生徒らに語り掛けた。 -
ハッチョウトンボ中間報告会

ハッチョウトンボの生息地として知られる伊那市富県新山の「トンボの楽園」生息調査の中間報告会が11日、市役所であった。本年の調査で3種を追加、合計30種になった。
新たに加わったのはアジアイトトンボ、オオヤマトンボ、コフキトンボ。
市は05年から、日本蜻蛉(とんぼ)学会長の枝重夫さん=松本市=に生息調査を委託。本年は6縲・月にかけ、現地を訪れた。
枝さんは指標昆虫であるハッチョウトンボやムカシトンボをはじめ、ルリイトトンボ、オツネントンボなどの写真をスクリーンに映し出し、名前の由来を交えながら、羽化や産卵などの生態を説明。「オオシオカラトンボのしっぽの先はひしゃくのようになっていて、水をはね上げて産卵する」など興味深い話に、集まった地域住民約30人が聞き入った。
流水性のトンボは調査していないため、市内で「60種はいるのではないか」という。
主催者の一つである新山山野草等保護育成会の北原重利委員長は「市民の協力を得ながら生息地を守り、後世に残していきたい」と話した。
会場には、トンボの標本なども展示された。 -
つくしんぼ保育園のシクラメン販売

伊那市御園のつくしんぼ保育園によるシクラメン販売が11日から、伊那市のニシザワショッパーズ双葉店前で始まった。鮮やかに咲いた約2千鉢以上のシクラメンが、訪れた人の目を楽しませている=写真。
私立である同園は、公立保育園より行政補助が少なく、補助金だけでは十分な運営ができない。そのため保護者や職員でつくる「つくしんぼの会」は例年、園の運営費を確保するためのバザーやシクラメン販売を実施。職員と保護者が協力しながら、園のあり方を考えている。
シクラメンは市内の生産者から購入しており、市価より安いだけでなく、丈夫で長持ちするとあって人気。毎年買いに来る人もいる。今年も赤やピンク色、絞り模様など、さまざまな種類を準備。昨年より花が大きく、株もしっかりしているという。
この日は、保護者や職員など約30人が朝から準備して1鉢1300円で販売。園の関係者だけでなく、地元住民も多数訪れ、盛況を見せた。
シクラメン販売は12日も同じ場所で行う予定で、時間は午前10時縲恁゚後3時。今後は、各地区に分かれて個別訪問販売も行う。
個人的に購入を希望する人への販売もしている。
問い合わせはつくしんぼ保育園(TEL78・4157)へ。 -
みのりんぐ箕輪ねっと
「生しぼり えごま油」一般販売12日から
箕輪町、南箕輪村、伊那市西箕輪で地域通貨を通した地域経済の活性化を図る「みのりんぐ箕輪ねっと」(寺平秀行代表)は、活動の一環で栽培したエゴマの商品「生しぼり えごま油」を12日から一般向けに販売する。
03年8月に発足。05年度、労働に対し地域通貨「みのり」を発行し、「みのり」に応じてエゴマ油を分配する事業に取り組んだ。一般販売したエゴマ油100本は1週間で完売した。
今年は、栽培面積を昨年の13アールから43アールに広げ、エゴマ240キロを収穫。駒ヶ根市の業者に依頼して1次販売用に107キロ搾油し、150ミリリットルビンで240本できた。「昨年よりフレッシュな香り。種を食べたときの味で、素材そのままの味が生きている」という。
会員分配用は、本年度コモンズ支援事業に認定され、購入した搾油機で搾油する。
販売は1本1980円(税込み)。取り扱い店は箕輪町内かしわや、立石、金星、南箕輪村内ファーマーズマーケットあじ縲怩ネ、伊那市内あびえんと。問い合わせは寺平代表(TEL70・5728)へ。 -
南箕輪村で地区防犯部の青色回転灯パトロール始まる

南箕輪村で10日夜、村内12地区に設置している防犯部による青色回転灯パトロールが始まった。初回は久保区の防犯部で、役員が青色回転灯を装着した自動車に乗り込み、1時間強かけて村内を回った。
村は、11月から毎月ゼロのつく日を「南箕輪村防犯の日」と定め、パトロールなどに取り組む。住民主体の各区の防犯部も活動に参加し、村所有の青色回転灯装着車両で順番にパトロールする。村内を1周するパトロールマップのコースを基本とし、各部で工夫して巡回。運行日報を書く。時間は定めず、各部に任せている。本年度は3月末までに全防犯部が1回実施する計画になっている。
久保の防犯部は原弘満部長ら役員4人が参加。原部長は「何事もないように祈って回りたい」と話し役場を出発した。 -
伊那防火管理協会 消火通報コンクール

伊那市など4市町村の企業でつくる伊那防火管理協会(藤澤洋二会長)は10日、消火通報コンクールを伊那市営プール駐車場で開いた。消火器操法など2種目に11事業所から16チームが参加し、訓練の成果を披露した=写真。
15回目のコンクール。消火器と屋内消火栓を正しく取り扱い災害発生時に活用すると共に、正確な119番通報の習得を目指す。
競技は、木箱とオイルパンからの出火を消火器を用いて消火する「消火器操法」と、ホースを伸ばし標的へ放水する「屋内消火栓操法」があり、それぞれ操作時間や動作の正確さを競った。
消火器操法では、用意した2本の消火器のうち、1本だけで消火するチームや、2本使用するチームなど成果はさまざまだった。
入賞したチームは次の通り。
【消火器操法】(1)伊那バス(2)中部電力伊那営業所(3)石川島汎用機械B
【屋内消火栓操法】(1)中部電力伊那営業所(2)石川島汎用機械(3)伊那市役所 -
ベル伊那で七宝展 14日まで
諏訪市にアトリエを構える平林義教さん(47)と妻の利依子さん(45)の「七宝展」は14日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。
有線七宝によるネコをモチーフとした「合子」「蓋物」などの器や、季節の花をテーマにした額、トンボ玉のアクセサリーなどの約300点を展示販売している。
義教さんは「美術工芸品としての七宝焼きで、いろいろなものが作れることを見てほしい」と来場を呼びかけている。
午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -
箕輪町公民館子育て学級おやつ作り

箕輪町公民館の子育て学級は9日、町保健センターで保育園の生活、昼食やおやつの話を聞き、親子でおやつ作りにも挑戦した。
町管理栄養士の柴倫子さんが指導。保育園の1日の流れを紹介し、昼食とおやつは手作りで、おやつは食事の一部との考えで出していることなどを話した。
来春からの保育園生活に向け生活リズムを整える、朝に排便をきちんとする、朝から野菜料理を出してあげることなどもアドバイスした。
おやつ作りは、9月下旬の町の「健康づくり週間」で募集したレシピの中から、「おからクッキー」と「混ぜ混ぜえびピラフ」の2品を紹介。ピラフはおやつとして少量をラップで包んでおにぎりにした。エプロン姿の子どもたちは、自分でラップにご飯を盛り、ぎゅっとにぎっておにぎり作りを楽しんでいた。 -
河川アダプトプログラム協定調印

駒ケ根市内を流れる天竜川の支流七面川の環境整備を昨年から行っている七面川管理委員会(会長・清水春雄市場割区長、13人)の活動を支援する県の河川アダプトプログラム事業の調印式が10日、駒ケ根市役所で行われた。県伊那建設事務所の松下泰見所長、中原正純市長らとともに清水委員長が協定書に調印し、笑顔で握手を交わした=写真。河川を対象にしたアダプトプログラム協定の締結は同事務所管内で初。
協定により、県は七面川の約千メートルの対象区間内で同委員会が行うアレチウリなどの外来植物の駆除、草刈り、ごみの回収、樹木の伐採などの美化活動に使う草刈り機の替刃やかまなどの消耗品を支給するほか、委員らの傷害保険料を支援する。
松下所長はあいさつで「この調印により、住民による河川環境整備が今後の大きな流れになることを期待する」と述べた。 -
南箕輪村開発公社
無料入浴券利用分の入湯税未納額15日に納付南箕輪村開発公社の無料入浴券利用分の入湯税が未納だった問題で公社は10日、村の更正決定に基づき入湯税と未納分の延滞金を15日に村に納入することを明らかにした。
入湯税については10月25日の公社理事会で、税法解釈の誤りから未納だったことを報告。税金更正決定の3年間、03年9月までさかのぼって調査し、資料が残っている範囲で延滞金も含め村に納付する方針を示していた。
村は11月1日付で更正決定した。未納分は、大芝荘の宴会利用客と宿泊客に配っている無料入浴券が05年4月から06年9月まで、大芝の湯回数券に付いている無料券は03年10月から06年9月まで、まっくんバス回数券の無料券は発売された03年11月から06年9月まで。納入される税額は12月の村議会に補正予算で計上する。
大芝荘での無料入浴券配布は来年2月末で終了し、配布分の入湯税は公社が負担。3月1日から300円の割引券に切り替える。公社は、「サービスを下げることなく今後も頑張っていきたい」としている。 -
伊那部宿を考える会 中村伯先らを調べ成果披露
伊那市の伊那部宿を考える会(田中三郎会長)は11、12日、伊那市西町の伊那部集会所、長桂寺などある、地元の文化祭で、伊那部出身の俳人で医者の中村伯先(1756竏・820年)を取り巻く人物などについての研究成果を資料や写真などで発表する。
同会は、伯先の弟で医師の吉川養性の碑や、伯先の息子・元恒が詠んだ「箕輪十勝之詩」などについての解読結果を展示。田中会長は「伯先の先祖や子孫にも立派な人がいたことを地元の人にも知ってほしい」と来場を呼び掛けている。
中村伯先関係の展示は長桂寺で開催。近くの旧井澤家住宅では恒例の骨董市もある。11日は午前9時縲恁゚後5時。12日は午後3時まで。
研究成果をながめる伊那部宿を考える会のメンバー -
一日女性消防体験

秋の全国火災予防運動(9日縲・5日)初日の9日、伊南防火管理協会と伊南行政組合消防本部は「一日女性消防体験」を駒ケ根市の北消防署で開いた。同本部管内の女性約20人が参加し、消火器操作の実習などを行ったほか、てんぷら油火災の実験などを通じて火の恐ろしさを再認識した。
消火器の操作訓練では、参加者らが署員の説明を受けながら訓練用の水の入った消火器を1本ずつ持って放水した=写真。参加者の約半数が消火器の操作は初めてとあって「いざという時のためによい経験ができた」と話していた。
てんぷら油の発火実験では署員が「コンロの火が油に燃え移るものと勘違いしている人が多いが、実は油が一定の温度になると発火する。つまり火を使わない調理器具でも火災は起きる」と説明すると参加者らは「知らなかった」と驚いていた。 -
伊那おやこ劇場
舞台を一緒に作り上げる楽しさ感じて伊那おやこ劇場の高学年例会「ミュージカル ファイブ」が4日、伊那市の県伊那文化会館であった。出演する5人の役者と共に、おやこ劇場のメンバーが搬入、搬出作業に加わった。ただ舞台を鑑賞するだけではない、役者との関わりや一緒に作り上げる楽しさを、子どもも大人も皆が感じた。
おやこ劇場は、高学年と低学年でそれぞれ年4回の生の舞台を鑑賞し、1回は大きな舞台を呼ぶ。
今回の「ミュージカル ファイブ」は、今年のメーン企画。半年以上も前から準備してきた。準備の中から生まれるものは、親子のふれあい、仲間づくり。「生ものの舞台に手をかけることに十分意味がある。劇を観るだけでない良さを知ってほしい」と春日伸子運営委員長は言う。
「手伝うことで観る意識が変わる。役者とも随分近くなれる」。搬入搬出の手伝いなどは主に中学生以上だが、例会によっては小学生も協力。舞台づくりの楽しさを味わっている。
会員は伊那市から辰野町まで300人いるが、特に小学校入学前の年代の加入が減少。「もし子育てで行き詰っている感じがあったら、ぜひ入会してほしい。おやこ劇場にはふれあいがある」と呼びかけている。
問い合わせは伊那おやこ劇場(TEL72・7447)へ。火曜日から金曜日の午前9時半から午後3時まで。 -
霜柱ができ始め

強い寒気の影響で朝方の最低気温が氷点下となる日が続き、霜柱も顔を出した=写真。
霜柱が良くできるのは、夜間を通して快晴で冷え込みの厳しい日。これは、日本付近一帯を高気圧が覆っているということでもあり、「霜柱が立てば晴れ」と言われるように、霜柱ができた日は好天に恵まれることが多い。
しかし、あまり寒すぎても霜柱はできず、柱のもととなる地中の水分が凍らない程度の寒さの時期にしか見られない現象でもある。
伊那地域では、放射冷却現象の影響も受けて7日にマイナス3度、8日にマイナス2・6度の最低気温を記録。これは12月上旬並の最低気温で、暖かな日が続いた影響もあり、一層の寒さが感じられた。 -
冬を前に地バチの交尾始まる

本格的な冬の到来を前に、伊那市地蜂愛好会(小木曽大吉会長)が市内に設置しているシダクロスズメバチのとりこみハウスでは、女王バチの交尾が始まった=写真。
3月末から活動を開始するシダクロスズメバチ。働きバチが羽化するのは6月ころだが、次世代のオスと女王は、10月下旬縲・1月中旬に羽化する。オスは女王にやや先行して羽化し、約1カ月弱で死んでしまうが、女王は卵を蓄えて越冬。翌年の春に再び目覚め、新しい巣を構える。
ハチ追いを楽しみながら、ハチ資源の増殖にも努めている同会は例年、人工的に越冬させた女王バチを山に放す活動を続けている。とりこみハウスは、越冬させる女王を確保するためのもので、小屋の中には今年営巣した巣箱を置き、えさを運ぶ働きバチだけが行き来きできる網を張り巡らせてある。外に出られない、女王バチとオスは小屋の中で交尾するため、卵を蓄えた女王は小屋の中で越冬体制に入る。その女王を回収し、マイナス2縲・度に保った冷蔵庫の中で保護。無事越冬させた女王を翌年の春に会員らに配り、山へと放つ。昨年は当初目標としていた1万匹を上回る約1万4千匹の越冬にも成功した。
1回の交尾で何万個という卵を蓄える女王バチ。自然会では天敵のクモに襲われるケースも多く、実際に冬を越せる割合は10分の1程度だという。
最後の力を振り絞り、女王の幼虫にえさを運ぶ働きバチが行き来する小屋の中では、新しい命を宿そうとするオスと女王バチが乱舞していた。
201/(火)
