-
手づくりの第九演奏会
伊那、木曽合同練習始まる
伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネル開通を記念した「手づくりの第九演奏会」に向け、伊那地域と木曽地域の合唱団の合同練習が始まった。26日夜、伊那市の県伊那文化会館での初練習は約270人が参加し、本番と同じ大ホールのステージで練習に励んだ。
有志でつくる合唱団は伊那地域240人、木曽地域80人の総勢320人。中学生から70歳代までが集まり、伊那は昨年6月、木曽は7月から月1回の練習を重ねてきた。
木曽地域からは遠い人で車で1時間かけて合同練習に参加。発声、緊張しても高い声が出る体操などをし、合唱指導を受けて歌った。
合唱はドイツ語で、4月末までに暗譜する。今後は合同練習が月2回あり、5月末からオーケストラやソリストと一緒にやる。
演奏会は6月18日午後2時から。「ソリストに合唱団320人、オーケストラ80人。迫力ある演奏になると思う」と事務局。チケットはすでに完売に近いという。 -
上伊那出身音高・音大在学生によるフレッシュコンサート

上伊那出身の音高・音大在学生による第9回フレッシュコンサートは26日、伊那市の県伊那文化会館大ホールであった。学生たちは一人ずつステージに立ち、若いエネルギーあふれる演奏を披露した。若い芽を育てる会主催。伊那毎日新聞社など共催。
音楽を学ぶ学生に発表の場を提供し大きなステージで発表する度胸をつけると同時に、地域の人に勉強の成果を聞いてもらおうと、保護者らでつくる同会が毎年開いている。
今年は音高生1人、音大生15人が出演。持ち時間は一人約10分で、ピアノ、サクソフォーンの独奏、ソプラノやバリトンの独唱を披露。それぞれが練習している曲、自分で作曲した曲など1曲から2曲を観客の前で堂々と演奏した。観客は学生たちの演奏に温かい拍手を送った。 -
長谷村消防団
最後の防火パレード
春の火災予防運動(3月1日縲・日)に先駆け、長谷村消防団(平出万彦団長)は26日、伊那市との合併を控え村消防団として最後の防火パレードで、村内全域を回って火災予防を呼びかけた。
部長以上の14人が、車両4台に分乗し、空気が乾燥し火災が発生しやすくなっているため火の取扱いに注意するよう啓発した。
宮下市蔵村長は、「自分たちの地域は自分たちで守る意識が強く、団長を先頭に積極的に活動してもらっていることが成果につながっている。地区の安全のために活躍し、合併しても伊那市長谷としての活動があるので、また頑張ってほしい」とあいさつした。
平出団長は、「ここ数年大きな災害がなく皆の啓蒙のたまものと感謝している。合併しても消防団として何ら変わらない。地域を守る、災害弱者に目を向ける活動は同じ。力を合わせ、さらなる発展をしていただきたい」と訓示した。 -
第2回いな歌謡祭

第2回いな歌謡祭が26日、伊那市生涯学習センターホールであった。上伊那の歌謡教室で学ぶ生徒らが出演して熱唱、熱演した。
昨年開催し好評だったことから計画。今年は歌に踊りや手品なども盛り込んだ51プログラムを繰り広げた。
出演者は着物やドレスなど華やかなステージ衣装に身を包み、スポットライトを浴びて熱唱。日ごろの練習の成果を存分に発揮して自慢ののどを披露した。会場は満席で、素晴らしい歌声や踊りに大きな拍手を送った。
今井愛子パッショングループ、藤華流・藤華久三社中、東原とし歌謡教室などのダンスや踊りも歌謡祭をより一層盛り上げた。 -
南信地区スポーツ少年団バドミントン冬季大会

南信地区スポーツ少年団バドミントン冬季大会は26日、伊那市の県伊那勤労者福祉センターなどであった。小学生185人が出場して熱戦を繰り広げた。
スポーツ少年団の大会は10月と2月の年2回。今大会は茅野、諏訪、伊那、駒ケ根、高森北、高森南、松川、飯田市上郷の8つのスポーツ少年団が参加した。
ダブルス、シングルスでそれぞれ学年別で競技。2階観客席からの熱い視線を受けながら、速いスマッシュを決めたり、さらに速いスマッシュで打ち返したりと白熱した。
結果は次の通り。
【女子ダブルス】▼3年以下=(1)小林澪奈(駒ケ根)吉川奈緒子(飯田市上郷)(2)佐々木梨衣・山崎琉奈(駒ケ根)(3)高田実花・高田侑花(飯田市上郷)富田綾音・森谷麻衣(高森南)▼4年=(1)花岡莉奈・伊藤朱音(茅野)(2)片桐綾美・杉山裕香(松川)(3)新井菜々美・小原梨紗(松川)鷲尾麻里菜・坪木祐奈(伊那)▼5年=(1)高田梨紗・後町萌絵(茅野)(2)依田史奈・玉木絵理(駒ケ根)(3)赤羽根舞子・竹村春香(駒ケ根)松田咲実・市瀬優菜(飯田市上郷)▼6年=(1)林加菜子・丸山さなえ(松川)(2)吉沢奈津子・嶽沢直美(駒ケ根)(3)宮沢采那・小原早貴(松川町)塩沢まどか・土橋里紗(茅野)
【男子ダブルス】▼4年以下=(1)柳沢守・高橋航(茅野)(2)山岸哲・松原大地(駒ケ根)(3)栗原宏樹・山岸賢治(伊那)新村樹・小松慎悟(諏訪)▼5・6年=(1)高田京佑・根岸将希(茅野)(2)北林宏太・北林翔太(松川)(3)小沢亮・原謙二郎(飯田市上郷)北沢慶尚・小沢貴弘(松川)
【女子シングルス】▼3年以下=(1)田畑まゆ子(伊那)(2)松下佳世(松川)(3)高田実花(飯田市上郷)伊藤朱音(茅野)▼4年=(1)後町萌絵(茅野)(2)新井菜々美(松川)(3)岩波四季恵(諏訪)小原梨紗(松川)▼5年=(1)高田梨紗(茅野)(2)赤羽根舞子(駒ケ根)(3)武田さやか(伊那)北原里美(高森南)▼6年=(1)吉沢奈津子(駒ケ根)(2)林加菜子(松川)(3)丸山さなえ(松川)藤森遙香(茅野)
【男子シングルス】▼4年以下=(1)柳沢守(茅野)(2)山岸哲(駒ケ根)(3)網野豊(伊那)原謙二郎(飯田市上郷)▼5・6年=(1)高田京佑(茅野)(2)北林宏太(松川)(3)北林翔太(松川)根岸将希(茅野) -
ベテラン卓球選手権南箕輪大会

第13回上伊那ベテラン卓球選手権南箕輪大会は26日、南箕輪村民体育館で開き、30歳以上の50人が出場した。
種目はシングルス、ダブルス。それぞれ30歳以上49歳以下の1部、50歳以上の2部に分かれて競技した。ダブルスは男女混合で、当日朝の抽選で決まったペアで試合に臨んだ。競技歴の長いベテランぞろいで大会は盛り上がりを見せた。
結果は次の通り。
【シングルス】▼1部=(1)西村礼文(駒ケ根)(2)有賀益美(美篶レディース)(3)小林清(中央病院)佐藤直己(南箕輪)▼2部=(1)伊沢佐恵子(高遠)(2)千村淳子(駒ケ根)(3)埋橋澄子(伊那西)篠田洋子(南箕輪)
【ダブルス】▼1部=(1)小林清(中央病院)伊沢佐恵子(高遠町)(2)西村礼文・村上三和子(駒ケ根)(3)佐藤直己・古川美智子(南箕輪)、大芝信(駒ケ根)・埋橋澄子(伊那西)▼2部=(1)本田雅則(駒ケ根)原伊穂子(南箕輪)(2)杉浦博男・西尾和子(駒ケ根)(3)小坂秀一・三石房子(南箕輪)、有賀恒夫(南箕輪)・阿部恵子(伊那ママ) -
第4回箕輪町なわとび大会

箕輪町教育委員会主催の第4回なわとび大会は25日、町民体育館であった。幼児から大人まで248人が、跳ぶ回数や跳び続ける時間などを競い合った。
種目は団体、個人、親子ペアの3競技。団体は長なわ1分間とび、長なわ5人並びとび、10人並びとびで、小学校単位で編成したチームが参加。箕輪西小学校が最多出場で、並び跳びでは皆が心を一つにして「1、2、3…」と大きな声で数えながらジャンプした。
個人種目は前回しの時間とび、二重とび、あやとび。時間とびは保育園児も参加し、軽快に前回しをする姿を保護者がビデオやカメラで撮影していた。 -
南箕輪村公民館物作り体験講座「折り紙に挑戦」

南箕輪村公民館は25日、物作り体験講座「折り紙に挑戦」を開いた。20人が折り紙でひな人形づくりを楽しんだ。
ひな人形は内裏、三人官女、五人囃子を作る。お内裏様は青、おひな様はピンクの紙を使い、手本を見ながら丁寧に折った。小さい子どもは三角に折るなど自分ができるところを担当し、お父さんやお母さんが作り上げる様子を楽しそうに見ていた。
三人官女、五人囃子は一人ずつ作って折り方を覚え、残りは参加者がそれぞれ家で完成させる。
北殿区の80歳の女性は、「女だもの、ひな人形を飾りたいよね」と話し、きれいに内裏びなを折っていた。 -
上農定時制、高校改革プラン実施計画策定を前に要請書を提出

定時制の機能を多部制・単位制の中で十分に確保してほしい竏窒ニ、上伊那農業高校同窓会定時制部会や定時制PTAなどが27日、県教育委員会に要請書を提出した=写真。
関係者は、第3通学区高校改革プラン推進委員会(池上昭雄委員長)の示した最終報告案は、現状の定時制の機能を十分確保できないとしている。要請書は(1)4学年を基本とした学年制にすること(2)20人を超えない少人数学級の実現(3)夜間部だけで独立した学習の場を確保すること竏窒・輪工業に設置する多部制・単位制に求め、定時制の役割を確保することが満たせないのであれば上農定時制の存続を訴える。
県教委は「基本的には4学年制を前提として3年でも卒業できるというもの」「夜間部だけで独立したしばりを持たせるのでなく、選択の余地をもたせて可能性の幅を広げたい」とこたえ、定時制の機能は損なわれないとした。
しかし、保護者や教員は「現状定時制を居場所とする生徒は必ずしも選択肢の多い環境を望んでいるわけではない。横のつながりを求めている」として、要請への十分な配慮を求めた。 -
南信病院公開講座

南箕輪村の蜻蛉(あきつ)会南信病院(近藤廉治院長)で25日、京都大学名誉教授でサル研究の第一人者・河合雅雄さんを招いた公開講座があった=写真。河合さんは、廃れ行く里山と「文化的関係」を築く中で、森林を保全していく取り組みを提唱した。
日本人にとって里山は「生活の糧」を育ててくれる重要な存在だった。しかし、化石燃料や安価な輸入林の普及によってその役割は薄れ、現在はほとんどが手付かずのまま放置されている。森林の荒廃を招くだけでなく、鳥獣被害の増加などほかの弊害にもつながっている。
一方、日本と同様に森林面積率の高い欧州を見ると生活の一部として森林を楽しみ、その中で保全が進んでいる。河合さんはこうした「森遊び」の感覚がこれまでの日本にはなかったことに目を向けた。今後、日本人も、欧州人と森林との関係性にヒントを得ながら、遊び、教育、スポーツなど、さまざまな側面から里山との関わり方を模索し「文化的資源」として里山を生かしていく方法を模索していくべきとした。 -
伊那商議所女性会が中華料理の講習会

伊那商工会議所女性会(久保田育子会長、41人)は24日、伊那北地域活性化センター(きたっせ)で中華料理の講習会を開いた。会員15人が水ギョーザなど3品に挑戦し、試食した。
市内で「地産地消」として地元産シメジを使ったギョーザを売り出していることから、家庭料理に生かしてもらおうと企画。講師に、飲食店有志でつくる「伊那手づくり餃子(ギョーザ)愛好会」のメンバー3人を迎え、ギョーザに加えて酢豚、カニ玉も作った。
ギョーザの具はひき肉、ハクサイ、タマネギ、ショウガなど。生地を伸ばすときは「中心に指を置き、生地を回しながら伸ばす」などポイントを交えて説明した。
具を入れすぎて皮からはみ出し、やり直す場面もあり、和気あいあいと楽しんだ。
参加者は「厚さを均等にしたり、丸く形を整えるのが難しい。皮は無理だが、家で作ってみたい」と話していた。 -
教育基金講演会
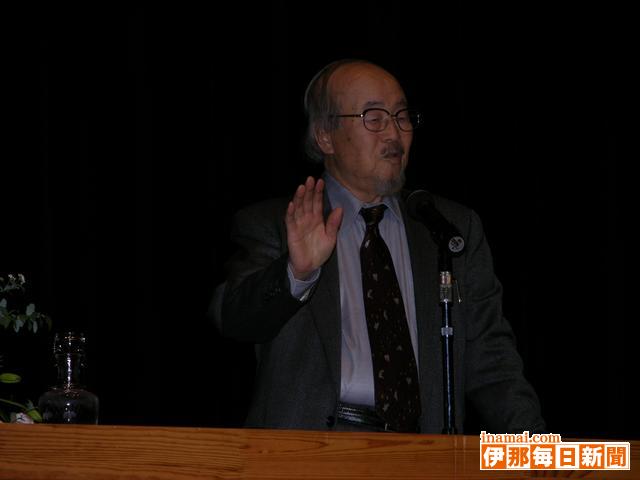
駒ケ根市教育委員会は24日、市内の小学6年生と中学2年生を対象にした教育基金講演会を同市文化会館で開いた。児童、生徒のほか学校関係者や一般など約700人が集まり、京都大名誉教授で、兵庫県立「人と自然の博物館」館長の河合雅雄さんによる「自然が育む豊かな心」と題した講演を聞いた。
小さいころは体が弱く、小学校にも半分ほどしか行けなかったことから「勉強は全然できず、成績が悪かった」という河合さんは「山や川で遊んだり、たくさんの生き物と触れ合ったことで生命や欲望について学んだ。皆さんも動物を飼ったり自然の中で遊んだりして豊かな心を育てていってほしい」と語り掛けた=写真。
河合さんは霊長類研究の第一人者として世界的に知られる。『子どもと自然』『少年動物誌』など著書多数。 -
キッズわくわく宿冬バージョン

親子で自然に親しむ共同生活を体験してもらおうと駒ケ根市教育委員会は25日、市内の保育・幼稚園の年中、年長園児と保護者らを対象にした1泊2日の宿泊体験「キッズわくわく宿(じゅく)冬バージョン」を同市東伊那の農林業体験宿泊施設「駒ケ根ふるさとの家」で開いた。22組・44人の親子が参加し、たこ作りや手打ちそばつくり、もちつきなどを通して家族や友達同士のきずなを深めた。
初日、参加者らはたこづくりに挑戦。中村新平さん(71)=伊那市西町=の指導で揚がりやすく、壊れにくいたこを作った。父親らが竹ひごで骨を組んだり紙や糸を切ったりし、子ども達はたこの表に動物や花など好きな絵をマーカーで思い思いに描いて約1時間で完成。参加者らは早速たこ揚げを楽しもうと外に出たが、幸か不幸か穏やかなポカポカ陽気でほとんど無風状態。それでも子ども達は何とかたこを揚げようと元気に走り回った=写真。しばらくするうちに少し風が出始め、子どもたちの「揚がった、揚がった」と叫ぶ興奮した歓声があちこちで響いた。中には10メートルほどに揚がる出来の良いたこもあった。
26日にはもちつきやゲームなどを楽しむことにしている。 -
県看護大入試

駒ケ根市の県看護大(深山智代学長)は25日、06年度一般入学試験(前期)を同大で行った。会場の指定の席に着いた受験生らはそれぞれ緊張した表情で試験開始を待ち、小論文と面接に取り組んだ。受験したのは志願者78人のうち76人で、定員42人に対し倍率は1・8倍。
3月13日に行われる後期試験は定員8人に対して出願者は60人(男子5・女子55)で倍率は7・5倍。05年度の前期2・7倍、後期12・1倍に比べて「広き門」となっている。
合格発表は前期が3月1日、後期は同20日の午前10時から同大に受験番号が掲示されるほか、インターネットでの閲覧もできる。 -
写真展「小町屋女性五人展」

駒ケ根市赤穂小町屋在住の5人の写真愛好家女性らによる写真作品展「小町屋女性五人展パートII」が市役所向かいのアルプス中央信用金庫南支店ロビーで3月20日まで開かれている=写真。藤澤房子さん、多胡善江さん、伊藤ひとえさん、小島千鶴枝さん、山本純子さんが撮影した花や風景などの写真10点が展示され、訪れる人の目を楽しませている。
5人は市内の写真クラブ「彩(いろどり)」と「フォトF」の会員で、互いに近くに住んでいることから親交が深まり「作品制作の励みになれば」と展示会を企画した。
入場無料。 -
むらづくり講演会
茅野市の事例に学ぶ
南箕輪村と南箕輪村むらづくり委員会は23日夜、住民と行政のパートナーシップを考える「むらづくり講演会」を村民センターホールで開いた。茅野市の矢崎和広市長が、「地域コミュニティの充実とパートナーシップのまちづくり」の取り組みを語った。
茅野市のパートナーシップを「知恵は住民から、予算は市長がつけ、方針が決まったら職員と住民が一緒に汗をかく」と説明。「これからのまちづくりは住民主導」との考えで、特に福祉、環境、教育の3分野で、一緒に知恵を出し汗を流すパートナー、実践集団を募集し、NPO法人が活躍しているプロジェクトを紹介した。
民間出身の矢崎市長は就任当初、行政の費用対効果という考え方の欠落、スピード感覚の無さにカルチャーショックを受け、前例主義、横並び主義、縦割り主義をやめるよう指示したことを話し、市民と行政の協働では行政は黒子となり、表彰など市民が世間から注目される働き掛けの必要性も述べた。
課題に自助、共助の原風景があった昭和30年代に住民の考え方が戻ることを挙げ、「自助、共助はちょっとしたことを住民やNPOができるかどうか。どれだけ互いに領域を広げ補完しあえるかにかかっている」とした。 -
西部花街道をつくる会
西県道沿いで伐採作業
箕輪町の県道与地辰野線(通称西県道)を花街道にしようと活動する「西部花街道をつくる会」(50人、唐沢弘三会長)は25日、西県道沿いで樹木を伐採するなど法面の整備に精を出した。
会は、ボランティアで地域の活性化のために-と西県道沿いの住民有志で昨年発足。5月に花桃の苗木350本を植え、草刈りなど管理をしてきた。
この日は40人が参加。新たに花桃を植えるため、下古田、一の宮、富田の3カ所の法面で植樹の妨げになる木や道路に出た枝などを伐採。箕輪西小学校に通う子どもたちの通学路でもあることから、見通しがよくなるように雑木なども切った。
会員は、まきストーブなどで使うために持ちかえる木、燃やして処分する木など手際よく片付け、法面は見違えるようにきれいになった。
今後は、4月に花桃650本を植樹する予定で、昨年分と合わせて千本にする。 -
清水洋県議の後援会「志清会」南箕輪地区新年会

清水洋県議の後援会「志清会」南箕輪地区(原一雄会長)の新年会が25日、南箕輪村の北殿公民館であった。
清水県議は、「権兵衛トンネル開通で伊那谷で注目されているのが南箕輪村。政治的課題がまだある。細かい所をどう詰めるかが地元の私の役目。うちの息子、兄ちゃんを使おうという気持ちで声をかけて頂き、仕事をさせて頂きたい」と支援を求めた。
県会関連では、廃棄物条例の問題は「一般廃棄物は村長がトップで解決すること。県が入ってくるのは問題」との考えを示した。
知事については「ここまで改革を進めたことは事実で、評価しないといけない」としながら、「議会と知事の間が実はうまくいっていない。これは大きな意味で長野県の損失。もう少し信頼関係を持ってほしい」とした。
今年8月の知事選挙は「県議としてどう戦うかが大きな課題」とし、来年4月の県議会議員選挙については「新年会をしているので選挙をやらないということはないと思いますけど…」と話すに留まった。
新年会は約200人が出席。宮下一郎衆院議員、向山公人県議、唐木一直南箕輪村長、池田輝夫村議会議長らが祝辞を述べた。 -
第3回キンボール大会

南箕輪わくわくクラブ第3回キンボール大会が25日、南箕輪村民体育館であった。今年は上伊那スポーツフェスティバルのニコニコブースとして開き、村内外から29チームが出場して競い合った。
中学生以上の大人は7チーム、小学生は22チーム。クラブ活動の仲間で編成した中学生チームや、伊那市の美篶小学校からの参加もあった。
キンボールは1チーム4人で編成し、3チームが約1キロの大きなボールを使って「ヒット」「レシーブ」を繰り返して得点を競う。
出場チームはそれぞれ黒、グレー、ピンクのゼッケンをつけ、「ピンク!」など色を指定されたチームはボールが床に落ちないように必死に追ってレシーブ。ボールを打つときにフェイントをかけたり、相手チームの立っていない場所にすかさず打つなど駆け引きし合い、競技に熱中していた。 -
アド・コマーシャル 伊那市に屋外用テント寄贈

アド・コマーシャルは24日、伊那市教育員会へ屋外用テント3張り(65万円相当)を寄贈した。赤羽通代表取締役が市役所を訪れ、小坂樫男市長に目録を手渡した。
「春の高校伊那駅伝06」(3月19日、同教育委員会など主催)の企画協力をするアド・コマーシャルは、同駅伝や他の屋外イベントで役立ててほしい竏窒ニテントを寄贈した。
テントの面積は縦3・6メートル、横5・4メートル(2×3間)で、高さは3メートル。「いままでのテントは風が吹きぬけていて寒そうだったから」(赤羽代表取締役)と風を防げる4面張りで、手軽に折り畳められるのが特長だ。
伊那市教育委員会ではテントを市陸上競技場へ常備する考え。初おろしは春の高校伊那駅伝になる予定だ。
27日に実物が同教育委員会へ贈られる。 -
健康体験会「京都西川健康紀行」 ベル伊那27日まで

伊那市日影のベルシャイン伊那店は寝具メーカー「京都西川」(本社・京都市)の協賛を得て25日から、同店の2階文化ホールで健康体験会「京都西川健康紀行」を開いている=写真。27日まで。
昨年9月末に続き、好評につき2度目の開催。温熱・電位の交互療法ができる家庭用電気治療器の敷布団のほか、掛け布団やまくらなど、血行促進、不眠症解消などに効能効果がある商品を紹介している。
羽毛掛け布団には「N型ゲルマニウム」と備長炭を使用。N型ゲルマニウムは摂氏(せっし)32℃以上になると原子核からマイナス自由電子が飛び出し、血液浄化や自律神経を調節する。同様の効果があるまくらは、自分が使いやすい高さを体感しながら選べる。
極寒に生息する「アイダーダック(毛綿鴨)」の高級羽毛布団や、ムートンラグもある。
関係者は「眠っている時間を健康のために有効活用できる商品を集めました。ぜひ来場していただき体感した上で、一緒に快眠について話し合いましょう」と呼びかけている。
午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -
現金返還率60・3%、物品返還率37・2%
伊那警察署は05(平成17)年に管内で届けられた遺失・拾得物の取り扱い状況をまとめた。遺失物の件数は1867件(前年比32件減)、拾得物は3114件(同57件減)、遺失者返還は731件(同43件増)、拾得者交付は1830件(同6件減)、県帰属は824件(同280件増)だった。
現金の遺失額は2169万6674円(同614万2863円減)、拾得額は704万664円(同128万9580円増)、遺失者返還額は424万5930円(同55万128円増)。遺失届けの最高金額は93万6059円(前年は230万円)、拾得届けは32万3394円(同22万円)だった。
物品の遺失数は1954点(前年比63点減)、拾得数は2781点(同440点減)、遺失者返還数は1034点(同278点増)。特異な拾得物としては、工事現場に置き忘れられた木箱(土力計)があり、記名などから遺失者が判明し返還した。
拾得物3114件のうち遺失者に返還されたのは731件で、現金の返還率は60・3%、物品は37・2%と現金のほうが返還率が高かった。理由は財布などのなかに持ち主の手がかりとなるカードなどが入っていて、警察から連絡が取れたため。
遺失物の内訳は財布類が733点、免許証類が224点、機械器具が179点、かばん・袋ものが161点の順に多い。機械器具については179点のうち173点が携帯電話で、前年と比べて携帯電話は37点も増えている。
月別の遺失・拾得物の届け出状況は、夏休みの8月、何かと慌ただしい1月、12月にともに多い。
伊那署では▼大切な物には住所、氏名、電話番号など連絡先が分かるようにする▼諦めないで警察に届出をする▼手荷物を多く持って歩かない▼いつも自分の物がどこにあるかを確認する竏窒ネどと注意を呼びかけている。 -
伊那市防犯協会の定期総会

伊那市防犯協会(会長・小坂樫男市長)は22日、市役所で定期総会を開いた=写真。約30人の役員が出席。新市誕生による会則改正や06年度の事業計画、歳入歳出決算などの5議案すべてを可決した。
同協会会則の役員については、各地区の防犯協会長から選任する理事は、7人から高遠地区を加えた8人に増員、評議委員には高遠消防署長を加えるなど改正。3月31日から施行する。
06年度の事業計画は▼各地区防犯協会による防犯活動▼伊那防犯協会連合会との連携による防犯活動▼暴力団追放活動▼女性部員の活動竏窒フ4項目の推進を掲げた。
小坂会長「子どもを狙った犯罪や高齢者を狙った振り込め詐欺などあるが、犯罪は未然に防ぐことが必要。その意味でも防協の果す役割は大きい」とあいさつした。 -
物語 抑揚豊かに演じて

伊那市の朗読愛好者でつくる伊那公民館サークル・伊那朗読の会(小林豊子会長)は25日、県文化会館小ホールで、年に一度の発表会を開いた。上伊那を中心に約100人が集まり、会員が語りかけるリズムや口調を目を閉じて聞き入った。
詩、エッセイ、小説などを会員16人が一人ひとり朗読したほか、全員参加の「群読」などの18プログラムを披露。会員の一年間の練習成果の発表に会場は大きな拍手で答えた。
発表会は2部構成で、前半は新入会員を中心に朗読を披露した。今年度の入会者は9人で、最高齢は80歳代の男性。それぞれのレベルはまちまちだが、初舞台に上がった会員たちは心を込め、聞き手に朗読の世界の魅力を伝えていた。
伊那朗読の会は、話し方の基礎を学ぼう竏窒ニ、1981(昭和56)年に創立。伊那公民館で月一回の練習や、NHKが主催する朗読セミナーへの参加などで朗読の腕を磨いている。 -
家族の大切さを孝行猿に学ぶ

長谷村公民館で25日、親孝行の讃歌記念事業「孝行猿の心に学ぶ」があり、地域住民ら130人余が集まって両親とのきずなや家族の大切さを考えた。
村合併40周年を記念し99年から5年間、村に伝わる「孝行猿」の民話にちなんで、全国から両親にまつわる思い出の手紙や詩を募り、約4千通が集まる反響を呼んだ讃歌事業を振り返り、将来につなげていく機会とした。
孝行猿は猟師に撃たれた母猿を慕い、小猿が夜通し傷口をあたためたとされる物語。「孝行猿の日」を設け、命の大切さを学んでいる長谷小学校は3年生が物語を影絵で上演。「戦争をなくし、自分の悪いところに気付く世の中になるといい。これからどのように世の中を変えればいいか考えていきい」とした。
長谷中学校は全校生徒が両親への思いをつづった短文を各学年の代表が発表。「いつも心配してくれるその一言が暖かい。そしてやる気をくれている」「お父さん体をもっと大切に。私のお父さんはあなた一人なんだから」など、感謝の気持ちを伝えた。
ジャーナリストの内山二郎さんの進行で、参加者全員と「親子のきずな縲恊eから子へ 子から親へ縲怐vをテーマにフリートークもした。
宮下市蔵村長はあいさつで「親孝行という言葉や絆が薄れてきた世相で、親の大切さや子どもに寄せる思いを考え、幸せな家庭や地域づくりの弾みになれば」と述べた。 -
身近な川の水質親子でで調べたよ

伊那市の信州INAセミナーハウスで25日、諏訪湖・天竜川水系などの健康診断「親子で水質調査」の自由研究レポートの報告会があった=写真。リサイクルシステム研究会(会長=向山孝一KOA社長)などの主催。
05年で7回目となった調査には、環境問題に関心の高い親が働く地元企業21社から、68親子が参加。簡易調査器具「パックテスト」を使用して、COD(化学的酸素要求量)などを調べた。
箕輪町の帯無川を調べ、3回目の参加となる長野日本電気に勤務する白鳥明子さん親子。南箕輪村の大泉川のほか、自宅の水道水や風呂の残り水なども調査したNTN長野製作所に勤める落合謙司さん親子など、6組が報告した。
子どもたちは「くさい」「ごみが落ちている」などの五感で感じ取った感想を交えて、生活排水が川に及ぼした結果などを報告。調査に初参加の家族は「今度は違う川を調べたい」と、常連家族は「このまま調査を続けたい」と最後に述べ、環境保護への関心の高さをみせていた。
日本珪藻学会会員の飯嶋敏雄さんが「川の中の生き物たち」と題して講演もした。水質調査は薬品のほか、水中に住んでいる水生昆虫などの種類や量でも判断できることを紹介し、カゲロウやカワゲラなどが天竜川のどこに生息しているかなども教えた。
リサイクルシステム研究所は親子の水質調査のほか、諏訪湖から遠州灘(静岡県)までの一斉ごみ拾い「天竜川環境ピクニック」、24時間定時に各個所で水質調査を実施する「天竜川水系健康診断」などを毎年している。 -
高遠美術館ギャラリー展

伊那市在住の書道家・泉石心さん(47)による個展「書画・篆刻・硯の世界」が、高遠町の信州高遠美術館で開かれている。春を思わせるサクラやモモなどをテーマとした書画を中心に、硯(すずり)や篆(てん)刻など約80点が、訪れた人の目を楽しませている。
伊那市内の高校に教師として勤める傍ら、製作活動を続けている泉さんは、東京書道会の会員などとしても活躍している。これまでも個展やグループ展を開催しているが、高遠美術館での個展は初めて。
今回は、書になじみのない人にも親しみやすいように竏窒ニ、絵を添えた作品も多く展示。正岡子規、バイロンなどが詠んだ「春の歌」を書いた作品は、春の和やかさをイメージさせる優しい書体で仕上げられており、見る人の心を和ませる。
落款は、篆刻した素材も一緒に展示しており、泉さんは「陰影だけでなく材料も楽しく見てもらえれば」と話していた。
3月21日まで。 -
どうぞのいすで障害者の自立を考える座談会
4月から施行となる障害者自立支援法に対し、地元は何が変わり、どう対応していけばいいかを話し合おう竏窒ニ21日、伊那市荒井区東町の福祉事業所「どうぞのいす」で障害者の自立をテーマとした座談会があった。障害者の自立支援をサポートしている生活支援コーディネーターや保護者、同事業所のスタッフなどが参加し、将来を見据えて現状の問題点などを話し合った。
新しい制度では、障害別で提供していた従来のサービス体系から目的別のサービス提供となり、市町村が責任を持って一元的なサービスを提供していく。各市町村は10月までにそれぞれどのようなサービス体系で運営していくかなどの方針を打ち出す必要があり、共同作業所など既存の各施設の運営形態は、方針次第で厳しい局面を迎える可能性もある。
その一方で、既存の施設が本当に十分機能しているかを疑問視する声もあり「もう一度既存の施設が十分機能しているか調べ、それらを十分活用していくことが必要」とする意見があった。 -
1円玉募金活動で14万3800円余を寄付
中川村老人クラブ連合会(金子功会長)は23日、村社会福祉協議会の前原茂之会長に1円玉募金活動で集まった浄財14万3800円余を「福祉向上に役立てて」と寄付した。
社協には金子会長ら役員4人が訪れ、「14支部800人の全会員が協力していただいた」と手渡した。
前原会長は恒例の募金に感謝し「みなさんの温かい気持ちを生かし、福祉活動に使いたい」と有効活用を誓った。 -
中学生水泳選手ニュージーランド遠征へ

ISC(アイスク)駒ケ根スイミングクラブ所属の赤穂中学校3年生小松原彩香さん(15)=駒ケ根市赤穂上赤須=は日本水泳連盟が中学生選手の強化を目的に行う2005ジュニアブロック・ニュージーランド遠征の選手に県内でただ1人選ばれた。遠征は3月2日縲・2日にかけて首都ウェリントンなどで行われ、参加選手らは合宿でニュージーランド選手らと練習を共ににするほか、ニュージーランドAG選手権大会にも出場する。「いつかは世界の舞台に立ちたい」と話す小松原さん。大きな夢に向かって第一歩を踏み出す。
小松原さんは2歳上の姉の影響で3歳から水泳を始めた。熱心に練習に打ち込み、めきめきと頭角を現して小学5年生で全国大会に出場。中学生になってからも恵まれた体格を生かしたダイナミックな泳ぎで国体にも出場するなど、逸材として将来を期待されている。進学が既に決まっている赤穂高校でも水泳部に入り、スイミングクラブと並行して練習したいという。「外国は今回が初めてなので言葉など少し不安もあるが楽しみ。大会では目標タイムを達成できるよう頑張りたい」と闘志を燃やしている。
1512/(月)
