-
上穂開発協議会総会

駒ケ根市の北割一、同二、中割、南割、上穂町福岡の竜西6区の正副区長市議会議員、農業委員らでつくる上穂開発協議会は29日、06年度総会を市役所で開いた=写真。委員48人のうち約40人が出席し、各区の正副区長らで組織する理事の互選によって選出された正副会長らの役員人事を了承したほか、06年度事業計画・予算案を承認した。06年度の事業として治山治水の促進や環境保全対策、交通安全対策、道路の改良と災害防止に関する活動などを行っていく。
役員は次の皆さん。
▽会長=福島紀六(北割一区長)▽副会長=小林治男(北割二区長)▽会計=中村雅典(中割区長)▽監事=吉澤智束(南割区農業委員)竹内稔(福岡区農業委員) -
市道しゅん工

歩行者の安全を図るための歩道新設とそれに伴う車道の改良を行っていた駒ケ根市赤穂経塚の市道III竏・0号線(通称農免道路)の工事が完成し29日、しゅん工祝賀会が駒ケ根駅前ビル・アルパで開かれた。地権者と工事関係者ら約30人が出席し、工事の無事完成と共用開始を祝った。中原正純市長は「しゅん工により、地域の一層の発展につながるものと期待する」と祝辞を述べた。
改良されたのは宮の前交差点から北630メートルまでの区間。道路西側に幅2・5メートルの歩道を新設し、車道も整備した=写真。交通量の多い割に歩道がなく危険竏窒ニの住民の要望を受けて調査を始め、02年に工事を開始した。総事業費は3億4800万円。 -
きょう 新伊那市が発足

31日、伊那市・高遠町・長谷村が合併して新伊那市が発足する。午前8時に伊那市開市式(市役所開庁式)、10時45分に長谷総合支所開所式、11時半に高遠町総合支所開所式をそれぞれ開く。
新市長が決まるまでの間、職務執行者を務める伊東義人氏(前高遠町長)が06年度の一般会計予算や条例制定などを専決処分するほか、部長級以上などに辞令交付する。
新市には、市役所(本庁舎)、高遠町総合支所、長谷総合支所、富県や美篶など6支所を置く。窓口の開設は午前8時半縲恁゚後5時15分(高遠町のみ月曜日は7時まで証明書交付する)。届け出・登録申請の受け付けは外国人登録申請などは市役所のみとなる。
新市は面積668平方キロメートルで、県内3番目の広さ。世帯数は2万6300戸で、人口7万4千人。
【経過】
03年12月、伊那市・高遠町・辰野町・箕輪町・南箕輪村・長谷村の任意合併協議会が解消となり、04年2月、高遠町・長谷村から伊那市に合併研究の申し入れがあった。南箕輪村にも申し入れ、4月に4市町村による合併研究会が発足した。7月の住民投票の結果、南箕輪村は反対が6割を占め、研究会が解散。9月に伊那市・高遠町・長谷村合併協議会を設置し「新設合併」など基本的な協議事項9項目に加え、住民生活に影響のある各種事業の取り扱い、新市建設計画などの協議に当たった。
◆ ◆ ◆
新伊那市発足を前に、30日、伊那市で閉市式、高遠町・長谷村で閉庁式がそれぞれあった。
●伊那市
伊那市では、歴代市長や議長、各種行政委員、市職員の部課長以上ら約120人が出席。
小坂市長は、54(昭和29)年の6町村合併からの歴史を振り返り「困難な問題を克服し、伊那市を築き、上伊那、南信の行政、経済、文化の中心的な役割を担ってきた」と感謝し、31日の新市発足に当たって「合併してよかったといわれる伊那市に育て上げることが全市民の義務であろうと思う」と述べた。
そのあと「伊那市の歌」を3番まで歌い、小学生代表4人が伊那消防署員の指揮に従って市旗を降納。
前市長原久夫さんの音頭で万歳三唱し、新市の発展を願った。
●高遠町
高遠町は職員や町議会議員ら約150人が見守るなか、伊東義人町長らが町旗を降納し、庁舎の館名板「高遠町役場」を取り外した。
伊東町長は町の歴史を振り返り「町民がより暮らしやすく、高遠を誇りと思える施策に取り組んできた。庁舎はなくなるわけではなく、高遠町総合支所として新たにスタートするが、さらなる発展に向けた次へのステップととらえ、地域住民のための庁舎として気軽に立ち寄れる場所であってほしい」と述べた。
また新市発足にあたり「合併は最終目標ではなく、それぞれの地域の特性を生かし、互いに尊重し合って、より暮らしやすいまちづくりを一日も早く築くことが大切」とし、職員に向けて「良い合併となるよう地域を愛する思いをもった活躍を願う。市民のための行政を目指して、常に公正の立場で地方自治進展に尽くしてもらいたい」と期待した。
●長谷村
長谷村では、職員など約70人が見守る中、宮下市蔵村長らが村旗と役場看板を降納した。
式辞で宮下村長は「合併は長谷村の将来のため、どのように進んでいくか考えたときの苦汁の選択で決めた。合併は決してゴールでない。これを契機に新しい街づくりに向けて、住民の皆さまと出発してほしい」と式辞を述べた。 -
南箕輪育苗センターで「温湯」方式開始

南箕輪村の南箕輪育苗センター(原英雄代表)で30日から、温湯種子消毒機による籾(もみ)消毒がはじまった。これまでの薬品殺菌に比べ環境にやさしい消毒方法に切り替えた。
JA上伊那の05年度環境負荷軽減技術導入促進事業で、同センターのほか箕輪町と伊那市の西春近に温湯種子消毒機を導入。今までの化学農薬消毒で問題となっていた廃液処理が解消され、環境汚染を心配することがなくなった。
消毒は籾を60度の湯に10分間、冷水に5分間浸すだけ。以前までの方法は薬品の水に籾を24時間浸していたので、作業時間の短縮にもつながった。
温湯消毒に切り替わり現在までに、苗床を持っていて籾の消毒だけを依頼する人は20縲・0人。原代表は苗床を所有している組合員に関しても「来年からはすべての籾の温湯消毒していきたい」と話している。
南箕輪育苗センターでは今シーズン、約7・2トンの籾を消毒予定。4月14日から育苗が開始される。 -
「霞提」後世に伝えよう 伊那市など美篶下川手に看板設置

伊那市は国土交通省・天竜川上流河川事務所(天上)などの協力を得て、美篶下川手の三峰川サイクリング・ジョギングロード沿いに、同河川の治水対策として古くから造られていた堤防「霞提(かすみてい)」の役割などを解説した看板を設置した。
昨年9月の議会一般質問で、議員から「三峰川治水の歴史として保存していく考えは」との質問。市では霞提が持つ機能を後世に伝えるための看板設置を考えた。霞提の維持管理している天上が看板を製作し、23日に設置した。
看板は三峰川の右岸に8、左岸に3の計11箇所に霞提があることや、堤防の一部を切って田畑などに水をあふれさせる役割があることを図などで説明し、36災害(1961年)時の霞堤の効果を写した航空写真なども掲示している。大きさは縦245センチ(うち看板部分140センチ)、横214センチ。総事業費は約200万円。
掲示内容は市、天上、霞提に詳しい地元住民などを交えて、昨年12月から検討。専門用語や難しい漢字などを使わないなど、表記は子どもたちでも分かるように工夫している。 -
高校改革プラン実施計画決定
長野県教育委員会臨時会が30日、県庁であり、県内4通学区の高校再編整備案を盛り込んだ「長野県高等学校改革プラン実施計画」を決定した。これにより89校の公立高校が79校に整備される。総合学科については各地区に1校ずつ設置することを予定していたが、推進委員会で設置の結論が得られなかった第3通学区は、当面の間設置を見合わせることになった。07年度生徒募集から実施することを基本としながらも、一般への周知が不十分である多部制・単位制高校は、08年度募集から実施していく。
第3通学区は(1)岡谷東、岡谷南を統合し、進学に特化した全日制単位制高校とすること(2)箕輪工業に上伊那農業定時制を統合し、3年間で卒業できる(三修制)の多部制・単位制を設置すること(3)飯田工業、飯田長姫の全日制・定時制を統合すること竏窒ェ掲示された。
定時制を希望する生徒に配慮して、三修制と明記しないよう求めてきた上伊那農業定時制関係者や、地域の合意形成のため、統合までの時間的な配慮を求めていた岡谷南、岡谷東関係者の声は届かなかった。
岡谷南、岡谷東への設置が示された「進学対応型単位制高校」は、県下でも初となる試み。教員配置の加配や、専門性を高めることができる単位制の中で、進学対応を目指す高校で、県教委は1つのモデルケースとしていきたいという思いもある。
4月以降、実施計画概要版の作成、該当校への説明、地域説明会などを進め、学校や地域の声を尊重しながら計画を進める。
校名の変更は、新入生が入学して3年間は仮の名前とし、入学者が3年生になった時、生徒たち自らで決定することなどを想定している。 -
花園「ポレポレの丘」に地主制度
高遠町東高遠の花園「ポレポレの丘」を管理・運営する高遠花摘み倶楽部(赤羽久人理事長)は28日夜、今年から導入する地主制度(仮称)の登録者を集めた会合を町総合福祉センターで開き、制度の内容や今後の作業について確認した=写真。
花園は遊休荒廃農地の復活や通年観光を目指して昨年5月に開園したが、「花が草で覆われるなど管理がいき届かず入園料は取れない」と2か月後に無料開放。対策の一つとして、花園2・5ヘクタールのうち約4割程度を区画分けし、各区画を賛同者に割り当て、管理してもらう地主制度を設けた。同日までに52人が登録している。
地主は花の種や苗を負担し、「自分の庭のように」(赤羽理事長)花壇を作って管理する。
また、地主制度以外では、月ごとに季節の花を咲かせるメーン花壇を作り、毎月イベントを組んでPRしていく。現在のところ、5月にアイリスまつり、6月にアヤメまつりを予定している。
赤羽理事長は「誇りと自信をもって、多くの人に薦められる花園にしたい」と話していた。
地主は今後も募集していく。問い合わせは、高遠花摘み倶楽部(TEL94・3916)へ。 -
ミニデイ利用者交流会

宮田村各区のミニデイサービスの利用者らに互いに交流してもらおうと30日、村内5地区の利用者を対象にした交流会が村老人福祉センターで開かれた。南割、町一、町二、大久保、大田切の各区から約60人が参加し、歌やゲーム、健康体操などを通じて親ぼくを深めた。
ゲームの時間では参加者をチームに分けて「お手玉送り」や満水リレーなどを行った。お手玉送りは1列に並んだ参加者が各チーム10個ずつのお手玉を次々に隣の人に手渡してゴールまでの時間と個数を競うものだが、特別ルールとして、受け取った人はお手玉を投げ上げ、その間に1回手をたたく竏窒ニいう難題が加えられた。参加者らは時折お手玉を落としたりしながらも笑顔で楽しそうにゲームに興じていた=写真。
参加した利用者は「1年に1回よその区の知り合いにも会えて楽しい。ありがたいことです」と笑顔で話していた。 -
水ぬるみイワナ放流

水ぬるみ、渓流釣りシーズンを迎え、天竜川漁業協同組合(後藤治也組合長)は29、30日、上伊那の主要渓流14河川約百カ所にイワナの成魚を放流した。 体長18-40センチ、70-100グラム前後の2年魚を中心に前年並の500キロ(約5000匹)を用意した。
30日は小雪が舞うあいにくな天気の中、駒ケ根市の太田切川、新宮川、宮田村の黒川など6河川13カ所で実施。太田切川のこまくさ橋下流のキャッチ&リリース区間では、バケツから放流されたイワナは銀鱗を踊られ、たちまち流れの中に消えた。
今回放流されたイワナは宮田村同漁協で養殖されたもの。
同漁協では、大型連休を前に、4月の中、下旬にイワナとアマゴ、ジャンボニジマスの放流を計画している。
漁協関係者は「今年は渇水状態が続き、釣果は今1つだったが、最近になって、数回雨が降り、水量が増え、水温も上がり、良い環境になった」と話していた。
遊魚料は1日券千円、年間6千円、中学生券300円。 -
無暖房・低燃費住宅セミナー

##(見出し(1))
駒ケ根市福岡で無暖房・低燃費住宅を分譲する駒ケ根市の井坪建設は26日、駒ケ根市文化会館で無暖房・低燃費住宅セミナーを開いた=写真。
講師は「信州の快適なすまいを考える会」会長の山下恭弘信大教授、住宅の空調システムを製造・販売する三菱電機中津川製作所の川渕勇さん。無暖房住宅に関心のある人など約20人が受講した。
快適な住環境のあり方を研究する山下教授は、信大構内に設置した無暖房、低燃費住宅の実験棟の断熱仕様を説明し、外気温と室内温度の変化をグラフで表わした。
また、実際に宿泊し、生活した人の体の各部位のサーモグラフィ、体験者の快適度評価も紹介し「寒くなく、ほぼ快適が多かった」とした。
川渕さんは「なぜ今、高気密、高断熱住宅なのか」を次世代省エネルギー基準に触れて解説し、井坪建設が建設予定の無暖房モデルハウスの断熱仕様(屋根や土間床、基礎、壁に10縲・5センチ前後の発泡スチロール板を張り付け、開口部の窓はペアガラス樹脂サッシ)で、生活発生熱を加算し、シュミレーションした。
暖房期(1月1日縲・1日)と冷房期(8月1日縲・1日)の外気温、居間、キッチンなど各室の温度をグラフで示し「最寒日(1月14日)は外気温がマイナス12・7度でも、室内は10度以上を保っている。熱損失量は一般の3分の1以下、無暖房に近い」と立証し「いよいよ無暖房住宅が実現の段階を迎える」とした。 -
「伊那谷の豊かさ」を支える流通の魂 - ニシザワ会長 荒木茂さん(82)【I】

伊那市日影に本社を置くニシザワは、中南信エリアを中心にグループ全体で59店舗を展開する。日常生活に欠かせない食品・服飾用品・書籍・文具などを供給するだけでなく、リサイクル書店や外食産業にも進出し、いまや押しも押されぬ伊那谷流通業の中核的存在。中部日本でも有数な総合小売業である。
創業は、1924(大正13)年、伊那市通り町の小さな書店。その後、創業者故荒木昌平氏急逝や、1949(昭和24)年の大火、県外資本による競合店進出竏窒ネどの度重なる難局を乗り越え、現在の地歩を築き上げた。
現在会長の荒木茂さんは、3月30日で82歳。1940(昭和15)年、母が守り続けた書店に18歳で入り、戦争とシベリア抑留の一時期を除いて、常に経営の先頭に立ってきた。
書店から、デパート(ニシザワデパート)、スーパーマーケット(ニシザワショッパーズ)、ショッピングセンター(ベルシャイン)、さらにディスカウントストア(サンマックス)、リサイクル書店(ブックオフ)、外食産業(「牛角」など)竏窒ニ、多角化による安定発展の道を歩み続けた荒木さんに、次世代に伝承するべき経営の秘訣と、流通業にかけた思いを聞いた。
【毛賀沢明宏】 -
「伊那谷の豊かさ」を支える流通の魂 - ニシザワ会長荒木茂さん【II】
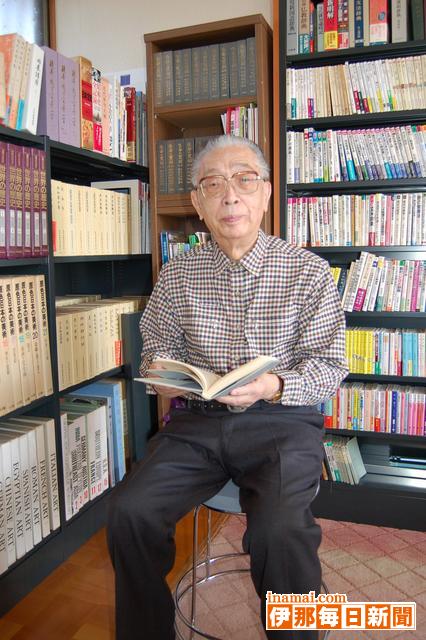
伊那谷流通業のリーディングカンパニー、ニシザワを育て上げてきた荒木茂さん(現同社会長)。その素顔に迫る特集の2回目。前号(29日掲載)では、「良い物を、より安く竏窒ニいうことに尽きる」と語る経営哲学の底に、地域への貢献の魂が脈打っていることを素描した。
本号では、そうした荒木さんの考えはどのような人生の苦闘の中で発酵してきたのか、そしていかなる深みを持つのか竏窒A青年期のエピソードの中に探ってみた。
【毛賀沢明宏】 -
「伊那谷の豊かさ」を支える流通の魂 - ニシザワ会長荒木茂さん【III】

伊那谷の流通業の中核を担うニシザワグループの創設者、荒木茂さんの特集3回目。さまざまな苦難を乗り越えてきた道筋の中に、心の拠り所となった哲学を探った。
-
宮田大学修了式、

宮田村公民館の生涯学習講座・宮田大学(所沢喜代子学級長、33人)は29日、本年度の修了式を村民会館で開いた。
式で白鳥剛公民館長は「他力本願」の解釈について「阿弥陀様のご加護で救済される。あなた任せの2通りの意味がある。長い人生、時には目に見えない大きな力、他力が働き、驚くほど力を発揮できることもあるが、じめじめと気落ちしている時もある。そんな時こそ、人間の力を超えた目に見えない力を信じ、前向きに元気で頑張って」と激励した。
所沢学級長は1年間の活動を振り返り「今日で本年度の学習は修了、来年も気持ちを新たに、活動しよう」と呼び掛けた。
大学院は昨年5月開講全10回開催。つけもの講習会やこけ玉づくり、心の健康講演会、木曽路の旅など多彩な活動を展開した。 -
駒ケ根市社協評議員会

駒ケ根市社会福祉協議会(竹内正寛会長)は28日、05年度第3回評議員会をふれあいセンターで開いた。評議員約30人が出席し、社協が運営する認知症高齢者グループホーム「ほほえみの家」に続く第2のグループホームの施設整備のため福祉基金から1350万円を取り崩すことを承認したほか、06年度事業計画・予算案などを承認した。役職の交代などに伴い、新たに5人が評議員に選任され、竹内会長から委嘱状が手渡された=写真。任期は前任者の残任期間で07年5月30日まで。
第2グループホームはJR伊那福岡駅の東約1キロにある民家を改修し、定員6人で今年10月の開設を目指している。
新評議員は次の皆さん。
塩沢昌壽(中沢地区区長会副会長)市村重実(東伊那区副区長)菅沼幸穂(伊南福祉会救護施設順天寮長)北原和明(駒ケ根青年会議所専務理事)吉村晴夫(駒ケ根市地区社協連絡会副会長) -
特養老人ホームに温泉プレゼント

駒ケ根市の早太郎温泉記念事業実行委員会(宇佐美宗夫実行委員長)は市内の特別養護老人ホームや老人保健施設などの利用者に施設内で温泉気分を味わってもらおうと温泉の湯のプレゼントを始めた。29日には宇佐美委員長ら委員5人が特別養護老人ホーム観成園(福島紀六園長)を訪れ、利用者にタオルをプレゼント=写真。この日の朝に源泉からくみ出してきた4トンの温泉の湯をタンクローリーから施設内の風呂に給湯した。利用者は「温泉の湯? うれしい」と手をたたいて喜び「午後の入浴が待ち遠しいね」などと笑顔で話し合っていた。
宇佐美委員長は利用者らに「早太郎温泉が誕生して今年で10年になるが、これは市民みんなの財産。今日は日ごろ温泉につかる機会の少ない利用者の皆さんにも温泉をゆっくり味わっていただきたい。いつまでも健康で長生きしてください」と呼び掛けた。
同委員会は4月6日までに市内の6施設に温泉をプレゼントすることにしている。 -
すずらん少年少女合唱団演奏会

今年創立33年を迎える駒ケ根市のすずらん少年少女合唱団は28日、第10回演奏会を駒ケ根市文化会館大ホールで開いた。小学4年生から大学生の団員27人は指導者の三澤照男さんの指揮に合わせ、澄みきった歌声を会場いっぱいに響かせた=写真。
ステージは5部構成。第1ステージでは伴奏なしのア・カペラで『アベ・マリア』『赤とんぼ』など内外の名曲を披露。第3ステージではプーラントの合唱曲『子どものための合唱曲』を伸び伸びと歌った。第2ステージでは三澤さんが指導する大人の合唱団「女声コーラス虹」が賛助出演して演奏会に華を添えた。会場を訪れた聴衆は次々に披露される美しいハーモニーの数々ににうっとりと聴き入っていた。
同団は全国コンクールで多くの賞を受賞しているほか、ハンガリー、オーストリア、フランスに演奏旅行をするなどの多彩な活動をしている。 -
南箕輪村交通安全協会合同会議
南箕輪村交通安全協会は28日夜、支部長・理事・女性部の合同会議を村役場で開いた。06年度の初顔合わせで、交通安全協会の組織や任務、交通安全指導の実施方法などの説明を聞いた。
交通安全協会は交通事故防止のためボランティアで春・夏・秋・年末の交通安全運動、各種交通事故防止対策、子どもと高齢者を対象とした安全教育、自動車や二輪車運転者の教育、地域・家庭・職場・学校などに対する安全教育、街頭の交通安全指導などの活動をする。
春の全国交通安全運動(4月6縲・5日)で7日に人波作戦、小学校と保育園の交通安全教室、交通環境チェックなどに取り組むことも確認した。
山崎喜美夫会長は、「自身が交通違反をしてはいけない、事故を起こしてはいけないと緊張して制服を着させてもらっている。そこから交通安全が始まる。交通安全の中心的役割を担う。ボランティア的仕事だが、地域のため、家庭のため1年間頑張って」とあいさつした。 -
箕輪町酪農振興協議会総会
箕輪町酪農振興協議会(会員42戸、唐沢重治会長)は28日、総会を町産業会館で開き、06年度事業計画案、予算案などを承認した。
06年度は、会員数の減少により支部体制を現在の8支部から5支部に統合する。事業計画は、酪農近代化の推進、畜産農政対策、優良事例の研修視察、消費拡大に向けた取り組み、認定農業者増加推進など。詳細は新年度に決定する。
05年度は、地元産牛乳の消費拡大のため町に要望書を提出。町営農センターが中心となり「すずらん牛乳」の保育園や学校給食の導入への取り組みとして小・中学校、2保育園、PTA総会、2小学校の保護者で試飲をした。
唐沢会長は、「牛乳は消費が伸びず深刻な問題。地産地消で消費拡大、酪農振興を行政にもお願いしたい」とあいさつした。
役員改選で会長に根橋英夫さん、副会長に桜井克成さん、会計に荻原省三さん、婦人部長に浦野チエ子さん、婦人部副部長に三井時子さんを選出した。 -
ながた荘 女性限定平日プラン「お姫様ご膳」4月1日~
箕輪町のみのわ温泉ながた荘は4月1日から、春の特別企画で女性限定平日プラン「お姫様ご膳」を始める。予約を受け付けている。
女性に、平日の昼間に温泉に入り、個室でゆっくり食事をしてくつろいでもらおうと初企画。
料理はちらし寿し、柔らかな鶏肉とカボチャ、トマトのサラダ風仕立て、有田焼の引き出し3段式の器に盛り込んだ煮物・焼き物・刺身、山菜の天ぷら、カボチャの茶わん蒸し、吸い物、漬物、カボチャのムース風デザート、ロゼワイン。関西風の味付けでヘルシー料理。食べやすく一口大になっている。
期間は4月1日から28日まで。1日30食限定。利用は午前10時縲恁゚後2時。2人以上、個室貸切、温泉入浴付きで料金1人3千円。土・日曜、祝日の利用は4千円。予約はながた荘(TEL79・2682)へ。 -
環境に関して市民らの活動紹介 八十二銀行伊那支店

伊那市境東の八十二銀行伊那支店(荻原英俊支店長)で31日まで、市民などによる環境保全運動の取り組みを写真などのパネルで紹介している=写真。
同支店は環境について多くの利用者にも関心を深めてもらおう竏窒ニ企画した。
パネルは市内各地の河川で展開している、児童と住民によるアマゴ放流や水質調査などの活動のほか、同市富県新山の湿地に生息しているハッチョウトンボの解説などが一目で分かるようになっている。
リサイクルシステム研究会が毎年開いている、諏訪湖から遠州灘(静岡県)までの一斉ごみ拾い「天竜川環境ピクニック」の様子も写真などで紹介している。 -
伊那木曽連絡道路の開通に伴う交通変化(速報値)とその効果
飯田国土交通事務所などは28日、伊那木曽連絡道路の開通に伴う交通変化(速報値)とその効果を発表した。
当初予想された大型車の利用は少なく、観光、医療、経済、雇用など、あらゆる面で地域間交流が進んでいる。
開通後の1カ月の1日平均交通量は、平日2216台、休日6559台。休日利用は平日の約3倍になる。大型車の利用は平日・休日を平均して約4・7%に留まった。
国道19号線の迂回路としての機能も発揮しており、上松町内で交通事故による通行止めがあった3月12日は、伊那木曽連絡道路の交通量が約2・5倍増加した。
医療方面では、以前は見られなかった木曽地域の外来者が伊那中央病院を訪れており、2月4日縲・8日で17人が来院した。うち4人は緊急患者として搬送されており、医療ネットワークが充実した。
観光では、もともと利用者数の少なかった木曽側観光施設の利用者数が3倍、5倍、7倍と大幅に増加。もともと利用者数の多い伊那側は、1・1倍、数にして約3500人増となった。
ほかにも、木曽地域の新聞へ折込み広告を入れる伊那側のスーパーなどが増加し、伊那市の公共職業安定所で木曽地域も対象とした求人が15件あった。2月末現在で木曽地域から照会登録している人も7人いる。
木曽地域トンネル付近には大型量販店がないため、伊那市西箕輪の日帰り温泉施設・みはらしの湯を訪れる観光客の中には観光の一環として大型量販店を訪れたいと希望するグループもあるという。 -
「山室ふれあい農園」開園 都会の13人オーナーが野菜栽培へ

高遠町の農事組合法人・山室はこのほど、06年度「山室ふれあい農園」の開園式を三義生活改善センターと現地で開いた。心身のリフレッシュに役立てようと、東京都などから農地を借りたオーナーたちが集まった。
1年契約で農地を貸出し、農作業体験を通して都市と農村の交流を深めるための事業。都内を中心に埼玉県から、本年度は前年度より3人多い、計13人のオーナーが農園を利用する。
それぞれのオーナーは1区画(200平方メートル)縲・区画を中心に農地を借地し、年間を通して山室に出向いて農作物を育てる。つくられる野菜は例年、ジャガイモ、ネギ、ダイコン、サツマイモなどがあるという。
開園式では地元関係者が苗付け方法などを指導する、野菜づくりの栽培相談会の日程を皆で調整。4月に2回、7月に1回の会を開くことを決めた。
新宿区の区報で農園について知った会社員の春田勝彦さん=新宿区喜久井町=夫婦は、初めての参加。「無農薬で大きなサツマイモとジャガイモを育てたい」と期待を膨らませていた。 -
水彩画サークル「葦の会」 個性溢れる力作披露

伊那市を中心とした水彩画愛好者でつくるサークル「葦の会」の展示会は4月5日まで、伊那市中央区の中部電力伊那営業所ギャラリーで開いている=写真。
20縲・0代の幅広い世代の会員17人が制作した、水彩画やシルクスクリーン版画の計35点を出品。「水彩画を楽しく描こう」と取り組むメンバーによる風景、静物、人物画などの力作が並ぶ。
毎年11、12月に取り組んでいるシルクスクリーン版画は初めて展示。会員が年賀状のために作った版画は、季節の到来を告げる花のほか、今年の干支(えと)の犬などを描いている。水彩画はそれぞれの色とタッチが個性的で「モチーフに合わせた背景の色使いを見てほしい」と会員は呼びかけている。
葦の会は伊那公民館講座「水彩画教室」(1990‐92年)を修了した仲間で14年前に設立。「パリ国際ル・サロン」会員の碓井伍一氏(伊那市山寺区)を講師に迎え、同公民館で月2回の教室で学ぶ。同ギャラリーでの展示は年に春と秋の2回を開いている。
土・日曜日、祝祭日は休館。午前8時30分縲恁゚後5時10分。 -
伊那市環境審議会 最後に推進5項目を具申

伊那市環境審議会(小松朝雄会長、15人)は28日、同市に対して重点的に取り組んでほしい「環境行政の推進に関する具申」のまとめを小坂樫男市長に提出した。
同審議会は市環境基本計画の推進母体である市環境協議会の年次報告書を協議、検討。2月28日の本年度3回目の会合で要望をまとめた。
「環境行政の推進竏秩vは▽ごみを限りなくゼロに近づける伊那市を目指して▽水辺空間の保全・創出について▽環境教育等に関する具体的提案▽里山相談窓口について▽帰化植物の撲滅について竏窒フ全5項目。
水辺空間の保全・創出について小坂市長は、三峰川の河川敷に帰化植物が繁茂している状況を「もう少し整備していく必要がある。今後も国土交通省と連携していきたい」と述べた。
同市では新市環境基本計画をつくるにあたり、今回の要望を歌いこんでいく考え。
市環境審議会は伊那市・高遠町・長谷村の3市町村合併に伴って消滅。新市では委員を3市町村から選出して構成する。 -
春日街道~R361直線で接続
県などは、県道伊那箕輪線(通称・春日街道)の沢尻交差点(南箕輪村)から国道361号へつながる道などを新たに造る工事を24日、終了させた。権兵衛トンネルが開通し、車の交通が頻繁になる状況を、特に県道から国道に向かう車両の流れをスムーズに通すための工事。31日午後4時から、新道路の交通を開放する。
国道に対して、沢尻交差点からほぼ直角に接する道路と交差点(仮称=沢尻南)を造った。それぞれの道路をつなぐ川北町交差点(伊那市)が鋭角だったため、これまで大型車が交道を曲がることが困難な状況だったことを解消した。
新しい道路の全長は約300メートル。全幅は本線6・5メートル、右折車線(国道に向かって)3・0メートル、片側歩道2・5メートルなどを含む13・5メートル。用地買収や計画設計などは県が受け持ち、本工事は飯田国道事務所が昨年夏からはじめた。
新しい道路を造るにあたり、沢尻交差点を直角交差に整備するなどの工事費用も合わせて約5億円。 -
「伊那谷の豊かさ」を支える流通の魂 - ニシザワ会長 荒木茂さん【IV】

伊那谷の流通業の中核を担うニシザワグループ。その先頭で牽引してきた荒木茂会長に迫るシリーズ4回目。会社プロフィールと、地域で関係のあった人々に「私の見た荒木さん」を語ってもらった。
-
高遠城址「さくら祭り」4月6日開幕

全国有数の桜の名所として知られる高遠城址公園のさくら祭りが4月6日、新伊那市として初めて開幕する。長野地方気象台の開花予想によると平年より4日、昨年より2日早い9日。最盛期は15日前後とみている。
祭りは5月5日までで期間中は、高遠まんじゅうの大食い大会、クイズ大会、高遠囃子(ばやし)巡行、町商工会女性部による桜茶サービスなどを予定している。
高遠町観光協会は高遠城址公園のさくら祭りに向けて、ポスターを昨年より200枚多い1600枚を印刷。権兵衛トンネルの開通で木曽谷にも配ってPRしている。
今年は新市発足によって、これまで町民に配布していた無料入園券を新市の住民に配る。何度でも利用が可能で、絵島の囲み屋敷や進徳館にも入れる。券には「祝 新伊那市誕生」などと記し、桜の絵を配している。
また、町商工会は29日、ぼんぼり135基を公園に設置した。関係者ら約60人が参加し、園内通路に沿って柱に協賛企業名が入ったぼんぼりを載せた。期間中の日暮れから午後9時(最盛期は11時)まで園内を灯す。
さくら祭りは83年の有料化以降、24年目。昨年の有料入園者数は31万4778人で、最盛期には1日に5万7600人が訪れる過去最多を記録。期間中に600万人を突破した。 -
伊那市養護老人ホームみすず寮の経営移管式典

伊那市から上伊那福祉協会に経営移管する伊那市美篶の養護老人ホームみすず寮で29日、経営移管協定書・契約書の調印式があった。
市町村から上伊那広域への経営移管は2カ所目。01年度以降みすず寮は、上伊那広域で整備を進めていくことを検討。効率的で安定的な民間経営手法を導入していくため、05年度を目途に上伊那福祉協会へ経営移管することとなっていた。みすず寮が加わり、上伊那福祉協会が運営する福祉施設は8カ所となる。
上伊那福祉協会が経営することで効率的な人員配置を実現し、伊那市外からの入所希望者の受け入れなど、よりスムーズにできるようになる。
上伊那福祉協会の平澤豊満会長(箕輪町長)は「入所者が安心できる施設となるように努めていきたい。経営移管しても利用者側はこれまで通りなので安心してほしい」と語った。
移管後は、老朽化した施設の改築などの検討も進める。また、隣接する特別養護老人ホームも、上伊那福祉協会に経営移管する予定で、06年度から検討を進めていく。 -
みはらしの湯で4月からさくらパフェを販売

伊那市西箕輪の日帰り温泉施設・みはらしの湯は4月1日から、桜をイメージしたオリジナルデザート「さくらパフェ」を1カ月限定で販売する。
高沢尚人調理長が考案したオリジナルパフェは4作目。出来るだけ地元の食材を使い、四季に合ったものを提供したい竏窒ニ、「いちごパフェ」「とうふパフェ」「秋のみのりパフェ」などをこれまで考案してきたが、みはらしいちご園のイチゴを使っているいちごパフェは数量が限定されてしまうため、春に楽しめる新たなパフェを考案することになった。
今回は、春をイメージさせる桜をテーマ。市町村合併ということもあり、高遠町のコヒガンザクラも意識した。桜の塩漬けを固めたゼリーの上に、桜アイス、桜色のくず餅などがトッピングされている。サクラの花が入っているゼリーは、口に入れるとほのかに桜の香りがし、和菓子感覚で楽しめる。
価格は450円。
2010/(月)
