-
南相馬市の親子 箕輪の学校通学を相談

大震災による津波や原発事故の影響で、福島県南相馬市から長野県に避難している親子らが、箕輪町の小学校に通学できないか、町に相談している事が分かりました。
箕輪町によりますと、南相馬市から避難している親子は12組で、24日、箕輪南小学校と箕輪中学校への通学について、町に相談がありました。
親子12組は現在、岡谷市に避難しています。
避難している子どもは、小学生12人、中学生7人です。
避難している家族の1組が、以前箕輪町に住み、子どもが箕輪南小学校に通っていたことなどから、今回相談がありました。
箕輪町では、全面的に受け入れたいとして、箕輪南小学校に通学できる住居の手配も含めて、検討を進めています。
また、今回箕輪中学校に通うには、制服が必要になるため、箕輪中学校の卒業生に対して、不要になった制服の提供などを呼びかけていくということです。 -
箕輪町が「防災マップ」作成
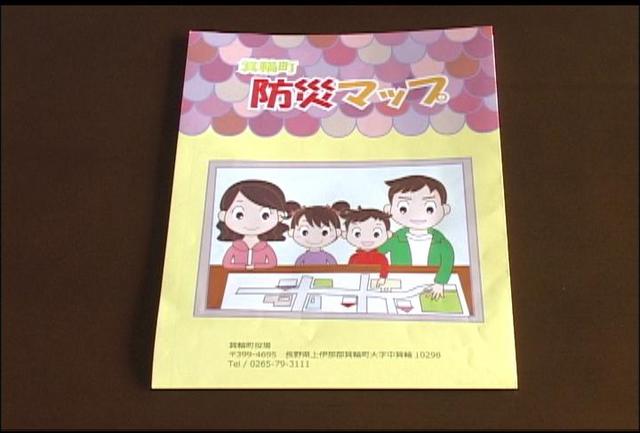
箕輪町は、水害や土砂災害の危険地域や日頃の備えなどを記した防災マップを作成し、全戸に配布します。
主に、水害と土砂災害に備えるためのもので、危険箇所を記した地図や、非常持ち出し品のチェックリスト、AEDの使用方法などが記されています。
箕輪町では、去年10月からこのマップの作成を進め、94万5千円かけ、9500部を作成しました。
町では、「このマップを使って、家族で災害について話し合うなどして活用してもらいたい」としているほか、マップを使った出前講座などを計画しています。
防災マップは、今月末に、町の広報誌とともに、全戸に配布されるほか、町役場で希望者に配布されます。 -
大明化学工業が義援金届ける

南箕輪村北殿の大明化学工業株式会社は24日、東日本大震災の義援金を村役場に届けました。
福島士郎社長ら2人が村役場を訪れ、唐木一直村長に義援金を手渡しました。
義援金は、会社から100万円と、全従業員から募った25万2500円です。
大明化学工業は、浄水場で水道水のために使用する薬品を製造していて、東北地方でも使われているといいます。
福島社長は、「国民全体で応援しないといけない。東北にもユーザーさんがいるので、いくらかでも応援したい」と話していました。
南箕輪村にはこのほか、南箕輪小学校PTAから20万円、南箕輪小学校教職員から2万7450円が23日、義援金として届けられたということです。 -
南原住宅団地焼却灰処分費用9千万円可決
24日開かれた伊那中央行政組合議会で、南箕輪村の南原住宅団地に埋め立てられていた焼却灰の処分費用9000万円などを盛り込んだ来年度の一般会計予算案が可決されました。
南原住宅団地内の焼却灰は伊那中央清掃センターから搬入されたもので、1800トンあります。
処分は土が混入するため、全体の処分量は2500トンと推定しています。
処分費用は9000万円で、伊那中央行政組合議会を構成する3市町村で分担します。
焼却灰の掘り起こしと処分作業は来年度実施されます。
議会ではまた、医療体制の充実を求める意見書が議員から提出され、可決されました。
意見書では▽上伊那地域に医師を優先して配置する▽県による3機目のドクターヘリの配備を進める▽上伊那地域でのドクターヘリの運航に格別な配慮をする竏窒ニいう3点を挙げています。
意見書は県と県議会に提出するということです。 -
保育園卒園式 富県保で記念植樹

伊那市と箕輪町の保育園で24日、卒園式が行われました。
伊那市の富県保育園では、新しい園舎で保育園生活最後の1年を過ごした園児22人が卒園しました。
式では、山崎富子園長が卒園証書を一人ひとりに手渡しました。
山崎園長は、「おはようと、ありがとうを心を込めて言える元気な小学1年生になってください」とあいさつしました。
卒園児は、保育園生活を振り返って呼び掛けをし、歌を歌いました。
式のあと、卒園の記念に、保護者と園児が、古い園舎にあったナツメの木を植樹しました。
園児が実をとるなどした思い出の木で、今回、現在の園舎に移植しました。
保護者会では、「このナツメの木で遊び、季節を感じて、自然に溶け込める子どもになってほしい」と話していました。
25日は、伊那市の大萱保育園と西箕輪北部保育園、南箕輪村の全保育園で卒園式が行われます。 -
箕輪町議選 説明会に15派出席

任期満了に伴い、4月19日告示、24日に投開票が行われる箕輪町議会議員選挙の立候補届出手続き等説明会が24日、箕輪町役場で開かれ、定数15人に対し15派が出席しました。
説明会には、すでに立候補を表明している12派と、近く立候補の表明を予定している3派、合わせて15派が訪れました。
説明会では、立候補に関する手続きなどの説明が、町選挙管理委員会などからありました。
町内では、無投票を避ける為、候補者を擁立する動きもあります。
箕輪町議会議員選は4月14日に立候補届出書類の事前審査が行われ、19日に告示、24日投開票となっています。 -
伊那公民館 野草講演会
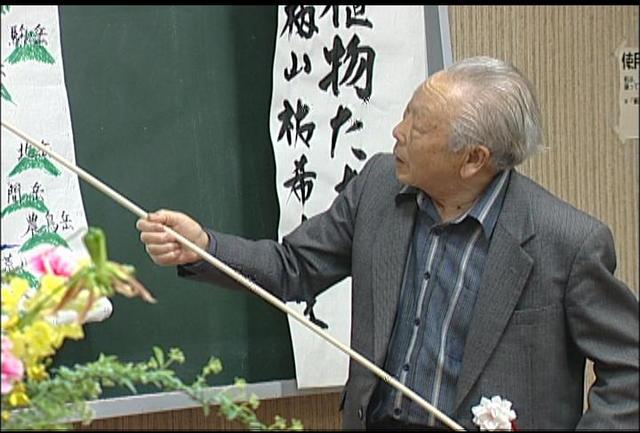
県植物研究会会員の柄山祐希さんの野草講演会が15日、伊那公民館で開かれました。
伊那公民館の野草講座は昭和59年から開かれていて今年で26年目です。
この講座の開始当初から講師を務めている柄山祐希さんが南アルプス入野谷の植物と題し講演しました。
柄山さんは「長谷の三峰川流域の地域には日本でも数少ない植物が見られる。入野谷は植物の名所だと思う」と話していました。
会場には市内などから80人が訪れ柄山さんの話に耳を傾けていました。
伊那公民館で開かれている柄山さんの講座は毎年人気で、新年度は7月からスタートするという事です。 -
天竜川漁協が、あまごの成魚放流

本格的な渓流釣りのシーズンを前に23日、天竜川漁業協同組合は、上伊那の主な河川で、あまごの成魚を放流しました。
23日は漁協の組合員が手分けして、伊那市の小沢川などにあまごの成魚500キロ分を放流しました。
渓流釣りは寒さがゆるむ、4月以降本格的なシーズンを迎えることから漁協では、4月にイワナの成魚の放流も計画しています。 -
寄せられた義援金2,000万円超える
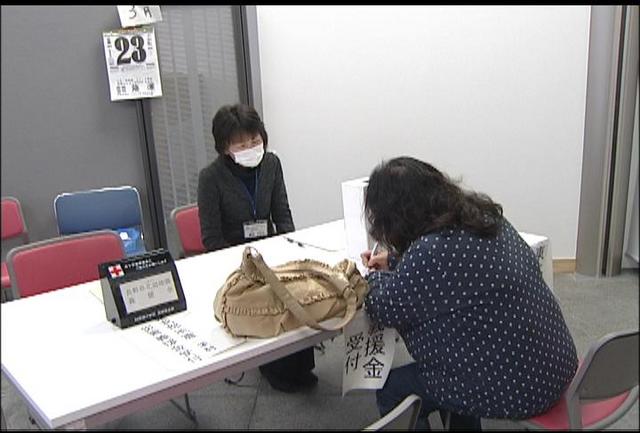
これまでに伊那市に届けられた震災による義援金は2千万円を超えたことがわかりました。
伊那市に届けられた東日本大震災の義援金は、今月13日から、昨日22日までの10日間で21,749,650円となっています。
また被災者の受け入れ可能となっている住宅と人数は、22日現在で89戸145人、そのうち、4戸18人が入居しています。 -
みんなで支える森林づくり上伊那地域会議

森林税を活用した事業について住民の意見を聞く「みんなで支える森林づくり上伊那地域会議」が11日、伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。
11日は、今年度3回目となる会議が開かれ、事業実施状況や、来年度の事業概要について意見交換しました。
上伊那地域会議は、信大農学部の教授や、林業関係の代表者など10人で構成されています。
平成23年度事業の概要について県は、「上伊那からの木育推進事業の要望が増え、今年度の倍の事業費を予定している。」と説明しました。
他にも「手入れの遅れている里山での間伐を促進するため、間伐面積を増加させる」としました。
委員からは、木育に関しての意見はなかったものの、森林整備については「場所によってはまだまだ整備が進んだ実感がない」などの意見が出ていました。 -
南箕輪村議選 立候補説明会に10派出席

任期満了に伴い、4月19日告示、24日に投開票が行われる南箕輪村議会議員選挙の立候補届出手続き等説明会が、23日、村役場で開かれ、定員10人に対し、これまでに立候補を表明している10派が出席しました。
説明会では、立候補に関する手続きなどの説明が、村選挙管理委員会からありました。
南箕輪村の議員定数は10人で、これまでに10人が立候補を表明しています。
村内では、無投票を避けるため、候補者擁立を模索する動きなどもあります。
南箕輪村議会議員選挙は4月14日に立候補届出書類の事前審査が行われ、19日に告示、24日投開票となっています。 -
「美篶の歌」マップとDVDできる

伊那市の「美篶の歴史を学ぶ会」は、地区の史跡や歴史などを歌った「美篶の歌」に出てくる史跡などを紹介する地図と、歌詞にあわせ映像をつづったDVDを制作しました。
16日は、美篶の歴史を学ぶ会の橋爪 英峯(ひでたか)会長など3人が伊那市役所を訪れ、地図とDVDの完成を報告しました。
県の地域発元気づくり支援金から27万2千円の補助を受け、地図2000部、DVD100枚を制作しました。
美篶の歴史を学ぶ会では、平成21年から、美篶の歌を元にして地区の歴史について学んできました。
16日は、制作したDVDも上映されました。
美篶の歌は、12番まであり、地区の歴史や文化、史跡などが紹介されています。
白鳥市長は、「地域のことが全て盛り込まれていておもしろい。地域の歴史が形として残りますね」と話していました。
地図とDVDは今月25日に美篶公民館で開かれる講座で公開されます。
美篶の歴史を学ぶ会では、地図を使っての史跡巡りを計画しているほか、小中学校や公民館などへDVDを配布したいとしています。 -
南箕輪村 人事異動内示 大規模な異動
南箕輪村は23日、4月1日付けの人事異動を内示しました。全体の3割が異動する大規模の異動で、異動総数は30人、課長級への昇格は3人となっています。
収納対策課長には財務課税務係長の有賀由起子さん、建設水道課長には総務課行政係長の藤田貞文さん、教育次長に産業課商工林務係長の田中聡さんが昇格します。
南箕輪村では、健康に力をいれた行政の推進を図るため、今回新たに健康指導員1人を住民福祉課に配置し、大芝高原のセラピーロードや食を通した健康づくりを進めます。
また、収納対策課に新たに係長を配置し収納率の更なる向上を図るという事です。 -
南箕輪中学校、南箕輪建設組合 義援金届ける

南箕輪中学校の生徒会は、卒業式で集めた東日本大震災の義援金を23日南箕輪村役場に届けました。
この日は、生徒会役員3人が村役場を訪れ、加藤久樹副村長に義援金を届けました。
南箕輪中学校では、16日に行われた卒業式で、玄関に募金箱を置いて義援金を募りました。
卒業生の保護者や来賓にも協力をよびかけたところ、東日本大震災の義援金として14万1,321円、長野県栄村の義援金として5万円が集まったという事です。
生徒会長の福澤悠樹君は、「テレビで災害の悲惨さを知って何としても力になりたいと思った」と話していました。 -
子ども地球サミットを中止
南箕輪村は東日本大震災をうけ、今年7月末に予定していた子ども地球サミットを中止する事を決めました。
子ども地球サミットは、コンサートやイベントを通して、環境について問題意識を高める事を目的に毎年開かれています。
今年は7月末に南箕輪村民センターを主会場に行う計画でしたが、災害の被災地に配慮し中止する事としました。
また震災を受け、子ども地球サミット関係者は、27日日曜日の午後3時半から、南箕輪村の南殿コミュニティセンターで義援金を募ることにしています。
なお、8月27日に予定されている大芝高原まつりについては、4月に実行員会を開き、開催か中止か決定したいという事です。 -
箕輪町 義援金1,000万円

箕輪町議会臨時会が23日、箕輪町役場で開かれ、東日本大震災で被災地に寄付する義援金を1千万円とする補正予算案が可決されました。
箕輪町などが加盟する長野県町村会では東日本大震災による被災地の復興のため町村単位で支援することを決めました。
義援金の額については、人口に応じて決められ、2万人以上の箕輪町は250万円と決まっていました。
町では平成18年7月豪雨災害で他市町村から多額の支援を受けたことなどから、決められた額の4倍となる1千万円を補正予算案として提出し、可決されました。
この額について、平澤豊満町長は、町内20歳以上の住民およそ2万人から1人500円を集めた金額と説明しました。
また平澤町長は23日、みのわ祭りについて、執行部の間では、中止で意思統一されたとして、30日に開かれるみのわ祭り実行委員会に中止を提案すると述べました。
中止となった場合、祭り予算の700万円については、今回1,000万円を送ることから義援金にあてるのではなく、予備費に繰り入れるとしています。
ほかに災害への備えなどを示した「住民支え合いマップ」を全戸配布することが報告されました。
箕輪町にはこれまでに各団体や個人から307万8640円が義援金として届けられているほか、毛布79枚、ペットボトル入りの水113本などが集まっています。
ほかに町営住宅5戸や町内のホテル、旅館が被災者の受け入れ施設となっていて、福島県いわき市の2世帯9人が避難しているということです。 -
箕輪町人事異動内示 小規模
箕輪町は23日、4月1日付けの人事異動を内示しました。
59人が異動する小規模で課長級への昇格は4人となっています。
課長級の消防室長には、消防室庶務係長の桑沢國一さん。
総務課付け伊那中央行政組合派遣となる経営企画課企画財務係長の笠原毅さん。
産業振興課長に総務課付け、厚生労働省派遣の長井正さん。
教育課長兼用務係長に建設水道課上下水道管理係長の戸田勝利さんが昇格します。
箕輪町では平成24年度のセーフコミュニティWHO認証取得に向けてセーフコミュニティ推進室をあらたに設置し、室長には、県警の元警備部長の向山静雄さんが就くことになっています。 -
富県小学校6年生 タイムカプセルを預ける

伊那市の富県小学校6年生は14日、近くの寺にタイムカプセルを預けました。
タイムカプセルを預けたのは、富県小6年生22人です。
小学校の思い出を残そうと、学校のそばにある金鳳寺に、今年初めてタイムカプセルを預けました。
14日は、集合写真や1人ひとりの手形、将来の夢を書いた作文などが詰められた箱を、児童が運び、寺の建物に預けました。
学級長の鹿野香沙さんは「8年後の成人式の日にとりに来るので、預かってください」と金鳳寺の山・ス智性副住職に挨拶しました。 -
伊那市の宮原徹也さんが青年海外協力隊でドミニカ国へ

伊那市の宮原徹也さんが、JICAの青年海外協力隊として3月28日にドミニカ国に出発します。
15日は、宮原さんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に出発の挨拶をしました。
宮原さんが行く中南米のドミニカ国は、カリブ海に面した国で、人口、面積とも伊那市と同じ規模の国です。
ドミニカ国は、水産資源が豊富な国ですが、漁業資源の組織的な管理がされておらず、現状把握や状況分析が十分に行われていません。
宮原さんは、統計を専門としていて現地ではデータの管理や、管理についての指導などを行います。
宮原さんの滞在期間は平成25年までの2年間を予定しています。
伊那市からの派遣は、37人目となります。 -
福島県会津若松市に伊那市職員を派遣

伊那市は、福島第一原子力発電所の事故で避難者を受け入れている福島県会津若松市に21日、職員5人を派遣しました。
この日は、伊那市役所で出発式が行われました。
伊那市は親善交流を結ぶ会津若松市からの要請を受け、避難所の運営を支援する職員5人を派遣しました。
現在、会津若松市は、福島第一現原発の事故により近隣市町村の避難者を4か所の避難所で受け入れています。
白鳥孝伊那市長は、「現地の様子を報告する事、現場の指示に従って安全に留意しながら支援にあたる事をお願いしたい」と激励しました。
5人は、24日(木)まで、会津若松市の総合体育館で避難所の運営を支援することになっていて、伊那市では、今後も継続して職員の派遣を行う予定です。 -
なでしこジャパン佐々木監督が講演

世界ランキング4位のサッカー日本女子代表チーム「なでしこジャパン」の佐々木則夫監督が20日に箕輪町のながたドームで講演しました。
佐々木監督は、すべての人に感謝することを忘れないで欲しいと前おきし、「アジア地域の女子は、サッカーに向いている。自信とプライドを持ってプレーして欲しい」と話しました。
県内の部活などでプレーしている高校生や中学生80人が、女子サッカーの頂点でチームを引っ張る佐々木監督の話しに耳を傾けていました。
佐々木監督は、山口県出身で、選手引退後、なでしこジャパンコーチを経て監督に就任。
2008年の北京オリンピックでは、女子サッカー史上最高の4位にチームを導き、去年のアジア大会では、初優勝を果たしました。
佐々木監督は、6月にドイツで開催される女子ワールドカップや来年のロンドンオリンピックに向けてのチームの目標などについても熱く語りました。
佐々木監督は「2年前に世界のチャンピオンになろうという目標をたてた。今後皆さんも一緒にトップを目指してがんばりましょう」と集まった選手たちに呼びかけていました。 -
救援物資受付 合庁、市役所で一時中止
東日本大震災の救援物資について長野県は、23日から受付を一時中止すると発表しました。これにより、伊那合同庁舎と伊那市でおこなっている受付が一時中止となります。
県の発表によりますと、支援先自治体から、現在新たな物資の受け入れが困難であるとの連絡があり、当分の間、救援物資の受付を中止するという事です。
これにより、伊那合同庁舎と、伊那市役所での受付が、23日から一時中止となります。
なお、義援金は引き続き受付を行っています。伊那合庁舎では、18日の時点で28万3,480円、伊那市では、21日までに1,932万1,081円寄せられているという事です。
また、箕輪町と南箕輪村では、救援物資、義援金ともに引き続き受付を行うという事です。 -
伊那商工会議所 被災者と商工会議所に対して支援

伊那商工会議所は、東日本大震災と長野県北部地震の被災者と商工会議所に対して支援をおこなっていきます。
これは、22日開かれた伊那商工会議所常議員会で決定されました。
17日に開かれた日本商工会議所会員総会では、全国の514商工会議所が団結して被災地の支援を行っていくことが決議されていました。
伊那商工会議所では、今後具体的な義援金額などを決めていくとしています。
また、伊那商工会館2階では、企業向けの緊急特別経営相談窓口がこの日から設置されました。
震災で経営に影響が出ている企業などに対し、融資や返済期間の延長などの経営相談を行っていくとしています。 -
伊那市西箕輪の大泉新田区 東日本大震災の義援金集める

伊那市西箕輪の大泉新田区は、東日本大震災の義援金を区内142戸から集め、22日伊那市に届けました。
22日は、大泉新田区の唐澤峻区長ら2人が伊那市役所を訪れ、集めた義援金25万106円を預けました。
大泉新田区では、3月15日から21日までの1週間に、組長らが区内142戸をまわり、義援金の協力を呼びかけました。
「市役所まで持っていくことができなかったので助かった」などというお年寄りからの声が多く寄せられたということです。 -
伊那市人事異動内示 中規模
伊那市は22日、4月1日付けの人事異動を内示しました。中規模の異動で異動総数は、312人、昇格は、85人、うち2人が部長級に昇格しています。
保健福祉部長には、伊那中央病院総務課長の原武志さん。
会計管理者兼会計課長には、総務部総務課長の廣瀬一男さんが昇格します。
伊那市では、新たに危機管理課を設置し消防、防災体制などの危機管理機能の充実を図る他、建設部の監理課、建設課の2課体制から、新たに都市整備課を設置し3課体制としました。
また、国との連携を強化するため国土交通省から1人、農林水産省から1人を受け入れます。 -
福島県いわき市から市内に避難

伊那市では東日本大震災での被災者を市営住宅や民間住宅で受け入れています。
21日、市内の民間住宅に避難してきた福島県いわき市の家族に話を聞きました。
持ち主の申し出により市内の民間住宅に昨日から住んでいるのは福島県いわき市の65歳男性家族3人と、娘の家族4人の、合わせて7人です。
自宅が福島県の原子力発電所から25キロほどにあり、15日から男性の妹が住む駒ヶ根市で20日まで滞在していました。
伊那市での受け入れを知り21日から市内の民間住宅に移りました。
この65歳男性は地震当時のことについて次の様に話しています。
「地震の時足場にいて揺れがすごく下に降りれなかった。余震が続き周りにいた小学生の子ども達が泣いていた。原発のニュースをみて早くこっちへ逃げてきた。
早く原発が復旧して福島県に帰りたい」と話していました。
伊那市では、現在市営住宅など32室138人、その他の5つの施設で140人の受け入れ態勢をとっています。
また、会津若松市からの要請で国立信州高遠青少年自然の家で100人程の受け入れを確保しています。
市では今後、福島県から市営住宅に2世帯8人を受け入れるということです。 -
富県公民館で春休みミニおいで塾
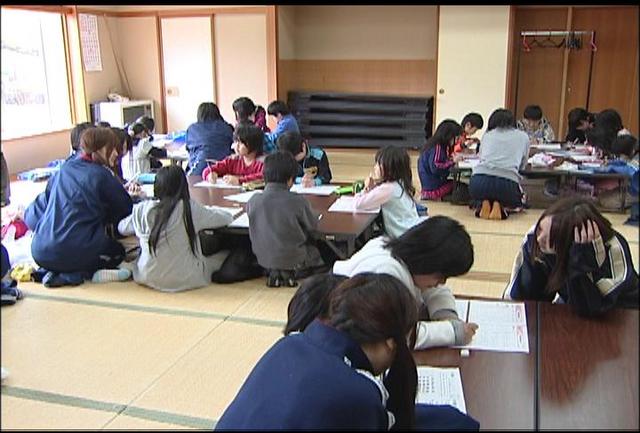
春休み中の子ども達が勉強などをして過ごす「春休みミニおいで塾」が、伊那市の富県ふるさと館で22日から始まりました。
春休みミニおいで塾は、子ども達の居場所作りや学習の場として、小学校1年生から5年生までの児童を対象にしています。
講師は、公民館職員などの他、高遠高校福祉コースの生徒がボランティアで務めます。
参加した児童およそ30人は、判らないところを教わりながら宿題に取り組んでいました。
春休みミニおいで塾は、22日から25日金曜日までで、期間中子供達は、宿題や工作の他、燻せい作りなどを行うということです。 -
高校伊那駅伝中止 練習に熱

震災の影響で中止になった春の高校伊那駅伝。
20日無料開放された伊那市陸上競技場には、練習に汗を流す高校生や中学生ランナーの姿がありました。
駅伝の発着点となつていた陸上競技場では、大会に出場する予定だった県内9つの高校生や中学校の生徒たちが、タイムを計ったり、ランニングをしていました。
中学生の記録会で初めて使用される予定だった写真判定システムも作動させました。
この日に備えて、練習を重ねてきた生徒たちのケアも必要として、高校生40人、中学生12人が参加してのタイムトライアルも
行なわれました。
上伊那農業高校陸上部は、参加者に義援金への協力を呼びかけました。
この日、集められた義援金は、伊那駅伝実行委員会を通じて、被災地に送られることになっています。 -
伊那市狐島区が被災地支援開始

伊那市狐島区では、公民館、地域社協合同で、狐島支援活動実行委員会を設置し、20日から救援物資や義援金を集めはじめました。
狐島第一公民館には、緊急の回覧を見た区民が、ティッシュや乾電池などを持ち込んでいました。
受け付けている救援物資は、保存食や粉ミルク、乾電池などです。
狐島区では、目標としている「支えあっていきるまちづくり」を実践する運動として、区民の協力を呼びかけています。 -
不登校の子どもたち支援「はぐカフェ」開店

不登校の子どもたちの地域交流や情報発信の場にしようと、上伊那子どもサポートセンターが初めてのイベント「はぐカフェ」を伊那市内で20日から開いています。
伊那市狐島のレストラン・ドマーニを会場に、不登校や引きこもりの子どもたちの作品展示、手作り品の販売などが行われています。
上伊那子どもサポートセンターは、不登校の子どもたちの支援をしています。
はぐカフェは、子どもたちの交流や情報発信の場を地域の中につくり、その動きを上伊那各地に広めていきたいと開かれました。
また、上伊那農業高校定時制の跡地に青少年支援センターを設立しようと活動していて、その取り組みをアピールするねらいもあります。
上伊那子どもサポートセンターでは、「不登校や引きこもりは多様化、複雑化している。子どもと向き合い、子どもの未来を考え、みんなの心が通う場をつくっていきたい」と話していました。
はぐカフェは、22日まで伊那市狐島のレストラン・ドマーニで開かれています。
1612/(火)
