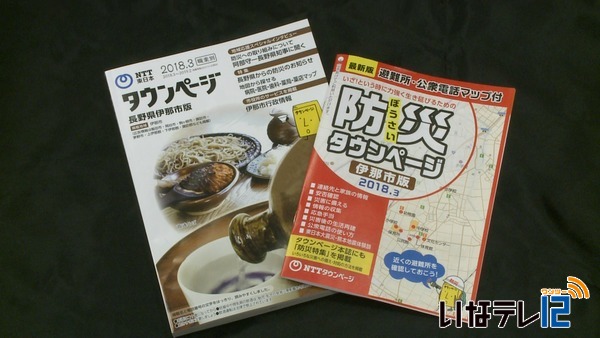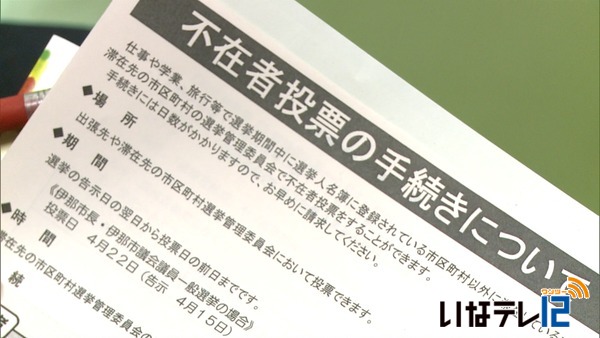-
新人の八木氏 市長選出馬表明
任期満了に伴う4月15日告示22日投開票の伊那市長選に無所属で新人の八木択真さんが立候補することを12日正式に表明しました。 八木さんは伊那市のセントラルパークで市民を前に決意を述べました。 出馬表明で「我々世代の新しい発想があればもっとこの地域は元気になっていくはずです。私は必ず結果を出します。可能性に溢れた伊那市を、胸を張って次の世代に引き継ぎたい。この地域の衰退に若い世代で立ち向かう」と話していました。 八木さんは昭和53年12月2日生まれで現在39歳です。 大阪府堺市出身で信州大学農学部に入学し約7年間、伊那市内で過ごしました。 大学卒業後、産経新聞の記者となり平成25年に伊那市坂下で飲食店の経営を始めました。 平成26年に伊那市議選に立候補し初当選。 今回の市長選立候補にともない13日議員の辞職願を提出しました。 伊那市長選は4月15日告示、22日投開票となっています。 市長選にはこれまでに無所属で現職の白鳥孝さんが立候補を表明しています。
-
木下北保育園 「満足」96%
箕輪町の木下北保育園で、「福祉サービス第三者評価」の結果報告会が9日開かれ、保護者へのアンケートで、96%が保育園を総合的に見て「満足」と回答したことがわかりました。 報告会には保護者およそ20人が参加し、調査員から結果の報告を受けました。 アンケートは78人の対象者のうち28人から回答を得ました。 その中で、「現在利用している保育園を総合的にみてどう感じているか」との問いに「満足」という回答は96%でした。 ほかに、改善する必要がある点として、不審者の侵入や火災、地震など「危機管理への更なる対応」があげられています。 「福祉サービス第三者評価」はアンケートや調査機関の現地調査で、保育園の取り組みや保護者の満足度を調査するものです。 全ての保育園に対し国が努力義務としていて、箕輪町では今年度木下北保育園と木下南保育園で行われました。 結果は今後県のHPで公開される予定です。
-
高遠のまちおこし アイディアを発表
伊那市高遠町の地域活性化に向けた取り組みを提案する、リノベーション高遠まちづくり塾のフォーラムが11日に開かれました。 この日は、高遠町総合福祉センターやますそでフォーラムが開かれ、地域住民などおよそ70人が集まりました。 まちおこしの様々なアイディアについて11人が発表し、このうち2011年に兵庫県神戸市から高遠に移り住んだ林亮さんは、現在準備を始めているビールでのまちおこしを提案しました。 林さんによると、長野県は、もともとビールに使われるホップの産地だったことから、いいものが採れる地域だということです。 林さんは「高遠ならおいしいビールが作れる。一連の作業を高遠で行うことで、利益を生む、地域が儲かる循環をつくりたい」と話していました。 リノベーション高遠まちづくり塾は、空家の活用法やまちのあり方を考え、まちづくりの意識を高めようと、去年7月に発足しました。 リノベーション高遠まちづくり塾の黒河内貴さんは「地域を元気にしようと活動している人は外から来た人の方が意外と多い。そういう人たちを支援するような活動もしていきたい」と話していました。 なお、まちづくり塾の今年度の活動には、県の元気づくり支援金が活用されています。
-
伝統の高遠だるま市 福だるま求め賑わう
江戸時代から続くと言われる伊那市高遠町伝統の「だるま市」が11日、鉾持神社参道で行われ、福だるまを買い求める人で賑わいました。 鉾持神社の参道にはだるまや縁起物の露店商が並び、訪れた人たちが買い求めていました。 大きいものを買った人や、たくさん買った人には、景気づけの手締めが行われていました。 訪れた人たちは、家内安全や受験合格などを祈願して、気に入った大きさや色のだるまを買っていました。 孫が今年大学受験だという男性は「毎年来て赤いだるまを買っているが、今年は合格祈願に白いだるまを買いました」と話していました。 だるま市は、五穀豊穣を願う鉾持神社の祭りに合わせて行われているもので、400年ほど続いていると言われています。
-
伊那市上牧で冬の野鳥観察会
伊那市上牧で冬の野鳥観察会が11日開かれました。 観察会は、上牧一帯を自然パークとして整備した「上牧里山づくり」が開きました。 地元や周辺地域、遠くは飯田市から20人ほどが参加し、自然パークの山すそで望遠鏡を片手に観察しました。 こちらは、ヒヨドリ、そしてシジュウカラ。 珍しい野鳥ではないということですが、参加者は、望遠鏡をのぞき込んでいました。 里山づくりメンバーで、日本野鳥の会会員、自然観察指導員の大村洋一さんの解説を聞きながら歩きました。 途中で鳥の巣も発見。興味深そうにのぞき込んでいました。 天竜川の明神橋周辺では、カルガモも見られました。 上牧里山づくりでは、植物観察会やマレットゴルフ大会など年間を通じて様々なイベントを開催していて、関係者は、「地元の里山に愛着を感じてもらいたい」と話しています。
-
弥生器楽クラブ定期演奏会
伊那弥生ケ丘高校器楽クラブの第10回定期演奏会が11日伊那市のいなっせで開かれ、めりはりの効いたやわらかくあたたかな音色が会場に響きました。 弥生の器楽クラブは、ギターマンドリン音楽を演奏するクラブで、昭和37年創部。55年の歴史があります。 11日は、1・2年生27人が、映画音楽やポップス、アニメソングを交えながら日頃の練習の成果を披露しました。 去年11月の県大会では、県知事賞を受賞し、7月の全国大会に出場するほか、8月の全国高校総合文化祭にも県代表として参加するなど全国レベルのクラブです。 この日は、OB・OGを交えての演奏も含め16曲を披露しました。
-
伊那市長谷で自動運転の実証実験始まる
国土交通省が、伊那市長谷の道の駅「南アルプスむら長谷」を拠点に行う自動運転サービスの実証実験が、10日から始まりました。 実験は6日間行われ、5キロの区間を実験車両が運行します。 10日は実験開始式が行われ、関係者を乗せたバスが道の駅南アルプスむら長谷を出発しました。 席に運転手は座っていますが、ハンドル操作や速度調節は自動で制御されます。 10日は美和診療所までの600mの区間を運行しました。 バスはGPSと道路に埋められた磁気マーカーから位置情報を読み取り運行します。 道路に埋められた磁気マーカーです。 実証実験は、高齢化が進む中山間地域のものや人の流れを支援しようと国土交通省が全国13か所で行っていて、中部地方では伊那市のみです。 実験は南アルプスむら長谷から長谷総合支所までの往復およそ5キロの区間で行われます。 募集によるモニターや小中学校の生徒およそ200人が期間中に乗車し、のりごこちなどのアンケートに答えます。 そのほか、ドローンポートの活用を想定した書類の受け渡しなどを行う予定です。 実験は16日までの予定です。 13日には運転席に運転手がいない状態での走行が行われます。 モニターの乗車は11日と12日に行われます。
-
南箕輪村創生総合戦略の検証を答申
南箕輪村むらづくり委員会は村創生総合戦略の検証について9日、唐木一直村長に答申しました。 9日は宮原袈裟夫会長らが村役場を訪れ唐木村長に答申書を手渡しました。 村創生総合戦略は、立地特性を生かした職住近接のむらづくりや若者定住と郷土愛の醸成による帰ってきたいむらづくりなどの項目があります。 それぞれの項目に数値目標が設定されていて答申では関係する情報のホームページへのアクセス数の目標値を上方修正することが望ましいとしています。 付帯意見として魅力的な農業経営の確立や村内定住、若者回帰の推進、村の魅力開発とブランドづくりなどをあげています。 唐木村長は村創生総合戦略について答申をもとに改訂していきたいとしています。
-
伊那市の西箕輪小学童クラブ 移転改築工事が完了
去年9月から進められてきた伊那市の西箕輪小学校学童クラブの移転改築工事がこのほど完了し開所式が7日に行われました。 新しい西箕輪小学校学童クラブは隣接する西箕輪中学校東側に建てられました。 以前校長の住宅として使っていた建物を改築したもので、木造平屋建て延べ床面積は180平方メートル総事業費は3,900万円です。 腰板には伊那市産のアカマツが利用されています。 きょうは、伊那市教育委員会など関係者が出席し開所式が行われました。 西箕輪小学校の竹松寿寛校長は「この地区に住む子供たちを大切に育てる環境が整ったことに感謝したい」と話していました。 学童クラブでは共働きなどで放課後、家庭に保護者がいない児童を預かります。西箕輪小学校では1年生から5年生の52人が対象となっていて、新しい施設は2月5日から利用が始まっています。
-
南箕輪村の大泉まんどの会 「子供の会」が発足
お盆の伝統行事「振りまんど」を伝えていこうと活動している南箕輪村の大泉まんどの会は、子ども達が自主的に活動できるようにと小学生でつくる会を立ち上げました。 10日に発足式が行われ多数決で会の名称を「子供の会」に決めました。 会長は南箕輪小学校5年生の増澤俊太郎君が、副会長は同じく南箕輪小学校4年生の原和花さんが務めます。 大泉では伝統の振りまんどを後世に伝えようと住民有志でつくる「大泉まんどの会」が主体となって活動しています。 昭和10年代頃までは、地域の子供たちが主体となって振りまんどの行事を行っていたという事で、自主的な活動をする機会をつくろうと小学生を対象とした会を立ち上げる事にしました。 この日はこのほか休耕田で振りまんど用に育てている大麦の麦踏み作業を行いました。霜で浮き上がった麦を土へ戻す作業です。 去年10月に種をまき、収穫は6月を予定しています。 大泉には106人の小学生がいますが、現在子供の会の会員は9人です。まんどの会の唐澤俊男会長は「会員を増やしながら、いずれは自分たちで麦の栽培計画を立て、行事を企画していけるようになってほしい」と話していました。
-
伊那西高校 1年間の成果を披露「芸術フェスティバル」
伊那市の伊那西高校の文化系クラブがこの1年で制作した作品を披露する芸術フェスティバルが、かんてんぱぱホールで10日から始まりました。 会場には、美術クラブ、書道クラブ、折り紙・工芸クラブ、写真クラブ、家庭科クラブのほか、保育の授業で制作した作品、合せて190点が展示されています。 茶華道クラブは訪れた人にお点前を披露しました。 伊那西高校の芸術フェスティバルは1年間の活動の成果を地域の人たちに発表する場として毎年開かれていて今年で11回目になります。 写真クラブ2年生の蟹澤悠月さんは、去年宮城県で開かれた全国高等学校総合文化祭で最優秀賞の文化庁長官賞を受賞した作品を展示しています。 生徒たちは来年の活動に活かすため、訪れた人たちの感想を大切にしているという事です。 伊那西高校の芸術フェスティバルは伊那市のかんてんぱぱホールで13日(火)まで開かれています。
-
伊那市の保育料 来年度からの減額案を諮問
伊那市は来年度から市内の保育園の利用料金を減額する見直しの案を、9日に審議会に諮問しました。 白鳥孝市長が、子ども・子育て審議会の倉澤邦弘会長に諮問書を手渡しました。 内容は来年度から保育園の利用料を減額するものです。 伊那市では、市民税の納税額に応じて12階層に分けて保育料を定めています。 見直し案は全ての階層で減額をするものです。 対象人数が一番多い12階層では、3歳児以上の8時間保育が現在の月額2万6,000円から2万3,000円に引き下げられます。 伊那市では、子育て世帯の負担軽減のため、県内19市のほか上伊那の他市町村と比較しながら最も安いレベルの料金設定にしたという事です。 見直し案は9日の審議会で了承されました。 市長への答申は来週の予定で、伊那市では保育料に関する規則の改正後、4月1日から施行する計画です。
-
新人の八木氏 市長選出馬へ
任期満了に伴う4月15日告示22日投開票の伊那市長選に新人で伊那市議会議員の八木択真さんが立候補することを明らかにしました。 市長選には現職の白鳥孝さんが出馬を表明していて選挙戦となる見通しです。 八木さんは伊那市議会議員1期目の39歳です。 大阪府堺市出身で信州大学農学部卒業後、産経新聞の記者となり平成25年に伊那市に移住し飲食店の経営を始めました。 平成26年の伊那市議会議員選挙に立候補し初当選を果たしています。 八木さんは「伊那市の人口は急速に減り続けている。住む場所として、子育てをする場所として選ばれる伊那市にする」としていて12日に正式に出馬表明します。 市長選ではほかに現職の白鳥孝さんが3期目を目指し立候補を表明していて選挙戦となる見通しです。
-
南原保50人 西部保10人 定員増へ
南箕輪村子ども・子育て審議会が8日開かれ、南原保育園の定員を50人、西部保育園の定員を10人増やす事を了承し唐木一直村長に答申しました。 8日は審議会終了後、宮下努会長が唐木村長に南原保育園と西部保育園の定員を増やす案について「審議会として了承しました」と口頭で答申しました。 村内5つの公立保育園の定員は、これまでの660人に対し、園児数はここ数年700人前後でした。 村では増加する園児数への対応と恒常的な保育園の定員オーバーを解消する為、南原と西部保育園で合わせて60人増やす事にしました。 南原保育園の定員は150人でした。 現在、増築を行っていて来年度はこれまでより50人増え200人となる予定です。 西部保育園は90人でしたが来年度は10人増え、100人となる予定です。 唐木村長は「今後も子育てに重点を置き、実情にあった園児数に対応していきたい」と話していました。 村では保育園の定員の変更に関する条例案を3月議会に提出する予定です。
-
クリスマスローズ・シクラメン原種 200鉢を展示
春に花を咲かせるクリスマスローズの展示会が9日から伊那市西春近のかんてんぱぱくぬぎの杜で始まりました。 「ヘレボルス」という学名のクリスマスローズは、ヨーロッパ原産の花で春に花を咲かせます。 展示会は、箕輪町に本部がある信濃クリスマスローズ愛好会が開いたものです。 展示会には会員45人が育てたクリスマスローズとシクラメンの原種、合わせて200鉢が並んでいます。 会のメンバーによりますと、クリスマスローズは種から育てると花が咲くまで3年かかるということです。 さらに小さい鉢から大きな鉢へと毎年植え替えを行うということで、会場には5年以上かけて育てているものもあるということです。 クリスマスローズ展は、11日までで期間中午後1時半から2時半まで育て方等の講習会も開かれます。
-
西天竜発電所 大規模改修へ
長野県企業局が管理する伊那市小沢の西天竜発電所の建て替え工事の安全祈願祭と起工式が9日行われました。 式には、長野県や伊那市、工事関係者などおよそ60人が出席しました。 西天竜発電所は昭和36年に建設されました。 しかし、発電する期間が農閑期の秋から冬にかけてと短く採算性が悪いこと等から長野県では平成21年度に廃止する事を決めました。 しかし、東日本大震災を契機に自然エネルギーの重要性が見直され、県も発電所を継続し改修する事を決めました。 事業費はおよそ30億円で平成31年度の運転開始を目指します。 改修により発電機は、農繁期でも運転できるようこれまでより小型のものを2基設置します。 これにより年間の発電可能日数は120日増え335日に、発電量は1250世帯分増え4400世帯分となる見込みです。 また、国の再生可能エネルギー固定価格買取制度を利用し売電価格は1キロワットアワーあたり、9円から24円に増え、収入は3億7千万円とこれまでより2億7千万円増える見込みです。 長野県企業局・公営企業管理者の小林利弘さんは「地域の人達と連携し、電力の地産地消をさらに目指したい」と挨拶しました。 上伊那郡西天竜土地改良区の平井眞一理事長は「発電所の継続と改修に感謝している。地域の農業、産業の源となる水の供給をしっかりとしていきたい」と話していました。 新しい西天竜発電所の運転開始は平成31年度中を予定しています。
-
防災タウンページを贈呈
NTTタウンページ株式会社は防災情報を盛り込んだ「別冊防災タウンページ伊那市版」と「タウンページ伊那市版」を8日、伊那市に贈呈しました。 NTTタウンページ株式会社の松永浩さんらが市役所を訪れ防災タウンページを贈りました。 市内の避難所の位置や災害時に携帯電話と比べて電話がつながりやすい公衆電話の設置場所などが記載されています。 また公衆電話のかけ方を知らない子どもが増えているということでその使い方の説明もあります。 伊那市とNTTタウンページは防災情報発信などの相互協力に関する協定を平成28年に結んでいて地域防災力の向上につなげています。 タウンページはおよそ3万2,000部発行し市内全戸と全ての事業所に配布するということです。
-
高遠だるま市 人形飾りを園児が見学
伊那市高遠町の商店街には11日のだるま市に訪れた人たちを出迎える人形飾りが並べられています。 9日は高遠町内の園児が人形飾りを見学しました。 人形飾りはだるま市に訪れた人たちに楽しんでもらおうと作られたものです。 今年は7団体が人形飾りを展示していて高遠保育園では、だるまを作りました。 高遠第2第3保育園は木にまつぼっくりなどをつけて人の顔を作りました。 いろは堂薬局は、ドラえもんを作りました。 アルプス中央信用金庫と八十二銀行はスターウォーズにちなんだ作品です。 春日医院は戌年にちなんだ作品となっています。 グループホーム桜は高遠の四季を貼り絵で表現しました。 伊那市職員だるま市を盛り上げる有志の会は去年開催されたドローンフェス・イン・イナバレーにちなんだ作品となっています。 だるま市は11日に高遠町の鉾持神社参道を中心に行われます。
-
南箕輪村特別職報酬等審議会「本則通り」 答申
南箕輪村特別職報酬等審議会は、平成30年度の理事者の給料の額について、「本則通りの支給が望ましい」と、8日に答申しました。 この日は、村特別職報酬等審議会の高見利夫会長が役場を訪れ、唐木一直村長に答申書を手渡しました。 去年5月に、村の理事者の給料について3%引き上げる条例改正が行われましたが、村長選直後だったため、給料の引き上げは据え置かれていました。 今回の答申では本則通りの支給が望ましいとしていて、これにより来年度から村長の給料は本則通りの74万円、副村長が62万9千円、教育長が53万6千円となります。 高見会長は「人口減少時代の中、村は人口増加を維持している。今後も健全財政の維持に努めてほしい。」と話していました。 唐木村長は、答申を尊重する考えです。
-
伊那地域の最低気温マイナス10.4度
伊那地域は8日の朝7時1分に、最低気温マイナス10.4度を記録しました。 長野地方気象台によりますと、伊那地域では、1月19日以降21日連続して最低気温が氷点下となっています。 9日の朝も8日と同じくらい冷え込む予想で、水道管の凍結や融けた雪による路面の凍結などに注意を呼びかけています。
-
上伊那岳風会伊那地区 初吟会
上伊那の詩吟愛好家でつくる上伊那岳風会伊那地区の初吟会が4日、伊那市のJA上伊那本所で行われました。 上伊那岳風会は、伊那市・駒ヶ根市・箕輪町に支部があり、この日は伊那地区の今年最初の吟会が行われました。 伊那地区には16の教室があり、小学校5年生から87歳まで、およそ70人が会員となっています。 この日は全員が1人ずつ吟じる「独吟」という形式で発表しました。 高校生は、去年12月に須坂市で行われた、第42回全国高等学校総合文化祭のプレ大会で披露した合吟と剣舞を行いました。 上伊那岳風会伊那地区では「緊張感がある中で良い声が出ていてよかった。今後も活動を続けていくために、若い世代の育成にも力を入れていきたい。」と話していました。
-
展示 「明治を生きた郷土の作家たちⅡ」
幕末から明治にかけて活躍した伊那谷にゆかりのある作家の絵画や書などが並ぶ展示会が、8日から伊那市高遠町の信州高遠美術館で始まりました。 会場には、中村不折や池上秀畝といった、伊那谷にゆかりのある作家7人の作品17点が並んでいます。 こちらは、中村不折の代表作のひとつ「卞和璞を抱いて泣く」です。 中国の故事を題材にした油彩画で、伊那市指定文化財となっています。 この他、池上秀畝が描いた幅7.5メートルの屏風など、美術館所蔵の作品5点も初めて展示されています。 信州高遠美術館では「不折の代表作をはじめ見ごたえのある作品が並んでいる。多くの人に見てもらいたい。」と来場を呼び掛けています。 この展示会は、4月2日まで、信州高遠美術館で開かれています。
-
長谷中学校 内藤とうがらしの活動で最高賞を受賞
伊那市長谷の長谷中学校は、自然体験活動のアイデアを全国の小中学校から募集する、第16回トム・ソーヤースクール企画コンテストで、最高賞を受賞しました。 7日は、3年生の生徒や田中祐貴教諭らが市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞を報告しました。 トム・ソーヤースクール企画コンテストは、ユニークな自然体験活動のアイデアを全国の小中学校から募集するもので、今回で16回目です。 長谷中学校は、地元で採れる伝統野菜「内藤とうがらし」を使った地域の活性化に取り組みました。 3年生の生徒を中心に内藤とうがらしを栽培し、乾燥させて一味唐辛子やラー油を作りました。 過疎化する地域の活性化に貢献した点などが評価され、今回最高賞にあたる文部科学大臣賞に選ばれました。 賞金の100万円は、唐辛子の製粉機や鍋などの購入費に充てたということです。
-
上農生産環境科 卒業前に成果を弁当で
南箕輪村の上伊那農業高校生産環境科の3年生は、卒業を前に学習の成果として、自分たちがそだてた米が入った弁当を8日、たのしみました。 弁当には3年生が今年育てた米「風の村米だより」が使われています。 素材の味をしっかりと味わえるようにと雑穀ごはんになっています。 ダイコンやニンジン、ネギなども、生徒たちが栽培したものです。 生産環境科の3年生は、米の生産から流通について学んできました。 8日も、生徒の保護者で、辰野町で瀬戸ライスファームを営む瀬戸真由美さんから話を聞きました。 稲作を行う瀬戸ライスファームでは、個人を対象に、米や餅などの販売を行っています。 付加価値を付けた米や米粉を使った料理方法の提案など、独自の販売を行っています。 生徒たちは、瀬戸さんのほかにも、地域の農家の生産から流通まで、米について学習を深めてきました。 今回は、その後、流通した米が飲食店に届き提供されるところまで学ぼうと、伊那市内の飲食店に協力してもらい弁当にしてもらいました。 3年生は現在、卒業を前に自宅研修の時期に入っていて、今日が、最後の授業です。 担任の岩崎 史(ふみ)教諭は、「地域で活躍している素晴らしい方々の背中を見て、自分たちの未来に役立ててほしい」と話していました。 上農高校の卒業式は、3月3日(土)となっています。
-
伊那市選管が高校生に不在者投票啓発
伊那市選挙管理委員会は、卒業し地元を離れる人も多い高校生を対象にした不在者投票の啓発を、8日、南箕輪村の上伊那農業高校で行いました。 卒業し、進学や就職で地元を離れる生徒も多い中で、住民票のある地域の選挙に不在者投票できることを知ってもらおうと、伊那市選挙管理委員会が初めて行いました。 伊那市では、4月15日告示・22日投開票の伊那市長選・市議選が予定されています。 市選管では、「地元に帰ってきての投票が難しい場合は、投票用紙を請求して取り寄せることができる」と説明していました。 上伊那農業高校の3年生は157人で、うち、72人が伊那市出身者となっています。 また、全体のうち、49人が進学などで県外にでるということです。
-
有賀さんからラジオ体操まなぶ
伊那市出身で、NHKテレビ体操のインストラクターを務めていた有賀 暁子さんのラジオ体操講座が、8日、いなっせでひらかれました。 有賀さんは、伊那市西町出身で、2003年から2014年までの11年間、NHKのテレビ体操やラジオ体操にインストラクターとして出演していました。 現在は、全国各地でラジオ体操の指導や普及活動を行っています。 8日は、まほらいな市民大学の講座の一環で、指導が行われました。 市民大学の講座で有賀さんを招くのは今年で3年目です。 講座では、正しい姿勢や動きを一つ一つ確認しながら体操していました。 有賀さんは、「正しく体を動かすと筋肉を使っているのが感じられると思います。健康に過ごすために体操を取り入れてほしい」と話していました。
-
高校入試前期選抜
高校入試の前期選抜試験が7日、県内一斉に行われました。 午前8時頃、上伊那農業高校では受験生が続々と会場に向かっていました。 上伊那の公立高校では、伊那弥生ヶ丘高校を除いた7校で前期選抜試験が行われました。 上農高校では4つの学科合わせて128人が志願していて、倍率は1.6倍となっています。 県内全体では6,889人が志願しています。 長野県教育委員会によりますと、入試にかかわるトラブルはなかったということです。 前期選抜の合格発表は15日の予定です。
-
伊那市高遠町の旧馬島家住宅 雛人形の飾りつけ
伊那市高遠町の旧馬島家住宅で、雛人形の飾りつけが7日に行われました。 高遠町内の女性でつくる「高遠をこよなく愛する会」のメンバーが200体ほどの雛人形を飾り付けました。 以前は3月に飾り付けを行っていましたが、だるま市に訪れた人にも見てもらおうと去年から2月に行っています。 会場では様々な時代のものを一堂に見る事ができます。 一番古いものは300年前、江戸時代中期の享保雛です。享保の改革で倹約を推し進めていた幕府により、大型の雛人形の製作や売買が禁止されていた時代に作られました。 このほか、江戸時代後期に作られた押絵雛のほか、明治、大正から現代のものが展示されています。 愛する会のメンバーは「趣のある雰囲気の中で様々な人形を楽しんでほしい」と話していました。 雛人形の展示は、あすから高遠城址公園の花見シーズンが終わる頃の4月24日まで行われます。 また3月10日には、抹茶の提供や着物の着付けを無料で行うイベントを開催する予定です。
-
布で山野草を再現 「花のは」展示会
布を使って山野草を再現する教室「アトリエ花のは」の展示会が、南箕輪村のコーヒー&ギャラリーなごみの樹で開かれています。 会場には、布を使って山野草を再現した作品50点が展示されています。 アトリエ主宰の白鳥敏子さんは、20年ほど前から制作に取り組んでいます。 実際の花を観察してスケッチし、布を切りぬいて染色します。 ワイヤーなどを使って形を作り、油絵具で色を付けています。 アトリエ花のはは、南箕輪村の南原コミュニティセンターで月に2回活動していて、現在3人が通っています。 また、会場には伊那市手良の竹内良知さんが撮影した写真も一緒に展示されています。 この展示会は、28日(水)まで、南箕輪村のコーヒー&ギャラリーなごみの樹で開かれています。
-
冬の渡り鳥 キレンジャク飛来
7日の伊那地域の最低気温はマイナス9.2度と厳しい冷え込みとなりました。 伊那市の伊那中央病院近くでは、黄色い尾が特徴の冬の渡り鳥「キレンジャク」が見られました。
1111/(火)